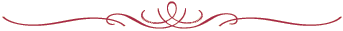
| キリシタン大名考 |
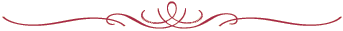
更新日/2018(平成30).12.24日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| キリシタン大名問題は勝れて現代的問題であるように思われる。今日かっての大名は存在しないが、これを現代的になぞらえればさしづめ国会議員、上場会社の社長、研究機関の学長ということになろうか。これらの連中の為している様が、当時のキリシタン大名の為している様と変らない。違っているのは、キリシタン大名は封殺されたが、今日のシオニスタンはますます隆盛し国家権力中枢を握っていることである。俗に、これを国家簒奪、権力乗っ取りと云う。 それはともかく、織田信長が憤死させられた本能寺の変の黒幕にバテレンの動きがあったという仮説は有効だろうか。れんだいこは然りと考える。しかしながらこれを証する資料が無さ過ぎるのでこれ以上のコメントはできない。いずれにせよ、歴史の真相はなかなか表には現われないとしたもんだ。「日本の宣教に貢献したキリシタン大名」、「ウィキペディア日本のキリシタン一覧」その他を参照する。 2006.2.3日 れんだいこ拝 |
| 【キリシタン大名】 |
| キリシタン大名(吉利支丹大名)とは、当時来日したキリスト教宣教師の伝道によりキリスト教を信仰するに至った大名のことを云う。聖フランシスコ・ザビエルは布教に当り、任地の大名に謁見して宣教の許可を願った。薩摩、平戸、山口と豊後ではそのようにした。その際、布教を円滑に進めるために大名自身に対する布教も行った。その4人の大名の中で、大友義鎮だけが信者になった。後から来日した宣教師たちも同様に各地の大名に謁見し、領内布教の許可や大名自身への布教を行った。宣教師達は、大名たちの歓心を得るために、布教の見返りに南蛮貿易や武器の援助などを提示した者もおり、大名側も宣教師を通じての利益を得ようとして、入信した者もいた。入信した大名の領地では、イエズス会の布教方針に則り領民が改宗し始め、爆発的にキリスト教が広がることになった。キリスト教が広まるにつれて、キリスト教の教義や、キリシタン大名の人徳や活躍ぶりに感化され、自ら求めて入信する大名が現れ、南蛮貿易に関係のない内陸部などでもキリシタン大名は増えていった。 洗礼を受けた大名は30名をこえていた。これは信憑(しんぴょう)性のある記録により判明している。主なキリシタン大名は次の通り。大村純忠(1563年洗礼)、高山右近父子(高山ダリオ飛騨守とその息子ユスト高山右近)(1564年洗礼)、大友宗麟(1578年洗礼)、有馬晴信(1580年洗礼)の九州大名。続いて、小西行長、黒田孝高(如水)父子(1585年洗礼)、蒲生氏郷、三箇伯耆守信長の孫岐阜中納言織田秀信等々。これらの大名は、程度の差はあれ熱心に宣教に協力した系譜である。他にも、宣教を迫害をしないで陰から支援した大名もいた。蜂須賀家政、豊後の佐伯の毛利高政、京極高知らがそうであった。キリシタン大名から迫害者になった大名も居る。黒田長政、有馬直純、寺沢広高がその道をとった。 他に、大名夫人の系譜もある。細川忠興夫人ガラシャ、大村純忠の娘大村メンシア(1564ー1634)、浅井久政の娘、長政の姉マリア京極(1542ー1618.2.28)らである。マリア京極は、京極高吉の妻である。1581年、イエズス会安土住院で、高吉とともにオルガンティノから受洗。次女龍子(豊臣秀吉の側室)をのぞく子どもたちにも受洗させ、大坂の布教に助力した。その後、長男・高次の領国若狭に退き、若狭や丹後の田辺(次男・高知の領国)で布教したといわれる。晩年は、若狭の泉源寺で暮らし、ここで亡くなった。 他方、毛利輝元、加藤清正などは最初から敵対を示していた。 豊臣秀吉の伴天連追放令以降、キリシタン大名には政治的な圧力が強まり、多くの大名が改易され、もしくは棄教した。江戸時代にはいり1613(慶長18)年には禁教令も出されたため、最後まで棄教を拒んだ高山右近はマニラの呂宋(ルソン)に追放され、有馬晴信は殉死し、以後キリシタン大名は絶滅した。 |
| 【大友宗麟】(1530.1.30−1587.6.11) | |
| 中世・豊の国は大友氏が豊後に入国し,蒙古合戦には大友氏ら二豊武士団が活躍した。南北朝の争乱に大友軍は京都周辺まで出陣。戦国時代は大友氏は山口の大内氏と争い、そしてキリシタン大名宗麟(ソウリン)の時全盛になる。 1530年、誕生。幼名、塩法師丸、後に新太郎、義鎮。入道して宗麟、休庵などと名乗る。1550年、父の後を継ぎ豊後(現在の大分県)の大友氏 21代当主として領主となる。大友氏は、戦国大名として豊後 を中心として九州6国を支配する戦国大名。1551年、フランシスコ・ザビエルの来訪を受け会見、彼の人格と確固たる信念、宣教への強い使命感にひかれキリスト教への関心を抱き、以後それを手厚く保護する。 1554年、肥後の菊池氏を滅ぼす。61年、毛利氏と門司城合戦。1569年、肥前で龍造寺氏と戦い、博多にて毛利氏と再び戦う。義鎮は、イエズス会宣教師達との密接な共存を続けていたが、その間に義鎮は禅宗に帰依し、入道して宗麟と名乗り、諏訪の丘に寿林寺を創設、開山として京都大徳寺の怡雲を招いている。事故で弟が怪我をした時、優れた西洋医術を目にし直ちにそれを導入した。1557年、府内でポルトガル人医師に外科手術を行わせた。これが日本における最初の西洋外科手術となり、さらに総合病院も作らせた。 1576年、既に48歳となっていた宗麟は自らの領土を息子の禅宗に譲り、ポルトガル人を忌み嫌っていた妻と離別。新しく洗礼を受けさせた次男、親家の妻の母にあたる女性と再婚している。ちなみに、宗麟の息子・娘は全て離婚した妻との間に生まれている。 1578(天正6).8.28日、宗麟をキリスト教信仰へ導きたいと常に願っていたイエズス会の日本布教長・フランシスコ・ガブラルは、当時48歳の宗麟に洗礼を施した。洗礼名はドン.フランシスコ。
豊後領主大友宗麟(ドン・フランシスコ)の他、大友宗麟の長男・大友義統(コンスタンチノ)、大友宗麟の次男・大友親家(セバスチャン)、大友宗麟の三男・大友親盛(パンタレアン)が洗礼を受けている。 こうして、領内でのキリスト教の保護育成に努め、キリシタン戦国大名として歴史に名を残した。南蛮貿易を盛んにして、豊後の府内を国際交易の拠点とし南蛮文化も取り入れた。1578年、薩摩の島津氏との日向の高城,、耳川の合戦で敗れて衰退する。日向に理想のキリスト教王国を建設しょうとしたが、高城、耳川の合戦に大敗して幻となった。1581(天正9).11月、養子に出した子息の田原親家を大将に宇佐神宮に兵を送り7000人余の兵をもってこれを包囲し焼き討ちにした。宇佐神宮は豊前の国にあり山口の大内氏の領土であった時代も長くて、又宇佐神宮の宮司の宮成、益永、時枝氏らが毛利方の秋月氏に通じて大友から離反した。こういう政治的事情もあったが、宗麟は神社、仏閣にかなりの不遜な行為をしているので、キリシタンが故のイデオロギーに染まった宗教戦争であったと考えられる。 1582.4月、キリシタン大名としてロ-マに伊東マンションら少年使節を送る。86年、秀吉に島津侵入の救援を大阪城で依頼して、九州征伐のきっかけを作る。 大友家は朝鮮征伐の時の失態で文祿2年、秀吉から除国とされ、豊の国は小藩分立の時代となる。大友氏は千石の旗本高家、鎌倉以来の名門として幕末まで続く。 |
| 【大村純忠】(1533ー1587) |
| 戦国時代の武将。長崎大村藩主のキリシタン大名。1533(天文2)年、島原の城主有馬晴信(純)の二男として肥前国有馬に生まれた。母は大村純伊の娘。純忠の実兄に有馬義貞がおり、その義貞の子供にあたるのが西肥前のもう一人の使節の派遣者有馬晴信である。したがって、大村純忠と有馬晴信は、伯父・甥の関係であった。晴信は永禄10年(1567)の生まれであるから、両者には34歳の年齢のへだたりがあった。幼名は勝童丸。丹後守,民部大輔。剃髪して理仙と称し,受洗名はバルトロメオ。文書には波留登路銘と署名。 1538(天文7)年、6歳の時、肥前の有力豪族であった大村純前の養嗣子となり、1550年、家督をつぐ。肥前国の西部を支配していた21万石という肥前最大の有力者有馬家は、勢力拡大の為に次男純忠を大村家に養子へ送ったことになる。大村家と有馬家の間には姻戚関係が成立した。純忠が養子に入った大村家には庶子嫡男として貴明がいたが、有馬家を気にした大村家は貴明を後藤家へ養子に出してしまい、この事を恨んだ貴明と純忠は長い戦いを繰り広げることになる。 有馬家の後ろ盾があったが、有馬家は積極的な動きをせず、2万石しかない大村純忠は自力で迫りくる敵と苦しい戦いを続けることになった。当時の大村領は攻撃的な佐賀の龍造寺隆信などによる周囲の圧迫もあり、打開策を模索していた。大村家は純忠の母親の実家だが、嫡男貴明を追い払い純忠が養子に入った事を嫌った一族や重臣の多くが後藤貴明の元へ去り、大村家へ攻め寄せる状況に、自分が養子に来た事が原因の戦いに悩み続けていた純忠は、そうした時にキリスト教に出会う。キリスト教の宣教師の話を聞くうち、不思議と惹かれるものを感じると共に、家臣や領民すべてをキリスト教徒にする事で一体化をし、今後迫り来る敵に備える事を思いつく。キリスト教に改宗した大村家に対し、後藤・西郷・諫早の三氏は連合を組み、仏教を棄てた事を理由に攻めてくるが、純忠を始めとする家臣達の懸命の働きにより撃退に成功する。 1561年、松浦氏の領土であった平戸港でポルトガル人殺傷事件が起こった。ポルトガル人は新しい港を探し始め、修道士アルメイダが大村藩との交渉を始めた。純忠は、自領にある横瀬浦(長崎県西海市)の提供を申し出た。1562年、布教を認めるだけなく、教会を建てること、港の半分をイエズス会に譲ることなど破格の条件で横瀬浦の開港を約束した。イエズス会宣教師がポルトガル人に対して大きな影響力を持っていることを知っていた純忠はあわせてイエズス会員に対して住居の提供など便宜をはかった。1562年、横瀬浦(西海町)を南蛮貿易港として開港。結果として横瀬浦はにぎわい、純忠のこの財政改善策は成功した。 1563(永禄6).6月、宣教師からキリスト教について学んだ第18代領主大村純忠は、横瀬浦で25名の家臣とともにコスメ・デ・トーレス神父から受洗した。日本最初のキリシタン大名)となった。教名をドン・バルトロメオと名乗り、日本最初のキリシタン大名となった。大村純忠の子・大村喜前(サンチョ)も洗礼を受けている。この25人のなかに、後に長崎の領主となる長崎甚左衛門もいた。領民の殆どがキリシタンになり、信徒6万、教会70を数えた日本の小ローマと呼ばれ、キリシタン王国と云われるほどであった。キリシタンを保護して南蛮貿易にも積極的に従事している。純忠の入信についてはポルトガル船のもたらす利益目当てという見方が根強いが、記録によれば彼自身は熱心な信徒で、受洗後は妻以外の女性と関係をもたず、死にいたるまで忠実なキリスト教徒であろうと努力していたことも事実である。 大村純忠とポルトガルとの交渉は、その実家である有馬氏にも強い影響を与えていった。横瀬浦港が武雄の後藤貴明の攻撃によって廃港になると、それにかわる長崎外港の福田浦を65年、天草の志岐とともに、有馬義貞によって島原半島の南端口ノ津にも南蛮貿易が誘致された。同時に宣教師アルメイダを口ノ津にまねき、教会となるべき寺を与えて布教を許した。 時に永禄6年のことである。 純忠は頃合を計って大村に戻り三城城を築く。1568年、城の側に大村市で最初の教会を造った。 1570(元亀元)年、純忠夫人、長男・喜前(よしあき)(洗礼名ドン・サンチョ)、長女・自証院(じしょういん)(洗礼名ドンナ・マリイナ)が大村で洗礼を受けている。 1570(元亀元)年、純忠はポルトガル人のために港を提供した。同地は良港として以後、大発展していく。当時100戸余りの寒村にすぎなかったこの港こそが、後の長崎である。1574年、諫早殿と他の敵の攻めのとき有名な「三城の七騎士」の戦いの後、全領土で積極的に宣教の手助けをした。その活動では後に準管区長になった。この時、ガスパル・コエリョ神父と図り、長崎開港と、少年使節の派遣を決めたと云われている。 1571(元亀2)年、龍造寺隆信の圧迫に耐えたが、息子たちを敵の手に人質として渡し、坂口に引退させられた。1578年、長崎港が龍造寺軍らによって攻撃されると純忠はポルトガル人の支援によってこれを撃退した。 1572(元亀3)年、大村純忠は、深堀純賢と図った西郷純堯からの攻撃を受けた。このとき、深堀純賢は長崎港を攻撃した。この攻撃で、深堀氏は長崎港の異人館や村、教会を焼きはらった。純忠は反撃し、西郷軍は兵を引き上げた。純堯は熱心な仏教徒で、大村純忠のキリシタン政策に反感を持っていたのが真相のようである。 1573(天正元)年、純堯は純忠の実兄にあたる有馬義貞を手中に抑えていて、義貞に命じて純忠を誘殺しようと企んでいる。純堯は、純忠のキリスト入信を咎め、キリシタンであることを止めれば純堯と敵対することもなくなると忠告した。これに対して純堯は、自分がキリシタンであることには異義を唱えないでいただきたい。自分は領国・家・家臣および生命を失っても棄教はしない、と返答している。 7月、後藤貴明も三城に攻め寄せている。貴明の要請を受けた平戸の松浦鎮信、諌早の西郷純暁も援兵を出し、三氏連合して1500の軍勢であった。大村方は、手勢僅かで籠城した。弓、鉄砲で威嚇するひとで窮地を脱した。この合戦が、大村家で「三城七騎籠」と伝えられている。 その後も深堀・諌早西郷氏による大村・長崎港攻撃は断続的に行われ、その都度、大村氏は援軍を純景に送り攻撃を退けた。1580(天正8)年の戦いでは、大村勢が150名で長崎氏方に来援して西郷勢を打ち破っている。 1574(天正2元)年、大改宗運動を展開して、領内すべての偶像崇拝の礼拝施設・神社仏閣を破壊し、先祖の墓所も打ち壊した。全領民6万人をキリシタン化していった。入信しないものは領外へ出ていくことを強要するほど徹底したものだった。純忠のキリシタン信仰は、この天正2年を契機として一気に高まった。それまでは、改宗後も伊勢神宮の神符をうけていたり、真言僧との交渉を保っていた。改宗後約10年を経て、イデオロギー的に純化させたものと思われる。「領民をキリシタンにすることと鉄砲との交換条件で領民何人で 鉄砲1丁との交換だった」とも伝えられている。 しかし、この行過ぎたやり方は家臣や領民の反発を招くことになる。前君の庶子後藤貴明が反乱を起こして横瀬浦を焼き払うという事件を引き起こしている。純忠は多良岳に逃れ、そこで出家して理専と言う名前を取得した。この事情を解くのは難しいが、純忠のキリシタン信仰を棄てさせようとする外圧が係り、仏教的出家を余儀なくされたのではないかと思われる。しかし、純忠は引き続き宣教師たちと連絡をとりあい、むしろ次第に攻勢に出始める。 1579(天正7)年、巡察使ヴァリニアーノの口ノ津来訪を機に、有馬義貞の子晴信も夫人とともに改宗した。教名をドン・プロタジオといい、時に13歳であった。 1580(天正8)年、大村氏に属した長崎氏は西郷・深堀勢の攻撃をよく撃退したが、純忠は長崎港周辺をイエズス会の耶蘇会領として寄進した(後に秀吉によってイエズス会から取り上げられ、直轄領となる)。この頃、巡察のため日本を訪問したイエズス会員アレッサンドロ・ヴァリニャーノと対面し、遣欧少年使節の派遣を決めている。 大村にはそれぞれ洗礼名を持つ四人の息子、喜前(サンチョ)、純宣(リノ)、純直(セバスチャン)、純栄(ルイス)がいたが、龍造寺隆信の圧迫により、人質に出さざるを得なかった。(後に純忠の後を継いだのは大村喜前であった) 彼の名代として甥にあたる千々石ミゲルが人選された。この年、長崎港、新町6か町、茂木をイエズス会に寄進することによって長崎港をキリスト教会領とする方策を取った。 1581(天正9).8月、純忠は、龍造寺隆信に降った。嫡子喜前を人質として佐賀に拘束された。 1582(天正10)年、巡察使ヴァリニャーニのすすめもあって、有馬晴信、大友宗麟と図りローマ法王庁に向けて遣欧使節を派遣している。 1583(天正11)年、次男の純宜・三男純直の二人に息子も人質として送るように要求される。三人の息子を人質にとった隆信はさらに純忠に、主だった親戚の者たちも渡すように要求してきた。この者たちはみな純忠が頼みとする者たちであった。しかし、純忠は、やむなく彼等を隆信に引き渡した。すると、隆信は、別の使者をよこして、純忠に三城を出て波佐見の地にある小さく不便な場所に蟄居するように命じてきた。ここに至り、隆信から逃れ得ないことを悟った純忠は城から出て、波佐見に向かった。このとき、家臣を伴うことは許されなかった。この隆信の仕打ちは、あまりにも屈辱的でみじめであったため、純忠は退去に際して人目につくところを避けて、遠回りをしたという。 隆信は純忠を三城から追放したのち、人質の喜前を三城に入れた。そして、自分の家来たちを伴わせて喜前を操り、キリシタン宗団の絶滅を狙った。大村に入ってきた隆信の家来たちは、キリシタンを殺害し、家財や妻子を奪うなど狼藉の限りを尽くした。こうして、大村氏を屈服させた龍造寺隆信は、同じキリシタン大名である有馬晴信に重圧をかえるようになる。晴信は先年、隆信の嫡子政家のもとへ政略として妹を嫁がせ、両家の和に心を砕いていた。しかし、領国内では隆信の残虐な仕打ちで離反する領主が増え、晴信もまた人望のない隆信を離れて島津義久の幕下となった。 1584(天正12).3月、隆信は、島津氏に寝返った有馬晴信を討つため、3万の大軍を率いて島原に渡り、晴信の本拠日之江城に向かった。大村純忠も島原出兵を命じられた。純忠はやむなくこの命に応じ、嫡子喜前を出陣させ、喜前は三百余の大村勢を率いて有馬攻撃に加わった。この戦いは、純忠にとって同じキリシタン同士であり、しかも甥で、実家の当主でもある有馬晴信とその家臣を討つことであり、かれの苦悩は深かった。有馬攻撃に投入された大村勢は、みな有馬の勝利を祈り、隆信の部将たちから有馬軍への攻撃を命じられたときは、弾丸を抜き、空鉄砲を撃つことを申し合わせていたという。 竜造寺隆信は、この一戦で一挙に有馬氏とキリスト教を壊滅させようとしていた。しかし、隆信の大軍は有馬・島津連合軍の巧みな作戦によって、沖田畷の戦いにおいて敗戦、隆信は戦死した。隆信の戦死で、龍造寺軍は敗走したが、大村勢は島津軍の危害も受けず、全員が武具、馬などとともに解放された。そして、純忠は隆信の死によってかろうじて大名の地位お回復し、三城に復帰した。 1585(天正13)年、秀吉の九州征伐が始まった。純忠は秀吉に従い、所領を安堵された。純忠の死後、子嘉前(喜前)が家督を継ぎ、二万七千石が安堵され、近世大名として続いた。 1587(天正15).5.18日、扁桃腺炎悪化により、隠居先の坂口館で祈りのうちに死去(享年55歳)。豊臣秀吉による第1回の禁教令・バテレン追放令発布の2か月前のことであった。没後、耶蘇会は聖堂内に葬り、のち改葬している。 純忠の死の2ヶ月後、豊臣秀吉によりバテレン追放令が出される。南蛮貿易の流れで教会領となっていた長崎を秀吉が没収した。17年間最大の収入源の長崎が大村氏の手から離れていくことになった。 純忠が亡くなって、 長男・喜前(よしあき)が第19代藩主として大村藩を引き継いだ。この年の5月、九州の雄藩島津義久が豊臣秀吉に降伏し、これ以来九州は秀吉の支配下に入った。秀吉は、突如として「バテレン追放令」を発し、 全ての宣教師たちに20日以内に日本から立ち退くよう要求し、同時に、当時イエズス会領となっていた長崎6町、茂木などを接収し、更に大村領内の教会を破壊したり、長崎のキリスト教徒には多額の罰金を課した。キリシタンの排斥が始まった。 1606(慶長11).1月、大村藩主・大村喜前(おおむらよしあき)も藩を守っていくためにはやむを得ず、マリイナの夫・浅田(あさだ)純盛(すみもり)と共にキリスト教を棄(す)て、日蓮宗に改宗し、大村に本経寺(ほんきょうじ)を建立した。 |
|
長崎開港と西洋医学の輸入 元亀2(1571)年に6町が成立したころの長崎の人口は、1,500人程度と見られる。長崎純景の鶴城は東北の高台(城の古祉)にあったため、これを中心に城下町を拡充する方法もあった。しかし純忠は、この方法をとらず、岬の突端に新たに都市を作った。それは明らかに、それがポルトガルとの貿易を展開する上で最適と考えたことからきたと思われる。海上から望見すると、この岬が後背地から長く海中に延び鶴のように見えたので、長崎港は鶴の港とも呼ばれた。 長崎の宣教師は、最初、ウイレラがあたったが、後にイエズス会修道士アルメイダに代わった。アルメイダは、リスボン生まれのユダヤ系新教徒の家に生まれ、青年期に商業、薬学、医学、特に、外科学の研究を進めていた。領主・長崎純景は、自分の土地をウイレラに与えており、これがトーマス・サントス教会として日本における筆頭格の教会となった。その付属地には薬草園が建設され、新しい薬草の移植が始まり、当時の植民地医学が移入される最大の基地になった。 修道士アルメイダの医学業績の一つであるヨーロッパ医学の伝播は、豊後府内から始まったが、アルメイダの影響により長崎に結実した。1583年、アルメイダが病没した年に、日本人キリシタン・ジュスティーノ夫妻がミセルコルディア(教会付属慈恵病院で、当時は慈悲屋という)を設立。さらに付属施設として養老院、癩病院、一般病院を含む7つの文院をもった施設を作り、その名声は東南アジアにまで知られ、海外から受診にくる患者まで現れた。 天正15(1587)年6月13日(太陽暦・7月18日)、九州の島津征伐を終えた秀吉は、博多の宿で諸将の所領を安堵した。その博多の宿に、イエズス会宣教師コエリョが長崎から訪問していた。ところが秀吉は、突然、長崎,浦上地方の宣教師に対して、6月18,19日付けで20日間の期限付による退去命令を出した。驚いたコレリョは、秀吉周辺のキリシタン大名にたより、秀吉をなだめようとしたが効果なく、かろうじて20日の期限を、6ヶ月間に延期するにとどまった。 キリスト教宣教師追放令がはかばかしく功を奏しないことに怒った秀吉は、近畿の教会堂22箇所を破壊し、浅野長政を長崎へ派遣して長崎をイエズス会から没収し、天正16(1588)年4月21日、鍋島直茂を代官として長崎を預ける処置を取った。ここからイエズス会領時代の長崎は変容を始めることになる。同年閏5月15日、秀吉は長崎の地子銀徴収を免じるが、翌年になると秀吉は小西隆佐を長崎へ派遣して、長崎港の白糸を買い占めてしまうなど、直接干渉に乗り出した。 天正18年のワリアーノ一行の帰国時、ワリアーノは加津佐コレジオ、セミナリオを禁教令下では危険とし、コレジオを天草河内浦へ、セミナリオを八良尾へ移すことにし、加津佐印刷所、コレジオ、修道院も天草へ移った。文禄元(1592)年から長崎奉行所が本博多町に置かれ、御朱印船貿易も始まった。このあたりから長崎は、キリシタンだけの町から仏教徒派の貿易商人もいる町に変わりつつあった。 |
| 【有馬晴信】(1567ー1612.6.5、永禄10〜慶長17.5.6日 ) | ||
|
肥前有馬のキリシタン大名。肥前国有馬日之江城主有馬義貞の次男。霊名アンドレ。鎮純・鎮貴・久貴・久賢・左衛門太夫・修理太夫とも称す。 1588(天正16)年、秀吉が長崎などを直轄地とする。自領長崎の浦上をイエズス会の地行に寄進する。同年コレジヨ(大神学校)を長崎より自領の千々石へさらに有家へそして加津佐へと移設した。そこへ1590(天正18)年、天正遣欧少年使節が長崎に帰る。活字印刷機が付設され,翌年日本最初の活版印刷が行われ出版活動が始まる。 当時の日本で最も贅を尽くしたと云われる「有馬の大天主堂
」をセミナリヨの敷地内に建設した。ヨーロッパ人の神父が与えた図面を基にした最新の天主堂であった。同時期には後に島原の乱の舞台となる「原城」の増強工事も行っていたが、晴信は原城建設を中止してまで天主堂建設を優先させた。
1601.12月、有馬の大天主堂が落成した。その後反キリシタン勢力からの告発により、徳川家康が有馬と大村のすべての教会を破壊することを命じた。このとき、有馬晴信と大村の両領主は家康に仲介人を立てて、懇願し、「領内に好むままの教会を持つことを許可する」との返答を引き出した。この時の家康の発言は次の通り。
1603年、徳川家康征夷大将軍となり江戸幕府を開く。御朱印船貿易では晴信に大名の中では第1号の朱印状を発行し海外交易の代理人とした。アジアに近い地の利とそれまでの海外貿易の実績を認めたものと考えられる。1604年、原之城の新城を完成した。さらに有馬晴信は嫡男「直純」を家康の側近に送り込むことに成功する。15歳で駿府城において家康の近習(きんじゅう)として身近に仕え、その後家康の曾孫の国姫と結婚することになる。結果として外様大名であったにもかかわらず有馬氏は、有馬から延岡(宮崎県)、丸岡(福井県)への移封を経て幕末まで栄えることとなる。1605(慶長10)年、松浦鎮信が朱印状を受ける。 1608年、晴信の運命を暗転させる事件が起る。晴信がチャンパに派遣した朱印船がマカオに寄航した際、乗組員がポルトガル人と紛争を起こし、乗組員と家臣あわせて48人が殺されるという事件が起きた。晴信は激怒し、徳川家康に仇討ちの許可を求めた。1609年、マカオにおけるポルトガル側の責任者アンドレ・ベッソアがマーデレ・デ・デウス号に乗って長崎に入港した来た。晴信は、多数の軍船でポルトガル船を包囲し船長を捕えようとした。ところが船長は船員を逃がして船を爆沈した。これを「デウス号事件」と云う。 続いて、「岡本大八事件」が起る。「デウス号事件」の後、家康の股肱・本多正純の臣、岡本大八が晴信に近づき、デウス号撃沈の功を幕府に上申し、有馬氏の旧領、肥前三郡の返還を斡旋しようと申し出て、口利き料として晴信から多額の金品を収賄した。これが発覚するや家康は激怒した。大八は火あぶり刑、晴信も賄の罪をとわれて連座し、1612年、甲斐国に配流預けとなった。配流地は初鹿野村(現大和村)で、鳥居土佐守成次の監視の下にこの初鹿野村(現大和村)に蟄居幽閉を命ぜられた。現在もこの旧跡が残されている。 1612(慶長17).5.6日、板倉周防守重宗及び鳥居土佐守成次は、検使役となり150人を従えて幕府の命を伝えて晴信に自刃を迫った。晴信はキリスト教徒であったため、自殺を選ばず、妻たちの見守る中で老臣梶左エ門に命じ首を切り落とさせた。霊名・ドン・ヨハネ、仏霊名・晴信院殿迷誉宗転大禅定門。 1616年、松倉重政が新しい領主になる。一国一城令により,原城は廃城となる。松倉氏のキリシタン弾圧ときびしい年貢取り立てに対し,寛永十四年(1637)10月25日に農民が起ち上がり,天草四郎時貞を中心に原城跡にたてこもり,島原の乱が起こる。原城には12月3日から翌年2月28日まで約37,000人がたてこもったが,最後は約12万人の幕府軍に倒された。 |
| 【結城忠正】(ー) |
| 山城守、松永久秀の家臣。1563年久秀の命でキリスト教の取調べを行うため日本人修道士ロレンソ了斎を尋問するが、ロレンソより話を聞くうちその教義に同感し、忠正自身が堺から来たビレラにより洗礼を受ける。洗礼名:エンリケ。畿内で最も早くキリシタンとなりキリスト教を保護した。彼の改宗によって畿内のキリスト教布教は大きく進展した。 |
| 【高山右近】(1552ー1615.2.5) |
| 「高山右近(キリシタン武将)考」(「歴史学院」所収)に記す。 |
| 【小西行長】(1558ー1600.11.6) |
1586年には小豆島、塩飽諸島、室津などを領していた。小豆島ではセスペデス神父を招いてキリスト教の布教を行う。1587年の九州の役にも水軍を率いる他食料輸送、補給役で従軍した。バテレン追放令の際に高山右近をしばらく島にかくまって庇護した。翌年の肥後国人一揆の討伐に功をあげる。 1588.7月九州征伐の功績で秀吉から肥後南半の24万石領主に任ぜられ宇土に移った。宇土城を新規に築城し、本拠とした。 1589(天正17)年、天草はキリシタン大名・小西行長の所領となる。その頃、天草には約60人の神父がいて、教会も30近くあったという。天草全島の人口、約3万人のうち約2万3千人の信者がいたといわれる。当時、志岐には美術アカデミアのような画学舎が置かれていた。イタリア人修道士のジョバンニ・ニコラオの指導の下、聖画や聖像の製作、賛美歌合唱用のオルガンや時計などの製作が行われていた。志岐で作られたオルガンは、竹のパイプを使って日本風にアレンジされたユニークなものだったという。 伴天連追放令で追われた神父を自領の小豆島にかくまった。文禄の役では先鋒部隊として加藤清正、黒田長政とともに朝鮮へ進攻。釜山や漢城の攻略や、平壌の防衛に功を挙げる。その後、李舜臣ら朝鮮水軍に制海権を握られ、兵力、補給が保てず苦戦した。この折、加藤、黒田らと対立関係になったと云われている。明との講和交渉に携わる。明の使者が秀吉を日本王に封じる旨を記した書と金印を携えて来日したところ、秀吉はこれに激し、このため講和は破綻、講和交渉の主導者だった行長は秀吉の強い怒りを買い、とりなしによって一命を救われる。慶長の役で、加藤清正と共に先鋒を命じられ、再び朝鮮へ進攻する。
|
| 【黒田孝高】(1546.12.22ー1604.4.19) | |
| キリシタン大名。姫路城に生まれる。小寺職隆の子で、はじめは小寺官兵衛と称した。1579年、黒田に姓を改めた。 織田信長の中国出兵のとき、毛利との和平のために、秀吉を助けた。 1585年、高山右近の影響で、大阪で洗礼を受ける。 1586年、九州の役では、秀吉の使者として西下し、宣教師を援助した。洗礼名はシメオン。小早川秀包、黒田長政たちを洗礼に導いた(彼は最も多くの武士を導いた)。 1600年、関ヶ原の役では徳川に与し、勝利を得て豊後を治めた。安部龍太郎「信長はなぜ葬られたのか」の「キリシタン十万の兵の根拠」p151は次のように記している。
1601年、筑前博多の新領に移った。 1604年に、伏見で病死。 |
|
官兵衛(如水)の葬儀に出席したマトス神父の1604(慶長4)年の報告書が次のように記している。
|
| 【蒲生氏郷】(1556ー1595.3.17)(弘治2年〜文禄4年) |
| キリシタン大名。会津若松城主。飛騨守。 近江国日野城主蒲生賢秀の子。13歳の時、織田信長の人質になる。その才を買われ織田信長の三女冬姫をめとった。1582(天正10)年の本能寺の変の際に、安土城城番であった父・賢秀と共に安土城に居た信長の妻子らを、蒲生氏の居城である日野城へ避難させ保護した。光秀の誘いに乗らず秀吉の下で軍功をたてた。 1584(天正12)年、伊勢松島城主。1585(天正13)年、茶人仲間の高山右近らの影響で大坂においてキリスト教の洗礼を受け、「レオン」というクリスチャンネームも得る。会津城下には教会やセミナリオ(神学校)が建てられ、南蛮(なんばん)文化が取り入れられていた。重臣の中にも切支丹が多かった。ユダヤ人にしてイタリア人宣教師・ロルテスを家臣とし、ローマへ使節団を送ろうともしていたという。ロルテスは蒲生の家臣として西洋の会計や測量技術をもたらした。「光秀はロルテスの影響を受けている」という推測も為されている。1590(天正18)年、巡察視のヴリニアーノが帰国する際には、「デウスが唯一の神であると言い」人々を驚かせたという。 1587(天正15)年、秀吉の九州征伐に従軍。1590(天正18)年、小田原、奥州の平定の功績によって、陸奥の会津を拝領し若松へ転封した。この氏郷の奥州への配置換えは伊達政宗を監視するという意味合いと、氏郷を出来るだけ畿内から遠ざけたい、という秀吉の意志とされる。この転封について、氏郷は京都から余りにも遠いことを悲嘆し「これで天下を望むべくもなくなった」と落涙したと伝えられている。 1592(文禄元)年、文禄の役が始まると、長駆、会津から肥前国名護屋城に参陣している。名護屋城滞在中に前田利家と徳川家康の配下の者同士の衝突が発生した際、氏郷はいち早く前田方に立ち、利家の親衛隊的な立場を示した。1593(文禄2).8月、秀吉の仲介で前田利家の次男・利政と娘の婚姻が成立する。 聚楽第で諸大名との雑談の中で、秀吉の後継者についての話題が出た時に、「徳川家康」という意見を退け「前田利家である」と言い放ち、「利家がダメなら次は自分の天下である」と豪語したとも言われる。 1595(文禄4).2.7日、伏見の蒲生屋敷で死去(享年40歳)。氏郷の最期を看取ったのは高山右近であったという。氏郷の死について「毒殺説」もある。辞世の句は、「限りあれば 吹かねと花は 散るものを 心短き 春の山風」。 茶事を嗜み、利休七哲の一人として数えられている(茶人大系図)。千利休が、秀吉の怒りにふれ亡くなると、その子、少庵(しょうあん)を会津領内に保護し、その後の茶道三千家への道筋をつくっている。「宗及記」等に、自ら茶会を催した記録がある。黒田家では、黒田孝高(シメオン)、黒田孝高の弟にして黒田直之、黒田二十四騎の一人・黒田長政(ダミアン)が洗礼を受けている。 |
| 【吉川広家】(1561年12月7日ー1625年10月22日)(永禄4年11月1日−寛永2年9月21日) | |
吉川広家と官兵衛の関係につき、最安部龍太郎「信長はなぜ葬られたのか」の「我らの仲が変わることはない」p170が次のように記している。
|
| 【支倉常長】(1571ー1622.8.7) |
|
1571年、山口常成の子として生まれ後、支倉時正の養子となる。洗礼名:ドン・フィリッポ・フランシスコ。 1609年、前フィリピン総督ドン・ロドリゴの一行がメキシコ(当時スペインの属領)への帰途難破した際救助し、日本とスペインとの交流が始まった。伊達政宗はヨーロッパに遣欧使節を送ることを決定し、遣欧使節はスペイン人のフランシスコ会宣教師ルイス・ソテロ Luis Sotelo をともない、常長は180人からの使節団を率いてローマに赴いた。 1612年、第一回目の使節として浦賀より出航するが遭難して失敗。1613年10月28日再度サン・ファン・バウティスタ号で月ノ浦を出航。その後、一行は太平洋を渡りメキシコに上陸し陸路で大西洋岸のベラクルスに、そこから大西洋を航海し、スペイン・アンダルーシア、コリア・デル・リオに上陸した。1615年1月30日国王フェリペ3世に謁見する。さらに陸路でローマに至り、1615年11月3日にローマ教皇パウルス5世に謁見した。ローマでは日本からの使節として温かく迎えられ貴族に列せられた。帰路もマドリードに立寄り再度フェリペ3世に謁見、使節団は数年間ヨーロッパに滞在した後、1620年9月20日に7年にも及ぶ航海の末帰国した。こうして大名(の名代)として日本から初めて欧州、ローマへの特務を果たしたが、すでに国内では禁教令による厳しいキリシタン弾圧が行われていることに落胆しつつその2年後に世を去った。 |
| 【織田秀信】(1580ー1605.6.24) |
| キリシタン武将。織田信長の嫡孫、信忠の長男。幼名、三法師。 本能寺の変で、二条御所にて父・信忠と共にいたが、前田玄以とともに脱出し尾張清洲城に避難した。信長と信忠父子亡き後、羽柴秀吉の後見で信忠の嫡男三法師(当時1、2歳)を擁立しようとする動きが高まり、織田家の家督を相続した。1582(天正10)年、秀吉によって安土に置かれた後、岐阜に移され、秀信と称した。1584(天正12)年、近江坂本城に移った。1592(文禄元)年、岐阜城に移り、美濃13万石を領有する。織田家は覇王の家門ではなく秀吉麾下の一大名にすぎなかった。 1595年、弟秀則とともにひそかに洗礼を受けたが、その後キリシタンとして振る舞った形跡はない。1600(慶長5)年、関ヶ原の役に先だって、石田三成からの誘いで西軍につき岐阜城に籠城するも、福島正則や池田輝政らの東軍先鋒隊によって攻撃され、降伏する。その後改易となり、高野山に追放された。1605.6.24(慶長10.5.8)日、同地で没した(享年26歳)。 織田家では織田信長の弟・織田有楽斎(ジョアン、利休七哲の一人。有楽斎は号) 、織田信忠の嫡男・織田秀信(三法師)、織田信忠の次男・織田秀則(パウロ)が洗礼を受けている。 |
| 【その他のキリシタン大名、武将】 |
| 他に宇喜多、中川秀政、市橋兵吉、瀬田佐馬之丞、吉川広家などがいる。受洗には至らなかったが、細川忠興、前田利家(洗礼名/オーギュスチン)、織田有楽斎など好意を持つものも多かった。細川忠興の妻ガラシャは、侍女清原マリヤ(ダリヨと共に入信した清原枝賢の娘)や右近の導きで入信した。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)