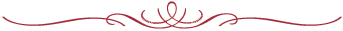
| 囲碁吉の天下六段の道、木鶏(もっけい)考、花伝書/至花道 |
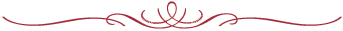
更新日/2025(平成31.5.1栄和改元/栄和7)年4.29日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
| ここで、「囲碁吉の天下六段の道、木鶏(もっけい)考、花伝書/至花道」を書きつけておく。 2005.6.4日、2015.3.3日再編集 囲碁吉拝 |
![]()
| 【木鶏(もっけい)考】 | ||||
| 心技体の「心」の鍛錬につき、荘子の達生篇に収められている中国故事の「木鶏(もっけい)譚」が参考になる。そのあらすじは、闘鶏好きの周の宣王の下問に答える形式で、紀悄子(きしょうし)という鶏を育てる名人が、最強の鶏育成について語る物語である。木彫りの鶏のように全く動じない最強の闘鶏を目指す訓話で、紀悄子の語りが秀逸なことにより世に知られている。これを囲碁吉流に意訳して確認しておくことにする。 | ||||
| 物語第一話。王が紀悄子に闘鶏を預ける。 10日ほど経過した或る日、王が仕上がり具合について質問する。
この下りは、「むやみに強がり」、「自己顕示欲」(空威張り)、「闘争心強過ぎ」がミソである。芸的に「未熟な粗野段階のお山の大将」であること、初心者特有の「単なる喧嘩好き」であることを教えている。 これを囲碁に例えれば次のような諭しになるのだろうか。相手の棋力を弁えず己の棋力を知らず「強がり」、「空威張り」、「闘争心強過ぎ」の三点セットの姿勢で対局している。相手の着手に対し大所高所の判断ができない未熟段階であるので、それが為に「大きいところに向かわず」、「小事に拘り過ぎ」、「突っかかり過ぎ」、後先考える分別なしの「攻め過ぎ」、相手の地が大きく見えてすぐ侵入する「せらい過ぎ」の傾向が強い。要するに「単なる喧嘩碁好き」の初級者段階にして「田舎初段」の段階である。と云うことになる。耳に痛い話ではある。 またこうも考えられる。県大会会場に向けて歩きながら発想した。囲碁の大会に出て、それが碁会所の大会だろうが県の大会だろうが全国大会だろうが構わないのだが、その出場資格を得る為の審査で、「むやみに強がり」、「空威張り」、「闘争心強過ぎ」が禍して通過できなかった。これを仮に一次審査とする。あるいは審査通過後の1回戦敗退の弁とも考えられる。 |
||||
物語第二話。更に10日ほど経過した或る日、王が質問する。
この下りは「身構え」、「いきり立つ」がミソである。これが初級者段階克服後に認められる特徴であることを教えている。多少は自制できるようになったが、依然として相手の仕掛けや出方に直反応し過剰興奮する。それは、芸的にまだまだ「未熟な拙(つたな)い段階」であることを教えている。逆からいうと、「直反応の過剰興奮」が次に克服すべき課題であることを教えている。 これを囲碁に例えれば次のような諭しになるのだろうか。相手からの本筋を離れたちょっかい誘導、引っ掻き等の挑発に未だに乗り易く、無用の反発傾向が依然として強い。勝負とは関係ないところでの見境のない「押せ押せのごり押し」、「調子に悪乗り」して相手の石を取ろうとする傾向、捻じ伏せて勝とうとする傾向が未だに残っており、要するに「未だ硬直型の柔軟さ不足、自制心不足レベル」の中級者段階」と云うことになる。耳に痛い話ではある。 またこうも考えられる。上述の囲碁の大会の出場資格を得る為の一次審査は通ったのだが、「身構え」、「いきり立つ」が禍して二次審査を通過できなかった。あるいは審査通過後の1回戦は勝ったが2回戦敗退の弁とも考えられる。 |
||||
物語第三話。更に10日経過した或る日、王が質問する。
この下りは「気負いたち」、「強さの誇示」がミソで、これが初級段階、中級段階克服後に未だ認められる特徴であることを教えている。どんな情況でも対応できるほど強くはなったが、「強さの誇示」をしている。それは、芸的にまだまだ「名人の域には達していない単なる強い段階」であることを教えている。逆からいうと、「強さの誇示」が次に克服すべき課題であることを教えている。 これを囲碁に例えれば次のような諭しになるのだろうか。無謀な攻撃や乱暴な手は打たなくなり、総じて大所高所の判断による自制ができるようになり、寄せも上手くなり、技術面ではいっぱしの強い上級者段階の打ち手になったが、今度は「強さを誇示する」ようになった。これではまだ十分ではない。あるいは、碁には強くなったが未だ徳分が足りないレベルと云う意味もあるのかも知れない。 またこうも考えられる。上述の囲碁の大会の出場資格を得る為の二次審査までは通ったのだが、「気負いたち」、「強さの誇示」が禍して通過できなかった。これを仮に三次審査とする。あるいは2回戦までは勝ったが3回戦敗退の弁とも考えられる。 |
||||
物語第四行程。さらに10日経過して王が下問する。
この下りは「泰然自若」がミソで、これが究極の心境である。この「泰然自若」が備わるようになれば「安心立命」の境地に至り、「鬼に金棒」の万全となることが教えられている。 これを囲碁に例えれば、闇雲に争わず、変化技に動じず、ちょっかいや引っ掻き、挑発に乗らず、我慢が必要なところでは辛抱強く耐え、変幻自在が要求されるところではしなやかに対応でき、手拍子打ちもなくなり、石が踊らずゆっくり柔らかく攻め、落ち着いてじっくり打てる域に入ったことになる。技術面、精神面共に申し分なく、これに徳分が備わり、この段階に至って漸く名人芸の水準に達する技量であることを示唆している。この段階に至ると自ずと無手勝流泰然自若の風格が備わっている。 またこうも考えられる。上述の囲碁の大会の出場資格を得る為の審査で三次審査まで通過して次の審査に挑んだところ、「泰然自若」、「安心立命」の境地に至っており見事に通過した。これを仮に四次審査とする。あるいは4回戦も勝利し遂に万全の天下無敵の境地に至ったとも考えられる。 |
||||
| 荘子は、この故事で、木鶏に例えて、達人、名人あるいは「真の王者たる者」の心得を隠喩している。真人(道を体得した人物)は、「空威張り」、「闘争心強過ぎ」、「いきり立ち」、「強さの誇示」の段階を経て遂には他者に惑わされることのない「泰然自若」の境地に達する。こうなると、鎮座しているだけで衆人の範となり徳の感化を為す。この有り様が王者の域であるとしている。木鶏の故事はこう訓話している。 | ||||
| この理解だけでは勿体なさ過ぎる。これをもう少し考察する。ここで云う木鶏とは達人ないしは名人あるいは王者の例えであろうが、それらの者と未熟者との違いは何かと問うのに、他の誰よりも真の勝ち方を知っている者を云うのではなかろうか。逆に未熟者とは未だ勝ち方を知らない一人よがりの者を云うのではなかろうか。 勝ち方を知る達人ないしは名人あるいは真の王者の要諦は、木鶏譚では「泰然自若の徳を持つ者」とあるが、考えてみればこれにも初等から高等まであるように思う。初等は平常心保持レベルへの戒めとなる。平常心とは何か。逆を考えれば良い。即ちアガル、動揺する、硬くなる、怖じける、腰が引ける、臆病になる等々の事態であり、これのない状態を云う。この状態を維持することが如何に難しいか。これもトレーニングを要する。こういう初等の泰然自若から名人の泰然自若へ向けての一歩一歩の積み重ねが「木鶏道」として注目されるべきではなかろうか。 2013.6.3日 囲碁吉拝 |
||||
「いまだ木鶏たりえず 「荘子」 /極楽坊主」参照。
|
| 【「昭和の大横綱」双葉山の「我、未だ木鶏たりえず」譚】 |
| プロとアマの差は、「木鶏譚」の教えるメンタルな面での差としても現れているように思える。「木鶏」という言葉はスポーツ選手に使用されることが多く、特に日本の格闘技(相撲、剣道、柔道)選手が好んで使用する。「昭和の大横綱」の双葉山が連勝記録を69でストップさせられた日、「我、未だ木鶏たりえず」と安岡正篤に打電したという故事がある。これの逸話は次の通り。 双葉山は子供の頃の事故で右目がほとんど見えず、右手小指の動きも不自由だった。この重大なハンデを乗り越えて相撲界に入り人気力士になった頃(横綱まえ)のこと。贔屓すじの紹介で、東洋学など博識なる陽明学者であり政治学、哲学者として高名な安岡正篤(やすおかまさひろ)(1898~1983年)と知己を得た。佐藤栄作はじめ昭和歴代首相の指南役を務め、さらに三菱グループ、東京電力、住友グループ、近鉄グループ等々日本の政財界のリーダー達に師と仰がれ、日本の進むべき道を常に指し示してきた人物である。敗戦の玉音放送で有名な「耐え難きを耐え」云々で知られる「終戦の詔勅」の草案者でもあり、「平成」の年号を考えた人でもある。 双葉山は或る時、その安岡氏と酒の席で一緒になった。この時、相撲は単なる勝ち負けでなく心を鍛錬し、天にいたる道だとする「木鶏」譚の教えを聞かされ、感銘した双葉山は「木鶏」を目指す相撲道を励み、昭和14年1月、69連勝の大記録を打ち立てた。その双葉山もついに安芸の海に破れ70連勝が阻まれた。大騒ぎの場内で双葉山は常と変わらぬ表情態度だった。彼は友人にして共に安岡を師とする中谷氏に電報「ワレイマダモッケイタリエズ フタバヤマ」を送った。中谷氏は ヨーロッパに向かうインド洋上の客船の中にいた安岡氏にこの電報を送り双葉山が敗れたことを知るところとなった。現役から引退した双葉山は時津風親方となり、のちに相撲協会理事長に就任した。昭和34年12月、時津風は安岡正篤の自宅を訪ね、「木鶏」の揮毫をお願いし稽古場に掲げた。これを契機に集まりが持たれるようになり、安岡正篤はこの会の名を「木鶏会」とした。 |
| 【花伝書/至花道】 | |
世阿弥は、「花伝書」から30年ほどたって新能理論として「至花道」を書く。「花伝書」は父親の観阿弥から継承した「花」を、「至花道」では自分が究明した「花」を説く。次のように記している。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)