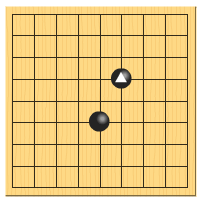 |

| 囲碁手筋用語篇2(カ行) |

更新日/2020(平成31、5.1栄和改元/栄和2).11.3日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
| ここで、囲碁用語と囲碁諺カ行を確認する。「ウィキペディア囲碁用語」、「囲碁事典」、「囲碁用語集」、「日中囲碁用語辞典」、「パンダネットの囲碁用語英訳集」、「囲碁用語和英辞書」、「囲碁用語集」、「Go Terms」等を参照する。 2015.01.17日再編集 |
| か行か |
| 外勢 |
| 隅に対して中央方向の外側に対して利いている勢力のことを云う。厚みとも云う。 |
| 外勢と実利(実利と外勢)は竜虎の戦い |
| 界に入りては、よろしく緩なるべし(入界緩宜) |
| カカエ(抱え)(kakae)(clutch) | ||||||
| 抱きかかえるような形で相手の石にアタリをして(ほぼ)逃げれない形にする手のこと。 | ||||||
|
| カカリ()(kakari)(approach move) | ||
| 主として隅の相手の石に辺の方から仕掛けていく手のこと。一間・二間・三間・ケイマ・大ゲイマ・大大ゲイマあたりをそう呼ぶことが多い。相手の単独でスミにある石の付近に打ち、攻撃するような手。 | ||
|
| 確定地()()() |
| 完全に囲い込んだわけではないが、ほぼ侵入が不可能なエリアを「確定地」と云う。 |
| 鶴翼()(kakuyoku)() |
| 鶴翼の陣 |
| カケ()(kake)() | ||||||||
| カケは囲碁用語の一つで、相手の石に接触せず、高い位置(上)から被せるように打って封鎖を図る、あるいは相手を低位に圧迫するような手のこと。動詞では「カケる」となる。 | ||||||||
例
|
| カケツギ()(kaketsugi)(diagonal connection、open connection, hanging connection) |
| ナナメに並んでいる石をツグこと。「キリ」を防ぐための手です。下の形がカケツギです。カタツギより1路ずらした場所に打ちます。 |
| カケツギにはノゾキあり(カケツギはノゾキ注意) |
| 欠け眼()(kakeme)(false eye) |
| 最終的につがないと石が取られてしまう形にされていて、一見眼に見えるが眼ではない所のこと。相手の石を欠け眼にする点は形をくずす急所である。「三子のまん中」をノゾくのも急所中の急所である。 |
| 欠け眼生き(かけめいき) |
| 欠け眼でも一周してつながっていることによって生きるのを欠け眼生きという。 |
| カス石 |
| 取られても大勢に影響しない石のこと。 |
| カス石は捨てよ(カス石逃げるべからず) |
| 形()(katachi)(shape) | ||||
| 眼を作りやすい、相手の攻撃を受けにくい、相手を封鎖しやすいなど何らかのメリットがある、部分的に定まった打ち方のことを指す。「ここはこう打つのが形」、「形を整えて反撃を狙う」といったように用いられる。逆に、石の働きが重複して能率が悪い形などを「悪形」、「愚形」などと表現する。「形」に従って打つことは絶対ではなく、愚形の妙手というものも存在するが、ある程度の形を身につけることは上達に重要である。 | ||||
|
| 肩()(kata)(shoulder) |
| 相手の石の斜め上の地点を云う。 |
| 肩ツキ()(katatsuki)(shoulder hit) | ||||||||
| 相手の肩のところへ打つ手を指す。文字通り、相手の石の「肩」を上方から衝く手段で、「カタツキ」とカタカナで表記されることも多い。動詞では「肩をつく」と表現される。肩ツキは、相手の模様を消す手段としてよく用いられる。 | ||||||||
例
|
| カタツギ(堅ツギ)(katatsugi)(solid connection) |
| ガタガタ血液ガタガタ |
| 固い方にツケよ |
| (If you plan to live inside enemy territory, play directly against his stones.) |
| 勝ち碁を勝ち切るむずかしさ |
| 勝ち碁を落とし負け碁を拾う |
| カッタカッタ(勝った勝った)とゲタの音 |
| 勝って奢(おご)らず、負けて腐らず |
| 勝てば官軍 |
| 活路(かつろ) |
| 「活路」(かつろ)とは、「苦しい状況から生き延びる方法のこと」です。 囲碁では、「石が生きる道」のことを「活路」と言います。 |
| カド()(kado)() | ||||
|
| 要(かなめ)石捨てるべからず、カス石逃げるべからず |
| 金持ち喧嘩(けんか)せず |
| カミトリ()()() |
| 相手の石1子を抱える手のこと。 |
| 亀の甲(かめのこう)(kamenoko)(tortoise shell) | ||
| 最短手数で、敵の二子を抜いた後の形。 | ||
|
| カラミ |
| カラんで攻めよ(カラミ、モタレは攻めの基本) |
| カラミ攻めは凌ぎにくい |
| 軽逃げは大ゲイマ |
| 勘定あって銭足らず |
| 観音開き()(kannonbiraki)(butterfly formation) | ||
|
||
|
||
| 観音開きは悪(愚)形 |
| 歓迎!三々入り |
| か行き |
| キカシ(利かし)(kikashi)(forcing move) | |||
| 相手が無視できないような手を打って相手に受けを強要させる着手を云う。 | |||
|
| 利(キ)キ |
| 雉(きじ)も鳴かずば撃たれまい |
| 傷があっては戦ができぬ |
| (解説) 「腹が減っては戦ができぬ」の代え囲碁諺 |
| 橘中の楽しみ |
| キツネその尾を濡らす |
| 昨日の淵は今日の瀬 |
| (解説) 「古今集」雑下の「世の中は 何か常なる 飛鳥(あすか)川 昨日の淵ぞ 今日は瀬になる」から。「昨日の花は今日の夢」に同じで、世の中はつねに動いていて、同じ状態が続くことはないのだという無常感を表現している。 |
| 君死に給うことなかれ |
| 肝っ玉が据わる |
| 急場 |
| 差し迫ってすぐに対処しなければならない局面の場所の状況をいう。 |
| 急場を知れ |
| 兄弟ゲンカ、兄弟ゲンカは身の破滅 |
| 今日の蛤(ハマグリ)は重い |
| 王座戦のトーナメントの一回戦、梶原武雄七段37歳-橋本昌二九段25歳対局の時の梶原の言葉) |
| 逆寄せ()() |
| 相手から打てば先手の所を、反対に自分の方から打ってよせること。先手で打たれることは大きいので、それを防いだ逆ヨセは、単なる後手のヨセと比較して倍ほど価値が大きい。 |
| 逆襲院(「学習院」のもじり) |
| キリ(切り、断)(kiri)(cut) | ||||
| 相手の石を切断し二つにする手を云い、相手のナナメに並んでいる石の間に打って、相手の石を分断する。「碁は断(キリ)に在り」(細川千仭)、「キリチガイ一方をノビよ」。 | ||||
|
||||
|
|
| キリチガイ(切り違え)(kirichigae)(cross cut) | |
| ハネられたときに切った場合で、お互いがキリ合っている形を云う。 | |
|
| キリチガイ一方をノビよ | |
| 相手にキリチガイを打たれた場合、一方の石をノビて強化しておくのがよい。多くは弱い石を、味方に連絡させるようにノビるとよい。下図、白1のキリチガイには黒2とノビて対応する。(本句は「アタリ、アタリのヘボ碁かな(アタリアタリはヘボ碁の見本)」の対句である。)
|
|
| (Extend one hand from the cross-cut.) |
| キリ賃 |
| 切り賃(きりちん)は、近代まで使われていた囲碁のルールの一つ。今日では使われていない。 |
| 切り賃のルールというのは「生きるための目を地に数えない」というもので、現代でいう2目の生きは、切り賃ルールのもとでは0目の地となり、20目の地は18目の地として計算される。一回相手の石を切るたびに二目もらえるので「切り賃」と呼ばれる。中国のある時代においては、切り賃が1目のときもあった。切り賃のルールは、古代の囲碁のルールが、純碁に近いことを示唆している。 |
| 棋力 |
| 囲碁・将棋などの強さのこと。具体的には段級位、レイティングなどで表す。 |
| キリンの顔()()() | |
|
| キリンの首()()() |
| 近所コウが多すぎる(と危険) |
| か行く |
| 愚形(ぐけい)()(stupid shape) | ||||
| 好形と逆に、石の働きが重複して石の効率が悪い姿になっている形を「愚形」と呼ぶ。本来広く展開できる石が不必要に固まっている状態などを呼ぶ。愚形の形を作ってしまうと、地が囲いにくくなったり、石を取られやすくなるなど、良くないことばかりとなる。下図ではここではD2よりC2が良い。 | ||||
|
||||
|
| 腐る |
| 相手の強い石にくっつくなどして、石の働きを失うこと。 |
| 腐った魚は目で分かる |
| クシ六 |
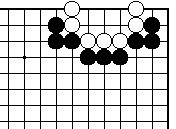 |
| 上図の形を「クシ六」と云う。黒先でも白生き。 |
| クシ形は生き(クシ六は生きなり) |
| (The comb formation is alive) |
| グズミ()(guzumi)(good empty triangle) | ||
| 何らかの理由があって自らアキ三角を作りに行く形を云う。動詞として「グズむ」「愚集む」とも。 | ||
黒1のような手がグズミ。「自らアキ三角を作りに行く形」と表現される。本来この手は自らアキ三角を作る手のため悪手に見えるが場合の手として打たれる。 |
||
|
| 靴底(「屈辱」のもじり) |
| 国破れて山河あり |
| 車の後押し()(kurumanoatooshi)(pushing from behind) | |
| 相手に遅れながら押していくこと。場合しだいだが、良くない事が多いとされている。 | |
| 車のあと押しヘボ碁の見本 | |
| 相手の石を必要以上にオシていくのは、敵を一歩先に進出させ、強化させるのでよくないという教え。下図のような状態を指す。
|
| 玄人(くろうと)、素人(しろうと)、上手、下手(囲碁用語が語源) |
| 「玄人」とは「ある分野について専門的な人」のことで、「素人」とは「専門的な知識や技術を持たない人」のことです。これは本来囲碁から生まれた言葉かどうか微妙です。 素人・玄人の語源については次のような説もある。平安時代には、「白塗りをしただけで芸のない遊芸人」を「白人(しろひと)」と呼び、それが室町時代に「しらうと」、江戸時代に「しろうと」に変化したというものです。「白人」が「素人」の漢字表記に変わった理由ははっきりしませんが、「素」には「ありのまま」という意味のほかに、「平凡な」「みすぼらしい」という意味もありますので、そこから来たとも考えられます。「素人」の対義語「玄人」は、「白人」に対して生じた言葉で、もともとは「黒人(くろひと)」と言ったそうです。「くろひと」が音便化して「くろうと」になったものです。「玄」も「黒」という意味です。「黒」よりも「玄」の方が奥深く容易ではない意味合いが強いので「玄人」と書くようになったそうです。 |
| か行け |
| 形勢判断 |
| 囲碁において、対局途中の局面を評価し、盤上の配置やハマの数から、どちらの対局者がどの 程度優勢かを判断すること。 |
| 形勢不利なら勝負手探せ |
| ケイマ(桂馬)(keima)(knight's move) | |
| 将棋の桂馬の動きと同じ形で、自分の石から2つ進んで右か左の場所に打つことを云う。自分の石から縦と横に1路と2路(2路と1路)離れた場所に跳ぶ手、またはその場所のこと。大ゲイマなどとの区別をはっきりさせるため、「小ゲイマ」という言葉が使われる時もある。 | |
|
|
|
| 桂馬ガケ()(keimagake)() |
| 桂馬ツギ()(keimatsugi)() |
| ケイマの急所 |
| ケイマの突き出し悪(俗)手の見本 | |||
| ケイマに対して出て行く手は相手を連絡させて安心させてしまう悪手となりやすい。下図黒1のような手。 | |||
|
| ケイマにツケコシ | ||||||
| ケイマにツケコシ切るべからず | ||||||
| ケイマの形の石に対しては、ツケコシに打つのが急所となる。下図黒1。 | ||||||
| (Strike at the waist of the knight's move) | ||||||
|
| ケイマの突き抜け |
| ケイマになっているところを突き抜けた形。突き抜けを許した方が悪い。 |
| 消し()()() |
| 相手の地を削減する目的で、相手の勢力圏に深く入らず、浅く侵入して地を手、その手段を云う。 |
| 消しは肩ツキ(消しは肩から)ケイマにツケコシ |
| ゲタ(門)(geta)(net) | |||||
| キリコミ状態になっている相手の石を取るテクニックのひとつで、相手の石に直接触れずに一路又は二路控えたところで待ち受ける手筋のことを云う。 | |||||
|
| 結局 |
| けんか小目()()() |
| 賢愚このなかに老ゆ |
| か行こ |
| 碁打(ごう)ちに時なし |
| 碁打ちは親の死に目に会えず |
| 碁で負けた恨みを将棋で晴らす |
| 碁なりせばコウを立てても活くべきを、死ぬるばかりは手もなかりけり |
| 碁に勝って勝負に負ける |
| 碁に負けてもコウに負けるな |
| 碁の力は局面評価能力と読みの力 |
| 碁は考えて打つものだが二手続けて考えるのはいただけん |
| 碁はバランスにあり |
| 碁は断にあり |
| 碁は封鎖にあり |
| 碁を打つより田を打て |
| 碁石(ごいし) |
| 囲碁、連珠に使用する用具で、黒・白2色の円形の玉である。碁笥(ごけ、ごす)ないし碁器(ごき)と呼ばれる容器に入れておく。単に「石」と呼ぶこともある。通常、黒石181個、白石180個を用意しておけば足りる。対局中に不足した場合はアゲハマを同数交換したり、余所から持ってくるなどの形で適宜補充する。連珠では「珠」と呼び、黒113個、白112個を用意するが、実際には60個程度ずつで差し支えない。 |
| コウ(劫)(kou)(ko)、コウ立て | ||||||||
| お互いの石がアタリになっており、取れば取り返しで無限に続く形のところ、その手段を云う。お互いが譲らなければいつまで経っても対局が終わらないので囲碁ルールで同型反復禁止としており、一度他の場所に打ってからでないと取り返すことができない。コウを取り返すために相手が受けそうなところ、相手が受けなければ二手連打することでソロバンが合いそうなところへ打つ手のことを「コウ立て」と云う。コウは漢字で「劫」と書き、仏教用語で非常に長い宇宙的世界の時間のことを云う。 | ||||||||
|
||||||||
|
| 好形()()() | ||||
|
石の働きが重複せず、打ちやすい姿であることを「好形」と表現する。眼が作りやすい、後に相手からの利かしや反撃の余地を与えないなどの状態を指す。 |
||||
|
| 好手のそばに悪手あり(好手と悪手は隣り合わせ) |
| (Good moves and bad moves are bedfellows.) |
| 古今同局なし |
| 攻撃は最大の防御なり(攻勢こそ身の守り) |
| 郷に入っては郷に従え |
| 碁会所で黙ってみている強い奴 |
| 小ケイマ()(kogeima)(small knight,s move) | |
| 黒1に対する白2のカカリが小ケイマガカリと云われる。将棋の駒の桂馬の動きを連想させるので「ケイマ」と呼ばれる。 | |
|
| 小ゲイマガカリ()(kogeimagakari)() |
| 小ゲイマシマリ()(kogeimashimari)(small-knight corner enclosure) |
| 虎穴に入らずんば虎子を得ず |
| これは囲碁&軍事用語であるように思われる。その趣意は、利を得るのにノーリスクはあり得ない、即ちある程度の危険をおかさないと利は得えられないのに、無傷で「濡れ手に粟」(「濡れ手で粟のつかみ取り」を省略した言葉。濡れた手で粟の実をつかむとやすやすとたくさんくっついてくることから、労せずして多くの利益を得ること、又はぼろもうけ、の意味がある
)、坊主丸儲けを図ろうとする精神に対して戒めの言葉と思われる。 囲碁の実例で言えば、コウに向かうよう仕掛けられた場合に、コウを避ける形で相手の要石を制し、当方の傷石を無難に凌ごうとする打ち方を指す。結果的に、安全と判断した石が攻められ頓死した場合、元に戻ってコウを引き受けるべきだった、コウを避けての丸儲けの発想が貧相だったと云うことになる。こういう場合に、「虎穴に入らずんば虎子を得ず」が身にしみる。 |
| ここで手洗う手水鉢(ちょうずばち) |
| ここは我慢の一手(ここは我慢のしどころ、ならぬ堪忍するが堪忍) |
| 小ナダレ()(konadare)(small avalanche joseki) |
| 小ザル()(kozaru)() |
| 2線の石から1線にスベリを打つことをサルスベリと云い、通常サルスベリといった場合大ゲイマスベリを指し、「大ザル」とも呼ぶ。小ゲイマスベリの場合は区別して「小ザル」と呼ぶことがある。大ザルは場合にもよるが先手8目ほどの大きなヨセであるため、ヨセの初期段階で打たれることが多い。藤沢秀行は、サルスベリの止め方を間違えて半目負けを喫したことがある。 |
| 小目(こもく)(komoku)(3-4 point) |
| 隅の星から辺に向かって一歩ずれた点。隅をとるために最初によく打たれる。 |
|
下図では、4手すべて小目に打たれている。
|
| コスミ(尖)(kosumi)(diagonal move) | |||||
| 味方の石からナナメの位置に打つ手段、その手のことを云う。二路をななめ(対角線方向)に簽す。例:コスむ、ヘボコスミ。 | |||||
|
| コスミツケ()(kosumitsuke )() | ||||
| コスんで相手の石につける手のこと。 | ||||
|
| 碁聖 |
| 五線・六線みだりにオスな |
| 五線、四線押すべからず、二線はうべからず |
| 五にも六にもならん |
| 五ノ五()()() |
| 碁盤上の位置を指す言葉。文字通り、碁盤の隅から数えて(5,5)の地点。布石の段階で隅の着点として稀に打たれる。「5の五」と表記されることも多い。昭和の新布石の時代に木谷實らによって試みられた他、2000年の碁聖戦など一時期の山下敬吾が愛用した。 |
| 五目中手は八手なり |
| 後手(ごて) |
| 二人で交互に着手するボードゲームにおいて、最初の一手(初手)を着手する側を先手と云い、その後の一手 (2手め)を着手する側を後手と云う。後手番ともいう。置き碁では、黒石を置かせた側を上手、置いた側を下手と いい、白を持つ上手から打ち始める。この場合は「後手」とは言わず「下手」という。 |
| 相手のある着手に対して相手が離れた場所に着手(手抜き)すると先の対局者に大きな得をする手段が残る場合 、先の対局者の着手を先手という。「手抜きする」ことを「手を抜く」ともいう。通常は先手と呼ばれる着手をされた相 手は手抜きせずに先の対局者に得をさせない着手で応じる。この着手を後手(で受ける)という。石を取るか取られ るかの戦いなどの場合、互いに手を抜けずに相手の着手の近くに着手することを繰り返す場合があり、その最後の 着手を「後手を引く」という。また、その最後の着手で「一段落」という。 |
| 後手をひく(囲碁用語が語源) |
| 後手の先 |
| この子、凡ならず |
| 実力制第四代名人・升田幸三が、小学生時代のひふみん(加藤一二三・九段)が指した将棋を見て、かけた言葉とされている。 |
| 碁盤(ごばん) |
| 碁石を打つ板のこと。盤の上面には縦横に直線が描かれ、それらは直角に交わっている。また、このような縦横の直線の交差により作られている格子状のものを、碁盤の目状と称することもある(京都市内の通りなど)。 |
| コビン()()() |
| コビンの急所(コビンがオキ殺しの急所) |
| 困ったときは手を抜け |
| 小目 |
| 隅の星の一路下に打つ手。 |
| 凝り形()(korigatachi)(overconcentrated shape、overconcentration) | |||
| 石がダブッており効率の悪い重複形になっていることを「凝り形」と云う。 | |||
|
| これは五目並べではないようだけど、何というゲームだろうね? |
| 転ぶ前の杖、転んでからの杖 |
| 根拠 |
| 石の生き死にに関わる眼形が作れそうなスペースのところを云う。封鎖されても、中だけで十分生きられるような状態を「根拠がある」と表現する。逆に、封鎖されると眼形に乏しい状態を「根拠がない」と表現する。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)