
| 囲碁手筋用語篇1(ア行) |

更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).8.26日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
| ここで、囲碁用語と囲碁諺ア行を確認する。「ウィキペディア囲碁用語」、「囲碁事典」、「囲碁用語集」、「日中囲碁用語辞典」、「パンダネットの囲碁用語英訳集」、「囲碁用語和英辞書」、「囲碁用語集」、「Go Terms」等を参照する。 2015.01.17日再編集 |
| あ行あ |
| 相碁もあれば井目(せいもく)の碁もある |
| 相手 |
| 相手の石をこちらの厚みに誘い込め(相手の石を我が厚みに誘い込め) |
| 相手の急所は我が急所(相手の急所は味方の急所) |
| 相手の進出、ボウシで止めよ |
| アオリ(あおり) |
| 相手の石の脱出進路を妨害せずに、むしろ催促する方法。模様を広げる時などに使用する。 |
| アキ三々に手あり |
| アキ三角(あきさんかく)(akisankaku)(empty triangle) | ||
| 四つ団子の一つが欠け3つの石が団子になっている形で、一子余計な石がある為にその分の働きがない愚形とされている。但し、欠けているところに相手の石があれば良い形でアキ三角とは言わない。 | ||
下図の黒の形がアキ三角である。黒○という不急の1手を打った形になっている。
|
||
| アキ三角と陣笠は愚形の見本 | ||
| (Don't make empty triangles)(Empty triangles are bad.) | ||
| アキ三角は作るな |
| アキ隅 |
| まだどちらの石も着手されていない、空いている隅のことを云う。 |
| 悪力(あくりき) |
| 「筋は悪いが読みの力の強い碁。妙なところで力を出す碁」を云う。典型的な実戦派を表現する言葉。 |
| 悪手が悪手を呼ぶ |
| アゲハマ |
| 対戦中に盤上の相手の石を取り上げた場合の、その取り上げた石をハマもしくはアゲハマと云う。数がわかるように手元に置いておかなければならず、通常碁笥の蓋を裏返して乗せておく。終局後、盤上の死んだ石もハマに加えられ、盤上の地の広さからハマを引いた合計が、白黒の対局者の総得点となる。整地では分かりやすいように、自分が取ったハマで相手の地を埋める(つまりハマが多いほど、相手の地が減る)。このようにハマを取っておくのが日本ルール。中国ルールでは、取った石を取った直後に相手の碁笥へ返却する。これは中国ルールでの計算の仕方が日本とは違い、領地内の空点のみを数えるのではなく、空点及び自分の石の数を数えるためである。 |
| アゴ(あご)(ago)() |
| 相手のコスんだ石からさらにコスめる位置で、相手のコスんだ石の最初の石と同一線上に単独の1子を打つこと。眼形の急所である。 |
| 浅く消すにはカタツキ・ボウシ |
| 味 |
| 味消し |
| アタリ(当たり)(ate、atari)(ate、atari)、アテ(当て) | |
| 相手が手を抜けば後1手で相手の石を取ることができる状態、もしくはそういう状態にする手のこと。将棋の「王手」みたいなもの。ただし、口にだして「アタリ」といわなくてもいい。 | |
| (Atari, atari is vulgar play) | |
| 下図の黒石はすべてアタリになっている。 | |
|
|
|
| やたらに次々とアタリをかけるのは味を消したり相手を強化させるだけで得にはならない。(本句は「切り違い一方伸びよ」の対句である)
|
|
| 上図左のように、白1から3などと次々にアタリをかけるのは黒の外勢を強化するお手伝いになってしまう。右のように単に白1とハネ、白3と進出する方が好形である。 |
| アタリ、アタリのヘボ碁かな(アタリアタリはヘボ碁の見本) |
| アタリ先手は媚薬 |
| アタリは最後まで打つな |
| (Keep inessential ataris till the end.) |
| あたり前だの英五郎 |
| 厚み()() |
| 外勢、壁とも云う。周囲へ威力を発揮している姿である。 |
| 厚い碁はコウ自慢 |
| 厚みに追いやれ(厚味から追うな、厚味へ追え) |
| 厚み地にするべからず(厚みを地にするな) |
| 厚みを囲うな(厚みを地にするな) |
| (Don't make territory near thickness) |
| 厚みに近よるな |
| (Keep away from thickness)。 |
| これは相手の厚みに対しても、自分の厚みに対しても言っている。 |
| アテ |
| 相手の石を完全に囲んで取る一歩手前の状態のこと。次に相手が逃げ出さなければ石を取られることになる。アタリの状態にすることを「アタリをかける」「アテる」などといい、アタリをかける手のことをアテと呼ぶ。 |
| アテコミ()(atekomi)(atekomi) | ||||||||
| 相手の石が斜めに並んでいる(コスんだ形)とき、その両方に接触させるように打って次の切断を狙う手のこと。動詞では「アテコむ」となる。「ガチャン」とも。 | ||||||||
アテコミの例
|
| 後の祭り |
| アマシ() |
| 先に地を稼ぎ、敵の攻撃をうまくかわして勝ちに持っていく打ち方。 |
| 荒らし(、、)、荒らす(arasu、lay waste to、wrest) |
| 上図のように、黒陣に白1と打ち込み以下9までと運べば、黒模様であった場所が白地に変わってしまい、荒らし成功となる。なお、相手が模様を張ってきた場合、「多少囲わせても最終的には勝てる」と判断するのであれば、模様の境界線付近に打って規模を削減するような打ち方もある。これは、「荒らし」ではなく消し(けし)と呼ばれる。 |
| 荒らし合い(、、)、 |
| 争碁に名局なし |
蟻が鯛(ありがたい)なら芋虫は鯨
| あれぇーっと絹を裂くような乙女の悲鳴 |
| 慌(あわ)てる乞食は貰いが少ない |
| あ行い |
| 囲碁九品(いごくぼん)()()() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
囲碁の九段~初段に対応する品格を云う。以下の通り。
|
| 囲碁殿堂(いごでんどう) |
| 囲碁の普及と発展に貢献した人物を顕彰するために設立された殿堂。日本棋院が2004年、創立80周年記念事業の一環として、野球殿堂を参考に設立した。 有識者や棋士らで構成する囲碁殿堂表彰委員会によって選考され、2004年5月の第1回では対象が江戸時代の人物に限定された。 殿堂入りした人物は、2004年11月15日に日本棋院内に開館する囲碁殿堂資料館(資料館内の研究室は「大阪商業大学アミューズメント産業研究所東京分室」となっている)に胸像と功績を掲げて顕彰される。 |
| 石の下()(ishinoshita)(under the stones) |
| 意図的に相手に石を取らせて空いた交点の急所に着手することで石を取る手筋のこと。実戦に現れることは稀で、詰碁の死活の問題で現れることが多い。 |
| 行き掛けの駄賃 |
| 行きはよいよい帰りは怖い |
| 行け行けドンドン |
| 生きている石から動くな |
| 生きている石の近くは小さい(苑田流格言) |
| 囲碁十訣 |
| 石()()() |
| 石音の反対に打て |
| 石取って碁に負ける(石取ってその碁に勝たず) |
| (Win the stones, lose the game) |
| 石飛んでその碁に勝たず |
| 石の効率「手割り」で考えよ |
| 石の余力を忘れるな |
| 石はからんで攻めよ |
| 石を裂く |
| 石を裂かれるのは最悪形、相手の石を裂くのは理想形。 |
| 医者の手余(あま)り |
| イタチの腹づけ()(itachinoharaduke)() |
| 板六(いたろく)()() |
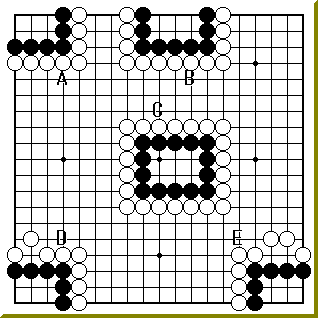 |
| 上図が板六の形である。黒は6目の地を縦横直線で囲んでいる。これで生きている。 但し、「隅の板六」はダメヅマリになると手入れが必要になる。櫛六との形の違いを踏まえる 必要がある。 |
| 板六の活き |
| 板のシメツケ避けるべし |
| 一局打てば百年の知己 |
| 一線トンで綱渡り |
| (Don't overlook the edge of the board) |
| 一線に妙手あり |
| 一線にワタリあり |
| 一にアキ隅、二にシマリかカカリ、三に大場の辺ヒラキ |
| 一隅、二辺、三中央、今もすたらぬ一・三・五 |
| (Corner, side, centre.) |
| 一に手抜き二に手抜き、三、四がなくて五も手抜き(アマ強豪で知られる西村修・氏の傑作囲碁格言) |
| 一手寄せ劫()(itteyoseko)(two step ko) |
| 一目置く(いちもくおく) |
| 「一目置く」(いちもくおく)も囲碁由来用語です。「自分より相手が優れていることを認め敬意を払うこと」を云う。強調して「一目も二目も置く」という場合もある。囲碁では、対戦者同士に実力差がある場合、ハンデとして弱い方があらかじめ碁盤に石を置いて対局することがある。これを「置き碁」という。通常、「黒が先手」と決まっているが、置き碁では、弱い方が対戦が始まる前に二目以上の碁石を置くので白が先手となる。将棋でも、上手の人から飛車・角行の大駒を取り除いて行う「二枚落ち」、あるいは角行だけを取り除く「角落ち」という。これをハンデ戦という。 |
| 1モク這えば10目の損 |
| 一間()(ikken)(one-space) |
| 既着のある石から一路あけて縦横に打った形のことを云う。 |
| 一間シマリ()(ikkenshimari)(one-space corner enclosure) |
| 一間高ガカリ()(ikkentakagakari)() |
| 相手の石に対して一路あけた同線上に打つカカリ手のこと。 |
| 一間トビ()(ikkentobi)(one-space jump) | ||||
| 石と石の間を1つスペースを空けて真っ直ぐに跳ぶこと。単に「トビ」とも言う。 | ||||
|
||||
|
| 一間バサミ()(ikkenbasami)(one space pincer) |
| 一間ビラキ()(ikkenbiraki)(one-space extension) |
| 石と石の間を1つ開けてヒラくこと。主に地を囲ったり、生きるためのスペースを広げるときに打つ手です。石と石の間がせまいのであまり地を囲うことには向いていません。しかし相手の陣地の中や、相手の勢力が強いところでは、2間ビラキよりも丈夫な1間ビラキの方が攻められにくくなる。 |
| 一方石に死になし |
| 一方碁は危険なり |
| 一方地に勝ちなし |
| 一方地を囲うな |
| 一方高ければ、一方低く(一方高く、一方低く) |
| 一日の長(いちじつのちょう) |
| 論語の「吾一日長乎爾、亟吾以也」(吾一日爾より長ずるを以て、吾を以てすることなかれ)(われいちにちなんじよりちょうずるをもって、われをもってすることなかれ)が由来。解釈は「私が君たちより少し年上だからと言って遠慮してはいけない」。これより発し、意味は、一日早く生まれた少し年長であること。転じて、ほんの少し経験、技能などが比べられる人よりも優れていることを云う。これを謙遜していう語。 「芸において彼に一日の長あり」。 |
| 犬の顔(いぬのかお)(inunokao)(dog's face) | ||||||
1間にトンだ形からケイマに打つ形。
猫の顔・犬の顔は凝形、石の働きに乏しく戦いに遅れます。馬の顔・キリンの顔は働いた石の形です。
|
| 犬が西向きゃ尾は東 |
| 今もすたらぬ一、三、五 |
| 命あっての物種(ものだね) |
| 岩より硬い梅鉢型 | |
|
|
| 梅鉢(うめばち)は好形のひとつ。ポン抜きの取り跡をツイだ形のこと。下図の黒のこと。 ただし余計な石がくっついていたりすると愚形になる。 |
| あ行う |
| 浮き石をつくるな |
| 浮き沈み |
| 受け()(uke)(respond)、受ける() |
| 相手の手に対し、その構想、目的を受け入れる形で対応する着手を云う。 |
| (いきなり行かず)受けねば次行くぞの手に良い手多し |
| 薄み()()() |
| 石の連絡が悪い欠点、弱点の箇所を指して云う。 |
| ウチカキ()(uchikaki)() |
| そこに打つことにより相手を[カケメ]にしてしまうこと。相手の石を欠け眼にする目的で打たれるホウリコミのこと。捨て石で味方の急を救う。カケメ、ダメズマリの筋。ウッテガエシ、ホウリコミでオイオトシ(ばたばた)を狙う。 |
| 打ち込み()(uchikomi)(invasion) |
| 相手の地を減らすために、相手の陣地や模様の中に飛び込んで行く侵略手のこと。 |
| 打ち出しはザルといえども小目なり |
| うっかりするなシッポ抜け |
| ウッテガエシ(打って返し)(uttegaeshi)(snapback) | ||||
| 放り込んで一子を取らせ、再度同じところに打って相手の石を取る一連の手順のこと。「えびで鯛を釣る」仕掛けになっている。黒1と打つと、白2で取られてしまうが、白の取った形がアタリになっているので、次に黒○と打つことで、白石3個を取ることができる。 | ||||
|
| 打つ手打つ手がダメばかり |
| 打つ前に一呼吸 |
| 内ダメ ()()() |
| 攻め合いの関係になっている2つの石の共通のダメのこと。次の図の[A]のダメ。[B]のダメのことは外ダメと呼ぶ。 |
| 内ヅケ ()(uchiduke)() |
| 宇宙の錐(きり、スイ)は、いずれその鋭鋒をあらわす |
| 馬の顔(うまのかお)(umanokao)(horse's face) | ||
1間にトンだ形からオオゲイマに打つ形。
|
||
|
| 梅鉢(うめばち)(umebachi)() | |
|
|
| 上図のようにポン抜いた後につないだ形のこと。黒はだんご石のようになって一見、悪い形のように見えるが意外と堅く勝率が高いため、梅鉢に負けなしと云われる。 | |
| 梅鉢に負けなし | |
| 売られた喧嘩を買う |
| あ行え |
| えぇてぇ元年(「えぇてぇ」を、元号じみた「永貞」と「良い手」に掛けている) |
| エグリボディー(「エブリ」を「えぐる」に掛けている) |
| 枝葉を攻めるな(枝葉を攻めては攻め合い負け ) |
| えらい今年や来年や |
| えらい目におうた道灌 (「おうた」を史上の「太田道灌」に掛けている) |
| あ行お |
| オイオトシ(追い落とし)(oiotoshi)(connect and die) | ||
| 連続でアタリとして相手の石を取る一連の手順のこと。 ツグ手を打っても引き続きアタリになり、取られてしまう状態をいう。別名をトントン、ツギオトシ、バタバタとも。 | ||
|
|
| 追うはケイマ、逃げるは一間 |
| おえんか白金バリウム(「おえんか」を「おえん」と化学の「塩化」に掛けている) |
| 大石死せず |
| 大模様は肩から消せ(大模様の消しは肩をつけ) |
| 大模様は浅く消せ |
| 大きく捨ててシメツケる |
| 大きく攻めよ |
| 大碁(おおご)の小碁(こご) |
| 大ザル8目 |
| 大中、小中(おおなかこなか、中手同士の攻め合いは大ナカの勝ち) |
| 大場より急場 |
| オオゲイマ()(oogeima)(large knight's move) | |
| 自分の石から縦と横に1路と3路(3路と1路)離れた場所に跳ぶ手、またはその場所のこと。 ケイマよりひとつ遠い位置のこと。下図。軽逃げは大ゲイマ。 | |
|
| 大ゲイマガカり() (ohgeimagakari)() |
| 大ゲイマシマリ() (oogeimashimari)(large knight's corner enclosure) |
| 大高目()(ohtakamoku)() |
| 大ザル()(ohzaru)(large monkey jump) |
| 2線から1線に大ゲイマにすべる手のこと。大ゲイマではなくケイマにすべる手は「小ザル」と呼ぶ。「大ザル8目」。 |
| 大中小中()(ohnakakonaka)() |
| 中手同士の攻め合いは大ナカの勝ち。 |
| 大ナダレ()(ohnadare)(large avalanche Top) |
| 大高目()()() | ||
| 碁盤上の位置を指す言葉。高高目とも呼ぶ。碁盤の隅から数えて(4,6)または(6,4)の地点。布石の段階で隅の着点としてまれに打たれる。小目へのカカリを受けての大型で複雑な変化を含む。 | ||
|
| 大場()()() |
| 打てば価値の大きい地点云う。 |
| 大目ハズシ(おおもくはずし、または大目外し)()() | ||
| 碁盤上の位置を指す言葉。碁盤の隅から数えて(3,6)または(6,3)の地点。 布石のバランスを取るために稀に打たれるが、 空き隅へ単独で打たれることは滅多にない。 | ||
|
| 往生しま(ン)こ |
| 岡(傍)目八目(おかめはちもく) |
| 「岡目八目」(おかめはちもく)も囲碁由来用語です。「岡目」とは他人がしていることをわきで見ていることを云い、「岡目八目」とは 「事の当事者よりも、そばで見ている第三者の方が物事の様子、物事の良し悪し、情勢や利害得失などを正しく判断できる」と云う意味になります。囲碁をわきから見ていると、実際に打っている人よりも冷静に幅広く考えられるので、実際に打たれた手よりも八目ぐらい得する手が見えると云う経験則に基づいております。なお「岡目」は「傍目」とも書きます。
余談ですが、「岡」の付く言葉としてはほかに、「岡惚(ぼ)れ」、「岡焼き」、「岡評議」があります。岡惚れは、わきから密かにその人に恋をすることで、岡焼きは、直接自分に関係がないのに、わきから他人の仲のいいのを妬(ねた)むことです。岡評議は、局外者の無用で無駄な評議のことです。「岡吟味」とも言います。 |
| 屋上屋を重ねる(屋根重ね) |
| オキ(おき、置き) |
| 相手の石にも自分の石にも触れないような位置に、文字通り「置く」ように打つ手のこと。動詞では「置く」となる。多くの場合一線や二線など辺の低い位置の、敵陣の急所に打つケースを指す。 |
| 置碁(置き碁、おきご) |
| 棋力の差がある二人が対局する場合、ハンデとしてあらかじめ碁盤に石を置いて対局することをいう。将棋の「駒落ち戦」に相当する。実力が下位の者を下手(したて)、上位の者を上手(うわて)と呼び、下手は黒石、上手は白石を持つ。通常の対局では黒が先に着手して対局が開始されるが、置き碁の場合は黒があらかじめ盤上に石を置き(棋譜の記録上は着手とされない)、白が先に着手して対局が開始される。あらかじめ置く石を置き石と言い、その数は対局者の実力差に応じて調整される。置き石の数によって9子局、8子局、…2子局のように呼ぶ。「1子局」という言い方はない。置き碁と互先の間に位置づけられるものに定先がある。これは下手が常に先手番を持ち、コミなしで打つ手合いを云う。 |
| オサエ(押え)(osae)(block) | ||||
| 石が接触している箇所で、相手の進路を止める手のこと。 相手の石がノビルのを防止するような手。進出を封じる。守り。上から頭を下へ按える。マゲてオサエコム。封鎖。形式としてはハネの形になるもの、マガリの形になるものなどが含まれ、きちんとした定義は難しい。二段オサエ(ハネ)。 | ||||
|
| オシ(押し)()() | |
| 相手の石に押しつけるように沿って打つ手のことを云う。相手を圧迫する効果がある。下図の白1と打つのがオシ。オサれると黒は2と受けることになる。 | |
相手の石にノビを促すような手。
|
| オシツブシ(押し潰し)()() | ||||||
| 相手の二団以上の石を同時にアタリにし、二眼を確保する手段。文字通り相手を押しつぶすイメージであることからつけられた。着手禁止点を利用して生きる手筋である。 | ||||||
例
|
| 恐れ入谷の鬼子母神 |
| お互いに秘術を尽くして、負けよう、負けようと努力している() |
| お尻かじり虫 |
| 重くして攻めよ |
| 温泉気分、温泉に入る |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)