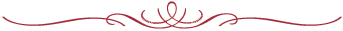
| 人はなぜ囲碁に興ずるのか考 |
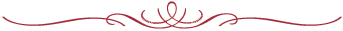
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).5.23日
| (囲碁吉のショートメッセージ) |
| ここで、「人はなぜ囲碁に興ずるのか考」を書きつけておく。 2005.6.4日、2015.3.3日再編集 囲碁吉拝 |
![]()
| 【人はなぜ囲碁に興ずるのか考】 |
| 人はなぜ囲碁に興ずるのだろうか。囲碁のみではない将棋、マージャン、チェス、トランプ、かるたも然りであろうが右代表として囲碁と記すことにする。囲碁の楽しさを理解する為には、いったん嵌まって味わわないと分からない解けないだろう。拙者の理解は、打ってみてとにかく面白い、その面白さは人生の処世術に似ているところにある、全てが似ているとかるたいうのではないが大まかな構えが共通しており良き知恵を授かる気がしてならない。ここに囲碁を愛好する所以がある。 |
| もう少し具体的に見ると、囲碁の駆け引きが人生のそれと近似している。自分の言い分を通し相手の言い分を聞き且つ折り合いをつけながら着手して行く道中が人生の軋轢とそっくりなように思う訳である。ここで必要になるのは良き分別である。これを知り鍛えることは人生に大いに役立つと思っている。ここに囲碁を愛好する所以がある。 |
| その駆け引きは、平時のそれと戦時のそれに分かれる。平時の駆け引きに於いては、相手が攻めてくれば応じ、守ればこちらも守る、その巧拙を問う。平時はやがて迎える戦時の準備であり戦線構築でもある。一応ここまでが布石、序盤となる。その間の手談が堪らない魅力である。 |
| 次に中盤を迎える。中盤は平時の続きの場合もあるし、戦時への突入の時機でもある。戦時のそれは闘うべきときには闘い、引くべきときには引く。あるいはこちらから仕掛ける場合もある。その間の手談が堪らない魅力である。 |
| 中盤が終ると終盤、ヨセとなる。終盤は混戦の場合には勝負不透明のままヨセに入る。優勢の場合には上手なクロージング狙いになる。非勢の場合には形勢逆転するまで勝負手連発が必要となる。その間の手談が堪らない魅力である。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)