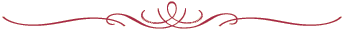
| 折々のれんだいこ提言 |
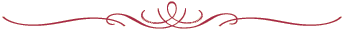
(最新見直し2005.12.9日)
| 著作権法はこのまま進めば今後お化け法になりそうだ。思想的な位置付けの無いまま次第に条文が太りつづけており、今では生活の隅々にまで適用がおよびそうな気配でさえある。本末転倒現象著しい格好の法として著作権法は考察されるに値する。 れんだいこ見解はこうだ。この権利発生が幅広く市民社会へ定着し始めたのはたかだか百年来(詳しいことを知りたいが)のことであり、それも圧力団体の要請を迎合的に取り入れ続けており、とはいえ理論的に功罪の認否は為されないまま進行中と考える。現下の風潮は、何でもかんにでも権利癖つければ良いとするかのように競って権利主張に向かいつつある。法益として守ること自体には咎が無いのかも知れないが、そのことによって大衆市民社会の文化的経済的基盤に損傷を与えていくことは許されない、つまり、むやみやたらに拡大していくのではなく厳しく精査されねばならないのではなかろうか、と考える。 「元々は文化の保護法」として生まれたものが、文化圧殺の道具として機能している愚かさが見えないわけではない。「公共と人権の関係。片方を無制限に認めると矛盾が起る」と云われている所以である。「自然発生権か届け出権なのか」についても見解が分かれている。「常識的な慣行と法律的規制の内容との擦り合わせ」が必要とも云われている。 著作権は、 1・著作者人格権、2・財産権としての著作利権、3・財産権としての請求権から構成されているようである。この種の権利の流れを概括すれば、まず発明的な知的所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、工業所有権等々)が第一次的に認められてきた歴史がある。次に、文芸的な知的所有権(作家の著作権、音楽の作詞作曲権、レコード印税権等々)が第二次的に認められてきた歴史がある。これに続いて、情報シンクタンク機能を持つマスコミ、図書館、政党等が「知の囲い込み」をするようになった。これを第三次知的所有権とみなせるだろうか。しかし、この頃から著作権の本来の吟味が薄れ、文字物その類似物一般に対する何でも保護対象とされつつあり、これに対しては未だ社会的に確認されていないと考えたい。続いて最近問題となってきつつあるのがインターネット上でのホームページ、掲示板での著作権利、漫画、パロディーなどの権利であり、これは第四次知的所有権とみなすべきかも知れない。次第に市民社会の内部の深いところにまで降りてきつつあるやに見受けられる。ここに看過出来ない問題性がある。 著作権が大衆的に普及し主張され始めるや、法的規制面とルール、マナー面で確認せねばならぬことが増えてきた。○・「模写と引用と改変」の原則とマナー、○・「紹介、転載、引用の要領、許諾を要するのか、任意に為せば公表権の侵害なるものにあたるのか」、○・「親告罪」規定問題等々。 爾来、市民社会では、相手様に迷惑をかけない限り互いに為すことが認められてきた。しかし、近時はこの理屈だけでは通じなくなりつつある。相手の名誉権、人格権、肖像権、人格権、財産権に対する侵害を為してはならないといういわば「準公理」的なものが尊重されねばならない時代に入りつつある。しかも、市民社会を健全育成する為と言う美名でこれが為されつつある。 果たしてそうだろうか。著作権をアンダーロー的に市民間のマナー確立に治めるのならば問題は無かろう。これを権利規定として条文化させ国家規制にまでせねばならない必然性がそれほどあるのだろうか。安易にこうした趨勢に流されること無く、表現の自由に対する裏側からの規制ではなかろうか、という観点からの考察をしておくべきではなかろうか。 |
| 門外漢のれんだいこが関心を持つのは、インターネット上のホームページ、掲示板における著作権の範囲と規制力に関するものである。それはもっとも新しいテーマであるが、ある意味で議論の余地が集約的でもある。驚くことに、これから解明されねばならないこれらのことに対して、既にあたかも既存の著作権法が適用されているかのようにふるまう一群の愛好家が存在する。しかも、連中は、ホームページ、掲示板の隆盛化の為の地ならしであるという美名で管理人権限を行使している。 それは、クロを白と言い含める逆さ言辞であろう。れんだいこの体験上、これだけ重宝なインターネットを活用するのにその価値に値する使用量を払っている訳ではない。それはどうやらインターネットのおいたちに関係しているらしい。そもそも軍事用に開発されたインターネット通信が民営用に転用された際、れんだいこの理解に誤り無ければ経費を別にすれば無料であった。このことは、その果実のほうに関心が向けられていた為と思われる。 インターネットの特殊性は、情報の公開性にも認められる。この空間に情報を載せた瞬間にいつでも誰でも認知し、望めば共有することが出来る。もしこの原理を厭うのであれば、インターネット空間に登場せねば良いだけの事ではなかろうか。せめて、会員制パスワード方式にして特定の者のみ入れる方式にすべきではなかろうか。そういう自律的な自由があるところに無防備にのこのこ登場してきながら、外在的な著作権法を振り回すなぞ滑稽では無かろうか。 ホームページのリンクに許可が要るいないという論議がある。れんだいこはナンセンスと云いたい。許可制を主張する者が、まずもってせめて会員制パスワード方式によるエンター方式にすべきではないのか。それを為さずしてリンク制限を加えるなどというのは、紳士面した者が云おうとも野蛮な精神ではなかろうか。 転載も同じことが云えよう。但し、転載であることの断りが要件で、情報の発信元を明記するのがマナーということになるだろう。しかし、これを法的規制まで高めるべきかどうか、それはまた別の論議である。付言すれば、サイト管理者には、コーナーごとに転載者向けの発信元マークとかを用意しておく親切さが要るかも知れない。コピー時に自動的に取り込めれば手間暇が省けることになるから。 「引用」の場合、転載と同様情報の発信元が明記されるべきだろう。この場合も同様に、サイト管理者には、コーナーごとに引用者向けの発信元マークとかを用意しておく親切さが要るかも知れない。 「引用」の場合、タイトル名の表記を廻って若干の問題が起こることがある。サイト内でリンク方式で次第に内容が狭められている場合、引用者は、タイトル名を表記する場合に困難に遭遇する場合がある。そもそものタイトルから最終のタイトルを表記すれば問題は起こらないが、非情に長く煩雑になる場合がある。この場合、引用者の判断において内容の意味を正確に継承する形での改題する自由が与えられても良いように思われる。その改題が不適切であれば、被引用者は引用者に対してクレーム請求権があるという方式でどうだろうか。 「パロディー」の場合、どう待遇すべきだろうか。 以上のことは、法規制の対象以前のマナー原則としても考えられる。問題は、これ以降の解明課題としての著作権についてである。れんだいこか思うに、インターネット上でのサイトの場合、活字出版物との大きな相違として容易に変更可能という状態の違いが考慮されてしかるべきではなかろうか。この違いは案外と無視されているが、ブックとしての著作権との違いは相応に認められねばならないと考える。 但し、サイトには一定の著作権が認められるのは良しとすべきだろう。とはいえ、解明すべき事項は多い。サイト運営者が非営利的な場合と営利的な場合。更に、個人の場合と組織の場合。更に、思想、宗教、政治運動、ジャーナル等に関するものの場合と文芸的なものの場合。これらは、同じ著作権にであっても、保護される法益が異なるべきではなかろうか。 「掲示板」の場合、どう待遇すべきだろうか。 「チャット」の場合、どう待遇すべきだろうか。 |
| 【素粒子理論からの考察】 |
| インターネットサイトは書き換え可能性に特徴があり、この件での出版物との識別(以下略)。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)