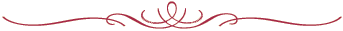
| クラブキャッツアイ訴訟事件 |
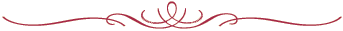
(最新見直し2008.3.3日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「クラブ・キャッツアイのカラオケ訴訟」を確認しておく。 2008.3.3日 れんだいこ拝 |
| 【「クラブ・キャッツアイ事件」】 | |
|
クラブ・キャッツアイのカラオケ訴訟で、民事訴訟「1988(昭和63).3.15音楽著作権侵害差止等クラブキャッツアイ事件、最高裁第三小法廷判決」が出ている。これを検証する。本件は、最高裁判決で、カラオケスナック等におけるカラオケ演奏を伴奏とする客の歌唱も、スナック経営者による歌唱と同視しうるものであるとして、演奏権の侵害になると判示している。
|
| 【「クラブ・キャッツアイ事件最高裁判決文」】 | |
|
「クラブ・キャッツアイ 事件(最判昭和63.3.15日)」を転載しておく。
|
| 「クラブ・キャッツアイ事件」の詳細は不明であるが、どうやら著作権料を取るなら歌った当人から取れ、店は機械を設置したに過ぎないと主張していたようである。この主張は大いに言い分が有ると云うべきであろう。ところが、裁判所はこの問題を解明せず、客の歌唱は店の歌唱と見なされる云々論で「著作権法上は、スナック側による歌唱と同視し得るとして、権利者の許諾なくカラオケ演奏を実施することは演奏権侵害を構成するとした」ようである。権力に阿る判決しか出ないと云う見本だろう。 |
| 判決に拠れば、最高裁はジャスラック的法理論をそのまま踏襲しており、店舗内でのカラオケ利用につき著作権違反だとしており、その対価請求を店側に負わせるべしとしている。上告人(クラブ・キャッツアイ)は、1、カラオケテープの製作に当たり、著作権者に対して使用料が支払われているので、ジャスラック的対価請求は二重取りである。2、対価請求するなら歌唱者に請求するのが筋で、店側に支払い義務は無い、としたようである。 裁判官伊藤正己氏が若干の異論を唱えている。上告人らに演奏権侵害の不法行為責任を負わせるべきとする法理論を踏襲するが、店側の関与しない客側の任意歌唱についてまで店側に負担さすべきだろうかと異論を述べている。「しかしながら、客のみが歌唱する場合についてまで、営業主たる上告人らをもつて音楽著作物の利用主体と捉えることは、いささか不自然であり、無理な解釈ではないかと考える」としている。 多数意見は、客側の単独利用であっても店側の管理下にある以上同視し得るとしているのに対し、「客は、上告人らとの間の雇用や請負等の契約に基づき、あるいは上告人らに対する何らかの義務として歌唱しているわけではなく、歌唱するかしないかは全く客の自由に任されているのであり、その自由意思によつて音楽著作物の利用が行われているのであるから、営業主たる上告人らが主体的に音楽著作物の利用にかかわつているということはできず、したがつて、客による歌唱は、音楽著作物の利用について、ホステス等従業員による歌唱とは区別して考えるべきであり、これを上告人らによる歌唱と同視するのは、擬制的にすぎて相当でないといわざるをえない」としている。 以上の考察から、歌唱による対価請求論は粗雑であるとして、カラオケ装置の再生即ち演奏権侵害論として理論構築すべしとしている。 れんだいこは、多数意見も少数意見も狂っていると考える。何とならば、本来の著作権は、著作者の権利を利用して営業物を制作する業者に対して規制するものであり、末端の利用段階にまで押し広げるものではないと考えるからである。流通で云うところの川上と川下の差である。 判例が、上記川上と川下の質的差を弁えず全域全方位に於いて著作権を適用せしめ始めたところに混乱の原因があるのであり、川下不適用の判決を出さない限り解決しないであろう。とりあえず以上をコメントしておく。 2008.3.3日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)