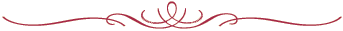
| 俰俙俽俼俙俠偺僇儔僆働:慽徸偦偺楌巎侾 |
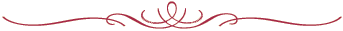
丂乮嵟怴尒捈偟俀侽侽俈丏俀丏俁擔乯
| 丂乮傟傫偩偄偙偺僔儑乕僩儊僢僙乕僕乯 |
| 丂 丂俀侽侽俇丏係丏俀侽擔丂傟傫偩偄偙攓 |
| 亂挊嶌尃朄偺晬懃侾係忦攑巭偺惀旕傪栤偊亃 | |||||
丂乽拞彫婇嬈巤嶔俥俙俻丒憡択帠椺乿偺乽憡択帠椺偦偺侾俁丗挊嶌尃巊梡椏傪弰傞僩儔僽儖乿偵師偺傛偆偵婰偝傟偰偄傞丅
|
|||||
丂偙傟偵傛傟偽丄尦乆偼丄挊嶌尃朄偺晬懃侾係忦偱丄揦曑偵墬偗傞俛俧俵傗儗僐乕僪丄俠俢丄僥乕僾曻壒偼帺桼偱偁偭偨傕偺偑丄俀侽侽侽乮暯惉侾俀乯丏侾寧偵巤峴偝傟偨夵惓挊嶌尃朄偱偙偺忦崁偑攑巭偝傟丄惗墘憈偱偁傞偐丄儗僐乕僪墘憈乮儗僐乕僪傗俠俢傪棳偡乯偱偁傞偐傪栤傢偢挊嶌尃幰偺嫋戻偑昁梫偵側偭偨丄偲偄偆偙偲偵側傞丅偙傟傕丄乽夵惓乿偲偐乽夵妚乿偲偐乽妚怴乿偲偄偆昞尰偱峴傢傟傞夵埆偩傠偆丅 丂偙偺夞摎偼丄怴朄偵嫆傟偽偙偆側傞偲偟偰丄擔杮壒妝挊嶌尃嫤夛偵栤偄崌傢偣傞傛偆巜摫偟偰偄傞偑丄栶強婡娭偲偟偰偼巇曽側偄偺偐傕抦傟側偄丅杮棃偼丄挊嶌尃朄偺晬懃侾係忦攑巭偺惀旕傪栤偆傕偺偱側偗傟偽側傞傑偄丅 丂俀侽侽俈丏俀丏俈擔丂傟傫偩偄偙攓 |
| 亂棎晳偡傞俰俙俽俼俙俠慽徸峫亃 | ||
丂乽俰俙俽俼俙俠傪峫偊傞乿丄乽J-CAST僯儏乕僗乿偵俰俙俽俼俙俠栤戣偺嬶懱揑帠椺偑悢懡偔曬崘偝傟偰偄傞丅僇儔僆働娭學偱偙傟傪尒傞偲師偺傛偆側帠椺偑偁傞丅傟傫偩偄偙偑堄栿偡傞丅
丂俀侽侽係丏俋丏侾俁擔嵞曇廤丂傟傫偩偄偙攓 |
| 亂乽棳偟偺僊僞乕乿偼墘憈尃偺怤奞偩偭偰偝亃 |
| 丂墘壧偺悽奅偱偍側偠傒偺乽棳偟偺僊僞乕乿傕丄挊嶌尃拞偺忋墘丒墘憈尃偺怤奞偵摉偨傞偲偝傟尩偟偔庢掲傝偝傟偮偮偁傞丅偙傟偼丄晄摿掕懡悢乮岞廜乯偺慜偱帺暘偺妝嬋傪墘憈偡傞偙偲傪嬛巭偱偒傞尃棙偱丄嵟崅嵸偼侾俋俉俉乮徍榓俇俁乯擭丄堸怘揦偺僇儔僆働偱媞偑壧偆峴堊傪丄揦懁偺墘憈峴堊偲摨偠傕偺偲傒側偟丄挊嶌尃朄忋偺墘憈尃偺怤奞偵側傞偲偺敾寛傪壓偟偰偄傞丅 |
| 亂乽僕儍僘媔拑僗儚儞慽徸乿亃乮乽怴妰JAZZ媔拑SWAN乿乯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
丂俀侽侽俁丏侾侾丏侾俋擔丄擔杮壒妝挊嶌尃嫤夛乮JASRAC)偼怴妰抧嵸偵懳偟丄怴妰偺榁曑僕儍僘媔拑乽僗儚儞乿偑丄揦撪墘憈偱巊傢傟傞嬋偺挊嶌尃巊梡椏屲昐屲廫枩墌梋傝傪巟暐偭偰偄側偄偲偟偰丄墘憈嵎偟巭傔丄妝婍丄儗僐乕僪偺嵎偟墴偝偊側偳傪媮傔傞壖張暘傪怽偟棫偰偨丅摨條偺惪媮偼懠偺壒妝媔拑偵懳偟偰傕嫮傔傜傟偰偄傞丅 丂俀侽侽俁丏侾俀丏侾俁擔丄怴妰擔曬偼僆僺僯僆儞婰帠偱偙偺栤戣傪庢傝忋偘丄乽僕儍僘暥壔偺摂徚偝側偄偱丂榁曑傗傓側偔暵揦傕丂墘憈巊梡椏偑廳埑偵乿婰帠傪宖嵹偟偰偄傞丅偙傟傪徯夘偡傞丅
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
丂偄偢傟乽JASRAC栤戣乿偑幮夛栤戣偵側傝偦偆側婥攝傪姶偠傞丅懡偔偺幰偑乽慡曽埵揑挊嶌尃乿傪擣掕偟偰偄傞屘偵偙偆偄偆杮枛揮搢帠懺偑敪惗偡傞丅乽慡曽埵揑挊嶌尃乿偲偼梫偡傞偵尰戙偺娭強惻偱偁傞丅偦偺愄丄帥幮丄慻崌乮僊儖僪乯偑枩擻幮夛傪嶌傝弌偟丄愴崙晲彨丒怐揷怣挿偑偙傟傜傪揚攑偟乽妝巗妝嵗惂乿傪摫擖偟偨丅偙傟偵傛傝宱嵪偺妶惈壔偑懀偝傟偨偺偼廃抦偺偙偲偱偁傠偆丅偙傟傪巚偊偽丄乽抦揑娭強惻乿偲偄偆偺偼摿庩尰戙偺宍懺偱偁傞偐傜丄戞擇偺怣挿偑尰傟側偄偲偄偗側偄偲偄偆偙偲偵側傞丅 丂乽挊嶌尃巊梡椏傪巟暐偆昁梫偑偁傞偺偼暘傞偑丄廂擖偵墳偠偨嶼掕傪偟偰傎偟偄乿側偳偲偄偆庛崢偱偼偄偢傟丄曎岇巑偺岥幵偵忔偣傜傟偰偟傑偆偱偁傠偆丅曎岇巑偺抦惈傪塎偆偺偵丄朄揘妛揑側抦惈偼奆栚昻崲偱丄扨偵朄暥傪怑恖揑媄朄偱憖傞弍巘偵夁偓側偄丅屘偵丄曎岇巑偵婜懸偟偰傒偰傕壗傜帠懺偼曄傢傜側偄偙偲傪抦傞傋偒偱偁傞丅傓偟傠丄庤慜枴慩側偑傜傟傫偩偄偙偺娤揰傪墖梡偟偨傎偆偑傛傎偳尗柧偱偁傞丅 丂偙偺栤戣偼丄挊嶌尃偦偺傕偺偺擣幆娫堘偄偐傜敪惗偟偰偄傞丅壖偵偦偺傛偆側尃棙偑乽慡曽埵揑挊嶌尃乿偲偟偰擣傔傜傟傞偵偟偰傕丄娞怱側帠偑慜採偵偝傟偰偄側偗傟偽偍偐偟偄丅娞怱側帠偲偼丄乽慡曽埵揑挊嶌尃乿偺揔梡偼彮側偔偲傕丄乽亀幮夛揑暥壔丄恖柉戝廜偺惗妶暉巸偺岦忋偵帒偡傞傕偺偱側偗傟偽側傜側偄偲偄偆岞棟亁偲掞怗偣偞傞尷傝偵偍偄偰偱偁傞乿偲偄偆朄棟榑偲偺惍崌惈偑栤傢傟偹偽側傜側偄丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅 丂偙偺曎偊偑柍偄偐傜乽JASRAC揑嫮尃乿偑旊傝捠傝丄壒嬋嶻嬈偺曐岇堢惉偲偄偆旤柤偺壓偱偺悐戅偑傕偨傜偝傟丄柧傜偐偵棙尃壔偟夁偓偰偄傞偲偄偆偺偵丄偙傟偵扤傕峈偡傞偙偲偑偱偒側偄偲偄偆杤抦惈揑帠懺偵捛偄崬傑傟傞偙偲偵側傞丅傟傫偩偄偙偵塢傢偣傟偽丄乽慡曽埵揑挊嶌尃偦偺傕偺偑僔儘傾儕棟榑乿側偺偱偁傝丄恖柉戝廜偼偙傟偵摤傢偹偽側傜側偄丅偟偐偟偩丄儅僗僐儈傕搒崌偺椙偄乽僕儍乕僫儖挊嶌尃乿傪庡挘偟偰偄傞栿偩偐傜丄僀儞僥儕妛夛傕傑偨峏偵椫傪偐偗偨傛偆側乽抦揑強桳尃乿偺庡挘偵寣娽乮偪傑側偙乯側栿偩偐傜丄楢拞偑JASRAC堎媍傪彞偊傞偙偲偼偱偒偼偟側偄丅摨偠寠偺儉僕僫偱偟偐側偄丅偮傑傝丄扤傕偁偰偵側傜側偄丄彆偗偰偔傟側偄丅 丂傟傫偩偄偙偼庡挘偡傞丅寷朄偺嬻摯壔尰徾偵墳偠偰奺奅偑摼庤彑庤側朄棟榑傪怳傝夞偟偰偍傝丄屳偄偵恎摦偒庢傟側偄幮夛傊撍擖偟偮偮偁傞丅偮傑傝丄幮夛偑傾僲儈乕壔偟偮偮偁傞丅偙偆偟偨愜偵偼丄崱堦搙崙撪朄偺嵟崅婯斖偱偁傞寷朄偐傜昍夝偄偰偄偐偹偽側傜側偄丅暥柧壔偲偄偆惓媊旤柤偺幚偼栰斬抦惈偺怳傝偐偞偟偵懳偟偰抐屌偲偟偰峈偡傞抦惈傪楙杹偣偹偽側傜側偄丅偙偺帇揰傪幐偟偨帪丄楌巎揑偵宍惉偝傟嵟傕変乆偑廗惈偲偝偣傜傟偰偄傞帿傪掅偔偟偰垼慽偡傞摴偟偐柍偔側傞偱偁傠偆丅 丂偪側傒偵乽懡偔偺椙怱揑側恖乆偼挊嶌尃幰偺尃棙傪擣傔丄嶌嬋幰偵宧堄傪暐偄丄偱偒傞尷傝壐曋偵巊梡嫋壜傪偟偰傕傜偄偨偄偲峫偊偰偄傞乿塢偆幰偑偁傞偑丄側傜偽偦偺懳壙偲偟偰JASRAC偺挜廂嬥偺宱棟柧嵶傪媮傔傛丅乽挊嶌尃幰偺尃棙傪擣傔傞乿偙偲偑宍懺丄條幃丄暘栰偺擛壗傪栤傢偢乽偁傜備傞嬻娫偦傟傕枛抂偵傑偱尃棙偑媦傇傋偟乿偙偲傪榑徹偟偰傒傛丅乽懡偔偺椙怱揑側恖乆偼慡曽埵慡堟揑挊嶌尃傪擣傔偰偄傞乿塢乆偲塢偄堊偟偰偄傞偑丄乽懡偔偺椙怱揑側恖乆乿偑偳偆偄偆恖偨偪偺偙偲側偺偐丄乽偦偺偳偙偑椙怱揑側偺偐乿榑徹偟偰傒傛丅擆丄尵梩偺撈傝曕偒偱缜缏偟偰偄傞偦偺埫嬸偝傪抪偠傛丅 丂俀侽侽係丏俀丏侾係擔丂傟傫偩偄偙攓 |
| 亂乽僼傽僢僔儑儞僷僽傜傝傞傟傠慽徸乿亃 | |||||
丂堬忛導偺堸怘揦乽僼傽僢僔儑儞僷僽傜傝傞傟傠乿偺敾寛暥乮乽帠審柤丒偮偔偽巗撪僷僽偺壒妝挊嶌尃怤奞帠審乮孻乯敾寛慡暥乿乿乮侾俋俋俈丏係丏係擔丄搚塝娙嵸丂暯惉俉擭乮傠乯戞侾係崋丂挊嶌尃朄堘斀旐崘帠審乯乮擔杮儐僯挊嶌尃僙儞僞乕丂http://www31.ocn.ne.jp/~jucccopyright/乯偼師偺捠傝丅
|
|||||
丂傟傫偩偄偙偺尒傞偲偙傠丄旐崘恖偼丄JASRAC偺壽嬥偐傜摝傟傛偆偲偟偰偄傞傛偆偵巚偊傞丅傓偟傠丄乽傟傫偩偄偙偺俰俙俽俼俙俠斸敾乿傪弬偵丄偦傫側傕偺偼暐偆昁梫偑側偄偲摪乆偲朄棟榑傪揥奐偟偰憟偭偨曽偑彑慽偟偨偺偱偼側偐傠偆偐丅桼乆偟偒帠懺偵側傞偱偁傠偆偐丅 丂俀侽侽俈丏俀丏俆擔丂偗傟傫偩偄偙攓 |
| 亂乽僋儔僽丒僉儍僢僣傾僀帠審乿亃 | ||
丂晄惓彜昳懳嶔僐儞僒儖僞儞僩丅敧栘惓晇巵偺乽抦揑嵿嶻尃栤戣偺尰崱(俆)乿偵乽僇儔僆働儃僢僋僗/巊梡椏晄暐偄偼挊嶌尃傪怤奞/搶嫗抧嵸敾寛乿側傞尒弌偟偺奣梫師偺婰帠偑偁偭偨偺偱偙傟傪揮嵹偡傞丅
|
||
丂乽僋儔僽丒僉儍僢僣傾僀帠審乿偺徻嵶偼晄柧偱偁傞偑丄偳偆傗傜挊嶌尃椏傪庢傞側傜壧偭偨摉恖偐傜庢傟丄揦偼婡夿傪愝抲偟偨偵夁偓側偄偲庡挘偟偰偄偨傛偆偱偁傞丅偙偺庡挘偼戝偄偵尵偄暘偑桳傞偲塢偆傋偒偱偁傠偆丅偲偙傠偑丄嵸敾強偼偙偺栤戣傪夝柧偣偢丄媞偺壧彞偼揦偺壧彞偲尒側偝傟傞塢乆榑偱乽挊嶌尃朄忋偼丄僗僫僢僋懁偵傛傞壧彞偲摨帇偟摼傞偲偟偰丄尃棙幰偺嫋戻側偔僇儔僆働墘憈傪幚巤偡傞偙偲偼墘憈尃怤奞傪峔惉偡傞偲偟偨乿傛偆偱偁傞丅尃椡偵垻傞敾寛偟偐弌側偄偲塢偆尒杮偩傠偆丅 |
| 亂乽僇儔僆働儃僢僋僗慽徸帠審乿亃 | |
| 丂晄惓彜昳懳嶔僐儞僒儖僞儞僩丅敧栘惓晇巵偺乽抦揑嵿嶻尃栤戣偺尰崱(俆)乿偵乽僇儔僆働儃僢僋僗/巊梡椏晄暐偄偼挊嶌尃傪怤奞/搶嫗抧嵸敾寛乿側傞尒弌偟偺師偺婰帠偑偁偭偨偺偱偙傟傪揮嵹偡傞丅 丂
|
|
丂偙傟偼偐側傝擄偟偄栤戣偱偁傞丅僗僫僢僋偵斾傋偰丄楌慠偲壧彞傪捈愙栚揑偲偟偰偄傞偐傜偱偁傞丅偟偐偟丄朄奜側惪媮偼宱塩偵巟忈偡傞偱偁傠偆偐傜丄揦庡偲偟偰偼憟傢偹偽側傜側偄丅壗傛傝傕丄壧彞偝傟偨壧偵懳偟偰壽嬥偝傟傞傋偒偱偁傞偲偙傠丄婡婍堦戜摉傝婔傜亊戜悢偱惪媮偡傞偲塢偆偺偼栤戣偑偁傠偆丅柉嬈偺棽惙傪搎偗偰憟偆傋偒偩傠偆丅変乆偼壧彞傪悽偵峀傔傞庤揱偄傪偟偰偄傞榑偱愗傝曉偟丄憡嶦偝偣傞傋偒偱偁傠偆丅傕偟偔偼悘暘偲掅妟偵愝掕偝偣傞傋偒偩傠偆丅寢嬊偼丄偦偺椏嬥偼僄儞僪儐乕僓乕偵墴偟晅偗傜傟傞偙偲偵側傞偺偩偐傜丅 丂俀侽侽俈丏俀丏俆擔丂傟傫偩偄偙攓 |
| 亂乽儔僕僇僙俛俧俵偵懳偡傞巊梡椏惪媮帠審亃 | ||||||||||||||
| 丂偙傟偼慽徸偱偼側偄偑丄僀儞僞乕僱僢僩専嶕偱尒偮偐偭偨丅乽憡択帠椺偦偺侾侾乿偲偟偰僒僀僩傾僢僾偝傟偰偄傞丅 丂偦傟偵傛傟偽丄梞昳彫攧揦偑巗斕偺俠俢壒妝傪偍揦偺儔僕僇僙偱棳偟偰偄偨偲偙傠丄JASRAC偐傜挊嶌尃巊梡椏偺巟暐偄傪媮傔傜傟偨帠椺偱偁傞丅嵟嬤偱偼嫃庰壆傗柉廻偱偺僇儔僆働愝旛偺摫擖巊梡偵懳偟偰傕摨條偺挊嶌尃偺巊梡椏傪媮傔傜傟偰傞丅 丂JASRAC懁偼丄師偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅傟傫偩偄偙偑拃忦僐儊儞僩晅偗偰偍偔丅
|
| 亂柍椏僐儞僒乕僩帠審亃 | ||
丂俀侽侽係丏侾侾丏侾係擔晅擔宱怴暦偼丄乽僼傽儈儕乕宱嵪乿棑偱丄僄僐僲扵掋抍乮宱嵪夝愢晹丒彫椦寬堦婰幰乯偵傛傞乽柍椏僐儞僒乕僩奐嵜側偤憡師偖丠乿婰帠傪宖嵹偟偰偄傞丅偙傟傪奣棯尒偰偍偔偙偲偵偡傞丅傟傫偩偄偙晽偵棟夝偡傞偲偙偆偄偆偙偲偵側傞丅
丂俀侽侽係丏侾侾丏侾係擔丂傟傫偩偄偙攓 |
| 亂惗墘憈僺傾僲墘憈帠審敾寛偦偺侾亃 | |||
丂乽挊嶌尃怤奞傪宲懕偟偰偄偨堸怘揦宱塩幰偵挦栶10儠寧乮幏峴桺梊3擭乯偺桳嵾敾寛乿丄乽價乕僩儖僘墘憈偱戇曔両 側偤偩偲偄偆慺杙側媈栤丄J-CAST僯儏乕僗乿偦偺懠傪嶲徠偡傞丅
|
| 亂惗墘憈僺傾僲揚嫀敾寛帠審亃 | |||
丂乽JASRAC偲壒妝偺巊梡幰 挊嶌尃傪弰傝暣憟乽揇徖乿丄J-CAST僯儏乕僗乿乮http://news.livedoor.com/article/detail/3012287/乯偦偺懠傪嶲徠偡傞丅
|
![]()
![]() (巹榑丏巹尒)
(巹榑丏巹尒)