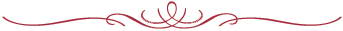
| 裁判長の決定文 |
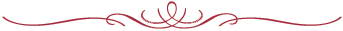
(最新見直し2008.2.21日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「パブかにっ子のジャスラック抗弁書1」、「パブかにっ子のジャスラック抗弁書2」のやり取りを経て、その後音沙汰が無く気にしていたところ、2008.1.25日、以下に記す決定が為された。この決定文は直ぐに郵送されず、次章の「執行、その後の経緯1」に記すように執行後に、かにこうせん経営者が裁判所まで取りに行ったことで入手されたものである。書記官は、それが普通だと説明したが、酷いのではないかと思うのは私だけだろうか。 決定文を転写した後、これを批判する事にしてとりあえず転写を急ぐ。 2008.2.21日 れんだいこ拝 |
| 【決定文】 | |
ここで、決定文を確認しておく。
|
| 【決定文考総論】 |
| 決定文から窺えることは、全編ジャスラックの言いなりであると云う事である。最高裁判決がこれを垂示しており、個々の裁判官はいとも容易く追従していることが判明する。個々の判決観点を取り出して批判してみても繰り返しになるので、最重要な論点を示しておく。 升川決定文も最高裁判決文も、著作権法の解釈に於いて、それが元々著作権者の権利を利用して業者活動する者及び行為に対する規制であり、個々人のあるいは末端店舗レベルでの利用について規制するものでは無いと云う弁えに対して無自覚過ぎる。全ての誤りはここから発生しているように思われる。 法が公布された当初の穏和な著作権が最近強権型著作権に転化しており、法の番人がこれに無自覚なままに後押ししているところに問題が発生していると思われる。司法が健全であれば、経済活動に於ける独占禁止法の如く、著作権の全面全域強権化に対して抑制するのを旨とするはずであるが、最近の司法はこの弁えを持っていない。 それは偏に法哲学、法思想が貧弱なところに由来しているように思われる。法が政治と経済の走狗として権力的に利用されており、チェックアンドバランス機能を自ら壊死させんとしているところに問題が宿されているように思われる。しかしながら、これを幾ら説いたところで、これを聞き分ける能力も意思も無い輩にどう通じるものか。ここに嘆息がある。 2008.2.22日 れんだいこ拝 |
| 【決定文考各論】 |
| 升川判事は、凡そありきたりの判決をしているに過ぎないが、それにしてもジャスラックの全面的言いなりであり酷すぎる。全ての間違いは、制作及びその制作物販売レベルでの著作権適用と、それら制作物の愛好レベルでの著作権適用の是非を分別せず、川上から川下まで一貫適用していることにある。升川判事は、一貫適用論者であるので、以下のような判示になるのも致し方ない。 升川判事は、カラオケ装置を単に営業的利用している場合と、それにより利益を上げている場合との識別をせず、営業的利用即権利侵犯なる見解に与し、ジャスラック側の対価請求当然論を判示している。 升川判事は、「かにっ子」側がこれについて充分に批判してきたにも拘らず、最高裁判例を判示しながら「客の来集を図って利益を上げることを意図しているときは」だとか「これにより営業上の利益を増大させることを意図していたというべきである」と述べ、「演奏権ないし上映権侵害による責任を免れない」と結論している。 しかし、この論法は、商売の基本的なからくりさえ不見識であることを証している。恐らく、士農工商社会に於ける商に対する不当な蔑視に由来しており、その観点を今日まで引きずっている事に関係しているように思われる。彼らは、「客の来集=利益」論に依拠しているが、正しくは「客の来集=売上」であり、売上と利益は大きく異なる。そ違いを弁える必要があろうが、にも拘らず売上=利益とみなすのは初歩的不見識であり、商の構造を余りにも知らなさ過ぎると云わざるを得ない。 升川判事は、「かにっ子」側のジャスラックの音楽著作物利用許諾契約書について種々問題がある旨の主張に対して、「本件の契約の内容も、著作権者の権利保護のために止むを得ないものと認められる」と述べている。叉、「契約条項の表示方法及び契約内容に不服があるからといって、著作権者の許諾を得ることなく著作物を演奏・上映することが許されることにもならない」ともしている。典型的なジャスラック加担暴論であろう。 本来の司法判断は、「著作権者の権利保護」のみ論うべきではなく、被請求者の権利保護をも考慮しつつ平衡的利益を図るべきであり、契約書の内容を逐一吟味して問題ありとみなせばその箇所につき早急に改善の余地有りと判示すべきであろう。既に反論書で述べているので繰り返さないが、類例の無い一方的強制契約であり常識外の内容が罷り通って要る。 升川決定文は一事万事がこの調子であり、露骨な御用理論の開陳でしかない。結論として、「契約を締結していないことが被保全権利の存在を否定する根拠とはならないから、債務者の主張は採用できない」としているが、かにこうせん側の主張を捻じ曲げている。かにこうせん側は、契約を締結していないことを盾にしているのではない。契約しようにも各条項の内容が酷すぎて契約できない状態にあることを指摘しているのであり、このジレンマを抗弁している。裁判官には、これを如何にクリヤーするべきかが問われている。この問題に対しての見識を示すべきのところ言及しないままジャスラック見解に与している。いわば詐術を弄していることになる。 升川判事は、これまたジャスラック見解を丸呑みして、カラオケ装置のリース料に含まれているのは音楽著作物の公衆送信及び複製に対してであり、公に演奏・上映する権利含まれておらず、別個に使用料が支払われるべきとしている。これも問題である。かにこうせん側は、カラオケ装置機器販売業者がジャスラックに支払っている著作権料の総額を明らかにさせて、ジャスラック側の権利分解理論の不毛とやり過ぎを突こうとしている。升川判事は、この問題に対して何ら見解を判示していないばかりか、ジャスラック見解を鵜呑みにしている。 升川判事は、「かにっ子」側の「歌唱料を無料としている店舗からは使用料を徴収すべきではない旨の主張」に対して、「客から歌唱料の名目で料金を徴収しているかどうかは関係が無いものというべきである」としている。しかし、この結論もジャスラック見解丸呑みでしかない。 敢えて考察するならば、歌唱料無料の場合、売上には寄与するものの利益には関係ない。判例が、売上に対してではなく利益に対して課金を判示している以上、利益が無ければ徴収できないとすべきであろう。従って、歌唱料無料制の場合、その当該店舗が赤字経営であるとするなら、取れないという推論がでてくるべきではなかろうか。こういうややこしい事になるのは、そもそも店レベルでの課金制を敷くからであり、その考察は徒労でしかない。 升川判事は、ジャスラックの現行の店舗面積別課金制に対しても、「免責により利用客数が推定され、それにより著作物の利用状況も推定されることから、合理性があると認められる」としている。これもジャスラック見解丸呑みでしかない。「かにっ子」側は、その種の権利が仮に理論上は認められても、著作権法の趣旨からして著作権利用に対して直接請求されるべきであり、その課金システムが開発されていない以上開発されるまでは課金できないとすべきであるとの主張に対して何ら判示していない。 升川判事は、「かにっ子」側のその他の指摘に対して、「その他、債務者は音楽著作物利用許諾契約締結及び使用料の支払いを不要とする理由を縷々述べるが、いずれも債務者の独自の主張に基くものであり、採用できない」としている。つまり、判示することを拒否している。このような姿勢で、結論として、ジャスラックの申し立てを全面的に認めた決定をしている。いかにも杜撰というべきではなかろうか。 この間の経緯で判明した事は、判事及び書記官及び執行官が、まるでジャスラックの番犬かのごとく振舞っており、ジャスラック問題のもう一つの問題となっていることである。これを逆から云えば、ジャスラックはあたかも、弁護士及び判事及び書記官及び執行官を暴力団を使うが如く利用している。 この不正を如何せんか。これが問われているのではなかろうか。私どもは新判例を期待する。 2008.2.25日 かにこうせん |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)