Q:はじめまして。私は都市部のとある公立図書館で司書をしている公務員です。たまたま図書館と著作権についてヤフーで検索していたら、このブログのQ6を見つけたので、図書館の著作権問題について質問させていただきます。
公立図書館でコピーをする場合には著作権法31条によりある一定の条件でコピーをすることが例外的に認められているのは知っていますが、当館の利用者から図書の一部分(半分)しかコピーできないのにおかしい、コンビニでセルフコピーをしても全部分のコピーが認められるのに、時代遅れでお役所的な仕事であるとのクレームが多数ありました。
そこで考えに考えた末、図書館の図書・雑誌のコピーは利用者が個人的に使用する目的で行われるのであるから、著作権法30条1項による私的複製によるコピーということにしようと考えつきました。これだったら複写の量の制限はありません。当館はあくまでコピー機の場所貸しをしているだけという立場に立ち、コピーは利用者とコピー機業者の間の問題であると処理することにしました。
早速実施したところ、利用者からのコピーについてのクレームはなくなり、職員も利用者も万々歳という状況になりました。ところがそれから1年経ったころ、わが市のウェブサイトの「市民なんでも目安箱」に、当館で行っているコピーサービスは著作権侵害であり直ちにやめるべきであるとの意見が寄せられました。
この意見に対しては、コンビニでセルフコピー機を便利に使える時代になったのに、著作権法31条は図書館利用者の利便性を阻害する時代遅れのものであるため、来館者の声を反映させて著作権法30条による複写とみなし、時代に順応した措置を行った旨回答しました。
これに対して意見提出者から、コンビニでのコピーは100%持込み資料であるのに対して、図書館でのコピーは図書館資料を使うものであり、著作権侵害を助長する許されない行為であるとの再意見が出されました。
一方のクレーマーを処理したと思ったら、またクレーマーが出てきて苦慮しておりますが、この「目安箱」への意見提出者の言っていることは本当なのでしょうか。よろしく御教示ください。
A:図書館員って憧れる人が多いけど(特にインテリなのんびり系の女性に)、実際は仕事のメインがクレーマー処理っつーのも因果なものだなあ。平日の昼間からノコノコやって来る客はまともに税金も払ってねー奴が多いのにな。せめて入館料は取った方が社会貢献のためだぜ。にもかかわらず「図書館無料利用の原則は憲法で保障された人権である」という意見が図書館業界誌に載っているのを見たことがあるが・・・。
質問だけど、「目安箱」のクレーマーが言っているとおり、あんたの図書館は著作権法上危ない橋を渡っているといわざるを得ないな。
個人利用目的で図書館のコピー機で図書館資料をセルフコピーする利用者に着目した場合、著作権法上次の2つの法的構成が考えられる。
【1】図書館が主体として著作権法31条に基づき複写を行い、利用者が図書館の手足として複写を行う考え方(『大学図書館における著作権問題Q&A(第5版)』1頁、附録3(国公私立大学図書館協力委員会大学図書館著作権検討委員会、2006)参照)
この場合には、図書館は次の5つの要件を満たす場合に限り、利用者に著作権法31条の範囲内(図書館資料の一部分に限り複写可能等)セルフコピーを行わせることができる。
① 図書館及び文献複写のために利用者の用に供する各コピー機について、管理責任者(及び運用補助者)を定める。
② コピー機の管理責任者は、司書またはそれに準じた者とする。
③ 図書館は、各コピー機の稼働時間を定めて掲示する。
④ コピー機の管理責任者は、管理するコピー機による文献複写の状況を随時監督でき る場所で執務する。
⑤ 図書館は、コピー機の稼動記録を残す
【2】図書館利用者が複写の主体として個人利用目的で著作権法30条1項に基づき複写を行えるとする考え方
なお、コンビニ設置のコピー機のように、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には原則として私的複製から除かれるが(著作権法30条1項1号)、文書又は図画の複製に利用する場合には暫定的に適用除外されている(附則5条の2)。
これら2つの考え方のポイントは、複写の主体をどのように捉えているかである。セルフコピー機で作業しその成果物を取得するのが利用者であることを考えれば、【2】の考え方が自然であろう。あんたの図書館もそう考えてんだろ。しかしそうするとだなあ、著作権法31条で複写の要件を定めている意味は何なのか、ということになろう。この【2】の法的構成については出版社(ひつじ書房・松本功氏など)や著作権管理団体(日本複写権センター「オピニオン/図書館におけるコピーサービス」コピライト477号(2001)67頁-68頁)など)が批判をしている。
この批判に対しては、あんたが「目安箱」で反論したように著作権法31条なんてセルフコピー機がない時代の古い規定だと言われそうだが、そうすると逆に、こんなに大量複写が可能になった時代に、(コピー機があまりなかった立法当時(昭和40年代前半)を前提にした)著作権料無料の複写を図書館(及びそれによってコピーをゲットできる利用者)に認めること自体がおかしいと言われかねないな。実際に現行著作権法を制定した加戸守行氏は図書館も一定の料金を払うべきであり31条自体が要らないと述べており、またその上司であった佐野文一郎氏に至っては「31条なんていうのは、かなり著作権思想の普及にとっては悪影響を与えているでしょうね」とまで言っている(加戸守行ほか「座談会 著作権法制100年と今後の課題」ジュリスト1160号(1999)25頁)。
では【2】の考え方を採った場合、図書館利用者は著作権法上堂々とセルフコピーを無限に行え、一方で図書館はクレームが減って、両者ともに「わたしはハッピー、あなたもラッキー」というWIN-WIN状態になるのだろうか。
ところがどっこい、その場合でも個々の利用者のセルフコピー全体の複写の主体を図書館と捉え、複製権侵害と認定される可能性がある。その根拠となるのがカラオケ法理だ。この法理は、物理的な利用行為の主体とは言い難い者を、「著作権法上の規律の観点」を根拠として、①管理(支配)性および②営業上の利益という二つの要素に着目して規範的に利用行為の主体と評価する考え方であり、クラブ・キャッツアイ事件(最判昭和63年3月15日民集42巻3号199頁)において採用されたものとされている(上野達弘「いわゆる『カラオケ法理』の再検討」紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』783頁(発明協会、2006))。
この法理を利用者のセルフコピーに適用した裁判例として、最近「土地宝典複写事件」判決(東京地判平成20年1月31日〈平成17年(ワ)第16218号〉最高裁HP掲載)が出された。この事件は、土地宝典という法務局備付けの「公図」に旧土地台帳の地目・地積等の情報を追加して編集したものを法務局が利用者(主に不動産・金融機関関係の業者)に貸し出した上、同局内にある民事法務協会(法務局の天下り的な財団法人)が設置するコインコピー機で複写させることが、土地宝典の著作権侵害行為に当たるかということを争ったものである。
この点裁判所は、コインコピー機の直接の管理者であり多数の一般人に土地宝典の複製行為をさせ利益を得ていた民事法務協会を侵害主体と認定すると同時に、法務局が同協会にコインコピー機の設置許可を与え、同設置場所の使用料を取得し、同コピー機が法務局が貸し出す図面の複写にのみ使用され、さらにコインコピー機の設置場所についても直接管理監督していることを考慮して、土地宝典の複製を禁止しなかった法務局は民事法務協会とともに複製権侵害の共同侵害主体であると認定している。さっき書いたカラオケ法理の①、②の要件を満たしているということだな。
この判決を踏まえると、おまえの図書館も、コピー機業者にコピー機の設置許可を与え、そいつから設置使用料を徴収していれば、カラオケ法理によって図書館が各利用者の複製行為の主体と認定され、著作権侵害!!という判決をされるおそれがあるということだな。
なお本件では、コピー機利用者は複数の公的申請の添付書類として土地宝典の写しの提出が求められ、あるいは他の書類に代えて土地宝典の写しを提出するなど業務目的で行っていることから、著作権法30条1項の私的複製とは認められていない(だからこそ、本件ではコピー機設置者の民事法務協会も、コンビニがセルフコピー機で複写されるのとは異なり、著作権侵害の主体と認定されたのだろう)。またコピーされているのは「土地宝典」という特定の著作物であり、様々な図書館資料を所蔵している図書館でのセルフコピーとは状況が異なる。
しかし前者については、先に述べたクラブキャッツアイ事件ではカラオケの楽曲を直接歌っている客は著作権法38条1項により著作権侵害とならない(演奏権制限)ことからカラオケ法理が考えられたように、同法理が適用される場合には直接の利用者が著作権侵害であるかどうかを問わず「著作権法上の規律の観点」からその利用者を支配する間接的関与者が著作権侵害の主体と認定される。また後者については、本件事案では土地宝典という特定の著作物の著作権者(株式会社富士不動産鑑定事務所)が訴えた事案であるが、確かに図書館では多くの著作物が所蔵されており、またその中には館内で複製利用されずに貸出しをされるものがあるため、特定の著作物の著作権者が図書館を訴えることは本件に比べ困難であろう。しかし日本複写権センターのような複製権管理団体が行えば複製権侵害された著作物の特定はある程度緩和され、またどれだけ館内複写されて損害が発生したかという損害額の認定については著作権法114条の5の適用(あるいは類推適用)によりクリアーされる問題であろう。
つうことで、Q6でも述べたが、法律上の無難さをこよなく愛する役人マインドからすれば、利用者のセルフコピーについて「そんなの関係ねぇ!」と言ってられないっつーことだな。まあ、一民間人に過ぎない俺様の戯言など、ほとんど無視されるんだろうがな。
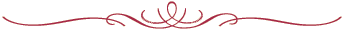

 ■北岡 弘章 (きたおか
ひろあき)
■北岡 弘章 (きたおか
ひろあき)





Commentaires
これ、比較法的にはどうなんでしょ。
村林古稀でまはらじゃ事件の判例評釈をかくときに特にしなかったんですけど、学者のかたでやっているかたはいないんでしょううか。
Rédigé par: madi | le 03/08/2006 à 16:27