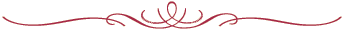
| JASRACの利権運動の広がりウオッチ |
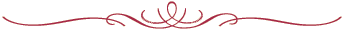
(最新見直し2007.4.1日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 最近の東京における超高層ビルの乱立競い合いを見て、更なる建設ラッシュに向うのを是とする観点を持つなら、その御仁はJASRAC運動にも同じく容易に賛意を示すであろう。なぜなら、通底する論理が似ているから。しかしながら、超高層ビルが観光用の為ならともかく生活し仕事するには全く不向きではなかろうかと訝り、一体どのような建築物が望ましいのかを考える御仁であれば、同様にJASRAC運動にも疑いの眼を持つであろう。思想における一事万事とはこういうことを云う。 問題は決して難しくは無い。大項目として類としての人間社会はどう有るべきか、権利(この場合、社会的生活権はともかく社会権益権として措定される権利とする)とはどのような抑制の下で行使されなければならないのか、というテーマの確認を為せば良いだけのことである。我々はこの種の法哲学的考察が滅法弱く、徒に法文を増やす時代に突入しているのでは無かろうか。 2004.9.12日 れんだいこ拝 |
| 【JASRACの法改正の流れ】 | ||||||||
| 詳細情報はURL(http://www.johnnycash.com/)で知ることができる。「作曲家/ヴァイオリニスト 玉木宏樹ホームぺージ 」の「音楽著作権とJASRAC問題」、「JASRACについて考える」のSWAN氏の2007.6.6日付け投稿「文化庁返信」その他を参照する。それによると、音楽著作権使用料規程策定は次のように改訂されている。 | ||||||||
| 1886(明治19)年、ベルヌ条約がヨーロッパ諸国を中心に創設された。ベルヌ条約に関する事務は、全世界の知的所有権保護の促進・改善を目的とする世界知的所有権機関(World
Intellectual Property Organization、略称WIPO)が行っている。数次の改正を経て、パリ改正条約が最新のものとなる。 ベルヌ条約の主な原則は、次のとおり。
1899年、日本がベルヌ条約加盟。 1899(明治32).3.4日、旧著作権法制定。この時点では、演奏、歌唱、録音媒体の使用ごとに著作権料を支払うという制度は無かった。 1970.5.6日、著作権法を全面改定し新著作権法公布。1971.1.1日、同法施行。 国民生活への多大な影響を懸念した政府(第三次佐藤栄作内閣)は、第22条(上映権及び演奏権)の権利が及ぶ範囲を、原則として生演奏、レコード演奏の区別なく権利が発生するとしつつも、著作権法附則14条と著作権法施行令附則第3条によって権利が及ぶ範囲を1.音楽喫茶(喫茶店その他客に飲食をさせる営業で、客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨広告し、または客に音楽を鑑賞させるためのの特別の設備を設けているもの)。2.キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他フロアにおいて客にダンスをさせる営業。3.音楽を伴って演劇、演芸、舞踏その他芸能を客に見せる事業に限定し、他の音楽利用は自由(無料)とした。 1971.2.20日、使用料規程の一部変更許可申請(著作物使用料規定一部変更認可申請理由書、著作物使用料規定新旧対照表)。1971.4.1日、使用料規程の一部変更認可。 1986.6.2日、使用料規程の一部変更認可申請(著作物使用料規定一部変更認可申請理由書、著作物使用料規定一部変更案)。1987.3.27日、使用料規程の一部変更認可(使用料規程改定、使用料率改定、現行の社交場既定制定、カラオケ管理開始)。 1997.9.26日、日本音楽著作権協会は、業務用通信カラオケ向けの音楽著作権料の規定について、音楽電子事業協会(AMEI)と合意した。この規定では、これまで複製権、優先送信権などの権利ごとに定めていた使用料の考え方を改め、通信カラオケのシステムを1つのくくりとして使用料を定めた。今後、家庭向け通信カラオケ、パソコン通信、インターネットなどを含めた利用形態に対応する規定も作られる。 |
||||||||
|
| 【ヤフーとJASRACがネット配信契約】 | |
|
「ヤフー、日本音楽著作権協会と基本契約を締結――音楽の無料配信で」は次のように伝えている。
|
「東京地裁、日本MMOの著作権侵害を認める中間判決──JASRACとRIAJ「高く評価できる」」を転載しておく。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)