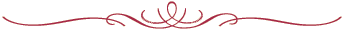
| 「JASRACの音楽著作物利用承諾契約条項」考 |
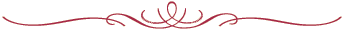
(最新見直し2008.2.26日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 本サイトでは、「JASRACの音楽著作物利用承諾契約条項」を考察する。見たところ非常に小細字で何やら保険の約款を思い起こさせる条項が記されている。人は一般にこういうものを読まず、JASPACの訴訟風聞を聞いて否応無く契約しているのだろう。しかし、JASRACの現在のような加盟強制、「債権取立て」には大いに問題があると考えるれんだいこは、目を通してみた。 結論から云えば、この条項書に拠れば契約はあくまで任意であり、そういう書式として行政官庁の認可を受けているのではなかろうか、という気がする。保険約款と体裁が似ているのはまさしくそうで本来任意契約なのではなかろうか、という気がする。それにしてもこれを作成した弁護士はかなり保守的と云うか、近代思想を持たない法匪的技術屋であることを暴露している。 にも拘らず従来、裁判所見解は、「JASRACの音楽著作物利用承諾契約条項」に何の疑問も湧かさず、JASRACの加盟強制、「債権」取立てを後押ししてきた経緯があるようである。れんだいこは、裁判長の見識を疑う。弁護士も検察も裁判長も、いわゆる法の番人がこの程度の見識しか持っていないことが分かる。以下、これを確かめる。 料金支払方法等の実務規定の箇所を省き、最低限知っておくべき条文のみ考察する。れんだいこにはかなり悪質にしてお上式の奴隷契約になっているように思われるが如何であろうか。「JASRACの音楽著作物利用承諾契約条項」がかようなものである限り、契約拒否こそ嗜みであると自負したい。誰か一度金銭問題ばかりに執着せずに、この問題を法廷で争えば良かろうに。 2004.8.25日 れんだいこ拝 |
| 【第1条(総則)第1項】 | ||
|
| 【第1条(総則)第2項】 | ||
|
| 【第1条(総則)第3項】 | ||
|
| 【第1条(総則)第4項】 | ||
|
| 【第1条(総則)第5項】 | ||
|
| 【第2条(包括的利用許諾・譲渡禁止)】 | ||||||
|
||||||
| 【第10条(違約金)】 | ||
|
| 【第12条(利用曲目の報告義務)】 | ||
|
| 【第13条(利用状況調査の便宜供与義務】 | ||||||
|
| 【第14条(許諾条件の範囲を超える利用等の届出義務】 | ||||||
|
||||||
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)