
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.5.22日
「た行」の ことわざ
| 「ドアは開けておくか、締めておくかしかない」 (A door must be either shut or
open) |
| (読解) |
| 【東】 |
| 「東男に京女」 |
| (読解) 男ならば、男らしい男の代表とされる関東のおとこがいい。女は美しく磨かれた京都の女がいいということ。 |
| 「東海を踏みて死す」 |
| (読解) 世の中のことを憤慨して死ぬこと。東海は渤海湾、または東シナ海をさす。「史記」 |
|
| 【灯】
|
| 「灯火親しむべし」 |
| (読解) さわやかな秋になり、気持ちよく読書ができる。気候がさわやかで夜の長い秋は、灯火の下で読書するのに適している。 |
| 「灯台下暗し
(とうだいもとくらし)」 |
| (読解) 灯台の真下が暗いように、身近な事はかえって気付かず見落としがちなことのたとえ。 |
| (類似諺) (教会に近いほど、神から遠くなる、The nearer the church, the farther, from God)、「ろうそくの下は暗い」(It is dark at the foot of a candle) |
|
| 【遠】 |
| 「遠くて近きは男女の仲」 |
| (読解) 男と女の間は、ちょっと見ると、遠くかけはなれているように見えるが、思ったより近い。男と女は、意外とかんたんに仲良くなったり、むすばれたりするものだ、という意。 |
| (類似諺) (男は火、女は麻くず、Man is fire, and woman is tow) |
| 「遠くの親戚より近くの他人」 (A good neighber
is better than a brother far off.) |
| (読解) 遠くにいる親類は、いざというときに役に立たない。他人でも近くにいる人の方が頼(たよ)りになる。近所の人とのつきあいはたいせつにしなさいという戒め。 |
| (類似諺) Strangers at hand are better than relations afar. |
| 「遠目は眺めに魔法をかける」 (Distance lends
enchatment to the view) |
| (読解) |
|
| 【十】 |
| 「十で神童 十五で才子 二十過ぎれば只の人」 |
| (読解) 小さいころ非常に優れていると思われていた子も、たいていは成長すると共に普通の人になってしまうこと。 |
| 「十日(とおか)の菊(きく)」 |
| (読解) 1.菊の節供(陰暦9月9日)の翌日の菊のこと。菊の節供を過ぎたのに、仏壇などに飾られている菊。2.転じて、時期に遅れて役に立たないことの喩え。 |
|
| 「頭角を現す」 |
| (読解) 才能や学識が人より一段と優れていること。 |
| 「蟷螂の斧(とうろうのおの)」 |
| (読解) 弱者が、自分の弱さをかえりみず、強敵に立ち向かうことのたとえ。 |
| 「冬至かぼちゃに年とらせるな」 |
| (読解) 冬至にかぼちゃを食べると、風邪をひかないし、しもやけにもなりずらいというのは昔からの言い伝え。確かにかぼちゃは、栄養素が豊富で冬至の時期の貴重な栄養源である。さらにかぼちゃは保存がきき、栄養素の損失も少ない。しかし、春まで保存し続けても効用がなくなるため、保存も冬至までが限度という意味。 |
| 【同】 |
| 「同情より少しの援助」 (A little help is worth a deal of pity) |
| (読解) |
| 「同族(骨肉)相食む」、「同族(骨肉)相食まず」 |
| (読解) |
| (類似諺) (犬は犬を食べない、Dog
does not eat dog) |
| 「同病相憐れむ」(Fellow suffers pity each other.)
|
| (読解) 同じ苦しみに悩む者同士は、その辛さがわかるので、互いにいたわりあい同情し合う気持ちが強い。 |
| (類似諺) (悲しみは悲しみの仲間の所に置かれるのが一番良い、Grief is best placed with
grief's company) |
|
| 「堂に入る」 |
| (読解) 物事に熟練している。身についている。 |
| 【問う】 |
| 「問うは一旦の恥 問わぬは末代の恥」 |
| (読解) 知らない事を聞くのは、その場では恥ずかしいものだが、聞かずに知らないまま過ごせば、一生恥ずかしい思いをしなければならないということ。 |
| 「問うに落ちず、語るに落ちる」 |
| (読解) 問われると、用心して中々真実を語らないものであるが、何気なく語るときには、ふと真実を漏らしてしまうものだということ。 |
|
| 「豆腐に鎹(かすがい)、糠に釘」 |
| (読解) かすがいとは、木材などの合わせ目をつなぎ止める大きな釘のこと。柔らかい豆腐にいくらかすがいを打ってもきかない。無駄なことのたとえ。「糠に釘」や「のれんに腕押し」と同じ意味。 |
| 「兎角亀毛」 |
| (読解) 「兎角亀毛
(とかくきもう)」 兎の角と亀の毛 の事で、 "この世にはありえないもの" をさす言葉です。 |
| 【時】
|
| 「時は金なり」(Time is money.) |
| (読解) 時間は貴重であるから、浪費してはならない。時間の貴さを教えることば。 |
| 「時は偉大ないやし手」(Time is the great
healer) |
| (読解) |
| 「ときに愚人の素振りをの出来ない人は、本当の賢人ではない」 |
| (読解) 西洋の諺。 |
| 「時の氏神」 |
| (読解) 争い事の収拾がつかなくなったところに現れて、仲裁してくれるありがたい人。 |
| 「時の砂に残る足跡は、ただ座っていて出来るものではない」(Footprints on the sands of time are not mede by sitting
down) |
| (読解) |
| 「時計は逆には戻せない」(One cannot put back
the clock) |
| (読解) |
|
| 【毒】 |
| 「毒にも薬にもならぬ」 |
| (読解) 害にもならないが、益にもならない。 |
| 「毒も薬も人によりけり」 |
| (読解) |
| (一人の人の食べ物はもう一人の人の毒である、One man's
meat is another man's poison) |
| 「毒薬変じて薬となる」 |
| (読解) 毒薬も使い方次第では良薬になる。はじめは害になったものが、一転して有益なものになること。 |
| 「毒を食らわば皿まで」 |
| (読解) 一度毒を食ったなら、どうせ命はないのだから、ついでに毒をもった皿までなめる。一度悪事を犯したからには、とことん悪事を重ねること。 |
| (類似諺) (子羊を盗んで縛り首になるより、親羊を盗んで吊される方がマシ、As well be hanged (hung) for a sheep as (for) a lamb)、(短靴もブーツも、Over shoes, over boots)、One may as well be hanged for a sheep as a lamb. |
| 「毒を以って毒を制す」 |
| (読解) 悪事・悪人を除くのに、他の悪事・悪人を利用すること。また、強力な薬を用いて難病を治療すること。 |
| (類似諺) (悪魔を追い払うには、悪魔に寄れ、Devil must be
driven out with devil.)、Poison drives out poison. |
|
| 「読書百遍義おのずから通ず」 |
| (読解) 何遍も読めば、意味は自然に分かってくるものであるという意味。 |
| 「所変われば品変わる」 |
| (読解) 土地が違えば、風俗や習慣、ことばなどが違うこと。 |
| (類似諺) (ところところにそれだけの数の風習がある、As many places,so many manners)、(たくさんの国にはたくさんの習慣がある、So
many countries so many customs) |
| 【何処(どこ)】 |
| 「何処に行こうとも我が家にまさる所はない」 |
| (読解) |
| (類似諺) (西だろうが東だろうが我が家が一番、East or west,
home is best) |
| 「何処の群にも黒い羊の一頭はいる」 (There's a
black sheep in every flock) |
| (読解) 何処にでも困りものはいるものだの意。 |
|
| 【年】 |
| 「年上の女房は金の草鞋をはいてでも探せ」 |
| (読解) 「かねの草鞋」が正解です。金の草鞋ってまだ履いたことはありませんが、 すごく重くって歩くとヘトヘトに疲れるんです。 価値あるものはそれほどの苦労をしてでも歩き回って探しなさい、
苦労するしただけの事はあるぞ という意味ですヨ。 「きんの草鞋」と読むと贅沢三昧の、金持ちのくせに義援金や寄付金もしない嫌われ者の イメージが浮かびますが、そういう類の諺、格言は今のところ知りません。 |
| 「年は取っても使い道はある」 |
| (読解) |
| (類似諺) (古いバイオリンでもいくつでも良い曲は弾ける、There's many a good tune
played on an old fiddle) |
|
| 【年寄り】 |
| 「(特に恋煩いをする)年寄りのバカは始末に負えない」(There's) No fool like an old fool) |
| (読解) |
| 「年寄りの冷や水」 |
| (読解) 年寄りが自分の身体の状態を考えずに無理をするのを戒めた言葉。身体のあらゆる機能は年とともに低下する。したがって、それに応じて行動も制限しなければならなくなる。刺激の強いものもよくない。冷たい水は、年寄りにとって刺激が強すぎるということからきた言葉。 |
| 「年寄りの昔話」 |
| (読解) 老人は、自分の若い時の話をしたがるものだということ。年寄りが昔話始めたら長いと云う意味もある。 |
|
| 「屠所(としょ)の羊」 |
| (読解) 屠殺場にひかれていく羊。刻々と死期が迫る喩え。 |
| 「塗炭の苦しみ」 |
| (読解) どろにまみれ、炭火で焼かれるような苦しみ。ひどい苦しみ、難儀のたとえ。 |
| 「土壇場に直る」 |
| (読解) 首切り刑を行なう土壇の上につくことから、最期の場に臨むこと。 |
| 「土手っ腹に風穴をあける」 |
| (読解) 土手っ腹とは、ふくれた腹をいい、そこに鉄砲の玉を撃ち込むぞというおどし文句。 |
| 「とどのつまり」 |
| (読解) 結局。いきつくところ。多く、よくない場合に用いる。「海の幸、山の幸に恵まれ」の言葉もある通り、魚から多大な恩恵を受けて来ただけあって、日本人の魚に対する関心と知識の深さは世界一だと言われている。その例が、成長につれて名前を使い分ける出世魚だろう。◆メジ→マグロ→シビ、◆ハマチ→ブリ、◆オボコ→イナ→ボラ→トドなどがある。もののゆき詰まりを「とどのつまり」と言うのは、ここから来ている。 |
| 【隣】
|
| 「隣の芝生は良く見える」、「隣の芝生は青い」(The neighbor's lawn is green.) |
| (読解) |
| (類似諺) (よその芝生は(うちの芝生より)青く見える、The grass is
greener (on the other side of the hill[fencel]) ) |
|
| 「斗南(となん)の一人(いちにん)」 |
| (読解) 北斗星より南で第一の人。また、天下第一の賢人。 |
| 【鳶(とび、とんび)】 |
| 「鳶(とんび)が鷹(たか)を産む」 |
| (読解) ふつうの親から、すぐれた子がうまれたというたとえ。とびより鷹のほうがすぐれているとの考えが前提になっている。平凡な親から、優秀な子供が生まれることのたとえ。 |
| (類似諺) (黒い雌鳥が白い卵を生む、A black hen lays a white egg.) |
| 「鳶(とんび)に油揚げをさらわれる」 |
| (読解) 鳶はいつも高い空にいるが、それがさっと降りてきて油揚げをさらったということから、不意に横合いから大切なものを奪われるたとえ。 大切なものを不意に横から奪われることのたとえ。 |
|
| 【飛】 |
| 「飛ぶ鳥を落とす勢い」 |
| (読解) イギリスの諺。権力や勢力が強く盛んなこと。 |
| 「飛んで火にいる夏の虫」 |
| (読解) 夏の虫が、明かりをめざして飛びこんできて火に身を焼かれるように、自分からすすんで危険なところに入りこむことを云う。 |
| (類似諺) (The fly flutters about the candle till at last it getsburned) |
|
| 【友、朋】 |
| 「朋有り遠方より来たる」 |
| (読解) 志を同じくする友人が、遠い所から訪ねてきてくれたことを喜ぶことば。 |
| 「友よりわれを守らせたまえ、敵より身を守ることはできますゆえに」
(My God defend me from my friends;I can defend myself from my
enemies) |
| (読解) |
| 「友を見れば人物が分かる」(A man is known by the company he keeps) |
| (読解) |
| 「友引に葬式をするな」 |
| (読解) この日に葬式をすると、続いて葬式を出すようになるという全国的な俗信。 |
|
| 【泥棒】 |
| 「泥棒をとらえて縄をなう」Locking the barn door after the horse has been stolen. |
| (読解)1.事件が起こってから慌てて準備をしても間に合わない。時機に遅れては用をなさないことの喩え。2.準備を怠(おこた)って行きあたりばったりにものごとを行なうこと。 |
|
| 【虎】 |
| 「虎に翼」 |
| (読解) 強いものに、さらに強い力が加わる事のたとえ。 |
| 「鬼に金棒」 |
| 「虎の威を借る狐」 |
| (読解) 他人の権勢をかさに着て威張ることのたとえ。また、そのような人。 |
| (類似諺) (ライオンの皮をかぶったロバ、An ass in a lion's
skin) |
| 「虎の尾を踏む」 |
| (読解) 非常に危険なことをすることのたとえ。強暴な虎の尾を踏めば、怒った虎にかみ殺されてしまう。そこから、非常に危険なこと、無謀なことをするたとえ。
|
| 「虎は死して皮を残し、人は死して名を残す」 |
| (読解) 虎は死後皮として珍重され、人は名誉や不徳が語りつがれる。生前から死後の名誉を重んじ。行ないを戒める諺。 |
| 「虎は千里を行って千里を帰る」 |
| (読解) 勢いが盛んな様子の例え。 |
|
| 【鳥】
|
| 「鳥のまさに死なんとする、その鳴くや悲し」 |
| (読解) 鳥の死に際の声は悲しい。「人のまさに死なんとする、その言や善し」の対句で、人の死に際には本音が出るという喩え。 |
| 「鳥無き里の蝙蝠(こうもり)」 |
| (読解) 鳥がいないところでは、みにくいこうもりが、鳥を気取って威張っている。優れた者がいない所では、つまらぬ者がいい気になってのさばっている。 |
| (類似諺) (目が見えない人たちの国では、片目は王様、In the
country of the blind, the one-eyed is king) |
|
| 「鳥は少しずつ巣を作る」 |
| (読解) フランス語の諺。 |
|
| 【取】 |
| 「取らぬ狸の皮算用」 |
| (読解) たぬきをつかまえる前から、もうその皮を売ってもうける計算をする。つまり、どうなるかわからないのに、あてにして、いろいろ計算をねる愚かさをからかう意。まだ手に入っていないのに、それを当てにして計画を立てることのたとえ。 |
| (類似諺) (ヒヨコがかえらないうちに雛の数を数えるな、Don't count
your chickens before they are hatched)、(木の枝に居る鳥を売るのは早まったことである、It is rash to sell the
bird on the bough) |
| 「取り越し苦労」、「取り越し苦労は身の毒」 |
| (読解) |
| (類似諺) (悩みと言えないほどのことで、悩むな、Never trouble
trouble till trouble trouble you )、「世話で猫が死んでしまう」(Care killed the cat). |
| 「取り付くしまもない」 |
| (読解) 頼りにする物が見つからず、どうして良いかわからない事。または相手の態度があらく、話すきっかけがつかめない 事を云う。しまを島と解せば、大海で困難に遭遇したときには島へ上陸するのが一番ですが、それすらもない。
相手の冷淡さを非難するときに使う諺ということになる。 |
|
| 「豚児(とんじ)」 |
| (読解) 他人に対して我が子のことをへりくだっていう。 |
| 「どんぐりの背比べ(せいくらべ)」 |
| (読解) どんぐりは、どれも形や大きさが同じでようであることから。どれも同じようで、とくにぬきでたものがなく、変わりばえしないことをからかっていう。 |
| 「とんでもはっぷん」 |
| (読解) 終戦後進駐軍より米語文化の導入で米語・日本語の混成語がはやりました。 never happen
と とんでもない を合わせて とんでも happen となったもの。 |
| 「どんな餌も突く魚はすぐに釣られる」 (The fish will
soon be caught that nibbles at every bait) |
| (読解) |
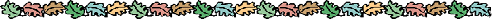



 (私論.私見)【と】
(私論.私見)【と】
329.灯台下暗し
330.問うに落ちず語るに落ちる
331.豆腐に鎹
332.東奔西走
333.桃李言わざれども下自ずから蹊を成す
334.登竜門
335.十日の菊
336.遠くの親類より近くの他人
337.時は金なり
338.読書百遍意自ずから通ず
339.毒を食らわば皿まで
340.毒を以って毒を制す
341.所変われば品変わる
342.年には勝てぬ
343.年寄りの冷や水
344.図南
345.斗南の一人
346.駑馬に鞭打つ
347.鳶が鷹を生む
348.飛ぶ鳥を落とす
349.虎の威を借る狐
350.虎は死して皮を残す
351.鳥無き里の蝙蝠
352.泥棒を見て縄を綯う
【な】
353.無い袖は振れない
354.泣いて馬謖を斬る
355.長い物には巻かれろ
356.泣き面に蜂
357.泣く子と地頭には勝てぬ
358.情けは人の為ならず
359.七重の膝を八重に折る
360.名は体を表わす
361.怠け者の節句働き
362.蛞蝓に塩
363.名を取るより実を取れ
364.南柯の夢
【に】
365.煮え湯を飲まされる
366.二階から目薬
367.逃がした魚は大きい
368.苦虫を噛み潰す
369.憎まれっ子世に憚る
370.錦を着て夜行くが如し
371.二豎
372.似た者夫婦
373.二度あることは三度ある
374.二兎を追う者は一兎をも得ず
【ぬ】
375.糠に釘
376.盗人に追い銭
377.濡れ手で粟
【ね】
378.猫に小判
379.猫の手も借りたい
380.猫を被る
【の】
381.嚢中の錐
382.残り物には福がある
383.喉元過ぎれば熱さを忘れる
384.暖簾に腕押し
【は】
385.背水の陣
386.掃き溜めに鶴
387.破鏡
388.白眼
389.白玉楼
390.白眉
391.破天荒
392.花は桜木人は武士
393.花より団子
394.早起きは三文の徳
395.腹も身の内
396.張子の虎
【ひ】
397.引かれ者の小唄
398.髭の塵を払う
399.庇を貸して母屋を取られる
400.尾生の信
401.顰に効う
402.人を呪わば穴二つ
403.髀肉之嘆
404.火のないところに煙は立たぬ
405.百聞は一見に如かず
406.瓢箪から駒
407.瓢箪鯰
【ふ】
408.風声鶴唳
409.風前の灯
410.笛吹けども踊らず
411.覆水盆に反らず
412.武士は食わねど高楊枝
413.豚に真珠
414.舟に刻みて剣を求む
415.武陵桃源
416.焚書坑儒
【へ】
417.臍が茶を沸かす
418.下手の考え休むに似たり
419.下手の横好き
420.弁慶の立ち往生
421.弁慶の泣き所
【ほ】
422.望蜀
423.坊主憎けりゃ袈裟まで憎い
424.墨守
425.仏作って魂入れず
426.仏の顔も三度
【ま】
427.蒔かぬ種は生えぬ
428.馬子にも衣装
429.眉毛を読まれる
430.眉に唾を塗る
431.眉に火が点く
432.真綿で首を締める
【み】
433.木乃伊取りが木乃伊になる
434.身から出た錆
435.水に油
436.味噌を付ける
437.三日天下
438.三日坊主
439.三つ子の魂百まで
440.耳を掩いて鐘を盗む
【む】
441.六日の菖蒲
442.昔取った杵柄
443.矛盾
444.娘一人に婿八人
445.胸に一物
446.無理が通れば道理が引っ込む
【め】
447.目から鼻へ抜ける
448.目屎鼻屎を笑う
449.盲蛇に怖じず
450.目には目歯には歯
451.目の上の瘤
452.目は口ほどに物を言う
【も】
453.孟母三遷の教え
454.餅は餅屋
455.沐猴にして冠す
456.本木に勝る未木なし
457.元の鞘に納まる
458.元の木阿弥
459.桃栗三年柿八年
【や】
460.焼け石に水
461.焼け野の雉子夜の鶴
462.安物買いの銭失い
463.柳に雪折れなし
464.柳の下にいつも泥鰌はおらぬ
465.藪から棒
466.藪を突突いて蛇を出す
467.病膏肓に入る
468.病は気から
469.山高きが故に尊からず
470.闇夜の鉄砲
【ゆ】
471.雪と墨
472.雪に白鷺
473.油断大敵
【よ】
474.欲に目が眩む
475.弱り目に祟り目
【ら】
476.楽は苦の種、苦は楽の種
477.洛陽の紙価を高む
【り】
478.律義者の子沢山
479.梁上の君子
480.両手に花
481.遼東の豕
482.良薬は口に苦し
【る】
483.類は友を呼ぶ
【ろ】
484.壟断
485.隴を得て蜀を望む
486.論語読みの論語知らず
【わ】
487.渡りに船
488.渡る世間に鬼はない
489.笑う門には福来たる


![]()
![]()
![]() (私論.私見)【と】
(私論.私見)【と】