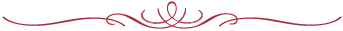
| 別章【名理論】 |
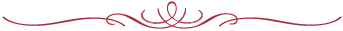
更新日/2020(平成31→5.1栄和改元/栄和2)年.8.3日
目次
| 【毛沢東「人間の正しい思想はどこからくるのか」(1963.5月)】 | ||
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
孫子曰く:亡地(ぼうち)に投じて然(しか)る後に存し、之を(しち)に陥(おとしい)れて然る後に生く。
夫(そ)れ衆は害に陥(おちい)りて然る後に
能(よ)く勝敗を為す。
解説例※ 絶対絶命の窮地に立ち、死地に追い込まれることでそこに活路が生じる。人間というものは
危難に陥ったとき、はじめて真剣に勝負する気持ちになるものである。
「カオス理論」によれば「蝶の羽ばたきが大嵐を招く」
米大統領諮問委員会のR・M・モンボイス教授は、「警察は対立する勢力のいずれに属してもならないが、その対立に巻き込まれることを避けることが出来ない」と述べた。警察の政治的中立とは、それほどに難しい。
魏晋南北朝時代、中国は南北分裂や北方民族の圧迫など、現代日本と同じような閉塞状態にありました。その時士大夫階級は何をしていたかと言うと、何もせず世から隠れ、儒教による秩序を嘲いながら老荘の虚無を謳い、大真面目に何の腹の足しにもならない、ロクでもない清談に耽っておったのです。
清談を行うのに重要なアイテムとして「トゼン草(徒然草?)」と言うものがあります。これを服用すると脳(の一部分が)活性化し、清談がよりエキサイトすると言うのです。トゼン草を服用してからする議論が「清談」で、それ以外の議論は形而下的な下等なものとされていました。
時の皇帝は、この風を「不謹慎である」と禁令を発したのですが、うまくいかなかったようです。その後この国は、あっさり北方民族により滅ぼされました。金・元に圧迫され続けた宋代にも流行しました。件の掲示板はこの文化を受け継いだ掲示板なのです。(多分)そのくせ中国文化に冷たいような気がするのは妙なものです。「腹の足しになる議論」とはまったく反対の作法の掲示板ですね。
毛沢東「持久戦論」
「若者は無名で失うものが無く、そのエネルギーは山をも砕く。だから、未来は若者のものだ」。
| 核兵器問題に関しての毛沢東の理論 |
| 「誰も核兵器を持たないのが最善、一方だけが保有するのは最悪、一方が持つ以上他方も保有するのが次善」 |
| ロバート・ペインの「チャーチル」 |
| 「私はいかなる政治体系も持つていない。私は政治原則は全て破棄している。私は生起してくる事象を自分の考えに照らして処理する男なのだ」 |
| レッシング(森田実氏のホームページから) |
| 「自分の経験はどんなに小さくとも、百万の他人の経験より値打ちのある財産である」 |
レッシングのこの言葉は、森田氏がとくに大切にしてきた格言の一つである。
(解説)
レッシング(1729−81)はドイツの劇作家で、18世紀のドイツ啓蒙主義を代表する思想家である。ザクセンの牧師の長男に生まれた。レッシングの立脚点は啓蒙思想である。啓蒙主義ないし啓蒙思想というのは17世紀末以降西ヨーロッパを中心に普及した考え方で、人間の理性を重視し、理性に光を与えることによって古い社会の旧弊を打破し、公正な社会をつくろうという思想のことである。
イギリスでは、啓蒙思想はベーコンからベンサムにいたる反封建主義思想を意味した。これはイギリスの市民革命をもたらした。フランスの啓蒙思想は、理性を中心とする人間の能力に信頼をおく人間主義である。中世の古い迷信と偏見を打破しようというのがフランス啓蒙主義者の共通の主張だった。これはフランス革命の原動力となった。これに対し、ドイツ啓蒙思想は時期的には少し遅れて18世紀になって登場し、主として内面的な精神運動として展開された。ドイツ啓蒙思想の先駆者はライプニッツである。そのあとにつづいたのがレッシング、メンデルスゾーン、カントらだった。19世紀半ばに登場するカール・マルクスは啓蒙主義最左派というのが私の位置づけである。
レッシングの言葉「自分の経験はどんなに小さくとも、百万の他人の経験より値打ちのある財産である」を意訳すれば、「自分自身の体験ほど大切なものはない。いかなる人間も自分自身の体験からは逃れようとしても逃れることはできない。自分自身の体験は死ぬまでついて離れない。人間は自分自身の体験を重視し、自分自身の体験から学ばなければならない。自分自身の体験をないがしろにする者は愚かである。同時に人間は恥ずべき過去をつくらないよう努力しなければならない」ということになる。
ほぼ同様な見地から、戦後日本の最も代表的な進歩的文化人であり、偉大な社会学者であり、現代社会思想講座の創始者であった故清水幾太郎教授も次のように述べている。
「人間は自分自身の経験からは絶対に離れられない。それがどんなに惨めなものであっても捨てることは不可能だ。いかなる体験であろうとも生涯背負っていかなければならないのだ」。清水教授のこの言葉は、森田氏にとって一つの大切な人生の指針となった。
その森田氏は次のようにも語っている。私はかってマルクス主義の信奉者だった。共産党のなかでは、自らの体験を重視する姿勢は「個人主義・経験主義」として厳しく批判された。党員個人の体験にもとづく創造的な提案はマルクス、エンゲルス、レーニンの言葉よりも下に見られ軽視された。私はこの共産党内の観念過剰の空気に同化することができなかった。私は1955年夏の六全協以後、党中央への厳しい内部批判活動を行い、中央本部と激しく対立し、ついに1958年に中央委員会決議により除名された。共産党から離れて自由にものを考えるようになった頃、清水教授から直接話を聞く機会が増え、清水教授の経験重視の思考から大きな刺激を受けた。清水教授の墓石には、自筆の次の言葉が刻まれている――「経験、この人間的なるもの」 「経験」が清水教授の生涯を通じての思索活動の中心におかれていたことが、この言葉に示されている。
体験の重要性
「体験」と「経験」は個人生活のレベルでは同じ意味である。『広辞苑』(岩波書店)は「体験」を「自分が身をもって経験すること、また、その経験」と定義している。しかし、哲学の世界では少し違いがある。『岩波哲学・思想事典』によると、その差は次のようなものである(丸山高司氏執筆)
「〈体験〉概念は、多くの点で〈経験〉概念と重なり合うが、それとの相違点をあえて強調するなら、直接性や生々しさ、強い感情の彩り、体験者に対する強力で深甚な影響、非日常性、素材性、などのニュアンスをもっている」
「体験」は私の人生を動かしてきた決定的な要素なのである。
故清水幾太郎教授の教えのとおり、自分自身の体験はいかなる偉人の体験よりもずっと大切で価値の高いものである。
しかも、たとえ自分自身の体験がどんなに醜く恥すべきものであったとしても、それから逃れることはできない。己の体験をしっかりと受け止め、これと共存する以外に道はないのである。この認識と強い自覚を持てば、人それぞれに前向きで個性ある人生を送ることが可能になるだろう。
| ヘーゲル「法哲学.序文」 |
| 「万事現実的なものは合理性があり、合理的なものには現実性がある」 |
| 碎啄同機(さいたくどうき) |
(解説)
卵が孵化してひなが誕生する時、ひなが中から殻をつついて母鳥に知らせるのが「碎」(口篇に卒)、母鳥がくちばしで殻を破るのが「啄」。
佐藤首相は、「決断を下すべき、その機が熟しているかどうかについて、国際情勢や国民世論の動向を十分見極めて『碎啄同機』の呼吸を計ることが何より肝要だ」とした。ともすれば、『待ちの政治、分かりにくい政治』となった。
| マルクス『資本論』第1部、S.791 |
| 「資本主義的生産様式の桎梏論」 |
「資本独占は、それとともに開花しそれのもとで開花したこの生産様式の桎梏となる。生産手段の集中も労働の社会化も、それがその資本主義的外皮とは調和できなくなる一点に到達する。そこで外皮は爆破される。資本主義的私有の最後を告げる鐘が鳴る。収奪者が収奪される。」()
「桎梏」というのは、手かせ足かせのことであり、何かに対してその自由をうばうもの、拘束するもののことです。つまり、Marxは「資本独占」が生産様式の自由を奪う、発展の障害とな
るとしているわけです。同じように、「資本主義的外皮」も「生産手段の集中」・「労働の社会化」――これらは大工業が社会に与える作用の結果――の進展にとって障害になるのです。つまり、「資本独占」≒「資本主義的外皮」≒「資本主義的私有」であり、これらのものが「生産様式」(=大工業)の発展を妨げているから、この障害物(「桎梏」)を取り除いて「生産様式」(=大工業)の正常な発展の条件を整えようとMarxは言っているのです。
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)