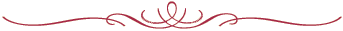
| 四文字熟語集7(マ行) |
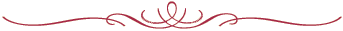
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、四文字熟語熟語言葉のマ行を確認しておく。 2008.8.31日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| マ | ||
| 真一文字 | まいちもんじ | 一の字のようにまっすぐなさま。一直線。わき目も振らないさま。 |
| 真帆片帆 | まほかたほ | 真帆は船首に対して真角に張る。片帆は、斜めに張る。追風は真帆で、横風は片帆で受けて帆走する。 |
| 麻姑掻痒 | まこそうよう | 物事が思いのままになること。 |
| 麻中之蓬 | まちゅうのよもぎ | 麻の生えている中に混じっているよもぎは自然にまっすぐに育つ。教育にはよい環境が必要だというたとえ。朱に交われば赤くなる。 |
| 麻縷糸絮 | まるしじょ | 麻と麻糸と生糸とわた。織物の材料。 |
| 磨斧作針 | まふさくしん | どんな難しいことでも忍耐強く努力すれば、必ず成功するという意味。 |
| 磨励自彊 | まれいじきょう | 大いに修行して、みずから努めはげむ。 |
| 負けじ魂 | 負けまいと奮いたつ気持ち。まけじごころ。 | |
| 末法思想 | まっぽうしそう | 末法の世には仏教が衰え世の中が乱れるという仏教思想。 |
| 万劫末代 | まんごうまつだい | 後世まで永久にわたっての意。永遠の末の世。きわめて長い歳月。 |
| 万能一心 | まんのういっしん | たくさんの才能に恵まれていても、向上・努力する心がけがなければ、物事は成就しない。 |
| 満漢全席 | まんかんぜんせき | 漢族の料理(本来の中国料理)108種類と満族の料理(北方の料理)108種類、合計216種類を、それぞれ満席・漢席(満席では満族の服装で調度も満民族の調度を揃え、漢席は漢族の服装をして漢民族の用いる調度を揃えた宴席)で味わうことをいう。 |
| 満場一致 | まんじょういっち | 全員の意見が一つにまとまること。 |
| 満城風雨 | まんじょうふうう | 町中全体に風雨が走る。事件などの噂が流れると、風雨に見舞われたように世間が騒ぎ出すこと。 |
| 満身創痍 | マンシンソウイ | からだ中が傷だらけの状態にあること。各方面から非難・中傷を受けて、精神的に痛めつけられているさま。徹底的に非難をうけ精神的にひどく痛めつけられること。体中が傷だらけの状態のことが転じて。「創痍」は、特に刃物でうけた傷。切り傷。 |
| 満目蕭条 | まんもくしょうじょう | 見渡す限り、ひっそりして物寂しいさま。 |
| 満目蕭然 | まんもくしょうぜん | 見渡す限り物寂しくひっそりしていること。 |
| 満を持す | まんをじす | 物事の最高潮の状態を維持すること。最高の状態で要人が登場する場合を表す表現として用いられることが多い。 |
| 漫言放語 | まんげんほうご | 深く考えず、思いついたまま口まかせに言い散らすこと。また、その言葉や話。 |
| 曼理皓歯 | まんりこうし | きめの美しい肌と白い歯。美人の形容。 |
| 蔓草寒煙 | まんそうかんえん | はびこる草と寂しい煙と。古跡などの荒れたてたさま。 |
| ミ | ||
| 未来永劫 | ミライエイゴウ | 仏教で、今後いつまでも続く果てしない時間。永遠、永久。 |
| 未練未酌 | みれんみしゃく | 相手の気持ちがくみ取れず、心残りであること。 |
| 見切り千両 | みきりせんりょう | 江戸中期に米沢藩を立て直した名君「上杉鷹山公」が残した言葉である。「見切り千両、無欲万両」と続く言葉が語源になっている。 |
| 彌陀名号 | みだのみょうごう | 南無阿弥陀仏をいう。また、その六字。これを唱えると浄土へいくいう思想がある。 |
| 微塵粉灰 | みじんこっぱい | こなごなになること。こっぱみじん。 |
| 水掛け論 | みずかけろん | |
| 水滴穿石 | みずしたたりていしをうがつ | 「雨垂石を穿つ」と 同じ意味。 |
| 以水投石 | みずをもっていしにとうず | 水を石にかけても、石が水をはね返すように、いかなる意見も全く受け入れてもらえぬこと。 |
| 以水減火 | みずをもってひをめつす | 水をもって火を消すことは、いとたやすいように、物事が安易にできるたとえ。 |
| 以水救水 | みずをもってみずをすくう |
水をそそいで水をとめようとする。手段を誤って、勢いをとめようとして反って勢いづかせること。「救」はとめること。 |
| 三日天下 | ミッカテンカ | 明智光秀が本能寺で織田信長を倒してから、わずか十三日で秀吉に倒されたことから、権力や地位を得た期間のきわめて短いことをいう。ほんのわずかな期間だけ実権を握ること。 |
| 三日坊主 | みっかぼうず | すぐに飽きてしまってなにをやっても長続きしないこと。 |
| 名詮自性 | みょうせんじしょう | 仏教で、名前はそのものの本性を言い表わすということ。名は体を表わす。 |
| 名聞利養 | みょうもんりよう | 世間の名声と利得。お金と地位に対する欲求。 |
| 苗字帯刀 | ミョウジタイトウ みょうじたいとう |
江戸時代、家柄や功労によって平民が特に苗字をとなえ、帯刀を許されたこと。 |
| 妙計奇策 | みょうけいきさく | 誰もが想像できなかった優れたはかりごと。 |
| 妙手回春 | みょうしゅかいしゅん | 手を触れれば春になるかのような、医師の凄い腕前をいう。敏腕の医師により、病気が良くなること。 |
| ム | ||
| 無悪不造 | むあくふぞう | ありとあらゆる悪事をはたらくこと。 |
| 無位無冠 | むいむかん | 重要な地位についていないこと。 類:無位無官。 |
| 無為徒食 | ムイトショク むいとしょく |
何もしないでただぶらぶらとして日を過ごすこと。働くこともせずに暮らすこと。何の仕事もせずにぶらぶらして暮らすこと。「徒食」は、働かずに遊び暮らすの意。 |
| 無為自然 | むいしぜん | 徳があれば教育しなくとも人は教化される。老子の主張する思想でことさらに法律で規制したり教育しなくても為政者の徳が高ければ人々は自然の本性に従って教化されてゆく。と言うこと |
| 無為無策 | ムイムサク | 何の対処・処置もないまま、ただ手をこまねいて見ていること。なにもしないこと。一定の計画が何もないこと。「無為」は何もせずにぶらぶらしていること。「無策」は前もって何の策もたてていないこと。 |
| 無援孤立 | むえんこりつ | 誰も助けるものがなく、ひとりぼっちのこと。 |
| 無官大夫 | むかんたゆう | 四位・五位の位にあって、官職のない者。公卿の子でまだ元服しない者。 |
| 無我夢中 | ムガムチュウ | 物事に熱中して自分を忘れること。あることに心を奪われて夢中になり、他のことを一切気にかけないこと。物事に熱中し、我を忘れること。一つの物事に心をとらわれて自分を忘れ、他のことを顧みないで行動すること。 |
| 無学文盲 | むがくもんもう | 学問がなく字も読めないこと。 |
| 無隅仔細 | むぐうしさい | こまかいところまで落度なく振舞うこと。 |
| 無芸大食 | ムゲイタイショク | 才能・特技などが何もなく、ただ大食をすること。そういう人。なんの特技、才芸もなくただ食べる量が多いこと。また、そのような無能な人。 |
| 無間地獄 | むげんじごく | 絶え間ない苦しみを受ける地獄。 |
| 無告之民 | むこくのたみ | だれにも自分の苦しみを告げ訴えることのできない者。転じて、妻・子・夫のいない身寄りのない貧しい人や孤児。 |
| 無私無偏 | むしむへん | 人に接するに私心なく、公平で偏りがないこと。 |
| 無常迅速 | むじょうじんそく | 万物が転変してやまないこと。人の世の移り変わりの非常に速いこと。 |
| 無色透明 | むしょくとうめい | 透き通ってにごりがない、汚れていないこと。 |
| 無水乾燥 | むすいかんそう | 猛暑で渇水が続き、天地万物乾燥しきって、生きとし生けるものすべてが水不足に悩むこと。 |
| 無知蒙昧 | ムチモウマイ むちもうまい |
知識・知恵がなく、物事の道理がわからないこと。知恵がなくておろかなこと。知識がなく物事の道理に暗いこと。 |
| 無茶苦茶 | むちゃくちゃ | でたらめで筋道が通らないこと。 |
| 無腸公子 | むちょうこうし | 蟹の別名。 |
| 無二無三 | むにむさん | ひたすらなこと。わき目もふらないこと。 |
| 無念無想 | むねんむそう | 無我の境地に入り、何も考えていないこと。いっさいの妄念を離れた無心のさま。あらゆる雑念がなくなり心が透明になるさま。仏教で無我の境地に入りすべての想念から離れること。 |
| 無病息災 | ムビョウソクサイ むびょうそくさい |
病気がなく健康であること。達者、元気でいること。健康で達者なこと。体のどこにも病気がなく、健康で無事であること。「息」は「呼吸」ではなく、「除く」の意。 |
| 無偏無党 | むへんむとう | 偏ることなく中立公平であること。 |
| 無味乾燥 | ムミカンソウ むみかんそう |
味わいや面白みがないこと。味もそっけもないこと。内容に少しもおもしろみのない様子。詩文などの文句が、修飾を欠き、または、意味の含蓄に乏しいことから。 |
| 無味無臭 | むみむしゅう | 味もにおいもない、つまり全く面白みがないこと。 |
| 無明長夜 | むみょうじょうや | 煩悩にさまよって悟りを開けない状態のこと。無明を闇の長夜に例えていう語。 |
| 無明世界 | むみょうせかい | 煩悩にとらわれた迷いの世界の意。「無明」は、真理にくらい無知のことで、もっとも根本的な煩悩。 |
| 無闇矢鱈 | むやみやたら | 「物事の結果・成否をよく考えずに、一途に(盲目的に)行動すること」を意味している。「物事の程度・状態が常軌を超えているさま、はなはだしくてひどいさま」という意味合いもある。 |
| 無用長物 | むようのちょうぶつ | 役に立たないじゃまもの。無駄なもの。 |
| 無用之用 | むようのよう | 一見無用と見えるものがかえって大用をなすことがある。 |
| 無欲恬淡 | ムヨクテンタン | 欲がなく、あっさりとしていて物にこだわらないこと。欲がなく淡々としていること。少しも物欲がなくあっさりとしていて、物事にこだわらないこと。 |
| 無理算段 | むりさんだん | 無理をしてお金を作ること。 |
| 無理往生 | むりおうじょう | 無理矢理に従わせること。強制的に承知・服従させてしまうこと。 |
| 無理難題 | ムリナンダイ | 道理に合わないいいがかり。できないことがわかっている問題や、とうてい承服できない条件。無法な言いがかり。 |
| 無理非道 | むりひどう | 道理にはずれたこと。 |
| 無理無体 | むりむたい | むりやりにする様子。道理にかなっていないことを無理矢理に押し通すこと。 |
| 無量寿物 | むりょうじゅぶつ | 阿弥陀如来の別名。 |
| 矛盾撞着 | ムジュンドウチャク むじゅんどうちゃく |
物事の前後がくい違い、うまくつじつまが合わないこと。 |
| 夢幻泡影 | むげんほうえい | 夢と幻と、泡と影。人生のはかなさを表わす語。 |
| 夢幻泡沫 | むげんほうまつ | ゆめまぼろしや水の泡。儚い事のたとえ。 |
| 武者修行 | むしゃしゅぎょう | 武芸者が修行のため諸国をめぐること。 |
| メ | ||
| 目茶苦茶 | めちゃくちゃ | ひどく混乱して普通でない状態のこと。 |
| 名公賢佐 | めいこうけんさ | 立派な君主と賢い家来。佐は補佐の臣。 |
| 名山勝水 | めいざんしょうすい | 美しい山や川に恵まれた景勝の地、晋の孫統は職務に専念するより、中国各地の山や川を訪ね歩いたという故事による。 |
| 名所旧跡 | めいしょきゅうせき | 名所は景色または古跡などで名高い所。旧跡は歴史の事件や事物のあったところ。旧蹟とも書く。 |
| 名声藉甚 | めいせいせきじん | 評判がひどく世に広まること。藉はしくの意味。 |
| 名誉棄損 | めいよきそん | 他人の社会的評価を公の場で傷つけること。 |
| 名誉挽回 | めいよばんかい | 失った信用を取り戻すこと。 |
| 名論卓説 | めいろんたくせつ | 優れた意見や議論。 |
| 明鏡止水 | メイキョウシスイ | 一点の曇りもない鏡や静止している水のように、よこしまな心がなく明るく澄みきった心境を指す。静かで物事に動じない状態。またそういう心境で物事をありのままとらえること。一点の曇りもなく磨き上げられた鏡と、澄みきった水。無私無欲で物事をありのままに見ることができる、静かに澄んだ心のこと。 |
| 明珠暗投 | めいしゅあんとう | 貴重なものでも、人に贈る方法が正しくなければ、かえって恨みを招く。 |
| 明窓浄机 | めいそうじょうき | 明るい窓と清潔な机。転じて、清潔で整頓された書斎のたたずまいをいう。 |
| 明哲保身 | めいてつほしん | 賢明で、身の処し方をよく心得ており、災いにかかわらず身を守れること。また、我が身の安全だけを考える人を非難する意味にも使われる。 |
| 明眸皓歯 | メイボウコウシ | ぱっちりした明るい瞳と真っ白に輝く歯の意。ひとみが澄み、目元、口元の美しい美人の形容。澄んだ瞳と白い歯。女性の顔かたちが非常に美しいこと。 |
| 明明赫赫 | めいめいかっかく | 明らかに輝く。 |
| 明明白白 | メイメイハクハク | はっきりしていて疑う余地のない様子。火を見るより明らか。はっきりとしていて少しも疑いようのない様子。「明白」をかさねて、意味を強める。 |
| 明目張胆 | めいもくちょうたん | 目を大きく見開き、腹を決め、何者も恐れないで事に当たること。 |
| 明朗闊達 | 性格が明るくさっぱりとしていること。「明朗」は、明るく朗らかなこと。心が広く物事にこだわらないこと。「闊達」は、「豁達」ともかき、心持ちが広くておおらかなこと。 | |
| 迷惑千万 | めいわくせんばん | 非常に迷惑であること。 |
| 冥冥之志 | めいめいのこころざし | 人には知られず努力する心。 |
| 銘肌鏤骨 | めいきるこつ | 肌にほりつけ、骨にちりばめる。心に覚えて忘れないこと。 |
| 銘心鏤骨 | めいしんるこつ | 心にほりつけ、骨にちりばめる。心に覚えて忘れないこと。 |
| 滅私奉公 | メッシホウコウ | 私心を捨て、国や社会のために尽くすこと。私心を取り去って公共的なことにつくすこと。滅私=自分の利益や都合を捨てさること。 |
| 免許皆伝 | メンキョカイデン | 師が芸術・武術などの奥義を残らずすべて弟子に伝授すること。その道の奥義をすべて伝えること。師から弟子に、芸道などのすべての奥義を伝授すること。「免許」は、伝授したことを証して与える許可状のこと。 |
| 面向不背 | めんこうふはい | どの角度から見ても美しいこと。前も後ろもともに美しくて表裏のないこと。「面向」はひたいの真ん中。もと、三方に正面をむけた仏像をいった語。転じて、どの角度から眺めても形が整い美しいことをいう。「背」は、後ろ、裏の意。「不背」は裏側がないこと。 |
| 面従後言 | めんじゅうこうげん | 従ったふりをして後で陰口をいうこと。人の面前では従いへつらい、退いてから陰で悪口を言うこと。 |
| 面従腹背 | メンジュウフクハイ | 面と向かっては服従していながら、腹の中では背反しているようす。相手の言うことに服従しているように見せかけて、心の中で背くこと。 |
| 面折廷争 | めんせつていそう | 主君の面前でその失政をくじき、朝廷でその是非を争うこと。剛直な家臣の形容。 |
| 面張牛皮 | めんちょうぎゅうひ | 性格が厚かましいこと。牛の皮を張ったように、つらの皮が厚く、尊大で厚かましいこと。 |
| 面目一新 | メンモクイッシン | 世間の評判が良くなるように、外見や内容を変化させる。改善されること。 |
| 面目躍如 | メンモクヤクジョ | 世間の評価を上げて面目をほどこし、生き生きしているようす。 |
| 面壁九年 | メンペキクネン | 一つの目的に長い歳月をかけて心を傾けること。長い年月をただひたすらに勉学することのたとえ。人の学業の精通していることをほめる言葉。 |
| モ | |||
| 妄言多謝 | モウゲンタシャ | 自分の独断偏見で述べた言葉について、その後に深くお詫びする意。 | |
| 妄想之縄 | もうぞうのなわ | 身を苦しめる迷い。 | |
| 孟母三遷 | モウボサンセン | 孟子の母が息子の教育にふさわしい環境を選んで住居を度々移したという故事。教育には環境が大事であるという戒め。孟子の母が三度も住居を移して幼い孟軻(孟子)の教育のための環境を選んだという故事による。 | |
| 孟母断機 | もうぼだんき | 孟子が途中で学をやめようとしたのを戒めた故事。続けていたことを途中で止めたら、これ以上進まないばかりか、すべて水の泡になるということ。 | |
| 猛虎伏草 | もうこふくそう | 英雄が世間から隠れていても、それは一時のことでいつかは必ず世に出るということ。 | |
| 盲管銃創 | もうかんじゅうそう | 銃弾が体を貫通せず、体内にとどまってできた傷。 | |
| 盲亀浮木 | もうきふぼく | 出会ったり、物事が実現したりすることがきわめて難しいことのたとえ。盲目の亀は、水上の浮き木には巡り会いにくい。 | |
| 網目不疎 | もうもくふそ |
|
|
| 罔極之恩 | もうきょくのおん | きわまりない父母の大恩。罔は無。 | |
| 蒙絡揺綴 | もうらくようてい | つる草の類が一面に絡み合い、枝葉が連なり動くこと。 | |
| 目使気使 | もくしきし | 口で指図せず、目つきや顔色で部下を使うこと。権勢の盛んなようすをいう。 | |
| 目営心匠 | もくえいしんしょう | 目ではかり、心の中で考えたくらむ。自分一人で工夫すること。 | |
| 目食耳視 | もくしょくじし | 見榮を張るために外見を飾ること。 | |
| 物見遊山 | モノミユサン | 物見とは祭や行事などを見にゆくこと。遊山は山や野に遊ぶことで、気晴しに見物や遊びに出かけること。気晴しに見物や遊びに出かけること。「物見」とは祭や行事などを見にゆくこと。「遊山」は山や野に遊ぶこと。 | |
| 諸刃の剣 | もろはのつるぎ | 両刃(諸刃)の剣は、振り上げると自らも傷つける恐れがあることから、利益をもたらす可能性がある一方で、損失をもたらす危険性もはらんでいることのたとえ。 | |
| 門外不出 | モンガイフシュツ | 貴重な物を家の外には絶対に出さずに大切に秘蔵すること。他人に見せたり持ち出さない。門(家)の外にださない(ほど大切にする)こと。 | |
| 門戸開放 | もんこかいほう | 出入りを自由にすること。 | |
| 門前雀羅 | モンゼンジャクラ | 門の前にスズメが群れて網でとらえられるくらい、ひっそりしていて閑散と寂しい様子。訪れる人がなく静まり返っていること。「雀羅」は、すずめを捕る網。訪れる人がいないので門前にすずめが群れ遊び、網を張って捕まえることができるほどであるの意。 | |
| 門前成市 | もんぜんせいし | 人が沢山集まるさま。→反・門前雀羅 | |
| 門生天子 | もんせいてんし | 唐の末に宦官が勢力をふるい、天子を門人同様に扱ったこと。 | |
| 問答無用 | もんどうむよう | 話し合っても無駄、話し合う必要がないこと。 | |
| 悶絶躄地 | もんぜつびゃくじ | 苦痛に耐えられず悶え苦しむこと。 | |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)