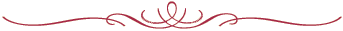
| 四文字熟語集5(ヤ~ワ行) |
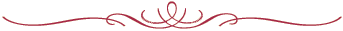
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、四文字熟語熟語言葉のヤ~ワ行を確認しておく。 2008.8.31日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| ヤ | ||
| 夜雨対床 | やうたいしょう | 兄弟が相思う心情。雨の夜、その音を聞きながら兄弟が床を並べて仲良く寝るさま。 |
| 夜深人静 | やしんじんせい | 夜が更けて、人が寝静まり、ひっそりとするさま。丑三つどきの静けさ。 |
| 冶金踊躍 | やきんようやく | 鍛冶屋の鋳る金鉄が、坩堝の中で跳ね返り、外に出ようとすること。分に安んじないたとえ。 |
| 薬石無効 | ヤクセキムコウ | 病人に対しての薬や治療も効果がなく、手当のかいが全くないこと。 |
| 薬籠中物 | やくろうちゅうのもの | 薬箱の中の常備薬。転じて、いつも手なずけておき、味方として自由に働かせられる人。 |
| 約法三章 | やくほうさんしょう | 法令を簡易にし、三ヵ条の法律にとどめること。 |
| 野心満々 | やしんまんまん | 大きな望みを持ってること。「野心」は、身分不相応の大きな望みのこと。 |
| 野無遺賢 | やむいけん | 官の任用から漏れた在野の賢人はいないはずだ。賢人はすべてしかるべき官庁に登用され立派な行政が行われること。 |
| 夜郎自大 | ヤロウジダイ | 自分の力量をわきまえず、仲間うちで威張ること。知識も力もないのに尊大にふるまう。世間知らずの人間が仲間内だけで威張ること。漢代に夜郎国が自分の国がもっとも強大であると思っていたことから。 |
| ユ | ||||
| 以湯沃雪 | ゆをもってゆきにそそぐ | 湯で雪をとかすことは、きわめて簡単なこと。物事が容易にできるたとえ。 | ||
| 油断大敵 | ユダンタイテキ | 油断すれば必ず失敗の元になるから、油断を非常に警戒しなくてはならない。油断は恐ろしい敵のようなものであること。「油断」はもともと仏教語で、灯明の油を絶やすことから、気を許して注意を怠ることをいう。 | ||
| 唯一無二 | ユイツムニ ゆいつむに |
ただそれ一つだけで二つとないこと。他にない貴重なものであること。 | ||
| 唯我独尊
|
ユイガドクソン ゆいがどくそん |
この世に自分より優れた者はいないという意。自分が一番偉いと思っている態度をいう。世の中で自分だけがえらいと思い上がること。釈迦が言ったとされる言葉で、天地で自分だけが尊いことから転じて。 | ||
| 惟適之安 | ゆいてきのあん | ただ自分の心にかなうことに安んじる。自分の心のままになるのをよしとする。 | ||
| 有害無益 | ゆうがいむえき | 害だけあって何の役にも立たないこと。 | ||
| 有脚書厨 | ゆうきゃくしょちゅう | 脚のある書斎。転じて、博学多識の人をいう。 | ||
| 有脚陽春 | ゆうきゃくようしゅん | 到る所に恩徳を施すこと。脚のある春の意味。春が万物を発生させるように、仁徳を施すこと。唐の宋璟の故事。 | ||
| 有形無形 | ゆうけいむけい | 形のあるものと形のないもの。 | ||
| 有言実行 | ゆうげんじっこう | 言葉通りのことを実行すること。 | ||
| 有識之士 | ゆうしきのし | 事の道理に明るい人。 | ||
| 有枝添葉 | ゆうしてんよう | 話などに尾ひれをつけてことさらおおげさにすること。 | ||
| 有終完美 | ゆうしゅうかんび | 何事も終わりが肝心であること。最後まで物事を立派にやり遂げること。「有終」は、「終わり有り」で、終わりをまっとうする意。 | ||
| 有終之美 | ゆうしゅうのび | 最後まで立派に成し遂げること。 | ||
| 有心故造 | ゆうしんこぞう | 人の足を引張ったり、陥れようと心に企みをもって、わざと事を行うこと。 | ||
| 有職故実 | ゆうそくこじつ | 公家や武家の制度、官職の先例。「有職」は、職に関する知識のある意。「故実」は、古い事柄。平安時代以降の公家や武家の儀式、法制、作法、服飾などの実例や習慣のこと。 | ||
| 有待之身 | ゆうたいのみ | いつかは事を成そうと時期を待つ身。 | ||
| 有天無日 | ゆうてんむじつ | 天空に太陽がない。途方も無いことをいう。 | ||
| 有名無実 | ゆうめいむじつ | 名ばかりで実質がともなわないこと。 | ||
| 勇往邁進 | ゆうおうまいしん | 目的を貫こうとしてわきめもふらず勇気を奮ってまっしぐらに進むこと。「勇往」は、勇んですすむこと。 | ||
| 勇気凛凛 | ゆうきりんりん | 勇気に満ちあふれて、いきいきとしたようす。 | ||
| 勇将弱卒 | ゆうしょうじゃくそつ | 強く勇ましい大将の元では、兵卒はそれに感化されて強くなり、弱い者はいない。 | ||
| 勇退高踏 | ゆうたいこうとう | 官職を辞して俗世間から離れた生活を送ること。 | ||
| 勇猛果敢 | ゆうもうかかん | 勇ましく強くて、決断力に富むこと。多少の抵抗にも負けず、思い切って物事を行うこと。「勇猛」は、勇ましく猛々しいこと。「果敢」は、決断力に富むこと。 | ||
| 勇猛精進 | ゆうもうしょうじん | 心を強く持って、わき目も振らず仏道を修行すること。困難に打ち勝って進み、一心に励む。 | ||
| 優柔不断 | ゆうじゅうふだん | ぐずぐずしていて決断の遅いこと。決断力に乏しいこと。 | ||
| 優勝劣敗 | ゆうしょうれっぱい | 能力のまさっているものが勝ち、劣るものが負ける。強者、適格者が栄えていくこと。 | ||
| 優游涵泳 | ゆうゆうかんえい | 「優游」は、急がずゆったりとした態度、「涵泳」は水にもぐって泳ぎをすることから対象に傾倒する。 ゆったりした気持ちで学問や技芸の深い味わいをすること。 | ||
| 優游恬淡 | ゆうゆうてんたん | ゆったりとしてあっさりしていること。物事にこだわらないこと。 | ||
| 優游無事 | ゆうゆうぶじ | 暇があってのんびりしていること。 | ||
| 優游不迫 | ゆうゆうふはく | ゆったりとしてこせこせしないこと。 | ||
| 融通無碍 | ユウズウムゲ | 滞りのないこと。考え方や行動に差別やこだわりのないさまをいう。何物にも妨げられることなく、自由なさま。自由でのびのびしていること。すらすら滞ることなく通り、障害があってつかえたりしないこと。「無碍」は、障害が無くて自由であること。「碍」は、「礙」とも書き、さまたげの意。 | ||
| 悠々闊歩 | ゆうゆうかっぽ | |||
| 悠悠緩緩 | ゆうゆうかんかん | のんきでゆったりとしているさま。のんびりしていること。 | ||
| 悠悠自適 | ゆうゆうじてき | 俗世間を退いて、のんびりと日々を過ごすこと。定年退職後の生活などをいう。 | ||
| 雄材大略 | ゆうざいたいりゃく | 雄々しい才能と遠大な計画。大きな事業を推進するのにふさわしい才能をいう。 | ||
| 宥座之器 | ゆうざのき | かたわらに置いて戒めとする道具。宥は右の意味。 | ||
| 熊虎之将 | ゆうこのしょう | 熊や虎のような、勇猛な大将。 | ||
| 熊羆之士 | ゆうひのし | 熊やひぐまのように勇猛な士。勇ましい侍。猛士。 | ||
| 右文左武 | ゆうぶんさぶ | 文を右にし武を左にする。文武二つの方法で天下を治める。 | ||
| 幽明異境 | ゆうめいいきょう | 死別すること。 | ||
| 遊刃余地 | ゆうじんよち | 余裕をもって物事を処理するたとえ。 | ||
| 邑里蕭条 |
|
|||
| 黝堊丹漆 | ゆうあくたんしつ | 青黒く塗ることと、赤く塗ること。青・白・赤・黒の色。 | ||
| 游雲驚竜 | ゆううんきょうりゅう | たなびく雲と驚く竜。書がいかにも思うさまのびのびとし、巧妙なさま。 | ||
| 兪扁之術 | ゆへんのじゅつ | 昔の名医である兪[足付]と扁鵲との医術。転じて名医の治療。 | ||
| 兪扁之門 | ゆへんのもん | 名医の門。昔の名医である兪[足付]と扁鵲との家の意味。 | ||
| 弓矢八幡 | ゆみやはちまん | 武神である八幡大菩薩。武士が誓いを立てるときにいう言葉。偽りのないことを誓う言葉。 | ||
| ヨ | ||
| 四方山話 | よもやまばなし | |
| 余韻嫋嫋 | よいんじょうじょう | 発声が終わってもなお残る響きが、絶えることなく続くようす。出来事や詩文などの余情にも。 |
| 余裕綽々 | ヨユウシャクシャク | ゆったりとしてあせらない、落ち着いていること。せこせこしない様子。落ち着き払い悠然としているさま。ゆとりがあってこせこせしない、ゆったりしているさま。 |
| 夜声八丁 | よごえはっちょう | 夜はあたりが静かだから、小声で言っても八丁先まで聞こえる、ということから聞こえやすいことのたとえ。ささやき八丁。 |
| 夜目遠目 | よめとおめ | 夜見たり、遠くから見ること。→実質を見極めない様。 |
| 夜雨対床 | やうたいしょう | |
| 用意周到 | ヨウイシュウトウ よういしゅうとう |
何事にも用意がすみずみまで行き届き、手抜かりのないこと。手段、方法、段取りが十分に行き届いて手抜かりがないこと。 |
| 用行捨蔵 | ようこうしゃぞう | 出処進退の態度が立派で巧みなたとえ。自分が用いられるなら理想を追及して行動し、捨てられるのなら、一時理想をしまいこんでチャンスを待つという態度。 |
| 用舎行蔵 | ようしゃこうぞう | 世に用いられれば、出て道を行ない、捨てられれば去って身を隠す。 |
| 用筆沈雄 | ようひつちんゆう | 絵や字の筆つきが落ち着いていて、力がこもっていること。 |
| 羊質虎皮 | ようしつこひ | 羊が虎の皮をかぶる。外見は立派だが、実質が伴っていないことにたとえる。 |
| 羊頭狗肉 | ようとうくにく | 羊の頭を看板に出しておき、その実は、いぬの肉を売ること。看板に偽りあり。見かけだけ立派にしていて、中身は悪いこと。看板に羊の頭をかかげて、実は狗(犬)の肉を売った。 |
| 要害堅固 | ヨウガイケンゴ ようがいけんご |
地勢が険しくて、攻め落とすのが非常に難しいようす。 |
| 容姿端麗 | ようしたんれい | 顔立ちも体形も整っていて美しいこと。普通は女性に使う。「端麗」は、きちんと整っていて麗しいこと。 |
| 容貌魁偉 | ようぼうかいい | 顔つき、体つきがたくましくて立派なさま。 |
| 陽関三畳 | ようかんさんじょう | 別れを繰り返し惜しむこと。陽関曲の第四句(結句)を三度繰り返しうたい別れを惜しむこと。 |
| 陽動作戦 | ようどうさくせん | 敵の注意をそらすために別の方面でわざと目立った動きをする作戦。 |
| 陽春白雪 | ようしゅんはくせつ | 高尚な歌は調子を合わせてともに歌える人が少ない。優れた言行を理解できる人は少ないことのたとえに用いる。 |
| 揚清激濁 | ようせいげきだく | 「清を揚げて濁を激す」。清らかな水を溢れさせて、濁った水を砕き遮ぎることから、善を賞で讃え、悪を除くこと。 「激」は流れる水が岩に当り砕け散ること。 |
| 妖怪変化 | ようかいへんげ | 不思議な現象や化け物のこと。 |
| 庸中侊侊 | ようちゅうのこうこう | 普通の人の中で、やや勝っている人のこと。 |
| 庸夫愚婦 | ようふぐふ | 並みの男や愚かな女。つまらぬ人々。 |
| 蝿頭細書 | ようとうさいしょ | 蝿の頭ほどの非常に小さい字。 |
| 瑤林瓊樹 | ようりんけいじゅ | 玉の木や林。人品が気高くて、常の人よりすぐれていること。 |
| 瑤宮瓊闕 | ようきゅうけいけつ | 玉で飾った宮殿。立派な宮殿。 |
| 浴沂之楽 | よくきのたのしみ | 人々とともに清遊する楽しみ。曾皙が孔子の問いに対して、大人5~6人、子供6~7人と沂という川で水浴し、雨乞いをする小高い所で涼をとり、歌いながら帰ろうといったのに対し、孔子が、わたしもそうありたいといった故事。 |
| 翼覆嘔煦 | よくふおうく | 翼でおおい、息を吹きかけて暖める。転じて、人をなでさすってかわいがること。 |
| 沃野千里 | よくやせんり | 肥えた平地が非常に広く広がりつづけていること。 |
| 抑揚頓挫 | よくようとんざ | 音楽や言葉の上げ下げの調子が急に変化してくじけること。 |
| 欲求不満 | よっきゅうふまん | 欲求が満たされず、いらいらする状態。 |
| ラ | ||
| 来来世世 | らいらいせせ | 来世の来世。遠い未来のこと。 |
| 頼芸求食 | らいげいきゅうしょく | 芸を売って生活する。芸が身を助ける。また、官位や禄に未練があってなかなかやめようとしない。 |
| 雷陳膠漆 | らいちんこうしつ | 友情の非常に厚いこと。 |
| 磊磊落落 | らいらいらくらく | 心が非常に大きく朗らかなこと。小さなことにこだわらないさま。石が積み重なって大変大きいさまも示す。「磊落」だけでも心が大きく、ちいさなことにこだわらないさま。 |
| 落英繽紛 | らくえいひんぷん | 散った花びらが乱れ散るさま。繽紛は、乱れる。 |
| 落月屋梁 | らくげつおくりょう | 入りかかった月が屋根を照らす。故人を思う心が切なること。 |
| 落地成根 | らくちせいこん | 植物の種子が地に落ちて、やがて根を張る。そして花が咲き、葉が繁り、また落葉となって根に帰る。 |
| 落筆点蝿 | らくひつてんよう | 画家の妙技、凄腕をいうたとえ。 |
| 落落之誉 | らくらくのほまれ | 心の大きな度量のある人物という名声。 |
| 落落磊磊 | らくらくらいらい | 石が重なり集まっている状態。また、物事にこだわらないさま。 |
| 落花時節 | らっかのじせつ | 春の末、花の落ちるころ。 |
| 落花翩翩 | らっかへんぺん | 散ってゆく花びらがひらひらと舞うさま。 |
| 落花流水 | ラッカリュウスイ らっかりゅうすい |
衰退という意味も。また、男女が相互に慕いあうことの意味も。男に女を思う情があれば、女にもまた男を慕う情があるということ。(落ちる花にも情あれば、流れゆく水にも情があり、散る花をのせていくという意)。 |
| 落花狼藉 | ラッカロウゼキ | 花が散り乱れているようす。そこから転じて物が入り乱れて散らかっているさまをいう。花やものが散り乱れている様子。ものがちらかっている様子。「狼藉」は、狼が草をしいて寝た後の乱れたさまから、乱暴なさま、散乱したさまを言う。 |
| 洛陽紙価 | らくようのしか | 著書が世の人々に賞賛され、盛んに売れて読まれることをいう。 |
| 乱離骨灰 | らりこっぱい | 散々に離れ散ること。めちゃめちゃになること。 |
| 乱臣賊子 | らんしんぞくし | 国を乱す悪臣と親に害を与える子供。不忠不孝の者をいう。 |
| 乱世之音 | らんせいのおん | 乱れた世の音楽。 |
| 乱筆乱文 | らんぴつらんぶん | 文字や文章を乱暴に書くこと。また、乱暴に書いた字。自分の文字・文章をへりくだっていうときにも用いる。 |
| 乱暴狼藉 | ランボウロウゼキ らっかろうぜき |
荒々しい振る舞いをしたり、道理にはずれた無法な行いをすること。暴力を振るって暴れまくること。「狼藉」は、狼が草をしいて寝た後の乱れたさまから、乱暴なさま、散乱したさまを言う。 |
| 乱脈経営 | らんみゃくけいえい | 筋道の立たない、でたらめな経営の仕方。 |
| 卵翼之恩 | らんよくのおん | 幼少から育てあげられた親の恩。父母が大事に子供を育てる恩をいう。 |
| 嵐影湖光 | らんえいここう | 山の青々としたかげと湖の光。山水の風景をいう。 |
| 藍田生玉 | らんでんせいぎょく | 「藍田」は地名。藍田からは美しい玉を産出する。転じて、名門から優れた子弟の出ることをほめていう。 |
| 蘭摧玉折 | らんさいぎょくせつ | 賢人や美人の死を例えて言う。「蘭摧玉折と為るとも、蕭敷艾栄(しょうふがいえい)とは作(な)らず」という語から。何の取り柄もなく漠然と生きるよりは、潔く死ぬ方が本望である意。 |
| 蘭秀菊芳 | らんしゅうきくほう | らんと菊との香り。 |
| 藍尾の酒 | らんびのさけ | |
| リ | ||
| 利益相反 | りえきそうはん | 役職にある人物(政治家、企業経営者、弁護士、医療関係者、研究者など)が、立場上追求すべき利益に反し、その人物が他にも有している立場での利益を求める行為に対して、そういう競合ないしは相反している状態をいう。略語として、COI(英語: conflict of interest)が用いられることもある。 |
| 利害得失 | リガイトクシツ りがいとくしつ |
利益と損害。儲けと損。 |
| 利敵行為 | りてきこうい | その言動が、敵側にとって有利になるような行い。 |
| 利用厚生 | りようこうせい | 人民の使う道具類を便利にし、衣食を豊かにし、暮らしが楽になるようにすること。 |
| 理非曲直 | リヒキョクチョク りひきょくちょく |
道理に合ったことと、合わないこと。間違ったことと、正しいこと。物事の善意・正不正のこと。物事の是非を問う場合に「理非曲直を糺(ただ)す」という言い方で多く使われる。 |
| 理路整然 | リロセイゼン りろせいぜん |
話や議論などのすじみちがよく整っているようす。話や考えの筋道がきちんと整っているさま。「理路」は、物事の道理。 |
| 離群索居 | りぐんさくきょ | 仲間から離れて一人でいること。 |
| 離合集散 | リゴウシュウサン りごうしゅうさん |
離れたり、合わさったり、別れたり集まったりすること。 |
| 離朱之明 | りしゅのめい | 目がよく見えることをいう。離朱は百歩を離れて、毛の先がよく見えたという視力のすぐれた人。 |
| 李下瓜田 | りかかでん | スモモの木の下で冠を正し、瓜の畑で履物を履き直す意であるが、人の疑惑を招くような行い。 |
| 李下之冠 | りかのかんむり | 疑われやすい言動は避けなければならないということ。李の木の下で冠をかぶり直すと、李の実を盗むのではないかと疑われるのでいう。 |
| 李広成蹊 | りこうせいけい | 「蒙求」の標題。立派な桃や李の木の下には、人が来て、自然に小道が出来るように、徳のある人は黙っていても、人が自然にその人に付き従うようになることのたとえ。漢の李広が死んだとき、みな悲しんで泣き、「桃李言わざれども、下おのずから蹊を成す」といわれた故事。 |
| 李杜韓柳 | りとかんりゅう | 唐の李白・杜甫・韓愈・柳宗元の四人の略。李・杜は詩、韓・柳は文に優れていた。 |
| 梨園弟子 | りえんていし | 俳優。役者。 |
| 履霜之戒 | りそうのいましめ | 霜が降るのはやがて氷が張る前兆で、前兆によって、あらかじめ災いを防がなければならないというたとえ。 |
| 鯉魚尺素 | りぎょせきそ | 手紙のこと。鯉の腹中から白絹に書かれた手紙が出たという故事。 |
| 力戦奮闘 | りきせんふんとう | 力を出し尽くして闘うこと。一所懸命努力すること。 |
| 六尺之孤 | りくせきのこ | 十四、五歳のみなしご。 |
| 六尺之託 | りくせきのたく | 幼君の後見を託されること。 |
| 六韜三略 | りくとうさんりゃく | 奥の手。虎の巻。中国の兵法書「六韜」「三略」より。 |
| 戮力協心 | りくりょくきょうしん | 一致協力して物事を行なうこと。 |
| 立身出世 | リッシンシュッセ りっしんしゅっせ |
社会的に認められて、世間に名を知られるようになること。立身して社会に認められること。 |
| 立錐之地 | りっすいのち | 錐の先を立てるほどの狭い土地。 |
| 竜虎相搏 | りゅうこあいうつ | 二人の強いものが勝敗を争う。両雄相戦う。 |
| 竜舟鷁首 | りゅうしゅうげきしゅ | 貴人の乗る船。二隻一対で、一隻はへさきに竜の頭を、一隻は鷁の首の形を彫刻してあるからいう。 |
| 竜驤虎視 | りゅうじょうこし | 天下に権威をふるうさま。竜のようにのぼり、虎のようににらむこと。「驤」は、おどりあがって天に昇る、勢いのさかんなこと。「虎視」は、虎が獲物を恐ろしい目でにらみすえる意。 |
| 竜攘虎搏 | りゅうじょうこはく | 竜と虎が喧嘩するように互角の強者が闘うこと。 |
| 竜頭鷁首 | りゅうとうげきしゅ | 貴人の乗る船。二隻一対で、一隻はへさきに竜の頭を、一隻は鷁の首の形を彫刻してあるからいう。 |
| 竜頭蛇尾 | リュウトウダビ | 最初は竜のように立派だが、終りになるに従い蛇の尾のように尻すぼみになること。すなわち、始めは盛んであるが、終りが振るわないこと。初めは立派であるが、だんだん尻すぼみになって終わりには全く勢いのないこと。頭は竜のように立派であるが、尾は蛇のように貧弱であることから。 |
| 竜蟠虎踞 | りゅうばんこきょ | 竜がとぐろを巻き、虎が蹲る。強いものがある場所で権勢を振るう事。 |
| 竜門之遊 | りゅうもんのゆう | すぐれた人の遊び。 |
| 竜門扶風 | りゅうもんふふう | 司馬遷と班固。司馬遷は竜門(山西省の地名)の人、班固は扶風(陜西省の地名)の人。ともに漢代の歴史家。転じて、歴史、また、歴史家。 |
| 竜駒鳳雛 | りょうくほうすう | 優れた少年のたとえ。 |
| 竜虎之姿 | りょうこのし | 竜や虎のすぐれた姿。風采。英雄の素質と威儀。 |
| 竜驤麟振 | りょうじょうりんしん | 竜のように登り、麒麟のように奮う。威勢のすぐれたさま。 |
| 竜瞳鳳頸 | りょうどうほうけい | 竜のような瞳と鳳凰のようなくび。極めて貴い人相とされる。 |
| 竜飛鳳舞 | りょうひほうぶ | 竜が飛び、鳳凰が舞っているかと思われるような霊妙な山のさま。 |
| 流芳後世 | りゅうほうこうせい | よい評判・名声を後世にまで残すこと。 |
| 流汗淋漓 | りゅうかんりんり | 流れる汗がしたたり落ちる様子。 |
| 流金鑠石 | りゅうきんしゃくせき | 暑気のはなはだしいこと。金を溶かし石を溶かすの意味。 |
| 流金焦土 | りゅうきんしょうど | 大日照りで、金石が溶けて流れ、土や山が焼けこげになるくらい暑いことをいう。 |
| 流寓漂泊 | りゅうぐうひょうはく | 落ちぶれてさすらう。 |
| 流血淋漓 | りゅうけつりんり | 血が流れしたたるさま。 |
| 流言飛語 | リュウゲンヒゴ | 誰いうともなく伝わる、根拠のない、いいかげんな噂。根も葉もないデマ。根も葉もないいい加減なうわさ。 |
| 流行坎止 | りゅうこうかんし | 流れに乗れば行き、険しい所に合えば止まる。流れに任せるたとえ。 |
| 流觴曲水 | りゅうしょうきょくすい | 陰暦三月三日に、曲水に杯を流し、その杯が自分の前に流れてこないうちに詩を作り、互いに詩才を競い合った故事。 |
| 流觴飛杯 | りゅうしょうひはい | 酒宴を開いて酒を酌み交わす。 |
| 流星光底 | りゅうせいこうてい | 振り上げた名刀の下。 |
| 流離零落 | りゅうりれいらく | おちぶれる。 |
| 流連荒亡 | りゅうれんこうぼう | 遊びにふけって家に帰らなかったり、飲酒などの遊興で、結果、国を滅ぼす意。 |
| 柳暗花明 | りゅうあんかめい | 柳が薄暗く茂り、花が明るく咲く、春の美しい景色。転じて、行き詰まったかと思った途端、新しい展開がひらけることにもたとえる。 「遊里」をいうこともある。 |
| 柳巷花街 | りゅうこうかがい | 柳が植えられ、花も咲いて風情のあった遊里、色町のこと。 |
| 柳眉倒豎 | りゅうびとうじゅ | 女性が怒って、眉を逆立てるさま。 |
| 柳緑花紅 | りゅうりょくかこう | 柳は緑、花はくれない。春の自然のありさま。物が自然のままで人工の加わらないこと。悟りを開いた状態の形容。 |
| 粒粒辛苦 | リュウリュウシンク りゅうりゅうしんく |
こつこつと努力、苦労を重ねること。長い間苦労を積み重ね仕事の完成に向かって努力すること。穀物の一粒一粒が農業に従事する人々の苦労の結果であるということから。 |
| 劉伶解酲 | りゅうれいかいてい | 「蒙求」の標題。劉伶が酒を好み、妻が諌めた時、一飲一斛を目標にし、それで酔えば、さらに五斗も飲み酲(よい)を醒ますことができようと言った故事。 |
| 旅進旅退 | りょしんりょたい | ともにそろって進み、そろって退く。進退をともにする。また、定見や節操をもたず、ただ他人の意見に従うこと。(=付和雷同) |
| 良玉精金 | りょうぎょくせいきん | すぐれた文章のたとえ。 |
| 良玉美金 | りょうぎょくびきん | すぐれた文章のたとえ。 |
| 良禽択木 | りょうきんたくぼく | 立派な人は立派な主君を選んで仕えること。 |
| 良金美玉 | りょうきんびぎょく | よい金と、うるわしい玉。すぐれた文章のたとえ。 |
| 良妻賢母 | りょうさいけんぼ | 夫に対してはよい妻であり、子に対しては賢い母であるような女性。 |
| 良史之材 | りょうしのざい | すぐれた歴史家としての才能。 |
| 良知良能 | りょうちりょうのう | 本来人間が生まれながらに持っている知恵と才能。 |
| 良風美俗 | りょうふうびぞく | その社会を支えている健全な風俗。 |
| 両部習合 | りょうぶしゅうごう | 本地垂迹説に基づき、仏教と神道を一つにした神道。 |
| 両鳳連飛 | りょうほうれんぴ | 二羽の鳳凰が翼を連ねて飛ぶ様子をいい、兄弟がともに出世することをいう。 |
| 凌雲之志 | りょううんのこころざし | 俗界を離れて高く別天地に遊ぶ願い。 |
| 凌霄之志 | りょうしょうのこころざし | 大空をもしのぐ高い望み。 |
| 燎原之火 | りょうげんのひ | 野原を焼く火。野火。勢い激しく、はびこって盛んになるたとえ。 |
| 陵谷之変 | りょうこくのへん | 高い丘が変わって深い谷となり、谷が変じて丘となる。世の中の変遷のはなはだしいことのたとえ。 |
| 両三行涙 | りょうさんこうのなみだ | 二筋三筋の涙。はらはら落ちる涙。 |
| 両手に花 | ||
| 量入制出 | りょうにゅうせいしゅつ | 収入をはかって、しかるのちに支出を定めること |
| 梁上君子 | りょうじょうのくんし | 盗人の別名。漢の陳寔が賊が忍び込んで、梁の上に隠れているのに気がついて、「人の本性は善良であるが、悪い習慣がつけば、悪人となる。梁の上の君子がそれだ」と子弟に訓戒した。それを聞いて盗賊は梁から降りて罪を謝したという故事。 |
| 綾羅錦繍 | りょうらきんしゅう | 美しい衣服、また、目もあやに美しいものを表現する時に使う言葉。 |
| 遼東之豕 | りょうとうのいのこ | 他の社会を知らないことから小さなことを得意に思うこと。 |
| 緑浄春深 | りょくじょうしゅんすい | 「緑は清く春は深し。」清く澄んで水に映える緑。春は今が盛りの新しい色に輝いている。 |
| 輪廻転生 | りんねてんしょう | 何度も死んでは生まれ変わること。 |
| 臨渕羨魚 | りんえんせんぎょ | 「渕に臨みて魚を羨む」。渕の傍らに立って魚が慾しいと思っているだけでは、魚は手に入らない。 効果的手段を考えることがたいせつの意。 |
| 臨渇掘井 | りんかつくっせい | のどが渇いてから、井戸を掘るということで、差し迫っての必要に、間に合わないたとえ。盗人を捕らえて縄をなう。 |
| 臨機応変 | リンキオウヘン りんきおうへん |
時と場合によって柔軟にうまく適切な処置をすること。状況の変化に応じて、ふさわしい処理をすること。「気に臨(いど)み変に応ず」と読む。 |
| 臨終正念 | りんじゅうしょうねん | 死に臨んで、心が乱れず、往生を信じて疑わないこと。 |
| 臨終之什 | りんじゅうのじゅう | 死に際に作る詩歌。辞世の句。 |
| 臨深履薄 | りんしんりはく | 非常に危険なこと。 |
| 隣里郷党 | りんりきょうとう | 村里。郷里。近所やその地方。五家が隣、五隣が里、四里が族、五族が党、五党が州、五州が郷(12500家)。 |
| 淋漓尽致 | りんりじんち | 話しことばや文章表現が流暢で、十分に意を尽くしていること。「淋漓」は水のしたり落ちること。 「尽致」は十分に意を尽すこと。 |
| 倫理道徳 | りんりどうとく | 人として守るべき道。モラル。 |
| 綸言如汗 | りんげんあせのごとし | |
| 麟角鳳嘴 | りんかくほうし | 麒麟の角と鳳凰のくちばし。きわめてまれにあるもののたとえ。 |
| 麟趾之化 | りんしのか | 皇后の徳化をいう。周の文王の后妃の徳を、詩人が「麟之趾」の詩を作って、ほめたたえたことよりいう。 |
| 鱗次櫛比 | りんじしっぴ | 細かくびっしりしているようす。(鱗や櫛のように。) |
| 麟鳳亀竜 | りんぽうきりょう | 麒麟と鳳凰と仙亀と神竜。四神にあたる。珍しいもの、また、すぐれた賢人のたとえ。 |
| ル | ||
|
類比推理 |
ルイヒスイリ るいひすいり |
物事の間に見られる類似点を比較したりして、相互関係や共通点を推測すること。 |
| 累進課税 | るいしんかぜい | 収入額が増えるにつれて税率も上がる税制。 |
|
累卵之危 |
ルイランノキ るいらんのあやうき |
卵を積み重ねたように崩れやすく、きわめて不安定で危険な状態にあること。 |
|
流転輪廻 |
ルテンリンネるてんりんね | 仏教で衆生の魂が車輪のように回転して巡り、生きかわり、死にかわりするという考え。 |
| 流浪落魄 | るろうらくはく | 落ちぶれる。 |
|
縷縷綿綿 |
ルルメンメン るるめんめん |
話が長くこまごまと続くようす。 |
| レ | ||
| 礼楽刑政 | れいがくけいせい | 礼儀、音楽、刑罰、政令。いずれも国の秩序を維持する基本となるもの。 |
| 礼勝則離 | れいしょうそくり | 礼儀も度をこえて強制すると、束縛として感じられ人心が離れてしまう。 |
| 礼煩則乱 | れいはんそくらん | 礼儀も度を越えて強制すると束縛と受けとられて、人心が離れてしまう |
| 冷汗三斗 | れいかんさんと | 非常に怖いこと。また、恥ずかしい思いをすること。「三斗」は量の多い例え。冷や汗が三斗も出る意から、非常に恥ずかしい思いや、恐ろしいことにあったときの気持ちに使う。 |
| 冷眼下瞰 | れいがんかかん | 「冷眼もて下瞰す」とも読む。白目でじろりと見下ろす。 |
| 冷眼傍観 | れいがんぼうかん | 冷静な態度で推移を見守る、冷ややかな眼付きで傍観すること。 |
| 冷吟閑酔 | れいぎんかんすい | さりげなく詩を口ずさみ、のんびりと酔う、という自由で気楽な暮らし。(白楽天) |
| 冷酷無残 | れいこくむざん | 人間らしい情がなくむごたらしく残忍なこと。 |
| 冷酷無情 | れいこくむじょう | 冷酷で、思いやりの気持ちがないこと。情け知らず。 |
| 冷静沈着 | れいせいちんちゃく | 落ち着いていて動揺しないこと。物事に動じず、あわてることのないさま。 |
| 冷暖自知 | れいだんじち | 水の冷たいか、暖かいかはそれを飲む人が知る。自分のことは他人にとやかくいわれなくても自分で判断することをいう。 |
| 令聞嘉誉 | れいぶんかよ | よい誉れ。立派な評判。 |
| 令聞広誉 | れいぶんこうよ | 世に広がった良い評判。 |
| 令聞令望 | れいぶんれいぼう | すぐれた令名と、立派な声望。令はすぐれて、立派、よい、という意。 |
| 令狸執鼠 | れいりしつそ | その人の長所・特技を生かして使うたとえ。「狸(野猫)に令して鼠を執らしむ」。 |
| 霊魂不滅 | れいこんふめつ | 肉体は滅びても魂はいつまでも滅びないこと。 |
| 零丁孤苦 | れいていこく | 落ちぶれて助ける人もなく、一人苦しむこと。 |
| 砺山帯河 | れいざんたいが | 国が永久に持続する意味。(黄河が帯のように細くなり、泰山が砥石のように平らになろうとも。) |
| 櫪馬籠禽 | れきばろうきん | 馬屋につながれた馬と籠に入れられた鳥の意で、拘束されて自由にならない身のたとえ。(= 籠鳥檻猿) |
| 連鎖反応 | れんさはんのう | 鎖のようにつぎつぎと反応が起こること。 |
| 連戦連勝 | れんせんれんしょう | 何度も戦ってそのたびに勝つこと。 |
| 連帯責任 | れんたいせきにん | 二人以上の人が連帯で責任を負うこと。 |
| 連篇累読 | れんぺんるいとく | だらだら無用の文章を書き綴ること。 |
| 蓮華往生 | れんげおうじょう | 死後、極楽浄土の蓮華台に生まれ変わる。死んで極楽に行くこと。 |
| 蓮華世界 | れんげせかい | 極楽浄土をいう。 |
| ロ | ||
| 路線転換 | ろせんてんかん | それまでの行き方を別方向へ切り替えること。 |
| 露宿風餐 | ろしゅくふうさん | 野宿すること。旅の困難をいう。 |
| 炉火純青 | ろかじゅんせい | 炉の火炎が純青になると温度も最高に達する。転じて学問や技芸が最高の域に達すること。名人の域に達するたとえ。 |
| 炉辺談話 | ろへんだんわ | 囲炉裏ばたでくつろいでするおしゃべり。ろばたの四方山語(よもやまご)。 |
| 蘆花浅水 | ろかせんすい | あしの花の咲いている水の浅いところ。 |
| 盧生之夢 | ろせいのゆめ | 一炊之夢に同じ。 |
| 魯魚亥豕 | ろぎょがいし | 文字の書き誤り。 |
| 魯魚之誤 | ろぎょのあやまり | 文字の写し誤り。魯の字と魚の字は字形が似ているので、よく間違えることから、文字を間違えることをいう。 |
| 魯陽之戈 | ろようのほこ | 戦国時代に、楚の魯陽公が韓と戦って激戦のさなか、日が暮れようとしたとき、彼がほこを上げて日を招くと日は三舎(九十里。軍隊の一日の行程。周尺で36.45粁)ほども返ったという故事。勢威の盛んなことにいう。 |
| 鱸膾蓴羮 | ろかいじゅんこう | 故郷を思う気持ちが強いこと。または、ふるさとの味という意味。中国の張翰(ちょうかん)という人が、故郷の蓴菜(じゅんさい)の羹(あつもの)と鱸(すずき)の膾(なます)のおいしい味を思い出し、なんで恋々と虚業にしがみついていることがあろうかと、辞職して故郷に帰ったという故事から。 |
| 驢鳴犬吠 | ろめいけんばい | 驢馬が鳴き、犬が吠える。聞くに足らないこと。つまらない文章。 |
| 老驥伏櫪 | ろうきふくれき | 年取った良馬が小屋のねだ(馬屋の床下に渡す横木)に寝る。賢者が年とってなお世に用いられないこと。 |
| 老少不定 | ロウショウフジョウ ろうしょうふじょう |
老人も少年もいつ死ぬかわからないこと。死期は予知できず、人の命のはかなく寿命の定めがたいたとえ。人間の寿命は、老少には関係なく誰が先に死ぬかわからないこと。仏教で、老人も若者も人間の生命というものはいつ尽きるともわからない、はかないものであることを言う。 |
| 老成円熟 | ろうせいえんじゅく | 豊富な経験をもとに考えや態度が柔軟な様。 |
| 老成持重 | ろうせいじちょう | 老練でしかも慎重なさま。経験を積んでいて物事を慎重冷静に処理すること。 |
| 老当益壮 | ろうとうえきそう | 老年になっても、ますます盛んな意気を持って困難にも立ち向かうべきであるということ。 |
| 老若男女 | ろうにゃくなんにょ | すべての人と言うこと。 |
| 老婆親切 | ろうばしんせつ | 老婆が余計な世話をやく事から、行き過ぎた余計な親切。老婆心とも言う。 |
| 老馬之智 | ろうばのち | 道に迷った時、放した老馬に付いて行けば道に出るものだ、ということから転じて、経験を積んだ者は、その行なうべき道を心得ている。 |
| 狼子野心 | ろうしやしん | 狼を手なずけようとしても、生来の野性があだとなり、なかなか慣れない。謀反の心や凶暴な人は容易に教化しにくいことにたとえる。 |
| 廊廟之器 | ろうびょうのき | 天下の政治を行うに十分な才能。大臣・宰相となりうる才能。 |
| 廊廟之計 | ろうびょうのけい | 大臣宰相となって政務を執るはかりごと。 |
| 弄翰戯語 | ろうかんぎご | 戯れに書いたものや冗談。 |
| 聾者之歌 | ろうしゃのうた | つんぼの歌ううた。聾者は、自分で歌ってもそれを聞いて楽しむことができないところから、自分で行ないながら、それにより自分を楽しませることのできないことにたとえる。 |
| 籠鳥檻猿 | ろうちょうかんえん | 自由を束縛されて、思い通りに生きられないもののたとえ。かごの中に閉じ込められた鳥と、おりに閉じ込められた猿の意から。▽不自由な生き方を強いられるこの二者は、白居易はくきょいとその友人の元禛げんしんを比喩して言ったもの。 |
| 籠鳥恋雲 | ろうちょうれんうん | 籠の中に飼われている鳥が空に浮かぶ雲を恋い慕うこと。転じて、束縛されている者が自由を得たいと望むことをいう。 |
| 六十耳順 | ろくじゅうじじゅん | 六十歳で異なる考えも素直に聞き入れられるようになると言うこと。孔子は六十歳になったとき、学問修養も進み、自分と異なる説を聞いても、理にかなえば抵抗なく理解できるようになった。「耳順」は、素直に聞くことが出きる意で、六十歳の意にも用いる。 |
| 六十六部 | ろくじゅうろくぶ | 日本内地の六十六か国の寺に参拝して一部ずつ経を納めること。諸国行脚の僧。雲水。 |
| 六菖十菊 | ろくしょうじっきく | 手遅れのたとえ。五月五日は菖蒲、九月九日は菊の節句であるが、それに遅れていること。 |
| 六道輪廻 | ろくどうりんね | 衆生(しゅじょう)は、迷っているうちはいつまでも六道をめぐって生死を繰り返す、という考え方。 |
|
六根清浄 |
ロッコンショウジョウ ろっこんしょうじょう |
眼、耳、鼻、舌、身、意の六根からくる、すべての迷いから抜け出て清浄になること。迷いをたって心身を清らかにすること。六根とは人の迷を生じる眼鼻耳舌身意の六つ。その六根から起こる迷いを断ち切ること。 |
| 鹿死誰手 | ろくしすいしゅ | 勝敗の決まらない状態をいう。天下は、まだ誰が統一するか不明ということから。 |
| 鹿苹之歓 | ろくへいのよろこび | 太平の宴会をいう。鹿が和らぎ鳴いて野の苹(よもぎ)を食べるさまから、賢人を集めてのなごやかな酒盛りをいう。 |
| 鹿鳴之宴 | ろくめいのえん | 科挙に及第して都に行くときの送別の宴。「詩経」の小雅の鹿鳴を歌うところからいう。賓客を迎え、また、めでたいことのあるときの宴会。 |
| 論功行賞 | ロンコウコウショウ ろんこうこうしょう |
功績をあげたものに、それにふさわしく~相応した賞を与えること。 |
| ワ | ||
| 和顔愛語 | わがんあいご | なごやかな表情と親愛の情がこもった言葉づかい。親しみやすく暖かい態度のこと。解 説: 「和顔」は、和やかな顔。「愛語」は、親愛の気持ちがこもった言葉。 |
| 和気藹々 | わきあいあい | なごやかで、楽しい気分が満ちあふれ、仲良く、穏やかにうち解けて談笑するさま。「和気」は穏やかな気分。「藹々」は満ち満ちる、また、「藹」は朝夕、田園に立ちこめるもやのこと。 |
| 和敬清寂 | わけいせいじゃく | 茶道の精神を表現するのに用いられた語。和敬は茶事における主客相互の心得、清寂は茶庭・茶室・茶道具などに関連する心得。 |
| 和羹塩梅 | わこうえんばい | いろいろの味を調和して羹を作ること。君主を助けて国の政治をとる大臣のこと。 |
| 和光同塵 | わこうどうじん | 知恵の光を和らげ、かつかくして俗世間に交わっているという意。 |
| 和魂漢才 | ワコンカンサイ わこんかんさい |
日本固有の精神を心に持ちながら、しかも、中国伝来の学問の才を有すること。日本固有の精神をもって、中国の学問を活用すること。 |
| 和魂洋才 | わこんようさい | 日本固有の精神を保ちつつ、もう一方で西洋の学問・知識を学び取ること。 |
| 和而不同 | わじふどう | 「和して同せず」とも読む。人と和らぎ親しんでも、正義をまげてまで、みだりに人に従うことはしない。 |
| 和醸良酒 | わじょうりょうしゅ | 蔵人達の「和」が良い酒を醸し出すと言うこと。 |
| 和衷共済 | わちゅうきょうさい | 心を合わせ助け合う。一致協力して仕事をすること。 |
| 和衷共同 | わちゅうきょうどう | 心を通わせ共に力を合わせて物事に対処すること。 |
| 和風細雨 | わふうさいう | 穏やかに吹く風と、静かにそぼ降る雨。人の過ちや欠点を改めるのに柔和な態度、方法でのぞむことのたとえ。 |
| 和洋折衷 | わようせっちゅう | 日本と西洋の二つの風俗、様式を適当に取り合わせること。 |
| 吾家顔子 | わがいえのがんし | 我が家で顔回のように優れた子。 |
| 吾家麒麟 | わがいえのきりん | 父母がその子の優れたさまをいう言葉。 |
| 吾家竜文 | わがいえのりゅうもん | 我が家で竜文のように優れた子。竜文は優れた馬の名。 |
| 吾党之士 | わがとうのし | わが仲間の者。 |
| 吾門標秀 | わがもんのひょうしゅう | 我が家の傑出した子。 |
| 吾唯知足 | われただたるをしる | 私はただ自分が満たされていることを知っている」という意味。いわゆる「知足」の精神。吾唯足知とも。 |
| 矮子看戯 | わいしかんぎ | 物事を判断する見識がない。自分の意見を持たず付和雷同すること。 |
| 矮人看戯 | わいじんかんぎ | 物事を判断する見識がないことのたとえ。背の低い人が芝居を見るとき、人にさえぎられてよく見えず、前の人の批評にわけもなく従うことからいう。 |
| 矮人観場 | わいじんかんじょう | 物事を判断する見識がないことのたとえ。背の低い人が芝居を見るとき、人にさえぎられてよく見えず、前の人の批評にわけもなく従うことからいう。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)