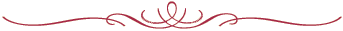
| 四文字熟語集6(ハ行) |
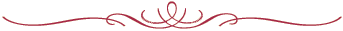
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、四文字熟語熟語言葉のハ行を確認しておく。 2008.8.31日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| ハ | |||
| 歯亡舌存 | はほろびてしたそんす | 硬い歯が抜けても軟らかい舌は残る。強い(硬い)ものより、弱い(柔らかい)ものが長持ちする喩(たとえ)。 『説苑(ぜいえん)』(漢の劉向(りゅうきょう)の書)に春秋時代の話として、叔向(しゅくきょう)という人物が、「臣は年八十なり、歯墮(お)ちて舌尚(なお)存す、老たん言えるあり、天下の至柔(しじゅう)は天下の至堅(しけん)を馳騁(ちてい)せしむと」(私は八十歳になりました。歯は落ちたが舌はまだ残っています。老子は”天下の最も柔らかいものは天下の最も堅いものを使役する”と言っています)と述べている。「墮」(おちる)は「亡」(なくなる)と同じ意味。 『老子(ろうし)』を見てみると「柔弱は剛強に勝つ」とあり、この話を裏付ける。「柳に雪折れなし」という日本の諺(ことわざ)もある。一見弱そうなものが却(かえ)って強い。 |
|
| 破顔一笑 | はがんいっしょう | 顔をほころばせ、嬉しそうに笑うこと。「一笑」は、軽く笑うこと。事態の好転に機嫌を良くしたような場合に用いる。「破顔」は、表情をほころばせるさま。 | |
| 破鏡重円 | はきょうじゅうえん | 戦乱などで生き別れになった夫婦が、無事に再会すること。中国の南北朝時代、陳が隋の文帝に滅ぼされたとき、侍従の除徳言は一枚の鏡を真っ二つに割って一方を妻に渡し、再会の時の証とした。のちにそれが縁となって再会し、故郷へ帰ることができたという故事による。ここから、夫婦の離婚を「破鏡」というようになった。 | |
| 破鏡不照 | はきょうふしょう | 夫婦が離婚すること。ひとたび別れた夫婦はもうもとのさやにおさまらない例え。「破鏡は照らさず」と読む。 | |
| 破邪顕正 | ハジャケンショウ | 不正を打破し、正義を実現すること。誤った考えを否定し、正道を明らかにすること。 | |
| 破竹之勢 | はちくのいきおい | 竹の勢いをも超えるような、勢いの盛んなこと。 | |
| 破天荒解 | はてんこうかい | 今までだれもなしえなかったことをはじめて成し遂げること。「天荒」は、天と地がまだ分かれていない、混沌とした状態のこと。 | |
| 波及効果 | はきゅうこうか | 次第に影響が及び効き目が出ること。 | |
| 波状攻撃 | はじょうこうげき | 次から次へとひっきりなしに攻撃を続けること。 | |
| 破釜沈船 | はふちんせん | 出陣に際し、食事をつくる釜を壊し、軍船を沈め、決死の覚悟で戦うこと。 | |
| 波瀾(乱)万丈 | はらんばんじょう | 波が非常に高いように物事の変化が起伏に富んではげしいことのたとえ。事件や人の一生など、物事の変化、浮き沈みのはげしいこと。「―の人生」 。 | |
| 覇王之資 | はおうのし | 覇者や王者になる資格。 | |
| 霸王之輔 | はおうのほ | 霸者や王者の補佐役。 | |
| 爬羅剔抉 | はらてっけつ | 隠れたものをかき集めえぐり出す。人の秘密・欠点などをあばき出す。隠れた人材を、広く捜し出して用いる。 | |
| 巴陵勝状 | はりょうのしょうじょう | 巴陵地方のよいけしき。巴陵は湖南省岳陽県の地方。 | |
| 馬耳東風 | バジトウフウ | 人に何を言われても少しも気にとめないこと。人の言うことや意見に聞く耳を持たず、心にとめず少しも反応がないたとえ。 李白の詩の「東風の馬耳を射るがごとき有り」という詩句による。東風、つまり春風がそよそよと馬の耳に吹き込んでも、馬は無関心であることから。 |
|
| 馬牛襟裾 | ばぎゅうきんきょ | 学のない人や、礼儀知らずの人をののしる言葉。 | |
| 罵詈雑言 | ばりぞうごん | 口汚くののしること。 | |
| 罵詈讒謗 | ばりざんぼう | 悪口の限りを言い、手ひどくののしること。また、その言葉。 | |
| 杯酒解怨 | はいしゅかいえん | 酒席で杯のやりとりをする間に、昔の恨みを忘れること。 | |
| 杯水車薪 | はいすいしゃしん | 杯(さかずき)わずか一杯の水で、車一台分もあろうという薪の燃えるのを消すには、余りにも微力で、全く役に立たぬ。 事を処理するには役立たぬ。またもどかし過ぎること。 | |
| 杯中蛇影 | はいちゅうのだえい | 神経質で、自分から疑い惑う心が生じて苦しむこと。河南の長官楽広の親しい友人が、役所の壁に掛けた弓が杯の酒に蛇に映って見えてから病んだが、楽広から訳を聞いてけろりと治った故事。 | |
| 杯盤狼藉 | はいばんろうぜき | 酒席の混乱の状態や酒宴の後、杯や皿が散乱しているさまをいう。 | |
| 背水之陣 | ハイスイノジン | 水辺を背にして陣をしけば、退却できないことから、決死の覚悟で戦に臨む。また、決死の覚悟で事に当たること。 | |
| 背井離郷 | はいせいりきょう | 「井に背(そむ)き郷を離れる」。井戸のほとりに人が集まり住んでいる故郷を捨てて、他郷に移りゆくこと。 | |
| 廃格沮誹 | はいかくそひ | 行われないように邪魔をしてそしる。 | |
| 廃藩置県 | はいはんちけん | 明治四年(1871)七月、藩を廃し全国を郡県に改めた行政上の大改革。 | |
| 廃仏毀釈 | はいぶつきしゃく | 仏法を排斥し釈迦の教えを捨てること。 | |
| 稗官野史 | はいかんやし | 小説のこと。 | |
| 吠日之怪 | はいじつのかい | 蜀の地(四川省)は雨が多く太陽を見ることが少ないので、犬が太陽を見ると、怪しんで吠える。珍しいものを見て驚くこと。 | |
| 妃匹之愛 | はいひつのあい | 夫婦の愛。 | |
| 敗柳残花 | はいりゅうざんか |
|
|
| 売名行為 | ばいめいこうい | 利益や人気のために名前を売ること。 | |
| 伯夷之清 | はくいのせい | 伯夷・叔斉のふたりが清廉潔白であったこと。 | |
| 伯夷之廉 | はくいのれん | 伯夷・叔斉のふたりが清廉潔白であったこと。 | |
| 伯牙断弦 | はくがだんげん | 知己の死を悲しむこと。伯牙の琴を愛していた鍾子期が死ぬと、伯牙は琴の糸筋を切って、再び弾かなかった故事。 | |
| 博引旁証 | ハクインボウショウ | 物事を決したり論じたりするとき、多くの材料を引きだし、証拠や関連の事物をあまねく示すこと。 | |
| 博学多才 | ハクガクタサイ | 広くいろいろな学問に通じ才能が豊かなこと。広くいろいろな学問に通じていて、多方面にわたって才知、才能が豊かなこと。 | |
| 博文約礼 | はくぶんやくれい | 広く学問を学び物事の道理を探究し、これを締めくくるのに礼をもってすれば、道にそむくことがないという教え。 | |
| 博覧強記 | ハクランキョウキ | 広く書物を読み、それらを非常によく記憶していること。知識が豊富なこと。広く書物を読み、物事を良く覚え、知識が豊かなこと。生き字引。 | |
| 博聞強識 | はくぶんきょうしき | 見聞が広く博識なさま。 | |
| 白華之怨 | はくかのうらみ | 愛を失った女性の嘆き。 | |
| 白魚入舟 | はくぎょにゅうしゅう | 周の武王が殷の紂(ちゅう)王を討ったとき、黄河の水の中から白い魚が躍って舟の中に飛び込んだ故事から、 敵が降参する前兆をいう。白は殷の正色、魚は兵を象徴している。 | |
| 白黒之弁 | はっこくのべん | 善か悪かのわきまえ。正邪の区別。 | |
| 白日昇天 | はくじつしょうてん | 真昼に天に昇ることで、仙人になることをいう。また、急に金持ちになること。 | |
| 白紙撤回 | はくしてっかい | 進行中の事案などをゼロに戻すこと。 | |
| 白首空帰 | はくしゅくうき | 年をとって頭が白くなっても学問が成就しないこと。 | |
| 白砂青松 | ハクシャセイショウ はくさせいしょう |
白い砂浜と青い松が続く、海辺の美しい景色のこと。日本に多い景勝を形容する語。長く続いた白い砂浜に青い松が生えている美しい景色。 | |
| 白首北面 | はくしゅほくめん | 才能の無い者は歳をとっても人の教えを受けるものだ。 | |
| 白水真人 | はくすいしんじん | 銭の別名。白水を足すと泉、真人を足すと貨。 | |
| 白頭如新 | はくとうじょしん | 互いに白髪となるまで交際していても、その心を知り合わなければ新しい知己と同じである。転じて、盟友がお互いの心を知らなかったことをあやまることば。 | |
| 白蘋紅蓼 | はくひんこうりょう | 白い花の咲くうきくさと、紅い花の咲くたで。 | |
| 白璧微瑕 | はくへきのびか | 白い玉にある少しの傷。ほとんど完全で、わずかの欠点があること。 | |
| 白面書生 | はくめんしょせい | 年少で経験に乏しい書生。青二才。 | |
| 白竜魚服 | はくりょうぎょふく | 白竜が魚に化けて予且という猟師に捕らえられたことから、転じて、貴人の忍び歩きのたとえ。貴人の微行。お忍びの外出。 | |
| 白竜魚腹 | はくりゅうぎょふく | 神聖で霊力をもつ竜が魚に姿を変えたため、猟師に捕まえられたことから、身分の尊い人がお忍び出歩いて危ない目に遭うことをいう。 | |
| 拍手喝采 | ハクシュカッサイ | 手をたたいて、さかんに褒めたたえること。拍手してほめそやすこと。「喝采」は、かけ声をかけてさいころを振る意から、やんやとほめそやすこと。また、ほめる時の動作にも使う。 | |
| 伯仲之間 | はくちゅうのあいだ | 優劣がないこと。似たり寄ったり。 | |
| 伯楽一顧 | はくらくのいっこ | 高位にある人に認められて重用されること。 | |
| 薄利多売 | はくりたばい | 利益を少なくして数多く売ること。 | |
| 薄志弱行 | はくしじゃっこう | 意志が弱く行動力に乏しいこと。物事を断行する力に欠けること。 | |
| 璞玉渾金 | はくぎょくこんきん | 磨かない玉とあらがね。人の性質の純美で、飾り気のないさまのたとえ。 | |
| 如履薄氷 | はくひょうをふむがごとし | 薄く張った水の上の氷を踏み歩くようなもの。慎重細心の注意をもって事を行うが、きわめて危険なことのたとえ。 | |
| 麦秀之歌 | ばくしゅうのうた | 殷の忠臣箕子が殷の古都を過ぎて作ったと伝えられる詩。転じて、故国の滅亡を嘆くこと。 | |
| 麦穂両岐 | ばくすいりょうき | 麦の穂がふたまたになって実ること。豊作の前兆とされる。 | |
| 麦隴菜畝 | ばくろうさいほ | 麦畑と野菜畑。 | |
| 幕天席地 | ばくてんせきち | 士気が壮大な形容。また、小さいことにこだわらないさま。 | |
| 莫逆之友 | ばくぎゃくのとも | 互いに逆らわない友。互いによく気が合い、心の通じ合う友人。 | |
| 八索九丘 | はっさくきゅうきゅう | 古書。 | |
| 八方美人 | はっぽうびじん | 誰にも悪く思われないように要領よくふるまうこと。また、そのような人。誰とでも要領よくつきあうこと。また、そういう人。「八方」は、東・西・南・北と、北東・北西・南東・南西の八つの方角のこと。どの方角から見ても難点のない美人のこと。転じて、誰からもよく思われるように、如才なく振る舞うこと。 | |
| 八元八愷 | はちげんはちがい | 善良な十六人の才子。 | |
| 八紘一宇 | ハッコウイチウ | 全世界を一つの家のように統一すること。宇は家のこと。 | |
| 八宗兼学 | はっしゅうけんがく | 八つの宗派の学問を全部学んでいること。そのことから、広く学問に通じてくわしいことの形容に使う。 | |
| 八方画策 | はっぽうかくさく | あらゆる方面に働きかけて、計画の実現をはかること。 | |
| 八面玲瓏 | はちめんれいろう | どの方面から見ても、美しく欠点がない。「八面」はすべての方面。「玲瓏」は玉などの美しく輝くようす。また、玉などが美しい音でなるさま。心中に何のわだかまりも持たず、円満で巧妙な行う意にも用いる。 | |
| 八面六臂 | はちめんろっぴ | 一人で多方面にわたって何人分もの活躍をすること。もとは、仏像の作り方などを言う。 | |
| 発蹤指示 | はっしょうしじ | 犬の縄を解き放って獲物にけしかける。戦いを指揮する人のたとえ。 | |
| 発憤忘食 | はっぷんぼうしょく | 食事を忘れるほど夢中で励むこと。学問や人生上の難問題にぶつかって、それを解明しようと精神を奮い起こしたときには、寝食を忘れてしまうほどであるということ。「憤りを発して食を忘る」とも読む。 | |
| 撥乱反正 | はつらんはんせい | 世の乱れを治め、もとの平和の世に返すこと。 | |
| 抜苦与楽 | ばっくよらく | 仏教で、衆生の苦しみを取り除いて安楽を与えること。仏の慈悲のはたらきをいう語。 | |
| 抜山蓋世 | ばつざんがいせい 山を抜き世を蓋(おお)う |
勢いが非常に強く、自信に満ち気力の雄大なさま。勇壮な気質のたとえ。 | |
| 抜本塞源 | ばっぽんそくげん | 一番のもととなる原因を抜き去ること。害を防ぐため、根本にさかのぼって物事を処理すること。 | |
| 跋山渉水 | ばっさんしょうすい | 「山を抜(ふ)み、水を渉(わた)る」。困難な道を克服して長い旅を続けること。 | |
| 鼻持ちならない | |||
| 鼻元思案 | はなもとじあん | 目先だけの浅はかな考え。場当たり的な思いつき。 | |
| 半官半民 | はんかんはんみん | 政府と民間とが共同で出資し、事業を経営すること。 | |
| 半死半生 | ハンシハンショウ | 死にかかっているようなとてもあぶない状態。今にも死にそうな状態。動植物や人について用いる。生死の境をさまよう意にも。「半生」は、「はんせい」、「はんじょう」とも読む。 | |
| 半信半疑 | はんしんはんぎ | 本当かどうか信じ切れないようす。真偽の判断に迷うこと。本当と思っていいかどうか迷うこと。半(なか)ば信じ、半(なか)ば疑うこと。 | |
| 半生半熟 | はんせいはんじゅく | 半分なまで、半分煮えていること。技芸のまだ熟達していない状態。未熟。 | |
| 半醒半睡 | はんせいはんすい | 半ば目覚め、半ば眠っていること。目覚めているのかどうか定かではない朦朧とした状態。 | |
| 半面之識 | はんめんのしき | ちょっと顔を知っているの意味。少し知り合っていること。 | |
| 反哺之孝 | はんぽのこう | 烏の子は母鳥に育てられた恩返しに、成長してから食物を口移しにして親鳥を養うの意味。成長して、親の恩に報いて孝養を尽くすことのたとえ。 | |
| 反哺之心 | はんぽのこころ | 「反哺之心」とは、「親に恩返しをすること」を表す四字熟語です。漢字からはあまり想像できない意味ですが、これは鳥に深く関係する四字熟語です。 | |
| 反間苦肉 | はんかんくにく | 自分の身を苦しめたり、自分にとって不利益に見えることをしたりして相手をあざむき、敵同士の仲を裂く計略を行うこと。 | |
| 反面教師 | はんめんきょうし | いましめとなる悪い手本。 | |
| 犯分乱理 | はんぶんらんり | 礼儀をおかし乱す。分限を犯して条理を乱すこと。 | |
| 飯店宿房 | はんてんしゅくぼう | 料理屋や旅館。 | |
| 阪路詰曲 | はんろきっきょく | 坂道が曲がりくねっていること。 | |
| 帆腹飽満 | はんぷくほうまん | 帆にいっぱい風を受ける様子。 | |
| 汎濫停畜 | はんらんていちく | 学問が広く深い。汎濫は大水のあふれるように広く、停畜は水がいっぱいたたえられているように深いの意味。 | |
| 繁文縟礼 | はんぶんじょくれい | 規律や礼法などがこまごまとしていて、わずらわしいこと。「繁文」は、規則が多く面倒なこと。「縟礼」は、わずらわしい礼儀や作法。 | |
| 翻雲覆雨 | はんうんふくう | 交友の情の変わりやすいさま。手のひらを仰向けると雲が涌き、手のひらをうつむけると雨が降るの意味で、少しのことですぐに心が変わってしまう、軽々しい友達付き合い。 | |
| 攀竜附驥 | はんりょうふき | 竜につかまり良馬に付き従う。優れた人に従うこと。 | |
| 攀竜附鳳 | はんりょうふほう | 竜につかまり鳳凰に付き従う。優れた人に従うこと。 | |
| 坂東太郎 | ばんどうたろう | 利根川の別名。 | |
| 伴食宰相 | ばんしょくさいしょう | 無能の大臣を言う言葉。伴食は正客のお相伴にあずかること。 | |
| 万古千秋 | ばんこせんしゅう | 永久、永遠の意。いつの世までも。 | |
| 万古不易 | ばんこふえき | 何年たっても変わらないこと。 | |
| 万死一生 | ばんしいっしょう | 助かる見込みのない命が助かること。九死一生よりも少ない確率で命を取り留めること。死を万とすると生はわずか一しかない。それほどきわめて危険な状態からかろうじて助かること。 | |
| 万事如意 | ばんじにょい | 全て思い通りになること。 | |
| 万寿無疆 | ばんじゅむきょう | 「万寿疆無し」とも読む。人の長寿を祝う言葉。 | |
| 万乗之君 | ばんじょうのきみ | 天子のこと。大諸侯のこと。 | |
| 万水千山 | ばんすいせんざん | 数多くの川や山々。はるか遠くへ旅をするときのたとえ。 「紅軍遠征の難(かた)きを怕(おそ)れず、万水千山只(た)だ等間」と、毛沢東の赤軍の遠征を歌った七言律詩の一句。 | |
| 万世一系 | ばんせいいっけい | 天子の血統が永久に続いて、その位にあること。 | |
| 万世不易 | ばんせいふえき | 永久に変わらない。 | |
| 万代不易 | ばんだいふえき | 永久に変わらない様子。万代=永久、万世。 | |
| 万物逆旅 | ばんぶつのげきりょ | 天地のこと。万物の生滅するさまが、旅人の旅館に去来するのに似ているから言う。逆旅は宿屋。 | |
| 万物之霊 | ばんぶつのれい | 万物の中で最も優れた心の働きを持つもの。人間。 | |
| 万物流転 | ばんぶつるてん | すべてのものはとどまることなく、移り変わるということ。 | |
| 万夫之望 | ばんぷののぞみ | 天下の万民が仰ぎ慕うこと。 | |
| 万夫不当 | ばんぷふとう | 多くの人があたってもかなわないほど、強くて勇ましいこと。 | |
| 万里同風 | ばんりどうふう | 広い地域に同じ風俗、文化が行き渡ること。→天下泰平なこと。 | |
| 万里比隣 | ばんりひりん | 万里の遠い地も、志の持ちようでは隣のように近く思われる。 | |
| 万緑一紅 | ばんりょくいっこう | 多くの物の中で際立って優れた物。男の中で女が一人。 | |
| 蛮触之争 | ばんしょくのあらそい | 小さなつまらないことで争うこと。魏の恵王が斉の威王に背かれて兵をおこそうとしたとき、戴晋人という者が「カタツムリの左の角に触氏が、右の角に蛮氏が国を構え、互いに領土を争って戦ったことがございます。宇宙の広大さに比べれば王とカタツムリの角の上の蛮氏との間に相違がありましょうか」と人事のいかに卑小であるかを説いた寓話による。 | |
| 盤根錯節 | ばんこんさくせつ | 地中に広く張り巡らされた根と入り組んだ節と。転じて、処理に困難な事柄。 | |
| 飜雲覆雨 | ばんうんふくう | 手を飜(ひるが)えせば雲となり、手を覆せば雨となるように、人情も移ろい変り易いこと。 また信念に乏しく、きわめて軽薄な場合にも用いる。 | |
| ヒ | ||
| 日下開山 | ひのしたかいさん | 武芸・相撲などで、天下無敵の者の意味に用いる。 |
| 非常手段 | ひじょうしゅだん | 非常の場合に行なう臨機の処置。暴力をもってことを処置すること。 |
| 非常之行 | ひじょうのおこない | 常人と違った、りっぱな行い。 |
| 非常之功 | ひじょうのこう | 普通の人と違った、華々しい手柄。 |
| 非常之人 | ひじょうのひと | 普通の人よりすぐれた人。非凡。 |
| 被堅執鋭 | ひけんしゅうえい | 堅いよろいかぶとを身につけて、鋭利な武器を手に持つ。 |
| 被害妄想 | ひがいもうそう | 他人から危害を加えられていると思い込むこと。 |
| 彼此安康 | ひしあんこう | あの国もこの国も安らかに治まる。 |
| 被髪纓冠 | ひはつえいかん | 髪を振り乱したまま冠のひもを結ぶこと。きわめて急ぐさま。 |
| 被髪左衽 | ひはつさじん | 髪を振り乱し、着物を左前に着ること。野蛮な風俗。 |
| 悲歌慷慨 | ひかこうがい | 悲しんで歌い世の中をいきどおり嘆くこと。世の中の不正や不運を憤り嘆くこと。 |
| 悲喜交々 | ひきこもごも | 悲しいことと喜ばしいことが入り交じること。また、悲しみと喜びをかわるがわる味わうこと。 |
| 飛花落葉 | ひからくよう | 花が散り、秋には葉が色づいて落ちること。絶えず移り変わる世の中のはかないことのたとえ。 |
| 飛耳長目 | ヒジチョウモク ひじちょうもく |
坂本竜馬を髣髴とさせる。遠くの情報を集め、長い目で見る。遠くの音を早く聞き取る耳と、遠くのものをよく見通す目。情報収集や観察に優れ、ものごとに精通していることのたとえ。(書物を指すことも。) |
| 飛竜乗雲 | ひりょうじょううん | 「飛竜雲に乗る」とも読む。竜が雲に乗って天に上るということで、英雄が時に乗じて勢いを得ること。 |
| 皮相浅薄 | ヒソウセンパク | 表面的で底が浅いこと。知識、思慮、学問などが非常に浅いこと。 |
| 皮裏陽秋 | ひりようしゅう | 表面に出ない心中での理非曲直の判断。 |
| 匪躬之節 | ひきゅうのせつ | 自分の利害を考えないで、王事に尽くす忠節。 |
| 非難囂囂 | ひなんごうごう | 騒がしくうるさく非難すること。 |
| 非礼之礼 | ひれいのれい | 礼にかなわない礼儀。 |
| 悲喜交交 | ひきこもごも | 悲しいことと喜ばしいことが入り交じること。また、悲しみと喜びをかわるがわる味わうこと。 |
| 悲憤慷慨 | ひふんこうがい | 悲しんで歌い世の中をいきどおり嘆くこと。世の中の不正や不運を憤り嘆くこと。社会的な不義や不正などについての怒りで、自己中心的悲しみや憤りについては使わない。 |
| 誹謗中傷 | ひぼうちゅうしょう | |
| 比肩随踵 | ひけんずいしょう | 肩と肩、踵と踵が接する。→後から後へと絶え間なく続くこと。 |
| 比翼連理 | ひよくれんり | 夫婦の深い契り。男女の愛が深いたとえ。夫婦仲のむつまじさ。 |
| 疲労困憊 | ひろうこんぱい | ひどく疲れ果てること。「困」は苦しい、「憊」は「憊色」の意で、疲れ果てた顔色を言う。 |
| 罷買同盟 | ひばいどうめい | 人々が団結して、物を買うことを拒否すること。ボイコット。 |
| 髀肉之嘆 | ひにくのたん | 実力を発揮するチャンスのないのを嘆くこと。 |
| 美辞麗句 | ビジレイク | 美しく飾った、聞いて心地よい言葉。最近では内容のない空疎な言葉の羅列を、多少皮肉まじりに軽蔑していう場合が多い。美しく飾った文句。うわべだけ美しく飾り立てた、真実みのない空虚な言葉。 |
| 美酒佳肴 | びしゅかこう | 大変美味しいご馳走のこと。 |
| 美人薄命 | ビジンハクメイ | 容姿が美しく生まれついた人はとかく不運であったり、短命であったりすること。美しい人は、その美しさゆえにかえって不幸せになることが多いこと。 |
| 眉目秀麗 | ビモクシュウレイ | 容貌がとても美しいこと。「眉目」は、眉と目、顔かたちのこと。とくに男性の容貌についていう。 |
| 媚眼秋波 | びがんしゅうは | 美人のなまめかしい媚びる目つきのこと。 |
| 微雨新晴 | びうしんせい | 『微雨、新たに晴る』。早々の晴々とした景観を言う。 冬去り春来る、降るとなくみえる微かな雨もやみ、天地に晴朗の気が満ち満ちている。 |
| 尾生之信 | びせいのしん | 約束を堅く守って、変わらないこと。春秋時代に、魯の尾生がある婦人と橋の下で会う約束をし、時刻が過ぎても女は来ず、大雨で増水したが去らず、ついに柱を抱いて死んだ故事。 |
| 彌望皎然 | びぼうこうぜん | 見渡す限り真っ白なこと。 |
| 左鮃右鰈 | ひだりひらめみぎかれい | 両目が体のどちら側についているかで「ヒラメ」と「カレイ」を見分けるということ。日本のことわざであることが、中華大字典にもふれられているが、必ずしもこのことわざのとおりとは限らないので、注意が必要。 |
| 筆耕硯田 | ひっこうけんでん | 文筆で生活すること。 |
| 筆端風雨 | ひったんふうう | 詩文などを作る筆の運びが、風雨が速やかに走り去るように早いこと。 |
| 筆誅墨伐 | ひっちゅうぼくばつ | 他人の罪悪を新聞・雑誌などに書き立てて責めること。 |
| 匹夫之勇 | ひっぷのゆう | 向こう見ずの勇気。 |
| 匹夫匹婦 | ひっぷひっぷ | 一人の男と一人の女。平凡な男女。また、夫婦暮らしの身分の低いもの。 |
| 一声千両 | ひとこえせんりょう | 一声に千両の値打ちがあること。 |
| 一人芝居 | ひとりしばい | 一人で数人の役を演じ分けて芝居を見せるもの。相手がないのに、自分の思い込みだけでいろいろな言動をとること。 |
| 一人相撲 | ひとりずもう | 一人で勝手に相撲を取る滑稽さのこと |
| 一人天下 | ひとりでんか | 天下を取ったように、自分だけで、思うようにすること。ひとりてんか。 |
| 人之安宅 | ひとのあんたく | 仁徳。仁徳のある人には危害を加える人がいないから、仁徳は人が安心していられる所だという意味。 |
| 人身御供 | ひとみごくう | いけにえとして神に供える、人の体。相手の欲望を満たすために犠牲になる人。 |
| 百花斉放 | ヒャッカセイホウ | 多くの花が一斉に開くこと。さまざまなものがその本領を発揮すること。さまざまな学問・芸術が同時に盛んになること。 |
| 百家争鳴 | ヒャッカソウメイ | いろいろな立場の学者が、自由に論争するさま。いろいろな議論が、にぎやかに自由になされる形容。様々な立場の人の活発な論争のこと。「百家」は、数多くの学者や専門家のこと。 |
| 百花繚乱 | ヒャッカリョウラン | 種々の花が咲きみだれるように、優れた人物や業績が一時にたくさん現れること。優れた人物や業績などが時を同じくして数多くあらわれること。数多くの花が一度に咲き乱れる華やかなさまから転じて。 |
| 百鬼夜行 | ヒャッキヤコウ | いろいろな妖怪が夜に列をなして歩き回ること。多くの化け物が夜中に列を作って歩くこと。多くの人がみにくい行いをすること。 |
| 百挙百全 | ひゃっきょひゃくぜん | 行う物事がすべてうまくいくこと。 |
| 百計経営 | ひゃっけいけいえい | いろいろと思案して、工夫や手段を尽くすこと。 |
| 百工五種 | ひゃっこうごしゅ | もろもろの職工と五穀の種子。 |
| 百尺竿頭 | ヒャクシャクカントウ ひゃくしゃくかんとう |
到達すべき最高点、向上しうる極致のたとえ。 |
| 百術千慮 | ひゃくじゅつせんりょ | いろいろな方策を考え思慮をめぐらすこと。 |
| 百姓一揆 | ひゃくしょういっき | 江戸時代、農民が領主・代官の悪政や過重な年貢に対して集団で反抗した運動。暴動・強訴(ごうそ)・越訴(おつそ)・逃散(ちようさん)・打ち毀(こわ)しなど種々の形をとった。 |
| 百世之師 | ひゃくせいのし | 百代の後までも人の師と仰がれる人。人の師範となりうる人。 |
| 百折不撓 | ひゃくせつふとう | 何度の失敗にもめげず挫けず挑戦すること。 |
| 百川帰海 | ひゃくせんきかい | あらゆる川は、すべて海に流れ込むように、方々に散逸しているものが一ヶ所に集まる。人民の心が一点に集中すること。 「百川、海に帰す」。 |
| 百戦百勝 | ひゃくせんひゃくしょう | 百度戦って百度勝つ。一度も負けることのないこと。 |
| 百戦錬磨 | ヒャクセンレンマ | 多くの経験を積んで技術や才能を向上・錬成すること。何度も戦って鍛えられること。 |
| 百度更張 | ひゃくどこうちょう | あらゆる制度や規則が改まり変わる。 |
| 百年河清 | ひゃくねんかせい | いくら待っても望みがかなえられないこと。 |
| 百八煩悩 | ひゃくはちぼんのう | 人間の迷いのもととなる欲望のすべてのこと。人間の感覚をつかさどる眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に、色・声・香・味・触・法の六塵の刺激があると、それぞれ好・悪・平の三種、あわせて十八の煩悩が生じる。これが浄・染の二種にわかれて三六種、さらに、過去・現在・未来の三つに配されて合計百八種とされる。 |
| 百発百中 | ヒャッパツヒャクチュウ | 矢や弾丸が撃つたびに必ず命中すること。予想、計画などがすべて当たり成功すること。発射すると必ず命中すること。予想がいつでも必ずあたること。楚の養由基は、弓の名人で、百発百中ではずすことがなかったという故事から。 |
| 百味飲食 | ひゃくみのおんじき | いろいろの美味な供物。 |
| 百黙一言 | ひゃくもくいちげん | 普段は黙っている人が、ここという時に言う、一言がとても本質をついているということ。 |
| 百薬之長 | ひゃくやくのちょう | あらゆる薬の中で最も優れた薬で、お酒のこと。 |
| 百も承知 | ひゃくもしょうち | 言われるまでもなく、十分わかっていること。 |
| 莫逆之友 | ばくぎゃくのとも | 気持ちがぴったり合った親密な友。「莫」は、否定を表す。ない。「逆」は、逆らうこと。 |
| 表敬訪問 | ひょうけいほうもん | 相手に敬意を表すための訪問のこと。 |
| 表裏一体 | ひょうりいったい | 一つのものの表と裏のように切り離せない関係にあること。 |
| 氷肌玉骨 | ひょうきぎょくこつ | 梅の形容。美人の形容。 |
| 氷消瓦解 | ひょうしょうがかい | 氷がとけてなくなるように、まるで跡形なく消え去ること。氷解、瓦解すること。 |
| 氷姿玉骨 | ひょうしぎょっこつ | 梅の形容。 |
| 氷炭相愛 | ひょうたんそうあい | 全く相反する二つのものが、相互に助け合うこと。氷と炭とは全然反対の性質をもつものであるが、 氷は炭火を消し、炭火は氷を融かして元の水に返してくれ、お互いにその特性を活かし助け合っている。 |
| 廟堂之器 | びょうどうのき | 朝廷で大政治家として立つことのできる才能。 |
| 廟堂之高 | びょうどうのたかき | 朝廷の尊い官職。高く尊い朝廷。 |
| 飄忽震蕩 | ひょうこつしんとう | すばやく震い動かすこと。 |
| 漂蕩奔逸 | ひょうとうほんいつ | 所を定めないでただよい、走り回る。舟がただよい、馬が駆けまわるように締りがないこと。 |
| 品行方正 | ヒンコウホウセイ | 行いや心がととのっていて正しいこと。道徳的にきちんとしていて模範的であること。 |
| 貧者一燈 | ひんじゃいっとう | 貧しい人の寄進は、たとえわずかであっても真心がこもっていれば、金持ちの多大な寄付にも勝るということ。 |
| 貧者一灯 | ひんじゃのいっとう | 貧しい人が真心から仏にささげる一灯は、金持のささげる万灯にまさるの意味。真心の尊ぶべきことのたとえ。 |
| 貧富貴賎 | ひんぷきせん | 貧しいこと(者)と富んでいること(者)。身分の高い(尊い)ことと身分の低い(卑しい)こと。また、貴人と賤民。 |
| 牝鶏晨鳴 | ひんけいしんめい | 「牝鶏晨(あした)に鳴く」とも読む。めすの鶏が鳴いてあさを告げること。婦人が勢力をふるうのは災いを作るというたとえ。 |
| 牝鶏之晨 | ひんけいのしん | 婦人が勢力をふるうのは災いを作るというたとえ |
| 牝馬之貞 | ひんばのてい | 柔順な徳によって、よく事に耐えて成功すること |
| 牝牡驪黄 | ひんぼりこう | 物事は外見にとらわれず、その本質を見抜くことが大切であるということ。めすとおす、黒色と黄色とを間違えること。「驪」は黒色の馬、くろい意。 |
| 鬢糸茶烟 | びんしさえん | 若い自分には派手に遊び暮らした者が、年老いてから枯淡な生活を楽しみながら余生を送る心境をいう。 |
| フ | ||
| 夫妻反目 | ふさいはんもく | 夫婦仲が悪いこと。夫婦が目をそらすの意味。 |
| 夫唱婦随 | ふしょうふずい | 夫が言い出し、妻がそれに従うこと。夫婦の仲がとても良く、和合していること。 |
| 婦人三従 | ふじんのさんじゅう | 婦人の従うべき三つの道。未婚の時は父に、嫁に行っては夫に、夫が死ねば子に従う。 |
| 婦人之仁 | ふじんのじん | 非常に小さな、取るに足りない情。 |
| 父子相伝 | ふしそうでん | 父から子へ子から孫へ学問などの奥義を代々伝えること。 |
| 父母之邦 | ふぼのくに | ふるさと。生まれ故郷。故国。 |
| 毋望之人 | ぶぼうのひと | 危急のとき、自分から助けを求めなくても、来て助けてくれる人。 |
| 毋望之福 | ぶぼうのふく | 望んでいなかった幸福。思いがけない幸い。もっけの幸い。 |
| 毋望之禍 | ぶぼうのわざわい | 思いがけない災い。 |
| 負薪汲水 | ふしんきゅうすい | 「薪をとり、谷川の水を汲む」山林原野で簡素で自然な生活をすること。 |
| 負薪之憂 | ふしんのうれい | 自分の病気を謙遜していう言葉。薪を負った疲れによって病むの意味。一説には病んで薪を負えなくなるの意味。 |
| 普天卒土 | ふてんそっと | 天の覆う限り、地の続く限りのすべての地。天下至る所。▽「普」は大の意。また、あまねくの意。「率土」は人の従い行く所。土地から土地へと続くこと。「率」は「循」の意。 |
| 普遍妥当 | ふへんだとう | ある範囲のすべての物に共通し、例外は考えられないこと。 |
| 富貴専横 | ||
| 富国安民 | ふこくあんみん | 国を豊かにして国民を安心させる。 |
| 富国強兵 | ふこくきょうへい | 国を富ませ軍隊を強くすること。 |
| 不易流行 | ふえきりゅうこう | 俳諧における永遠の本質は、新しさを求めて常に変化する流行の中にこそあるという考え。松尾芭蕉が提唱した俳諧理念の一つ。「不易」は永遠に変わらない、伝統や芸術の精神。「流行」は新しみを求めて時代とともに変化するもの。相反するようにみえる流行と不易も、ともに風雅に根ざす根源は実は同じであるとする考え。 |
| 不可抗力 | ふかこうりょく | 人の力ではどうすることも出来ないことがら。 |
| 不可思議 | ふかしぎ | 考えも及ばない、わけのわからないこと。計り知れないこと。不思議。 |
| 不刊之書 | ふかんのしょ | 永久に滅びることなく伝わる書物。 |
| 不学無術 | ふがくむじゅつ | 学問も無ければ策略も無い。無学無能。 |
| 不羈奔放 | ふきほんぽう | 世間のしきたりにとらわれないで自由なこと。転じて、才知があまりにも優れていて、ふつうの基準では判断しきれないこと。「不羈」は、束縛されないこと。 |
| 不急之察 | ふきゅうのさつ | さほど必要でないことを細かく調べる。 |
| 不朽之芳 | ふきゅのほう | 永久に朽ちない名誉。 |
| 俯仰之間 | ふぎょうのかん | たちまちの間。少しの間。 |
| 不協和音 | ふきょうわおん | 意見が分かれ、協調関係が乱れること。 |
| 不倶戴天(の敵) | フグタイテン | 「ともにはてんをいただかず」と読む。深い恨みや憎しみのため相手をとてもこの世に生かしておけないこと。復讐しないではいられないこと。非常に恨みを抱いていて決して許すことの出来ない敵のこと。 |
| 不虞之誉 | ふぐのほまれ | 思いがけずに得た名誉。 |
| 不繋之舟 | ふけいのふね | 繋がない舟の意味。人の世を超越した心のたとえ。さすらって、定まった居所が無い人のたとえ。 |
| 不言実行 | フゲンジッコウ | あれこれ言わずに、黙って実際に行動すること。何も言わずに成すべき事を実際にやること。理屈を言わずに行動する場合に使われる。 |
| 不言之教 | ふげんのおしえ | 言葉に表わさないで自然に教えを行う老荘の教え。 |
| 不言之化 | ふげんのか | 言葉に出さず、自然に徳によって感化する。 |
| 不言之花 | ふげんのはな | 桃や李を言う。「成蹊」の故事より。 |
| 不惜身命 | フシャクシンミョウ ふじゃくしんみょう |
仏の教えを修めるためには自分の身も命もささげて惜しまないこと。自分の身をかえりみないこと。命を懸けて修行に励むこと。 |
| 不召之臣 | ふしょうのしん | 敬意を払って迎えねばならぬ賢臣。招き寄せることのできかねる賢臣。 |
| 不将不迎 | ふしょうふげい | 過ぎたことでくよくよ悩んだり、未来のことであれこれ悩んだりしないこと。去るものを送ったり、来るものを迎えたりしないということから。出典『荘子』。 |
| 不死之薬 | ふしのくすり | 飲めば死なないという薬。 |
| 不時不食 | ふじふしょく | その季節に応じてその季節の物を食べなさいということ |
| 不承不承 | ふしょうぶしょう | いやいやながら。しぶしぶ。 |
| 不生不滅 | ふしょうふめつ | 生じもせず、滅びもせず、変化しない宇宙の本体。 |
| 不世之材 | ふせいのざい | 滅多に世に出ない優れた才のある人。 |
| 不即不離 | フソクフリ | 二つのものがつきも離れもしないこと。当たらずさわらずあいまいなようす。つきも離れもしないこと。 |
| 不知案内 | ふちあんない | 実情・様子を知らないこと。 |
| 不定愁訴 | ふていしゅうそ | 特定の病気としてまとめられない漠然としたからだの不調の訴え。頭が重い、疲れやすい、食欲がないなど。 |
| 不逞之輩 | ふていのやから | 勝手に振る舞うひとのこと。道義に従わないひと。 |
| 不撓不屈 | フトウフクツ | 「不撓」は、たわまない、「不屈」は、屈しないの意で、志が堅くどんな困難にあってもくじけないこと。 |
| 不同不二 | ふどうふじ | 同じではないが、また別のものでもない。 |
| 不得要領 | ふとくようりょう フトクヨウリョウ |
物事の要点がはっきりしないこと。あいまいでわけのわからないこと。要領を得ない様子。わけが分からない様子。 |
| 不道之道 | ふどうのみち | 普通にいう道とは異なるが、真理にかなっている道。 |
| 不平不満 | ふへいふまん | ある物事や状態に対して、心持ちが穏やかでなく満ち足りないさま。 |
| 不偏不党 | ふへんふとう フヘンフトウ |
どちらにもかたよらず公平中立の立場に立つこと。一党一派に組みしないこと。 |
| 不眠不休 | ふみんふきゅう | 一生懸命に努力すること。眠らず休まず頑張ってすること。 |
| 不要不急 | ふようふきゅう | 必要でなく、また急ぎでもないこと。 |
| 不立文字 | ふりゅうもんじ | 文字を用いずに教えを授けること。悟りは言葉で書けるものではないから、言葉や文字にとらわれてはいけない、言葉によらず心で悟るべきだという禅宗の考え方。 |
| 不老長寿 | ふろうちょうじゅ | 老いることなく長生きすること。高年齢まで長生きしても肉体的に衰えることなく、老人にならないこと。 |
| 不老不死 | ふろうふし | 年をとらず、しかも死なないこと。年を重ねても老人にならず、いつまでも生き続けて死なないこと。 |
| 付贅懸疣 | ふぜいけんゆう | 体についたこぶと、ぶら下がるいぼ。無用の物のたとえ。 |
| 付和随行 | ふわずいこう | 自分の見識がなく他の説に賛成して行動すること。 |
| 付和雷同 | ふわらいどう | 自分の主義主張を持たず、人の言動につられて行動すること。深く考えず、他人の意見に簡単に同調すること。「不和」は、他人の言葉にすぐにあいずちをうつこと。「附和」とも書く。「雷同」は、雷が鳴り響くと、ものがそれに応じて反響するように、わけもなく軽率に同調するの意。 |
| 布衣之極 | ふいのきょく | 平民として最高の出世。 |
| 布衣之友 | ふいのとも | 庶民的な付き合いをしている友。身分や地位に関係なく付き合っている友。 |
| 布衣之交 | ふいのまじわり | 身分の低いもの同士の交際。また、お互いの身分地位を考慮に入れない心からのつきあい。 |
| 布置按排 | ふちあんばい | 物を適当なところに配り並べる。物事を適当に処置する。 |
| 芙蓉覆水 | ふようふくすい | 「芙蓉水を覆い、秋蘭は涯(きし)を被(おお)う」芙蓉は蓮の花。夏、蓮の花が水面を覆うように群がり咲く。 四季それぞれの花の咲き乱れるさまをいう。 |
| 巫山雲雨 | ふざんうんう | 昔、楚の襄王が夢に神女と契った山で、神女は去るときに、自分は朝には雲となり、夕暮れには雨となると言ったことに由来し、転じて男女の情交を謂う。 |
| 巫山之夢 | ふざんのゆめ | 男女の情交をいう。 |
| 浮石沈木 | ふせきちんぼく | 「石が流れて木の葉が沈む」という諺がある通り、物事がさかさまで、善悪が転倒していること。 |
| 譜代相伝 | ふだいそうでん | 代代受け継いでその家に伝えること。代代、家系を継ぐこと。 |
| 浮雲朝露 | ふうんちょうろ | 空に浮かび漂う雲と朝の露。はかなく頼りないもののたとえ。また、あてにできないもののたとえ。 |
| 浮雲之志 | ふうんのこころざし | 空に浮かびただよう雲のような、富貴にとらわれぬ気持。 |
| 斧鉞之誅 | ふえつのちゅう | 極刑に処せられること。重刑。 |
| 釜魚甑塵 | ふぎょそうじん | 貧しいため、飯を炊かないので、甑に塵がたまり、釜に魚を生じたという故事から、非常に貧乏で飯も満足に炊くことのできないたとえ。 |
| 釜中之魚 | ふちゅうのうお | 釜の中の魚はやがて煮られるという意から、死の危険がせまっていることのたとえ。 |
| 釜底遊魚 | ふていゆうぎょ | 前途に全く望みなく絶望的な状況のこと。釜の底に残った僅かの水で泳いでいる魚。煮られる前に死ぬ運命にある。 |
| 腐腸之薬 | ふちょうのやく | うまい食い物や酒。 |
| 俛首帖耳 | ふしゅちょうじ | 首をたれ耳をたれて媚びへつらい、憐れみを乞う。 |
| 無事安穏 | ぶじあんのん | 何事もなくすべてが安らかで穏やかなこと。 |
| 無事息災 | ぶじそくさい | 事故や病気などの心配事がなく、平穏に暮らしていること。 |
| 無礼千万 | ぶれいせんばん | 失礼きわまりないこと。 |
| 武運長久 | ブウンチョウキュウ | 戦いにおける良い運が久しく続くこと。戦士としての命運が長く続くこと。「武運」は、戦いの勝敗の運命。「長久」は、長く久しいこと、長く続くこと。「武運長久を祈る」と使う。 |
| 武士の情け | ぶしのなさけ | |
| 武陵桃源 | ぶりょうとうげん | 俗世間から離れたところにある平和でのどかな別世界。 |
| 舞文曲筆 | ぶぶんきょくひつ | 文辞をもてあそび、事実を曲げて書くこと。 |
| 風雨淒淒 | ふううせいせい | 風や雨で、物寂しいこと。 |
| 風雨対状 | ふううたいしょう | 夜、雨の音を聞きながら、兄と弟がベッドを並べて寝る、仲の良い兄弟の思いやりの心情をいう。 |
| 風雲月露 | ふううんげつろ | 世間の人の修養には何の役にも立たない花鳥風月ばかり詠じた詩文。 |
| 風紀紊乱 | ふうきびんらん | 風俗や男女の仲がだらしなく乱れている意。 |
| 風魚之災 | ふうぎょのわざわい | 海上に暴風の起こること。一説に風雨の誤りとし、一説に大風を予知する魚の名とする。 |
| 風光明媚 | フウコウメイビ ふうこうめいび |
山水の風景が清らかで美しいこと。 |
| 風餐雨臥 | ふうさんうが | 風に吹かれ雨に打たれる。風雨にさらされて苦労すること。 |
| 風餐露宿 | ふうさんろしゅく | 風の中で食事を取り、露に濡れて宿る。野宿をすること。 |
| 風櫛雨沐 | ふうしつうもく | 風でくしけずり、雨で髪を洗う。苦労を忍んで奔走すること。 |
| 風樹之嘆 | ふうじゅのたん | 思い通りにゆかないこと。 |
| 風声鶴唳 | ふうせいかくれい | 些細なことにおそれること。敗軍の兵が風の音や鶴の鳴き声にもびくびくおびえること。 |
| 風前之灯 | ふうぜんのともしび | はかなく、もろいことのたとえ。 |
| 風霜高潔 | ふうそうこうけつ | 風は高く吹き、霜は白く清い。秋の景色を述べたもの。 |
| 風俗壊乱 | ふうぞくかいらん | 世の中の健全・善良な風俗や風習が乱れ、害されること。 |
| 風俗紊乱 | ふうぞくびんらん | 秩序・風紀などが乱れること。また、乱すこと。 |
| 風木之悲 | ふうぼくのかなしみ | 風樹之嘆に同じ。 |
| 風流韻事 | ふうりゅういんじ | 詩歌、書画、華道、茶道などの風流な遊び。俗から離れ自然を友として詩歌などをつくる高尚な態度。 |
| 風流三昧 | ふうりゅうざんまい | 心が風雅で詩歌・文芸のほかは省みないこと。 |
| 風流篤厚 | ふうりゅうとっこう | 昔の風流の遺風で、後の人が自然に奥ゆかしく誠実で、行ないが手厚いこと。 |
| 風林火山 | ふうりんかざん | 何かを実行するときに重要なポイントを言った熟語。 |
| 複雑怪奇 | フクザツカイキ | 内容が込み入っていて不可解なこと。奇妙きてれつ。複雑で怪しく不思議なこと。内容が込み入っていてよくわからないこと。「怪奇」は怪しく不思議なこと。 |
| 複雑多岐 | フクザツタキ | 物事が多方面に分かれ、込み入っているさま。事情が込み入っているさま。物事の関係が多くの方面にわたっていて、込み入っているさま。「多岐」は分かれ道が多いこと。多方面にわたっていること。 |
| 覆車之戒 | ふくしゃのいましめ | 前人の失敗を見て戒めとすること。 |
| 覆水不返 | ふくすいふへん | 取り返しのつかないことの例え。一度盆からこぼした水は再び盆には返らない。一度離婚した夫婦は元通りにはならないということ。 |
| 覆負之患 | ふくはいのうれい | 覆り敗れる心配。舟のひっくりかえる心配。戦いに敗れるおそれ。家運の傾くおそれ。 |
| 福徳円満 | フクトクエンマン ふくとくえんまん |
福と徳、すなわち幸福と財産が充分に備わって満ち足りていること。 |
| 腹心之友 | ふくしんのとも | 心から信頼できる親友のこと。 |
| 腹中之書 | ふくちゅうのしょ | 腹の中に蓄えた書物。晉の?隆が世間の人が虫干しをして衣装を見せびらかすのを見て、おれは腹中の書の虫干しをするのだと、ひなたに出てあおむけに腹をさらしたこと。 |
| 伏波将軍 | ふくはしょうぐん | 漢の武帝の時の水軍の将軍の名。後漢の馬援がこの官につけられたので、馬援の呼び名。 |
| 伏竜鳳雛 | ふくりゅうほうすう | 池中深く潜む竜や鳳凰の雛が、天を駆ける才能がありながら、その才を現さないように、世を治める才能を持ちながら、まだ機会を得ずに活躍できない者のたとえ。伏竜は諸葛亮孔明、鳳雛は?統士元をいう。どちらも後漢の人。 |
| 二股膏薬 | ふたまたこうやく | 定見を持たないこと。節操がないことをいう。内股にはった膏薬(練り薬を紙や布に塗ったもの)は、あちこちにはりついてしまうことから。「ふたまたごうやく」とも読む。 |
| 物情騒然 | ぶつじょうそうぜん | 世の中が騒々しいこと。「物情」とは、物事のありさま、人の心情などの意。 |
| 物心両面 | ぶっしんりょうめん | 物質的な面と精神的な面、両方で。 |
| 刎頚之友 | ふんけいのとも | 生死をともにし、首を刎ねられても心を変えないほどの親しい友人。 |
| 刎頸之交 | ふんけいのまじわり | 生死をともにし、首を刎ねられても心を変えないほどの親しい交わり。 |
| 紛紅駭緑 | ふんこうがいりょく | 赤い花、青い葉が風に乱れ、翻るさま。 |
| 紛更之故 | ふんこうのこ | かき乱して改め変えた事柄。 |
| 粉骨砕身 | フンコツサイシン | 力の限り努力すること。非常に苦労して働くこと。全力を傾けてやる。力の限り努力することのたとえ。骨を粉にし、身を砕く意から。 |
| 粉骨報効 | ふんこつほうこう | 非常に骨を折って恩返しをする。 |
| 紛擾多端 | ふんじょうたたん | ごたごた乱れてまとまりがつかないこと。 |
| 粉白黛緑 | ふんぱくたいりょく | おしろいを白く塗り、まゆずみで青くまゆを引く。化粧をすること。美人。 |
| 紛紛聚訴 | ふんぷんしゅうそ | ごたごたといろいろなことを訴える。 |
| 紛紛擾擾 | ふんぷんじょうじょう | ごたごたと乱れる。 |
| 奮励努力 | ふんれいどりょく | 目標に向かって気を奮い起こし、つとめ励むこと。物事を成就し、成功させるための心構えとして使われる。 |
| 忿忿之心 | ふんぷんのこころ | 怒る心。 |
| 焚書坑儒 | ふんしょこうじゅ | 書物を焼き捨てたり儒者を穴に埋めたりするように、言論や学問思想を弾圧すること。 |
| 焚琴煮鶴 | ふんきんしゃかく | 風流の心がなく殺風景なこと。 |
| 文質彬彬 | ぶんしつひんぴん | 外見の美と内面の実質とが、程よく調和してそろっていること。 |
| 文人墨客 | ブンジンボッカク | 文人と芸術家。詩文、書画など風雅ないとなみに携わる人。詩文や絵画などに親しむ風流な人。文人と墨客と。「墨客」は、書画・詩文にすぐれたひと。「ぼっきゃく」とも読む。 |
| 文恬武嬉 | ぶんてんぶき | 世の中が平和で、文官も武官も喜び楽しむこと。 |
| 文武兼備 | ぶんぶけんび | 一人の人間が、文芸・武事の両方を兼ね備える。 |
| 文武両道 | ぶんぶりょうどう | 学問と武芸の両方にすぐれている人のこと。 |
| 文明開化 | ブンメイカイカ | 人知が発達し世の中が開けて生活が便利になること。(未開の状態から)人間の知恵が進歩して世の中が開けること。 |
| 蚊虻之労 | ぶんぼうのろう | 蚊や虻の労力。極小さいものの働きをいう。 |
| へ | ||
| 平易明快 | へいいめいかい | わかりやすく筋道がはっきりしていること。 |
| 平穏無事 | へいおんぶじ | 平和で穏やかなこと。これといった事件や事故もなく穏やかである意。 |
| 平原督郵 | へいげんとくゆう | 悪酒の異名。晉の桓温の下役のものが、よい酒を青州従事、悪い酒を平原督郵といった故事に基づく。青州には斉郡があり、平原には鬲県があったので、斉を臍(へそ)、鬲を膈(胸のあたり)に音を通わせ、よい酒はへそのあたりまで通り、悪い酒は胸のあたりにつかえるの意味から用いた隠語。 |
| 平沙万里 | へいさばんり | 果てしなく広がっている砂原。 |
| 平身低頭 | ヘイシンテイトウ | ひれ伏して、地面に頭をつけること。へりくだって恐縮するさま。頭も腰も低くして恐縮すること。ひれ伏して敬うこと。また、ひたすらあやまること。 |
| 平談俗語 | へいだんぞくご | 日常の会話にふつうに現われるような、ふつうの言葉。 |
| 平談俗話 | へいだんぞくわ | 日常の会話で話される普通のことば。平談俗語。 |
| 平旦之気 | へいたんのき | 夜明けの清明な気持。明け方のすがすがしい精神。 |
| 平地風波 | へいちのふうは | 穏やかな所に、しいて波風を起こす。わざと争いを起こすたとえ。 |
| 平平坦坦 | へいへいたんたん | きわめて平らなこと。何の変化もないさま。 |
| 平平凡凡 | ヘイヘイボンボン へいへいぼんぼん |
普通の人と同じで特に優れた点や変わった特色のないこと。「平凡」を強めた言い方。 |
| 平明之治 | へいめいのち | 公平で明らかな政治。 |
| 平和克服 | へいわこくふく | 戦争が終わって再び平和な世の中になること。 |
| 兵革之事 | へいかくのこと | 戦争。 |
| 兵革之士 | へいかくのし | 戦士。兵卒。 |
| 兵貴神速 | へいきしんそく | 戦争では一瞬の遅速で運命が決まる。用兵を動かすのは敏速果敢でなければいけない。 |
| 兵車蹂蹴 | へいしゃじゅうりん | 軍隊の車が踏みにじり蹴立てること。また、その被害を受けること。 |
| 兵車之会 | へいしゃのかい | 兵車を率い武力によって行う会合。 |
| 兵馬倥偬 | へいばこうそう | 戦争で忙しいこと。世の困難多事なさま。倥偬は忙しい、また、苦しいこと。 |
| 閉月羞花 | へいげつしゅうか | 美人を形容する言葉。月は雲間に隠れてしまい、花も恥じらってしぼんでしまう。 |
| 閉戸先生 | へいこせんせい | 年中、戸を閉め切って読書にふける人。学問に没頭する人物。 |
| 弊衣破帽 | ヘイイハボウ へいいはぼう |
服装がバンカラなこと。ぼろぼろの衣服と破れた帽子。またそれを身につけたさま。蛮カラ。ぼろぼろの衣服と破れた帽子のこと。特に、旧制高等学校の学生の蛮カラを気取った服装のこと。 |
| 弊絶風清 | へいぜつふうせい | 悪事・悪習が絶えて風習が改まってよくなる。政治の行き届いた状態をたとえていう。 |
| 并州之情 | へいしゅうのじょう | 第二の故郷ともいえる所を懐かしむこと。唐の賈島が長く并州に住み、去るとき、并州を故郷だといって別れを惜しんだ故事。 |
| 秉燭夜遊 | へいしょくやゆう | 人生ははかなく短いので、せめて夜も灯(あかり)をともして遊び、生涯を楽しもうということ。「秉(と)る」は持つことで、灯をともして夜も遊ぶということ。 |
| 萍水相逢 | へいすいそうほう | 「いすいあいあう」とも読む。「萍」は浮き草、水草。浮き草が水の流れに漂っているように、人が人に偶然出合うこと。 離れているものが偶然一つになることをいう。 |
| 米塩之資 | べいえんのし | 生活にまず必要な、米と塩を買う金。生計費。 |
| 米塩博弁 | べいえんはくべん | 細かいことまで詳しく論じる。米や塩は細かいのでいう。 |
| 碧波浩蕩 | へきはこうとう | 青々とした海水を広々とたたえているありさま。 |
| 碧落一洗 | へきらくいっせん | 大空がからりと晴れること。青空を雨で一洗いした意味。 |
| 変幻自在 | ヘンゲンジザイ へんげんじざい |
自分の思い通りに変化したり、現われたり消えたりすること。種々変化すること。思いのままに変化すること。 |
| 変幻出没 | へんげんしゅつぼつ | 自在に姿を変えたり、出没したりすること。 |
| 変身願望 | へんしんがんぼう | 自分ではない他のものに姿を変えたい願望。 |
| 片言隻句 | へんげんせきく | ちょっとした短い言葉の意。ひとことふたこと。「片言」は簡単な言葉。ちょっとした言葉。「隻句」は、わずかなことば。=片言隻語。「へんげんせっく」とも読む。 |
| 片言隻語 | へんげんせきご | ちょっとした短い言葉の意。ひとことふたこと。「片言」は簡単な言葉。ちょっとした言葉。「隻語」は、わずかなことば。=片言隻句。 |
| 片言隻辞 | へんげんせきじ | わずかな言葉。ひと言、ふた言。 |
| 辺幅修飾 | へんぷくしゅうしょく | 体裁をつくろうこと。 |
| 偏旁冠脚 | へんぼうかんきゃく | 漢字の字形を構成する要素の名称。偏と「つくり」と上部のかんむり、下部の脚。 |
| 便宜施行 | べんぎしこう | 頃合を見計らって都合の良いように事を行う。情勢を見て処置する。 |
| 鞭声粛粛 | べんせいしゅくしゅく | 馬に鞭打つ音をそっと慎んださま。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)