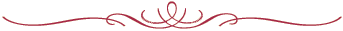
| 四文字熟語集4(ナ行) |
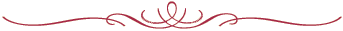
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、四文字熟語熟語言葉のナ行を確認しておく。 2008.8.31日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| ナ | ||
| 南無三宝 | なむさんぽう | 仏・法・僧の三宝に帰依すること。失敗したときに発する語。 |
| 南郭濫芋 | なんかくらんう | 実力も無いのに其の地位にしがみついている人のこと。 |
| 南華真経 | なんかしんぎょう | |
| 南華真人 | なんかしんじん | 『荘子』の別名。 |
| 南華之悔 | なんかのくい | 上司に逆らい、また余計なことを言って嫌われ、出世できないこと。 |
| 南柯之夢 | なんかのゆめ | 人生がはかなく、空しいことのたとえ。 |
| 南橘北枳 | なんきつほっき | 江南の橘を江北に移植すると枳殻に変わる。人もその居所によって善にも悪にもなることのたとえ。 |
| 内外之分 | ないがいのぶん | 内と外の区別。自分とともにあるものと外にあるものの別。 |
|
内柔外剛 |
ないじゅうがいごう | 内心は弱々しいのに外見は強そうに見えること。本当は気が弱いのに外に現れた態度だけ強そうに見せること。 |
| 内助の功 | ないじょのこう | 夫が外で十分働けるよう家で支援する妻の働き。 |
| 内政干渉 | ないせいかんしょう | 他国の政治、外交に口だしをすること。 |
| 内清外濁 | ないせいがいだく | 「内は清く、外は濁る」。心中、高潔を保っていても、表面は濁り汚れた様子に見せかけ、今の俗世間と妥協してゆくこと。 転じて乱世の時代に危険をさけ、身を全うする処世術をいう。 |
| 内地雑居 | ないちざっきょ | 外国人が国内のどこにでも自由に居住できること。 |
| 内的生活 | ないてきせいかつ | 精神生活。 |
| 内典外典 | ないてんげてん | 仏教の書とそれ以外の書。また、国内の書物と外国の書物のこと。 |
| 内憂外患 | ないゆうがいかん | 国内の心配事と、外国からしかけられるわずらわしい事態。また、個人における内外の心配事もいう。国内の心配事と外国からうける心配事。「憂」も「患」もともに、心配事、心を痛める意。 |
| 長五百秋 | ながいおあき | 長く久しい年月。長秋。 |
| 難解難入 | なんかいなんにゅう | 法華の法理のように理解しにくく、悟りに入りにくいこと。 |
| 難行苦行 | なんぎょうくぎょう | 辛く苦しい修行。転じて、非常な困難の中で苦労をすること。 |
| 難兄難弟 | なんけいなんてい | どちらがすぐれているか区別がつかない。優劣の判断がつきにくいさま。 |
| 難攻不落 | なんこうふらく | 攻撃が難しく、なかなか陥落しない状況のこと。攻撃するのが難しくて、なかなか落ちないこと。 |
| 難中之難 | なんちゅうのなん | 難しいことの中でも難しいこと。最も難しいこと。至難。 |
| 難問奇問 | なんもんきもん | 難しい質問や問題、とっぴな質問のこと。 |
| 南柯一夢 | なんかいちむ | 不思議(ふしぎ)な夢。はかないことの喩(たと)え。『異聞(いぶん)集』という不思議な話を集めた唐代の物語集に見える。唐の淳于芬(じゅんうふん)という男が酔って庭の鬼(えんじゅ)の木の下で眠ると、夢に2人の使者が現れて、鬼安(かいあん)国の南可郡の郡主に任命するという。郡主にとりたてられてそのまま20年を過ごし、そこで夢がさめた。さめた後、槐の木の根もとを調べてみると、大きな穴があいていて、中に大蟻(あり)がいた。これが夢の中の鬼安国王であった。また1つの穴があって槐の木の南の柯(えだ)に通じていたが、これが芬(ふん)の治めていた南可郡であった、と。「黄粱一炊(こうりょういっすい)」とよく似ている。この種の話を「伝奇(でんき)」という。小説の源流だ。 |
| 南行北走 | なんこうほくそう | あちこち忙しく駆けまわる。 |
| 南山之寿 | なんざんのじゅ | 終南山が崩れないのと同じで、その人の事業の長く久しいこと。転じて、長寿を祝う言葉。 |
| 南船北馬 | なんせんほくば | 南の地は船で行き、北の地は馬で行く~~~所々、方々をたえず旅していること。南や北へ絶えず各地を旅すること。忙しく動き回ること。中国の南部は、川が多いので船を利用し、北部は、山や平原が多いので馬を交通手段に用いたことからいう。 |
| 南都北嶺 | なんとほくれい | 奈良興福寺と比叡山延暦寺。 |
| 南蛮鴃舌 | なんばんげきぜつ | やかましいだけで意味の通じない言葉。外国人の、意味の通じない言葉を卑しめていう。 |
| 二 | ||
| 二河百道 | にかびゃくどう | 仏教でいう没後の理想国「極楽」をいう。また信徒の心得として彼岸に達する道をいう。 二河は水と火の二つの河で、その間に一筋の白い道がある。「白道」とは清らかに往生を願う心、 一心不乱に白道を進めば西方の極楽浄土に到着するといわれる。仏教で言う来世の理想国、極楽の事。 |
| 二者択一 | ニシャタクイツ | 二つの事物のいずれか一方だけを選ぶこと。二つのもののうち、一方を選ぶこと。黒か白か、イエスかノ-か、など、どうしても二つのうち一つを選ばなくてはならない場面に使われる。派生して「三者択一」などともいわれるようになった。 |
| 二十四史 | にじゅうしし | 中国の正史の総称。史記・漢書・後漢書(三史)・三国志(四史)・晉書・宋書・南斉書・梁書・陳書・後魏書・北斉書・周書・隋書・南史・北史・唐書・五代史(十七史)・遼史・金史・宋史・元史(二十一史)・明史(二十二史)・旧唐書・旧五代史(二十四史)。新元史を加えて二十五史という。 |
| 二姓之好 | にせいのよしみ | 夫の家と妻の家とのよしみ。結婚することを、二姓のよしみをかわすという。 |
| 二束三文 | にそくさんもん | 数が多くても値段が大変安いこと(もの)。「二束」は、「二足」とも書く。 |
| 二桃三士 | にとうさんし | 「二桃、三士を殺す」奇計で豪傑を自滅させるたとえ。 |
| 二人三脚 | ににんさんきゃく | 二人で仲良く責任を分け合ってすること。二人の人が自分の片足をひもで縛って走る競技。 |
| 二律背反 | にりつはいはん | 互いに対立、または矛盾する二つの命題が、同等の権利をもって主張されること。二つの命題がお互い矛盾していて両立しないこと。(あちらをたてればこちらがたたないこと) |
| 二六時中 | にろくじちゅう | 一日中。しじゅう。いつも。(むかし、朝夕をそれぞれ六つのときに分けたのでいう)。 |
| 肉山脯林 | にくざんほりん | 肉が山のように、干し肉が林のように多いの意味。贅沢な宴会をいう。 |
| 肉食妻帯 | ニクジキサイタイ | 肉を食べ妻をもつこと。在家(一般人)の生活。出家は逆に菜食独身であった。 |
| 日常茶飯 | ニチジョウサハン にちじょうさはん |
毎日毎日の食事。転じて、あたりまえのこと。ごくありふれた事柄。毎日のありきたりの物事や行動。普段の食事の意から転じて平凡なことの意。 |
|
日常坐臥 |
ニチジョウザガ | 毎日行われるいつもの生活。ふだん常々。いつも。 |
| 日暮道遠 | にちぼどうえん | 日暮れて、道遠し。多忙のたとえ。年老いたのにしなければならないことが残っていること。 |
| 日昃之労 | にっしょくのろう | 昼食抜きで昼過ぎまで働く骨折り。 |
| 日新月盛 | にっしんげっせい | 日に日に新しい物ができ、月を追って盛んになること。 |
| 日進月歩 | ニッシンゲッポ | 日に、月に、絶え間なく進歩すること。絶えず進歩し、発展すること。絶え間なく急速に進歩、発展すること。 |
| 衣錦還郷 | いきんかんきょう にしきをきてきょうにかえる |
きらびやかな衣服を着て故郷に帰ることから、立身出世して、故郷へ帰ることのたとえ。「錦」は、にしき。金糸銀糸などを織り込んで美しい文様を表した紋織物の総称。主に絹織物をいう。いわゆる「故郷へ錦を飾る」こと。南史柳慶遠/故郷の新聞社から、郷土出身の芸術家として、招待を受けるということは、これは、衣錦還郷の一種なのではあるまいか〈太宰治・善蔵を思う〉 |
| 入境問禁 | にゅうきょうもんきん | 他国に入ったら、まずその国の禁止事項を聞いて、それを犯さないようにすることが大切、という意味。 |
| 如是我聞 | ニョゼガモン にょぜがもん |
「このように私は聞いた」という意味。「是(かく)の如く我は聞けり」とよむ。 |
| 如渡得船 | にょどとくせん | 「渡りに船を得たるが如し」と読む。渡し場で都合良く船に乗れるという意味で、必要とする物や状況が、望むとうりになること。 |
| 如法暗夜 | にょほうあんや | 真っ暗闇。 |
| 女人禁制 | にょにんきんせい | 宗教修行の地域・霊場などへの女性の立ち入りを禁止する風習。 |
| 人間不信 | にんげんふしん | 人間でありながら人間を信用できないこと。 |
| 人三化七 | にんさんばけしち | 容貌が醜い人を酷評して「人が三分で化け物が七分」くらいに見えるという。それを省略していったもの。 |
| 認識不足 | にんしきぶそく | 物事について正しい判断を下すだけの知識がないこと。 |
| 忍之一字 | にんのいちじ | 忍耐が一番大切だということ。 |
| ヌ | ||
| 盗人根性 | ぬすびとこんじょう ぬすっとこんじょう |
盗みを働く人に特有の、ずる賢く卑しい性質。他人の隙を狙おうとする抜け目のない態度。 |
| 盗人上戸 | ぬすびとじょうご | 甘い物、お酒のどちらもいける「両刀使い」のこと。いくら酒を飲んでもケロリとしていて顔に出ない人のことも指す。 |
| ネ | ||
| 寝耳に水 | ||
| 涅槃寂静 | ねはんじゃくじょう | 仏教における三法印・四法印の一つ。煩悩の炎の吹き消された悟りの世界(涅槃)は、静やかな安らぎの境地(寂静)であるということ。 |
| 佞言似忠 | ねいげんじちゅう | 媚びへつらう言葉は、誠実な真心に似ているもの。佞言はおべっか、へつらう言葉。 |
| 熱願冷諦 | ねつがんれいてい | 求める時には熱心に願望し、かなわぬ時には冷静にさらりと諦念すること。 |
| 熱烈歓迎 | ねつれつかんげい | 感情を高ぶらせ熱っぽく歓迎すること。 |
| 年期奉公 | ねんきぼうこう | ある期間、無給で奉公すること。 |
| 年功加俸 | ねんこうかほう | 年功によって、本俸以外に給与する俸給。 |
| 年功序列 | ねんこうじょれつ | 年齢や勤続年数が増すにしたがって、地位や給料が上がること。また、そうした体系。長年の熟練によって地位や給料が決まること。能力や仕事の成績によらず、年齢や勤続年数によって、地位や給料が決まること。また、その体系。 |
| 年中行事 | ねんちゅうぎょうじ | 一年の間、各季節に決まって行われる行事。 |
| 年頭月尾 | ねんとうげっぴ | 一年月、一年中のたとえ。(年のはじめ、月末。)合わせて一年中の意。 |
| 年年歳歳 | ねんねんさいさい | 毎年、年ごとに。来る年も来る年も。 |
| 年百年中 | ねんびゃくねんじゅう | ねんがらねんじゅう。 |
| 念念刻刻 | ねんねんこくこく | 始終。かた時。時時刻刻。 |
| 念念生滅 | ねんねんしょうめつ | 世界のすべての物事は時々刻々に生じたり滅びたりして、少しの間もやむことがない。 |
| 念仏三昧 | ねんぶつざんまい | 一心不乱に念仏を唱えること。 |
| 念力徹岩 | ねんりきてつがん | 「念力岩を徹す」と読む。不可能と思われるようなことでも、真心をもって一心不乱に事を行えば、成らぬことのないたとえ。 |
| 燃眉之急 | ねんびのきゅう | 眉が焦げるほどの火急の時。差し迫った急場の情勢。(焦眉之急) |
| 燃犀之明 | ねんさいのめい | 見識があること。物事を明確に見抜くことのたとえ。 |
| 拈華微笑 | ねんげみしょう | 言葉を使わずお互いが理解しあうこと。心から心へ伝わる微妙な境地・感覚のたとえ。 |
| 黏皮帯骨 | ねんぴたいこつ | 詩歌などが、浅薄で余情に乏しいことの形容。 |
| ノ | ||
| 能工巧匠 | のうこうこうしょう | 技能に優れた大工、腕の良い職人。現代風にいうと、優秀なアーチスト、デザイナー、エンジニアなどのこと。 |
| 能事畢矣 | のうじおわれり | 成し遂げなければならないことは、すべてやり尽くした、の意。 |
| 嚢沙之計 | のうしゃのはかりごと | 韓信がたくさんの土嚢で川の上流をふさぎ、敵が河を渡ろうとしたときに、一度に水を流して大いに敵を破った計略。 |
|
嚢中之錐 |
のうちゅうのきり | 才能のある人は、大勢の中にいてもすぐに才能を発揮して目立つようになること。嚢は袋、~袋の中の錐はすぐその先が突き出てしまう。 |
| 述而不作 | のべてつくらず | 先賢の説を受け継いで述べ伝えるだけで、しいて自分の新説を立てようとしない。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)