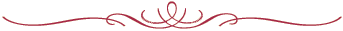
| 四文字熟語集4(タ行) |
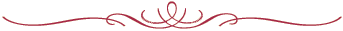
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、四文字熟語熟語言葉のタ行を確認しておく。 2008.8.31日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
| チ | ||
| 治山治水 | ちざんちすい | 植林などによって山を整え、用水路やダムを作って洪水を防ぐこと。水資源開発公団の大きな任務をもいう。 |
| 治乱興亡 | ちらんこうぼう | 歴史は治まったり、乱れたりが次々と繰り返されるという。 |
| 地殻変動 | ちかくへんどう | 地球のかたい部分が変化し、動き出すこと。 |
| 地祇逡巡 | ちぎしゅんじゅん | 疑い迷ってためらい、ぐずぐずして決行しないこと。また、そのさま。 |
| 地水火風 | ちすいかふう | 宇宙ができる根源だという元素。四大元素。 |
| 知行合一 | チコウゴウイツ | 真に知ることは必ず実行を伴う。知と行とは表裏一体で別のものではないという説。知識と実践の合致の意。明の王陽明の学説。真の知識があれば必ず行えるのであり、行ってのちにはじめて知ったことになる、の意。 真に知ることは必ず実行を伴う。知と行とは表裏一体で別のものではないという説。 |
| 知者一失 | ちしゃのいっしつ | 知者も時には過失するということ。知恵のある優れた人でも多くの考えや行ないのうちに一つぐらいの失敗はあるの意味。 |
| 知者楽水 | ちしゃくらくすい | 「知者は水を楽しむ」。識見豊かに智恵のある人は、物事に精通して滞ることがない。 あたかも水に似ていて、水を好む風格の人である。 |
| 知足安分 | ちそくあんぶん 足るを知り分に安んず |
高望みをせず、自分の境遇に満足すること。▽「知足」は足ることを知る意。分をわきまえて欲をかかないこと。「安分」は自分の境遇・身分に満足すること。 |
| 知勇兼備 | ちゆうけんび | 知恵と勇気を併せ持っていること。 |
| 魑魅魍魎 | ちみもうりょう | 山や水に住むいろいろの化け物。怪物。妖怪変化。山や水に住むいろいろの化け物。怪物。妖怪変化。山野にいる妖怪などのこと。いろいろな化け物や妖怪。 |
| 竹馬之友 | チクバノトモ | 幼年時代に竹馬で遊び合った仲のよい友人。幼児からの親しい友。 |
| 竹林七賢 | ちくりんしちけん | 晋代の中国で竹林の中で談論したという七賢人。 |
| 茶煙鬢糸 | ちゃえんびんし | 年老いて、青春の思い出にふけること。晩唐の杜牧(とぼく)の詩から出た語。「茶煙鬢糸の感」という。 |
| 着眼大局 | ちゃくがんたいきょく | 広い視野で問題をとらえること。 |
| 着手小局 | ちゃくしゅしょうきょく | 小さな事柄にも心を配り実践すること 。部分を正確に捉え着手すること。 |
| 直情径行 | チョクジョウケイコウ | 自分の思うままに行動して相手の立場を思いやらないこと。礼儀知らず。感情をそのまま挙動に現す。まわりの事情は他人の考えなどにかまわず、単純に行動すること。 |
| 丁丁発止 | ちょうちょうはつし | 激しく議論し合うさま。また、刀などで激しく音を立てて打ち合うさま。▽「丁丁」は続けて打ちたたく擬音。「発止」は堅い物どうしが打ち当たる擬音。「丁丁」は「打打」、「止」は「矢」とも書く。 |
| 猪突猛進 | ちょとつもうしん | 目標に対して、向こう見ずに突き進むこと。▽いのししの突進するのにたとえていう。 |
| 中途半端 | ちゅうとはんぱ | 途中までしかできあがってない様子。 |
| 中原之鹿 | ちゅうげんのしか | 中原は天下、鹿は帝位にたとえたもので、群雄が天下を争うことを、狩の競争にたとえた言葉。 |
| 中産階級 | ちゅうさんかいきゅう | 中間層を階級としていった言葉。社会成層の資本家階級と労働者階級との中間に位置する階層。 |
| 中肉中背 | ちゅうにくちゅうぜい | ふとりすぎもやせすぎもしないこと。 |
| 忠君愛国 | ちゅうくんあいこく | 主君に忠義を尽くし、自分の国を大事にする。 |
| 忠臣義士 | ちゅうしんぎし | 忠義な家来と正道を守る人。 |
| 忠勇義烈 | ちゅうゆうぎれつ | 忠義で勇気があり、正義の思いの激しいこと。 |
| 昼夜兼行 | ちゅうやけんこう | 非常に急ぐさま。昼も夜も休まず続行すること。転じて、仕事を急ぎ行うことにもいう。 |
| 朝雲暮雨 | ちょううんぼう | 男女の契り・情交のこと。▽「朝雲」は朝の雲、「暮雨」は夕暮れに降る雨の意。「暮雨朝雲」ともいう。 |
| 朝改暮変 | ちょうかいぼへん | 朝改めたことを夕暮れにまた変えること。 |
| 朝憲紊乱 | ちょうけんびんらん | 合法的な手段によらずに、政府の転覆など、国家存在の基本的組織を破壊すること。暴力革命のこと。 |
| 朝三暮四 | ちょうさんぼし | 目前の利害に捕われて結果が同じになるのを見抜けないこと。また、そのような状態に相手を追い込んで巧妙にだますこと。見かけの違いにだまされても結果は同じことであるというたとえ。 |
| 朝朝暮暮 | ちょうちょうぼぼ | 毎朝毎晩。 |
| 朝令暮改 | チョウレイボカイ | 朝出した命令を夕方にはもう改めるというように、法律や命令が頻繁に変えられて、一定しないこと。命令や法律がたびたび変更されて一定しないこと。朝に命令を出して、夕方には改める。 |
| 長者三代 | ちょうじゃさんだい | 初代が苦労して財産をつくり、それを見て育った子の二代目はその遺風をよく守るが、三代目の孫の代になると、生活が贅沢になり、ついに祖父が築いた家産を傾けてしまうことが多いということから、長者の家は参台り続かないということ。 |
| 長身痩躯 | ちょうしんそうく | 背丈の高い、痩せた体。鶴のような痩身。 |
| 長舌三寸 | ちょうぜつさんずん | 人前では調子のいいことを言いながらへつらいこびているが、陰では舌を出して笑うこと。 |
| 長汀曲浦 | ちょうていきょくほ | 長く続くみぎわと曲がりくねった入り江。曲がりくねって続いている海辺。▽「汀」はなぎさ・みぎわ、「浦」は浜辺・湾の意。 |
| 長目飛耳 | ちょうもくひじ | 見聞が遠くに及ぶこと。書物のことをいう。 |
| 長幼之序 | ちょうようのじょ | 年長者と年少者の、家庭及び社会上における位置の順序。 |
| 丁丁発止 | ちょうちょうはっし | はげしく議論をたたかわす様子。 |
| 頂門一針 | ちょうもんのいっしん | 相手の痛いところをついた一言。 |
| 懲戒処分 | ちょうかいしょぶん | 不正に対する懲らしめや戒めの処分。 |
| 彫虫篆刻 | ちょうちゅうてんこく | 虫を彫ったり篆書を刻んだりするように、文章で字句ばかり飾ることをいう。小刀細工。 |
| 寵愛一身 | ちょうあいいっしん | 高貴な人の愛を独占すること。 |
| 跳梁跋扈 | ちょうりょうばっこ | 悪人などが権勢をほしいままにして、わがままにのさばること。我が物顔にのさばりはこびること。悪人など好ましくないものが動き回る場合などに用いる。 |
| 直情径行 | ちょくじょうけいこう | 感情のままに行動すること。相手の気持ちなどは考えずに、感情をむき出しにして行動すること。浅はかで単純な行動のたとえ。礼儀知らず。 |
| 直截簡明 | ちょくせつかんめい | 見たり感じたりしたことをきっぱりと言い切ること。 |
| 直立不動 | ちょくりつふどう | まっすぐに立って少しも身動きしないこと。 |
| 猪突猛進 | ちょとつもうしん | 猪のように激しい勢いで突進する。融通がきかない人が向こうみずに事を進めることをいう。向こう見ずに突進するたとえ。猪のようにまっしぐらに突っ走ることから。周囲をかえりみない行動の場合にも使う。 |
| 沈魚落雁 | ちんぎょらくがん | 魚や雁も恥じらって身を隠すほどの美人。▽もともとは荘子(そうじ)斉物論(せいぶつろん)に見える逸話で、人間の基準での美人を見ても魚や鳥は逃げるだけだという、価値の相対性を表した語。「落雁沈魚」ともいう。 |
| 沈思黙考 | ちんしもっこう | 思いに沈み、黙って考えこむ。思案にふけること。静かに黙って深く考え込むこと。落ち着いてよく考えること。 |
| 沈着大胆 | ちんちゃくだいたん | 腹のすわった性格。 |
| 沈着冷静 | ちんちゃくれいせい | 落ち着いていて物事に動ぜず冷静であること。 |
| ツ | ||
| 痛快無比 | つうかいむひ | このうえなく胸がすうっとするように、愉快になること。 |
| 追善供養 | ついぜんくよう | 死者の年忌などに法事を営み、故人の善行を供養すること。 |
| 九十九折 | つづらおり | ツヅラのつるのように、山道などがはなはだしく曲がりくねっていること。 |
| 九十九髪 | つくもがみ | 老女の白髪。百から一を引くと「白」で白髪。次百(つぐもも)の略が九十九(つくも)となった。 |
| 津々浦々 | ツツウラウラ | いたるところの港や海岸。全国くまなくいたる所~の意味。全国の至る所(の港や浦)。 |
| テ | ||
| 手枷足枷 | てかせあしかせ | 自由な行動を束縛するもの。 |
| 手薬煉引く | てぐすねひく | 手ぐすねを引くとは、十分に準備して待ち構えること。手ぐすねを引くの「くすね(薬煉)」とは、松脂(まつやに)を油で煮て練り混ぜたもので、弓の弦などを強くするために塗られる粘着剤である。この薬煉を手に塗ることを「手ぐすね」と言う。合戦の前、十分な態勢で待ち構えるために、薬煉を手に取り弓の弦に塗ることから、十分に準備して機会を待つことを「手ぐすね引いて待つ」と言うようになった。 |
| 手前勝手 | てまえがって | 自分につごうのいいようにばかりふるまうこと。 |
| 手前味噌 | てまえみそ | 自分で自分の作ったものをほめること。 |
| 手練手管 | てれんてくだ | 人をだます手段。「手練」も「手管」もともに人を操る駆け引きの手際、技巧。同義語を重ねて意味を強めたもの。 |
| 低徊趣味 | ていかいしゅみ | 世俗を離れて自然や芸術を楽しむ趣味。 |
| 低頭平身 | ていとうへいしん | 頭を下げ身を伏せてあやまること。 |
| 亭主関白 | ていしゅかんぱく | 家庭の中で夫が妻に支配者のように威張っていること。 |
| 泥中之蓮 | でいちゅうのはす | 悪い環境に染まらず清く生きることのたとえ。 |
| 適材適所 | テキザイテキショ | もっともよくあてはまる才能を持つ人を、もっとも合った位置におくこと。うまい人材の配置。(その仕事に)適当な才能のひとを適当な位置に置くこと。 |
| 適者生存 | てきしゃせいぞん | 生存競争の結果、その環境に適するものだけが生き残り、他は滅びること。 |
| 敵国外患 | てきこくがいかん | 外にあって自国に害をなすもの。 |
| 徹底抗戦 | てっていこうせん | 相手にとことん手向かって戦うこと。 |
| 徹底大悟 | てっていたいご | 学問の奥義に達して、深く悟る。 |
| 徹頭徹尾 | てっとうてつび | 始めから終わりまで。一つの考えや方針などを、徹底してあくまでも貫くさま。始めから終わりまで通すこと。すこしも、決しての意味で使用することもある。 |
| 丁稚奉公 | でっちぼうこう | 少年が一定期間、雑役で奉公すること。 |
| 天威咫尺 | てんいしせき | 天子の側に仕える事。咫尺は近い意味。 |
| 天衣無縫 | てんいむほう | 文章や詩歌などが自然な出来栄えで技巧をこらした跡がなく、完璧に美しいことをいう。また、人柄などが無邪気で素直なさま。物事に手を加えた形跡のないこと。天人の着物には縫い目のないことから、 |
| 天涯孤独 | テンガイコドク | 身寄りがこの世にひとりもいないこと。また異郷にただ独りで暮らすこと。この広い世間でひとりぼっちであること。「天涯」は、空の果て。 |
| 天下一枚 | てんかいちまい | 天下すべてが一様であること。世間一般に共通であること。 |
| 天下一品 | てんかいっぴん | 他に比べるものがないほどすぐれていること(もの)。 |
| 天下国家 | てんかこっか | 天下と国家。全国家。全世界。特に、その政治面をさしてもいう。※清原国賢書写本荘子抄(1530)九「帝王の天下国家を治る功は、聖人の余りものにて治る也」 〔礼記‐中庸〕 |
| 天下三分 | てんかさんぶん | 昔、中国で魏・呉・蜀の三つに分かれて、互いに対立したこと。 |
| 天下太平 天下泰平 |
てんかたいへい | 世の中が極めて穏やかに治まっていて平和であること。安穏無事でのんびりしているさま。 |
| 天下大乱 | てんかたいらん | 大いに乱れること。戦乱や事変などで世の中が非常に乱れること。 |
| 天下無双 | てんかむそう | 天下に比べるものがない。 |
| 天下無敵 | てんかむてき | 世の中に並び比べる者がいないほど、強いこと。 |
| 天災地変 | てんさいちへん | 自然界に起こるさまざまな災害や異変。地震、台風、落雷、洪水など。 |
| 天子之気 | てんしのき | 天子または将来天子となるべきもののいる所に立ち上る雲気。 |
| 天井桟敷 | てんじょうさじき | 劇場などで、二階もしくは三階などの天井に近く、一番後方にこしらえてある見物席で、下等席。 |
| 天壌無窮 | てんじょうむきゅう | 天地とともに窮(きわ)まりのないこと。永遠に続くこと。 |
| 天神地祇 | てんしんちぎ | 天の神と地の神~すなわち、すべての神々。 |
| 天真爛漫 | テンシンランマン | 自然のままで飾り気がなく、偽りのないさま。ありのままの真情が言動に現われること。飾り気のない心がそのままあらわれていること。天与の純粋な心のままを言動にあらわして包み隠しのない態度。 |
| 天地開闢 | てんちかいびゃく | 天地の開け初め。天地発生のとき。 |
| 天地神明 | テンチシンメイ | 天地の神々。「天地神明に誓って」の形で用いられることが多い。天や地の神々。すべての神々。「神明」は神の意。 |
| 天然自然 | テンネンシゼン | あるがままに、人の手が加わらないで存在する状態。 |
| 天地父母 | てんちのふぼ | 天子。天子は万民を子のように慈しむものであることからいう。 |
| 天地の隔たり | てんちのへだたり | |
| 天地無用 | てんちむよう | 「(荷物、貨物などを)さかさまにするな」という意味の注意を与える言葉。 |
| 天地悠久 | てんちゆうきゅう | 天地は永久に尽きることがない。 |
| 天長地久 | てんちょうちきゅう | 天地は永久に尽きることがない。 |
| 天然自然 | てんねんしぜん | あるがままに、人の手が加わらないで存在する状態。 |
| 天馬行空 | てんばこうくう | 天馬行空は言動が自由である様や、思考の柔軟性を表す。また、あまり見ない用法ではありますが、文章が次々に浮かんでくる順調さや筆の進みが良いことも表します。 |
| 天罰覿面 | てんばつてきめん】 | 悪事を働くとすぐにその報いをうけること。「天罰」は、天の与える悪い報い。「覿面」は、まのあたりにあらわれるの意。 |
| 天変地異 | てんぺんちい | 天上界に現われる異変と、地上に起こる異変。天地自然の中で起こる異変・災害。天変や地震など、空や地上に起こる異変。 |
| 天馬行空 | てんばこうくう | |
| 天網恢恢 | てんもうかいかい | 天の網は大きすぎて目があらいようだが、物をすくい漏らすことはない。悪事をすれば必ず天罰を受ける意。「~~疎にして漏らさず」 |
| 天佑神助 | テンユウシンジョ | 天の助け、神の加護。思いがけない偶然によって助かることのたとえ。天や神のたすけ。 |
| 恬淡虚無 | てんたんきょむ | すべて、世間のうるさいことを捨てて、心を無我の境地に置く。老子の学説。 |
| 点滴穿石 | てんてきせんせき | 「点滴石をも穿(うが)つ」と読む。「雨垂石を穿つ」と同じ意味。 |
| 電光石火 | でんこうせっか | 行動などが非常に速いことのたとえ。石を打ち合わせてでる火のような、ちょっと光る瞬間。 |
| 田園詩人 | でんえんしじん | 田園に住み、田園の自然美をうたう詩人。 |
| ト | ||
| 徒手空拳 | トシュクウケン としゅくうけん |
手に何も持たないこと。事を始めるのに資金や地位などがまったくなく、自分の力だけがたよりであること。手に何も持たない、素手のこと。また、自分以外に頼るべき何物もないこと。 |
| 塗炭之苦 | とたんのくるしみ | 泥にまみれ、炭で焼かれたような苦しみ。 |
| 吐哺捉髪 | とほそくはつ | 昔、周公旦が、客が来ると、食事中でも口中の食物を吐き、髪を洗っているときでも髪を握ってすぐに出迎えた故事で、つとめて賢士を優待する意味にいう。 |
| 土階三等 | どかいさんとう | 入り口にある土の階段が三段しかない、質素な宮殿のたとえ。転じて、住居や生活の質素なことのたとえ。▽「等」は階段の段のこと。 |
| 土牛木馬 | どぎゅうもくば | 土製の牛と木製の馬との意味で、見かけは良いが内容のないもののたとえ。家柄だけで才能のない人。 |
| 土豪劣紳 | どごうれっしん | 横暴な土地のならず者のこと。「土豪」は、その土地で勢力のある豪族。「劣紳」は、農民を搾取した地主・資産家の蔑称で、卑劣不正な紳士の意。 |
| 土崩瓦解 | どほうがかい | 土がくずれ瓦が崩れ落ちる。物事が崩れて手のつけようがないこと。 |
| 怒髪衝天 | どはつしょうてん | 髪に毛が逆立つほど怒る様。 |
| 駑馬十駕 | どばじゅうが | 才能がない人でも、努力をすれば才能のある人に並ぶことができるということのたとえ。「駑馬」は、足の遅い馬のこと。「駕」は、馬に車をつけて走ること。足の速い馬は一日で千里もの距離を走るが、足の遅い馬でも十日間休まず走り続ければこれに追いつけるという意味から。 |
| 当意即妙 | トウイソクミョウ | その場にうまく適応した即座の機転をきかせるようす。当座の機転。その場の様子にうまくあうように機転をきかすこと。 |
| 当代随一 | とうだいずいいち | 現代でもっともすぐれた第一人者のこと。 |
| 当代無双 | とうだいむそう | この時代に並ぶ者がいない第一等の人。 |
| 党利党略 | とうりとうりゃく | 党としての利益とそのためのはかりごと。 |
| 闘志満々 | とうしまんまん | 闘争心の旺盛なこと。「満々」は、満ちていることで、戦おうとする意志がみなぎっていること。 |
| 東西古今 | とうざいここん | 東洋と西洋、昔と今。 |
| 東西南北 | とうざいなんぼく | 天下いたる所。どこでも。居所の一定しないこと。 |
| 東山高臥 | とうざんこうが | 世俗を離れて、山野に隠れ住み、自由気ままに暮らすこと。隠居して出仕しないことのたとえ。隠遁。 |
| 東奔西走 | とうほんせいそう | 東西に奔走する。あちらこちらに、なにかと忙しく駆け回ること。あちこち忙しく駆け回るさま。東に奔(はし)り、西に走る。 |
| 東来西走 | とうらいせいそう | 東から来て西へ去るの意で定めのないことをいう。 |
| 桃李成蹊 | とうりせいけい | 立派な人物は自ら求めなくてもその徳をしたって自然に人々が集まってくるたとえ。桃や李(すもも)は、何も言わないが花や実にひかれて自然に人々が集まるので木の下にはいつの間にか小道が出来てしまうという意。 |
| 桃李満門 | とうりまんもん | 桃やスモモが門に満ちあふれる意で、優秀な人材が一門に多く集まること。 |
| 橙黄橘緑 | とうこうきつりょく | だいだい(橙)が黄色くなり、みかん(橘)が緑色になるころ。初冬の小春日和の時節。蘇東皮(そとうば)の詩から出た語。 |
| 蟷螂の斧 | とうろうのおの | 弱いものが強いものに挑むこと。 |
| 棟梁之器 | とうりょうのき | 重任にたえうる人材。大事に任じる人材。 |
| 冬扇夏炉 | とうせんかろ | 冬の扇と夏の火鉢。時節に合わないで不用になったもののたとえ。 |
| 同音異義 | どうおんいぎ | 漢字の音は同じでも、意味が違うこと。 |
| 同工異曲 | どうこういきょく | こしらえや手際が同じで、趣が違う。見かけは違うように見えるが内容は同じである。 |
| 同床異夢 | どうしょういむ | 同じ床に寝ていながら、違う夢をみるように、いっしょに仕事をして意見が一致しないこと。同じ床に寝ていながら、違う夢をみるように、いっしょに仕事をして意見が一致しないこと。身体は同居していながら心が隔絶すること。同じ床に寝ながらそれぞれ別の夢を見る意。同じ場所、同じ物事に取り組みながら別々のことを考え、心が一致しないことの例え。 |
| 同床各夢 | どうしょうかくむ | 立場や仕事が同じでも、考え方や目的が違うこと。同じ寝室で寝ても、見る夢の内容はそれぞれ違うという意味から。 |
| 同病相憐 | どうびょうそうりん どうびょうあいあわれむ |
同じ苦しみに悩む者は、互いにいたわり合い同情し合う気持ちが強い。どうびょうあいあわれむ。 |
| 同文同種 | どうぶんどうしゅ | 使用する文字が同じく、人種も同じであること。日中関係や南北朝鮮の関係に使う。 |
| 同袍同沢 | どうほうどうたく | 戦友。親しい友達。衣服を共通にし、苦しみをともにするの意味。沢ははだぬぎ。 |
| 同盟罷業 | どうめいひぎょう | 労働条件の改善などの要求を通すために、集団的に全員が作業をやめること。ストライキ。 |
| 同盟罷工 | どうめいひこう | 労働条件の改善などの要求を通すために、集団的に全員が作業をやめること。ストライキ。 |
| 童男童女 | どうだんどうじょ | 男の子供と女の子供。 |
| 動天驚地 | どうてんきょうち | 天を動かし地を驚かすの意から、世間を驚かすことをいう。 |
| 堂堂巡り | どうどうめぐり | 1 祈願のために、仏堂などのまわりをぐるぐるまわること。 2 同じようなことが何度も繰り返され、進行しないこと。「議論が—する」 3 国会で投票によって議決するとき、議員が演壇上の投票箱に順次投票することの俗称。 |
| 堂塔伽藍 | どうとうがらん | 寺院の建物の総称。 |
| 洞房花燭 | どうぼうかしょく | 婦人の部屋に灯火が美しく輝くこと。新婚。また、結婚の祝い。 |
| 時世時節 | ときよじせつ | その時々のめぐりあわせ。その時々の移り変わり。 |
| 得意満面 | トクイマンメン | 誇らし気なようすが顔じゅうに満ちていること。物事が思い通りになって、誇らしげな様子が顔全体に満ちあふれているさま。 |
| 特立独行 | とくりつどっこう | 自ら信じる所を守り、世俗の外にぬきんでて立ち、初志を貫徹すること。 |
| 読書三到 | どくしょさんとう | 宋の朱熹しゅきの唱えた、読書に大切な三つの心得。目でよく見ること(眼到)、声を出して読むこと(口到)、心を集中して読むこと(心到)の三つ。 |
| 読書三余 | どくしょさんよ | 読書をするのに好都合な三つの余暇。一年のうちでは冬、一日のうちでは夜、時のうちでは雨降りをいう。中国三国時代、魏の董遇(とうぐう)が勉学する時間がないと嘆く弟子を諭した語。▽「余」はひま・余暇の意。 |
| 読書尚友 | どくしょしょうゆう | 書物を通じて昔の賢人に親しむこと。 |
| 読書百遍 | どくしょひゃっぺん | 何度も繰り返して書物を読めば、意味は自然にわかるようになる。何度もていねいにゆっくり読むべきことをいう。 |
| 読書亡羊 | どくしょぼうよう | 他のことに心を奪われ大切なことを忘れること。 |
| 独学孤陋 | どくがくころう | 先生や友人のいない独学者は見聞が狭いので、その学問は独り合点のところが多く、見識が狭いこと。 |
| 独断専行 | どくだんせんこう | 他人に相談しないで勝手に決め、物事を行うこと。自分だけの考えで決めて、勝手に行動すること。「専行」は、「擅行」とも書き、欲しいままに行う意。 |
| 独立自営 | どくりつじえい | 人に頼らず自分自身の力で事業を営む。 |
| 独立自尊 | どくりつじそん | 自分自身に誇りを持つこと。何事も自力で行い、他の援助を受けないこと。 |
| 独立独行 | どくりつどっこう | 人に頼らず自分で自分の信じるところを行なう。 |
| 独立独歩 | どくりつどっぽ | 他人にたよらず、自分で自分の考えを実行する。他の力を借りず、また他の支配束縛を受けず、自己の所信を遂行すること。 |
| 特立之士 | とくりつのし | 世俗の外にぬきんでて立派な人。 |
| 独立不撓 | どくりつふとう | 自分の力だけでやり抜くこと。「不撓」は、困難に負けないさま。どのような困難に遭遇しても屈することなく自分の力で自分の意志によって、目標を達成するさま。 |
| 突然変異 | とつぜんへんい | 突如として親と違うものに変わる現象のこと。 |
| 特権階級 | とっけんかいきゅう | 特別の権利や権限で優遇される階級。 |
| 特筆大書 | とくひつたいしょ | 特に大きく書く、特に強調すること。 |
| 床屋政談 | とこやせいだん | 床屋でするような政治に関する気楽な議論。 |
| 途轍もない | とてつもない | 筋道をはずれること、並外れたこと、途方もないこと。 |
| 図南鵬翼 | となんほうよく | 大志を抱いて大事業を計画すること。「図南」は南方に向かって飛び立とうとする意。「鵬翼」は大きな鳥の翼。よって大きな鳥が南方にはばたくこと。 |
| 呑牛之気 | どんぎゅうのき | 牛を丸のみにするほど、気持の大きいこと。 |
| 呑舟乃魚 | どんしゅうのうお | 舟を丸呑みにするほどの大魚。善・悪ともに大人物のたとえ。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)