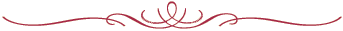
| 四文字熟語集3(サ行) |
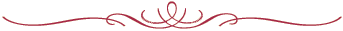
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、四文字熟語熟語言葉のサ行を確認しておく。 2008.8.31日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| サ | ||
| 塞翁之馬 | さいおうのうま | 人間の運命・幸不幸は定まりなく、吉凶はわからないもの、ということ。したがって、小さな出来事にいちいち一喜一憂すべきでないこと。 |
| 斎戒沐浴 | さいかいもくよく | 神聖な行事の前に心身を清めて、穢れを取り除くこと。 |
| 才気煥発 | さいきかんぱつ | 才気がひらめくようにあらわれること。頭の働きが速く優れていること。才能が光り輝き目立つこと。才気が盛んに外に現れる様子。 |
| 再起不能 | さいきふのう | 病気、失敗、事件などでもう立ち直れないこと。 |
| 再三再四 | さいさんさいし | たびたび。 |
| 再従兄弟 | さいじゅうけいてい | またいとこ。祖父母の兄弟の孫。日本では従兄弟同士の子。父母の兄弟姉妹の孫。 |
| 歳月不待 | さいげつふたい | 歳月は人の都合を待ってくれないこと。このことから今の時を大切にし日々怠けることなく努力せよ。と言う戒めに用いることが多い。 |
| 歳歳年年 | さいさいねんねん | としどし。毎年。 |
| 再三再四 | さいさんさいし | たびたび。 |
| 在在所所 | ざいざいしょしょ | あちこちの村々。ここかしこ。あちこち。 |
| 才子佳人 | さいしかじん | 才能のある男と美女。好一対の取り合わせの男女にいう。 |
| 才子多病 | さいしたびょう | 才能のある人物は、とかく体が弱く、病弱なものであるということ。 |
| 才色兼備 | サイショクケンビ | 女性が優れた才能と、そして美しい顔立ちと、両方ともに恵まれていること。女性が優れた才能を持ち、容貌もまた美しいこと。「才色」は、才能と容貌の意。 |
| 妻子眷属 | さいしけんぞく | 妻子と親族。一家一門。 |
| 再従兄弟 | さいじゅうけいてい | またいとこ。祖父母の兄弟の孫。日本では従兄弟同士の子。父母の兄弟姉妹の孫。 |
| 載舟覆舟 | さいしゅうふくしゅう | 君主は人民によって立ち、また、人民によって滅ぶ。人は味方にも敵にもなる。 |
| 祭政一致 | さいせいいっち | 宗教上の権威者と政治上の権力者が一体となっていること。古代社会で多く見られる、神の神託に基づいて国を治める政治形態。 |
| 西方浄土 | さいほうじょうど | 阿弥陀仏のいるという極楽浄土。仏教で西の方にあるといわれる清らかなところ。 |
| 坐臥行歩 | ざがこうほ | 立ち居ふるまい。 |
| 左顧右眄 | さこうべん | なかなか決心のつかないこと。(右を見たり左を見たりして)。=右顧左眄 |
| 砂上の楼閣 | さじょうのろうかく | 砂の上に建てた建物は不安定で壊れやすい。外見は頑丈でも基礎が脆弱ですぐ駄目になること。また、実現不可能なことをいう。 |
| 座右之銘 | ざゆうのめい | 常に身近に備えておいて、日常の戒めとする言葉や文。 |
| 三衣一鉢 | さんいいっぱつ | 僧侶が持ち歩く僅かな持ち物。「三衣」は三種の衣、王宮に行く時、講義を聴く時、作業等で日常着る時に衣を替えた。「一鉢」は食器。それだけあればとりあえず足りるとした。「衣」はネとも読む。 |
| 三益之友 | さんえきのゆう | 交わって利益となる三種類の友人。①正直な友②誠実な友③多聞な友 |
| 三王之佐 | さんおうのさ | 夏・殷・周の三王を助けるほどの賢人。 |
| 三界一心 | さんがいいっしん | 佛教-三界は「心をもつものの存在する欲界・色界・無色界の三つの世界。仏以外の全世界。三界は全て心に映る現象で、人間の心の中以外に三界はないということ。「三界無安」「三界唯一心」「三界流転」「三界に家なし」「三界の火宅」「三界の頚枷」等の用語。 |
| 三階九級 | さんがいくきゅう | 奈良時代以後に制定された僧官。僧正・僧都・律師の三階を、さらに大僧正・僧正・権僧正、大僧都・権大僧都・少僧都・権少僧都、律師・権律師の九つに分けたもの。 |
| 三角関係 | さんかくかんけい | 三人の男女間にもつれる恋愛関係のこと。 |
| 三寒四温 | サンカンシオン | 冬や春先の周期的で順当な気候変化のこと。寒い日が三日ほど続いた後、暖かい日が四日ほど続くこと。冬季、寒い日が三日続くと、その後四日ほどは暖かい日が続き、これが繰り返される気象現象のこと。 |
| 三管四職 | さんかんししょく | 室町時代の重要な職制で、管領と侍所所司に補された家柄で、「三管」は斯波・細川・畠山「四職」は赤松・一色・山名・京極をいう。 |
| 三跪九叩 | さんききゅうこう | 何度も最敬礼する。 |
| 三詭九拝 | さんききゅうはい | 中国清朝の敬礼の法。三度膝まずいて、九度頭を地につけて拝礼すること。「詭」はひざまずく「叩」はぬかずく。 |
| 三教一致 | さんきょういっち | 三つの教えが根本的には一体であること。中国では儒・道・佛、日本では神・儒・佛の一致が説かれる。 |
| 三教九流 | さんきょうきゅうりゅう | 三教は儒教・佛教・道教。九流は戦国時代の儒家・道家・陰陽家・法家・名家・墨家・縦横家・雑家・農家の九学派を総称したもの。 |
| 三言市虎 | さんげんしこ | 町に虎はいないが、三人まで虎がいるというと、最後にはこれを信じてしまう。誤った話も、多くの人が言えば真実と同じ力を持ってしまうという意味。 |
| 三権分立 | さんけんぶんりつ | 権力の濫用を防止し、国民の政治的自由を保障するため、国家権力を立法・司法・行政の三権に分け、それぞれ独立した機関にゆだねようとする原理。 |
| 三賢十聖 | さんけんじっしょう | 大乗で、菩薩の修行階位のうち、聖位である十地(十聖)と、それ以前の十住・十行・十廻向(三賢)。 |
| 三公九卿 | さんこうきゅうけい | 三公(司徒・司空・太尉)と九卿(時代によって違うが、太常・光録勲・衛尉・太僕・廷尉・大鴻臚・少府・大司農・宗正・執金吾・将作大匠など)。 |
| 三公七民 | さんこうしちみん | 江戸時代、収穫の三分を領主、七分を農民の所得とする税法。多くは領主の山野に農民が植林し、その成木を三公七民の割合で分収する造林法をいう。 |
| 三綱五常 | さんこうごじょう | 人間が常に守るべき大道。臣の守るべきしるべは君妻の守るべきしるべは夫子の守るべきしるべは父五常=仁・義・礼・智・信 |
| 三綱六紀 | さんこうろっき | 「三綱五常」に似た言葉であるが、君臣・父子・夫婦の道に「諸父、兄弟、族人、諸舅、師長、朋友」の道をいい、綱はおおづな、紀はこづなの意を表し、ともに中国における人間関係において守るべき教えを表す言葉である。 |
| 三皇五帝 | さんこうごてい | 中国伝説上の帝王。伏羲・神農・女[女+窩-穴]の三皇と、少昊・黄帝・[喘-口+頁][王+頁]・帝[學-子+告]・堯・舜の五帝。 |
| 三国四師 | さんごくしし | 日蓮宗で特に法華経を尊んでこれをひろめたインドの竜樹菩薩、中国の天台大師、日本の伝教大師・日蓮上人をいう。 |
| 三国鼎立 | さんごくていりつ | 鼎に三本の足があるように、三者が天下を三分して並び立つこと。 |
| 三顧之礼 | さんこのれい | 目上の人が、ある人に仕事を引き受けて欲しいと礼を厚くして頼む意。 |
| 三三九度 | さんさんくど | 結婚式で杯を酌み交わす儀式。 |
| 三三五五 | さんさんごご | 人々がちらほら道を行(歩)くようす。 |
| 三思一言 | さんしいちげん | 繰り返し考えたのちにことばに出すこと。ことばを慎むこと。 |
| 三辞三嬢 | さんじさんじょう | 三度勧められたら三度断り四度目で受取る。最初は遠慮することも必要であるという礼儀のたとえ。 |
| 三豕渡河 | さんしとか | 「三豕河を渡る」とも読む。文字を誤読誤用すること。「己亥河を渡る」と読むところを、己亥の字を三豕と読み間違えた故事。 |
| 三者三様 | さんしゃさんよう | やり方や考え方などが人それぞれで違いがあること。三人の者がいれば、三つのさま、様子、形がある意。類)各人各様・十人十色・百人百様 |
| 三者鼎立 | さんしゃていりつ | 三つの勢力が鼎のように立っている様。 |
| 三十三身 | さんじゅうさんしん | 佛教-観音が衆生済度のため姿を変えたという三十三体の称。 |
| 三十三天 | さんじゅうさんてん | ?利天(とうりてん)。六慾天の下から二番目の天。帝釈天がその中心に住み、周囲の四つの峰にそれぞれ八天がいる。「六慾天」は慾界に属する六種の天上界、四王天・?利天・夜摩天・兜率天・楽変化天・他化自在天の総称をいう。 |
| 三十四身 | さんじゅうししん | 妙音菩薩が衆生に経典を説き示すために化身したという34種の変化身の総称。 |
| 三従七去 | さんじゅうしちきょ | 儒教の倫理観。女子として則るべき、三つの規範と七つの婦徳をいう。七去は妻が夫の家を去るべき場合を規定したもの。父母に従順でない・子供がない・品行がみだら・ねたみ深い・悪い病気がある・お喋りである。盗みをする。の七つをいう。 |
| 三汁七菜 | さんじゅうしちさい | 贅沢で豪華な食事のたとえ。本膳料理。正式な日本料理の膳立ての菜数。「三汁」は汁物三品。「七菜」はおかず七品。本膳・二の膳・三の膳に焼き物膳と台引き物がつく。 |
| 三十而立 | さんじゅうじりつ | 三十歳になり、自分の確固とした立場をもって自立すること。 |
| 三十二相 | さんじゅうにそう | 仏のもつ三十二の優れた身体的特徴。女性の容貌・容姿に備わる美しさのすべて。 |
| 三秋之思 | さんしゅうのおもい | 1日会わないでいるとずいぶん長い間会わないでいるように思うこと。強く待ちこがれる気持ちをいう。(= 一日千秋) |
| 三十番神 | さんじゅうばんじん | 本地垂迹説により、日本天台宗と日連宗で、法華経を守護する神として月の三〇日に割り当てる三〇の神 |
| 三十六策 | さんじゅうろくさく | 古代中国の36の策略 |
| 三十六神 | さんじゅうろくしん | 仏道に志して三帰戒を受ける人を守護すると言われる36部の護法神王。三十六善神。 |
| 三十六鱗 | さんじゅうろくりん | 体側に三十六枚の鱗が並んでいることから「鯉」の異名・「六六魚」ともいう |
| 三十六禽 | さんじゅうろっきん | 一昼夜12時に夫々一獣を配し、更に1時に二つの属獣をつけた計36の鳥獣。三十六獣。 |
| 三十六計 | さんじゅうろっけい | 「三十六策走(にぐ)るはこれ上計なり」「三十六計逃ぐるに如(し)かず」を略したもので、古代中国の兵法で三十六の策略のうち、逃げるべきときは逃げて身の安全を計るのが最良の策だという意味。 |
| 三十六俵 | さんじゅうろっぴょう | 相撲の土俵。土俵は直径13尺で36の俵で作られたことから言う。 |
| 三十六峰 | さんじゅうろっぽう | 日本では小さな峰が多いため、京都東山のことを言う。 |
| 三旬九食 | さんじゅんきゅうしょく | 生活が極めて貧しいたとえ。一ヶ月に九回しか食事をとれない意から。「三旬」を「二旬」としても用いられる。子思が衛の国にいたとき生活が苦しく、表側の布のない衣服で、三十日間に九回しか食事をとることが出来なかった故事から。 |
| 三聖二師 | さんしょうにし | 天台宗の「伝教」「慈覚」「智証」の三大師と「安然和尚」と「慈慧大師」の二人をいう。 |
| 三職八科 | さんしょくはちか | 一八六七年の王政復古により新政府の要職として設置された総裁・議定・参与の総称と八つの科。のちに三職八局となりのち廃止された職制。 |
| 三事六府 | さんじろっぷ | 三事は世の中を治めるのに大切な「正徳」「利用」「厚生」を意味し六府は「水・火・金・木・土・穀」を表す。政治倫理。 |
| 三津七湊 | さんしんしちそう | 室町時代、日本最古の海商法である廻船法度に定められた十の大港。三津は伊勢の安濃津、筑前の博多津、和泉の堺津。七湊は能登の輪島、越前の三国、加賀の本吉、越中の岩瀬、越後の今町、出羽の秋田、津軽の十三湊。 |
| 三水四石 | さんすいしせき | 大阪天王寺の七不思議 |
| 三途大河 | さんずたいが | 仏教の三途の川には流れのちがう三つの瀬が冥途の途中にあり、人が死んで初七日に渡るが、 生前の行いによって渡る瀬が異なるといわれる。 |
| 三寸之轄 | さんずんのくさび | 車のくさびは、わずか三寸であるけれども、これがなければ車の用をしない。物事の主要なものをいう。 |
| 三寸不律 | さんずんふりつ | 筆。不律の「ふりつ」をつづめて発音すると「ひつ」で、三寸はその長さ。 |
| 三世一爨 | さんせいいっさん | 三世代の家族がなかよく同居すること。三代の家族が一つの竃(爨)で煮炊きする意から。《出典》新唐書「崔?伝」[類義語]三世同居・三世同財・三世同爨・三世同堂。中国・老舎、日本・三浦朱門に「四世同堂」の題名の書がある。 |
| 三世一身 | さんぜいっしん | 養老七年に公布された開墾奨励の法。新たに灌漑用水路を開発して開墾した者は本人から三代にわたってその土地の保有を許し、既存の用水を利用して開墾した者は本人一代かぎり保有を許した。 |
| 三尺童子 | さんせきのどうじ | 子供。三尺は小さいことの形容。また、一尺は二歳半で、七,八歳の子供。 |
| 三世十方 | さんぜじっぽう | 三世と十方。過去・現在・未来と、東・西・南・北・西北・西南・東北・東南・上・下の称。また、無限の時間と空間。 |
| 三戦三走 | さんせんさんそう | 三度戦って三度逃げる。 |
| 三千諸法 | さんぜんしょほう | 三千法ともあらゆるものの総称地獄から仏界の十界が円融の理で互いに他の十界を含むので百界等々これが宇宙の全ての存在と総摂するので三千法という(仏教用語) |
| 三千世界 | さんぜんせかい | 広い世界。全宇宙。 |
| 三千寵愛 | さんぜんのちょうあい | 多くの侍女に対する寵愛。 |
| 三草四木 | さんそうしぼく | 江戸時代、穀類以外に農家にとって重要な三種の草(麻・藍・紅花または木綿)と、四種の木(桑・茶・楮・漆)。その収穫は米や麦より有利であった。 |
| 三草二木 | さんそうにぼく | あらゆる草木がその大きさに関わらず平等に雨の惠を受けて育つように、資質・能力に差がある衆生も仏の教えによっていつかは平等に悟りを開くことが出来るということ。また仏のおしえは一つであるが、衆生の受け取り方はさまざまであることのたとえ。「三草」は三種の有用な草、「二木」は大樹・小樹のこと。《出典》法華経「薬草喩品」(やくそうゆほん) |
| 三多三上 | さんたさんじょう | 文章を作るのに適した三つの場所。「馬上」「枕上」「厠上」、乗馬をしているとき、寝床に入っているとき、便所にいるときをいう。[類義語]作文三上(サクブンサンジョウ)宋の欧陽脩の語。 |
| 三炭三露 | さんたんさんろ | 茶の湯で、三炭と、席入前・中立前・退席前に露地に打水をする三露とをいう。 |
| 三茶九茶 | さんちゃくちゃ | あばた顔(天然痘による顔)を京浜で「みっちゃくちゃ」といったところから出た言葉。 |
| 三長三本 | さんちょうさんぼん | 日蓮宗の寺でいづれも「長」と「本」のつく三つの寺をいう。長興山妙本寺(相模)長栄山本門寺(武蔵)長谷山本土寺(下総) |
| 三徴七辟 | さんちょうしちへき | 真心・礼儀をつくして、優れた人材を招くこと。また目上のものが、ある人物を信頼して手厚く迎えること。「三顧之礼」の類義語である。他に草蘆三顧(ソウロサンコ)《出典》諸葛亮「前出師表」(ぜんすいしのひょう) |
| 三町三所 | さんちょうみところ | 広い場所のうち、ただ三か所だけに事を行ってすます意。掃除などを粗略にすること。雑にてばやく仕上げてしまうこと。 |
| 三敵四友 | さんてきしゆう | 帝国主義・封建主義・官僚資本主義の三つの敵と、労働者・農民・小資産・民俗資産の四つの友、をいう中国名数辞典 |
| 参天弐地 | さんてんじち | 徳と天地を等しくすること。天地と同じほど大きな徳をもつこと。「参天」は天と交わる「弐地」は地に徳を比すこと、地と自分と天に並び合わせて「三」になることで「参天」という。《出典》文選「楊雄・劇秦美新」 |
| 三殿八役 | さんでんはちやく | 江戸時代、三卿(三殿ともいうが)の田安・清水・一橋に付けられた役職であり、八役は家老・番頭・用人・旗奉行・長柄奉行・物頭・郡奉行・勘定奉行をいう。 |
| 三島一連 | さんとういちれん | 作庭の形式、池の中に三つの島を置き、各々に三神山である、蓬莱・方丈・瀛州を表現するもの。中国伝説で渤海中にあって仙人が住むという三神山をかたどる方式をいう。 |
| 三同一交 | さんどういっこう | 幹部が大衆と一緒に食べ(同吃)、住み(同住)、労働(同働)して心を交じり合わせようとすること。 |
| 三当四落 | さんとうしらく | ナポレオンの故事にならって、三時間の睡眠ならば入試に合格できるが、四時間の睡眠では不合格になるといった、受験戦争での言葉。 |
| 三刀之夢 | さんとうのゆめ | 出世する吉兆の夢をいう。三刀は刕(州の古字)の隠語。晉の王濬が三刀にさらに一刀を益す夢を見たところ、後はたして益州の刺史(長官)となった故事。 |
| 三度三度 | さんどさんど | 食事に関して、一日の朝・昼・晩。 |
| 三途八難 | さんとはちなん | 三途は「地獄」「畜生」[餓鬼](途を道としたものが日本)と「鬱単越」「長寿天」「聾盲」「膏唖」「世智弁徳」を加えて八難という。 |
| 三人吉三 | さんにんきちざ | 歌舞伎「三人吉三廓初買・サンニンキチザクルワノハツカイ」の通称。世話物・河竹黙阿弥作。お坊吉三・和尚吉三・お嬢吉三の三人を主人公とし、百両の金と名刀庚申丸を巡る白浪物。白浪とは泥棒のこと。 |
| 三人五徳 | さんにんごとく | 火鉢に用いる三本足の五徳に似るところから三人が車座になること。三人いっしょに事を行うこと。 |
| 三人成虎 | さんにんせいこ | 「三人虎を成す」とも読む。町に虎がいるはずはないが、三人まで虎がいるというと、しまいにはこれを信じてしまう。誤った話も、多くの人が言えば真実と同じ力を持ってしまうという意味。 |
| 三人文殊 | さんにんもんじゅ | 凡人でも衆知を集めれば、いい考えも浮かぶということ。 |
| 三年之喪 | さんねんのも | 父母の喪。三年は足掛け三年で二十五か月。 |
| 三拝九叩 | さんはいきゅうこう | 中国清朝の敬礼の法。三度膝まずいて、九度頭を地につけて拝礼すること。「詭」はひざまずく「叩」はぬかずく。 |
| 三拝九拝 | さんぱいきゅうはい | 何度も頭を下げて人に敬意を表したり、物事を頼んだりすること。 |
| 三百諸侯 | さんびゃくしょこう | 全ての大名のこと |
| 三武一帝 | さんぶいってい | 道武帝(北魏)、武帝(北周)、武帝(唐)、世宗(後漢)が佛教を禁止し、僧尼を還俗せしめた四人の王子のことをいう。佛教では「三武一帝の法難」という。 |
| 三風十愆 | さんぷうじっけん | 巫・淫・乱の三つの悪風習とその内容を為す、恒舞・酣歌・貨・色・遊・等々の十の悪業。「愆」はあやまる・過失をおかすの意 |
| 三不三信 | さんぷさんしん | 「三心」とは浄土に生れようとする信心で真実にかなったもの。即ち「淳心・一心・相続心」をいう。「三不心」はこれに反する心をいう。 |
| 三分一銀 | さんぶいちぎん | 江戸時代、田畑の年貢の三分の一を銀に換算して納めた制度。主として関西地方で行われた。三分一銀納。 |
| 三分五厘 | さんぷんごりん | それほど値打ちのないことにいう。一分五厘。一銭五厘。 |
| 三分鼎足 | さんぶんていそく | 鼎に三本の足があるように、三者が天下を三分して並び立つこと。 |
| 三分之国 | さんぶんのくに | 後漢の末、魏の曹操、呉の孫権、蜀の劉備がそれぞれ天下を三分してその一つを保ったこと。 |
| 三分之計 | さんぶんのけい | 天下を三つの勢力に分けて、その一つを保つはかりごと。 |
| 三平ニ満 | さんぺいにまん | 三でも平安、ニでも満足の意から、心が平安で満足していること。また、額、鼻、顎の三つが平らで、両方の頬がふくらんでいる顔。おかめ。「二」はじとも読む。 |
| 三法三到 | さんぽうさんとう | 宋の米子の読書法。三法は少看熟読・反覆体験・没頭理会、三到は心到・眼到・口到。 |
| 三方四方 | さんぼうしほう | あちらこちらの方角。諸方。四方八方。 |
| 三木一草 | さんぼくいっそう | 建武中興に功のあった南朝方四忠臣の称。三木は名の一部に「き」のつく結城親光・伯耆守名和長年・楠木正成、一草は千種(ちぐさ)忠顕をいう。 |
| 三木三鳥 | さんぼくさんちょう | 「三木」は普通「をがたまの木」「めどのけずりばな」「かはなぐさ」をいい「三鳥」は「喚子鳥」「百千鳥」「稲負鳥」または「百千鳥」のかわりに「都鳥」 |
| 三百代言 | さんびゃくだいげん | もと、資格を持たない代議人(弁護士の元の呼び名)を軽蔑して呼んだ言い方。相手を言いくるめてしまうこと。 |
| 三方四方 | さんぼうしほう | あちらこちらの方角。諸方。四方八方。 |
| 三位一体 | さんみいったい | 三つのものが心を合わせて一つになること。別々の三つのものがしっかりと結びつくこと。三者が心を合わせること。 |
| 三面記事 | さんめんきじ | 昔の新聞は見開きの4ページになつており、3面に事件ものやスキャンダラスな記事を書いていたことに由来。 |
| 三面六臂 | さんめんろっぴ | 一人で何人分もはたらくこと。顔が3つでうでが6本ある仏像の形式をいう。多方面に活躍する意もあるが、悪い意味では何にでも手を出し、狡猾(こうかつ)に、動き回る人を例えていう場合もある。 |
| 三問三答 | さんもんさんとう | 鎌倉・室町時代の訴訟手続き。訴人の訴状に対して論人(被告)が陳状を提出することを三度繰り返してそれぞれの主張を述べること。 |
| 山河之固 | さんがのかため | 山河の要害が堅固なこと。 |
| 山窮水尽 | さんきゅうすいじん | 山も川も突き当りに来て、これ以上進めなくなる。進退に窮すること。「山窮(きり)まい水尽く」 |
| 山高水長 | さんこうすいちょう | |
| 山紫水明 | さんしすいめい | 山水(自然)の景色が清らかで美しいこと。日の光に照り映えて山は紫に流れる川は清らかに澄んで見えること。 |
| 山川草木 | さんせんそうもく | 自然の大地、自然の景色のこと。 |
| 山川万里 | さんせんばんり | 山を越え、川をへだててはるかに遠く相隔っている景観。「万里」は、はるかに遠いこと。 |
| 山中暦日 | さんちゅうれきじつ | 俗世間を脱して悠々自適にのどかな生活をするさま。「山中暦日無し」の略。山の中にこもって浮き世と交わらず、歳月の過ぎるのも忘れて静かに日を送ることをいう。 |
| 山容水態 | さんようすいたい | |
| 山林隠逸 | さんりんいんいつ | 官に仕えず山林に隠れ住む。また、その隠者。 |
| 山林之士 | さんりんのし | 才能を隠して山林に隠れ住む人。 |
| 散髪箕踞 | さんぱつききょ | ざんばら髪をし、足を投げ出して座る。隠者のさま。「散髪」は、冠をかぶらず髪をざんばらにする。床屋の意味ではない。そちらの方は「理髪」という。冠をかぶらないとは、仕官しないこと、つまり隠者の姿である。後漢書(ごかんじょ)袁広(えんこう)の伝記に「広は散髪して世と絶ち、迹(あと)を深林に投ず」(世間から離れて深林に身を隠す)と見える。「箕踞」は、農具の箕(み)のような形に足を投げ出すこと。礼儀に外れた座り方。「箕坐(きざ)」ともいう。 |
| 残虐非道 | ざんぎゃくひどう | 人の道にはずれた非常に悪い行いをすること。道徳に背いた残虐な行為。 |
| 残虐無道 | ざんぎゃくむどう | 人の道にはずれた非常に悪い行いをすること。道徳に背いた残虐な行為。 |
| 残酷無残 | ざんこくむざん | 人の道にはずれた非常に悪い行いをすること。道徳に背いた残虐な行為。 |
| 残酷非道 | ざんこくひどう | 人道に背いたむごたらしいさま |
| 残酷無比 | ざんこくむひ | 人の道にはずれた非常に悪い行いをすること。道徳に背いた残虐な行為。 |
| 残山剰水 | ざんざんじょうすい | 山水の眺めのつまらない景色。戦いに敗れて荒れ果てた景色。 |
| 残忍非道 | ざんにんひどう | 人の道にはずれた非常に悪い行いをすること。道徳に背いた残虐な行為。 |
| 残忍無道 | ざんにんむどう | 人の道にはずれた非常に悪い行いをすること。道徳に背いた残虐な行為。 |
| 残忍無比 | ざんにんむひ | 人の道にはずれた非常に悪い行いをすること。道徳に背いた残虐な行為。 |
| 斬新奇抜 | ざんしんきばつ | 極めて新しく、ふつうの人が思い付かないようなこと。思いもよらないこと。 |
| 散髪箕踞 | さんぱつききょ | |
| 賛否両論 | さんぴりょうろん | 賛成意見と反対意見が対立すること。 |
| シ | ||
| 四夷八蛮 | しいはちばん | 昔の中国で、四方八方の異民族をさげすんでいった語。転じて、四方八方の、帰順しない者。 |
| 四海一家 | しかいいっか | 真心と礼儀を尽して他者に交われば、世界中の人はみな兄弟のように仲良くなること、またそうすべきであること。「四海」は四方の海、転じて天下。世界中の意。 |
| 四海兄弟 | しかいけいてい | 世界中の人々は、すべて兄弟のように仲良く親しく交際・交流すべきだということ。 |
| 四海困窮 | しかいこんきゅう | 天下の人民が困ってしまう。 |
| 四海同胞 | しかいどうほう | 天下の人はみな兄弟のように分け隔てなく親しむべきだということ。 |
| 四角四面 | しかくしめん | 極めてまじめなこと。厳格なこと。堅苦しいこと。 |
| 四規七則 | しきななそく | 茶道、千利休が説いた茶のこころ。四規は「和」「敬」「静」「寂」、「和敬」は茶会において主客がもっぱらとすべき精神、「静寂」は茶室・茶庭・茶器など全般にそなわるべき精神をいう。 |
| 四苦八苦 | シクハック | 非常な苦しみ。さんざん悩み、苦労すること。(どうにもならなくなって)非常に苦しむこと。仏教では人間を悩ませる大きな苦しみの根元を、生・老・病・死の四苦といい、これに愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五陰盛苦の四苦を加えて八苦という。 |
| 四散五裂 | しさんごれつ | ちりぢりばらばらに分かれること。 |
| 四十不惑 | しじゅうふわく | 四十歳で人生に迷わなくなること。孔子は四十歳になったとき、自らの学問に対して自信を固め、道理も明らかになり、人生の問題に迷うことがなくなったという。 |
| 四書五経 | ししょごきょう | 儒学の重要な書物。四書は、「大学」「中庸」「論語」「孟子」のこと。五経は、「易経」「詩経」「書経」「春秋」「礼記」のこと。 |
| 四戦之地 | しせんのち | 山や川の険しいところがなく、四方から攻撃される土地。 |
| 四塞之地 | しそくのち | 四方がふさがっていて、攻めにくい地。 |
| 四鳥之別 | しちょうのわかれ | 親子の別れのこと、中国、桓山の鳥が四羽の子を産んだが、これらの子が育ち飛び立っていくとき、母鳥が悲しんで鳴いて送ったという故事から。 |
| 四通八達 | しつうはったつ | 往来の激しい賑やかな所をさす。いろいろな方面に道が通じていること。 |
| 四百四病 | しひゃくしびょう | 病気のすべて。 |
| 四百余州 | しひゃくよしゅう | 中国全体の称。 |
| 四分五裂 | シブンゴレツ | ちりぢりばらばらに分裂して秩序・統一を失い、乱れている様子。バラバラになること。いくつにも分裂し、秩序・統一がなくなること。 |
| 四方八方 | しほうはっぽう | あらゆる方向(方面)。 |
| 四方之志 | しほうのこころざし | 四方をめぐる志。四方を征伐しようとする志。諸国の記録。 |
| 四方之民 | しほうのたみ | 天下四方の民。国々の民。 |
| 四面楚歌 | シメンソカ | 四方がすべて敵に囲まれ孤立している状況]助けがなく、周囲が敵や反対者ばかりであること。敵の中ですっかり孤立すること。 |
| 四六時中 | しろくじちゅう | いつもの意。一日中。四六は24時間で一日中のこと。(昔は二六時中といった。) |
| 四六駢儷 | しろくべんれい | 漢文の文体。四字と六字から成る対句を多用する華麗な文体。誇大で華美な文辞を用い、典故のある語句を繁用し、平仄(ひようそく)を合わせて音調を整えるのが特徴で、朗誦に適する。漢・魏(ぎ)の時代に起こり、南北朝時代に盛んに行われた。四六駢儷文。 |
| 子々孫々 | ししそんそん | 孫や子供の末。子孫代々。 |
| 士魂商才 | しこんしょうさい | 武士の精神と商人の才能を兼ね備えていること。実業家のモラルとして言われる語。 |
| 士農工商 | しのうこうしょう | 昔、職業別の人民の四階級。 |
| 志士仁人 | ししじんじん | 国家・社会のために心を尽くす人や、仁徳のある人。 |
| 志操堅固 | しそうけんご | 何があっても志を堅くもって変えないこと。環境が変わっても強い意志を持って、気持ちが動かないこと。「志操」は、堅く守っている志やみさお、主義のこと。 |
| 市井之臣 | しせいのしん | 城下の人民。官につかない都の住人。 |
| 市井之人 | しせいのひと | 町に住む庶民。 |
| 市井無頼 | しせいのぶらい | 町のならず者。 |
| 市道之交 | しどうのまじわり | 商売上の付き合い。利欲によって結ぶ付き合い。 |
| 至公至平 | しこうしへい | 少しも片寄らず、非常に公平である。 |
| 至上命令 | しじょうめいれい | 絶対に服従しなければならない命令。他のすべてに優先して行わなければならない事柄。 |
| 至聖先師 | しせいせんし | 明代に贈られた孔子の尊号。 |
| 至誠奉公 | しせいほうこう | 真心を込めて、国家や社会のために尽くす。 |
| 至誠憂国 | しせいゆうこく | 真心をもって国のためを思う。 |
| 至大至剛 | しだいしごう | 非常に大きく、非常に強い。 |
| 死屍累累 | ししるいるい | 沢山の屍が重なり合っている様子。 |
| 死生契闊 | しせいけいかつ | 死生を共にしようと約束し、共に努力し、共に苦しむこと。 |
| 死生之際 | しせいのさい | 生死のさかい目。 |
| 死節之臣 | しせつのしん | 命を捨てて、操を守る家臣。 |
| 死中求活 | しちゅうきゅうかつ | どうにもならない中で、活路を求めること。 |
| 死灰復燃 | しはいふくねん | 消えた火が再び燃え始めるという意から、いったん勢いを失ったものが再び盛んになること。また、一度おさまったことが再び問題になること。 |
| 私利私欲 | しりしよく | 自分の利益だけを考えた欲望。 |
| 師資相承 | ししそうしょう | 師弟の間でうけつぐこと。 |
| 支分節解 | しぶんせっかい | 書物などの内容を、部分部分に分けほどいて、詳しく調べる。 |
| 支離滅裂 | しりめつれつ | 筋道が立たずてんでんばらばらでまとまりがないさま。また、はなればなれになること。 |
| 思案投首 | しあんなげくび | しきりに思案して首を傾けること。名案がなくて困っていること。 |
| 思慮分別 | しりょふんべつ | よく考えて判断すること。普通人生経験もあり、常識的で道理にもとづいた考え方のできる人や、そういう大人の考えをいう。 |
| 資弁捷疾 | しべんしょうしつ | 弁舌が人にすぐれてはやく、また、気がきくこと。 |
| 枝葉末節 | しようまっせつ | 本質から外れた些細な部分、主要でない物事のたとえ。 |
| 試行錯誤 | しこうさくご | 試みと失敗を繰り返しながら解決策を見いだしていくこと。困難な課題を成し遂げるためにあれこれと試み、失敗を繰り返しながら目的に向かっていくこと。 |
| 詩歌管弦 | しいかかんげん | 漢詩や和歌、管楽器と弦楽器のこと。 |
| 詩的情緒 | してきじょうちょ | 詩の感興を強く引き起こすような感情。 |
| 指腹之約 | しふくのやく | まだ腹中にいる胎児を指差して結婚の約束をすること。後漢の光武帝が賈復の妻が妊娠したと聞き、その生まれてくる子をわが子と結婚させようと言った故事。 |
| 芝蘭之化 | しらんのか | 美しい徳の感化。友人から受けるよい感化。 |
| 芝蘭之室 | しらんのしつ | 香草を入れてある部屋。 |
| 紫翠蒙密 | しすいもうみつ | 紫や濃い緑がこまかに立ち込める山の景色。 |
| 紫電一閃 | しでんいっせん | 研ぎ澄まされた刀の一瞬のひらめき。 |
| 獅子身中 | しししんちゅう | 味方でありながら害をなす、身内の敵。 |
| 獅子奮迅 | シシフンジン | 獅子が奮い立って激しく進む意から、物事に対処する際の意気込み、勢いがすさまじく強いことのたとえ。勢いが盛んで勇ましく動き回ること。獅子のように奮い立ち、素早く動く意。 |
| 屍山血河 | しざんけつが | 死体が山のように積み重なり、血が河のように流れること。激しい戦闘のたとえ。 |
| 只管打座 | しかんだざ | 禅宗で、ただひたすらに座禅することをいう。 |
| 孜孜汲汲 | ししきゅうきゅう | せっせと励むさま。 |
| 揣摩憶測 | しまおくそく | 根拠もなく自分勝手にあれこれ推量すること。「揣摩」は、自分の心で他人を推し量ること。「憶測」は「臆測」ともかく。 |
| 鴟目虎吻 | しもくこふん | ふくろうの目つきと虎の口もと。ともに、残忍でむさぼりあきない表情。 |
| 舐犢之愛 | しとくのあい | 子供を溺愛すること。 |
| 尸位素餐 | しいそさん | 高位の者がなにもせずに高給をとること。 |
| 咫尺千里 | しせきせんり | 考えようによっては、短い距離も千里の遠さに感じられることのたとえ。 |
| 咫尺之地 | しせきのち | しせきのち |
| 泗上弟子 | しじょうのていし | 孔子の門人。孔子が泗水のほとりで弟子に教えたことから。 |
| 自家撞着 | じかどうちゃく | 自分の言うことが前後で食い違うこと。自己矛盾。 |
| 自家薬籠 | じかやくろう | 自分が自由に使えるものの意。「薬籠」は、薬箱。自分の薬箱の中にある薬のように、思うとおりに利用できるもの。また、すっかり身に付いた技術をいう。 |
| 自画自賛 | ジガジサン | 自分の描いた絵に自分で賛(絵画に書き加える詩や文)をすることから、自分で自分のしたことを褒めること。自分で自分のしたことをほめること。自分の描いた絵に自分で賛すること。 |
| 自給自足 | じきゅうじそく | 自分に必要なものを他から求めずに、すべて自らの手で作り出し、まかなうこと。自分(の国)に必要な物資は、自分(の国)で間に合わせること。 |
| 自己欺瞞 | じこぎまん | 自分で自分をあざむき、だますこと。 |
| 自己啓発 | じこけいはつ | 自分自身を開発し向上させていくこと。類:自己研鑽。 |
| 自己嫌悪 | じこけんお | 自分がいやになること。自分で自分にいやけがさすこと。 |
| 自己顕示 | じこけんじ | 自分の才能・力・実績をことさら他人にみせびらかすこと。「顕示」は、はっきりとしめすこと。謙虚さをともなわない場合が多い。 |
| 自己撞着 | じこどうちゃく | 自分の中で矛盾することをいう。同じ人の発言や文章などが前後で一致せず、つじつまがあわないこと。 |
| 自業自得 | ジゴウジトク じごうじとく |
自分がなした悪事のために、自分の身にその報いを受けること。自分がしたことの報いは、必ず自分自身が受けるという教え。自分のやった悪事のために自分が報いをうけること。 |
| 自作自演 | じさくじえん | 自分でつくった通りに自分で演じること。 |
| 自主独立 | じしゆどくりつ | 独力で行うこと。自分の力で、自分の意志で、自分の責任において物事を成していくこと。 |
| 自助努力 | じじょどりょく | 他人を頼らず自分の力でやっていくこと。 |
| 自縄自縛 | ジジョウジバク | 自分の縄で自分を縛ること。自分自身の心がけや行動によって、動きがとれなくなり、苦しむことのたとえ。自分の言葉や行動のためにかえって自分が苦しくなること。もともとは、進退きわまり、降伏の表現として自分の体を縛り許しを請うこと。 |
| 自信満満 | じしんまんまん | 自信に満ち溢れたさま。 |
| 自責内訟 | じせきないしょう | 自分で自分の言行を責めとがめる。 |
| 自然淘汰 | シゼントウタ | 生物は周囲の状態に適したもののみが生存して子孫を残し、そうでないものは子孫を残さずに滅びるということ。適切なものだけが自然に選択されること。自然の環境に適応できるものは生き残りそうでないものは死滅する現象。淘汰は、洗い分けるの意。 |
| 自然之理 | しぜんのり | 天地自然のことわり。道理。 |
| 自然法爾 | じねんほうに | 仏語。もののありのままの姿が真理にのっとっていること。浄土真宗で、阿弥陀仏の本願のはからいの中に包まれていること。 |
| 自重自戒 | じちょうじかい | 自ら行動を慎み、自らを戒めること。 |
| 自暴自棄 | じぼうじき | 自分の思い通りにならないでやけくそになって理性をなくし、なげやりな気持ちになること。「自暴」は、自分の身を損なうまでにめちゃめちゃな行動をとること。自分で自分の身を持ちくずすこと。やけのやんぱち。 |
| 自問自答 | じもんじとう | 自分の心の中で問答すること。 |
| 自由闊達 | じゆうかったつ | 心が広く、物事にこだわらないさま。明るくて思いのままのびのびしていること。人の言動を受け入れる大きな度量のある場合などに言う。 |
| 自由自在 | じゆうじざい | 自分の思いのままに出来るさま。思う存分ふるまうさま。「自由」も「自在」も、自分の心のままと言うこと。 |
| 自由平等 | じゆうびょうどう | 法律の範囲内で、一様に自由な行動をする権利があること。 |
| 自由放任 | じゆうほうにん | 各人の思いのままに任せて、干渉・束縛・統制などをしないこと。「子供の―はよくない」。 |
| 自由奔放 | じゆうほんぽう | 思いのまま自由勝手にふるまうこと。世間の慣習やおもわくなどいっさい気にせず、束縛されずにやりたいことをやるさま。他人の迷惑など気にせず、やりたい放題にふるまうことにも言う。 |
| 自由無礙 | じゆうむげ | 自由に何ものにもとらわれないこと。 |
| 自立自存 | じりつじそん | ひとり立ちすること。他人の力を借りず、自分の力だけでいきること。「自存」は、自分の力だけで存在すること。 |
| 時雨之化 | じうのか | 時雨とは日本でいう秋のしぐれのこと。ほどよいときに降る雨が草木の成長を助けるように、 師の教えが適格に行われると、学ぶ弟子との信頼関係がより緊密になるという意。 |
| 時期尚早 | じきしょうそう | まだその時期になっていないこと。時期が早すぎること。焦っている人を説得し、落ち着かせるときに使うことが多い。社会全体の情勢などを考慮し、機会がくるのを待ってからやるべきだと教えるときに使われる。 |
| 時機到来 | じきとうらい | しおどきの意。 |
| 時々刻々 | じじこっこく | 時刻を追って。しだいしだいに。 |
| 時羞之奠 | じしゅうのてん | その時節の食物を神前に供える。また、その供え物。 |
| 時節到来 | じせつとうらい | 好機が訪れること。 |
| 時代考証 | じだいこうしょう | 文献を調べてその時代のことを明らかにすること。 |
| 時代錯誤 | ジダイサクゴ | 時代おくれ。時代の流れに合わない物事の考え方。特に時代に遅れた古い考えや行動を言う。昔の考えで今の世の中を生きていこうとする誤ったやり方。 |
| 時代寵児 | じだいのちょうじ | その時代に合うような成功をして、世間の人々からもてはやされる人。 |
| 耳提面命 | じていめんめい | 顔と顔を突き合わせて、懇切丁寧に教えること。 |
| 耳目之官 | じもくのかん | 天子の耳目となって国家の治安を保護する官。御史大夫をいう。耳や目の働き。官は司。 |
| 耳目之欲 | じもくのよく | 耳に聞き、目に見ることによって生じる欲望。諸種の欲望。感覚的欲望。 |
| 耳目肺腸 | じもくはいちょう | 耳と目と肺と腸。からだのすべて。 |
| 事実無根 | じじつむこん | 事実だという根拠が全くないこと。 |
| 事事物物 | じじぶつぶつ | すべての物事。あらゆること。 |
| 事上磨錬 | じじょうまれん | 実際のことにあたって心を磨くこと。王陽明の説。 |
| 事大主義 | じだいしゅぎ | 自分のしっかりした考えを持たず、権力のあるものに従って自己の安全を図る態度。「事大」は、強大なものにつかえること。 |
| 事半功倍 | じはんこうばい | 「事半ばにして功倍す」とも読む。わずかの努力で多大の効果をあげる。 |
| 児女之債 | じじょのさい | 子供の教育、結婚の費用などのように免れない費用。 |
| 辞理明暢 | じりめいちょう | 言葉の筋道が明らかでよくとおること。文意が明らかで通達する。 |
| 慈悲心鳥 | じひしんちょう | じゅういちの別名。カッコウ目カッコウ科。鳩より少し小さい渡り鳥。 |
| 慈悲忍辱 | じひにんにく | いつくしみぶかいことと恥を忍ぶこと。僧が必ず守るべき道。 |
| 慈母敗子 | じぼはいし | 過保護の母親は子供をだめにしてしまうこと。子を甘やかすことを戒める語。 |
| 而今而後 | じこんじご | 今からのち。今後。 |
| 爾汝之交 | じじょのまじわり | 互いに「おまえ」などと呼び合うような、親密な交際。「爾汝」は、相手を軽んずるか、または、親しみをもって呼び捨てににすること。 |
| 色即是空 | しきそくぜくう | 万物はいろいろの形を備えているが、すべては現象であって、永劫不変の実体などというものはなく、本質は空である。この世にあるいっさいの物の本質は空(くう)だということ。 |
| 舌先三寸 | したさきさんずん | 口先だけの巧みさで、人をだますこと。 |
| 七花八裂 | しちかはちれつ | 花びらが細かく分かれているように、バラバラにちぎれる様子。 |
| 七擒七縦 | しちきんしちしょう | 七回捕らえ七回放免すること。いとも簡単に捕らえるという意味。諸葛亮が孟獲を七回捕らえ七回放免したことに基づく言葉。 |
| 七言絶句 | しちごんぜっく | 漢詩で、七言の句が四句からなる近体詩。七絶。 |
| 七言律詩 | しちごんりっし | 漢詩で、七言の句が八句からなる近体詩。七言律。七律。 |
| 七十古稀 | しちじゅうこき | 七十歳まで生きる人は少ないと言うこと。唐の詩人杜甫のことば。「人生七十古来稀(ま)れなり」から。「古稀」のみで、七十歳の意に用いられる。 |
| 七縦七擒 | しちしょうしちきん | 敵を七度逃がして七度捕らえる。相手を自分の思いのままにする。諸葛孔明が孟獲をとりこにした故事。 |
| 七転八起 | しちてんはっき | 何度失敗してもあきらめないこと。七たび転んで八たび起きることから。度重なる失敗にくじけず、そのたびに勇気を出して立ち上がること。転じて、人生の浮き沈みの激しいことの例え。 |
| 七転八倒 | シチテンバットウ | 何度も何度も倒れるように、苦痛のために激しく苦しみ悶えるさま。何度も転び倒れること。のたうち回って苦しむこと。 |
| 七堂伽藍 | しちどうがらん | 寺院の堂宇の規模で、型どおりに七つの建物が完備しているもの。古くはふつう塔・金堂・講堂・鐘楼・経蔵・僧房・食堂(じきどう)をいうが、後に宗派によって異なり、中堂・金堂・東金堂・西金堂・南円堂・北円堂・講堂、または三門・仏殿・法堂(はつとう)・僧堂・庫裏(くり)・浴堂・西浄(便所)などをいう。 |
| 七歩之才 | しちほのさい | 詩才に恵まれていること。 |
| 七難八苦 | しちなんはっく | いろいろな災害・苦しみのこと。人間のうけるさまざまな苦難。「七難」は、七種類の災難のことで、流行病・外国の侵略・内乱・風水害・火災・霜害・日月食などを指す。「八苦」については、「四苦八苦」参照のこと。 |
| 七里結界 | しちりけっかい | 七里四方に境を作って、仏道のじゃまものを防ぐこと。 |
| 七珍万宝 | しっちんまんぽう | 様々な種類の宝物のこと。 |
| 叱咤激励 | しったげきれい | 激しく強い言葉や大声で人を励まして奮い立たせること。 |
| 疾言遽色 | しつげんきょしょく | 落ち着かない様子。早口でものを言い、あわてた顔つきをするの意味。 |
| 疾風勁草 | しっぷうけいそう | 疾風に遭うと強い草がわかる。 |
| 疾風迅雷 | しっぷうじんらい | 事態の急変や敏速な行動。強く吹く風と激しい雷の意が転じて。強い軍勢の攻撃の形容に使われる。 |
| 疾風怒濤 | しっぷうどとう | 時代や社会がめまぐるしく変化し、国家の形勢が大きく転換する時代を形容して言う。強い風と逆巻く荒波の様子。 |
| 質実剛健 | しつじつごうけん | 飾り気がなくまじめで、体も丈夫なこと。 |
| 質素倹約 | しっそけんやく | 「飾り気がなく、慎ましく暮らすこと」。日常会話では、余計なものを買わず、節約している時などによく使われる。 |
| 失意泰然 | しついたいぜん | 悪い局面で失敗や挫折があってもゆったりと落ち着いていなければならない。 |
| 失地回復 | しっちかいふく | 失った勢力範囲を取り戻すこと。 |
| 執行猶予 | しっこうゆうよ | 執行猶予とは、有罪ではあるが、その刑の執行が一定期間先送りされる制度をいう。実刑判決は、判決後すぐに刑に服する必要があるのに対し、執行猶予付き判決の場合は、判決後すぐに刑に服する必要はない。さらに、執行猶予期間内に犯罪を起こし執行猶予が取り消されることなく過ごすことができれば、基本的には刑が免除されることになる。実刑判決が下されるか、執行猶予付き判決が下されるかは、被告人にとっては大きな違いがある。執行猶予が付く条件や執行猶予が取りけられ刑に服さなければならなくなってしまう条件などを知っておきましょう。 |
| 執鞭之士 | しつべんのし | 御者。むちをとって貴人の先触れとなる者。転じて、卑しいことに従う身分の低いもの。 |
| 膝癢掻背 | しつようそうはい | 膝がかゆいのに背中をかく。議論などが道理に合わないことのたとえ。 |
| 櫛風沐雨 | しっぷうもくう | 風雨にさらされながら、苦労して働くこと。また、世の中のさまざまな辛苦にさらされることのたとえ。▽「櫛風」は風に髪が櫛くしけずられること。「沐雨」は雨で髪が洗われること。 |
| 実事求是 | じつじきゅうぜ | 事実に基づいて、物事の真相・真理を求めたずねる。清朝の学風。 |
| 実践躬行 | じっせんきゅうこう | 身をもって実際に行うこと。口先だけではいけない、まず行動せよの意。理論や信条を自ら進んで行為にあらわしていくこと。 |
| 実力行使 | じつりょくこうし | 行政側が権力で目的を達しようとするもの。 |
| 実力伯仲 | じつりょくはくちゅう | 互いの力が接近して優劣の差がないこと。 |
| 十死一生 | じっしいっしょう | 生きる見こみがほとんどないこと。 |
| 十室之邑 | じっしつのゆう | 家が十戸ある小さい村。 |
| 十中八九 | じっちゅうはっく | 十の内、八か九まで。→ほとんど。 |
| 十把一絡 | じっぱひとからげ | いろいろな種類のものを無差別に一まとめにすること。よい悪いの区別をしないで、何もかもいっしょくたに扱うこと。また、数は多くても価値のないこと。 |
| 十杯機嫌 | じっぱいきげん | 酒を飲んでよい機嫌であること。また、そのさま。 |
| 十方世界 | じっぽうせかい | 東・西・南・北・東南・西南・東北・西北・上・下をいう。全世界のこと。 |
| 十歩之内 | じっぽのうち | わずかな距離。 |
| 徙木之信 | しぼくのしん | 政治を行うものは人民を欺かないの意味。戦国時代末、秦の商鞅が法令の改正を行うにあたって国都の市の南門に三丈の木を立て、これを北門に移す者には十金を与えるとふれ、さらに五十金に増額したところ、申し出て三丈の木を移した者があったので、約束どおりその者に五十金を与えて、政府の法令の信頼すべきことを示した故事。 |
| 駟不及舌 | しふきゅうぜつ しもしたにおよばず |
一度口から出た言葉は、四頭の馬車で追いかけても、もはや追いつくことができないから、口は慎むべきものだという教訓。 |
| 社交辞令 | しゃこうじれい | 世間づきあいの挨拶。つきあいのためにいう誉めことば。 |
| 社稷之器 | しゃしょくのき | 国政に任じうる器量・人物 |
| 社稷之臣 | しゃしょくのしん | 国家の大任を引き受ける大臣。国家の重臣。 |
| 車載斗量 | しゃさいとりょう | 車にのせ、一斗ますで量るの意味。物が非常におおくあることのたとえ。平凡な物が数多くあることの形容。 |
| 車轍馬跡 | しゃてつばせき | 車のわだちと馬の足跡。車馬に乗って天下を巡遊すること。 |
| 遮二無二 | しゃにむに | 前後の見境なく、強引に行なうこと。 |
| 奢侈淫佚 | しゃしいんいつ | 贅沢な暮らしにふけり、不道徳的でしまりのない行いを楽しむこと。「奢侈」は、おごる意で、必要以上のまたは分限を越えた生活をすること。「淫佚」は「淫逸」とも書き、男女間のみだらなこと、遊興にふける意。 |
| 奢侈淫靡 | しゃしいんび | 身分以上のおごり。おごって淫らなこと。 |
| 洒洒落落 | しゃしゃらくらく | 性格や態度、言動などがさっぱりしていて、こだわりのない様子。 |
| 杓子果報 | しゃくしかほう | 食物をたくさん配分してもらうこと。おいしい食べ物にたくさんありつける好運。転じて、好運に恵まれること。 |
| 杓子定規 | しゃくしじょうぎ |
すべてに一つの基準や感覚を当てはめて判断・処理しようとする応用や融通の利かないやり方。態度。型にはまって融通のきかないこと。また、正しくない基準のこと。「杓子」は飯、または汁などの食事をすくい取る用具で、しゃもじのこと。杓子のように曲がって正しくない定規のことから。 |
| 弱肉強食 | じゃくにくきょうしょく | 弱者が強者に征服されること。弱いものは強いものに征服される理。 |
| 寂光浄土 | じゃっこうじょうど | 仏の住んでいる所。 |
| 寂滅為楽 | じゃくめついらく | 生死を超越し、煩悩から解放されて初めて、真の安楽が得られるということ。 |
| 主客転倒 | しゅかくてんとう | ものごとの軽重が、いれかわること。 |
| 主義主張 | しゅぎしゅちょう | 各人の持つポリシ-。常に守って変えない一定の考え・方針・思想上の立場。 |
| 首施両端 | しゅしりょうたん | どちらにもつかずに、二心を抱くこと。また、はきはき事を決めずに、ぐずぐずすること。 |
| 首善之地 | しゅぜんのち | 京師(みやこ)のことをいう。「漢書」儒林伝に「故教化之行也、建首善、自京師始」とある。 |
| 首鼠両端 | しゅそりょうたん | どっちつかず。形勢をうかがっているあいまいな態度のたとえ。日和見。 |
| 首尾一貫 | しゅびいっかん | 始めから終わりまで同じ方針や態度で通すこと。始めと終わりで矛盾しないこと。「首尾」は、始めと終わり。また、ことの顛末や結果のこと。 |
| 取捨選択 | しゅしゃせんたく | 多くのものの中から、よりよいもの、必要なものを選び取り、他は捨て去ること。「取捨」は、採否とおなじ。「択」は、一列に並べ、あるいは順次に引き出し、適当なものを選び出すこと。 |
| 朱唇皓歯 | しゅしんこうし | 赤い唇と白い歯並み。美人の形容。 |
| 朱頓之門 | しゅとんのもん | 金持の家。 |
| 守株待兎 | しゅしゅたいと | いたずらに古い習慣やしきたりにとらわれて、融通がきかないたとえ。また、偶然の幸運をあてにする愚かさのたとえ。木の切り株を見守って兎うさぎを待つ意から。 |
| 守秘義務 | しゅひぎむ | 職務上で知った秘密を守るべき務めのこと。 |
| 種種雑多 | しゅじゅざった | いろんなものが、雑然と入り混じっている様。 |
| 衆生済度 | しゅじょうさいど | 人々に悩みを救い、悟りを得させること。「衆生」は、人間を含む生のあるもの。「済度」は、救済し解脱させること。 |
| 衆議一決 | しゅうぎいっけつ | おおぜいの議論、相談の結果、意見が一致し結論が出ること。 |
| 衆人環視 | しゅうじんかんし | 大勢の人が周りを取り囲んでみていること。 |
| 首鼠両端 | しゅそりょうたん | ぐずぐずして、どちらか一方に決めかねているたとえ。また、形勢をうかがい、心を決めかねているたとえ。日和見ひよりみ。穴から首だけ出したねずみが外をうかがって、両側をきょろきょろ見回している意から。▽「首鼠」は「首施しゅし」に同じで、躊躇ちゅうちょするさまともいう。「両端」はふた心の意。 |
| 酒嚢飯袋 | しゅのうはんたい | 大酒を飲み、飯を腹一杯食うだけで何の役にも立たない人のことをあざけって言う。 |
| 酒池肉林 | しゅちにくりん | 豪奢(ごうしゃ)な酒宴の意。豪遊の限りをつくすこと。殷の紂王(ちゅうおう)が酒をためて池を作り、肉を木の枝にかけて林のようにして酒宴をおこなったという故事。紂王のぜいたくを極めた酒宴、放逸な生活ぶりをいった。みだらな酒宴の場合などにもいう。 |
| 趣味嗜好 | しゅみしこう | 個人的な好み、楽しみ、たしなみなどのこと。 |
| 株連蔓引 | しゅれんまんいん | 株を連ね、つるを引っ張るように、手づるによって、残らず関係者を罰すること。 |
| 殊塗同帰 | しゅとどうき | 行く道は異なるが、落ち着くところは同一である。始めは違っても終わりは同じ。 |
| 銖積寸累 | しゅせきすんるい | 銖をつみ、寸をかさねる。わずかな物も積もれば、大きくなる。塵も積もれば山となる。 |
| 銖両之姦 | しゅりょうのかん | ささいな悪事。 |
| 受命之君 | じゅめいのきみ | 天命を受けて天子となった人。 |
| 寿山福海 | じゅざんふくかい | 人の長寿を祝う言葉。 |
| 樹下石上 | じゅかせきじょう | 野山や道端に寝泊まりすることのたとえ。 |
| 秀外恵中 | しゅうがいけいちゅう | 外見が立派で頭脳も優秀である。容貌がよくて頭がよい。 |
| 囚首喪面 | しゅうしゅそうめん | 顔かたちを飾らないこと。囚人のように頭髪に櫛を入れず、喪のときのように顔を洗わない。 |
| 舟中敵国 | しゅうちゅうてっこく | 味方の中にも敵がいることのたとえ。 |
| 秋霜烈日 | しゅうそうれつじつ | きわめて厳しいこと。刑罰がひどく厳しかったり、権威などがきわめて強固だったりすることのたとえ。(秋の霜や夏の激しい日光のように) |
| 秋風索莫 | しゅうふうさくばく | 夏が過ぎて秋風が吹くと自然界が衰えを見せ、ものさみしい光景に様変わりすること。盛んだったものが衰えてものさみしくなるさま。 |
| 周章狼狽 | しゅうしょうろうばい | うろたえ騒ぐこと。あわてふためくこと。「周章」も「狼狽」も、うろたえあわてるの意。 |
| 終始一貫 | しゅうしいっかん | 始めから終わりまで行動や態度などが変わらないこと。周囲の情勢や変化に影響されることなく、主義主張を持ち続ける場合にも用いる。「一貫」は、一つの態度や方法などを始めから終わりまで一筋に突き通すこと。 |
| 終食之間 | しゅうしょくのかん | わずかな間。食事を済ますわずかな時間の意味。 |
| 終身之計 | しゅうしんのけい | 一生涯のために立てるはかりごと。自分の一生を安全に暮らすはかりごと。 |
| 修身斉家 | しゅうしんせいか | |
| 執熱不濯 | しゅうねつふたく | 「執」は物をしっかりと握ること、熱いものはつかんで洗うことができぬから、まず水を入れ冷やしてから洗う。 「熱を執りて濯はず」という。転じて困難を救うには賢人を用うべきであるのに、それをしようとせぬことのたとえ。 |
| 洲渚歴落 | しゅうしょれきらく | 砂のなぎさが出たりかくれたりしていること。 |
| 羞悪之心 | しゅうおのこころ | 自分の不善を恥じ、他人の不善を憎む心。 |
| 羞花閉月 | しゅうかへいげつ | 花も恥じらい、月も隠れる。美人の容姿のすぐれて麗しい形容。 |
| 羞月閉花 | しゅうげつへいか | 美しい容姿に対して月もはじらい、花も閉じてしまう意。容姿の美しい女性を形容する語。 |
| 羞渋疑阻 | しゅうじゅうぎそ | 心に恥じてためらう。恥じためらい、断行できないこと。 |
| 袖手傍観 | しゅうしゅぼうかん | 手出しをしないで成り行きにまかせ、ただ見守っていること。 |
| 聚斂之臣 | しゅうれんのしん | 地位を利用し、上の権力をかさに来て人民を厳しく責め、租税または財貨をむさぼり取る臣。 |
| 十五志学 | じゅうごしがく | 十五歳で学問に志すこと。晩年の孔子が自分の人生を振り返って述べた一説より。孔子は十五歳になったとき、学問を志した。「志学」のみで、十五歳の意にも用いる。 |
| 十字砲火 | じゅうじほうか | 左右から交差して発射する砲弾。 |
| 十人十色 | じゅうにんといろ | 人それぞれの考え方や好みには違いがあるということ。人の考え方や好みは十人いれば十人とも違っているということ。 |
| 十年一日 | じゅうねんいちじつ | 長い間同じことを繰り返していること。 |
| 十年一剣 | じゅうねんいっけん | 永年かけて武を練り機会を狙うこと 。 |
| 十年一昔 | じゅうねんひとむかし | 十年を一区切りにすると人の心も世の中も変化する。 |
| 十八史略 | じゅうはっしりゃく | 中国の歴史読本。元の曾先之(そうせんし)撰。史記から新五代史までの一七正史に宋史を加えた一八史を取捨選択して編纂した入門書。日本には室町中期に伝来。 |
| 十万億土 | じゅうまんおくど | 死んだ人が行くといわれている非常に遠いところ。極楽浄土。 |
| 十羊九牧 | じゅうようきゅうぼく | |
| 十風五雨 | じゅっぷうごう | 十日に一度風が吹き、五日に一度雨が降る、順調な天候のこと。 |
| 重厚長大 | じゅうこうちょうだい | どっしりとして大きい様。 |
| 重箱日和 | じゅうばこひより | 雨が降ったりやんだりして、一向に天気が定まらぬこと。九州地方のことわざといわれる。 |
| 縦横自在 | ||
| 縦横無碍 | じゅうおうむげ | 自由自在で何の滞りもないさま。どちらにも差し障りのないこと。 |
| 縦横無尽 | じゅうおうむじん | 思う存分、自在にふるまうこと。この上なく自由自在であること。本来の「限りがない」という意から転じて、自由自在に四方八方(縦横)へ、力が及ぶさまを言う。また、そこかしこと走り回るさま。 |
| 縦説横説 | じゅうせつおうせつ | 思うまま、勝手な議論をする。 |
| 縦塗横抹 | じゅうとおうまつ | 縦横に書いたり消したりすること。書きなぐること。 |
| 縦覧謝絶 | じゅうらんしゃぜつ | 勝手気ままに出入りして見回ることはお断り。 |
| 獣蹄鳥跡 | じゅうていちょうせき | 世の中が乱れ、鶏や獣の足跡が天下に満ちること。 |
| 什佰之器 | じゅうひゃくのき | 普通の人に十倍、百倍する器量。 |
| 宿契之限 | しゅっけいのかぎり | 前世の定めどおり。 |
| 縮衣節食 | しゅくいせっしょく | 節約すること。 |
| 縮地補天 | しゅくちほてん | 地をちぢめ、天をおぎなうの意味。天子が、天下の行政機構などを大改革すること。 |
| 縮頸駭汗 | しゅっけいがいかん | 首をちぢめ、恐れ驚いて冷や汗が出る。 |
| 菽水之歓 | しゅくすいのかん | 豆を食い水を飲み貧しく暮らしながら親を喜ばせる。貧苦にめげず親に孝養をを尽くすこと。 |
| 熟読玩味 | じゅくどくがんみ | 詩文や物事の意味・道理などをよく考え味わうこと。文章をていねいに読み、意味、内容を深く味わうこと。 |
| 熟慮断行 | じゅくりょだんこう | 「熟慮」は、よくよく考えること。思いめぐらすこと。「断行」は、思い切ってすること。 |
| 出谷遷喬 | しゅっこくせんきょう | 春、鳥が谷間から出て高い木に移るように、人が出世すること。 |
| 出将入相 | しゅっしょうにゅうしょう | 文と武を兼ね備えて、戦いに出ては大将として兵を指揮し、平時は大臣として政治をとる。 |
| 出処進退 | しゅっしょしんたい | 事にあたっての身の振り方。宮に使えるか民間に退くか、現在の職、地位にとどまるか、辞職するか、などの選択を迫られた場合に用いる。今の役職・地位にとどまるか、それをやめて退くか、という身の処し方をいう。 |
| 出藍之誉 | しゅつらんのほまれ | 教えを受けた弟子が先生よりもすぐれた人になるたとえ。青色の染料は藍という草の葉から取ったものだが、もとの藍の葉よりも美しい色をしていることから。 |
| 出離生死 | しゅつりしょうじ | 仏語。悟りを開いて、生死の苦海から脱すること。涅槃(ねはん)の境地に入ること。 |
| 春蚓秋蛇 | しゅんいんしゅうだ | 書の字体が細くうねリ曲がってつたないこと。 |
| 春花秋月 | しゅんかしゅうげつ | 自然の美しい景色。風流。 |
| 春華秋実 | しゅんかしゅうじつ | 春の花と秋の果実。 |
| 春日遅遅 | しゅんじつちち | 春に日は長くて暮れるのが遅いこと。 |
| 春風化雨 | しゅんぷうかう | おだやかな春の風と、ほどよい適当な雨降り。化雨は植物の成長を促す適度のおしめりをいう。 これより転じて立派な教育が行われることについていう。 |
| 春風秋雨 | しゅんぷうしゅうう | 長い年月。 |
| 春風駘蕩 | しゅんぷうたいとう | 春の景色がのどかな様子。何事もなく平穏なことや、人の態度や性格がのんびりとしていて温和なことをさす。のどかに吹く春風。 |
| 春風満面 | しゅんぷうまんめん | 春の風が頬にいっぱい。心地よくいい感じ。 |
| 春蘭秋菊 | しゅんらんしゅうぎく | 両者ともにすぐれており捨てがたい、の意。 |
| 渉于春氷 | しゅんびょうをわたる | 春がきて薄く溶け易くなった氷の上を歩いて渡るという、甚だ危険なこと。 |
| 純一無雑 | じゅんいつむざつ | 不純なものや混じりけのまったくないこと。人物がいちずでうそや邪念のまったくないようす。 |
| 純情可憐 | じゅんじょうかれん | 心が純粋で、いじらしくかわいらしいさま。世間慣れしてなく、素直で清らかな少女の様子にいう。 |
| 純真無垢 | じゅんしんむく | 心が純粋で清らかなこと。汚れや偽りがなく、ひとをだましたり、疑ったりする気持ちがないこと。「無垢」は、元々仏教用語で、欲望・執着がなく、清浄なこと。 |
| 純粋無垢 | じゅんすいむく | 心が純粋で清らかなこと。汚れや偽りがなく、ひとをだましたり、疑ったりする気持ちがないこと。「無垢」は、元々仏教用語で、欲望・執着がなく、清浄なこと。 |
| 順水推舟 | じゅんすいすいしゅう | 水の流れを見て、その流れに合わせて舟を進める。「水に順いて舟を推す」。すなわち成行きにまかせて事を行う。「推」は推し進める。 |
| 順中之逆 | じゅんちゅうのぎゃく | 幸中の不幸。 |
| 順風満帆 | じゅんぷうまんぱん | 追い風に帆をいっぱいにふくらませているように、物事が快調に進むようす。 |
| 醇風美俗 | じゅんぷうびぞく | 人情の厚い、美しく優れた風俗や習慣のこと。 |
| 遵養時晦 | じゅんようじかい | 道に従って志を養い、時勢を見て愚人のまねをして言行をくらますこと。 |
| 蓴羹鱸膾 | じゅんこうろかい | じゅんさいの吸い物と鱸のなます。故郷を思う情のたとえ。晉の張翰が故郷の名産であるこの二品を味わうために官を辞して帰郷した故事。 |
| 初志貫徹 | しょしかんてつ | 最初にたてた志をくじけることなく最後まで貫き通すこと。 |
| 諸行無常 | しょぎょうむじょう | 世の中のすべての物事は常に移り変わって、少しの間も同じことはない。仏教の根本主義のひとつで、人生ははかなく無常であるという教え。 |
| 諸子百家 | しょしひゃっか | 春秋時代の、儒教以外の多くの学者・学派。また、それらの学者の著書。「老子」「荘子」「韓非子」など。 |
| 諸説紛紛 | しょせつふんぷん | いろいろな学説や意見が入り乱れて定まらないようす。皆が自分の説を正しいと主張しているようす。 |
| 諸法無我 | しょほうむが | 仏教における三法印・四法印のひとつ。めてすべての存在には、主体とも呼べる我(が)がないことをいう。 |
| 暑雨祁寒 | しょうきかん | 蒸し暑い雨季と厳しい寒さ。貧しい民の苦しみをいう。 |
| 叙位叙勲 | じょいじょくん | 位階を授けること。および国家や公共事業に功労のあった人に勲等を授け、勲章を与えること。 |
| 鋤蹶斬断 | じょけつざんだん | ねだやしにする。根絶する。蹶は抜き取る。斬も断も切る。蹶は縦並びらしいですが、字義が同じなのでこっちの字使ってます。 |
| 生涯現役 | しょうがいげんえき | |
| 生者必滅 | しょうじゃひつめつ | 生命あるものは、必ず死ぬときがあるということ。平安中期以降、厭世(えんせい)思想の風潮にともない、人生の無常をいうように使われた。会者定離。 |
| 生死事大 | しょうじじだい | 生と死の真相をきわめることが大切だということ。 |
| 生死不定 | しょうじふじょう | 人の生死の定めがたいこと。人の寿命は年齢とは関わりなく、いつどのようにつきるかわからないということ。 |
| 生者必衰 | しょうじゃひっすい | この世は無常であるから、命のある者は必ず死滅するときがあるということ。 |
| 生者必滅 | しょうじゃひつめつ | 生命あるものは、必ず死ぬときがあるということ。平安中期以降、厭世(えんせい)思想の風潮にともない、人生の無常をいうように使われた。 |
| 生生世世 | しょうじょうせぜ | 生まれかわり、死にかわりして経験する世。永遠をいう。 |
| 生死流転 | しょうじるてん | 万物が絶えず形を変えて生まれ変わること。 |
| 生滅滅已 | しょうめつめつい | 現世を超越し、仏果を得る。 |
| 生滅流転 | しょうめつるてん | 世界のすべての物事は時々刻々に生じたり滅びたりして、少しの間もやむことがない。 |
| 生老病死 | しょうろうびょうし | 人生の四つの苦しみ。人間としてこの世にある限りさけることの出来ない苦しみ。すなわち、生まれること、年をとること、病気をすること、そして死ぬことの四大苦。 |
| 正直正路 | しょうじきしょうろ | 正しくてうそや偽りのない人のふみ行うべき正しい道理。 |
| 正真正銘 | しょうしんしょうめい | まったくうそ偽りのないこと。まちがいなく本物であること。 |
| 商売繁盛 | しょうばいはんじょう | 商売が賑わって栄えること。 |
| 小康状態 | しょうこうじょうたい | 病気の進行がちょっと収まっているという意味。 |
| 小人閑居 | しょうじんかんきょ | つまらぬ人間は暇を持て余して、とかくよからぬことをしがちであるの意。「小人」は「君子・大人(たいじん)(ともに、有徳者・人格者の意)」に対する語で、徳のない品性の卑しい人のこと。「閑居」は仕事もなくて暇でいること。「小人閑居して不善をなす」と使う。 |
| 小人之勇 | しょうじんのゆう | 血気にはやる、浅はかな勇気。考えの浅い小勇。 |
| 小心翼々 | しょうしんよくよく | 臆病で絶えずびくびくしている様子。本来は、慎み深く細かいことにも注意を配って何事もおろそかにしないさま。 |
| 小水之魚 | しょうすいのうお | 僅かな水の中に棲んでいる魚の意から、死が目の前に迫っていることのたとえ。 |
| 小利大損 | しょうりだいそん | 少しの利益を得ようとして、大きな損害をこうむること。 |
| 少数精鋭 | しょうすうせいえい | 選び抜かれた少数の優秀な人材。 |
| 少壮気鋭 | しょうそうきえい | 若くて(20歳から30歳くらいまで)意気込みの盛んなこと。 |
| 松喬之寿 | しょうきょうのじゅ | 長命で名高い二人の仙人、赤松子と王子喬の長寿。転じて、長命。 |
| 松柏後凋 | しょうはくごちょう | |
| 松柏之寿 | しょうはくのじゅ | 長生き。長命。 |
| 松風水月 | しょうふうすいげつ | 松風のささやき、水に映える月、清くしっとりとしたたたずまい。澄んだ気持ちで自然を鑑賞する心境を詠んだことば。 |
| 従容整暇 | しょうようせいか | ゆったりとして乱れず、余裕のあること。 |
| 従容不退 | しゅうようふたい | ゆったりと落ち着いていて慌てないこと。 |
| 従容無為 | しょうようむい | 自然に従ってゆったりとしており、思慮を労して人為を施すことをしない。 |
| 笑止千万 | しょうしせんばん | この上もなくばかばかしくて吹き出したくなる様子。 |
| 笑比河清 | しょうひかせい | 「笑いを河清に比す」。「河清」とは、黄河の水が清く澄むこと。 黄河は名前のごとく、いつも濁って澄むことがないのにたとえて、謹厳実直めったに笑うことのない人が笑う時を待っていることをいう。 |
| 焦心苦慮 | しょうしんくりょ | 心配していらだつさま。思い悩み心が焦ることの意。 |
| 焦頭爛額 | しょうとうらんがく | 頭を焦し、額をただれさせるということから、身の危険を顧みずに火災の消防に従事すること。転じて、事変の渦中に入って奔走すること。 |
| 焦眉之急 | しょうびのきゅう | 眉が焦げるほど火が迫っている。→差し迫った危険、急務など。 |
| 証拠隠滅 | しょうこいんめつ | 証拠を隠し、消してしまうこと。 |
| 勝敗之数 | しょうはいのすう | 勝つか負けるかの運命。 |
| 将相之具 | しょうしょうのぐ | 大将や大臣の器にかなった人。力量のある人物。 |
| 傷弓之鳥 | しょうきゅうのとり | 一度、矢傷を受けた鳥の意味。前の事に懲りて、深く怖気づいたもののたとえ。 |
| 消長之数 | しょうちょうのすう | 盛衰のことわり。 |
| 祥月命日 | しょうつきめいにち | 一周忌以後、その人が死んだ月日と同じ月日。 |
| 升竜降竜 | しょうりゅうこうりゅう | 上り竜と下り竜。旗や幟の模様に使われる。 |
| 精進潔斎 | しょうじんけっさい | 飲食、行動を慎み心身を清め、清浄な状態であること。 |
| 掌中之珠 | しょうちゅうのたま | 愛する子ども。最も大切にしているもののたとえ。 |
| 鐘鼓之楽 | しょうこのたのしみ | 音楽の楽しみ。 |
| 鐘鼎玉帛 | しょうていぎょくはく | 食前に音楽が奏せられ、食堂には山海の珍味が並べられ、酒盛りのあとでは、玉や帛(きぬ)の引出物が出る豪華な宴。鼎は、なべ。 |
| 鐘鳴鼎食 | しょうめいていしょく | 鐘楽器の一種を鳴らし鼎(なべ、転じて、ごちそう)を並べて食べる。食前に音楽が奏せられ、食堂では山海の珍味が並べられること。富貴の人の生活をいう。 |
| 瘴雨蛮烟 | しょううばんえん | 毒気を含んだ雨と煙。 |
| 猖狂之勢 | しょうきょうのいきおい | たけり狂った勢い。 |
| 蕭牆之憂 | しょうしょうのうれい | 内から起こる心配事。家族・身内などの内輪もめ、内乱など。蕭牆は君臣が会見する所に立てる屏風。 |
| 嘯風弄月 | しょうふうろうげつ | 風にうそぶき、月をもてあそぶ。詩歌・風流に心を寄せること。 |
| 上意下達 | じょういかたつ | 上の者の意志や命令が下の者に伝わること。 |
| 上雨旁風 | じょううぼうふう | 屋根から雨がもり、両わき(旁)からはすきま風がふきつける、あばら家を形容することば。 |
| 上水之魚 | じょうすいのうお | 死が目前であることを知らないで僅かの溜り水の中で泳いでいる魚。 |
| 上善如水 | じょうぜんじょすい | 最も優れた「善」は水のごときものである。その理由は第一に水は方円の器に随い、天地間に水なくして存在するものはない。 第二に水は低い方へ低い方へと流れること。第三に低いところに水が溜るから自分も大きくなる。 このように上善は最大の善のほか、古代の善とも称される。 |
| 条件反射 | じょうけんはんしゃ | つくられた条件のもとに起きる反射作用のこと。 |
| 常在戦場 | じょうざいせんじょう | |
| 常山蛇勢 | じょうざんのだせい | 左右前後に応じ合って隙のないこと。また、そういう陣の態勢。転じて、文章の首尾がうまく照応していること。常山に両頭の蛇がおり、その首を打てば尾が応じ、その尾を打てば首が応じ、その中を打てば首尾が応じ互いに相救うという故事。 |
| 常住坐臥 | じょうじゅうざが | ふだん。いつも。座っているときも寝ているときも、の意。本来は「行住坐臥」であり、「歩く・止まる・座る・横になる」という日常の基本になる行動をいう。 |
| 常住不断 | じょうじゅうふだん | 常に続いて絶えないこと。ずっと続いていること。 |
| 常調挙生 | じょうちょうきょせい | 官吏の試験に応じる一般の人々。常調は、官吏を試験すること。挙生は、官吏登用試験を受けるもの。 |
| 常套手段 | じょうとうしゅだん | 同じような場面になると、いつも決まってとる手段や行動。 |
| 常鱗凡介 | じょうりんぼんかい | 凡庸な人間のたとえ。どこにでも見られる魚や普通の貝が転じて。 |
| 乗風破浪 | じょうふうはろう | 「風に乗って浪を破る」。順風に乗じて万里の波濤をのりきってゆくさま。時の流れに乗じて困難を排し勇躍前進するありさま。 |
| 情意投合 | じょういとうごう | お互いの間に気持ちが通じること。 |
| 情状酌量 | じょうじょうしゃくりょう | 判決にあたって同情できる事情を考えに入れて刑罰を軽くすること。 |
| 情緒纏綿 | じょうしょてんめん | 情感の深いさま。情愛が深く細やかで離れにくいこと。「情緒纏綿」は、「じょうちょてんめん」とも読む。「纏綿」は、まつわりつく、からみあう。 |
| 城下之盟 | じょうかのめい | 敗戦国が敵兵により城下(或いは大群により国境に迫る事)に厳重な脅威にさらされ、追い込まれて結ぶ屈辱的な条約のこと。 |
| 城狐社鼠 | じょうこしゃそ | 身を安全な所に置いて悪事を働くもののたとえ。特に君主の傍らにいる悪臣をたとえる。 |
| 浄土之学 | じょうどのがく | 仏教の学問。 |
| 浄潔快豁 | じょうけつかいかつ | さっぱりとしていて晴々しい気持。 |
| 盛者必衰 | じょうしゃひっすい | どんな勢いの盛んなものでも、必ず衰えるということ。仏教の人生観でこの世の無常を言う言葉。 |
| 饒舌多弁 | じょうぜつたべん | 口数が多くて、よくしゃべるさま。「饒舌」はおしゃべりのこと。 |
| 食牛之気 | しょくぎゅうのき | 牛を飲むほどの大きな気性。幼くして大きな気性のあることをいう。 |
| 食前方丈 | しょくぜんほうじょう | ぜいたくな料理のこと食事をするときに、席前に一丈(長さの単位)四方いっぱいに料理を並べることから、豪華な料理のたとえ。 |
| 職人気質 | しょくにんかたぎ | 職人仲間に共通な気質。粗野偏狭であるが実直である。 |
| 職務怠慢 | しょくむたいまん | 職業上の義務をなまけて怠ること。 |
| 職権乱用 | しょっけんらんよう | 職務上の権力をむやみに使うこと。 |
| 蜀犬吠日 | しょくけんはいじつ | 無知な人は、当たり前の事柄にも、怪しんで恐れること。また、見識もなく劣った者が、他人の言動をむやみに批判すること。 |
| 燭照数計 | しょくしょうすうけい | 灯火でよく照らし、そろばんで数える。物事が明らかで、誤りのないこと。 |
| 嗇夫利口 | しょくふりこう | 身分の低い男が口上手なこと。 |
| 白川夜船 | しらかわよぶね | 熟睡していて何も知らないこと。何も気がつかないほどよく寝入っているさま。眠り込んでしまって、周りで何が起こったのか、わからない様。京都見物をしてきたふりをする者が、京の白河のことを尋ねられたが、川の名と思い、夜船で通ったから知らないと答えたということから、よく寝込んでいて何も知らないことの例え。「白河」は「白川」とも書く。 |
| 白羽の矢 | しらはのや | |
| 心願成就 | しんがんじょうじゅ | 宿願の達成。心の中で願い続けていた希望・夢が、その通りにかなうこと。 |
| 心機一転 | しんきいってん | 気持ちをすっかり変えて出直すこと。今の状態より良い方向に変化する場合に使う。「心機」は、心の働き、「一転」は、すべて変えるという意。 |
| 心象風景 | ||
| 心身一如 | しんしんいちにょ | 心身の充実。精神と肉体が一体になること。物事に向かって集中している様子。「心身」は、「身心」とも書く。 |
| 心神耗弱 | しんしんこうじゃく しんしんもうじゃく |
善悪を判断して行動する精神のはたらきがひじょうに弱いこと。裁判では刑を軽くする。 |
| 心神喪失 | しんしんそうしつ | 善悪を判断して行動する精神のはたらきがまったくないこと。裁判ではその状態で犯した罪は罰しない。 |
| 心想羸劣 | しんそうるいれつ | 心が弱く劣っているということ。どれほどしっかりしたことを言いどれほど固く信じていても、その時その時の状況や仏教でいう縁によって、心は揺れ動く。 |
| 心頭滅却 | しんとうめっきゃく | 心の中の雑念を消し去ること。無念、無想の意。D467もと仏教語。 |
| 心腹輸写 | しんぷくゆしゃ | 心に思うところを全て打ち明ける。真心を示す。 |
| 神韻縹渺 | しんいんひょうびょう | 芸術作品などに、きわめてすぐれた趣が感じられるさま。 |
| 神機妙算 | しんきみょうさん | 神が行うような絶妙のはかりごと。常人には思い付かないすぐれたはかりごと。 |
| 神算鬼謀 | しんさんきぼう | 人間が考えたとは思えない優れた計略。 |
| 神出鬼行 | しんしゅつきこう | 出没が人間業でなく、自由で変化のはかりしれないこと。 |
| 神出鬼没 | しんしゅつきぼつ | 非常にすばやく現れたり見えなくなったりすること。不意に出没して居所のわからないこと。鬼神のように自由にあらわれたり隠れたりすること。 |
| 神色自若 | しんしょくじじゃく | 何事が起こっても冷静で落ち着いているさま。 |
| 神仏混交 | しんぶつこんこう | 神と仏はもともとは一体であるという信仰から、神仏をいっしょに祭ること。 |
| 深計遠慮 | しんけいえんりょ | 深いはかりごと、および将来に対する考え。 |
| 深山幽谷 | しんざんゆうこく | 人があまり行かないようなひっそりとした奥山の自然をいう。人里離れた奥深い山々や、深い静かな谷間。 |
| 深識長慮 | しんしきちょうりょ | 深くさとり、遠くおもんぱかる。 |
| 深造自得 | しんぞうじとく | 学問の深い奥義を窮めて、深くみずから了解する。 |
| 深謀遠慮 | しんぼうえんりょ | はるか先まで考えて、周到な計画を巡らすこと。「深謀」は、深いはかりごと。「遠慮」は、遠く思いはかる(前もって思いめぐらす)の意。 |
| 新旧交代 | しんきゅうこうたい | 新しいものが古いものと入れ替わること。 |
| 新進気鋭 | しんしんきえい | 新しく加わったばかりで非常に意気込みが盛んであること。ある分野において新しく登場して認められ、意気込みや才能が鋭いこと。 |
| 新陳代謝 | しんちんたいしゃ | 古いものが去り、新しいものが変わってあらわれること。 |
| 真剣勝負 | しんけんしょうぶ | 本物の刀剣を用いて勝負をつけること。また、命がけで争ったり、事に対処すること。 |
| 真実一路 | しんじついちろ | 一筋に真実を求めて生きていくこと。ひたすらにおのれの真実を尽くすこと。 |
| 進取果敢 | しんしゅかかん | 自ら進んで物事に取り組み、決断力に優れていること。「進取」は、自分から進んでことを成す。「果敢」は、決断力が強く大胆なこと。 |
| 進寸退尺 | しんすんたいせき | 得ることが少なく、失うことが多いことのたとえ。一寸進んでは一尺退くの意味。 |
| 進退両難 | しんたいりょうなん | 進むも退くも両方ともに困難なこと。ニッチもサッチもいかないこと。 |
| 身後之諫 | しんごのいさめ | 死後に残すいさめ。死んで諌めること。 |
| 身体髪膚 | しんたいはっぷ | からだ全体のこと。体と髪と皮膚の意から身体をさし、肉体のことを言う。 |
| 臣一主二 | しんいつしゅに | 臣下として仕える身は一つであるが、主君として仕えるべき人は数多くある。主君として仰ぐべき人を、どこの国に行って求めるのも自由であるという意味。 |
| 臣籍降下 | しんせきこうか | もと、皇族が皇族以外の者との結婚や賜姓などで、皇族の身分を失うこと。 |
| 震天駭地 | しんてんがいち | 天をふるわせ、地をおどろかす。勢力や音響が盛んなたとえ。 |
| 震天動地 | しんてんどうち | 天地をふるい動かすほどの大変な出来事。元は威勢の盛んなことで、大音響などのたとえ。 |
| 森羅万象 | しんらばんしょう | 宇宙の間にあるいっさいのもの。万有。 |
| 信賞必罰 | しんしょうひつばつ | 賞罰を厳密、正確に行うこと。功の有った者には必ず賞を与え、罪を犯した者には必ず罰を与える。賞罰を厳格に行うこと。 |
| 針小棒大 | しんしょうぼうだい | ごく小さな事柄を大げさにいうこと。 |
| 慎重居士 | しんちょうこじ | |
| 紳士協定 | しんしきょうてい | 非公式な国際協定。また、互いに相手を信頼して行う約束事(紳士協約)。 |
| 親戚知己 | しんせきちき | 親しい人々。親戚と知り合い。 |
| 薪水之労 | しんすいのろう | 骨身を惜しまず雑事を行なうこと。 |
| 参差錯落 | しんしさくらく | ものが一様でなく、様々なものが入り混じっていること。 |
| 晨星落落 | しんせいらくらく | 明け方の空に、星が僅か二つ三つ見えるように、友人が次第に少なくなること。 |
| 晨入夜帰 | しんにゅうやき | 朝早く官舎に入って、夜遅く帰ること。 |
| 晨入夜出 | しんにゅうやしゅつ | 朝早く官舎に入って、夜遅く出ること。 |
| 脣歯之国 | しんしのくに | 利害関係が最も深い国。 |
| 唇歯輔車 | しんしほしゃ | 二つのことの関係が密接で、一方がダメなら他方もダメになること。 |
| 如臨深渕 | しんえんにのぞむ がごとし |
深いところの水をのぞきこむように慎重の上にも慎重に注意して大事にことに当ること。 「臨」はのぞきこむこと、「渕」は深く水の貯っているところ。 |
| 人為淘汰 | じんいとうた | 生物の品種改良において、形状や性質の変異性の中から、人間に役立つ遺伝型を選んで、その形質を一定の方向に変化させること。 |
| 人海戦術 | じんかいせんじゅつ | 多数の兵力を動員して、損害は覚悟の上で数の力で敵を打ち破ろうとする戦術。転じて多数の人間を投入して物事に対処すること。 |
| 人間青山 | じんかんせいざん | 人間は世間の意味。青山は青々とした山。世間は広い、殻にこもらず挑戦しろの意。 |
| 人琴之嘆 | じんきんのたん | 人の死を悲しむ気持のはなはだしいこと。晉の王献之の死後、その愛用の琴の調子も合わなくなった故事。 |
| 人権蹂躙 | じんけんじゅうりん | 基本的な権利を踏みにじること。 |
| 人権侵害 | じんけんしんがい | 他人の権利を侵して損なうこと。 |
| 人権擁護 | じんけんようご | 人間の基本的な権利を守ってやること。 |
| 人口膾炙 | じんこうかいしゃ | 「なます」や「あぶり肉」は誰の口にも美味に感ぜられるように、広く人々の口にのぼって、もてはやされること。広く世間の話題となる。 |
| 人山人海 | じんざんじんかい | 黒山の人だかり。 |
| 人事不省 | じんじふせい | 大病や大けがで、意識不明になること。昏睡状態に陥ること。 |
| 人心一新 | じんしんいっしん | 現状に飽きた世間の心をすっかり新しくすること。 |
| 人心収攬 | じんしんしゅうらん | 人々の心をうまくつかむこと。政治的によく使われる。 |
| 人生一世 | じんせいいっせい | 人の一生。 |
| 人生行路 | じんせいこうろ | 人がこの世に生きていく道のこと。「行路」は、道・旅路のこと。 |
| 人跡未踏 | じんせきみとう | 今までに人が足を踏み入れたことがないこと。人の通ったことが全くないこと。 |
| 人畜無害 | じんちくむがい | 人にも家畜にも害の無いこと。 |
| 人中騏驥 | じんちゅうのきき | 多くの人に秀でた天才のたとえ。 |
| 人中獅子 | じんちゅうのしし | 多くの人に秀でた天才のたとえ。 |
| 人馬絡繹 | じんばらくえき | 人馬の往来が絶えないこと。往来の激しいさま。 |
| 人品骨柄 | じんぴんこつがら | 見た目の品位や人格のこと。 |
| 人物月旦 | じんぶつげったん | 人物批評、品定めのこと。 |
| 人面獣心 | じんめんじゅうしん | 情けを知らないものをののしって言う言葉。顔は人でも、心は獣のようであること。「にんめんじゅうしん」とも読む。 |
| 人面桃花 | じんめんとうか | 以前佳人に会った場所で、再びその人に会えないこと。美人の顔と桃の花の意味。中唐の詩人崔護の詩から出た言葉。 |
| 尽忠報国 | じんちゅうほうこく | 忠義を尽くして、国の恩に報いること。 |
| 尽未来際 | じんみらいさい | 未来永劫。永遠の未来。 |
| 迅速果敢 | じんそくかかん | 素早く大胆に物事を行うこと。「迅速」は、きわめて速く、すみやかなこと。 |
| 迅速果断 | じんそくかだん | 物事をすばやく決断し、実行すること。思いきりがよく決行にすばやい。 |
| 尋常一様 | じんじょういちよう | ふつうと変わりのない様子。なみひととおり。 |
| 仁義礼智 | じんぎれいち | 人の心に生まれながら備わっている四つの徳。 |
| 陣頭指揮 | じんとうしき | 上の者が先頭に立って指図を与えること。 |
| ス | ||
| 頭寒足熱 | ずかんそくねつ | 頭をすずしくし、足を暖かくすること。 |
| 頭脳明晰 | ずのうめいせき | 頭が良くて、知力、判断力が優れていること。 |
| 水温躍層 | すいおんやくそう | 海や湖沼の深さに伴う水温の減少率が特に大きな層をいう。海洋水産学の専門用語。 |
| 水火氷炭 | すいかひょうたん | 火と水、氷と炭のごとく、お互いに相容れぬこと。また非常に仲の悪いことをいう。 |
| 水鏡之人 | すいきょうのひと | 「水鏡」は物の姿を写す水鏡。曇りのない清らかな水鏡の意味から、人の道の手本となるような人物、 また人の師表となる聡明な人のたとえ。 |
| 水魚之交 | すいぎょのまじわり | 非常に仲がよい、信頼できる交際。水と魚のように離れることができない親密な間柄。 |
| 水光接天 | すいこうせってん | 「水光天に接す」。月の光りが川面に映り輝き、その水面がはるか彼方で天に接していること。揚子江の夜景の雄大な景影のさま。 |
| 水髄方円 | すいずいほうえん | 「水は方円の器に随う」。水は四角な、円い器にも素直に従うように、民の善悪は君の善悪に原因し、人の善悪は交友の良否によるということ。 |
| 水清無魚 | すいせいむぎょ | 「水清ければ魚無し」。水が非常に清く澄んでいると、反って魚は棲みにくい。人も清廉潔白すぎると厳しすぎて、人がなついて来ない。寛大な思いやりの態度が大切であること。 |
| 水積成川 | すいせきせいせん | 小さな水の流れも、集い合って大きな川となるように、小も積もれば大となるたとえ。 |
| 水天一碧 | すいてんいっぺき | 晴れ渡って、水と空と一続きに青々としている。 |
| 水天髣髴 | すいてんほうふつ | 遠い沖の水面と空とがひとつづきになって、水平線の見分けがつきにくいこと。 |
| 水到渠成 | すいとうきょせい | 「水到りて渠成る」と読む。水が流れてくると、自然に土が削られ溝ができる。時が経てば物事は自然に成功すること。 |
| 水乳交融 | すいにゅうこうゆう | 水と乳が互いにまざり合い融け合うことから、互いの関係が密接で堅く結び合って、解くことのできぬたとえに用いる。 |
| 水密隔壁 | すいみつかくへき | 防水隔壁ともいう。船の外板が破損して、船の中に水が侵入しても、船内に区画、侵入止めの隔壁のある設備のこと。 |
| 水落石出 | すいらくせきしゅう | 「水落ち石出ず」という。谷川を流れる水量が減って、川の底の石が露出することから転じて事の真相が明らかになるたとえ。 |
| 水陸並進 | すいりくへいしん | 水軍と陸軍の兵士を同時に並べて前進させること。「水陸並び進む」。 |
| 水路之勝 | すいろのしょう | 舟路のけしきのよいこと。 |
| 不通水火 | すいかをつうぜず | 日常生活に必要不可欠の飲み水や薪などを融通し合おうとしない。近所づき合いをせぬこと。 |
| 垂髫戴白 | すいちょうたいはく | たれ髪の子供と白髪の老人。 |
| 垂天之雲 | すいてんのくも | 空いっぱいに垂れ下がる雲。大きいことの形容。 |
| 垂堂之戒 | すいどうのいましめ | 将来のある子は危険な所に近寄ってはならないという戒め。 |
| 垂簾之政 | すいれんのまつりごと | 幼少の天子に代わって太后・皇太后が政治をとること。 |
|
酔眼朦朧 |
スイガンモウロウ | 酒に酔って目も意識もぼんやりし、はっきりしないさま。酒に酔った状態。酒によってはっきりみえないさま。目がぼんやりとしていること。 |
| 酔生夢死 | スイセイムシ | 酒に酔い、夢を見て一生を終えること。有意義なことは何もせず無駄に一生を過ごすこと。何もしないでぼんやりと一生を過ごすこと。無自覚で一生を送ること。夢見心地で一生を終える意から、一生を無駄に過ごすことのたとえ。後世に残るような仕事や、意義のある仕事をなにもしないような場合にいう。 |
| 酔歩蹣跚 | すいほまんさん | 酔ってふらふら歩くこと。酔った足取りのおぼつかない様子。 |
| 吹毛之求 | すいもうのきゅう | しいて他人の欠点を探し求めること。 |
| 吹毛之剣 | すいもうのけん | 吹きつけた小さな毛をも切る剣の意から、非常によく切れる剣。 |
| 炊臼之夢 | すいきゅうのゆめ | 妻に先立たれるたとえ。また、妻の死を知らせる夢。 |
| 炊金饌玉 | すいきんせんぎょく | 金をかしぎ、玉を食物とする。ごちそう。見事な食事をほめていう。 |
| 穂状花序 | すいじょうかじょ | 無限花序の一。伸長した花軸に柄のない花が穂状につくもの。麦・イノコズチ・オオバコなどにみられる。 |
| 翠帳紅閨 | すいちょうこうけい | 翡翠(かわせみ)の羽で飾った帳(とばり)と紅色の寝室。美しく飾った貴婦人の寝室のこと。 |
| 錐刀之末 | すいとうのすえ | わずかな利益。 |
| 綏綏灑灑 | すいすいさいさい | 水の流れ落ちるさま。さらさら。たらたら。 |
| 隋和之材 | ずいかのざい | 隋は隋侯の珠、和は和氏の璧。ともに天下の貴重な宝である。転じて、すぐれた人材にたとえる。 |
| 随喜渇仰 | ずいきかつごう | 喜んで仏に帰依し、深く信仰すること。 |
| 随処為主 | ずいしょいしゅ | 常に主体性を持つこと。人は環境や境遇に左右されて行動しやすいものであるが、どのような場合にも主体性を失わずにいきることが真の生き方であるということ。「随処に主と為る」とも読む。 |
| 随処作主 | ずいしょさくしゅ | どんな仕事につくにせよ、その主人公になった気持ちで勉励すれば必ず道が開けて正しい成果が得られよう、という教え。 |
| 随波逐流 | ずいはちくりゅう | 「波に随し、流れを逐う」。自分には本来の主義、主張がなく、ただ世間の大勢の流れに従うことのたとえ。 |
| 枢機之位 | すうきのくらい | 天子の近くに仕えて重要なことに参与する地位。枢要な地位。 |
| 筋金入り | 昔の建築に使われた金属製補強材を筋金と呼んでおり、これが転化して「強靭で不屈の精神の持ち主」を形容する言葉として使われ始めた。 | |
| 鄒魯遺風 | すうろのいふう | 孔子・孟子の遺風。孟子は鄒国出身、孔子は魯国出身のためにいう。 |
|
|||||||||||||||||||||||
| セ | ||
| 世運隆替 | せうんりゅうたい | 世の気運が栄えたり、衰えたりして移り変わること。 |
| 世間惨風 | せけんさんぷう | 世の中の辛いこと。 |
| 世道人心 | せどうじんしん | 世の中の道徳と世間の人の心。 |
| 世渫不食 | せいせつふしょく | 「世渫(せいきょ)けれども食(くら)われず」とも読む。 井戸の水は清く澄んでいるのに人々がその水を汲んで用いることがない。 賢人と言われ乍ら、世間に用いられることがない人のこと。「渫」は清潔、潔白、「食」は汲みとるの意。 |
| 是耶非耶 | ぜかひか | 良いこと、悪いことに迷って判断に迷うこと。 |
| 是々非々 | ぜぜひひ | 道理にかなう公平な判断のこと。良いことははっきりと良いとし、悪いことは悪いと正しい判断を下す。「是を是とし、非を非とす」と読む。 |
| 是非曲直 | ぜひきょくちょく | 正しいか正しくないかということ。「是非」は、正しいことと間違っていること。「曲直」は、曲がったこととまっすぐなこと。 |
| 是非善悪 | ぜひぜんあく | 物事のよしあし。正邪。 |
| 是非之心 | ぜひのこころ | 良いことを是とし、悪いことを非とする心。世の出来事について、そのよしあしをやたらと気にかける心。 |
| 正々堂々 | せいせいどうどう | 態度が正しくて立派な様子。態度や方法が正しくて立派なさま。陣営などの勢いが盛んなさま。 |
| 正当防衛 | せいとうぼうえい | 急迫した不正の侵害に対して、これを防ぐためにやむを得ず行う加害行為。刑法上では違法性を欠くものとして犯罪とならず、民法上も不正行為としての損害賠償責任を生じない。 |
| 生殺与奪 | せいさつよだつ | 生かすも殺すも、与えるも奪うも思いのままであること。他のものを自由自在に支配することのたとえ。 |
| 生死肉骨 | せいしにくこつ | 人に恩を施したことに対する感謝の表現。 |
| 生死之境 | せいしのさかい | 死ぬか生きるかの危ない場合。 |
| 生生化育 | せいせいかいく | 万物を育てて、宇宙を経営すること。 |
| 生生流転 | せいせいるてん | 万物が永遠に生死の間を巡ること。万物が絶えず変化し移り変わってゆくこと。 |
| 生知安行 | せいちあんこう | 生まれながらにして道徳の何であるかに通じていて、努力することもなく難なくそれを実行すること。 |
| 生呑活剥 | せいどんかっぱく | 他人の詩文をそっくり盗むこと。活剥は生きたままはぎとるの意味。 |
| 青雲之志 | せいうんのこころざし | 立身出世しようと願う心。 |
| 青雲之士 | せいうんのし | 学徳の高い人。高位高官に出世した人。 |
| 青雲之交 | せいうんのまじわり | 同時に官に仕えた縁による交わり。 |
| 青眼白眼 | せいがんはくがん | 親しい人には青眼(くろめ)を出し、嫌いな人には白眼(しろめ)をむく。「青白眼」(せいはくがん)ともいう。青は黒の意。 晋(しん)の阮籍(げんせき)の故事。阮籍の母が死ぬと、喜(けいき)(康(けいこう)の兄)がお悔(くや)みに来た。喜は俗物なので阮籍は白眼をむいて対応した。喜は怒って立ち去る。弟の康がそれを聞き、酒をぶらさげ琴を携(たずさ)えて行くと、阮籍は喜び今度は青眼を出した。この話から、人を拒絶したり無視したりすることを白眼視(はくがんし)というようになった。にらむ目つきである。 |
| 青山一髪 | せいざんいっぱつ | 海上はるかに青山が一本の髪を引いたようにかすかに見えるさま。 |
| 青苔黄葉 | せいたいこうよう | 青いこけと黄色い秋の木の葉。山家のよいけしき。 |
| 青天霹靂 | せいてんのへきれき | 晴れた空の雷の意味で、突然に起こった変動。また、急激な変動。突然起こる大事件。 |
| 青天白日 | せいてんはくじつ | やましいところが全くなく潔白なこと。疑いが晴れて罪のないことがはっきりすること。心の中が明白で、少しも隠しごとや疑われることがない状態。うたがいや無実の罪がはれること。 |
| 晴雲秋月 | せいうんしゅうげつ | 晴れた空の雲と秋の月。胸中の清らかに澄みとおることをいう。 |
| 晴好雨奇 | せいこううき | 山水の景色が、晴れの日に素晴しいだけでなく、雨の日にも珍しい味わいを呈すること。晴れても雨でも景観が良いこと。 |
| 晴耕雨読 | セイコウウドク | 晴れた日には外に出て田畑を耕し、雨の日には家の中で読書をするというように、思いのままのんびりと生活するということ。晴れた日には外にでて畑を耕し、雨の降る日には、家で本を読む。悠々自適な生活ぶり。自然とともに気ままに暮らす、理想的な老後の生活の意にもいう。 |
| 清栄峻茂 | せいえいしゅんも | 木が美しく高く茂ること。 |
| 清酌庶羞 | せいしゃくしょしゅう | 神にすすめる酒ともろもろの供物。 |
| 清秀深穏 | せいしゅうしんおん | 清らかに高くひいでて、奥ゆかしく落ち着いたさま。 |
| 清浄寂滅 | せいじょうじゃくめつ | 清浄無為を説く老子の道と、寂滅為楽を説く仏教。道家の道と仏教の教え。 |
| 清濁併呑 | せいだくへいどん | 善悪分け隔てなく受け入れること。 |
| 清淡虚無 | せいたんきょむ | 清く淡泊で物にこだわらず、さっぱりしていること。 |
| 清風明月 | せいふうめいげつ | すがすがしい夜風と明るい月。美しい自然や風雅な遊びなどの形容。 |
| 清廉潔白 | せいれんけっぱく | 心が清く澄み、後ろ暗くないこと。また絶対に不正をしていないこと。 |
| 精神一到 | せいしんいっとう | 精神を集中して努力すれば、どんなことでもできないことはない、ということ。朱熹の「陽気の発する処、金石も亦た透る。精神一到、何事か成らざらん」から。 |
| 精力絶倫 | せいりょくぜつりん | 心身の活動がきわめて強くすぐれているさま。精力が飛び抜けて強いさま。▽「精力」は心身の活動力のこと。「絶倫」は群を抜いてすぐれている意。 |
| 精励恪勤 | せいれいかっきん | きわめて熱心に仕事に励むこと。「精励」は、仕事に勤め励むこと。「恪」は、慎むこと。「恪勤」は、職務に忠実で、怠りなく勤めることの意。 |
| 誠歓誠喜 | せいかんせき | 心から喜ばしい。この上なく喜ばしい。臣下が天子に奉る書に用いる言葉。 |
| 誠惶誠恐 | せいきょうせいこう | 真心から恐れかしこまり、地にぬかずくことの意。手紙の終りに敬意を表わして添える。 |
| 誠心誠意 | せいしんせいい | まごころのこと。誠をもって相手に接する正直な心。 |
| 政教一致 | せいきょういっち | 政治と宗教が一体であること。 |
| 政教分離 | せいきょうぶんり | 政治と宗教が分離され、独立していること。 |
| 政権亡者 | せいけんもうじゃ | 政治権力に固執し、それに恋々たる連中。 |
| 井蛙之見 | せいあのけん | 井戸の中に住んでいる蛙には、世の中の広い話をしても通じない。 見界の狭い 、世間知らぬ人には踏み行うべき道を語ることができぬ。 |
| 井底之蛙 | せいていのあ | 井戸の底の蛙。世間知らず。見識の狭いもの。 |
| 西施之顰 | せいしのひそみ | 「呉越の興亡」を彩(いろど)ったのが、絶世の美女西施(せいし)の物語である。西施は越の村娘であったが、谷川で紗(さ、うす絹)を洗っていたのを、越王勾踐(こうせん)に見染められ愛人となった。美しい西施は持病の胸の痛みのため、手を胸に当てて顔を顰(ひそ)め(しかめ)る。これもまた美しいので男がチヤホヤする。それを見た隣村の不美人東施(とうし)は、「私も」と顔を顰めたら、男たちは逃げ出した、と。 不美人が、柄(がら)でもないのに美人の真似(まね)をする、ということから、他人の優れた仕事にならったり、業績にあやかったりすることを、「西施の顰に倣(なら)う」という。謙遜(けんそん)の語である。 越王勾踐は西施を呉王夫差(ふさ)に贈り、魂をとろかせて、その隙(すき)に軍備を整えた。 |
| 西施捧心 | せいしほうしん | むやみに人の真似をして、笑い者になるたとえ。 |
| 斉東野人 | せいとうやじん | 斉の国、東部地方の人は愚かでそのいうことが信じられないというところから、事理をわきまえない田舎者をいう。 |
| 斉紫敗素 | せいしはいそ | 粗悪品でも、紫色に染め上げるだけで価格はもとの十倍にもなるということから、賢者が豊かな知識を用いて災いを転じて福となし、失敗を成功へと導くことのたとえ。 |
| 斉眉之礼 | せいびのれい | 食事の膳をまゆの高さまでささげてする礼。慎んで夫に仕えること。 |
| 済勝之具 | せいしょうのぐ | じょうぶな足。健脚。けしきのすぐれた所を渡り歩く道具の意味。 |
| 成竹胸中 | せいちくきょうちゅう | 竹の絵を描こうとするとき、まず完全な竹の形を思い浮かべたのちに筆をおろす意から、あらかじめ心に決めた計画をもつ。また、確かな成算があることのたとえ。 |
| 成敗之機 | せいばいのき | 勝ち負けのはずみ。成功するか失敗するかのきっかけ。 |
| 声音笑貌 | せいおんしょうぼう | 声色や笑い顔。外見だけの様子。 |
| 星火燎原 | せいかりょうげん | 些細なことでもほっておくと、手におえなくなるというたとえ。 |
| 聖子神孫 | せいししんそん | 聖人の子や神の孫。天子の血筋のこと。 |
| 臍下丹田 | せいかたんでん | 下腹。へその下5㎝ぐらいの丹田というところ。 |
| 勢利之交 | せいりのまじわり | 権勢と利益をめあてにする交際。 |
| 棲神之域 | せいしんのいき | おくつき。父祖の墓地。 |
| 凄風苦雨 | せいふうくう | 寒く長い厳しい冬の雨風。悲惨な境遇のたとえ。「凄」は氷雨の降るさまで凄まじく、冷たく寂しさが肌身にこたえること。 |
| 坐井観天 | せいにざしててんをみる | 井戸の底に坐って天を眺めても、広い天地のほんの一角しか見えぬように、見識や世界観の狭い人のことを言う。 またそれを自ら自覚せずに自慢したり、人を批判すること。 |
| 贅沢三昧 | ぜいたくざんまい | 思うままに贅沢にふけること、したい放題の贅沢をすること。 |
| 責任回避 | せきにんかいひ | 責任をとらずに逃げる、逃れること。 |
| 責任転嫁 | せきにんてんか | 責任、罪などをほかのもののせいにする(になすりつける)こと。 |
| 赤衣使者 | せきいのししゃ | 赤とんぼの別名。 |
| 赤子之心 | せきしのこころ | あかごのように、偽りがない心。世の罪悪に汚れない清い心。 |
| 隻言半句 | せきごんはんく | |
| 隻紙断絹 | せきしだんけん | 文字を書いたわずかな紙。または絹のきれ。書画のわずかな切れ端。 |
| 積羽沈船 | せきうちんせん | 羽のように軽いものも、たくさん積めば重くなって船を沈めるようになる意から、小事も積もり積もれば大事になることのたとえ。また、小さなもの、非力なものでもたくさん集まれば、大きな力となるというたとえ。 |
| 積玉之圃 | せきぎょくのほ | 名文の多いたとえ。 |
| 積薪之嘆 | せきしんのたん | 下積みになって長く用いられないこと。 |
| 積衰積弱 | せきすいせきじゃく | しだいしだいに衰え弱る。 |
| 積土成山 | せきどせいざん | 「積土山を成す」とも読む。塵も積もれば山となる。 |
| 尺呉寸楚 | せきごすんそ | 呉・楚はともに春秋時代の大国の名前。高い所から見下ろすと呉・楚の大国も小さく見えるように、物が小さく見えるさま。 |
| 尺山寸水 | せきざんすんすい | 高山や大河が小さく見えるように、物が小さく見えるさま。 |
| 尺寸之功 | せきすんのこう | 少しの手柄。 |
| 尺寸之兵 | せきすんのへい | 短い武器。寸鉄。 |
| 尺沢之鯢 | せきたくのげい | 小さな池の山椒魚。見聞の狭いこと。一説にはめだか。 |
| 石破天驚 | せきはてんきょう | 群を抜いて素晴らしいという意味の香港のことわざ。 |
| 碩師名人 | せきしめいじん | 徳のある人や名声のある人。 |
| 雪案蛍窓 | せつあんけいそう | 勉学に励むこと。蛍(ほたる)の光、窓の雪である。「蛍雪之功(けいせつのこう)」ともいう。 東晋(しん)のころ(4世紀)、車胤(しゃいん)は貧しくて油が買えないので、夏、蛍を集めて袋に入れ、その明かりで書物を照らした。また、孫康(そんこう)は冬の日、窓べに雪を積んで明るくして、書物を読んだ。(『蒙求(もうぎゅう)』)歌にもなっている有名な話。昔は、金持ちは蝋燭(ろうそく)で、貧しい人は菜種(なたね)油を使って火を灯(とも)した。 |
| 雪月風花 | せつげつふうか | 自然の景色、四季の景観をいう。 |
| 雪中松柏 | せっちゅうのしょうはく | 松や柏(桧に似た常緑樹)は寒い雪の中でもその緑色を変えない。人の節操の堅いことのたとえ。 |
| 雪泥鴻爪 | せつでいのこうそう | 雪解けの泥の上に水鳥が爪跡をしるすの意味で、人生のはかなく跡形の残らないことのたとえ。 |
| 切磋琢磨 | せっさたくま | 学問や道徳に励んでやまないこと。お互いに励まし合って学問や技芸を磨き上げて、人格を向上させること。また、競争しあって進歩向上を図ること。 |
| 切歯扼腕 | せっしやくわん | 激しく怒ったりしてじりじりいらいらすること。はぎしりをし、うでをにぎりしめてくやしがり、残念がったり激怒すること。 |
| 折衝之臣 | せっしょうのしん | 攻撃してくる敵を千里の先で追い払う忠義な臣。 |
| 折花攀柳 | せっかはんりゅう | 花柳界で遊ぶこと。 |
| 殺生禁断 | せっしょうきんだん | 殺生をさしとめること。 |
| 絶体絶命 | ぜったいぜつめい | せっぱ詰まった立場に追い込まれること。進退きわまった、どうしようもない状態。「絶体」は身体を損なうこと。「絶命」は、生命を落とすこと。 |
| 用銭如水 | ぜにをもちいること みずのごとし |
湯水のごとくお金をむだ遣いすること。 |
| 千客万来 | せんきゃくばんらい | 多くの客が次々に来ること。多くの客が入れ代わり立ち代わり入って来ること。 |
| 千金之価 | せんきんのか | 高価な品物。また、大金。 |
| 千軍万馬 | せんぐんばんば | (多くの戦場を駆けめぐって)経験の豊かなこと。 |
| 千言万語 | せんげんばんご | いろいろ言葉を尽くして言うこと。長たらしい言葉。 |
| 千古不易 | せんこふえき | 永遠に変わらないこと。 |
| 千古不磨 | せんこふま | 永久に伝わる。不磨は磨り減ってしまわないこと。不朽。 |
| 千載一遇 | せんざいいちぐう | 絶好のチャンス。千年にたった一度あうほどの、滅多にない絶好のチャンス。 |
| 千差万別 | せんさばんべつ | 種々さまざまな違い。千万(数多く)差別(ちがい)があるということ。 |
| 千秋万歳 | せんしゅうばんざい | 歳月の非常に長いこと。また、長寿を祝う言葉。▽「千」「万」は数の非常に多いことを示す。「秋」「歳」はともに年のこと。千年、万年の非常に長い年月の意。「万歳」は「ばんぜい」「まんざい」とも読む。 |
| 千手観音 | せんじゅかんのん | 体は金色で27の顔と40本の手を持つ観音。 |
| 千波万波 | せんぱばんぱ | 次から次へと絶え間なく押し寄せてくる波。 |
| 千篇一律 | せんぺんいちりつ | どれもこれも変わりばえがなく、面白みがないこと。みな同じ調子。「千篇」は、「千編」とも書く。 |
| 千変万化 | せんぺんばんか | いろいろさまざまに変わること。変化がきわまりないこと。 |
| 千仞之谿 | せんじんのたに | きわめて深い谷。周尺で千仞はおよそ1575m。 |
| 千仞之山 | せんじんのやま | きわめて高い山。周尺で千仞はおよそ1575m。 |
| 千方百計 | せんぽうひゃっけい | いろいろと思いはかること。 |
| 千万無量 | せんまんむりょう | 数が多くて数えきれないこと。計り知れないこと。 |
| 千慮一失 | せんりょのいっしつ | どんなに考えたつもりでも、思いがけない失敗がある。 |
| 千両役者 | せんりょうやくしゃ | 演技の優れた俳優。一般に芸の優れた人。 |
| 先義後利 | せんぎこうり | 義を先にして利を後にするものは栄えるということ。 |
| 先見之明 | せんけんのめい | 将来を見通す能力。 |
| 先祖伝来 | せんぞでんらい | 先祖から代々伝わっていること。 |
| 先手必勝 | せんてひっしょう | 攻撃を先に仕掛ければ、必ず勝てるということ。 |
| 先憂後楽 | せんゆうこうらく | 優れた為政者は心配事については世の人がまだ気付かないうちからそれを心にとめていろいろ処置をし、楽しみは世の人の楽しむのを見届けたあとに楽しむ。政治家の心がけを表した語。 |
| 浅学短才 | せんがくたんさい | 学問が浅く、才知の乏しいこと。 |
| 浅学非才 | せんがくひさい | 学問・知識が浅く、才能もないこと。自分の学問や才能をへりくだって言う場合に用いる。 |
| 浅酌低唱 | せんしゃくていしょう | ほどよく酒を味わい飲みながら、小声で詩歌を口ずさんで楽しむこと。▽「浅酌」はほどよく酒を飲むこと。「低唱」は小さい声で歌うこと。 |
| 専売特許 | せんぼうしっと | うらやんでねたむこと。 |
| 戦々兢々 | せんせんきょうきょう | おそれおののく様子。おそれてびくびくする様子。また、「戦々恐々」とも書き、「恐々」は、ふるえるを意味する「兢々」のかきかえ字。 |
| 宣戦布告 | せんせんふこく | 戦争開始を内外に知らせること。 |
| 潜在意識 | せんざいいしき | 意識にのぼらない概念。下意識。 |
| 羨望嫉妬 | せんぼうしっと | 羨んで妬むこと。 |
| 全身全霊 | ぜんしんぜんれい | 体力も精神力もすべて。身も心も全部。 |
| 全知全能 | ぜんちぜんのう | 知識が完全で少しの欠点もないこと。 |
| 前後不覚 | ぜんごふかく | 前後の区別もつかなくなるほど正体がなくなること。全然覚えがなくなる。 |
| 前車之轍 | ぜんしゃのてつ | 前に行った車のくつがえったわだちの跡。転じて、前の人の失敗。また、あとの人の戒めとなるような物事。神皇正統記下「前車の轍(テツ)をみることはまことに有りがたき習ひなりけんかし」。 |
| 前人未到 | ぜんじんみとう | 今までに誰も行ったことのないこと。今まで誰も到達したことがないほど、実現の困難なこと。新分野を切り開く場合や空前の偉業などをいうときに用いる。「ぜんじんいまだいたらず」と訓読みする。「未到」は、「未踏」とも書く。 |
| 前代未聞 | ぜんだいみもん | あまりにもふつうと違っていて、今まできいたことのないこと。 |
| 前途多難 | ぜんとたなん | 行く手、将来に多くの困難があると予想されること。「前途」は、さきゆき・将来・目的地までの道のり。「多難」は、困難や災難の多いこと。 |
| 前途有為 | ぜんとゆうい | 将来、活躍の見込みのあること。「前途」は、将来の意。「有為」は、何か立派なことを行うこと。 |
| 前途洋々 | ぜんとようよう | 将来が明るく可能性に満ちあふれているさま。「洋々」は、広々として限りないさま。将来のある人の前途、また、若い人の門出を祝福するときなどに使う。 |
| 前途遼遠 | ぜんとりょうえん | 行く先の道がはるかに遠い。望みがすぐには達せられない。 |
| 前度劉郎 | ぜんどりゅうろう | 一度去った人物が戻ってくること。長い旅から帰ってくること。「前度」は前回、以前といった意味で使われます。「劉郎」はこの四字熟語の由来である詩の作者で、中国の中唐期の詩人、政治家である「劉禹錫(りゅう うしゃく)」自身のこと。劉禹錫は中央政界で活躍したが、政治改革に敗れてた後は左遷され、戻っては左遷される人生でした。初めて左遷される前に植えた桃の木が戻ったころには花を咲かせてました。また戻ってきたときにはすべて切り倒され跡形もなく、当時の仲間はすでにどこかへ行ってしまいました。その時に詠ったのが「前度劉郎今又来(桃を種えし道士何処にか帰す、前度の劉郎今又た来たる)」。どんなに地元が変わって仲間がいなくなろうと、私は帰ってくるといった悲しくもあり決意に満ちた言葉。 |
| 前門の虎、後門の狼 | 一つの危難や障害から身を守っても、さらにまた他の危難や障害が現れることのたとえ。 | |
| 善因善果 | ぜんいんぜんか | よい行いはよい結果をうむこと。 |
| 善男善女 | ぜんなんぜんにょ | 仏法に帰依した男女。また、一般に信仰心のあつい人々や、寺社に参拝する人々をいう。 |
| 善は急げ | ぜんはいそげ | よいことはためらわず、ただちに実行せよ。 |
| 善隣友好 | ぜんりんゆうこう | 隣り合った同士が、友好関係を結ぶこと。 |
| 禅譲放伐 | ぜんじょうほうばつ | 天子の位を有徳者に譲ることと、家来が天子を武力によって追放し、自分が天子になること。 |
| ソ | ||
| 粗衣粗食 | ソイソショク | 粗末な食事と粗末な衣服。簡素な暮らし。質素なつつましい生活。粗末な衣服と粗末な食事。また、そのような生活をすること。 |
| 粗製濫造 | そせいらんぞう | 質の悪い品をむやみにたくさん作ること。 |
| 楚越同舟 | そえつどうしゅう | 犬猿の仲の者同士が同じ場所に居合わせることのたとえ。(=呉越同舟) |
| 楚材晋用 | そざいしんよう | 楚国の材を晉人が用いる。楚と晉とは春秋時代の国名。他のものを、自分に利用すること。 |
| 創意工夫 | そういくふう | 独創的な考えや方法を編み出すこと。「創意」は、模倣でない新しい思いつき。「工夫」は、方法、手段。 |
| 創業守成 | そうぎょうしゅせい | 新しく事を始めることと、それを受け継ぎ守ること。 |
| 壮言大語 | そうげんたいご | 意気盛んに大変勇敢で、大きなスケールの話しをすること。 |
| 相互依存 | そうごいぞん | たがいに頼りあって生存をはかること。 |
| 相互扶助 | そうごふじょ | 互いに助け合うこと。互助。ダーウィンの生存競争説に反対したクロポトキンの理論の中心概念。生物や社会は競争や闘争によってではなく、自発的な協同によって進歩するという考え。 |
| 相互理解 | そうごりかい | 互いによく理解し合うこと。 |
| 相思相愛 | そうしそうあい | 男女が互いに恋いしあい、愛し合うこと。非常にむつまじい男女の仲。 |
| 相乗効果 | そうじょうこうか | 2つ以上のものを掛け合わせて効果をあげること。 |
| 相即不離 | そうそくふり | 互いに関係しあっており、切り離すことができないさま。密接な関係をいう。 |
| 糟糠之妻 | そうこうのつま | 貧しい生活を共にしてきた妻。 |
| 蒼梧之望 | そうごののぞみ | 帝王の崩御のこと。昔、舜が死んだ地といわれる。蒼梧はいまの広西省蒼梧県の地。 |
| 桑弧蓬矢 | そうこほうし | 昔、中国で男の子が生まれると、桑の木で作った弓と蓬の葉で作った矢で四方を射て将来の雄飛を祝ったことから、男子が志を立てること。 |
| 草行露宿 | そうこうろしゅく | 山野に野宿しながら旅行すること。 |
| 草根木皮 | そうこんぼくひ | 漢方薬のこと。草の根と樹木の皮。 |
| 草木皆兵 | そうもくみなへい そうもくかいへい |
敵を恐れるあまり、全山の草木までが皆敵兵のように見えるということ。 |
| 草莽之臣 | そうもうのしん | 官に仕えず、民間にある人。在野の人。 |
| 桑田碧海 | そうでんへきかい | 桑畑が青い海に変わること。世の中の変遷が激しいことのたとえ。 |
| 喪家之狗 | そうかのいぬ | やつれてしまって元気のない人、落胆して志を得ない人のたとえ。また、身を落ち着かせるところがなく放浪している者のたとえ。▽「喪家」は葬式を出して喪に服している家のこと。「狗」は犬。喪中の家では悲しみのあまり犬に餌えさをやることも忘れてしまい、犬がやせ衰えてしまうという意。また、「喪」を失うという意味にとって、宿なしの犬と解釈する説もある。「狗」は「く」とも読み、また、「犬」とも書く。 |
| 宋襄之仁 | そうじょうのじん | 無益な哀れみをかけることのたとえ。また、おろかな情けのたとえ。不必要に情けをかけて、その結果、自分が痛い目に遭うこと。宋襄の思いやりの意から。▽「宋襄」は中国春秋時代の宋国の王襄公。「仁」は情け。 |
| 漱石枕流 | ソウセキチンリュウ | 自分の言ったことの誤りを指摘されても直そうとしないこと。また、負け惜しみをしてひどいこじつけをするような偏屈な態度。負け惜しみの強いことの例え。間違えてあべこべのことをいうこと。自分の間違いにへりくつをつけてうまく言い逃れすること。 |
| 造反有理 | ぞうはんゆうり | 反逆にも理屈がある、ということ。 |
| 聡明英知 | そうめいえいち | 聖人が備える四つの徳。聡はあらゆることを聞く。明はあらゆることを見る。叡はあらゆることに通じる。智はあらゆることを知る。 |
| 滄海遺珠 | そうかいいしゅ | 滄海中に取り残された珠。世に知られずに埋もれている賢者にたとえる。 |
| 滄海桑田 | そうかいそうでん | 世の中の移り変わりが激しいこと。 |
| 惻隠之心 | そくいんのこころ | 憐れみや思いやりのこころ。 |
| 惻隠之情 | そくいんのじょう | 人の不幸を哀れみ、かわいそうに思うこと。 |
| 即身成仏 | そくしんじょうぶつ | 密教の教義。人が肉身のままで仏になること。 |
| 速戦即決 | そくせんそっけつ | 短時間で闘争・論争の決着をつけること。短時間で戦いの勝利を得ようとすることが転じて。一気に勝敗を決してしまうこと。 |
| 即決即断 | そっけつそくだん | 時機・チャンスを逃さず、即座に決断を下すこと。 |
| 即断即決 | そくだんそっけつ | 即座に判断すること。議案や判決などを、ぐずぐずしないでその場で決めること。 |
| 則天去私 | そくてんきょし | 自己本位の考えを捨てて、自然の中において物事を見極めようとする姿勢。 |
| 息災延命 | そくさいえんめい | わざわいをなくし、無事に長生きをすること。 |
| 俗談平和 | ぞくだんへいわ | 俗談や日常的な話しことば。世間話。 |
| 率先躬行 | ソッセンキュウコウ | 人より先に自分からすすんで実行すること。衆に先んじて自ら行う意。 |
| 率先垂範 | ソッセンスイハン | 自分がすすんで手本を示す。模範を見せること。人の先に立って行動し、模範を示すこと。「垂範」は、手本を示すこと。 |
| 尊皇攘夷 | そんのうじょうい |
天皇を尊び、外敵を打ち払うこと。幕末の志士の標語。
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)