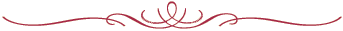
| 二字三字熟語(タ行~ワ行) |
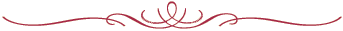
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、二字三字熟語熟語言葉のタ行~ワ行を確認しておく。 2008.8.31日再編集 れんだいこ拝 |
![]()
| タ | ||
| 大往生 | ダイオウジョウ | 苦痛や心の乱れがなく安らかに死ぬこと。 |
| 対抗馬 | たいこうば | |
| 大黒柱 | ダイコクバシラ | 家や国家などの中心になって頼りとなる人。 |
| 大車輪 | だいしやりん | |
| 大上段 | ダイジョウダン | 居丈高な態度。 |
| 大丈夫 | ダイジョウブ | とてもしっかりしていること。確かなこと。 |
| 大団円 | ダイダンエン | 劇・小説などで、すべての筋がぐあいよく解決する、最後の場面。フィナーレ。「団円」は結末の意。 |
| 大道芸 | だいどうげい | |
| 太公望 | タイコウボウ | 釣りをする人の異称(呂尚が文王に召しだされるまで毎日釣りをしていたことから) |
| 太平楽 | タイへイラク | 好き放題。のんきに構えていること。 |
| 醍醐味 | ダイゴミ | 何ものにもかえられない妙味、楽しさ。 |
| 手弱女 | タオヤメ | 優雅で優しい女性。 |
| 駄菓子 | だがし | |
| 駄洒落 | だじやれ | |
| 多数決 | タスウケツ | 賛成者が最も多い意見や議案を、全員の一致した意見とみなすやり方。 |
| 泰斗 | たいと | 泰山と北斗七星。ともに人々から仰ぎ尊ばれることから、大学者・権威者の呼び名。 |
| 台無し | だいなし | |
| 高飛車 | タカビシャ | 頭ごなしに押さえつけること。高圧的。 |
| 高嶺の花 | たかねのはな | |
| 伊達男 | だておとこ | |
| 伊達女 | だておんな | |
| 棚牡丹 | タナボタ | 「棚からぼた餅」の略で、思わぬ良いことがあること。 |
| 狸親父 | たぬきおやじ | |
| 旅支度 | たびじたく | |
| 玉手箱 | たまてばこ | |
| 玉虫色 | たまむしいろ | |
| 単独行 | とんどくこう | |
| 短日月 | タンジツゲツ | わずかの月日。 |
| 短兵急 | タンペイキュウ | だしぬけ。性急に。 |
| 断末魔 | ダンマツマ | 息をひきとる間際の苦しみ。死に際。 |
| チ | ||
| 知恵袋 | ちえぶくろ | |
| 知音 | 心をよく知りあっている親友。 | |
| 乳兄弟 | ちきょうだい | |
| 猪口才 | チョコザイ | 生意気なこと。差し出がましいこと。 |
| 長広舌 | チョウコウゼツ | 長々としゃべりたてること。 |
| 長大息 | チョウタイソク | 長く大きなため息をつくこと。 |
| 超弩級 | ちょうどきゅう | |
| 珍無類 | ちんむるい | |
| ツ | ||
| 辻説法 | つじせっぽう | |
| 土気色 | つちけいろ | |
| 美人局 | ツツモタセ | 女が夫と打ち合わせて、他の男に身をまかせ、それを種に夫がその男から金銭などをゆすること。 |
| 突慳貪 | つっけんどん | |
| テ | ||
| 出鱈目 | でたらめ | 出たとこ勝負の無責任な言動。 |
| 鉄火場 | てつかば | |
| 鉄火肌 | てっかはだ | |
| 鉄面皮 | テツメンピ | ずうずうしこと。厚顔。 |
| 出歯亀 | でばかめ | |
| 手弁当 | てべんとう | |
| 手拍子 | てびょうし | |
| 天王山 | テンノウザン | 勝敗の決め手となる重要な場面。 |
| 電車道 | でんしゃみち | |
| ト | ||
| 渡世人 | とせいにん | |
| 土性骨 | ドショウボネ | 生まれつきの性質。土性根。 |
| 道産子 | ドサンコ | 北海道生まれの人の称。 |
| 度外視 | ドガイシ | 問題にしないこと。 |
| 湯治場 | とうじば | |
| 桃源郷 | トウゲンキョウ | 俗世間を離れた別天地。 |
| 唐変木 | トウへンボク | 鈍くて気のきかない人をののしっていう言葉。まぬけ。 |
| 登竜門 | トウリュウモン | 立身出世の関門。 |
| 逃避行 | トウヒコウ | トウヒコウ |
| 泥仕合 | ドロジアイ | 互いに相手の弱点や失敗などを暴露しあってみにくく争うこと。 |
| 泥棒猫 | どろぼうねこ | |
| 丼勘定 | どんぶりかんじょう | |
| 独擅場 | どたんば | その人だけが思うままに活躍する場所。一人舞台。 |
| 頓珍漢 | とんちんかん | |
| 丼勘定 | ドンブリカンジョウ | お金の管理が大雑把なこと。 |
| ナ | ||
| 南無三 | ナムサン | 失敗したときに言う言葉。しまった。もとは仏教で、仏法僧の三宝にすがる意。 |
| 生意気 | ナマイキ | 知ったかぶりをしてでしゃばったり、差し出がましい言動をしたりすること。 |
| 生半可 | ナマハンカ | 知識や言動が正確さや徹底を欠く状態。 |
| 生兵法 | ナマビョウホウ | 知識や技術が十分身についていないこと。 |
| 生返事 | なまへんじ | |
| 並大抵 | ナミタイテイ | ひととおり。 |
| 二 | ||
| 二枚舌 | ニマイジタ | うそをつくこと。 |
| ヌ | ||
| 微温湯 | ヌルマユ | 低い温度の湯。 |
| ネ | ||
| 根無草 | ネナシグサ | しっかりした拠り所をもたない物や事のたとえ。 |
| 寝物語 | ネモノガタリ | 寝ながら話すこと。また、その話。 |
| ノ | ||
| 野放図 | ノホウズ | 放っておけば、どこまで脱線するか分からないようす。突拍子もない。 |
| 能天気 | ノウテンキ | 常識はずれで軽薄なようす。 |
| ハ | ||
| 破天荒 | ハテンコウ | 人がまだなし得なかったことを行うこと。前代未聞。未曾有。 |
| 破魔矢 | ハマヤ | 棟上のときに屋根に飾る2本の矢の形をしたもの。 |
| 破廉恥 | ハレンチ | 恥を恥とも思わないこと。鉄面皮。不正不徳の行いをすること。 |
| 白眼視 | ハクガンシ | 冷たい目で見ること。対義語は「青眼」。 |
| 端境期 | ハザカイキ | 新米が古米に代わって市場に出回り始める9、10月ころ。 |
| 裸一貫 | ハダカイッカン | 自分の体のほか、何の資本も持っていないこと。 |
| 花吹雪 | ハナフブキ | 花びらの、吹雪のようにたくさん舞い散るもの。 |
| 花言葉 | はなことば | |
| 花電車 | はなでんしゃ | |
| 破魔矢 | はまや | |
| 春一番 | はるいちばん | |
| 半人前 | ハンニンマエ | ひとり分の半分。技能や経験などが不足して、人並みの働きができないこと。 |
| ヒ | |||||
| 他人事 | ヒトゴト | 自分に関係ない事。他人に関する事。 | |||
| 一筋縄 | ヒトスジナワ | 一本の縄。普通の方法。尋常な手段。 | |||
| 檜舞台 | ヒノキブタイ | 晴れの場所。もとは、歌舞伎で使われた最高級の舞台。 | |||
| 秘密裏 | ヒミツリ |
|
|||
| 日和見 | ヒヨリミ |
|
|||
| 広小路 | ヒロコウジ |
|
|||
| フ | |||
| 不得手 | フエテ | 不得意。苦手。⇔得手 | |
| 不可解 | フカカイ | 理解できないこと。 | |
| 不可欠 | フカケツ | 欠くことができないこと。 | |
| 不気味 | ブキミ | 何となく気味が悪いこと。「無気味」とも書く。 | |
| 不行跡 | フギョウセキ | 行状のよくないこと。不行状。 | |
| 不謹慎 | フキンシン | つつしみがないこと。ふまじめなこと。 | |
| 不作法 | ブサホウ | 礼儀・作法にはずれていること。無礼。「無作法」とも書く。 | |
| 不思議 | フシギ | 「不可思議」の略。想像のつかないこと。 | |
| 不始末 | フシマツ | 不都合な行い。だらしのないこと。 | |
| 不死身 | フジミ | どんなに痛めつけられても弱らない身体。 | |
| 不条理 | フジョウリ | 筋道の通らないこと。 | |
| 不世出 | フセイシュツ | めったに世に現れないほど、すぐれていること。 | |
| 不退転 | フタイテン | へこたれずにがんばること。もとは仏道の修行を積んで、退くことがなくなる意。 | |
| 不調法 | ブチョウホウ | 行き届かず、手際の悪いこと。 | |
| 不手際 | フテギわ | 手際の悪いこと。やり方や出来が悪いこと。 | |
| 不如意 | フニョイ | 思うようにならないこと。生計が苦しいこと。 | |
| 不文律 | フブンリツ | 文章に明記されていない法。慣習法など。 | |
| 風馬牛 | フウバギュウ | 自分とはまったく関係がないという態度をとること。 | |
| 風物詩 | フウブツシ | 景色や季節をうたった歌。季節の感じを表しているもの。 | |
| 風来坊 | フウライボウ | 風のようにどこからともなくやって来た人。気まぐれな人。 | |
| 袋小路 | フクロコウジ | 行き止まりになった小さい道。物事が行き詰まること。 | |
| 仏頂面 | ブッチョウヅラ | 無愛想な顔。ふくれ面。 | |
| 仏法僧 | ブッポウソウ | 仏と法と僧。三宝。 | |
| 筆不精 | フデブショウ | 面倒がってなかなか手紙や文字を書かないこと。また、そういう性質の人。⇔筆まめ | |
| 冬木立 | フユコダチ | 冬枯れの立ち木。 | |
| 冬将軍 | フユショウグン | 寒さの厳しい冬の異称。 | |
| 無礼講 | ブレイコウ | 上下の区別なく礼儀を気にしない酒宴・会合。 | |
| 雰囲気 | フンイキ |
|
|
| 文化財 | ブンカザイ | 芸術品など、文化によって生み出されたもの。 | |
| へ | |||
| 下手糞 | |||
| 平方根 | へイホウコン | 与えられた数に対し、平方するとちょうどその数になる数のこと。 | |
| ホ | ||
| 木鐸 | 世論を喚起して世の人々を導く人。 | |
| 朴念仁 | ボクネンジン | 無口で愛想のない人。ものわかりの悪い人。 |
| 没交渉 | ボツコウショウ | かかりあいのないこと。無関係。 |
| マ | ||
| 真面目 | マジメ | 誠実で、一生懸命に事に当たるようす。 |
| 益荒男 | マスラオ | 猛々しく勇ましい男子。丈夫。 |
| 股旅物 | ||
| 摩天楼 | マテンロウ | 天に届くほどの大高層建築。 |
| 窓際族 | ||
| 愛弟子 | マナデシ | 特に期待をかけ、かわいがっている弟子。 |
| 豆台風 | マメタイフウ | 小規模な台風。 |
| 豆知識 | ||
| 眉唾 | まゆつば | |
| 眉唾物 | マユツバモノ | 信用の置けないもの。 |
| ミ | ||
| 木乃伊 | ミイラ | 死体が腐敗せずに原形をとどめたまま乾燥して固まったもの。 |
| 身支度 | ミジタク | 身なりを整えること。身ごしらえ。 |
| 水菓子 | ミズガシ | 果物。 |
| 未曾有 | ミゾウ | 今までに一度もなかった珍しいこと。「未だ曾(か)つて有らず」と読む。 |
| 未知数 | ミチスウ | 将来どうなるかわからないこと。方程式の中の文字で、数値の知られていないもの。 |
| 身代金 | ミノシロキン | 誘拐犯がさらった人の解放と引き換えに要求する金銭。 |
| 身贔屓 | ||
| 未亡人 | ミボウジン | 夫に死なれた婦人。もとは、夫といっしょに死ぬべきだったのに、まだ死なない者という自称だった。 |
| ム | ||
| 無邪気 | ムジャキ | 悪意がないこと。邪心がないこと。あどけないこと。 |
| 無尽蔵 | ムジンゾウ | いくら取ってもなくならない。「尽くること無き蔵」と読む。 |
| 無造作 | ムゾウサ | 大変なこととは考えずに気軽にするようす。 |
| 無定見 | ムテイケン | 自分の決まった考えがなく、他人に追随したり、ころころ変わったりして頼りないようす。 |
| 無頓着 | ムトンジャク | 相手の事情・思惑や細かいことについて気にかけないようす。 |
| 無分別 | ムフンベツ | 分別がないこと。前後のわきまえがないこと。 |
| 矛盾 | ||
| 胸算用 | ムナザンヨウ | 心の中で見積もりを立てること。 |
| メ | ||
| 目一杯 | メイッパイ | 許される限度ぎりぎりのところまで。 |
| 盲滅法 | ||
| モ | ||
| 目論見 | モクロミ | くわだて。目算。 |
| 門外漢 | モンガイカン | 直接それに関係ない人。専門以外の人。「漢」は、男の意味。 |
| ヤ | ||
| 八百長 | ヤオチョウ | 勝負事で、あらかじめ勝ち負けを打ち合わせておいて、表面上は真剣に争っているようにみせること。 |
| 香具師 | ||
| 野次馬 | ヤジウマ | 火事場・事故現場などでの興味本位の関係のない見物人。 |
| 厄介者 | ||
| 屋台骨 | ヤタイボネ | 一家の生計をささえるもと。屋台の骨組み。 |
| 八千代 | ヤチヨ | 八千年。または非常に長い年代。 |
| 薮蛇 | ||
| ユ | ||
| 有意義 | ユウイギ | 意義があること。 |
| 夢心地 | ユメゴコチ | 夢を見ているような心持ち。 |
| 夢物語 | ユメモノガタリ | 夢のようにはかない話。空想にしかすぎない話。 |
| ヨ | ||
| 用心棒 | ヨウジンボウ | ボディーガード。戸締り用の棒。 |
| 夜汽車 | ヨギシャ | 夜間に走る汽車。夜行列車。 |
| 横恋慕 | ヨコレンボ | 他人の妻・夫または恋人に恋をすること。 |
| ラ | ||
| 楽隠居 | ラクインキョ | 気楽な隠居生活をすること。また、その人。 |
| 落成式 | ||
| 濫觴 | 物事の始まり | |
| 乱高下 | ランコウゲ | 相場の動きが高低はなはだしいこと。 |
| 乱痴気 | ランチキ | 男女間の嫉妬。入り乱れること。 |
| り | ||
| 理不尽 | リフジン | 道理も情理もわきまえないこと。無理を言うこと。 |
| 立候補 | リッコウホ | 選挙で、候補者として届け出ること。 |
| 立太子 | リッタイシ | 公式に皇太子を定めること。 |
| ル | ||
| レ | ||
| 連枝 | 互いに同じ木に連なっている枝。血統の連なっているもの。兄弟姉妹をいい、日本では特に貴人の兄弟をいう敬語。 | |
| ロ | ||
| 狼藉者 | ||
| 老婆心 | ロウバシン | 行き過ぎた親切心。 |
| 壟断 | 利益を独占すること。独り占め。 | |
| ワ | ||
| 和菓子 | ワガシ | 日本風の菓子。製法により、生菓子・干菓子・半生菓子などに大別される。 |
| 和楽器 | ワガッキ | 日本で伝統的に使われてきた楽器。和琴(わごん)・三味線・尺八・小鼓などのこと。 |
| 和芥子 | ワガラシ | 和食で使用されるからし。洋がらし(マスタード)に対していう。 |
| 和漢書 | ワカンショ | 和書と漢籍。 |
| 和漢薬 | ワカンヤク | 和薬と漢薬の総称。生薬(しょうやく)のこと。 |
| 和漢洋 | ワカンヨウ | 日本と中国と西洋。また、和学と漢学と洋学。 |
| 和牛香 | ワギュウコウ | 和牛の肉を加熱したときに感じられる、独特の甘いかおり。 |
| 和合僧 | ワゴウソウ | 仲よく親しみ合う僧衆の教団。律では成員五人以上とする。 |
| 和三盆 | ワサンボン | 日本産の粒子の細かい淡黄色の上等な砂糖。 |
| 和集合 | ワシュウゴウ | 二つ以上の集合のどちらかに属している要素の全体からなる集合。記号「∪」で表す。ジョイン。カップ。結び。合併集合。 |
| 和声法 | ワセイホウ | 和声を基とした作曲技法。 |
| 和装本 | ワソウボン | 日本古来の装丁様式の本。⇔洋装本。 |
| 和太鼓 | ワダイコ | 日本で伝統的に使われる太鼓の総称。大太鼓(だだいこ)・楽太鼓・締太鼓などがある。 |
| 和包丁 | ワボウチョウ | 主に日本料理で使われる包丁。出刃包丁や刺身包丁など。→洋包丁 |
| 和蝋燭 | ワロウソク | 和紙や灯心草(藺(い))を灯心に用い、木蝋(もくろう)を塗り重ねて作ったろうそく。福島・愛知・福井・京都・愛媛など... |
| 輪後光 | ワゴコウ | 仏像などの、輪状の後光。 |
| 山葵色 | ワサビイロ | ワサビのような色。柔らかい黄緑色。 |
| 山葵餅 | ワサビモチ | ワサビをつきまぜた餅で小豆餡(あずきあん)をくるんだ餅菓子。 |
| 早稲女 | ワセジョ | 俗に、早稲田大学に在学する女子学生、または、卒業した女性をいう。 |
| 早稲田 | ワセダ | 早稲(わせ)を作る田。早稲の実っている田。わさだ。 |
| 早稲米 | ワセマイ | 早稲からとった米。9月ごろから出荷される。 |
| 猥褻罪 | ワイセツザイ | 猥褻な行為をする罪の総称。公然猥褻罪、猥褻物頒布等罪、強制猥褻罪など。 |
| 賄賂罪 | ワイロザイ | 収賄罪と贈賄罪の総称。 |
| 若隠居 | ワカインキョ | 老年にならないうちに家業を譲って隠居すること。また、その人。 |
| 若後家 | ワカゴケ | 年が若くて夫に死別した女性。 |
| 若白髪 | ワカシラガ | 年が若いのに生える白髪。 |
| 若大将 | ワカダイショウ | 年若い一軍の大将。 |
| 若竹色 | ワカタケイロ | 若竹のような色。鮮やかな薄緑。 |
| 若竹汁 | ワカタケジル | 春の新ワカメとタケノコのすまし汁。木の芽を添える。 |
| 若竹煮 | ワカタケニ | 春の新ワカメとタケノコを炊き合わせた煮物。 |
| 若旦那 | ワカダンナ | 商家などで、主人のあとを継ぐ息子を敬っていう語。小旦那。 |
| 若苗色 | ワカナエイロ | 染め色の名。早苗のような薄い青色。 |
| 若葉色 | ワカバイロ | 新緑のような、明るい黄緑色。 |
| 若武者 | ワカムシャ | 年若い武者。 |
| 若芽色 | ワカメイロ | 植物の若い芽のような淡い緑色。 |
| 脇在郷 | ワキザイゴウ | 都会に近接した村。 |
| 脇障子 | ワキショウジ | 神社・書院の側面の縁の、行き止まりの所に設ける衝立(ついたて)状の仕切り。 |
| 綿菓子 | ワタガシ | 白ざらめを加熱して溶かし、遠心分離機で噴き出させ、糸状になったものを棒に巻き付けた綿状の砂糖菓子。電気飴(でんきあめ)。綿飴。 |
| 綿帽子 | ワタボウシ | 真綿を広げて作ったかぶりもの。初めは防寒用として主に女性が用いた。 |
| 藁人形 | ワラニンギョウ | わらで作った人形。おもちゃとしてのほかに、実際の人間の代わりに傷つけて相手を呪(のろ)うのにも用いる。 |
| 藁半紙 | ワラバンシ | わらまたは木材パルプの繊維にミツマタやコウゾの繊維をまぜて漉(す)いた粗末な半紙。ざら紙。 |
| 藁蒲団 | ワラブトン | 綿の代わりにわらを中に詰めた布団。 |
| 藁屋根 | ワラヤネ | わらでふいた屋根。 |
| 藁工品 | ワラコウヒン | わらを原料として作った品物。むしろ・縄・帽子・人形など。 |
| 藁金剛 | ワラコンゴウ | わらで編んだ金剛草履。 |
| 草鞋親 | ワラジオヤ | 他村からの移住者が村入りを承認してもらうために、保証人に頼む家。また、その家の主人。寄り親。 |
| 草鞋酒 | ワラジザケ | 旅立ちの際に、わらじをはいたまま飲む酒。別れに際しての酒盛り。 |
| 草鞋銭 | ワラジセン | わらじを買うぐらいの金。旅費としてのわずかの金銭。 |
| 割賦金 | ワップキン | 何回かに分割して支払う金。 |
| 割看板 | ワリカンバン | 劇場で、複数の俳優の名または演目を1枚に並べて書いた看板。 |
| 割引券 | ワリビキケン | 決められた価格や料金の何割かを差し引く旨を記した券。 |
| 割引債 | ワリビキサイ | 券面に利札(りさつ)がなく、額面金額から利息相当分を差し引いた価格で発行され、償還日に額面金額が償還される債券。 |
| 割引率 | ワリビキリツ | 割引される額の割合。 |
| 割引料 | ワリビキリョウ | 手形割引の際に手形の額面金額から差し引かれる金額。 |
| 割安株 | ワリヤスカブ | 企業の株価水準を測る指標からみて、割安と判断される株式のこと。指標にはPER・PBR・PCFRなどを用いる。 |
| 吾亦紅 | ワレモコウ | バラ科の多年草。山野に生え、高さ約1メートル。葉は長楕円形の小葉からなる羽状複葉で、互生する。8、9月ごろ、分枝した茎の先に暗紅紫色の短い花穂をつける。 |
| 腕足類 | ワンソクルイ | 腕足綱の触手動物の総称。海産で、二枚貝のような貝殻をもつが、殻は体の背腹に位置する。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)