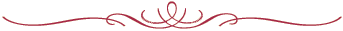
| 二字三字熟語(アカサ行) |
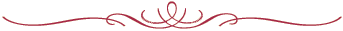
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.2.26日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
|
ここで、二字三字熟語熟語言葉のアカサ行を確認しておく。 |
![]()
| 三字熟語 |
| ア | ||
| 合言葉 | アイコトバ | 味方どうしであらかじめ決めてある合図の言葉。 |
| 青海原 | アオウナバラ | 青々として広い海。 |
| 青写真 | アオジャシン | 青地に白く設計図・文字などを焼き付けた複写写真。どうするかについての大体の計画。 |
| 青天井 | アオテンジョウ | 青空。青空を天井に見立てていう言葉。 |
| 青二才 | アオニサイ | 年が若く未熟な男。青年をののしっていう言葉。 |
| 悪趣味 | アクシュミ | 下品な趣味。人の嫌うことを好んでし、いやがらせて喜ぶこと。 |
| 悪太郎 | アクタロウ | 「いたずらっ子」の擬人名的表現。 |
| 朝寝坊 | アサネボウ | 朝寝をすること。 |
| 朝飯前 | a piece of cake(とても簡単なこと)。 | |
| 阿修羅 | アシュラ | 争いを好むインドの鬼神。悪鬼。 |
| 価千金 | アタイセンキン | とても価値があること。 |
| 頭金 | ||
| 天下り(降り) | ||
| 天邪鬼 | あまのじゃく | わざと人の言にさからって、片意地を通すもの。 |
| 雨模様 | アメモヨウ | 雨の降りそうなようす。雨もよい。「あまもよう」ともいう。 |
| 現人神 | アラヒトガミ | 人の姿になって現れる神。天皇。 |
| 安楽死 | アンラクシ | 助かる見込みのない者を、本人の希望により苦しめずに死なせること。 |
| イ | |||
| 居心地 | イゴコチ | そこにいるときの心持ち。 | |
| 依怙地 | イコジ | かたくなに意地を張ること。 | |
| 偉丈夫 | イジョウフ | すぐれた男子。たくましく堂々とした男。大丈夫。 | |
| 意気地 | イクジ | 気力。ものごとをやり遂げようとする気の張り。「いきじ」が転じた。 | |
| 居丈高 | イタケダカ | 尊大なようす。 | |
| 韋駄天 | イダテン | 猛烈な勢いで走る人。もと、仏法守護の神の名。 | |
| 一大事 | イチダイジ | 重大な事件。 | |
| 一見識 | イチケンシキ | ひとかどの識見。 | |
| 一目散 | イチモクサン | わき目もふらずに走っていくさま。 | |
| 一家言 | イッカゲン | その人独特の主張。 | |
| 一隻眼 | イッセキガン | 物を見抜く力のある独特の見識。 | |
| 一張羅 | イッチョウラ | とっておきの一枚の晴れ着。「羅」は、夏に着る薄絹のこと。 | |
| 一辺倒 | イッペントウ | ある一方だけに傾いてしまう。一つのことだけに執着する。 | |
| 一本気 | イッポンギ | いちずに思い込む性質。純粋な性質。 | |
| 居留守 | イルス | 在宅しながら、不在をよそおうこと。 | |
| 岩清水 | いわシミズ |
|
|
| ウ | ||
| 魚河岸 | ウオガシ | 魚市場のたつ河岸。 |
| 氏素性 | ウジスジョウ | 家柄。家すじ。 |
| 嘘八百 | ||
| 歌物語 | ウタモノガタリ | 和歌を中心とした物語文学。和歌に関する話。 |
| 内弁慶 | ウチベンケイ | 外では意気地がないが、家の内では威張り散らすこと。 |
| 有頂天 | ウチョウテン | 仏教用語で、欲界、色界などの形ある世界「九天」のうち、最も高いところにある天が有頂天。これは有漏(うろ、煩悩のこと)の世間の絶頂にある天ということで、この天に昇ればどんな望みも叶えられる。これが、現世的な喜びの最高にものの意に使われ、喜びの絶頂を表す言葉となった。仏陀はこの有頂天をも超越し、流転の世界を脱したと言われる。うまくいった喜びのあまり、我を忘れること。 |
| 運鈍根 | ウンドンコン | 幸運に巡り会うこと、鈍重で愚直であること、根気のあることが、成功の秘訣であるということ。 |
| エ | ||
| 似而非 | エセ | 偽物のこと。「似非」とも書く。 |
| 絵空事 | エソラゴト | 現実からかけはなれたでたらめ。 |
| 江戸前 | エドマエ | 江戸湾(東京湾)で獲れる魚の称。もとは「江戸の前の海」の意。江戸風。 |
| 円熟味 | エンジュクミ | 十分に熟達して豊かな内容を持ったさま。 |
| オ | ||
| 往生際 | オウジョウギわ | 死に際。あきらめ。 |
| 大海原 | オオウナバラ | 海の美称。広々とした海。 |
| 大袈裟 | オオゲサ | 実際より誇張したさま。 |
| 大御所 | オオゴショ | 隠退しているが、なお隠然たる勢力を有する者。 |
| 大雑把 | オオザッパ | 細かいことにこだわらないこと。おおまか。 |
| 大時代 | オオジダイ | ひどく古風なこと。 |
| 大手、大手筋 | 城の正面。追手の転化したもの。反対は、からめ手。 | |
| 幼馴染 | オサナナジミ | 小さいときからの友人・知人。 |
| 御題目 | オダイモク | 口先だけの主張。 |
| カ | ||
| 快気祝 | カイキイワイ | 病気の全快を祝うこと。 |
| 街路樹 | ガイロジュ | 道路に沿って植えつらねた樹木。 |
| 案山子 | カカシ | 鳥獣をおどしてその被害を防ぐために田畑に立てた人形。 |
| 河川敷 | カセンシキ | 河川法によって規定された河川の敷地。 |
| 片意地 | カタイジ | がんこに我意をたてとおすこと。 |
| 金釘流 | カナクギリュウ | 金属に釘で書いたように見える下手な字のこと。 |
| 過不足 | カブソク | 過ぎたことと足らぬこと。 |
| 間一髪 | カンイッパツ | 非情に切迫していて、あと少しで危険な事態になるたとえ。髪の毛一本が入るほどのわずかなすきま、の意。 |
| 閑古鳥 | カンコドリ | カッコウ。 |
| 感無量 | カンムリョウ | しばらく感慨に浸って、何もいえない状態になるようす。感慨無量。 |
| キ | ||
| 杞憂 |
杞の国の人が、天が落ちてこないか憂いたという故事より、取り越し苦労の意味。 |
|
| 生一本 | キイッポン | 心が真っ直ぐで、思い込んだらそれにひたむきに打ち込んでいくようす。 |
| 几帳面 | キチョウメン | 物事に隅々まで気をつけ、きちんとするさま。 |
| 急先鋒 | キュウセンポウ | 真っ先に立って進むこと。また、その人。 |
| 橋頭堡 | キョウトウホ | 橋をまもるために築く陣地。川や海をへだてた敵地につくる拠点。 |
| 桐一葉 | キリヒトハ | 桐はほかの木より早く秋の気配を感じて落葉することから、一枚の桐の葉の落ちるのを見て、形勢の悪化、衰亡の兆しが現れたことの暗示とする。 |
| 麒麟児 | キリンジ | 将来、大成する期待が持てる、非常に優秀な少年。 |
| 近似値 | キンジチ | 近似計算によって得られた数値。 |
| 金字塔 | キンジトウ | 後世まで残るすぐれた事業。 |
| ク | ||
| 空中戦 | ||
| 草野球 | ||
| 糞味噌 | ||
| 糞度胸 | ||
| 口上手 | ||
| 口下手 | ||
| 口八丁 | ||
| 口喧嘩 | ||
| 口真似 | ||
| 口約束 | ||
| 口達者 | ||
| 黒装束 |
|
|
| 黒魔術 |
| ケ | ||
| 閨秀 | 主に文学や書画にすぐれた才能をもつ女性をさしていう。 | |
| 形而上 | ケイジジョウ | 形のないもの。見たりさわったりできない、抽象的・観念的なもの。⇔形而下 |
| 下克上 | ゲコクジョウ | 下の者が上の者をしのぎおかすこと。「下剋上」とも書く。 |
| 月桂冠 | ゲッケイカン | 月桂樹の冠。古代ギリシアで、競技の勝利者にかぶせた。 |
| 下馬評 | ゲバヒョウ | 世間で種々の評判をすること。また、その評判。 |
| コ | ||
| 小意気 | コイキ | ちょっとしゃれていること。小粋。 |
| 恋女房 | コイニョウボウ | 恋愛して結婚した妻。 |
| 紅一点 | コウイッテン | 多くの男性の中に、ただ一人の女性がいること。 |
| 好好爺 | コウコウヤ | 優しい一方のおじいさん。 |
| 好事家 | コウズカ | ふつうの人には何の興味もないような物事に関心を寄せる人。 |
| 嚆矢 | 物事の始まり。昔、闘いの火ぶたを切るとき、最初にかぶら矢を射交わしたことによる。 | |
| 古希 | 70歳。 | |
| 小気味 | コキミ | 「気味」を強めていう語。 |
| 小細工 | コザイク | すぐそれと見破られるような工夫。 |
| 御破算 | ゴハサン | 今までやって来たことがすっかりだめになって、元の状態にもどること。 |
| 御利益 | ゴリヤク | 神仏の霊験。効能。 |
| 金輪際 | コンリンザイ | あくまでも。絶対に。もと、仏教で厚い大地の最下底の金輪のある所の意。 |
| サ | ||
| 左遷 | 中国の律令政治時代の「右尊左卑」に由来。 | |
| 左袒 | 味方すること。賛成すること。着物の左をかたはだぬぎにする意。前漢の周勃(しゆうぼつ)が、朝廷に味方する者は左袒せよ、と言った故事による。 | |
| 最高潮 | サイコウチョウ | いちばん緊張し興奮する場面や状態。クライマックス。 |
| 歳時記 | サイジキ | 一年中の行事とそれにまつわる生活などを書いた本。 |
| 早乙女 | サオトメ | 手甲、脚絆、赤襷姿で農作業に臨む女性。 |
| 殺風景 | サップウケイ | 美しさや趣きが何も感じられないようす。 |
| 茶飯事 | サハンジ | 毎日経験するような、ありふれた事。 |
| 五月雨 | サミダレ | 梅雨どきの雨。 |
| シ | ||
| 式次第 | シキシダイ | その式の内容と順序。 |
| 試金石 | シキンセキ | それが本物か、またはうまく行くかどうかを見極めるためにやってみる物事。 |
| 七福神 | シチフクジン | 七人の福徳の神。 |
| 注連縄 | シメナワ | 神前などに掛け渡して神聖な場所とその外との境界を示し、不浄の入るのを禁じるための縄。 |
| 仕舞屋 | シモタヤ | 以前は商売をしていたが、やめてしまった家。 |
| 集大成 | シュウタイセイ | たくさんのもの広く集めて一つのものに完成すること。 |
| 修羅場 | シュラバ | 悲惨な戦場。生存競争の激しい現実社会をたとえていう言葉。 |
| 上機嫌 | ジョウキゲン | 機嫌がよいこと。⇔不機嫌。 |
| 正念場 | ショウネンバ | 歌舞伎などで、俳優にとって失敗が許されない最も重要な場面。 |
| 処方箋 | ショホウセン | 医師が処方を書き記した文書。 |
| 蜃気楼 | シンキロウ | 熱や冷気によって大気中の光が屈折し、空中や地上に何か物があるように見える現象。 |
| 真骨頂 | シンコッチョウ | それが本来もっている真価をよく現わしている姿。 |
| 神通力 | ジンツウリキ | 何事もなしうる霊妙な力。 |
| ス | ||
| 水蒸気 | スイジョウキ | 水が蒸発して気体となったもの。 |
| 枢機卿 | ||
| 数奇屋 | スキヤ | 茶の湯のために建てた茶室。 |
| 助太刀 | スケダチ | 昔、あだ討ちなどの手助けをしたこと。また、その人。 |
| 助兵衛 | ||
| 素寒貧 |
| セ | ||
| 掣肘 | わきから他人の肘をひいて、行動を妨げること。そばから干渉して自由を奪うこと。 | |
| 赤裸々 | セキララ | 包み隠しのないこと。 |
| 世間体 | セケンテイ | 外聞。世間への体面。 |
| 雪月花 | セツゲツカ | 雪と月と花。四季における美しい風物。 |
| 瀬戸際 | セトギわ | さしせまった場合。 |
| 先覚者 | センカクシャ | 学問や見識にすぐれた人。世間に先んじて、物事の道理や移り変わっていく先を覚る人。 |
| 善後策 | ゼンゴサク | あとのためによく計る策。 |
| 千秋楽 | センシュウラク | 相撲や演劇などの興行の最後の日。 |
| 先入観 | センニュウカン | 実際にその物事を見聞きする以前に、あらかじめつくりあげられている固定的な見解や観念。「先入見」「先入主」も同義。 |
| 千里眼 | センリガン | 遠隔の地の出来事を直覚的に感知する神秘的能力。 |
| ソ | ||
| 走馬灯 | ソウマトウ | 回転するにつれて影絵が回って見える灯籠。 |
| 素封家 | ソホウカ | 財産家。大金持ち。「素」はむなしいこと。「封」は領地。領地や官位を持っていないが、非常な資産を持っている者という意味。 |
| 忖度 | 他人の気持をおしはかること。 | |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)