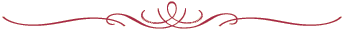
| 153 | 必須故事来歴集 |
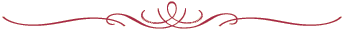
(最新見直し2013.07.20日)
| 【知識教養】 |
| 「巳、己、已」 |
| 「巳は上に、己は下に、しこうして中までなるは既に已みなむ」。 |
| 「昭和」 |
| 「百姓昭明、万邦協和」(中国書経)より |
| 「太平洋、大西洋」 |
| (解説) 世界の三大海洋は、太平洋、大西洋、インド洋。太平洋の面積は1億6524万平方キロで、地球海洋面積の46%を占めている。地球上の陸地総面積よりも一回り大きい。大西洋は太平洋の半分の8244万平方キロ。 太平洋の名前の由来は、マゼランに拠る。1519年、ポルトガル軍人マゼランが提督となって5隻の艦隊を率いてスペインを出港。南アフリカ南端の後のマゼラン海峡を越え、やがてグアム島を経てフィリピン諸島に至った。マゼランは、マゼラン海峡以降の広大な海の航海中幸運にも一度の暴風雨にも遭遇しなかったので、ラテン語で「Mar Pacifico」(太平なる海)と命名した。その漢字訳が「太平洋で」で、「太」を使う。 大西洋は、中国の明国(1368年~1644年)で布教活動していたイタリア人宣教師マテオ・リッチが命名した。「大」を使う。 太平洋は、「太平+洋」、大西洋は「大+西洋」ということになる。・ |
| 「馬鹿」 |
| 絶大な権力を誇った秦の高官・趙高(ちょうこう)が、幼少の皇帝に鹿を「馬です」と言って献上した。皇帝が笑って左右を見わたすと、居並ぶ家臣は誰もが趙高を恐れ、口々に鹿を馬だと追従した。趙高のこの故事から「鹿を指さして馬と為(な)す」という慣用句が生まれている。権力をかさに着て間違ったことを強引に押し通す、という意味になる。「馬鹿(ばか)」の語源ともいわれるが、真偽のほどは定かでない。 「馬鹿」は古くは、「破家」とも書かれた。家財を台なしにするほど愚か、の意味だろう。権力の横車を押し、国家の家財をも台無しにするのも「破家」ということになる。「史記」(秦始皇本紀)は、栄耀(えいよう)栄華の秦帝国も趙高の専横からほどなくして滅びた、と記している。(「2006.10.21日付け読売新聞編集手帳」参照) |
| 「呉越」 |
|
(解説) |
| 「月旦」 |
| (解説) 後漢の許しょう(きょしょう)が毎月はじめに郷里の人々の批評をしたことから始まる故事で、人物評のことを云う。 |
| 「皮肉」 |
| (解説) 中国禅宗の祖、達磨(だるま)大師は、門人に対して、「お前の得たものは皮だ」、「お前の得たものは肉だ」とかいって、門人の悟りの心のレベルをそれとなく、しかも辛辣に批評した。そこから「皮肉を云う」が婉曲的ではあるが辛辣な批判という意になり、これが昂じてあてこすりや嫌味なことを指すようになった。 |
| 「濫觴(らんしょう)」 |
|
(解説) |
| 「出藍の誉れ(しゅつらんのほまれ)」 | ||
中国の戦国時代の儒家で、孟子の性善説と反対の性悪説を主張していた荀子(じゅんし、筍況、(B.C.300~240頃)の次の言葉が遺されている。
関連するところを現代口語で訳せば、「学問というものは止まる事がないものである。藍染めに於いて、青い色は藍(藍玉と呼ばれる染色の材料)から作り出すが、元の藍よりも鮮やかな青色をしている。冰は水から出来るものだが、水よりも冷たいものだ」という意味である。西暦1世紀の後半の後漢(ごかん)に編纂(へんさん)された「新論(しんろん)」にも次のような同じような記述がある。
この例えから、弟子が師匠に優る意に通じる。「藍」が師匠として、そこから作り出された「青」という弟子は元(師匠)の藍よりも優れていると例えられ、これを「出藍の誉れ」と云う。広辞苑は、「弟子がその師匠を越えてすぐれているという名声」と記している。中国の南北朝時代の北朝に李謐という人物が居た、李謐は初め孔潘に就いて学んでいたが、その進歩はめざましく、数年の後、孔潘は李謐の方が自分より学問が進んだと考え、自ら進んで李謐の弟子になった。この時、同門のものは筍況のこの言葉を引用して、李謐の優秀さと孔潘の実直さを褒め称えている。 荀子のこの言葉にも拘わらず、世の大方は、弟子はいつまで経っても弟子であり、一人前或いは自分と同等と認めたがらない。ましてや、弟子の「弟子」になるなどとんでもない事例が多い。「学は、もって已むべからず」を踏まえないからであろう。もっぱら、「青は藍より出でて藍よりも青し」という言葉で表現されることが多く、水と冰のたとえは使われることはあまりない。(「出藍の誉れ」その他参照) |
| 「矛盾」(韓非子) |
|
(解説) |
| 「統率」 |
| 「戦略」 |
| 「決断」 |
| 【人生】 |
| 【交際】 |
| 【処世】 |
| 【人物】 |
| 【練磨】 |
| 「水揚げ」 |
| (解説) 水揚げの語源は、江戸時代初期、売春制度の確立と共に用いられるようになった。「色道大鏡(しきどうおおかがみ)」によれば、女郎の初仕事に新ぞう(船)を仕立て、これを買う者を水上の客と云い為したとある。「この名目、新ぞう女郎を舟に比していい出たる詞なり」。いわば進水式ということになる。ちなみに、水揚げ後の遊女を「新造」と云い、ここから転じて若妻のことを「御新造」というようになった。 |
| 「漁夫の利」 |
| 「三顧の礼」 |
| 「塞翁が馬」 |
|
(解説) |
| 「会稽の恥」 |
| 敗戦者の恥辱 |
| 「刻舟求剣」 |
| (解説) 舟に刻みて剣を求む。秦代の書「呂氏春秋」に書かれている。楚の国の人が舟で川を渡っている時、大切な宝剣を水中に落とした。慌てて剣を落とした船べりの場所に印を刻み、舟を止めてこれを目印に川底を探した。しかし、僅かの間にも舟は動いており、見つかる筈も無い。手法を間違えた方法では実を結ばない、時勢の変化を見誤ってはならない、との戒め。 |
| 「君子の三畏」(論語) | |
|
| 「背水の陣」 |
| 「三舎を避く」 |
| 「他山の石」 |
| 「他人の謝った言行も、自分の行いの参考になる」の意。出典は、詩経の小雅「鶴鳴」(かくめい)の「他山の石、以って玉を攻(みが)くべし」。 |
| 「呉下の阿蒙」 |
| 「臥薪嘗胆」 |
| (解説) 古代中国で宿命的な抗争を続けた呉越二国間の戦いの故事。紀元前496年、呉王こうりょは越との戦いに敗れ、息子の夫差に「越を忘れるな」と遺言して死んだ。その三年後、夫差は越軍を会稽山に囲み破壊寸前まで追い込む。但し、越王こうせんの和議の嘆願を受け入れ敗走させる。九死に一生を得たこうせんはこの恥を忘れず、国に帰るや臥薪(たきぎの上で寝る)し始め、常に干し肝(熊の胃という苦い薬)を身の回りに置き、飲食のたびになめ自戒し、ついに紀元前473年、呉王夫差を姑蘇山に囲み、これを滅ぼし会稽の恥をそそいだ。 |
| 「合従連衡」 |
| 「四面楚歌」 |
| (解説) このことわざの意味は、四方皆敵の孤立無援の窮地をあらわしている。楚の項羽が漢の高祖にガイ下(がいか)で包囲された。夜、項羽は自陣の四方に、楚歌を聞き、楚人が皆、漢に味方してしまったと驚いた故事から、孤立無援のことを四面楚歌といった。(「史記」) |
| 「呉越同舟」 |
| 【酒池肉林】 |
| 「国士無双」 |
| 【酒池肉林】 |
| 「温故知新」 |
| 【社会批評】 |
| 【弱肉強食】 |
| (解説) 唐の韓愈(かんゆ)が文暢(ぶんちょう)という僧侶の旅立ちの際に送った文章の一節に、鳥や獣の生存競争の厳しさを述べて、「弱の肉は強の食」と云ったところから来ている。韓愈が主張したのは、鳥獣世界の自然摂理となっている捕食関係(生物の食物連鎖現象)が、太古よりの人間世界にも当てはまり、禽獣同様の生存競争をしてきている。尭(ぎょう)、舜(しゅん)を始祖とする儒教の教化により始めて秩序ある文明世界になったのだ、ということであった。この比喩が「弱肉強食」という4字成語となり、伝えられていくことになった。 |
| 「鳴かず飛ばず」 |
| 「兵は死地なり」 |
| 「先んずれば人を制す」 |
| 「奇貨置くべし」 |
|
(解説) |
| 「四十にして惑わず」 |
| 「人生、意気に感ず」 |
| 「刎頸の交わり」 |
|
(解説) |
| 「愚公山を移す」 |
| (解説) このことわざの意味は、物事は急がず、無理をせず、こつこつと真面目に努力すれば必ず希望通りの事が成し遂げられるというたとえ。 昔、中国に愚公という老人がいた。この人は家族と共に二つの山を越えた所に住んでいたが、年齢も90に近いのでこの山歩きが辛くなった。 そこで家族を集めて「この二つの山をどこかに移そう」と相談した。家族の中に知者といわれる老人がいて、「あなたの年齢と体力でそのようなことは到底不可能だ」 と止めたところ、愚公は「私には子もあり、孫もある。そして、子や孫もやがて子や孫を作るから、子々孫々この仕事を受け継いでいけばよい。山はいつまでも今のままで、大きくはなるまい」と言った。時の天帝は愚公の根強さに感心し、山を他に移してやったという。このようないわれのことわざのようです。 まあ、現実に山を移せるかどうかは別として、他の人々から見れば到底不可能なことを、子々孫々に渡るような長い時間をかけてでもやり通そうとした気概に感心したのでしょう。こういう話は少なくなりました。皆、小さな目先の成功ばかりを目指しているのが現代社会ではないでしょうか。 |
| 「泰山は土壌を譲らず」 |
| 「水清ければ魚棲むまず」 |
| 「天知る地知る」 |
| (解説) このことわざの意味は、悪いことは誰も知るまいと思っても自然と現れるものであって決して隠し仰せるものでない。中国で王密という人が高官であった揚震の家を深夜密かに訪れて賄賂を送ろうとしたとき揚震はこういって断った。「天知る地知る我知る人知る」というもので、後年、「四知の戒め」 として尊ばれている。「今あなたが行おうとしている悪いことは、私とあなたの他に天地の神々と、やがて他の人が知ることになりましょう。 悪いことや不正は隠そうとしても、必ず現れるものです」。このような意味合いのことわざです。 |
| 「三人行けば必ず我が師あり」 |
| 「忍の一字は衆妙の門」(呂本中〈りょほんちゅう〉) |
| 「韓信の股くぐり 」(史記) |
| 「曽参人を殺す (そうしんひとをころす)」 |
|
(解説) |
| 「道は近きにありて遠きに求む 」 |
|
(解説) |
| 「狡兎死して走狗烹らる」 |
| 「知らぬ顔の半兵衛」 |
| (解説) 尾張の織田信長と美濃の斎藤龍興(たつおき)との間に戦いが始まろうとしていた。その時織田方では、斎藤家の軍師竹中半兵衛の知謀を警戒し、できれば味方につけて取り込もうと考えた。そこで前田犬千代を半兵衛に接近させた。犬千代は半兵衛の娘、千里と親しくなり、半兵衛の心を動かそうとしたが、半兵衛のほうが一枚上手。知らぬ顔をしながら、逆に犬千代を利用して織田方の情報を入手。斎藤家を勝利に導いたという。この故事から、知らぬ顔の半兵衛は、知っていながら知らないふりをして、相手の意にならないことの意に。 |
| 「百聞は一見に如かず」 |
| (解説) その昔、中国の漢の国で反乱が起った際に、鎮圧の命を受けた趙充国将軍は、「百聞は一見に如かず」と発して、直ぐに戦地に向かい、地形や兵力などを入念に調べて作戦を立て、一年後に平定した。物事を処理する上で、机上の空論の議論を費やすよりも実地の調査が肝心という意味で広く伝えられることになった。 |
| 「一張一弛(いっちょういっし)」 |
| (解説) 出典は「例記」(らいき)。「張りて弛めざるは、文武も能くせざるなり。弛めて張らざるは、文武も為さざるなり。一張一弛(いっちょういっし)は、文武の道なり」(弓は張ったままにして弛めないと、弓の力が落ちるものであるが、そんなやり方では、文王・武王でも世の中を治められない。弦を張ることなく弓を緩めたままにしておくと、弓そのものが狂ってくるものだが、そんな治め方は文王も武王もとらなかった。弓は或る時は張り、又或る時は緩めるのが良いように、文王や武王は、寛大であったり厳格であったりの、ほどよい治め方をした)(文王・武王とは、殷王朝を倒して周王朝を建国した文王と武王父子を云う) |
| 「八百長(やおちょう)」 |
|
(解説) |
| 【こんにゃく問答】 |
| (解説) 落語の話で、仏教語を駆使した名作で、サゲ(落ち)も「見立て落ち」とよばれる傑出したものとなっている。同じ身振りを二人でそれぞれまったく違う意味にとる滑稽さが値打の落語となっている。三代目林家正蔵(俗に二代目といわれるが、正しくは三代目)の作といわれる。 あるお寺のお坊さんが、旅の僧から問答を申し込まれた。問答に負けると、から傘一本で寺から追い出される。その話を聞いたコンニャク屋の主人が、「私が代わりに相手をしてみましょう」と買って出た。旅の僧がやって来た。コンニャク屋の主人は問答で何を聞かれても黙っていることにしていた。旅の僧は無言の行問答と勘違いし、両手の親指と人差し指とで小さな○(マル)を作った。コンニャク屋の主人は、両方の腕で大きなマルを作って見せた。次に、旅の僧が右手の10本の指を突き出すと、コンニャク屋の主人は右手の5本の指を広げる。最後に、旅の僧が右手の3本の指を突き出すと、コンニャク屋の主人が右の人差し指を目の下に当てアカンベエをした。 旅の僧は恐れ入り、「大和尚の胸中は大海のごとし。十方世界は五戒で保つ。三尊の弥陀(みだ)は目の下にあり」、「到底拙僧の及ぶところにあらず。両三年修行を致しまして……」と述べ逃げ出した。曰く、お日様のつもりで○(マル)を出したらお月様と答えられた。次に、10本の指で「十方世界は」と問えば、「五戒で保つ」との仰せ。次に、指3本で「仏教で言う三千(さんぜん)世界、つまり大宇宙とは?」と問えば、「してはならない五つの戒めで保たれる」と答えられた。さらに「人が受ける四つの恩はどこにあるか」と問えば、「目の下にあり」と答える。これはかなわない。 ところが、コンニャク屋の主人曰く、「問答なんてつまらないもんだなあ。お前のところのコンニャクはこんなに小さいだろうというから、いやこんなに大きいぞと言ってやった。10丁でいくらかと値を聞いてきやがった。500だって言ったら、一つ三文(さんもん)か?と聞いてくるから五文だと答えてやった。それを四文にまけろと言うから、アカンベエをしてやった。そしたら逃げていったよ。 互いに全く別の話をしているのに、話はつじつまが合ってどんどん進展していくサマを面白おかしく語っており、ここから「こんにゃく問答」と云う言葉が生まれている。会話が一見通じているようで本当は全く噛み合っていないサマを云う。(モノローグ(monologue)は独白、ダイアローグ(dialogue)は対話) |
| 【木鶏(もっけい)】 |
|
(解説) 木鶏という言葉はスポーツ選手に使用されることが多く、特に日本の格闘技(相撲・剣道・柔道)選手が好んで使用する。昭和の大横綱の双葉山が、連勝記録が69でストップした日、「我、未だ木鶏たりえず」と安岡正篤に打電したという故事がある。 |
| 【杞憂(きゆう)】 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 杞憂(きゆう)は、その昔、中国の杞の国の人が、天が落ちてこないか地が割れやしないのかを憂えたという故事に基づく、将来のことについてあれこれと無用の心配(取り越し苦労)をすること。「杞人の憂い」とも云う。
(出典) 列子の天瑞編の第十四章より(小林信明著、明治書院、昭和42年5月25日初版の新釈漢文大系22列子)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 以上が「杞憂」の原文である。著者は中国の戦国時代の鄭(てい)の人であり、その名を列禦寇(れつぎょこう)と云う。道家の思想家としては列子(れっし)の名で知られている。老子よりややおくれ、荘子より前、孔孟の中間の頃の人ともいうが伝未詳である。唐の玄宗は冲虚真人と諡(おくりな)した。春秋戦国時代の著名な人物の多くは、司馬遷の『史記』によって伝えられているが、列禦寇は列伝を立てられていない為、その事績を知ることができない。列禦寇の著作とされる『列子』から、その人となりは恬淡(てんたん)としており、乱世に巻き込まれることなく、鄭(てい)の国に四十年間隠棲していたことが分かる。但し実在の人物ではなかったとする意見もあり実像は定かではない。『列子』という書の基本的な体裁は、前漢の時代には整っていたと考えられる。しかし、現在に伝わる『列子』に記されている内容のなかには、戦国時代の思想ではなく、漢から魏晋時代にかけての思想も幅広く含まれており、成立の過程についても諸説紛々(ふんぷん)としている。そういうベールに包まれてはいるが『列子』は同じく道家の必読の書である『荘子』と並び寓言(ぐうげん)に富んだ書として知られている。そのなかの一節に「杞憂」がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中国故事「杞憂」の面白さは、「天が落ちてこないか地が割れやしないのか」の疑問に対して、入れ子構造のような手法で3人の回答者が登場し問答をしていることにある。天が崩落せず、地が陥没しない理由については、恵施(けいし)と黄繚(こうりょう)という人物が問答を交わしたことが『荘子』にも見えており、人々の議論の対象であったことが伺われる。杞憂の故事は中国の漢民族の理論好きな面を示しており、この点にも興味がわく。 |
| 【「九仞の功を一簣に虧く」(きゅうじんのこうをいっきにかく)】 |
| 出典は「書経」にある「周の武王を家臣の召公が諌めた」話。周の武王が、殷の紂王を討ち、殷を滅ぼして新に周朝を創めてから間もなくのことです。周の威令は遠く四方の蛮夷の国々にまで及び、各地から貢物が献上されてきました。当時、西方に旅という国があり、旅からもゴウが献じられてきた。ゴウとは高さ四尺に及ぶ大犬のことで、能く人の意を解すという珍獣だった。この贈り物をまえにして、武王は大いに喜んだが、その時、召公が、珍奇なものに心を奪われて、せっかくの周王朝の創業を危うくしてはならないと諌めた言葉のなかに出てくる。「九仞」の「仞」は八尺のことで、「九仞」はその九倍ですから非常に高いものと言う意味です。例えば、土で山を築くときに「九仞」の一歩手前まで築いていてもそこで油断して怠れば山は完成しないし、それまでの努力(功)も無駄になってしまうと言うことです。「一簣」は、「一籠」で「一籠の土」ということです。あと「一籠」で九仞の高さになったのにを表しています。つまり「今一歩と言うところで油断したり、手違いをしたりすると失敗して、それまでやってきたことが無駄になる」と言う譬えである。 |
| 【「男子三日あわざれば、刮目してみるべし」()】 |
| 原文は、「士別れて三日なれば刮目して相待すべし」 。見所のある人物は3日も経つと見違える程成長しているものだと言う意味。出典は、三国志演義。三国志の3国の1国・呉の国に呂蒙という勇猛な武将がいた。呂蒙は勇猛さで呉の国はおろか他の2国の魏や蜀にもその名が響いていたが無学だった。君主の孫権が、少しは学問を学び人間の幅を広げるよう呂蒙に諭した。それから時が流れて、呉の国有数の知将魯粛が前線司令官として赴任する途中に呂蒙を訪ねた。呂蒙は、魯粛の赴任先の正面に、当時中国で最強と言われた蜀の関羽将軍が指揮官として居ると聞いて、関羽の性格を分析し、適切な献策をした。呂蒙は学問に励み、いつしか勇に智が伴う武将になっていた。武骨な呂蒙しか知らない魯粛は驚き、「いつまでも、呉の城下を走り回っていた蒙ちゃんと言う訳ではないなぁ(復た呉下の阿蒙にあらず)」と言ったところ、呂蒙は、「士別れて三日なれば刮目して相待すべし」と言った。この故事による。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)