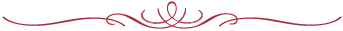
| その10 | 政治、左派運動考察 |
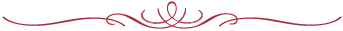
更新日/2024(平成31.5.1栄和改元/栄和6)年.2.24日
| 【「伝記の重要さ」】 | |
|
「戦後日本の宰相たち」(渡辺昭夫編、中央公論社、1995年)
|
| 【「他人事(ごと)主義の非」】 | |
ナチスに抵抗した牧師のマルチン・ニーメラの有名な言葉。
|
|
マルチン・ニーメラの指摘は「他人事(ごと)主義の非」をうまく表現している。しかし、ナチスを意識してのみ適用すべきではなかろう。ユダヤ原理主義のそれこそ真性陰謀主義的圧政であろうから。れんだいこがもじり歌する。
|
| 【「近眼的組織主義の非」】 | |
|
19世紀末のイギリスの歴史学者、バーカー(J.E.Barker)が国の興亡について語っている(安岡正篤著「活眼活学」)。
|
| 【「教本字面読みの非」】 |
| 教本は単に字面を読んだだけでは真意が分からない。文書は行間を読まなければ本当の意味は分からない。 |
| 【マックス・ヴェーバー「職業としての政治」の名言】 |
| マックス・ヴェーバー「職業としての政治」の名言。 |
| 「政治とは、情熱と判断力の二つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である」。 |
| 「現実の世の中が―自分の立場からみて―どんなに愚かであり卑俗であっても断じて挫けない人間。どんな事態に直面しても『それにもかかわらず!』と言い切る自信のある人間。そういう人間だけが政治への天職を持つ」。 |
| 【日本に棲みつく正体不明の謎の鳥】 | |
|
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)