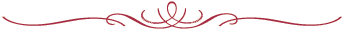
| 【論争】論理学 |
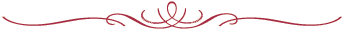
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.1.13日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 「論争論理学」の分野も考究を要する。人は一般に、「論争」を通じて認識を深めることができるので、好んで論争に向わねばならない。いわば「論争の効用論」であるが、案外と理解されていない。この場合、論理学というより「論争の際のルールとマナー基準」の確立に向っておく必要がある。如何なるルールとマナーの下で論争がなされるべきかの基準設定論である。(以下略後日に記す) |
すえいどん「人はなぜ論争をするのか? 」。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)