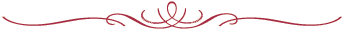
| �y�F���z�_���w |
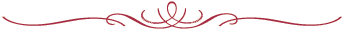
�@�X�V���^�Q�O�Q�R�i�����R�P�D�T�D�P�h�a�����^�h�a�T�j�N�D�P�D�P�R��
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
| �@�����ł͍ŏ��̍��ڂł���F���_�i���۔F���̍�@�A��Ƃ��ĕ��́j�ɂ��čl������B�_���w�̑Ώۂ̍ŏ��P�ʂ́A���ۂ��ǂ�����̂��A���f����̂��A���H�ɐ������̂��Ƃ������Ƃ̑����Ƃ��Ă̔F���_����n�܂�Ƃ������Ƃł���B�_���w�̊w�Ɏ���O���ł���B �@�F���w�͏]���T�O�_�Ƃ��Ă�Ă��邪�A�ڂ�������ƁA�F���_�A�F�����x�_�A���ʘ_�A�T�O�_�A���e�_����\������Ă��邱�Ƃ�������B��������A�f�{�Ƃ��Č���w�ƓN�w�̍��{��肪�W���Ă���B����ɕ��͋Z�p�I�Ȗ���_�������B�����ݒ肷��Ƃ��낪��������H�_���w�̊w�I�̋Ƃł���B |
| �y�F���_�z | ||||||||||||
| �@�F���_�Ƃ́A�]���A��ʂɂ͊��o�Ƃ̑Η��Ƃ��Ė���闝���I�v�Ҋ����̂悤�ɂ݂Ȃ���Ă��邪�A�����ł͂Ȃ����낤�B�l�Ԃ������Ă��邠����\�́i���o�A�k�o�A���o�A���o�A�G�o�A�@�m�o�A�����j���A�ǂ̂悤�Ɋ��o���͎v�l�Ŕc�����A����ŕ\�����邩�̑��`�I�̈�̎v�Ҙ_�Ɖ]����B�܂�A�l�Ԃ̔F�������͊��o��r��������̂ł͂Ȃ��B�����������ׂ����낤�B���̋K�����������H�_���w�̊w�I�̋Ƃł���B�Ȃ����̂悤�Ɏ��^���邩�Ƃ����ƁA���˂ΈႢ��������Ȃ�����ł���B �@�F���́A�O�ϖ@�i�̌��A�o���A�ώ@�A�����j���琶�܂�邪�A������̗͂����Ɠ��ϓI�ґz�@��������܂��B����������͔��f�ɂ���čX�ɋᖡ�����B |
||||||||||||
|
�@�F���ɂ́A��i�܂Ȃ��ėǂ�����ςƂ����̂����邪�A����͊w�ɂȂ�Ȃ��B�ߑ�N�w�̈̑�ȓN�w�҂̈�l�C�M���X���x�[�R���iFrancis Bacon�A�P�T�U�P�`�P�U�Q�U�N�j�́A�Ό��Ƃ��A������i����ρj�Ƃ��A���e�ɂ��������u�C�h���v�ƌĂ�ōl�@�����B����ɂ��A�C�h���ɂ͎��̂S��ނ�����Ƃ����B�_���w�ɂ����ẮA������m��r�����邱�Ƃ��O��ɂȂ��Ă���B
|
||||||||||||
|
�@�F���_�ł́A�P�E����w��̌��t�̊e�Ӗ��̒�`�ƕ��@�A�Q�E�B���_�ƊϔO�_�A�ُؖ@�ƌ`����w�̍��{���A�F���̐��x�_�A�R�E�T�O�̒�`�A�S�E����̍\�����͂������B�ȉ��A�P�̌���w�́A�_���w�ȑO�̖��Ƃ��čl�@��ʂ̉ӏ��ɏ���B�Q�̗B���_�ƊϔO�_�A�ُؖ@�ƌ`����w�̍��{�����ʂ̉ӏ��i�}���N�X��`�_�̍��j�ɏ���A�����ł͔F���̐��x�_�����グ��B�R�̊T�O�_���N�w�̏͂Ř_����B�S�̖���̍\�����͂ł͊O�`�\�������グ�邱�Ƃɂ���B |
| �y�F���̐��x�_�z |
|
�@�_���w�̍ŏ��ɂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ����ƂƂ��āy�F���̐��x�z��肪����B�������͂���B�y�F���̐��x��肻�̈�z�Ƃ��āA�]���ւ̋q�ϓI���f�̒���@���Ƃ�����肪����B�܂�A�X�g���[�g�ɔ��f����̂����܂��Ĕ��f����̂��Ƃ������ł���B�]���A�_���w�ケ�̖��̍l�@�͕s�\���ŁA����I�Ȕ��f�_��O��Ƃ��ĔF���_���W�J����Ă���悤�Ɏv����B�������A������́A���̂悤�ȗ����͑e�G���Ǝv���Ă���B���㎟�̂悤�Ɍ��������K�v�����邾�낤�B �y�F���̐��x�z�̍l�@�����ɘ_���w���l�@���邱�Ƃ́A�_���w��̐^�U���ƔF���_��ł̐^�����Ƃ̍����Ɍq����B���̎w�E�̏d�v���͓���_���w�̍��ő傢�ɊW���Ă���B |
| �y���ʘ_�z |
|
�y�F���̐��x�z�����߂Ă������Ƃ́A�s�f�Ɏ��ہE�����̎��ʂ����Ă����ߒ��ł�����B���̎��ʉߒ��́A�y�{���Ɖ��ہz�A�y�����ƌ��ہz�A�y���̂ƌ`���z�A�y���Ɨʁz�A�y�������ʁz���X���ׂ����Ƃɂ���B |
| �y�T�O�_�z |
|
�@�F�������ɂ�����y���x�E���ʁz�ߒ���ʂ��đ[�肳�ꂽ�X�̎��ہE�����̊T�O���T������F���c���Ɍ��������ƂɂȂ�B���̉ʎ����T�O�Ɖ]���B�T�O�́A�N�w�j��̊ϔO�_�I�K��ɂ��A�C�f�A�̊O�����ꂽ���̂ł��邩�炵�Ď����Ƃ��ẴC�f�A���ς邱�ƂɂȂ�A�B���_�I�ɂ͂��̂��̂���̖{���K��Ƃ������ƂɂȂ�B�A���A������`����w�I�Ɋς�̂��ُؖ@�I�Ɋς�̂��ŗ��h��������Ă���B������̎��H�_���w�͗B���ُؖ@�̊ϓ_�ɗ��B |
| �y���e�i���e�j�i�h�C�c��ŃJ�e�S���[�EKategorie�j�z |
|
�@�u���o�i�^�́j�v�́u�^�͋��e�v�̌�ɂ����N���Y�̖��Ƃ��āu���e�v�����邪�A�F���_�̑f�{�Ƃ��Ă��̈Ӗ������܂����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B������̗����ɂ��ƁA�u���������̂��̂������镔�ށA����A�̈�ɑ��鑍�̊T�O�v�Ɖ�����B |
| �y����z |
|
�@�T�O�Ӊ����邱�Ƃɂ��u����iproposition�j�v���^������B�u�����v�́A����T�O�̉��ł́u��`�idefinition�j�v�A�u�����itke axiom�j�v�A�u����ia hypothesis�j�v�A�u��O�v�̊e�K�肩��\�������B����A�����͘_���w��̏�����ł���Ɖ]����B |
| �y����_(propositio)�z |
| �@�A���X�g�e���X�́u����_�v�S�͈ȉ��ŁA����̎�ꍀ�Əq�ꍀ����Ȃ�\���A����̎�(�m��E�ے�)�A��(�S�́E���̓�)����т���̑g�ݍ��킹�ɂ��S��(A���S�̍m��EI�����̍m��EE���S�̔ے�EO�����̔ے�)�̒茾����Ԃ́q�Γ��r�W�A����ɂ́A�����̒茾�����ڑ������Ăł��鉼������A�\�E�s�\��K�R�E���R�Ƃ������l������ɂ͂���ɉߋ��▢���Ƃ�����������������l������Ȃǂ̊�{�I���������k�ɍl�@����Ă���B �@�ߐ��ɂ����ẮA�l������͏ȗ�����邱�Ƃ������A�܂��X�b�|�V�V�e�B�I�_�������_���痎�������ƂƊ֘A���āA�����Ŏ�ꍀ����яq�ꍀ�́A�q�����r�ɂ��Ă��_������悤�ɂȂ����B �@�������ď]���̘_���w�ł́A����́u���f�v�Ƒ������邽�߁A���̕����́u���f�_�v�̔��e�ɓ������B���A������̎��H�_���w�ł́A����̊O�`�\���ɂ��Ă̓v�����f�_�Ƃ݂Ȃ������K�ł͂Ȃ��낤���Ƃ�������������F���_�Ƃ��Ď�荞�ނ��Ƃɂ���B |
| �y����̊O�`�\�����̂P�A�v�f����ƕ�������z | ||||||||||||||||||||
�@�u����̊O�`�\���v�́A�u�v�f����ƕ�������v���琬��B������u����̊O�`�\�����̇@�v�Ɖ]���B
|
||||||||||||||||||||
| �y����̊O�`�\�����̂Q�A����̌����W�̎�ށz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�@�e���肠�邢�͖���Ԃ́A���̘_���I�����q�ɂ���Čq�����Ă���B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)