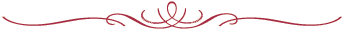
| 実践論理学の意義について |
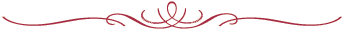
更新日/2023(平成31.5.1栄和改元/栄和5)年.1.13日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
|
国際交流時代を迎えて、異文化の人々とのコミュニケーションの機会は増すことあれどその逆はない。その際、 そのコミュニケーションを誤解のないものにするために、自己主張と聞き分けの双方向の能力を高めねばならない。そうなるといきおい論理学を学んでおくに越したことはない。即ち論理的な思考、表現能力が必要となるという訳である。 人は、脳髄の発達により、第一次本能的な感覚的機能を衰えさせたが、替わりに体験・観察→認識→判断→推論→企画(青写真)→実践→検証→その繰り返しによる認識の螺旋(らせん)的発展という頭脳機能を高めた。まさに脳髄活動もまた弁証法的になっており、これに即することが自然の成り行きであろう。これを仮に言語コミュニケーション能力と云うとすれば、いわばこれが人間たる所以のものを証する第二次本能と云えるかも知れない。 体験・観察から始まり検証に至る過程は、認識及び判断と実践の不断の交叉である。その意図するところは、認識の精度が次第に高まり、実践の的を次第に正確に射ることにある。野球で例えれば、ピッチャーがストライクゾーンに習熟し自在に球を投げ込むことができる如くである。剣士が打撃部位を正確に打つことができるが如くである。この効果を求める気持ちなくしては意味を持たない。 そういう意味で、人は、論理学を学ぶ者も学ばない者も皆な経験的に利用している。それを学問的に別途考察して理論化するかしないかだけの違いである。ところが、学者に理論化された論理学が実践経験と合致しないものであったとしたら意味を為すであろうか。有害ではなかろうか。そういう訳で、れんだいこが論理学を極力実践適用できるように既存論理学の革命を試みようと思う。れんだいこが「実践論理学」と銘打つ所以がここにある。 従来の論理学の欠陥は実践の意義を組み込んでいないところに認められる。実践は論理学上の必須要素であり、この導入なくしては全てが形式に出してしまう。或る人曰く、「理念像(S=Socialist concept)→法制体系化(I=Institutionalization)→運用・操作(O=Operation)→現実分析(A=Analysis)→理念像(S)というS→I→O→A→Sの循環図式」(「社会主義とは何だったのか 岩田昌征さんに聞く上」)としているが唯物弁証法公理に従えば当たり前のことといえよう。 この間、コミュニケーション手段としての言語活動をより良くなすために約束事が決められ、歴史の風雪に揉まれるうちに次第にセオリー化され論理学を生み出すことになった。交通信号、手旗信号、あるいはその種の取り決めが為され、これを総称して仮に言語活動の約束事とする。人は特に論理学を学ばなくても普通にその手法で判断していっているのであるが、学として学ぶことにより一層の上達が為されるとならば、これを学ばぬ手はなかろう。 ところが、この約束事が非常に小難しくされ、却って分かりにくくされているきらいがある。そこで、れんだいこはまずれんだいこ自身が分かるように翻訳してみたい。囲碁・将棋を嗜む者にはピンとくるであろうが、囲碁には定石というものがある。上達の為には定石は習って忘れろが一番ではあるが、やはり知らぬよりは知っておいた方が良いであろう。そういう捉え方で整理してみたい。 囲碁・将棋を挙げたついでに補足しておけば、日本には論理学の発達がなかったと云うのはウソである。西欧学的な手法による論理学の発達がなかっただけのことで、日本式論理学は、囲碁・将棋その他で鍛えに鍛えたよほど高度なものが伝えられているとみなすべきである。学者と云う種族にはこのことが分からない程度の凡庸な頭脳の者が多くて困る。 もとへ。本稿の考察はまったくのオリジナルであるから内容は他のものと大きく違っている。れんだいこ自身が分かる範囲で実践に役立つようにまとめている。そういう観点から「実践論証論理学」と命名した。これを簡略に「実践論理学」と命名する。「実践論理学」では、思考(思惟)活動全体を広義な意味では「推論(推理)」と呼ぶが、狭義に見るとそれぞれ認識論、判断論、類推論、論証論、論法論、検証論に分かれるように思われるのでこの順に見ていくことにする。 論理学の有益性について次のような面白話もあるようである。ゲーテの「ファウス」の中で、学生が「これから学問を始めるにあたって何から勉強したらよいか」と相談する場面がある。博士の弁は、端的に「まず最初に論理学の講義を聞きなさい」であった。つまり、論理学は正しい思考の訓練をなす故に古来より学問研究の基礎学といわれてきた。多くの用例を通して正しい思考法則を学んでいくことが重要であるということであろう。「料理に対する切れ味の良い包丁」で例えられる場合もある。 2005.3.19日再編集、2014.07.05日再編集 れんだいこ拝 |
| 【論証考】 |
| 論理学の要諦に論証如何問題がある。何事も云うのは勝手であるが、論証を要する。論証不要のまま手前勝手な持説を振り回されると傍迷惑である。最新の傍迷惑は、手前の所論が論証できないご都合理論だという理由で、相手の持論をも同一視して批判を浴びせる傾向である。天に唾する行為であるが、相手を己の低みに何とかして巻き込もうとする意図のように思われる。 そういう者は次のことに気づかなければならない。論証できない理論を持つことは勝手である。或る時のひらめきとか着想は元々非論証的にふともたらされるからである。しかし、それらも次第に論証すべく精励されねばならず、やがて理論として結実せねばならない。これが義務要件とされる。論証抜きの着想を長年にわたってひけらかされると、得意になって言えば言うほど終いには聞きたくなくなるものである。 ここで云う論証は、論理学上耐え得るような証明である必要はない。歴史には主因や真実は隠されるとしたものだから、論証を求めすぎると却って言及しにくくされてしまう。従って、多くの事例紹介と、それら事例を結ぶ糸の流れを解析できれば、それも論証とすべしだろう。あるいは、「シオンの議定書」のように、記載されている内容と歴史の歩みが合致しておれば、同書の価値を認めるべきだろう。証言が真っ二つに割れて肯定派と否定派の見解が並立するような場合には真偽定めを要するだろう。 これらの場合、既成論理学では殆ど役に立たない。形式論理学と云われる所以である。実践論理学は、これら諸問題をも解けるような法理を発見し、それらの定式を使って実践に役立ててみたいという狙いがある。れんだいこの実践論理学にはそういう抱負がある。しかし、この道は未開の原野であり、これからが大変だ。 2006.11.26日 れんだいこ拝 |
| 【実践論理学上の気づき考】 |
| 実践論理学を生み出そうとするとき面白いことに気づいたので書きつけておく。今日論理学として学を為しているのは西欧式のものである。それは知の練磨には多少役立つが形式論理に過ぎて実践には役立たない。その理由として、そもそも論理学の始初の「三大命題の欠陥」が考えられる。三大命題とは、同一律、矛盾律、排中律を云うが、れんだいこが云うところの中間律がない。現実にあるところの動態的な中間律を措定しないので、明快ではあるが実際を規定できなくなっている。他にも論法上の良質的なものと性悪的なものとの区別をしていないので口だけ達者になる弁論術に堕すことになる。 そういうものを学んで役に立つのか逆に愚昧になるのか、この辺りは興味ある考察である。それはともかく、日本に於いて論理学的なものは存在しなかったのだろうか。これにつき然り否と応えたい。然りは、西欧的な論理学は存在しなかった故にと云う意味の然りである。否は、西欧的なものとしての論理学は存在しなかったが代わりのものを用意していたと云う意味で否である。ここでは否の秘密を問うことにする。これが、れんだいこの気づきである。 日本では西欧的な論理学は形成されていない。しかし、それに代わるもっと立派な論理学が非学問的に形成されていたのではなかろうか。それは何かと問えば囲碁、将棋の棋理学がそれに当る。何も囲碁、将棋的棋理学だけではない。日本の「何々道」と付くもの全てに内在している。日本人は、これに暁通することにより西欧的論理学以上のものを伝統的に会得していたのではなかろうか。その高度さは西欧論理学なぞ足元にも及べないと分別すべきではなかろうか。 去る日の黒船来航以降、西欧化の名の下に西欧文明を先進文明国のものとして学び逆に日本的なものを卑下してきたが、そういう作法からそろそろ抜け出さねばならないのではなかろうか。西欧的なるものの陽と影が明瞭化されつつある今日、このことを指摘しておきたい。それは何も西欧的なるものを拒否せよと云うのではない。そろそろ日本の優れた伝統的芸を見直し得意とする咀嚼発酵に向かわねばならないと云うことを示唆しようとしている。日本的なるものと西欧的なるものの両者から新たな高次なものを生み出さねばならない即ち現状から出藍せよと云いたい訳である。 もとへ。囲碁、将棋の棋理学とはどういうものであるのか、これを確認する。但し、れんだいこの熟達は囲碁でアマチュアの5段(県代表クラスに3子の手合い)、将棋はアマチュアの初段程度のものでしかないので偉そうに言う訳には行かない。このレベルの者の発言として聞いてもらいたい。囲碁、将棋の棋理学の筆頭に「詰め」が挙げられる。俗に「詰め碁」、「詰め将棋」と云われる。ここに論理学的な意味での理論的な例題が用意されており理詰めの宝庫となっている。囲碁、将棋の棋理学は「詰め」に限られるものではない。序盤、中盤、終盤、寄せにそれぞれ合理的な思想、それを裏付ける棋理が内在している。それぞれ局面に合わせた適切な応じ手を生み出す。その応酬の型として囲碁では定石、将棋では定跡が生み出されている。その極めつけの手が手筋と云われるものである。古来、東洋人は、この種の芸の習得により棋理諺(きりことわざ)を生み出し、それを会得することにより西欧的な意味での論理学に比して決して劣らない論理的な能力を身に付けて来たのではなかろうか。 してみれば、西欧的な論理学を学ぶにせよ、それを鵜呑みにせず同時に東洋的な論理学を誇りに思い学ぶことが必要なのではなかろうか。欲を云えば、こたびれんだいこが企図しているように西欧的な形式論理学から出藍する実践論理学を創造せねばならない。これを俗に鬼に金棒と云うのではなかろうか。この発想は論理学に止まらない。18世紀以降、とみに顕著になった西欧式(正確には「国際ユダ屋式」)の諸学問、諸制度、諸思想を同様の見地から洗い直し組み立て直す必要があるのではなかろうか。こういうことに気づいた次弟である。 付言しておけば原発問題も、この発想で解決すべきである。原発的知性は西欧的なものがもたらした悪魔科学によるものである。その根本に自然を支配せよなるユダヤ教神言が介在する。その種の知性の蓄積された発達によりもたらされた科学が今日では地球の生態系を滅ぼそうとしているのではないのか。今必要なのは始初に於ける自然との共生観であり、西欧的な自然を支配せよなる神言を却下する非西欧的な自然の摂理と共生する神言を見いだし、これに従うべきではないのか。論理学上の気づきからここまで問うのは越権だろうか。 2013.1.27日 れんだいこ拝 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)