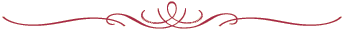
| 語源 |
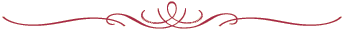
(最新見直し2005.9.17日)
| 【「お袋」】 |
| 「おふくろ」という言葉は鎌倉時代から使われている。「大言海」は、「母は家政を取り、袋の出し入れの締め括りをすれば、時世の詞(ことば)にて称したるなり」(江戸後期の国学者・橘守部の「俗語考」の一節より)と記している。異説として、江戸中期の故実学者・伊勢貞丈は、意訳概要「カンガルーが体外の袋に子を入れて育てる例から類推して、母の袋で子育てされているようなものとなぞり、母を表わす別表現となった」と記している。他には、漢語の「北堂(家の北方にある主婦のいる堂)から発生しており、「おほくどう」が「おふくろ」に転じたという説もある。 |
| 【「混沌」】 |
| 辞書的には。「無秩序でものごとの区別がつかない状態、あるいは天と地が分かれる前の太古の世界のこと」と解する。 「混沌」を理解する上で、荘子の「混沌物語」が示唆的で評価が高い。それによると、「世界の中央を治める混沌は徳は高い。が、目、耳、鼻、口の七つの穴を持たない故に混沌と云われる。ある時、南海の神と北海の神が混沌に招かれた。南海と北海の両神は、その徳に報いるべく、一日に一つずつ七日間で七つの穴を混沌に開けることにした。ところが、最後の仕上げとなった七日目、混沌は死んだ」。この神話は、いらざる世話を焼いて、逆に害を与え、台無しにしてしまうことの例えに使われている。 この「混沌物語」をどう解するのか、今日的にも興味深い。科学史家の山田慶児氏は、混沌物語を、空間分割、支配構造の歴史だとするユニークな解釈をしている。横暴で傍若無人、他の意見など聞く耳を持たない混沌を、南海と北海の神が、示し合わせて殺し、この世を南北で分割支配したという。最初は中央の混沌による一極支配、次は中央と南北の三極支配、そして、最後に秩序だった二極支配で安定へ云々。(2003.11.14日、日経「春秋」参照)。 れんだいこは、もっと素直に受け取れば良いと思う。荘子は、この世の本質に混沌を見た。それは最も価値があるものである。ところが、技巧的な南北両神が、この混沌の良きところを更に生かそうとして、その足らざるところを補強していった。しかし、出来上がったものは不細工で、混沌の持っていた本質的に深い価値を損ねてしまい、「いらざる世話を焼いて、逆に害を与え、台無しにしてしまった」。留意すべきは、技巧的な南北両神の浅知恵に対する批判と混沌の価値の高さに対する称揚という観点を保持することであろう。卑俗に言えば、この世の全てを明らかにしようとして為す文明の知恵は、曖昧を残したまま価値を持つ混沌の徳に及ばない、と云うことではなかろうか。つまり、何でも博学ぶる自称インテリらに対する警句ではなかろうか。 |
| 【「トラウマ」(trauma)】 |
| 最近、語源のラテン語では「外傷」の意味だけだったのに、精神病の術語で「精神的外傷」を意味するようになった「トラウマ」(trauma)が、普通の会話でも流行っているが、似たようなものである。 |
| 【「プロレタリアート」】 |
| 「プロレタリアート」のProres(ラテン語)が語源であり、これは子孫を意味する。つまり、プロレタリアートとは、子孫しか財産の無い者、あるいは、子孫を作る以外能の無い者つまり無産者という意味である。 |
| 【「歴史】 |
| 日本語の「歴史」という言葉は、中国の明末の漢語からきたとされている。「歴」は「経る」、「史」は「記録」という意味で、これを合わせる意味合いが「歴史」になる。これが東洋的な意味での「歴史」である。欧米では、ギリシャ語の「ヒストリア」(探求)と、ドイツ語の「ゲシヒテ」(出来事)という意味を加味して「ヒストリー」を捉えている。 歴史は、客観的な事実の記録という側面と、それをどう観るのか、語り伝えるのかという主観的な側面を持つ。歴史事象の単なる事実や現象の羅列の認識だけでは歴史にならない。その現象がいかなる意味合いをもち、後世にいかなる教訓を残しているのか、といった価値判断が問われている。そうした価値判断を加えた著者の統一的な解釈を史観と云う。 歴史上の高名な歴史家を確認する。 ヘロドトス(B.C.484〜430)。彼は、紀元前5世紀の古代ギリシャの歴史家として高名である。小アジアのハリカルナッソス出身で、ペルシャ各地や南イタリア、ギリシャなど広範囲にわたって旅行し、こうした見聞をもとに「歴史」(9巻)を著している。同書はペルシャ戦争を主題としており、東洋と西洋との衝突という広い見地から説き起こし、単なる出来事の羅列ではなく、ギリシャとペルシャの戦いを物語風に、そしてヘロドトス自身の価値判断を加えて綴っている。当時の世界各地の歴史地誌も織り交ぜられており、一大叙事詩のように歴史が綴られている。後にキケロとアリストテレスが「歴史」に言及したことから「歴史の父」と呼ばれるようになった。 レオポルド・ランケ(1795〜1886)。彼は、19世紀のドイツの歴史家としてとして高名である。マルクスとほぼ同世代のドイツの歴史家でチューリンゲンの小村ビーエ出身。ライプチヒ大学で学んだ後、ベルリン大学教授(1825〜71)となり、当時のロマン主義的な歴史哲学に反対して資料、文献にもとづく史料中心主義の厳密な客観的実証的な歴史叙述を唱道した。歴史を初めて「科学」の地位に押し上げたことで評価されている。これにより「近代歴史学の始祖」と称される。大学に歴史学演習の制度を設け、その門下から多くの逸材が出たことでランケ学派が形成された。として「近代歴史学の始祖」と呼ばれている。 アーノルド・ジョセフ・トインビー(1889〜1975)。彼は、イギリスの代表的な歴史学者として高名である。オクスフォード大学卒業後、外務省に勤務し第一次大戦後のパリ和平会議ではイギリス代表団の一員となる。ロンドン大学などで歴史学の教鞭を執り、外務省調査部長などを歴任。主著「歴史の研究」では世界を20余の文明圏に分けて、その興廃を論じた。シュペングラーやマルクスの決定論的歴史観や西洋中心史観を排して、人間・人間社会の自由な決意と行為による歴史を強調し、独自の文明史観を展開したことで、真の世界史的視点に立った歴史家・文明批評家と評されている。トインビーの、人類史の時空を貫く全体像を捉えようという壮大な歴史解釈の試みはトインビー史観と呼ばれている。 戦後、日本では京大教授の梅棹忠夫氏が生態史観というユニークな歴史解釈を展開して話題になった。作家の司馬遼太郎氏の歴史小説が司馬史観と名づけられるのも、そこに氏の独特の歴史解釈があるからである。 |
| 【「馬鹿】 |
| 馬鹿の語源についてはいくつか説があるが決定的なものはない。馬鹿には、1・知能が劣る。思慮が足りない。2・道理・常識からはずれている。常軌を逸している。3・程度が並はずれている。度はずれている。4・役に立たない。機能を果たさない等の意味がある。日本語で相手をからかったり、侮蔑したり、相手の感情を損なわせる形で使われる。同じような言葉に阿呆がある。馬鹿は関東で、阿呆は関西で使われることが多い。 「馬鹿」の由来は次の通り。中国の「史記列伝」の故事で、古代の秦の時代、始皇帝が亡くなった後、権力を握っていた宦官の趙高という大臣が自分の権力をかさにきて、二世皇帝である胡亥に鹿を差し出し「珍しい馬が手に入りました」と言ってのけた。皇帝は「これは鹿ではないのか」と群臣達に尋ねたところ、趙高の権勢を恐れた者は馬と言い、気骨のある者は鹿と答えた。鹿と答えた者は、趙高によって処刑された。このことより、「馬鹿」とは自分の権勢をよいことに、矛盾したことを押し通す意味から転じた云々。「破家」という漢語から来ているという説もある。 梵語(サンスクリット語)から来ているという説もある。これによれば、無知や迷妄を意味する「baka」「moha」の音写「莫迦(ばくか)」「募何(ぼか)」から転じたものということになる。僧侶が使っていた隠語であって馬鹿という表記は後の当て字であるとする。江戸時代の国学者天野信景が提唱した説であり、広辞苑をはじめとした主要な国語辞典で採用されている。しかし馬鹿に「愚か」という意味が当初はなかったことから、疑問視する研究もある。 日本では、鎌倉時代末期頃から「ばか」の用例がある。南北朝時代の太平記での「馬鹿者(バカノモノ)」の使用が初出であるとも云う。室町中期の「文明本説用集」には、馬鹿の異表記として、「母娘」「馬娘」「破家」をあげ、「とんでもない」の意味で「狼藉之義也」と説明している。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)