| 【35、若菜下(わかなげ)(後半)37節】 |
| あらすじは次の通り。 |
| 源氏物語の主人公となる光源氏の生母が帝に見初められ、桐壺更衣として宮仕えする。帝の寵愛を受けるが、生母の父は大納言、母は旧家の出で教養もあったが身分が中位であった為、高位の女御()、更衣()のイジメを受け悩まされる。体調を悪くして宮 |
| 35.40 柏木、小侍従を語らう |
かくて、院も離れおはしますほど、人目少なくしめやかならむを推し量りて、小侍従を迎へ取りつつ、いみじう語らふ。
「昔より、かく命も堪ふまじく思ふことを、かかる親しきよすがありて、御ありさまを聞き伝へ、堪へぬ心のほどをも聞こし召させて、頼もしきに、さらにそのしるしのなければ、いみじくなむつらき。
院の上だに、『かくあまたにかけかけしくて、人に圧されたまふやうにて、一人大殿籠もる夜な夜な多く、つれづれにて過ぐしたまふなり』など、人の奏しけるついでにも、すこし悔い思したる御けしきにて、
『同じくは、ただ人の心やすき後見を定めむには、まめやかに仕うまつるべき人をこそ、定むべかりけれ』と、のたまはせて、『女二の宮の、なかなかうしろやすく、行く末長きさまにてものしたまふなること』
と、のたまはせけるを伝へ聞きしに。いとほしくも、口惜しくも、いかが思ひ乱るる。
げに、同じ御筋とは尋ねきこえしかど、それはそれとこそおぼゆるわざなりけれ」
と、うちうめきたまへば、小侍従、 |
こうして、源氏が離れている間に、人目が少なくひっそりしている間に、柏木は、小侍従を度々邸に呼んで説得するのだった。
「昔からこんなに命を宿めるほど思っているのを、こんな近しい伝があって御有様を聞き伝え、抑え難い心の程を、伝えて、頼もしく思っていたのに、その効果がなければ、ずいぶんひどいことでしょう。
朱雀院さえ、『(源氏が)このようにたくさんの女性に情けをかけていて、(女三の宮が)紫の上に気圧されるようになって、姫君は一人寝る夜が多く、所在なく過ごしている』などの報告がある、院は少し悔いる気色をされて、
『同じことなら、臣下を気楽なお世話役に決めていれば、そしてまじめに仕える人にすればよかった』と仰せになって、『女二の宮は、かえって心配がなく、行く末長く無事に過ごすことになるのか』
と仰せになったと伝え聞いております。残念で、口惜しくて、院はどんな気持ちでいることか。実際、同じ血筋と思って、頂戴したのだが、それはそれとして別なのだ」
と思わず嘆声を上げると、小侍従は、 |
|
| 35.41 小侍従、手引きを承諾 |
「いで、あな、おほけな。それをそれとさし置きたてまつりたまひて、また、いかやうに限りなき御心ならむ」
と言へば、うちほほ笑みて、
「さこそはありけれ。宮にかたじけなく聞こえさせ及びけるさまは、院にも内裏にも聞こし召しけり。などてかは、さてもさぶらはざらましとなむ、ことのついでにはのたまはせける。いでや、ただ、今すこしの御いたはりあらましかば 」
など言へば、
「いと難き御ことなりや。御宿世とかいふことはべなるを、もとにて、かの院の言出でてねむごろに聞こえたまふに、立ち並び妨げきこえさせたまふべき御身のおぼえとや思されし。このころこそ、すこしものものしく、御衣の色も深くなりたまへれ」
と言へば、いふかひなくはやりかなる口強さに、え言ひ果てたまはで、
「今はよし。過ぎにし方をば聞こえじや。ただ、かくありがたきものの隙に、気近きほどにて、この心のうちに思ふことの端、すこし聞こえさせつべくたばかりたまへ。おほけなき心は、すべて、よし見たまへ、いと恐ろしければ、思ひ離れてはべり」
とのたまへば、
「これよりおほけなき心は、いかがはあらむ。いとむくつけきことをも思し寄りけるかな。何しに参りつらむ」
と、はちふく。
「いで、あな、聞きにく。あまりこちたくものをこそ言ひなしたまふべけれ。世はいと定めなきものを、女御、后も、あるやうありて、ものしたまふたぐひなくやは。まして、その御ありさまよ。思へば、いとたぐひなくめでたけれど、うちうちは心やましきことも多かるらむ。
院の、あまたの御中に、また並びなきやうにならはしきこえたまひしに、さしもひとしからぬ際の御方々にたち混じり、めざましげなることもありぬべくこそ。いとよく聞きはべりや。世の中はいと常なきものを、ひときはに思ひ定めて、はしたなく、突き切りなることなのたまひそよ」
とのたまへば、
「人に落とされたまへる御ありさまとて、めでたき方に改めたまふべきにやははべらむ。これは世の常の御ありさまにもはべらざめり。ただ、御後見なくて漂はしくおはしまさむよりは、親ざまに、と譲りきこえたまひしかば、かたみにさこそ思ひ交はしきこえさせたまひためれ。あいなき御落としめ言になむ」
と、果て果ては腹立つを、よろづに言ひこしらへて、
「まことは、さばかり世になき御ありさまを見たてまつり馴れたまへる御心に、数にもあらずあやしきなれ姿を、うちとけて御覧ぜられむとは、さらに思ひかけぬことなり。ただ一言、物越にて聞こえ知らすばかりは、何ばかりの御身のやつれにかはあらむ。神仏にも思ふこと申すは、罪あるわざかは」
と、いみじき誓言をしつつのたまへば、しばしこそ、いとあるまじきことに言ひ返しけれ、もの深からぬ若人は、人のかく身に代へていみじく思ひのたまふを、え否び果てで、
「もし、さりぬべき隙あらば、たばかりはべらむ。院のおはしまさぬ夜は、御帳のめぐりに人多くさぶらひて、御座のほとりに、さるべき人かならずさぶらひたまへば、いかなる折をかは、隙を見つけはべるべからむ」
と、わびつつ参りぬ。 |
「まあ、とんでもない。女二の宮を差し置いて、途方もないことをお考えになるなんて」
と言えば、微笑んで、
「そういうものです。三の宮に恐れ多くも求婚したことは、院も帝もご存じです。どうして、柏木に不足があろう、とことのついでに(院も)仰せになったのです。いや、今少しお情けがありましたら」
などと言えば、
「難しいです。元々、宿世ということもあるし、源氏の君が口に出してお望みになったとき、それを阻止でできるほど御身に威勢があったと思っておられるのですか。このころになって、少し出世されて、衣の色も深くなったようですが」
と言えば、とても敵わないほど口達な女房なので、(柏木は)最後まで言えずに、
「もうよい。過ぎたことを言うのは止めよう。ただこのようなめったにない機会で、近くにいるのに、わたしの心の内の一端でも、少しでも伝えてもらえませんか。大それたことは、そんな恐ろしいことは、よく見ていてください。考えていません」
と言うと、
「これ以上大それた心は、ないでしょう。とても恐ろしいことを思いついたものです。わたしは何しに来たのでしょう」
と、口をとんがらせた。
「まあ、何とも聞きにくいことを。あまり嫌なことを言いなさんな。世は定めなきものにて、女御、后も、事情があって男と情けを交わすこともあるでしょう。まして、宮の様子と言ったら。思えば、大そう高貴な身分に恵まれたお方が、内心不満に思っていることも多いのです。
「朱雀院の多くの御子の中で、並びようもないほどに大切にされて、身分から言えば劣る六条の婦人方に、心外な扱いを受けることもあるのです。よく知っているでしょう。男女の仲は常なきものだから、一概に決めてかかって、はしたなく、言い切るのはよしなさい」
と言えば、
「ほかの方に引けを取っているからと言って、よい縁組に代えることなどできないでしょう。今の有様は、世の普通の夫婦ではありません。ただ後見がなく頼りない境遇でなく、親代わりにと、譲ったものですから、お互いにそう思ってまじわっているのです。的外れな悪口を言うもんではありません」
と、最後は腹が立ったのを、あれこれ言いなだめて、
「本当のところ、あれほど世にも稀な源氏の立派な姿を見馴れた姫君に、物の数でもないあやしい姿を、親しく御覧に入れることなど、思ってもいません。ただ一言、物越しに伝えるだけでは、どんなに御身を汚すことになりましょう。神仏にも思うこと申すのは、罪でしょうか」
と、大そうな誓約をしながら言うと、初めのうちは、とんでもないことと断って言い返していたが、考えの浅い若い女房は、柏木が命懸けで思い込んでいるのを断れきれず、
「もしそのような隙があれば、やってみましょう。源氏の院のいない夜は、几帳の周りに女房が多く侍していますので、姫君の御座の側に、侍女が必ず侍しているので、その折がむつかしいのですが、そのうちに、適当な隙を見付けましょう」
と詫びながら帰っていった。 |
|
| 35.42 小侍従、柏木を導き入れる |
いかに、いかにと、日々に責められ極じて、さるべき折うかがひつけて、消息しおこせたり。喜びながら、いみじくやつれ忍びておはしぬ。
まことに、わが心にもいとけしからぬことなれば、気近く、なかなか思ひ乱るることもまさるべきことまでは、思ひも寄らず、ただ、
「いとほのかに御衣のつまばかりを見たてまつりし春の夕の、飽かず世とともに思ひ出でられたまふ御ありさまを、すこし気近くて見たてまつり、思ふことをも聞こえ知らせては、一行の御返りなどもや見せたまふ、あはれとや思し知る」
とぞ思ひける。
四月十余日ばかりのことなり。御禊明日とて、斎院にたてまつりたまふ女房十二人、ことに上臈にはあらぬ若き人、童女など、おのがじしもの縫ひ、化粧などしつつ、物見むと思ひまうくるも、とりどりに暇なげにて、御前の方しめやかにて、人しげからぬ折なりけり。
近くさぶらふ按察使の君も、時々通ふ源中将、責めて呼び出ださせければ、下りたる間に、ただこの侍従ばかり、近くはさぶらふなりけり。よき折と思ひて、やをら御帳の東面の御座の端に据ゑつ。さまでもあるべきことなりやは。 |
いつだ、いつだ、と日々責められて、窮してその折をうかがっていて、その時が来て知らせた。喜びながらも、やつれて忍んでやって来た。
実に、自分でもけしからぬことと思うが、近くで見れば、かえって思い乱れる気持ちがまさることまでは、思い及ばなかった、ただ、
「かすかに衣の端を見ることができた春の夕べの、いつまでも忘れられず思い出すようなお姿を、少し近くで見て、思うことをお伝えすれば、一行の返事もいただけるだろう、自分をあわれと思ってくれるだろう」
と思うのだった。
四月十余日ほどのことだった。御禊は明日なので、斎宮に侍する女房たち十二人、ことに身分は高くない若い人々、童女など、それぞれが縫物ををしたり化粧などをしたり、見物に出ようと支度している、それぞれに忙しそうに、御前の方は人があまりいない頃であった。
近くに侍する按察使 の君も、時々通る源中将 も、無理に呼び出して、局に下がっている間、ただ小侍従だけ、近くにいる折になった。いい折だと見て、やおら帳の東面の御座の端に柏木を座らせた。そんなところに座らせていいものか。 |
|
| 35.43 柏木、女三の宮をかき抱く |
宮は、何心もなく大殿籠もりにけるを、近く男のけはひのすれば、院のおはすると思したるに、うちかしこまりたるけしき見せて、床の下に抱き下ろしたてまつるに、物に襲はるるかと、せめて見上げたまへれば、あらぬ人なりけり。
あやしく聞きも知らぬことどもをぞ聞こゆるや。あさましくむくつけくなりて、人召せど、近くもさぶらはねば、聞きつけて参るもなし。わななきたまふさま、水のやうに汗も流れて、ものもおぼえたまはぬけしき、いとあはれにらうたげなり。
「数ならねど、いとかうしも思し召さるべき身とは、思うたまへられずなむ。
昔よりおほけなき心のはべりしを、ひたぶるに籠めて止みはべなましかば、心のうちに朽たして過ぎぬべかりけるを、なかなか、漏らしきこえさせて、院にも聞こし召されにしを、こよなくもて離れてものたまはせざりけるに、頼みをかけそめはべりて、身の数ならぬひときはに、人より深き心ざしを空しくなしはべりぬることと、動かしはべりにし心なむ、よろづ今はかひなきことと思うたまへ返せど、いかばかりしみはべりにけるにか、年月に添へて、口惜しくも、つらくも、むくつけくも、あはれにも、いろいろに深く思うたまへまさるに、せきかねて、かくおほけなきさまを御覧ぜられぬるも、かつは、いと思ひやりなく恥づかしければ、罪重き心もさらにはべるまじ」
と言ひもてゆくに、この人なりけりと思すに、いとめざましく恐ろしくて、つゆいらへもしたまはず。
「いとことわりなれど、世に例なきことにもはべらぬを、めづらかに情けなき御心ばへならば、いと心憂くて、なかなかひたぶるなる心もこそつきはべれ、あはれとだにのたまはせば、それをうけたまはりてまかでなむ」
と、よろづに聞こえたまふ。 |
三の宮は、無心に眠っていたが、近くに男の気配がしたので、源氏の君か来たのかと思ったが、相手はかしこまった様子で、床の下に抱き下ろすので、魔物に襲われたか思い、必死に見上げると、それは違う人だった。
あやしく聞いたこともないことを言うのだった。あさましく気味が悪くなって、人を呼んだが、近くにおらず、聞きつけてくる者もない。わなわなと震えて、水のような汗が流れて、気が動転している様は、あわれに痛々しかった。
「数ならぬ身だが、このようなつれない扱いを受けるとは、思いませんでした。
昔から大それた思いを持っていたので、一心に心に籠めておりましたが、心の中に朽ちさせるべきを、かえって、漏らして言いましたので朱雀院にも聞こえたのですが、まったく問題にならないことのように、仰せにならなかったので、望みをかけておりましたが、一段劣っていただけで、人より深い心ざしを空しくしてしまう、無念に思う気持ちが、何もかも甲斐なく思い返すのですが、どれほど深く心に取りついてしまったのか、年月が経つにつれ、口惜しくも、つらくも、気味悪くも、あわれにも、さまざまに深く思いがつのるので、堪えかねて、このような大それた様をご覧に入れることになって、いかにも浅はかで恥ずかしいのですが、これ以上の罪を重ねるつもりはありません」
とあれこれ言ったので、この人だ分かったが、何とも意外で恐ろしく、一言も返事をしなかった。
「ご返事がないのもごもっともですが、世に例がないわけでもないが、つれない仕打ちをされるなら、心憂く、かえって一途な気持ちが起きてしまいます、せめて不埒者とだけ仰っていただければ、それを受けて辞去します」
と、あれこれ言うのだった。 |
|
| 35.44 柏木、猫の夢を見る |
よその思ひやりはいつくしく、もの馴れて見えたてまつらむも恥づかしく推し量られたまふに、「ただかばかり思ひつめたる片端聞こえ知らせて、 なかなかかけかけしきことはなくて止みなむ」と思ひしかど、いとさばかり気高う恥づかしげにはあらで、なつかしくらうたげに、やはやはとのみ見えたまふ御けはひの、あてにいみじくおぼゆることぞ、人に似させたまはざりける。
賢しく思ひ鎮むる心も失せて、「いづちもいづちも率て隠したてまつりて、わが身も世に経るさまならず、跡絶えて止みなばや」とまで思ひ乱れぬ。
ただいささかまどろむともなき夢に、この手馴らしし猫の、いとらうたげにうち鳴きて来たるを、この宮に奉らむとて、わが率て来たるとおぼしきを、何しに奉りつらむと思ふほどに、おどろきて、いかに見えつるならむ、と思ふ。
宮は、いとあさましく、うつつともおぼえたまはぬに、胸ふたがりて、思しおぼほるるを、
「なほ、かく逃れぬ御宿世の、浅からざりけると思ほしなせ。みづからの心ながらも、うつし心にはあらずなむ、おぼえはべる」
かのおぼえなかりし御簾のつまを、猫の綱引きたりし夕べのことも聞こえ出でたり。
「げに、さはたありけむよ」
と、口惜しく、契り心憂き御身なりけり。「院にも、今はいかでかは見えたてまつらむ」と、悲しく心細くて、いと幼げに泣きたまふを、いとかたじけなく、あはれと見たてまつりて、人の御涙をさへ拭ふ袖は、いとど露けさのみまさる。 |
(女三の宮は)、はたから見れば、威厳があり、馴れ馴れしくお会いするのも気が引ける方と見られるが、「ただこれほどまでに思いつめている一端でも、伝えて、好色なことはしない」と思っていたが、姫はそれほど気位が高くなく、近づきがたいことはなく、やさしく可憐な感じで、どこまでももの柔らかな感じに見える気配で、上品でとても美しく思われるところは、誰とも違う感じだった。
賢く冷静に自制する気持ちも失せて、「どこでもいいから宮を連れ出して隠して、わが身も世に生きず、姿をくらましてしまおう」とまで思い乱れた。
ほんのしばらくうとうとした夢の中で、馴らした猫が、可愛げに鳴いて来るのを、この宮にさしあげようと、自分が連れてきたと思われるのだが、どうしてお返しするのだろうとおもって、目が覚めて、どうしてこんな夢をみたのだろう、と思うのだった。
宮は、ことの成り行きに呆然として、うつつとも思えず、胸がふさがって、悲しみに沈んでいた。
「やはり、このように逃れられない宿世が、浅くなかったのです。わたしの所業だが、正気ではなかったとお考えください」
あの、宮にしてみれば覚えがなかった御簾の端を、猫が引いた夕べのことを語った。
「なるほど、そんなことがあったのか」
と、情けなく、こんな宿縁にあった憂きわが身なのだ。「源氏の君にどうしてお会いできようか」と悲しく心細く、子供のように泣きじゃくるのを、柏木は、恐れ多く、あわれと見て、宮の涙ををぬぐう袖は、いつまでも乾くことがなかった。 |
|
| 35.45 きぬぎぬの別れ |
明けゆくけしきなるに、出でむ方なく、なかなかなり。
「いかがはしはべるべき。いみじく憎ませたまへば、また聞こえさせむこともありがたきを、ただ一言御声を聞かせたまへ」
と、よろづに聞こえ悩ますも、うるさくわびしくて、もののさらに言はれたまはねば、
「果て果ては、むくつけくこそなりはべりぬれ。また、かかるやうはあらじ」
と、いと憂しと思ひきこえて、
「さらば不用なめり。身をいたづらにやはなし果てぬ。いと捨てがたきによりてこそ、かくまでもはべれ。今宵に限りはべりなむもいみじくなむ。つゆにても御心ゆるしたまふさまならば、それに代へつるにても捨てはべりなまし」
とて、かき抱きて出づるに、果てはいかにしつるぞと、あきれて思さる。
隅の間の屏風をひき広げて、戸を押し開けたれば、渡殿の南の戸の、昨夜入りしがまだ開きながらあるに、まだ明けぐれのほどなるべし、ほのかに見たてまつらむの心あれば、格子をやをら引き上げて、
「かう、いとつらき御心に、うつし心も失せはべりぬ。すこし思ひのどめよと思されば、あはれとだにのたまはせよ」
と、脅しきこゆるを、いとめづらかなりと思して物も言はむとしたまへど、わななかれて、いと若々しき御さまなり。
ただ明けに明けゆくに、いと心あわたたしくて、
「あはれなる夢語りも聞こえさすべきを、かく憎ませたまへばこそ。さりとも、今思し合はすることもはべりなむ」 とて、のどかならず立ち出づる明けぐれ、秋の空よりも心尽くしなり。
「起きてゆく空も知られぬ明けぐれに
いづくの露のかかる袖なり」
と、ひき出でて愁へきこゆれば、出でなむとするに、すこし慰めたまひて、
「明けぐれの空に憂き身は消えななむ
夢なりけりと見てもやむべく」
と、はかなげにのたまふ声の、若くをかしげなるを、聞きさすやうにて出でぬる魂は、まことに身を離れて止まりぬる心地す。 |
夜が明けてゆき、帰る気にもなれず、なまじいな逢瀬であった。
「どうしたものでしょう。ひどくわたしを憎んでいるようですが、また話ができる機会はないだろうから、ただ一声言ってください」
と、あれこれと言って悩ますが、宮はにはうるさく情けなく、何も仰らないので、
「しまいには、疎ましくなる。それにこんなことはほかに例がないでしょう」
と、ひどいと思って、
「それでは駄目なのですね。いっそ死んだ方がましだ。命に未練があるから、こうして逢いに来ているのです。今宵限りの命と覚悟を決めますのも悲しい限りです。少しでも気持ちを聞いてくだされば、その代わりに命を捨ても悔いがありません」
とて、抱いて出ようとすると、どうするつもりと、姫君は呆然としいる。
隅の間の屏風を開いて、妻戸を押し開ければ、渡殿の南の戸が、昨夜入って来たままに開いていたので、まだ明け切れていないほの暗さのなかで、少しでも宮を見たい気持ちで、格子をやおら引き上げて、
「こんなに、つれない御心に正気も失せます。少し落ち着かせようとお思いなら、不憫な奴とだけでも仰ってください」
と脅すように言うのを、宮は、珍しい人と思って、物を言おうとしたが、わなわなと震えが止まらず、いかにも幼いのだった。
だんだんに明けてゆくので、とても気が気でなく、
「あわれな夢物語もしたいですが、こんなに憎まれては。それでも、いずれ思い当たることもありましょう」 とて、気もそぞろに、明けてゆく朝を、秋の空よりもありとあらゆる悲しみをそそる。
(柏木の歌)「起きてどこへいったらいいのか明けぐれの
どこの露がこの袖にかかっているのか」
と、袖を引き出して憂いを述べれば、帰ろうとするので、少しほっとして、
(女三の宮の歌)「明けぐれの空に悲しいこの身は消えてほしい
あのことは夢であってほしい」
とか細く言う声の、幼く可愛らしい声が、聞き果てぬように帰ってきた魂は、本当に身を離れて(宮のもとに)止まった気がする。 |
|
| 35.46 柏木と女三の宮の罪の恐れ |
女宮の御もとにも参うでたまはで、大殿へぞ忍びておはしぬる。うち臥したれど目も合はず、見つる夢のさだかに合はむことも難きをさへ思ふに、かの猫のありしさま、いと恋しく思ひ出でらる。
「さてもいみじき過ちしつる身かな。世にあらむことこそ、まばゆくなりぬれ」
と、恐ろしくそら恥づかしき心地して、ありきなどもしたまはず。女の御ためはさらにもいはず、わが心地にもいとあるまじきことといふ中にも、むくつけくおぼゆれば、思ひのままにもえ紛れありかず。
帝の御妻をも取り過ちて、ことの聞こえあらむに、かばかりおぼえむことゆゑは、身のいたづらにならむ、苦しくおぼゆまじ。しか、いちじるき罪にはあたらずとも、この院に目をそばめられたてまつらむことは、いと恐ろしく恥づかしくおぼゆ。
限りなき女と聞こゆれど、すこし世づきたる心ばへ混じり、上はゆゑあり子めかしきにも、従はぬ下の心添ひたるこそ、とあることかかることにうちなびき、心交はしたまふたぐひもありけれ、これは深き心もおはせねど、ひたおもむきにもの懼ぢしたまへる御心に、ただ今しも、人の見聞きつけたらむやうに、まばゆく、恥づかしく思さるれば、明かき所にだにえゐざり出でたまはず。いと口惜しき身なりけりと、みづから思し知るべし。
悩ましげになむ、とありければ、大殿聞きたまひて、いみじく御心を尽くしたまふ御事にうち添へて、またいかにと驚かせたまひて、渡りたまへり。
そこはかと苦しげなることも見えたまはず、いといたく恥ぢらひしめりて、さやかにも見合はせたてまつりたまはぬを、「久しくなりぬる絶え間を恨めしく思すにや」と、いとほしくて、かの御心地のさまなど聞こえたまひて、
「今はのとぢめにもこそあれ。今さらにおろかなるさまを見えおかれじとてなむ。いはけなかりしほどより扱ひそめて、見放ちがたければ、かう月ごろよろづを知らぬさまに過ぐしはべるぞ。おのづから、このほど過ぎば、見直したまひてむ」 など聞こえたまふ。かくけしきも知りたまはぬも、いとほしく心苦しく思されて、宮は人知れず涙ぐましく思さる。 |
(柏木は)北の方の所へゆかず、実家にこっそり帰った。うつぶせになっても目を合わせられず、見た夢が確かにその通りになることも難しく、あの猫の有様を、恋しく思い出すのだった。
「それにしてもとんでもない過ちをした。この世に生きてゆくことができなくなった」
と、恐ろしくもひどく恥ずかしく、外歩きもできない。女のためにも、自分の心にもあるまじきことをしたという気持ちでいっぱいになり、恐ろしいことをしたという思いで、思うままに外歩きもできない。
たとえ、帝の妻と間違いを犯し、このことが露見したとしたら、これ程の慚愧の念に落ちるのなら、命を捨ててしまえば、苦しまなくてすむだろう。それほどの罪には当たらなくても、源氏の君に睨まれたら、大そう恐ろしく顔向けできないと思った。
この上なく高貴な婦人とはいっても、少し男女の仲も知り、表面はたしなみがあり無邪気でも、生地はそうでない人は、あれやこれやの男の甘言になびき、情を交える例もある。女三の宮は、情を交えて承知の上で許したわけではなく、ただ一途にものにおびえる性分で、今も、人に知られたらどうしよう、後ろめたく、顔向けできないと思うので、明るい所にいざり出ることもしない。いかにも情けない身と自分でも思うのであった。
病気のようだ、と連絡があり、源氏がそれを聞いて、紫の上の看病に専念していることに加えて、またどうしたことかと驚いて、見舞いに来た。
どことなく苦しいところもよくわからず、ひどく恥じらって、目を合わせるのを避けてはっきりとは顔も見せないので、「久しく来なかったので、恨んでいるのだろうか」と、かわいそうになって、紫の上の病状をあれこれ話して、
「もうこれが最後なのかもしれません。この期に及んで、薄情な扱いを受けたと思われてもいけない。幼いころから面倒を見ているから、このまま放っておけません。ここ何か月は、ほかのことは全部放置してきましたので。この時期が過ぎましたら、改めましょう」など、仰せになる。こうして源氏が何も知らないのも、申し訳なく心苦しく思って、宮は人知れず涙むのであった。 |
|
| 35.47 柏木と女二の宮の夫婦仲 |
督の君は、まして、なかなかなる心地のみまさりて、起き臥し明かし暮らしわびたまふ。祭の日などは、物見に争ひ行く君達かき連れ来て言ひそそのかせど、悩ましげにもてなして、眺め臥したまへり。
女宮をば、かしこまりおきたるさまにもてなしきこえて、をさをさうちとけても見えたてまつりたまはず、わが方に離れゐて、いとつれづれに心細く眺めゐたまへるに、童べの持たる葵を見たまひて、
「悔しくぞ摘み犯しける葵草
神の許せるかざしならぬに」
と思ふも、いとなかなかなり。
世の中静かならぬ車の音などを、よそのことに聞きて、人やりならぬつれづれに、暮らしがたくおぼゆ。
女宮も、かかるけしきのすさまじげさも見知られたまへば、何事とは知りたまはねど、恥づかしくめざましきに、もの思はしくぞ思されける。
女房など、物見に皆出でて、人少なにのどやかなれば、うち眺めて、箏の琴なつかしく弾きまさぐりておはするけはひも、さすがにあてになまめかしけれど、「同じくは今ひと際及ばざりける宿世よ」と、なほおぼゆ。
「もろかづら落葉を何に拾ひけむ
名は睦ましきかざしなれども」
と書きすさびゐたる、いとなめげなるしりうごとなりかし。 |
督の君(柏木)は、鬱屈した気持ちがつのって、起き伏し所在なく明け暮れして暮らしている。葵祭の日は、物見に競ってゆく君達が連れ立って、誘ってくるが、病気をよそおって、物思いに沈んでいる。
北の方の二の宮を、かしこまって遇しているが、親しくお逢いすることもしない、自分の部屋に籠って、所在なげに心細く思いに沈んでいて、童の持っている葵を見て、
(柏木の歌) 「悔いている大それた過ちを犯した葵草
神の許した仲でもないのに」
と思うが、鬱屈した気持ちは晴れない。
世の中のあわただしい車の音など、他所のことに聞いて、誰のせいでもない所在なさに一日がとても長く感じる。
女二の宮も、柏木のこのようなすさまじい様子も知っているので、その理由は知らなかったが、自尊心は傷つき、おもしろくない思いでいる。
(女宮の)女房たちは、皆物見に出かけて、閑散として、物思いに沈み、筝の琴を懐かしそうに弾いている様子は、さすがに上品で優雅であり、(柏木は、)「同じ皇女でも、今ひとつ上の女三の宮を頂けなかった」と、今でも思っている。
(柏木の歌)「ご姉妹の中で、どうして落ち葉を拾ったのか
どちらも朱雀院のご息女だけど」
と書きすさんでいる。いかにも馬鹿にした言い草だ。 |
|
| 35.48 紫の上、絶命す |
大殿の君は、まれまれ渡りたまひて、えふとも立ち帰りたまはず、静心なく思さるるに、
「絶え入りたまひぬ」
とて、人参りたれば、さらに何事も思し分かれず、御心も暮れて渡りたまふ。道のほどの心もとなきに、げにかの院は、ほとりの大路まで人立ち騒ぎたり。殿のうち泣きののしるけはひ、いとまがまがし。我にもあらで入りたまへれば、
「日ごろは、いささか隙見えたまへるを、にはかになむ、かくおはします」
とて、さぶらふ限りは、我も後れたてまつらじと、惑ふさまども、限りなし。御修法どもの檀こぼち、僧なども、さるべき限りこそまかでね、ほろほろと騒ぐを見たまふに、「さらば限りにこそは」と思し果つるあさましさに、何事かはたぐひあらむ。
「さりとも、もののけのするにこそあらめ。いと、かくひたぶるにな騷ぎそ」
と鎮めたまひて、いよいよいみじき願どもを立て添へさせたまふ。すぐれたる験者どもの限り召し集めて、
「限りある御命にて、この世尽きたまひぬとも、ただ、今しばしのどめたまへ。不動尊の御本の誓ひあり。その日数をだに、かけ止めたてまつりたまへ」
と、頭よりまことに黒煙を立てて、いみじき心を起こして加持したてまつる。院も、
「ただ、今一度目を見合はせたまへ。いとあへなく限りなりつらむほどをだに、え見ずなりにけることの、悔しく悲しきを」
と思し惑へるさま、止まりたまふべきにもあらぬを、見たてまつる心地ども、ただ推し量るべし。いみじき御心のうちを、仏も見たてまつりたまふにや、月ごろさらに現はれ出で来ぬもののけ、小さき童女に移りて、呼ばひののしるほどに、やうやう生き出でたまふに、うれしくもゆゆしくも思し騒がる。 |
源氏は、たまに宮のところに寄って、すぐにも帰るわけにもゆかず、落ち着きなく思っていると、
「息が絶えました」
と、使いが来たので、もう何も考えられず、心が真っ暗になって帰った。道のほども心もとなく、実に二条院は、大路まで人が騒いでいた。邸の中は、泣き叫ぶ声がかしましい、不吉な感じがして、我を忘れて邸に入ると、
「ここ数日は、容体が少しよろしかったのですが、にわかにお亡くなりました」
と、侍する限りの女房たちは、遅れずに後をお供しようと惑い泣くこと限りない。修法の壇を壊して、僧たちもしかべき僧たちを残して辞去した。ほろほろと騒ぐのを見ると、「もう最後なのだ」と思い果てる様は、何にたとえられよう。
「しかし、それでも物の怪のしわざであろう。そんなに大仰に騒ぐでない」
と静めて、いよいよ蘇生の願を立てようとするのだった。すぐれた験者たちだけ集めて、
「限りある命は、この世では尽きた。しかし今少し命を延したまえ。不動尊の御本尊もあります。その日数だけこの世に命を長らえて止めてください」
と頭から本当に黒煙を立てて、僧たちは必死に加持祈祷する。源氏も、
「ただ今一度、会わせてください。はかない最後のときも、会えなかったのですから、口惜しく悲しい」
と思いまどう様に、命が止まるべくもないのだが、見ている人々の動揺は、推し量ってください。必死の願いに、仏も見てあわれを感じたのであろう、月ごろ現れなかった物の怪が、小さい童女に移って、大声で呼びののしるうちに、死者はようやく生き返って、うれしくも由々しくも騒ぐのだった。 |
|
| 35.49 六条御息所の死霊出現 |
いみじく調ぜられて、
「人は皆去りね。院一所の御耳に聞こえむ。おのれを月ごろ調じわびさせたまふが、情けなくつらければ、同じくは思し知らせむと思ひつれど、さすがに命も堪ふまじく、身を砕きて思し惑ふを見たてまつれば、今こそ、かくいみじき身を受けたれ、いにしへの心の残りてこそ、かくまでも参り来たるなれば、ものの心苦しさをえ見過ぐさで、つひに現はれぬること。さらに知られじと思ひつるものを」
とて、髪を振りかけて泣くけはひ、ただ昔見たまひしもののけのさまと見えたり。あさましく、むくつけしと、思ししみにしことの変はらぬもゆゆしければ、この童女の手をとらへて、引き据ゑて、さま悪しくもせさせたまはず。
「まことにその人か。よからぬ狐などいふなるものの、たぶれたるが、亡き人の面伏なること言ひ出づるもあなるを、たしかなる名のりせよ。また人の知らざらむことの、心にしるく思ひ出でられぬべからむを言へ。さてなむ、いささかにても信ずべき」
とのたまへば、ほろほろといたく泣きて、
「わが身こそあらぬさまなれそれながら
そらおぼれする君は君なり
いとつらし、いとつらし」
と泣き叫ぶものから、さすがにもの恥ぢしたるけはひ、変らず、なかなかいと疎ましく、心憂ければ、もの言はせじと思す。
「中宮の御事にても、いとうれしくかたじけなしとなむ、天翔りても見たてまつれど、道異になりぬれば、子の上までも深くおぼえぬにやあらむ、なほ、みづからつらしと思ひきこえし心の執なむ、止まるものなりける。
その中にも、生きての世に、人より落として思し捨てしよりも、思ふどちの御物語のついでに、心善からず憎かりしありさまをのたまひ出でたりしなむ、いと恨めしく。今はただ亡きに思し許して、異人の言ひ落としめむをだに、はぶき隠したまへとこそ思へ、とうち思ひしばかりに、かくいみじき身のけはひなれば、かく所狭きなり。
この人を、深く憎しと思ひきこゆることはなけれど、守り強く、いと御あたり遠き心地して、え近づき参らず、御声をだにほのかになむ聞きはべる。
よし、今は、この罪軽むばかりのわざをせさせたまへ。修法、読経とののしることも、身には苦しくわびしき炎とのみまつはれて、さらに尊きことも聞こえねば、いと悲しくなむ。
中宮にも、このよしを伝へ聞こえたまへ。ゆめ御宮仕へのほどに、人ときしろひ嫉む心つかひたまふな。斎宮におはしまししころほひの御罪軽むべからむ功徳のことを、かならずせさせたまへ。いと悔しきことになむありける」
など、言ひ続くれど、もののけに向かひて物語したまはむも、かたはらいたければ、封じ込めて、上をば、また異方に、忍びて渡したてまつりたまふ。 |
(物の怪は)ひどく懲らしめられて、
「人払いをしてください。あなたにのみ言いましょう。わたしを月ごろ懲らしめなさり容赦なく調伏されるので、どうせ取りついたので、知らせようと思いましたが、君が命懸けで、一心に祈っているのを見ますと、いまでこそ悪道に堕ちた身ですが、昔の愛執が残っていますので、事ここに至ったのなら、お気の毒な様子を見過ごすことができず、とうとう正体を現しました。決して知られまいとしておりましたのに」
といって、顔を隠そうと髪を振りかけて泣く様は、昔見た物の怪と同じと見た。こんなことがこの世にあろうか恐ろしいことだ、と思ったことも同じく思い出され、この童女の手を取って、引き据え、無様な振舞いをさせない。
「本当にあなたなのか。質の悪い狐の狂ったのが、亡き人の不名誉になることを口走るのもあるようだ、はっきり名乗りなさい。他の人が知らないことで、わたしにはっきり思い当たることを言ってみるがよい。それが示せたら、いささかでも信じよう」
と仰せになると、ほろほろとひどく泣いて、
(物の怪の歌)「わが身はあさましい姿になりましたが、
昔のとおりのあなたはあなたで素知らぬふりをするのですか。
ほんとにひどい、ひどいこと」
と泣き叫び、恥じらいを見せている気配は、昔に変わらず、かえって嫌らしく、気味悪く、喋らせないようにしようと思う。
「中宮のことは、うれしくかたじけないと思う。霊界で天かけってみておりましたが、世界が違うので、子のことまで深く思いやることができないので、自分がつらいと思ったあなたへの執念に、思いがとどまるもののようです。
その中でも、生きていた世で、人よりも軽んじて捨てられたことよりも、思い出すままに語られた話の中で、ひにくれていて扱いにくい女だったと仰っていたことが、ひどく恨めし。今は死んだ人と大目に見て、他人が悪口を言っても、打ち消してかばってください。こんな恐ろしい身になったので、思い通りにできず厄介なのです。
紫の上を心底憎いと思っているわけではないが、あなたの身の守りが強く、お側に寄れないので、近づくことができず、あなたの声がかすかに聞こえるだけです。
ぜひ今は、わたしの罪が軽くなる法要をやっていただきたい。修法、読経とののしることも、この身には苦しくつらい炎に包まれるので、尊いお経も聞こえず、大そう悲しく思っています。
中宮にもこの由をお伝えください。宮仕えにも、人と争って妬む心を持ってはいけません。斎宮の頃のお勤めで仏事を遠ざけていた罪もあり功徳を積んでください。必ずするようにしてください。心から悔やまれます」
などと言い続けるが、物の怪に向かって話をするのも、具合の悪いことなので、別室に憑坐を封じ込めて、紫の上はまた別の部屋へ秘かに移した。 |
|
| 35.50 紫の上、死去の噂流れる |
かく亡せたまひにけりといふこと、世の中に満ちて、御弔らひに聞こえたまふ人びとあるを、いとゆゆしく思す。今日の帰さ見に出でたまひける上達部など、帰りたまふ道に、かく人の申せば、
「いといみじきことにもあるかな。生けるかひありつる幸ひ人の、光失ふ日にて、雨はそほ降るなりけり」
と、うちつけ言したまふ人もあり。また、
「かく足らひぬる人は、かならずえ長からぬことなり。『何を桜に』といふ古言もあるは。かかる人の、いとど世にながらへて、世の楽しびを尽くさば、かたはらの人苦しからむ。今こそ、二品の宮は、もとの御おぼえ現はれたまはめ。いとほしげに圧されたりつる御おぼえを」
など、うちささめきけり。
衛門督、昨日暮らしがたかりしを思ひて、今日は、御弟ども、左大弁、藤宰相など、奥の方に乗せて見たまひけり。かく言ひあへるを聞くにも、胸うちつぶれて、
「何か憂き世に久しかるべき」
と、うち誦じ独りごちて、かの院へ皆参りたまふ。たしかならぬことなればゆゆしくや、とて、ただおほかたの御訪らひに参りたまへるに、かく人の泣き騒げば、まことなりけりと、立ち騷ぎたまへり。
式部卿宮も渡りたまひて、いといたく思しほれたるさまにてぞ入りたまふ。人の御消息も、え申し伝へたまはず。大将の君、涙を拭ひて立ち出でたまへるに、
「いかに、いかに。ゆゆしきさまに人の申しつれば、信じがたきことにてなむ。ただ久しき御悩みをうけたまはり嘆きて参りつる」
などのたまふ。
「いと重くなりて、月日経たまへるを、この暁より絶え入りたまへりつるを、もののけのしたるになむありける。やうやう生き出でたまふやうに聞きなしはべりて、今なむ皆人心静むめれど、まだいと頼もしげなしや。心苦しきことにこそ」
とて、まことにいたく泣きたまへるけしきなり。目もすこし腫れたり。衛門督、わがあやしき心ならひにや、『この君の、いとさしも親しからぬ継母の御ことを、いたく心しめたまへるかな』、と目をとどむ。
かく、これかれ参りたまへるよし聞こし召して、
「重き病者の、にはかにとぢめつるさまなりつるを、女房などは、心もえ収めず、乱りがはしく騷ぎはべりけるに、みづからもえのどめず、心あわたたしきほどにてなむ。ことさらになむ、かくものしたまへるよろこびは聞こゆべき」
とのたまへり。督の君は胸つぶれて、かかる折のらうらうならずはえ参るまじく、けはひ恥づかしく思ふも、心のうちぞ腹ぎたなかりける。 |
紫の上がこうして、死んだという噂が世の中に満ちて、弔いに訪れる人々があるので、源氏は縁起でもないと思う。葵祭の斎院の帰りの日の見物をした上達部たちは、道々にこの話題を出せば、
「それはまことに大へんなことになったものだ。この世の栄華を極めた人が、亡くなる日だから、雨がそぼ降るのですね」
と突然言う人もある。また、
「このように満ち足りた人は、必ずしも長生きしない。『何を桜に』という古言もある。このような人の、長生きして、世の楽しみを尽くしたなら、はたの人が困るというものだ。いまこそ女三の宮は、本来のご寵愛を受けるだろう。おいたわしくも紫の上に圧されていた寵愛を」
などと、噂しあっていた。
柏木は、昨日の過ごしがたいつれづれに懲りて、今日は、弟たち、左大弁、藤宰相などと、奥の方に乗って見物に出かけた。こんな噂話に、胸ふさがって、
「桜は早々と散る、世に久しいものはない」
と吟じて独りごとを言って、二条の院へ皆行くのだった。確かではないので、縁起でもないことになっては、とて、普通の訪問を装って参上したが、人々が泣き騒いでいるので、本当だ、と騒ぐのであった。
式部卿の宮も二条院を訪問して、悲しみにご放心した様子で入っていった。人の来訪にも、ご挨拶もできず、夕霧の君が涙を拭って出てくると、
「一体どうしたのですか。縁起でもないことを皆が言っている、信じがたい。久しく病気と承っていたのでお見舞いに来ました」
などと仰せになる。
「病気が重くなって、月日が経ちますが、この暁に息が絶えたのですが、物の怪の仕業でありました。ようやく息をふきかえしたと聞いております。今皆ほっとしているようですが、まだ安心できません。おいたわしい限りです」
と言って、本当にひどく泣いた気色であった。目元が少しはれていた。柏木は、自分の恋心にてらして、『この君も、さして親しくもしていない継母のことを、ずいぶん心に思っていたのか』、と目に止めた。
このように見舞客が来てるのを源氏は聞いて、
「病気が重くなり、にわかに臨終かと思われる様子になり、女房たちは、落ち着かず、騒がしいので、わたしも落ち着きもなくなって、あわただしい。後日改めて、こうしてお出で下さったお礼は申し上げよう」
と源氏は仰せになった。柏木は胸がつぶれて、このようなのっぴきならぬ事情がなければ参上できず、何がしか気が引けるのも、心のうちが、後ろめたいからだ。 |
|
| 35.51 紫の上、蘇生後に五戒を受く |
かく生き出でたまひての後しも、恐ろしく思して、またまた、いみじき法どもを尽くして加へ行なはせたまふ。
うつし人にてだに、むくつけかりし人の御けはひの、まして世変はり、妖しきもののさまになりたまへらむを思しやるに、いと心憂ければ、中宮を扱ひきこえたまふさへぞ、この折はもの憂く、言ひもてゆけば、女の身は、皆同じ罪深きもとゐぞかしと、なべての世の中厭はしく、かの、また人も聞かざりし御仲の睦物語に、すこし語り出でたまへりしことを言ひ出でたりしに、まことと思し出づるに、いとわづらはしく思さる。
御髪下ろしてむと切に思したれば、忌むことの力もやとて、御頂しるしばかり挟みて、五戒ばかり受けさせたてまつりたまふ。御戒の師、忌むことのすぐれたるよし、仏に申すにも、あはれに尊きこと混じりて、人悪く御かたはらに添ひゐて、涙おし拭ひたまひつつ、仏を諸心に念じきこえたまふさま、世にかしこくおはする人も、いとかく御心惑ふことにあたりては、え静めたまはぬわざなりけり。
いかなるわざをして、これを救ひかけとどめたてまつらむとのみ、夜昼思し嘆くに、ほれぼれしきまで、御顔もすこし面痩せたまひにたり。 |
こうして生き返った後も、恐ろしくて、またまた大そうな修法を数多く尽くして、加持祈祷を行わせた。
(六條御息所は)生きていたときでさへ、恐ろしい人だったのに、まして死後に、妖しい物になってしまったことを思うと、まことに気味が悪く、中宮をお世話すのも、この際は物憂くとどのつまりは、女というものは、皆同じく罪深い根源になっているのだ、男女の仲のすべてが厭わしく、あの、他の人が聞いていないはずの寝間の睦言も、すこし言い出したので、確かにそうだった、と思うと、ひどくわずらわしく思うのだった。
病人が剃髪出家したいと切に望んでいるので、持戒の功徳で回復することもあろうかと、頭髪にしるしばかりに鋏をいれて、五戒だけを受けさせた。戒を授ける師は、持戒の功徳が大きいことを、仏に申すにも、尊い言葉も交っていて、源氏は見苦しくまでに側に添って、仏を一心に念じ申し上げる様、世に偉い方も、このように心惑うことにあっては、冷静ではいられないのだ。
どんなことをしても紫の上を救いたいと思いつめていたので、夜昼思い嘆くに、腑抜けになってしまったように、顔も痩せてしまった。 |
|
| 35.52 紫の上、小康を得る |
五月などは、まして、晴れ晴れしからぬ空のけしきに、えさはやぎたまはねど、ありしよりはすこし良ろしきさまなり。されど、なほ絶えず悩みわたりたまふ。
もののけの罪救ふべきわざ、日ごとに法華経一部づつ供養ぜさせたまふ。日ごとに何くれと尊きわざせさせたまふ。御枕上近くても、不断の御読経、声尊き限りして読ませたまふ。現はれそめては、折々悲しげなることどもを言へど、さらにこのもののけ去り果てず。
いとど暑きほどは、息も絶えつつ、いよいよのみ弱りたまへば、いはむかたなく思し嘆きたり。なきやうなる御心地にも、かかる御けしきを心苦しく見たてまつりたまひて、
「世の中に亡くなりなむも、わが身にはさらに口惜しきこと残るまじけれど、かく思し惑ふめるに、空しく見なされたてまつらむが、いと思ひ隈なかるべければ」、思ひ起こして、御湯などいささか参るけにや、六月になりてぞ、時々御頭もたげたまひける。めづらしく見たてまつりたまふにも、なほ、いとゆゆしくて、六条の院にはあからさまにもえ渡りたまはず。 |
五月になって、梅雨がちで晴れることのない空の気色で、すっきりした気分にはなれないが、以前よりは良くなった。それでも、絶え間なく物の怪に悩まされる。
御息所の死霊の罪を救うべく、毎日法華経を一部ずつ供養させていた。日ごとにあれこれと尊い供養をさせるのだった。枕上近くで、不断の読経、声の好い僧ばかりで読ませた。物の怪は現れそうになって、時々悲しげなことを言うが、それでもまったく消え去ることはなかった。
暑くなると、紫の上は息も絶えそうになるが、いよいよ弱ってくると、言いようもなく源氏は思い嘆くのだった。意識もないような状態でも源氏の悲しむ様子を心苦しく見て、
「世の中からわたしが亡くなっても、わたしは未練がないが、このような心痛をされて、はかなくなった自分の姿を空しくご覧に入れるのは、わたしの思いが至らないのです」と気を奮い起こして、薬などを飲んだせいか、六月になって、時々頭をもたげるようになった。源氏は、久しぶりのことと喜ばれるが、まだとても心配で、六条の院には、時折でも帰らないのであった。 |
|
| 35.53 女三の宮懐妊す |
姫宮は、あやしかりしことを思し嘆きしより、やがて例のさまにもおはせず、悩ましくしたまへど、おどろおどろしくはあらず、立ちぬる月より、物きこし召さで、いたく青みそこなはれたまふ。
かの人は、わりなく思ひあまる時々は、夢のやうに見たてまつりけれど、宮、尽きせずわりなきことに思したり。院をいみじく懼ぢきこえたまへる御心に、ありさまも人のほども、等しくだにやはある、いたくよしめきなまめきたれば、おほかたの人目にこそ、なべての人には優りてめでらるれ、幼くより、さるたぐひなき御ありさまに馴らひたまへる御心には、めざましくのみ見たまふほどに、かく悩みわたりたまふは、あはれなる御宿世にぞありける。
御乳母たち見たてまつりとがめて、院の渡らせたまふこともいとたまさかになるを、つぶやき恨みたてまつる。
かく悩みたまふと聞こし召してぞ渡りたまふ。女君は、暑くむつかしとて、御髪澄まして、すこしさはやかにもてなしたまへり。臥しながらうちやりたまへりしかば、とみにも乾かねど、つゆばかりうちふくみ、まよふ筋もなくて、いときよらにゆらゆらとして、青み衰へたまへるしも、色は真青に白くうつくしげに、透きたるやうに見ゆる御肌つきなど、世になくらうたげなり。もぬけたる虫の殻などのやうに、まだいとただよはしげにおはす。
年ごろ住みたまはで、すこし荒れたりつる院の内、たとしへなく狭げにさへ見ゆ。昨日今日かくものおぼえたまふ隙にて、心ことにつくろはれたる遣水、前栽の、うちつけに心地よげなるを見出だしたまひても、あはれに、今まで経にけるを思ほす。 |
姫宮は、あの思いもかけなかった出来事を思い嘆いて以来、やがていつもの具合ではなく、病気がちなり、ひどい病状ではなく、月が改まってから、食欲もなく、青ざめてやつれている。
柏木は、思い堪えかねる時々には、夢のようにはかなく逢いに来たが、宮は、どこまでも無体なことと思っていた。源氏をひどく怖がっていて、所作や人柄も柏木は源氏と同列と言えようか、とんでもない、ひどく気取っている様子など、大かたの人の目には、並みの人より優れていて褒められるだろうが、幼いころから源氏の類ない素晴らしさに馴れた身には、柏木を身の程知らずと見ていて、こんな胤を宿して病んでいる身には、あわれな宿世だった。
乳母たちは気が付いて、源氏がお越になるのもほんのたまになのに、とつぶやいている。
こうして(宮が)病気がちと聞いて、源氏が(六条院に)来た。紫の上は、暑くうっとうしいので、髪を洗って、少しさっぱりして風情で応じていた。横になったまま、髪を広げて、すぐには乾かないので、少し湿気を含んで、いささかも癖はなく毛筋はまっすぐ伸びて、美しくゆらゆらして、青味がかってやつれた顔が白くはえて、透き通るように見える肌の色など、この上なく愛おしかった。脱皮した虫の殻などのように、まだひどく頼りなさそうであった。
長く住んでいなかったので、少し荒れた(二条の)院の中は、大分狭くさへ見える。昨日今日と気持ちのはっきりした隙に、心をこめて作った鑓水、前栽の突然に心地よげなのを紫の上は見出して、今まで生きてこられたあわれを思った。 |
|
| 35.54 源氏、紫の上と和歌を唱和す |
池はいと涼しげにて、蓮の花の咲きわたれるに、葉はいと青やかにて、露きらきらと玉のやうに見えわたるを、
「かれ見たまへ。おのれ一人も涼しげなるかな」
とのたまふに、起き上がりて見出だしたまへるも、いとめづらしければ、
「かくて見たてまつるこそ、夢の心地すれ。いみじく、わが身さへ限りとおぼゆる折々のありしはや」
と、涙を浮けてのたまへば、みづからもあはれに思して、
「消え止まるほどやは経べきたまさかに
蓮の露のかかるばかりを」
とのたまふ。
「契り置かむこの世ならでも蓮葉に
玉ゐる露の心隔つな」
出でたまふ方ざまはもの憂けれど、内裏にも院にも、聞こし召さむところあり、悩みたまふと聞きてもほど経ぬるを、目に近きに心を惑はしつるほど、見たてまつることもをさをさなかりつるに、かかる雲間にさへやは絶え籠もらむと、思し立ちて、渡りたまひぬ。 |
池は、実に涼し気で、蓮の花が咲きわたって、葉は青く、露がきらきらと玉のように見えて、
「あれを見てごらんなさい。自分ひとりで涼し気にしている」
と仰せになって、紫の上が起き上がって見ようとすると、ついぞ最近ないことで、
「こうして見ていることが、夢のような心地がする。悲しみのあまり、この身も終わりかと思った折もあったが」
と涙を浮かべて仰せになるので、紫の上もあわれをもよおし、
(紫の上の歌)「消え残る露の間ほども生きていけるでしょうか
たまたま蓮の露が残っているだけのような私ですのに」
と紫の上が詠む。
(源氏の歌)「お約束しよう、あの世でも同じ蓮の葉の上にいると
私に露ほども隔てをおいてくださるな」
(源氏は)気が進まなかったが、帝も朱雀院もどうお聞きになるか、その手前もあり、(宮の)具合が悪いと聞いてほど経ているので、目前のことにかまけて、しばらくお逢いしてなかったので、このような雲の晴れ間に籠っているわけにはゆかない、と出かける。 |
|
| 35.55 源氏、女三の宮を見舞う |
宮は、御心の鬼に、見えたてまつらむも恥づかしう、つつましく思すに、物など聞こえたまふ御いらへも、聞こえたまはねば、日ごろの積もりを、さすがにさりげなくてつらしと思しけると、心苦しければ、とかくこしらへきこえたまふ。大人びたる人召して、御心地のさまなど問ひたまふ。
「例のさまならぬ御心地になむ」
と、わづらひたまふ御ありさまを聞こゆ。
「 あやしく。ほど経てめづらしき御ことにも」
とばかりのたまひて、御心のうちには、
「年ごろ経ぬる人びとだにもさることなきを、不定なる御事にもや」
と思せば、ことにともかくものたまひあへしらひたまはで、ただ、うち悩みたまへるさまのいとらうたげなるを、あはれと見たてまつりたまふ。
からうして思し立ちて渡りたまひしかば、ふともえ帰りたまはで、二、三日おはするほど、「いかに、いかに」とうしろめたく思さるれば、御文をのみ書き尽くしたまふ。
「いつの間に積もる御言の葉にかあらむ。いでや、やすからぬ世をも見るかな」
と、若君の御過ちを知らぬ人は言ふ。侍従ぞ、かかるにつけても胸うち騷ぎける。
かの人も、かく渡りたまへりと聞くに、おほけなく心誤りして、いみじきことどもを書き続けて、おこせたまへり。対にあからさまに渡りたまへるほどに、人間なりければ、忍びて見せたてまつる。
「むつかしきもの見するこそ、いと心憂けれ。心地のいとど悪しきに」
とて臥したまへれば、
「なほ、ただ、この端書きの、いとほしげにはべるぞや」
とて広げたれば、人の参るに、いと苦しくて、御几帳引き寄せて去りぬ。
いとど胸つぶるるに、院入りたまへば、えよくも隠したまはで、御茵の下にさし挟みたまひつ。 |
宮は、気が咎めて、源氏に会うのが空恐ろしく気が引けるので、源氏の質問にも答えられないでいると、源氏は日ごろのご無沙汰を、さすがに表には出さないがひどいと思っているのだと気の毒になったので、何かとなだめるのだった。年配の乳母を呼んで、気分のほどを問いただす。
「普通とは違ったお加減です」
と患いの様子を申し上げる。
「どうしたのだろう、今頃になって珍しいこともあるものだ」
と仰せになって、心の内では、
「長く連れ添った夫婦でも子に恵まれないのもあるのに、確かなのか」
と思うに、(源氏は)特にあれこれと仰ることもなく、ただ、苦しんでいらっしゃる様子がとても痛々しげなのを、あわれと見るのだった。
ようやく思い立って六条院に来たので、すぐにも帰らず、二、三日いるうちに、「紫の上はどうしているか」と心配で、文をのみたくさん書くのだった。
「いつの間にか積もる言葉があるのでしょう。何かと、心配なのでしょう」
と姫君の過ちを知らない女房は言う。侍従だけはこのようなことに胸騒ぎした。
柏木も、源氏が三の宮の元へ行っていると聞くと、身の程知らずにも料簡違いを起こして、文を届けた。東の対に、源氏が束の間行った時を見はからって、人が少なくなった時、秘かに見せた。
「厄介なものを見せるのね、気が進まないときに。気分が悪いのです」
と言って臥していると、
「でも、この端書がかわいそうで。」
と広げると、誰か来る。処置に困って、几帳を引き寄せて行ってしまった。
どきっとしていると、源氏が入って来たので、よく隠すこともできず敷物の下に挟んだ。 |
|
| 35.56 源氏、女三の宮と和歌を唱和す |
夜さりつ方、二条の院へ渡りたまはむとて、御暇聞こえたまふ。
「ここには、けしうはあらず見えたまふを、まだいとただよはしげなりしを、見捨てたるやうに思はるるも、今さらにいとほしくてなむ。ひがひがしく聞こえなす人ありとも、ゆめ心置きたまふな。今見直したまひてむ」
と語ひたまふ。例は、なまいはけなき戯れ言なども、うちとけ聞こえたまふを、いたくしめりて、さやかにも見合はせたてまつりたまはぬを、ただ世の恨めしき御けしきと心得たまふ。
昼の御座にうち臥したまひて、御物語など聞こえたまふほどに暮れにけり。すこし大殿籠もり入りにけるに、ひぐらしのはなやかに鳴くにおどろきたまひて、
「さらば、道たどたどしからぬほどに」
とて、御衣などたてまつり直す。
「月待ちて、とも言ふなるものを」
と、いと若やかなるさましてのたまふは、憎からずかし。「その間にも、とや思す」と、心苦しげに思して、立ち止まりたまふ。
「夕露に袖濡らせとやひぐらしの
鳴くを聞く聞く起きて行くらむ」
片なりなる御心にまかせて言ひ出でたまへるもらうたければ、ついゐて、
「あな、苦しや」
と、うち嘆きたまふ。
「待つ里もいかが聞くらむ方がたに
心騒がすひぐらしの声」
など思しやすらひて、なほ情けなからむも心苦しければ、止まりたまひぬ。静心なく、さすがに眺められたまひて、御くだものばかり参りなどして、大殿籠もりぬ。 |
夜になって、二条院へ行くために、暇を乞うた。
「あなたは、具合が悪そうには見えないし、紫の上はまだ頼りなげな様子で、見捨てたように思われたらかわいそう、わたしを悪しざまに言う人もいるでしょうが、気にしないでください。いずれ分かってくれます」
と(源氏が)仰せになる。いつもは、子供っぽい冗談も、無邪気に話すのだが、(三の宮が)ひどく沈んでいてまともには顔を合わせないのは、いつもそばにいないのを拗ねているのだと理解した。
昼の御座に臥して、三の宮に物語などするうちに暮れになった。少しうとうとして、ひぐらしが派手に鳴いているのに驚いて目が覚めると、
「それでは、途中暗くならないうちに」
とて、衣などをあらためる。
「月の出を待ってから、と歌にもあります」
(女三の宮は)いかにも初々しく仰るのは、愛くるしい。「その間にも」と仰せになると、心苦しげに思って立ち止まった。
(女三の宮の歌)「夕暮れの露に袖を濡らして泣けとや
ひぐらしの鳴くのを聞いて起きて行かれるのですね」
子供のようにあどけない気持ちのまま歌に詠うのも可憐であった。膝まづいて、
「ほんとうに困りました」
と源氏は嘆くのであった。
「帰りを待っている里でどんな気持ちで聞くことだろう
心騒がすひぐらしの声だ」
などと思って、それでも薄情なのもお気の毒なので、泊まった。あちらが気にかかって、さすがに気持ちが沈んで、果物ばかり食べて、寝た。 |
|
| 35.57 源氏、柏木の手紙を発見 |
まだ朝涼みのほどに渡りたまはむとて、とく起きたまふ。
「昨夜のかはほりを落として、これは風ぬるくこそありけれ」
とて、御扇置きたまひて、昨日うたた寝したまへりし御座のあたりを、立ち止まりて見たまふに、御茵のすこしまよひたるつまより、浅緑の薄様なる文の、押し巻きたる端見ゆるを、何心もなく引き出でて御覧ずるに、男の手なり。紙の香などいと艶に、ことさらめきたる書きざまなり。二重ねにこまごまと書きたるを見たまふに、「紛るべき方なく、その人の手なりけり」と見たまひつ。
御鏡など開けて参らする人は、見たまふ文にこそはと、心も知らぬに、小侍従見つけて、昨日の文の色と見るに、いといみじく、胸つぶつぶと鳴る心地す。御粥など参る方に目も見やらず、
「いで、さりとも、それにはあらじ。いといみじく、さることはありなむや。隠いたまひてけむ」
と思ひなす。
宮は、何心もなく、まだ大殿籠もれり。
「あな、いはけな。かかる物を散らしたまひて。我ならぬ人も見つけたらましかば」
と思すも、心劣りして、
「さればよ。いとむげに心にくきところなき御ありさまを、うしろめたしとは見るかし」
と思す。 |
まだ朝涼しい頃に帰ろうとして、早く起きた。
「昨夜の扇を落としてしまった。この扇は風が生ぬるいな」
といって、扇を置いて、昨日うたた寝したあたりを、立ち止まって見回しすと、敷物の少しめくれた端から浅緑の薄様な文の、少し巻いた端が見えるので、何気なく引き出して見ると、男の手の文だった。紙の香りなどたいそうしゃれていて、ひどく気取った書き方であった。二重にこまごまと書いてあり、「まぎれもなく柏木の手だ」と見た。
鏡をかかげる女房は、源氏の見るべき文だろうと、事情も知らないでいると、小侍従が見つけて、昨日の文の色と見て、大へんなことになった、胸がどきどきした。お粥の方には目もくれず、
「まさか、あの手紙ではないだろう。そんなことがあるはずがない。きっと隠したに違いない。」
と思い直す。
宮は何心もなく、まだ寝ている。
「何と幼い。このような文を、こんな処に放置して。わたし以外の人が見たら」
と思うが、見下す気持ちが生じて、
「やっぱりだ。もう全くたしなみ深いところがないお人だから、心配させるのだ」
と思う。 |
|
| 35.58 小侍従、女三の宮を責める |
出でたまひぬれば、人びとすこしあかれぬるに、侍従寄りて、
「昨日の物は、いかがせさせたまひてし。今朝、院の御覧じつる文の色こそ、似てはべりつれ」
と聞こゆれば、あさましと思して、涙のただ出で来に出で来れば、いとほしきものから、「いふかひなの御さまや」と見たてまつる。
「いづくにかは、置かせたまひてし。人びとの参りしに、ことあり顔に近くさぶらはじと、さばかりの忌みをだに、心の鬼に避りはべりしを。入らせたまひしほどは、すこしほど経はべりにしを、隠させたまひつらむとなむ、思うたまへし」
と聞こゆれば、
「いさ、とよ。見しほどに入りたまひしかば、ふともえ置きあへで、さし挟みしを、忘れにけり」
とのたまふに、いと聞こえむかたなし。寄りて見れば、いづくのかはあらむ。
「あな、いみじ。かの君も、いといたく懼ぢ憚りて、けしきにても漏り聞かせたまふことあらばと、かしこまりきこえたまひしものを。ほどだに経ず、かかることの出でまうで来るよ。すべて、いはけなき御ありさまにて、人にも見えさせたまひければ、年ごろさばかり忘れがたく、恨み言ひわたりたまひしかど、かくまで思うたまへし御ことかは。誰が御ためにも、いとほしくはべるべきこと」
と、憚りもなく聞こゆ。心やすく若くおはすれば、馴れきこえたるなめり。いらへもしたまはで、ただ泣きにのみぞ泣きたまふ。いと悩ましげにて、つゆばかりの物もきこしめさねば、
「かく悩ましくせさせたまふを、見おきたてまつりたまひて、今はおこたり果てたまひにたる御扱ひに、心を入れたまへること」
と、つらく思ひ言ふ。 |
源氏がお帰りになり、女房たちが空いたので、小侍従が寄って、
「昨日の文はどうされましたか。今朝院がご覧になっていた文の色が似ていたようですが」
と問うと、大へんだと驚いて、ただ泣いてばかりだった、小侍従はかわいそうになり、「どうしようもないお方だ」と思うのだった。
「どこに置かれたのですか。女房たちが来たので、わけあり顔に近くにいてはいけないと、わたしはこんな気を遣っているのに。源氏の君が入って来た時は、少し間があったので、きっと隠したに違いない、思いましたが」
と言えば、
「いいえそれが、見ているときに君が入ってこられたので、すぐにも仕舞えずに、敷物の下にさし挟んで、忘れてしまったのです」
と言うので、あきれて返事のしようがない。寄って探したが、どこにあろうか。
「あら、大へんだ。柏木の君も、源氏の君をひどく恐れて、露ほども知られまいと、恐れていましたので、いくばくも経たないでこんなことになるなんて。大体が、幼くて不用心にも、外から人に見られたので、相手が忘れがたくなり、わたしをも恨んで、手引するよう言い続けまして、これほどまでに思い込んだのです。誰にとっても、困ったことになってしまいました」
と、あけすけに言うのであった。気の置けない若い同士なので、馴れているのであろう。(宮は)答えることもせず、ただ泣きじゃくっている。つらそうに、何も食べないので、
「こちらはこんなに具合が悪いのに、放置してしまって、すっかり良くなった方の世話をやいている」
と源氏の仕打ちに不平を言う。 |
|
| 35.59 源氏、手紙を読み返す |
大殿は、この文のなほあやしく思さるれば、人見ぬ方にて、うち返しつつ見たまふ。「さぶらふ人びとの中に、かの中納言の手に似たる手して書きたるか」とまで思し寄れど、言葉づかひきらきらと、まがふべくもあらぬことどもあり。
「年を経て思ひわたりけることの、たまさかに本意かなひて、心やすからぬ筋を書き尽くしたる言葉、いと見所ありてあはれなれど、いとかくさやかには書くべしや。あたら人の、文をこそ思ひやりなく書きけれ。落ち散ることもこそと思ひしかば、昔、かやうにこまかなるべき折ふしにも、ことそぎつつこそ書き紛らはししか。人の深き用意は難きわざなりけり」
と、かの人の心をさへ見落としたまひつ。 |
源氏は、この文を不審に思ったので、人に見られなところで、繰り返しご覧になる。「お付きの人の中で、あの柏木の手に似せて書いたのか」とまで思ったが、言葉遣いははっきりして、本人に間違いようがないものだった。
「長年思い続けたことの、本意がたまたまかなって、それ以来不安でならない恋心を連綿と書き綴った言葉は、見る者の心を打つものだったが、こんなにはっきり書くものだろうか。柏木ともあろう人が、迂闊な文を書いたものだ。落として人に見られることもあろうに、昔は、このように細かく書きたい時でも、言葉を省略して分からないようにしたものだ。深く用心することはむつかしいものだ」
と柏木の心根さえ見分けるのだった。 |
|
| 35.60 源氏、妻の密通を思う |
「さても、この人をばいかがもてなしきこゆべき。めづらしきさまの御心地も、かかることの紛れにてなりけり。いで、あな、心憂や。かく、人伝てならず憂きことを知るしる、ありしながら見たてまつらむよ」
と、わが御心ながらも、え思ひ直すまじくおぼゆるを、
「なほざりのすさびと、初めより心をとどめぬ人だに、また異ざまの心分くらむと思ふは、心づきなく思ひ隔てらるるを、ましてこれは、さま異に、おほけなき人の心にもありけるかな。
帝の御妻をも過つたぐひ、昔もありけれど、それはまたいふ方異なり。宮仕へといひて、我も人も同じ君に馴れ仕うまつるほどに、おのづから、さるべき方につけても、心を交はしそめ、もののまぎれ多かりぬべきわざなり。
女御、更衣といへど、とある筋かかる方につけて、かたほなる人もあり、心ばせかならず重からぬうち混じりて、思はずなることもあれど、 おぼろけの定かなる過ち見えぬほどは、さても交じらふやうもあらむに、ふとしもあらはならぬ紛れありぬべし。
かくばかり、またなきさまにもてなしきこえて、うちうちの心ざし引く方よりも、いつくしくかたじけなきものに思ひはぐくまむ人をおきて、かかることは、さらにたぐひあらじ」
と、爪弾きせられたまふ。
「帝と聞こゆれど、ただ素直に、公ざまの心ばへばかりにて、宮仕へのほどもものすさまじきに、心ざし深き私のねぎ言になびき、おのがじしあはれを尽くし、見過ぐしがたき折のいらへをも言ひそめ、自然に心通ひそむらむ仲らひは、同じけしからぬ筋なれど、寄る方ありや。わが身ながらも、さばかりの人に心分けたまふべくはおぼえぬものを」
と、いと心づきなけれど、また「けしきに出だすべきことにもあらず」など、思し乱るるにつけて、
「故院の上も、かく御心には知ろし召してや、知らず顔を作らせたまひけむ。思へば、その世のことこそは、いと恐ろしく、あるまじき過ちなりけれ」
と、近き例を思すにぞ、恋の山路は、えもどくまじき御心まじりける。 |
「さて、この宮をどのように遇したらいいものだろう。妊娠しているのも、このことのせいだろう。いや、嫌だ。こうして人伝ではなく嫌なことを知るのも、今まで通り妻としてお世話するのだろうか」
と、自分の心ながら、決して昔に戻れないと感じていた。
「軽い遊びの気持ちで、初めから愛してもいない女でも、他の男に秋波を送る女は、興覚めの気持ちになるものだが、まして、これは全く違う、身の程知らずの柏木は大胆なことをしたものだ。
「帝の妻にも、過ちは昔もあったが、それはまた別の事情だ。宮仕えといっても、男も女も同じ帝に馴れ仕えるのだから、自ずと、それ相応のいきさつがあって、心を交わし合うようになり、密事もいろいろあって不思議はない。
女御、更衣といっても、あれこれ事情もあって、どうかと思われる人もあり、必ずしも心ざしやたしなみが深いとはいえぬ人も混じっていて、思いもかけないこともあるが、はっきりと不始末が人目につかないまま、表沙汰にならないでしまうこともある。
これ程にも、この上なく丁重なお世話をして、本当に惹かれている紫の上よりも、いっそう大切な人とお世話している自分をさしおいて、こんなことは例がないだろう」
と非難するのだった。
「帝に仕えるといっても、ただ素直に、内裏の宮仕えを務めているだけで、後宮がなんとなく面白くなく、思い込んだ男の熱意に靡き、それぞれが思いを尽くして、見過ごせない文に返事もするようになり、自然に心が通うような仲になるのは、同じくけしからんことだが、まだ許せるというものだ。自分のことながら、柏木ごときの男に宮が心を傾けるとは思えないのだが」
と、不愉快だが、また、「決して態度に出してはいけないこと」などと思い乱れるにつけ、
「故桐壷帝も、このようにすべてを知っていて、知らん顔をしていたのだろうか。思えば、あの昔の一件こそ、恐ろしいことで、あるまじき過ちだった」
と、自分のことを思い恋の山路は非難できないという気持ちになる。 |
|
| 35.61 紫の上、女三の宮を気づかう |
つれなしづくりたまへど、もの思し乱るるさまのしるければ、女君、消え残りたるいとほしみに渡りたまひて、「人やりならず、心苦しう思ひやりきこえたまふにや」と思して、
「心地はよろしくなりにてはべるを、かの宮の悩ましげにおはすらむに、とく渡りたまひにしこそ、いとほしけれ」
と聞こえたまへば、
「さかし。例ならず見えたまひしかど、異なる心地にもおはせねば、おのづから心のどかに思ひてなむ。内裏よりは、たびたび御使ありけり。今日も御文ありつとか。院の、いとやむごとなく聞こえつけたまへれば、上もかく思したるなるべし。すこしおろかになどもあらむは、こなたかなた思さむことの、いとほしきぞや」
とて、うめきたまへば、
「内裏の聞こし召さむよりも、みづから恨めしと思ひきこえたまはむこそ、心苦しからめ。我は思し咎めずとも、よからぬさまに聞こえなす人びと、かならずあらむと思へば、いと苦しくなむ」
などのたまへば、
「げに、あながちに思ふ人のためには、わづらはしきよすがなけれど、よろづにたどり深きこと、とやかくやと、おほよそ人の思はむ心さへ思ひめぐらさるるを、これはただ、国王の御心やおきたまはむとばかりを憚らむは、浅き心地ぞしける」
と、ほほ笑みてのたまひ紛らはす。渡りたまはむことは、
「もろともに帰りてを。心のどかにあらむ」
とのみ聞こえたまふを、
「ここには、しばし心やすくてはべらむ。まづ渡りたまひて、人の御心も慰みなむほどにを」
と、聞こえ交はしたまふほどに、日ごろ経ぬ。 |
源氏は、何気ない風をよそおっているが、物思いに悩んでいるのは、明らかなので、紫の上は、命を取り留めたので、こちらへ来ているのだ、「自分のために、心配しているのでは」と思い、
「気分は良くなりました。あの宮はご病気でいらっしゃるのに、すぐにこちらへ来るのが、お気の毒です」
と(紫の上が)申し上げると、
「そうですね。普通のお身体ではないように見ましたが、別段病気でもないので、これなら安心と思って戻りました。帝からもたびたび使いがある。今日も文を使わされたようです。朱雀院から格別に頼まれているので、帝も気遣っているのです。 少しでも宮を疎略に扱おうものなら、お二人はどう思うであろうか、困ったことです」
と嘆息されたので、
「帝が何と思召されるかよりも、宮ご自身が自分を責めているのが、お気の毒です。自分で自分を咎めずとも、周りの者が良からぬ噂を言う人々が、必ずあることだから、わたしもつらい」
など(紫の上が)仰せになるので、
「なるほど、わたしがひたすら愛しく思っているあなたには、宮は煩わしい縁者になるでしょうが、あなたは万事につき深い思慮をめぐらして、女房たちがどう思うかまで思いめぐらすが、わたしはただ帝の機嫌ばかり気にして、考えが浅かった」
と微笑んで仰せになられる。宮のもとへお越になることは、
「一緒に六条院に帰ってから、のんびり過ごしましょう」
とだけ仰せになるのだった。
「わたしはしばらくここ二条院で、 のんびりしましょう。まず君が渡って三の宮の心を慰めてください」
と言葉を交わすうちに、日が経った。 |
|
| 35.62 柏木と女三の宮、密通露見におののく |
姫宮は、かく渡りたまはぬ日ごろの経るも、人の御つらさにのみ思すを、今は、「わが御おこたりうち混ぜてかくなりぬる」と思すに、院も聞こし召しつけて、いかに思し召さむと、世の中つつましくなむ。
かの人も、いみじげにのみ言ひわたれども、小侍従もわづらはしく思ひ嘆きて、「かかることなむ、ありし」と告げてければ、いとあさましく、
「いつのほどにさること出で来けむ。かかることは、あり経れば、おのづからけしきにても漏り出づるやうもや」
と思ひしだに、いとつつましく、空に目つきたるやうにおぼえしを、「ましてさばかり違ふべくもあらざりしことどもを見たまひてけむ」、恥づかしく、かたじけなく、かたはらいたきに、朝夕、涼みもなきころなれど、身もしむる心地して、いはむかたなくおぼゆ。
「年ごろ、まめごとにもあだことにも、召しまつはし参り馴れつるものを。人よりはこまかに思しとどめたる御けしきの、あはれになつかしきを、あさましくおほけなきものに心おかれたてまつりては、いかでかは目をも見合はせたてまつらむ。さりとて、かき絶えほのめき参らざらむも、人目あやしく、かの御心にも思し合はせむことのいみじさ」
など、やすからず思ふに、心地もいと悩ましくて、内裏へも参らず。さして重き罪には当たるべきならねど、身のいたづらになりぬる心地すれば、「さればよ」と、かつはわが心も、いとつらくおぼゆ。
「いでや、しづやかに心にくきけはひ見えたまはぬわたりぞや。まづは、かの御簾のはさまも、さるべきことかは。軽々しと、大将の思ひたまへるけしき見えきかし」
など、今ぞ思ひ合はする。しひてこのことを思ひさまさむと思ふ方にて、あながちに難つけたてまつらまほしきにやあらむ。 |
姫宮は、源氏が来ない日々に、これまでは源氏のすげなさのせいにしていたが、今は、「わたしの不始末のせいだ」と思うと、朱雀院もお聞きになったらどう思うだろうと、世間に顔向けできない気持ちだった。
柏木も、切なさそうに文を使わして手引を頼むが、小侍従もわずらわしく思い、「源氏が文を見付けた、」と告げると、柏木は、唖然として、
「いつそんなことがあったのだろう。こんなことは、日が経てば自ずから、気配で知れることだろう」
と思うと、身もすくむ思いで、空から見られているように覚えたので、「ましてあれほど間違えようもない文を見られたのでは」恥ずかしく、恐れ多く、いたたまれない思いで、朝夕、暑い頃でもあったが、身も凍るような気持ちがして、言いようもなく恐ろしく思った。
「年来,何かにつけて源氏のお側近くに参じて親しくさせていただいた。特に細かく目をかけていただいた、その気持ちがありがたく身にしみて感じているのに、あきれた不届き者と思われては、どうして顔を出すことができよう。しかし、まったくご無沙汰して参上しないのも、人が変に思うだろうし、源氏もやはりそうかと思い合わせるのが、恐ろしい」
などと、不安にさいなまされ、気分も重くすぐれず、内裏にも参上しない。さして重い罪にはならないだろうが、身の破滅になる心地がして、「やはりそうか」と自分でも思い、ひどくつらく思うのだった。
「考えてみれば、静かで心憎い気配が見えなかったのではないか。あの御簾の隙間も、あってはならなかった。軽々しい、と夕霧が思ったのが見えた」
などと、今思い合わせるのだった。しいて宮への思いを冷まそうとして、身勝手に宮を責めようとするのであろうか。 |
|
| 35.63 源氏、女三の宮の幼さを非難 |
|
|
| 35.64 源氏、玉鬘の賢さを思う |
右の大臣の北の方の、取り立てたる後見もなく、幼くより、ものはかなき世にさすらふるやうにて、生ひ出でたまひけれど、 かどかどしく労ありて、我もおほかたには親めきしかど、憎き心の添はぬにしもあらざりしを、なだらかにつれなくもてなして過ぐし、髭黒の大臣の、さる無心の女房に心合はせて入り来たりけむにも、けざやかにもて離れたるさまを、人にも見え知られ、ことさらに許されたるありさまにしなして、わが心と罪あるにはなさずなりにしなど、今思へば、いかにかどあることなりけり。
契り深き仲なりければ、長くかくて保たむことは、とてもかくても、同じごとあらましものから、心もてありしこととも、世人も思ひ出でば、すこし軽々しき思ひ加はりなまし、いといたくもてなしてしわざなり」と思し出づ。 |
右大臣の北の方(玉鬘)は、取り立てて後見もなく、幼少より、はかない世にさ迷うようにして、成長し、利発で思慮深く、源氏も表向きは親のように振舞ったが、憎からぬ気持ちも持っていたが、玉鬘は、かどを立てずにさりげなく受け流して、髭黒の大臣が、心無い女房の手引きで入って来たときも、自分のせいではない、と人にもはっきり分からせて、最終的にはわざわざ実父内大臣にも源氏にも正式に許された結婚として、自分が罪にならないようになしたのは,今思えば、大そう賢明であった。
(髭黒と玉鬘が)宿世が深かった仲なので、長くこうして絆を保っているのは、始めはどうあれ、同じことであったので、自分もその気があったのだと、世人も思い出せば、少し軽率な感じはするけれど、大そう見事に身を処したものだ」と思った。 |
|
| 35.65 朧月夜、出家す |
二条の尚侍の君をば、なほ絶えず、思ひ出できこえたまへど、かくうしろめたき筋のこと、憂きものに思し知りて、かの御心弱さも、少し軽く思ひなされたまひけり。
つひに御本意のことしたまひてけりと聞きたまひては、いとあはれに口惜しく、御心動きて、まづ訪らひきこえたまふ。今なむとだににほはしたまはざりけるつらさを、浅からず聞こえたまふ。
「海人の世をよそに聞かめや須磨の浦に
藻塩垂れしも誰れならなくに
さまざまなる世の定めなさを心に思ひつめて、今まで後れきこえぬる口惜しさを、思し捨てつとも、避りがたき御 回向のうちには、まづこそはと、あはれになむ」
など、多く聞こえたまへり。
とく思し立ちにしことなれど、この御妨げにかかづらひて、人にはしか表はしたまはぬことなれど、心のうちあはれに、昔よりつらき御契りを、さすがに浅くしも思し知られぬなど、かたがたに思し出でらる。
御返り、今はかくしも通ふまじき御文のとぢめと思せば、あはれにて、心とどめて書きたまふ、墨つきなど、いとをかし。
「常なき世とは身一つにのみ知りはべりにしを、後れぬとのたまはせたるになむ、げに、
海人舟にいかがは思ひおくれけむ
明石の浦にいさりせし君
回向には、あまねきかどにても、いかがは」
とあり。濃き青鈍の紙にて、樒にさしたまへる、例のことなれど、いたく過ぐしたる筆づかひ、 なほ古りがたくをかしげなり。 |
二条の尚侍の君すなわち朧月夜を、源氏は絶えず思い出していたが、このような後ろめたいことは、嫌なことと思い知って、相手の弱い心も、少し見下すのfだった。
女がついに、出家の本懐を遂げたと聞いて、大そうあわれにまた口惜しく思い、心が動いて、まず訪問した。今出家すると露ほども言わなかった仕打ちに、心から恨むのだった。
(源氏の歌) 「尼になること、他人事に聞けません、
須磨の浦に、海女の詫び住まいをしたのはこのわたしですから
さまざまな世の無常を心に思い知りましたが、今では出家に後れた口惜しさに、わたしを見捨てても、せめて修行の廻向のうちに、わたしを入れて下さるでしょうね」
など、多く書くのであった
(朧月夜は)早くに思い立っていたが、源氏の反対でのびて、人にはそのようにはっきり言わなかったが、心のうちは感無量で、昔からつらい契りだったが、さすがに浅い縁とは思わず、あれこれと思い出されるのだった。
返事の文は、今はこのように通う文も最後と思えば、あわれを感じ、心を込めて書くのだった、墨付きなど、趣があった。
「無常な世とはわが身ひとつに知っておりましたが、先を越されたとの仰せは、実に、
(朧月夜の歌)尼となったわたしの出家になぜに後れたのでしょう
明石の浦で漁をしたあなたが
廻向は、あまねく至りますのに、入らぬことがありましょうか」
とあり。濃い青鈍の紙に、樒にさした、おきまりの趣向ながら、ひどくしゃれた筆使い、いつまでも見ていたいく趣があった。 |
|
| 35.66 源氏、朧月夜と朝顔を語る |
二条院におはしますほどにて、女君にも、今はむげに絶えぬることにて、見せたてまつりたまふ。
「いといたくこそ恥づかしめられたれ。げに、心づきなしや。さまざま心細き世の中のありさまを、よく見過ぐしつるやうなるよ。なべての世のことにても、はかなくものを言ひ交はし、時々によせて、あはれをも知り、ゆゑをも過ぐさず、よそながらの睦び交はしつべき人は、 斎院とこの君とこそは残りありつるを、かくみな背き果てて、斎院はた、いみじうつとめて、紛れなく行なひにしみたまひにたなり。
なほ、ここらの人のありさまを聞き見る中に、深く思ふさまに、さすがになつかしきことの、 かの人の御なずらひにだにもあらざりけるかな。女子を生ほし立てむことよ、いと難かるべきわざなりけり。
宿世などいふらむものは、目に見えぬわざにて、親の心に任せがたし。生ひ立たむほどの心づかひは、なほ力入るべかめり。 よくこそ、あまたかたがたに心を乱るまじき契りなりけれ。年深くいらざりしほどは、さうざうしのわざや、さまざまに見ましかばとなむ、嘆かしきをりをりありし。
若宮を、心して生ほし立てたてまつりたまへ。女御は、ものの心を深く知りたまふほどならで、かく暇なき交らひをしたまへば、何事も心もとなき方にぞものしたまふらむ。御子たちなむ、なほ飽く限り人に点つかるまじくて、世をのどかに過ぐしたまはむに、うしろめたかるまじき心ばせ、つけまほしきわざなりける。限りありて、とざまかうざまの後見まうくるただ人は、おのづからそれにも助けられぬるを」
など聞こえたまへば、
「はかばかしきさまの御後見ならずとも、世にながらへむ限りは、見たてまつらぬやうあらじと思ふを、いかならむ」
とて、なほものを心細げにて、かく心にまかせて、行なひをもとどこほりなくしたまふ人びとを、うらやましく思ひきこえたまへり。
「尚侍の君に、さま変はりたまへらむ装束など、まだ裁ち馴れぬほどは訪らふべきを、袈裟などはいかに縫ふものぞ。それせさせたまへ。一領は、六条の東の君にものしつけむ。うるはしき法服だちては、うたて見目もけうとかるべし。さすがに、その心ばへ見せてを」
など聞こえたまふ。
青鈍の一領を、ここにはせさせたまふ。作物所の人召して、忍びて、尼の御具どものさるべきはじめのたまはす。御茵、上席、屏風、几帳などのことも、いと忍びて、わざとがましくいそがせたまひけり。 |
二条院へ行っていたときに、紫の上にも、今は関係はすっかり関係のない人なので、文を見せた。
「すごく恥をかかされたものだ。実に、自分に愛想が尽きました。様々に心細い世の中の有様を、よく見過ごしてきたものだ。普通の世間の、取りとめもない文を交わし、時々に寄せて、あわれを知り、深い情趣も見逃さず、さっぱりした親しい付き合いのできる人は、前斎院(朝顔の君)とこの朧月夜の君だけになってしまいました、こうして皆出家してしまって、斎院はまた熱心に仏前のお勤めをしています。
なお、たくさんの女性の有様をあれこれと見聞きするなかで、思慮深く心やさしいという点では、あの朝顔の君に比べられる人はいないのです。女子を教え育てるということは、なんと難しいことでしょうか。
宿世などというのは、目に見えないことでして、親の思い通りにならないものです。女を一人前になるまでの親の配慮は、それでも力を入れるべきものです。よくぞ、たくさんの女子の身の振り方について心配しなくてもよかった定めであった。若い頃は、物足りない、たくさんの女子がいればいいと、嘆いたものだが。
若宮を、大事に育ててください。母の女御はまだ物の心を深く知れる年ではないので、帝の寵愛厚く暇がなく交じらっていて、何事にしろ行き届かないでしょう。御子たちは、できる限り人に非難されることなく、世の中を穏やかに過ごせるように、心配のないように育ててほしい。宮は身分的制約があって、あれこれの後見になる夫を持つ普通の人は、自ずからそれに助けられることもあるだろうが」
などと仰せになると、
「きちんとお世話はできませんまでも、世に生きている限りは、面倒見させていただきたいと思っていますが、どうなりますやら」
とて、紫の上は、それでも心細げに、思い通りに、お勤めも滞りなくする人を、うらやましく思うのだった。
「尚侍の君に、出家のための装束など、まだ裁ち馴れていないうちはお世話するべきだが、袈裟などはどう縫うものか。やってください。一領は、六条の東の君の花散里にお願いしよう。正式な法服では見た目もなじみにくいでしょう。しかし一応は法衣らしく調えてください」
など、仰せになる。
青鈍の法衣一領を、紫の上方で用意させる。作物所の人を呼んで、内々に、尼として使用する手道具類を作るように下命する。御茵、上席、屏風、几帳なども内々に特別念を入れて支度させるのだった。 |
|
| 35.67 女二の宮、院の五十の賀を祝う |
かくて、山の帝の御賀も延びて、秋とありしを、八月は大将の御忌月にて、楽所のこと行なひたまはむに、便なかるべし。九月は、院の大后の崩れたまひにし月なれば、十月にと思しまうくるを、姫宮いたく悩みたまへば、また延びぬ。
衛門督の御預かりの宮なむ、その月には参りたまひける。太政大臣居立ちて、いかめしくこまかに、もののきよら、儀式を尽くしたまへりけり。督の君も、そのついでにぞ、思ひ起こして出でたまひける。なほ、悩ましく、例ならず病づきてのみ過ぐしたまふ。
宮も、うちはへてものをつつましく、いとほしとのみ思し嘆くけにやあらむ、月多く重なりたまふままに、いと苦しげにおはしませば、院は、心憂しと思ひきこえたまふ方こそあれ、いとらうたげにあえかなるさまして、かく悩みわたりたまふを、いかにおはせむと嘆かしくて、さまざまに思し嘆く。御祈りなど、今年は紛れ多くて過ぐしたまふ。 |
こうして、山の帝の御賀も延びて、秋の予定だったのが、八月は夕霧の母の忌月なので、夕霧が音楽のことを仕切るのは不都合だろう。九月は弘徽殿の皇太后の亡くなった月なので、十月を予定したが、姫宮の病が悪くなって、また延びた。
衛門督(柏木)が預かる二の宮は、十月には院の元に参上した。太政大臣が仕切って、厳かに細々と、気品に満ちて、儀式を尽くして行った。柏木も、ついでに、意を決して出かけた。まだ、気分がすぐれず、いつもと違って病気がちに過ごしていたのである。
三の宮も、引き続いて、世間に顔向けできないとの思いがつのって嘆くからか、懐妊の月が多くなるにつれ、苦し気になっていったので、源氏は、情けないことをしてくれたとの思いはあったが、つらそうにか弱くしている様子に、このように苦しんでいるのでどうなるかと心配であった。祈祷など今年は何かと取り込みが多く過ごした。 |
|
| 35.68 朱雀院、女三の宮へ手紙 |
御山にも聞こし召して、らうたく恋しと思ひきこえたまふ。月ごろかくほかほかにて、渡りたまふこともをさをさなきやうに、人の奏しければ、いかなるにかと御胸つぶれて、世の中も今さらに恨めしく思して、
「対の方のわづらひけるころは、なほその扱ひにと聞こし召してだに、なまやすからざりしを、そののち、直りがたくものしたまふらむは、そのころほひ、便なきことや出で来たりけむ。みづから知りたまふことならねど、良からぬ御後見どもの心にて、いかなることかありけむ。内裏わたりなどの、みやびを交はすべき仲らひなどにも、けしからず憂きこと言ひ出づるたぐひも聞こゆかし」
とさへ思し寄るも、こまやかなること思し捨ててし世なれど、なほ子の道は離れがたくて、宮に御文こまやかにてありけるを、大殿、おはしますほどにて、見たまふ。
「そのこととなくて、しばしばも聞こえぬほどに、おぼつかなくてのみ年月の過ぐるなむ、あはれなりける。悩みたまふなるさまは、詳しく聞きしのち、念誦のついでにも思ひやらるるは、いかが。世の中寂しく思はずなることありとも、忍び過ぐしたまへ。恨めしげなるけしきなど、おぼろけにて、見知り顔にほのめかす、いと品おくれたるわざになむ」
など、教へきこえたまへり。
いといとほしく心苦しく、「かかるうちうちのあさましきをば、聞こし召すべきにはあらで、わがおこたりに、本意なくのみ聞き思すらむことを」とばかり思し続けて、
「この御返りをば、いかが聞こえたまふ。心苦しき御消息に、まろこそいと苦しけれ。思はずに思ひきこゆることありとも、おろかに、人の見咎むばかりはあらじとこそ思ひはべれ。誰が聞こえたるにかあらむ」
とのたまふに、恥ぢらひて背きたまへる御姿も、いとらうたげなり。いたく面痩せて、もの思ひ屈したまへる、いとどあてにをかし。 |
朱雀院も、宮のことを聞き、いとおしく会いたいと思った。月ごろ、源氏が二条の院にいて、宮をに訪問していないと奏上する人があり、どんな事情かと胸が騒ぎ、世の中を今さらに恨めしく思い、
「紫の上が重態だったころは、その看病のためと聞いていたときも、心穏やかならぬものがあったが、その後も源氏の態度が元の通りにならないのは、そのころに、不都合なことが起こったのであろう、宮の責任ではないにしても、料簡のよくない女房がいて、何かあったのだろう。内裏でも、雅を交わす仲間内で、ありうべからざる不愉快な噂を耳にすることがあった」
とまで思い寄るが、肉親の情は捨てて出家したのだが、それでも親子の情は捨てがたく、宮にこまやかな文を遣わしたのを、源氏、そばにいたので、見たのだった。
「改まった用事もないので、しばしご無沙汰していましたが、様子も分からぬまま、年月が過ぎました。具合が悪いと聞きましたので、念誦をしながらも思いやられましたが、いかがですか。男女の仲は寂しくなる時もありますが、我慢が必要です。夫を恨むような素振りは、いい加減なことで、心配顔をするのは、品のいいことではありません」
などと諭している。
(源氏は、)帝をお気の毒に思い、「こうした内々の不始末はお聞きになるはずもなく、皆わたしの薄情のせいにして、不満に聞いておられるだろう」とばかり思って、
「どのように返事をするのでしょう。お気の毒なお手紙ですが、わたしこそ苦しいです。わたしは仮に心外に思うことがあっても、つれない振る舞いをして、人に咎められることだけはしまいと思っている。誰が告げ口したのか」
と仰せになるに、宮が恥じらって背を向けている姿は、痛々しい。ひどく面痩せして物思いに沈んでいる様は、いよいよ気品があった。 |
|
| 35.69 源氏、女三の宮を諭す |
「いと幼き御心ばへを見おきたまひて、いたくはうしろめたがりきこえたまふなりけりと、思ひあはせたてまつれば、今より後もよろづになむ。 .かうまでもいかで聞こえじと思へど、上の、御心に背くと聞こし召すらむことのやすからず、いぶせきを、 ここにだに聞こえ知らせでやはとてなむ。
いたり少なく、ただ、人の聞こえなす方にのみ寄るべかめる御心には、 ただおろかに浅きとのみ思し、また、今はこよなくさだ過ぎにたるありさまも、あなづらはしく目馴れてのみ見なしたまふらむも、かたがたに口惜しくもうれたくもおぼゆるを、院のおはしまさむほどは、なほ心収めて、かの思しおきてたるやうありけむ、さだ過ぎ人をも、同じくなずらへきこえて、いたくな軽めたまひそ。
いにしへより本意深き道にも、たどり薄かるべき女方にだに皆思ひ後れつつ、いとぬるきこと多かるを、みづからの心には、何ばかり思しまよふべきにはあらねど、今はと捨てたまひけむ世の後見に譲りおきたまへる御心ばへの、あはれにうれしかりしを、ひき続き争ひきこゆるやうにて、同じさまに見捨てたてまつらむことの、あへなく思されむにつつみてなむ。
心苦しと思ひし人びとも、今はかけとどめらるるほだしばかりなるもはべらず。女御も、かくて、行く末は知りがたけれど、御子たち数添ひたまふめれば、みづからの世だにのどけくはと見おきつべし。その他は、誰れも誰れも、あらむに従ひて、もろともに身を捨てむも、惜しかるまじき齢どもになりにたるを、やうやうすずしく思ひはべる。
院の御世の残り久しくもおはせじ。いと篤しくいとどなりまさりたまひて、もの心細げにのみ思したるに、今さらに思はずなる御名の漏り聞こえて、御心乱りたまふな。この世はいとやすし。ことにもあらず。後の世の御道の妨げならむも、罪いと恐ろしからむ」
など、まほにそのこととは明かしたまはねど、つくづくと聞こえ続けたまふに、涙のみ落ちつつ、我にもあらず思ひしみておはすれば、我もうち泣きたまひて、
「人の上にても、もどかしく聞き思ひし古人のさかしらよ。身に代はることにこそ。いかにうたての翁やと、むつかしくうるさき御心添ふらむ」
と、恥ぢたまひつつ、御硯引き寄せたまひて、手づから押し磨り、紙取りまかなひ、書かせたてまつりたまへど、御手もわななきて、え書きたまはず。
「かのこまかなりし返事は、いとかくしもつつまず通はしたまふらむかし」と思しやるに、いと憎ければ、よろづのあはれも冷めぬべけれど、言葉など教へて書かせたてまつりたまふ。 |
「院はあなたの幼い心ばえをよくご承知の上で、たいそう心配されていることを、思い合わせると、これからも心配でなりません。こんなことまで申し上げるのも何ですが、院が、わたしが約束に背いていると仰せになるのが、心外で安心できず、気が滅入るのですが、せめてあなたにだけには言っておこうと思います。
あなたは、考えが浅く、ただ人の言う方にのみ寄りがちなので、わたしがつれなくて愛情が薄いとばかりお考えで、今は盛りを過ぎたこの年を見くびって飽き飽きしていると思うのも、残念で情けないのだが、それでも院の在世中は、心に納めて、院のお考えもあったでしょうから、盛りを過ぎた人にも、父院と同じようにお考えになって、軽蔑しないようにしてください。
昔から出家願望がありました仏道の道にも、本来思慮の浅いはずの女方に後れをとっておりますが、実にはっきりせずにおりましたが、わたしとしては、何も思いまどうことはありませんが、院がいよいよと世を捨てて出家された後見にと譲られた心ばえが、あわれにうれしく、まるで競争するように、わたしも同じように出家して院をがっかりさせてはならない、と思いとどまっているのです。
わたしの出家後が心配だと思われる人々も、今は出家の妨げになるものもいません。女御もこうして、行く末は分かりませんが、御子たちもたくさんいらっしゃるので、わたしが生きている間は、無事でいると見てよいでしょう。そのほかは、それぞれが、事情によって、一緒に出家するもよし、悔いのない年になりましたので、ようやく安心できます。
院の余生も長くはないでしょう。病気が重くなって、心細げに思っているのに、今さら思いもしない噂が漏れ聞こえて、御心を乱すことはしないように。この現世だけのことなら、問題ありません。院の成仏の妨げになりかねない、その罪は恐ろしいのです」
など、まともに柏木の件とは言っていないが、しみじみと話続けるうちに、宮は涙を流し、心もここにない様子で悲しみに沈んでいるので、源氏も涙を流して、
「他人のこのような話を昔はおせっかいなと聞いていました。今は自分がするようになりました。ひどい爺と、うっとうしく思うでしょう」
と源氏は恥じながら、硯を引き寄せて、自ら硯を摩って、紙を取って用意して、書かせようとしたが、宮は手が震えて、まったく書けないのであった。
「あの細々した柏木の文の返事は、これほど気後れすることなく書くのであろう」と思いやると、憎らしいが、すべてに興醒めしてしまって、言葉を教えて書かせたのだった。 |
|
| 35.70 朱雀院の御賀、十二月に延引 |
参りたまはむことは、この月かくて過ぎぬ。二の宮の御勢ひ殊にて参りたまひけるを、古めかしき御身ざまにて、立ち並び顔ならむも、憚りある心地しけり。
「霜月はみづからの忌月なり。年の終りはた、いともの騒がし。また、いとどこの御姿も見苦しく、待ち見たまはむをと思ひはべれど、さりとて、さのみ延ぶべきことにやは。むつかしくもの思し乱れず、あきらかにもてなしたまひて、このいたく面痩せたまへる、つくろひたまへ」
など、いとらうたしと、さすがに見たてまつりたまふ。
衛門督をば、何ざまのことにも、ゆゑあるべきをりふしには、かならずことさらにまつはしたまひつつ、のたまはせ合はせしを、絶えてさる御消息もなし。人あやしと思ふらむと思せど、「見むにつけても、いとどほれぼれしきかた恥づかしく、見むにはまたわが心もただならずや」と思し返されつつ、やがて月ごろ参りたまはぬをも咎めなし。
おほかたの人は、なほ例ならず悩みわたりて、院にはた、御遊びなどなき年なれば、とのみ思ひわたるを、大将の君ぞ、「あるやうあることなるべし。好色者は、さだめてわがけしきとりしことには、忍ばぬにやありけむ」と思ひ寄れど、いとかく定かに残りなきさまならむとは、思ひ寄りたまはざりけり。 |
女三の宮が院の賀に参画する予定の十月はこうして過ぎた。二の宮が格別のご威勢で参られたので、身籠った身で、競うようにするのも、気が引けた。
「十一月は父桐壷院の忌月だった。年の瀬は何かとせわしない。また身籠った姿も見苦しく、お待ちかねの院がご覧になるだろうと思うと、どうして延せようか。くよくよ思い悩んだりせず、気分を切り替えて明るく振舞って、そのひどく面痩せした姿をつくろいなさい」
など、痛々しいとさすがに思うのであった。
衛門督は、何のことであれ、趣向をこらす催しには必ずつくろって、召されていたのだが、ぴったり来なくなり案内も出さなくなった。人は変に思うだろうと思ったが、源氏は「会えば、自分の馬鹿さ加減が恥ずかしくなるだろうし、また会えば平静ではいられなくなるだろうし」とあれこれ思うのだった。やがて来なくても、咎めなくなった。
世間一般の人は、例によって病気がすぐれないし、管弦の遊びなどない年だったので、とだけ思っていたが、夕霧は、「何か子細があるのだろう。柏木のような好き者は、わたしの勘では、恋心が修まらないのだろうと思うけれど、まさか、これほど収拾がつかないまでになっているとは思わなかった。 |
|
| 35.71 源氏、柏木を六条院に召す |
十二月になりにけり。十余日と定めて、舞ども習らし、殿のうちゆすりてののしる。二条の院の上は、まだ渡りたまはざりけるを、この試楽によりてぞ、えしづめ果てで渡りたまへる。女御の君も里におはします。このたびの御子は、また男にてなむおはしましける。すぎすぎいとをかしげにておはするを、明け暮れもて遊びたてまつりたまふになむ、過ぐる齢のしるし、うれしく思されける。試楽に、右大臣殿の北の方も渡りたまへり。
大将の君、丑寅の町にて、まづうちうちに調楽のやうに、明け暮れ遊び習らしたまひければ、かの御方は、御前の物は見たまはず。
衛門督を、かかることの折も交じらはせざらむは、いと栄なく、さうざうしかるべきうちに、人あやしと傾きぬべきことなれば、参りたまふべきよしありけるを、重くわづらふよし申して参らず。
さるは、そこはかと苦しげなる病にもあらざなるを、思ふ心のあるにやと、心苦しく思して、取り分きて御消息つかはす。父大臣も、
「などか返さひ申されける。ひがひがしきやうに、院にも聞こし召さむを、おどろおどろしき病にもあらず、助けて参りたまへ」
とそそのかしたまふに、かく重ねてのたまへれば、苦しと思ふ思ふ参りぬ。 |
十二月になった。十余日と定めて。舞どもを練習して、六条の院の邸中が大騒ぎであった。紫の上は、まだお越しにならかったが、試楽の当日、落ち着いてもおられず、お越しになった。女御の君も里帰りしていた。この度の御子は、また男子であった。次々とかわいらしくていらっしゃるので、明け暮れ遊び相手をして過ごしていた。長生きしたおかげとうれしく思うのだった。試楽には、右大臣の北の方(玉鬘)もお越しになった。
夕霧は、丑寅の町で、内々に練習を、毎日していたので、花散里は、御前での試楽はご覧にならなかった。
衛門督が、このような催しにも参加しないのは、いかにも催しが引き立たず、物足りないので、世間の人が不審に思うので、参加するよう催促されたが、病が思いということで、断るのだった。
しかし、はっきりとどこが悪いという病でもないので、自分に気がねしているのではと思い、特別に文を遣るのであった。父大臣も、
「どうして辞退するのか。不届きな態度のように、源氏も聞くであろうが、重病でもないので、何とかして行きなさい」
と(父大臣が)重ね重ね催促するので、つらいと思いながらも参上した。 |
|
| 35.72 源氏、柏木と対面す |
まだ上達部なども集ひたまはぬほどなりけり。例の気近き御簾の内に入れたまひて、母屋の御簾下ろしておはします。げに、いといたく痩せ痩せに青みて、例も誇りかにはなやぎたる方は、弟の君たちにはもて消たれて、いと用意あり顔にしづめたるさまぞことなるを、いとどしづめてさぶらひたまふさま、「などかは皇女たちの御かたはらにさし並べたらむに、さらに咎あるまじきを、 ただことのさまの、誰も誰もいと思ひやりなきこそ、いと罪許しがたけれ」など、御目とまれど、さりげなく、いとなつかしく、
「そのこととなくて、対面もいと久しくなりにけり。月ごろは、いろいろの病者を見あつかひ、心の暇なきほどに、院の御賀のため、ここにものしたまふ皇女の、法事仕うまつりたまふべくありしを、次々とどこほることしげくて、かく年もせめつれば、え思ひのごとくしあへで、型のごとくなむ、斎の御鉢参るべきを、御賀などいへば、ことことしきやうなれど、家に生ひ出づる童べの数多くなりにけるを御覧ぜさせむとて、舞など習はしはじめし、そのことをだに果たさむとて。拍子調へむこと、また誰れにかはと思ひめぐらしかねてなむ、月ごろ訪ぶらひものしたまはぬ恨みも捨ててける」
とのたまふ御けしきの、うらなきやうなるものから、いといと恥づかしきに、顔の色違ふらむとおぼえて、御いらへもとみに聞こえず。 |
まだ上達部たちが集っていない頃であった。源氏は、いつもの御座所で,柏木を近くに招じ入れて、母屋の御簾は下ろしてあった。実際、柏木は、ひどく痩せていて青味がかって、普段の陽気で華やかな様子は、弟君たちに圧倒されて、いかにも物静かに振舞う様子だが、今日は一段と物静かで、「皇女たちの側に夫として並べても、まったく遜色がない、ただ今度のことはどちらも配慮が足りない点が、許しがたいのだ」など気にかけてこだわっていたが、何事もなくさりげなく、やさしく語りかける、
「これといった要件もなく、会うのは久しぶりですね。この頃は、いろいろな病人の世話をして、隙がなかったので、院の御賀のため女三の宮の法事を執り行うことになっていたが、次々と延び延びになって、こうして年も詰まってくれば、思いどおりもできず、型通りに、精進料理をさしあげる予定ですが、御賀などといえば、大げさになりますので、家に生まれた子らが数多くなりましたので、ご覧に入れようと、舞など習わし、そのことだけでもやろうと思い、拍子調えることを、誰に頼もうかと思いめぐらしていましたが、幾月も顔を見せぬ恨みを捨ててあなたにお願いしようと思います」
と(源氏が)仰せになる気色の、何のこだわりもないようなので、柏木は顔も上げられないで、顔色も変わるような気がして、返事もすぐにはできなかった。 |
|
| 35.73 柏木と御賀について打ち合わせる |
「月ごろ、かたがたに思し悩む御こと、承り嘆きはべりながら、春のころほひより、例も患ひはべる乱り脚病といふもの、所狭く起こり患ひはべりて、はかばかしく踏み立つることもはべらず、月ごろに添へて沈みはべりてなむ、内裏などにも参らず、世の中跡絶えたるやうにて籠もりはべる。
院の御齢足りたまふ年なり、人よりさだかに数へたてまつり仕うまつるべきよし、、致仕の大臣思ひ及び申されしを、『冠を掛け、車を惜しまず捨ててし身にて、進み仕うまつらむに、つくところなし。げに、下臈なりとも、同じごと深きところはべらむ。その心御覧ぜられよ』と、催し申さるることのはべしかば、重き病を相助けてなむ、参りてはべし。
今は、いよいよいとかすかなるさまに思し澄まして、 いかめしき御よそひを待ちうけたてまつりたまはむこと、願はしくも思すまじく見たてまつりはべしを、事どもをば削がせたまひて、静かなる御物語の深き御願ひ叶はせたまはむなむ、まさりてはべるべき」
と申したまへば、いかめしく聞きし御賀の事を、女二の宮の御方ざまには言ひなさぬも、労ありと思す。
「ただかくなむ。こと削ぎたるさまに世人は浅く見るべきを、さはいへど、心得てものせらるるに、さればよとなむ、いとど思ひなられはべる。大将は、公方は、やうやう大人ぶめれど、かうやうに情けびたる方は、もとよりしまぬにやあらむ。
かの院、何事も心及びたまはぬことは、をさをさなきうちにも、楽の方のことは御心とどめて、いとかしこく知り調へたまへるを、さこそ思し捨てたるやうなれ、静かに聞こしめし澄まさむこと、今しもなむ心づかひせらるべき。かの大将ともろともに見入れて、舞の童べの用意、心ばへ、よく加へたまへ。物の師などいふものは、ただわが立てたることこそあれ、いと口惜しきものなり」
など、いとなつかしくのたまひつくるを、うれしきものから、苦しくつつましくて、言少なにて、この御前をとく立ちなむと思へば、例のやうにこまやかにもあらで、やうやうすべり出でぬ。
東の御殿にて、大将のつくろひ出だしたまふ楽人、舞人の装束のことなど、またまた行なひ加へたまふ。あるべき限りいみじく尽くしたまへるに、いとど詳しき心しらひ添ふも、げにこの道は、いと深き人にぞものしたまふめる |
「月ごろ、方々のご病気のことをお聞きしまして、胸を痛めておりましたが、わたしも春ころから、普段からみだり脚病(脚気)を病んでおります。大そうひどくなって苦しみまして、しっかり立ち歩むこともできず、月が経つにつれて、弱ってきました。内裏などにも参上せず、世間とも交渉を絶つようにして籠っておりました。
朱雀院のお年がちょうど五十になる年です。誰よりも心を込めてお祝いするべき由、致仕の大臣も申しておりました、『冠を挂け、車を惜しまず捨てて官職を退いた身で、進んでお祝い申し上げるのも、どうかと思われる。そなたはまだ卑官の身であっても、自分と同じように深い気持ちは持っていよう。その気持ちを御覧に入れなさい』と、申されましたので、重い病をおして、参上しました。
院には、穏やかな日々でひっそりお暮しのようですし、静かに仏道に余念がないようですので、盛大な儀を待ち望んではおられないと思われますので、諸事簡略にして、親娘のしみじみとした対面が叶いますようにしてさしあげるのが、上策かと思います」
と申し上げれば、盛大に執り行った女二の宮の賀を夫として仕切ったことを、一言も言わないのも、大したものだと思うのであった。
「ただご覧の通りの支度なのです。簡略にしたのを世間は志が浅いと見るでしょうが、よく分かってそう言って下さるので、安心しました。夕霧は、お役目の方は段々一人前になるようですが、このような風情の面では得手ではないのでしょう。
朱雀院は何事も心得ていらっしゃるので、楽の方は格別に造詣が深く、お話のように、すっかりこの世とを思い捨てたようですが、静かに耳をすましてお楽しみいただけるようにするべきでしょう。夕霧と一緒に面倒みていただいて、舞の童の準備や、心構えなど、よく教えてやってください。音楽の師などというものは、自分の専門の分野はともあれ、どうしようもないものです」
など、打ち解けてお頼みするので、うれしくも、苦しく身のちぢむ思いで、言葉少なく、御前を早く立去りたい思っていたので、いつものように、親しいお話も申し上げず、やっとの思いでさがった。
東の御殿で、夕霧が整えさせた楽人、舞人の装束のことなど、柏木がまた手を加えて教える。夕霧が念入りに手立てを尽くしたものに、事細かな趣向が加わって、柏木は音楽の道にはいかにも造詣が深かった。 |
|
| 35.74 御賀の試楽の当日 |
今日は、かかる試みの日なれど、御方々物見たまはむに、見所なくはあらせじとて、かの御賀の日は、赤き白橡に、葡萄染の下襲を着るべし、今日は、青色にの蘇芳襲、楽人三十人、今日は白襲を着たる、辰巳の方の釣殿に続きたる廊を楽所にて、山の南の側より御前に出づるほど、「仙遊霞」といふもの遊びて、雪のただいささか散るに、春のとなり近く、梅のけしき見るかひありてほほ笑みたり。
廂の御簾の内におはしませば、式部卿宮、右大臣ばかりさぶらひたまひて、それより下の上達部は簀子に、わざとならぬ日のことにて、御饗応など、気近きほどに仕うまつりなしたり。
右の大殿の四郎君、大将殿の三郎君、兵部卿宮の孫王の君たち二人は、「万歳楽」。まだいと小さきほどにて、いとらうたげなり。四人ながら、いづれとなく高き家の子にて、容貌をかしげにかしづき出でたる、思ひなしも、やむごとなし。
また、大将の典侍腹の二郎君、式部卿宮の兵衛督といひし、今は源中納言の御子、「皇じやう」。右の大殿の三郎君、「陵王」。大将殿の太郎、「落蹲」。さては「太平楽」、「喜春楽」などいふ舞どもをなむ、同じ御仲らひの君たち、大人たちなど舞ひける。
暮れゆけば、御簾上げさせたまひて、物の興まさるに、いとうつくしき御孫の君たちの容貌、姿にて、舞のさまも、世に見えぬ手を尽くして、御師どもも、おのおの手の限りを教へきこえけるに、深きかどかどしさを加へて、珍らかに舞ひたまふを、いづれをもいとらうたしと思す。老いたまへる上達部たちは、皆涙落としたまふ。式部卿宮も、御孫を思して、御鼻の色づくまでしほたれたまふ。 |
今日は、試楽の日であったが、夫人方たちが見物するので、見所があるようにと、御賀の当日は、赤い白橡に、葡萄染の下襲を着る予定であったが、今日は、青色に蘇芳襲を着せて、楽人三十人、今日は白襲を着せていた。辰巳の方の釣り殿に続く廊を楽所にして、山麓の南の側から御前に来るにつれて、「仙遊霞」を演奏し、雪がちらつき、春がちかく、梅の花がほころんでいた。
(源氏は、)御簾の中にいるので、式部卿の宮と髭黒の右大臣ばかりが側に控えていて、それより下の上達部は、簀子に、事々しくない試楽のなので、饗応なども手軽な感じでお出しになる。
右大臣の四郎君、夕霧の三郎君、蛍兵部卿の宮の孫王の君たちの二人は、「万歳楽」を舞う。まだ幼い年頃で、可愛らしい。四人とも、誰もかれも、高い家柄の子で、容貌はよくよそおわれている、そう思うせいか、気品がある。
また、夕霧の典侍腹の二郎君、式部卿宮の兵衛督という人の、今では源中納言になっている御子は、「皇じやう」。右大将の三郎君は、「陵王」、夕霧の子の太郎は、「落蹲」。そして、「太平楽」、「喜春楽」を舞った、同じ一族の君たちや、大人たちも一緒に舞った。
夕暮れになって、御簾を上げて、興が高じて、とても可愛らしい孫たちの容貌、姿、舞の様子も、素晴らしい秘技を尽くしていて、師たちも手を尽くして教えたので、深い利発さもあって、めったに見られぬ舞で、どの子も可愛らしいのだった。老いた上達部たちは、皆涙を流した。式部卿も、孫を思って、鼻の色が赤く色づくまで泣くのだった。 |
|
| 35.75 源氏、柏木に皮肉を言う |
主人の院、
「過ぐる齢に添へては、酔ひ泣きこそとどめがたきわざなりけれ。衛門督、心とどめてほほ笑まるる、いと心恥づかしや。さりとも、今しばしならむ。さかさまに行かぬ年月よ。老いはえ逃れぬわざなり」
とて、うち見やりたまふに、人よりけにまめだち屈じて、まことに心地もいと悩ましければ、いみじきことも目もとまらぬ心地する人をしも、さしわきて、空酔ひをしつつかくのたまふ。戯れのやうなれど、いとど胸つぶれて、盃のめぐり来るも頭いたくおぼゆれば、けしきばかりにて紛らはすを、御覧じ咎めて、持たせながらたびたび強ひたまへば、はしたなくて、もてわづらふさま、なべての人に似ずをかし。
心地かき乱りて堪へがたければ、まだことも果てぬにまかでたまひぬるままに、いといたく惑ひて、
「例の、いとおどろおどろしき酔ひにもあらぬを、いかなればかかるならむ。つつましとものを思ひつるに、気ののぼりぬるにや。いとさいふばかり臆すべき心弱さとはおぼえぬを、言ふかひなくもありけるかな」
とみづから思ひ知らる。
しばしの酔ひの惑ひにもあらざりけり。やがていといたくわづらひたまふ。大臣、母北の方思し騷ぎて、よそよそにていとおぼつかなしとて、殿に渡したてまつりたまふを、女宮の思したるさま、またいと心苦し。 |
源氏が仰せになる、
「年をとると、酔って泣いてしまう。衛門の督が、目を止めて微笑んでいるのが、(わたしは)気恥ずかしく思う。しかしそれも、しばらくのことでしょう。逆さまに時は流れて行かぬもの。年をとるのは、逃れられない」
とて、簀子にいる柏木を見やると、人よりかしこまって元気がなく、気分も悪そうなので、素晴らしい舞も見ていられないような気分の人を相手に、酔ったふりをしてこう仰せになる。冗談のように聞こえるが、柏木は源氏の言葉がこたえて、盃がめぐってくるのも、頭が痛いので、形ばかりで紛らわすのを、ご覧になって、無理に盃を持たせと、(柏木が)困りきっている様子は、並みの人と違って優雅であった。
気分が相当悪く、堪えがたいので、まだ宴が終わっていないのに退出したが、ひどく苦しく、
「いつものように、悪酔いしたわけでもないのに、どうしてこんなに気分が悪いのだろう。御前で、つつましく控えていたので、のぼせてしまったのか、そんなことで臆する自分ではないはず、何とも府甲斐ない」
と自ら思い知るのだった。
一時の悪酔いの苦しみではない。やがて本当に病気になった。大臣、母北の方が心配されて、別々に住んでいたのでは不都合と考えて、実家に戻したのだった。二の宮の心配される様子、お気の毒であった。 |
|
| 35.76 柏木、女二の宮邸を出る |
ことなくて過ぐす月日は、心のどかにあいな頼みして、いとしもあらぬ御心ざしなれど、今はと別れたてまつるべき門出にやと思ふは、あはれに悲しく、後れて思し嘆かむことのかたじけなきを、いみじと思ふ。母御息所も、いといみじく嘆きたまひて、
「世のこととして、親をばなほさるものにおきたてまつりて、かかる御仲らひは、とある折もかかる折も、離れたまはぬこそ例のことなれ、かく引き別れて、たひらかにものしたまふまでも過ぐしたまはむが、心尽くしなるべきことを、しばしここにて、かくて試みたまへ」
と、御かたはらに御几帳ばかりを隔てて見たてまつりたまふ。
「ことわりや。数ならぬ身にて、及びがたき御仲らひに、なまじひに許されたてまつりて、さぶらふしるしには、長く世にはべりて、かひなき身のほども、すこし人と等しくなるけぢめをもや御覧ぜらるる、とこそ思うたまへつれ、いといみじく、かくさへなりはべれば、深き心ざしをだに御覧じ果てられずやなりはべりなむと思うたまふるになむ、とまりがたき心地にも、え行きやるまじく思ひたまへらるる」
など、かたみに泣きたまひて、とみにもえ渡りたまはねば、また母北の方、うしろめたく思して、
「などか、まづ見えむとは思ひたまふまじき。われは、心地もすこし例ならず心細き時は、あまたの中に、まづ取り分きてゆかしくも頼もしくもこそおぼえたまへ。かくいとおぼつかなきこと」
と恨みきこえたまふも、また、いとことわりなり。
「人より先なりけるけぢめにや、取り分きて思ひならひたるを、今になほかなしくしたまひて、しばしも見えぬをば苦しきものにしたまへば、心地のかく限りにおぼゆる折しも、見えたてまつらざらむ、罪深く、いぶせかるべし。
今はと頼みなく聞かせたまはば、いと忍びて渡りたまひて御覧ぜよ。かならずまた対面賜はらむ。 あやしくたゆくおろかなる本性にて、ことに触れておろかに思さるることありつらむこそ、悔しくはべれ。かかる命のほどを知らで、行く末長くのみ思ひはべりけること」
と、泣く泣く渡りたまひぬ。宮はとまりたまひて、言ふ方なく思しこがれたり。 |
何事もなく過ごした日々は、のんきに先のことを当てにして、格別の愛情はなかったが、今は死出の門出と思うのだろうか、あわれに悲しく、二の宮が自分の死後に残って嘆くのを、恐れ多いと、(柏木は)思うのだった。二の宮の母の御息所も、嘆いて、
「世の通例として、親はひとまずさしおいて、このような夫婦の仲は、どういうことがありましょうとも、離れないのが普通です。別れ別れに生活して、すっかり治癒するまで過ごすのは、心配でならないでしょうから、しばらくは、こちらで養生したらどうでしょう」
と(母御息所は)病床の傍らに几帳だけを隔てて看病した。
「ごもっともです。数ならぬ身で、及びもつかぬ夫婦という縁に、無理にもお許しいただきまして、長く世に生きて、はかない身で少しは人と肩を並べるところまでは出世をしてご覧に入れられると、思っておりましたが、残念ながらこんなことになりましたので、深い心ざしもご覧んにいれられないと思うと、この世にはもう留まれないにしても、あの世には安心して行けそうにないように思われます」
などと、互いに泣きつくして、すぐにも父邸に移らないのを、母北の方は、心配されて、
†「どうして、まずわたしに顔を見せようとしないのでしょうか。わたしは少しでも心細いときは、多くの子らの中で、そなたに会いたいともまた頼りだとも思われるのです。どうしておられたか」
と恨みがましく言うのも、またもっともなことだ。
「人より先に生まれたからなのでしょう。取り分けかわいがっていただいたのを、今なお私を愛おしく思っていただいて、少し見ないとつらいと言ってくるのに、もう駄目かと思うときに、お会いできないのは、罪深く気にかかかることでしょう。
今はもう最後です、となれば、忍んでも来ることでしょう。必ず対面できるでしょう。どうしたわけか、わたしは気がきかないなおざりな性分で、何かにつけて疎略にお扱いしたのではないか、と後悔しております。こうした短い命とも知ず、末永く生きられると思っていました」
と、(柏木は)泣く泣く父の邸に帰っていった。宮は残って、たいそう思いこがれた。 |
|
| 35.77 柏木の病、さらに重くなる |
大殿に待ち受けきこえたまひて、よろづに騷ぎたまふ。さるは、たちまちにおどろおどろしき御心地のさまにもあらず、月ごろ物などをさらに参らざりけるに、いとどはかなき柑子などをだに触れたまはず、ただ、やうやうものに引き入るるやうに見えたまふ。
さる時の有職の、かくものしたまへば、世の中惜しみあたらしがりて、御訪らひに参りたまはぬ人なし。内裏よりも院よりも、御訪らひしばしば聞こえつつ、いみじく惜しみ思し召したるにも、いとどしき親たちの御心のみ惑ふ。
六条院にも、「いと口惜しきわざなり」と思しおどろきて、御訪らひにたびたびねむごろに父大臣にも聞こえたまふ。大将は、ましていとよき御仲なれば、気近くものしたまひつつ、いみじく嘆きありきたまふ。
御賀は、二十五日になりにけり。かかる時のやむごとなき上達部の重く患ひたまふに、親、兄弟、あまたの人びと、さる高き御仲らひの嘆きしをれたまへるころほひにて、ものすさまじきやうなれど、次々に滞りつることだにあるを、さて止むまじきことなれば、いかでかは思し止まらむ。女宮の御心のうちをぞ、いとほしく思ひきこえさせたまふ。
例の、五十寺の御誦経、また、かのおはします御寺にも、摩訶毘盧遮那の。 |
父大臣邸では柏木を待ち受けていて、何かと大騒ぎである。そうはいっても、急に重態になったわけではない。月ごろ、食事も召し上がらず、軽い柑子なども手に触れない。ただ、何か少しづつ物に引き込まれるように弱っていくように見えるのだった。
このような、当代の重要人物が、病気になって、世の人惜しみ残念がって、お見舞いに次々と来た。内裏からも院からもしばしばお見舞いがやって来て、たいそう残念がるのであった、いよいよ深まる親たちの心配も気も狂わんばかりだった。
源氏も、「大そう残念なことだな」と思い驚いて、たびたびお見舞いに遣わせて、父大臣にも見舞いの文を遣るのであった。まして夕霧は、とりわけ仲の良い友人なので、近くに寄って、ひどく嘆くのだった。
朱雀院の御賀は、二十五日になった。このようなとき、身分の高い上達部が重い病にかかって、親、兄弟、多くの人々など、多くの身分の高い仲間たちが嘆きしおれている折に、興醒めのようであるが、次々に延期したので、止めることではないので、どうして源氏が思いとどまることがあろう。女宮(三の宮)の心のうちを、推察し、ひどくお気の毒に思うのだった。
例によって、五十の寺に読経を依頼する。院がおられる御寺にも。摩訶毘盧遮那の。 |
|
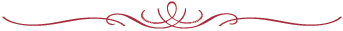
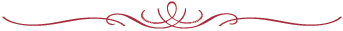
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)