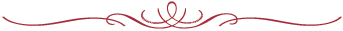
| 漢字の当て字考 |
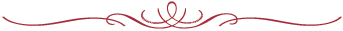
(最新見直し2016.2.1日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、漢字の当て字考をしておく。「 当て字・難読・国名漢字 」、「熟字訓・当て字一覧表・検索」その他参照 2016.2.1日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【食べ物、飲み物、台所】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【生物、草花】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【宝石】 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【器具、機械】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【スポーツ、ゲーム】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【医療、生活用品】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【着物】 | ||||||||||||
|
| 【文化芸術、音楽、祭り】 | ||||||||||||||||||
|
| 【その他】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【国名、地域名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【日本の古地名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【人名】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【家族、縁戚】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【天文、歳時季】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)
| № | 漢字 | 読み方 | ひとこと |
|---|---|---|---|
| 嗚呼 | ああ | =于嗟・吁嗟 | |
| 弧光灯 | あーくとう | 2本の炭素棒を放電させる電灯。 | |
| 匕首 | あいくち | =合口 「ひしゅ」とも。 鍔のない短刀。 | |
| 彼奴 | あいつ、あやつ、かやつ、きゃつ | ||
| 鮎魚女、 鮎並 | あいなめ | =鮎並 アイナメ科の海魚。 | |
| 生憎 | あいにく | 都合が悪いことに。 | |
| 相部屋 | あいべや | 他人と同じ部屋になること。 | |
| 白馬 | あおうま | 「はくば」とも。 白い葦毛の馬。 | |
| 青麻 、青苧 | あおそ | アサの皮からつくった繊維。 | |
| 青苔 、青海苔 、緑苔 | あおのり | 緑藻類。 | |
| 赤麻 、赤苧 | あかそ | イラクサ科の植物。 | |
| 贖児 | あがちご | 大祓に用いた人形。 | |
| 班田 | あかちだ | 「はんでん」とも。律令制で人民に与えられた田。 | |
| 赤蜻蛉 | あかとんぼ | 小形で赤い色のトンボ。 | |
| 贓贖司 | あがないもののつかさ | 律令制で罪人の資財や盗品を扱う役所。 | |
| 茜草 、地血 | あかね | アカネ科の植物。 | |
| 明衣 | あかは、あかはとり | 「めいい」、「みょうい」とも。神事などで着る白い礼服。 | |
| 白地 、明白 | あからさま | 明白 露骨なこと。「はくち」は白い生地や乾いた田畑を指す。 | |
| 秋茄子 | あきなす | cf.秋茄子は嫁に食わすな。 | |
| 商人 | あきんど | 「あきびと」「しょうにん」とも。 商売人。 | |
| 灰汁 | あく | しつこさをいうことも。 | |
| 欠伸 | あくび | 「けんしん」は背伸びも意味する。 | |
| 趺坐 、胡座 、胡坐 | あぐら | 「ふざ」とも。 | |
| 山女 | あけび、やまめ | 木通・通草。植物名。 「やまめ」はサケ科の魚 | |
| 揚げ雲雀 | あげひばり | 春に空高く舞うヒバリをいう。 | |
| 総角 、揚巻 | あげまき | 「そうかく」とも。古代の少年の髪形。 | |
| 朝餉 | あさげ | 朝食。「あさがれい」は天皇の食事を意味する。 | |
| 朝勤 | あさじ | 朝事、浄土真宗の朝の勤行。 | |
| 明後日 | あさって | 「みょうごにち」とも。 | |
| 海豹 、水豹 | あざらし | ||
| 葦牙 | あしかび | 葦の若い芽。 | |
| 八仙花 、紫陽花 | あじさい | ユキノシタ科。 | |
| 小豆 | あずき | ||
| 小豆餡 | あずきあん | こしあん、つぶあんなど。 | |
| 小豆粥 | あずきがゆ | 1月15日の朝に食べる。 | |
| 叉倉 、校倉 | あぜくら | 柱を用いず材木を井桁状に組んで壁にした倉。 | |
| 按察使 | あぜち | "あんさっし"とも。奈良時代の地方監視の役職。 | |
| 庵室 | あぜち | 奈良時代の一般の寺。"あんしつ""あんじつ""あんじち"と読むと「いおり」を指す。 | |
| 按察 | あぜち | "あんさつ"とも。奈良時代の地方監視の役職。 | |
| 馬酔木 | あせび、あしび | ツツジ科の樹木。 | |
| 汗疹 、汗肬 、汗疣 | あせも | 「かんしん」とも。 | |
| 彼所 | あそこ | ||
| 彼処 | あそこ、かしこ | ||
| 朝臣 | あそん | 平安時代の五位以上の貴族。 | |
| 渾名 、諢名 、綽名 | あだな | 「こんめい」とも。 | |
| 可惜 | あたら、あったら | もったいないことに。 | |
| 彼方此方 | あちこち | ||
| 彼方 | あちら | ||
| 天晴 | あっぱれ | ||
| 宛行 、充行 | あてがい | 一方的に決めて与えること。 | |
| 宛行扶持 | あてがいぶち | 雇用主が一方的に決めた給料の支払い。 | |
| 当所 | あてど | 目的のこと。 | |
| 貴人 | あてびと | 貴族。「きじん」とも。 | |
| 恐惶 、穴賢 | あなかしこ | 「きょうこう」とも。ああ、こわい、もったいない 決して~ない | |
| 貴女 、貴男 、貴方 | あなた | ||
| 痘痕 | あばた | もとは天然痘の痕をいった。 | |
| 荒家 、荒屋 | あばらや | 荒れた家。 休息所。 | |
| 家鴨 | あひる | ||
| 天児 、天倪 | あまがつ | 祓に用いた幼児の形代。 | |
| 天魚 、甘子 | あまご | サケ科の淡水魚。 | |
| 天道 、天路 | あまじ | 天上への道。天上界。「てんとう」、「てんどう」は太陽や天帝を指す。 | |
| 許多 、数多 | あまた | 数多 たくさん。 | |
| 淡漬 、味漬 | あまづけ | 味漬・甘漬 塩分控えめの漬物。 浅漬け。 | |
| 紫菜 、甘海苔 、紫菜 | あまのり | 甘海苔 海藻類。 | |
| 網結 | あみすき | 網を作ること。 | |
| 漢氏 | あやうじ | 古代の中国から日本への渡来人。 | |
| 漢織 | あやはとり | 昔中国から日本に機織りの技術を伝えた渡来人の名前。 | |
| 漢人 | あやひと | 古代の中国から日本への渡来人。 | |
| 菖蒲 | あやめ | アヤメ科の植物。 「しょうぶ」はサトイモ科の別の植物。 | |
| 年魚 、鮎 | あゆ | ||
| 足結 | あゆい | 「あしゆい」とも。 袴を膝のあたりで結んだ紐 | |
| 洗魚 、洗膾 | あらい | 新鮮なコイやスズキを薄切りした料理。 | |
| 新墾田 | あらきだ | 新田。 | |
| 荒塊 | あらくれ | 大きな土のかたまり。 | |
| 愛発関 | あらちのせき | 越前にあった関所で、三関の1つ。 | |
| 曠野 | あらの | 荒れ果てて人気のない野。 「こうや」は広大な野を指す。 | |
| 所有 、所在 、在処 | あらゆる | 「しょゆう」は別の意味。 | |
| 在所 、存処 | ありか | 「ざいしょ」は故郷、田舎、住んでいるところの意味。 | |
| 荒磯 | ありそ | 「あらいそ」とも。 波が荒く岩に覆われた海岸。 | |
| 主人 | あるじ | 「しゅじん」とも。 | |
| 彼是 、彼此 | あれこれ 、かれこれ | 様々。「かれこれ」はとやかく、およその意味も。「ひし」とも。 | |
| 周章る | あわてる | cf.周章狼狽 熟字訓+送り仮名。 | |
| 許嫁 、許婚 | いいなずけ | 婚約者。幼少時に親の間で取り決めるものもいう。 | |
| 飯粒 | いいぼ | 「めしつぶ」とも。肬も指す。 | |
| 五百 | いお | 「ごひゃく」とも。 数の多いさまも意味する。 | |
| 硫黄 | いおう | S。 | |
| 五十日 、墨魚 、烏賊 | いか | "五十日(いか)の祝い"など 「ごじゅうにち」とも。漢字より読みの数が多い。 | |
| 如何 | いかが、どう、いかん | ||
| 斎垣 | いがき | 神社などの垣。 | |
| 沃懸地 | いかけじ | 金銀の粉をまき研ぐ蒔絵の技法。 | |
| 如何様 | いかさま、いかよう。 "いかさま"は"いんちき、"いかよう”はどのようにの意味。 | ||
| 如何様師 | いかさまし | ペテン師。いんちき。 | |
| 如何に | いかに | どのように。 どれほど。 | |
| 如何物食い | いかものぐい | 食べるものなど、趣味や好みが普通の人と異なること。 | |
| 斑鳩 | いかる、いかるが | 鵤。アトリ科の鳥。 | |
| 如何 、何若 、何如、何奈 、奈何 | いかん | ||
| 生霊 | いきすだま | 生魑魅。「いきりょう」。「せいれい」とも。生きている人の怨霊。 | |
| 生魑魅、生霊 | いきすだま | 生きている人の怨霊。 | |
| 寝穢い | いぎたない | なかなか起きない。寝相が悪い。 | |
| 意気地 | いくじ | cf。依怙地 | |
| 斎串 | いぐし | 玉串。竹の串。 | |
| 幾人 | いくたり | どれほどの人数。 多くの人数。 「いくにん」とも。 | |
| 欠唇 、兎唇 | いぐち | 縦に裂けた唇。口唇裂 | |
| 幾許 、幾何 | いくばく | どれくらい。 | |
| 犠牲 、生贄 | いけにえ | 「ぎせい」とも。 | |
| 居心地 | いごこち | ||
| 寝聡い | いざとい | 眼が覚めやすい。 | |
| 磯魚 | いさな | 磯の近くに棲む魚。 | |
| 細小魚 、小魚 | いさな | 小さな魚。 | |
| 伊弉諾尊 、伊邪那岐命、伊弉冉尊 | いざなぎのみこと | 神話で国土を産んだ男神。 | |
| 伊邪那美命 | いざなみのみこと | 神話で国土を産んだ女神。 | |
| 五十集 | いさば | 魚商人 江戸時代の小型の漁船。 | |
| 膝行る | いざる | 座ったまま移動する。熟字訓+送り仮名。 | |
| 水亀 、石亀 | いしがめ | ||
| 石椁 、石城 | いしき、いわき | 墓の石室。 | |
| 尻当 、居敷当 | いしきあて | 着物の尻の部分を補強する布。 | |
| 石塊 | いしころ、いしくれ | ||
| 石投 、石子 | いしなご | 昔の遊び。石投げ。 | |
| 何処 | いずこ、いずく、どこ | ||
| 出石焼 | いずしやき | 兵庫県の陶磁器。 | |
| 幼気 | いたいけ | 子どもなどがいじらしくかわいいこと。 | |
| 悪戯 | いたずら | ||
| 神巫 、巫子・市子 | いちこ | 死者の霊を借りてその考えを語る女性。口寄せ。 | |
| 壱越調 | いちこつちょう | 雅楽の六調子の一。 | |
| 映日果 、無花果 | いちじく | クワ科の果実。 | |
| 公孫樹 、銀杏 | いちょう | 公孫樹 | |
| 銀杏返し | いちょうがえし | 昔の女性の髪形の一つ。 | |
| 何時 | いつ | ||
| 稜威 、厳 | いつ | 神聖なこと。威勢が強いこと。「りょうい」は天子の御威光を意味する。 | |
| 田舎 | いなか | ||
| 牛宿 、稲見星 | いなみぼし | 「ぎゅうしゅく」とも。中国の星座の1つ。 | |
| 稲荷 | いなり | 五穀の神。 狐。 油揚げ。 | |
| 居囃子 | いばやし | 能の略式演奏。 | |
| 息吹 | いぶき | 呼吸。生気。 | |
| 気吹戸 | いぶきど | 神が穢れを払うところ。 | |
| 今際 | いまわ | 死に際。 | |
| 斎子 、忌子 | いむこ、いみこ | 神に奉仕する少女。 | |
| 稲熱病 | いもちびょう | 「とうねつびょう」とも。イネの病害。 | |
| 弥終 | いやはて | 最後の意味。 | |
| 弥弥 、愈愈 | いよいよ | ||
| 郎子 | いらつこ | 若い男性の呼び方。 | |
| 郎女 | いらつめ | 若い女性の呼び方。 | |
| 海豚 | いるか | 「かいとん」とも。 | |
| 刺青 、文身 | いれずみ | 「しせい」とも。 | |
| 煎汁 、色利 | いろり | 鰹節や大豆の煮出し汁。 | |
| 斎人 、忌人 | いわいびと | 神を祀る人。 | |
| 忌瓮 、斎瓮 | いわいべ | お神酒を入れる容器。"瓮"は"かめ""もたい"と読む。 | |
| 磐座 、岩座 | いわくら | 神が住む場所。 | |
| 岩清水 | いわしみず | 岩の間から流れ出る水。 | |
| 岩魚 、嘉魚 | いわな | サケ科の魚 =嘉魚 | |
| 所謂 | いわゆる | 世間で俗に言う。 | |
| 羊墨 | インク | ||
| 魚河岸 | うおがし | 魚介類を競り売りする市場。 中央卸売市場を指すことも。 | |
| 倉稲魂 、稲魂 | うかのみたま | =宇迦御魂・稲魂 五穀、イネの神。 | |
| 窺見 | うかみ | =斥候 間諜。スパイ行為。 | |
| 斥候 | うかみ | =窺見 「せっこう」とも。 間諜。スパイ行為。 | |
| 拝所 | うがんじゅ | 沖縄で神を拝むところ。 | |
| 祈狩 | うけいがり | 獲物を占いに用いる狩り。 | |
| 大人 | うし、おとな | "うし"(「たいじん」とも)は先生や貴人の尊称。 "おとな"は「たいじん」「だいにん」とも。 | |
| 薄粧 | うすけわい | 薄化粧。 | |
| 泡沫 | うたかた | 「ほうまつ」とも。 水泡。 はかないもののたとえ・ | |
| 仮寝 | うたたね | 「かりね」とも。 =転た寝。 | |
| 雅楽頭 | うたのかみ | 律令制で宮廷音楽を担当した役所の長官。 | |
| 雅楽寮 | うたりょう | 「ががくりょう」とも。 律令制で宮廷音楽を担当した役所。 | |
| 団扇 | うちわ | 「だんせん」とも。 | |
| 楊櫨木 、卯木 | うつぎ | =卯木・空木 ユキノシタ科の樹木。 | |
| 呆気者 | うつけもの | =空け者 愚か者のこと。 | |
| 現身 | うつしみ | 生き身 | |
| 現世 | うつしよ | 「げんぜ」、「げんせ」とも。 この世。 | |
| 現人 | うつせみ | =空蟬 生き身。 現世。 | |
| 打棄る 、打遣る | うっちゃる | =打遣る 投げ捨てる。 ほうっておく。 | |
| 独活 | うど | =土当帰 アコギ科の植物。 | |
| 内舎人 | うどねり | 律令制で宮中の宿直などを担当した役人。 | |
| 首肯く | うなずく | =頷く・肯く 熟字訓+送り仮名。 | |
| 項垂れる | うなだれる | しょげかえる。 | |
| 池溝 | うなて | 溝。田に水を引く溝。 | |
| 己惚れる 、自惚れる | うぬぼれる | ||
| 采女 | うねめ | 宮中で天皇や皇后の世話をした女官。 | |
| 乳母 | うば、おんば、めのと | 母親代わり。 | |
| 初心 | うぶ | 「しょしん」とも。純情で恋愛感情に疎いさま。 | |
| 産土 | うぶすな | 生まれた土地。 | |
| 産土神 | うぶすながみ | 生まれた土地の守護神。 | |
| 孕女 、産女 | うぶめ | 妊娠前後の女性。 | |
| 美味い 、上手い | うまい | 旨い、甘い。 | |
| 味酒 、 | うまさけ、うまざけ | 美酒のこと。 | |
| 美し国 | うましくに | すばらしい国。 | |
| 石女 | うまずめ | =不生女 子を産めない女性の蔑称。 | |
| 不生女 | うまずめ | =石女 子を産めない女性の蔑称。 | |
| 卜兆 | うらかた | 占形・占象。甲羅や骨を焼いて占った結果。 | |
| 心悲しい | うらがなしい | なんとなく悲しい。物悲しい。 | |
| 卜書、占文 | うらぶみ | 占いの結果を記した文書。 | |
| 五月蝿い 、五月蠅い | うるさい | ||
| 狼狽える | うろたえる | 予期しないことに慌ててまごつく。熟字訓+送り仮名。 | |
| 釉薬 | うわぐすり | 陶磁器のつやを出す薬。 | |
| 譫言、囈言 | うわごと | 「せんげん」とも。正気を失い口走る言葉。無責任な言葉。 | |
| 次妻 、後妻 | うわなり | 後に娶った妻。嫉妬。 「ごさい」は再婚した妻。 | |
| 蟒蛇 | うわばみ | 巨大な蛇。大酒飲み。 | |
| 嘔吐く | えずく | 吐く。もどす。 | |
| 似非 、似而非 | えせ | 似ているが異なるもの。 | |
| 藍菊 、蝦夷菊 | えぞぎく | キク科の植物。 | |
| 岐路 、枝道 | えだみち | 本筋を離れた方向。「きろ」は分かれ道を指す。 | |
| 胞衣 | えな | 出産直後の母体からの排出物。後産。 | |
| 蛭子 、恵比寿、恵比須 | えびす | 漁業や商売繁盛の神で七福神の一人。 |
| 吉方、恵方 | えほう | 縁起が良いとされる方角。 |
| 烏帽子 | えぼし | 元服した男性の帽子。 |
| 疫病 | えやみ | 「えきびょう」とも。流行病や熱病。 |
| 美味しい | おいしい | |
| 追風 | おいて | 順風。 |
| 老次 | おいなみ | 老年期のこと。 |
| 花魁 | おいらん | (地位の高い)遊女。 |
| 老女 | おうな | 「ろうじょ」とも。年を取った女性。 |
| 大炊 | おおい | 天皇の食事。 |
| 大炊寮 | おおいりょう、おおいのつかさ | 律令制で納められた米を各官庁に配分した役所。 |
| 大鼓、大革 | おおかわ | 「おおつづみ」とも。 囃子に用いる大きな鼓。cf."たいこ"は"太鼓"で別。 |
| 大塊 | おおぐれ | 体格が大きいこと。「たいかい」は土のかたまり、大地を指す。 |
| 大世帯 | おおじょたい | =大世帯 構成する人の多い家族や組織。 |
| 大殿油 | おおとなぶら | 宮殿の灯火用の油。 |
| 大連 | おおむらじ | 大和朝廷の政治の担当者。 |
| 大凡 | おおよそ | あらまし。 ほぼ。 |
| 極光 | オーロラ | 「きょっこう」とも。 |
| 大曲 | おおわだ | 川や湖の入江。 「おおまがり」は地名。 |
| 大鋸屑 | おがくず | のこぎりの切りかす。 |
| 可笑しい | おかしい | |
| 御菜 | おかず | =御数 副食。 |
| 御河童 | おかっぱ | |
| 女将 | おかみ | 「じょしょう」とも。 料亭や旅館の女主人。 |
| 御内儀 | おかみ | =御上 他人の妻の敬称。 |
| 清器 | おかわ | =御厠 おまる。 |
| 御髪 | おぐし、みぐし | 他人の頭髪の敬称。 |
| 晩稲 | おくて | =奥手 他より遅く実るイネ。 |
| 晩生 | おくて | =奥手 他より遅く熟す品種。 成熟の遅い人。 |
| 童男 | おぐな | 男の子。 |
| 噫気 、噯気 | おくび | "あいき"とも。ゲップ |
| 白朮祭 | おけらまつり | =朮祭 京都の八坂神社の正月の祭。 |
| 襁褓 | おしめ、むつき | 「きょうほう」とも。おむつ |
| 御洒落 | おしゃれ | |
| 白粉 | おしろい | 化粧用の粉や液。 |
| 御為倒し | おためごかし | 相手を思いやるふりをしつつ自らの利益を考えること。 |
| 遠方 | おちかた | 「えんぽう」とも。 |
| 遠近 | おちこち | =彼方此方 あちこち。 |
| 彼方此方 | おちこち | =遠近 あちこち。 |
| 零落れる 、落魄れる | おちぶれる | =落魄れる 熟字訓+送り仮名。 |
| 変若水、 復水 | おちみず | =復水 飲めば若返るという水。 「ふくすい」は気体を液体に戻すことをいう。 |
| 落人 | おちゅうど、おちうど | 戦いに敗れ忍んで生活するもの。 |
| 御汁 | おつけ | =御付 味噌汁。 |
| 仰有る | おっしゃる | |
| 追而書 | おってがき | 追伸。二伸。 |
| 良人、 夫 | おっと | |
| 御頭 | おつむ | あたまを意味する幼児語。 |
| 俠気 | おとこぎ | 「きょうき」とも。 =男気 弱い物を助ける男らしい気質。 |
| 男伊達 | おとこだて | 男として仁義を重んじること。 |
| 大殿 | おとど | =大臣 貴人の住居。 公卿。 貴婦人。 |
| 大臣 | おとど | =大殿 「だいじん」とも。 貴人の住居。 公卿。 貴婦人。 |
| 少女 | おとめ | =乙女 「しょうじょ」とも。 |
| 荊棘 | おどろ | =棘 草木や髪の毛が乱れていること。 「けいきょく」はいばらや障害を意味する。 |
| 各各 | おのおの | |
| 十八番 | おはこ | 「じゅうはちばん」とも。 得意技。 陳腐な動作。 |
| 男茎 | おはせ | ペニス。 |
| 未通女 | おぼこ | 世間や男性を知らない人。うぶ。生娘。 |
| 御火焼 | おほたき、おひたき | =御火焚 京都や大阪の火祭り。 |
| 御巡りさん | おまわりさん | |
| 小斎 、小忌 | おみ | =小忌 神事で身を清め慎む行為。 |
| 大神酒 、御神酒 | おみき | =御神酒。 神に供える酒。 |
| 御神籤 | おみくじ | =御御籤 |
| 小忌衣 | おみごろも | 神事で身を清めるための白地の服。 |
| 女郎花 | おみなえし | 秋の七草の一つ。 |
| 以為 | おもえらく | 思うには。 |
| 面瘡 | おもくさ | 顔のできもの。 |
| 玩具 | おもちゃ | 「がんぐ」とも。 |
| 重傷 | おもで | =重手 「じゅうしょう」とも。 |
| 母屋 、母家 | おもや | =母家 「もや」とも。 建物の中央部分。 本店。 |
| 女形 | おやま | 「おんながた」とも。 歌舞伎で女役の男。 女の操り人形。 |
| 下風 | おろし | 山から吹く強風。 =颪 |
| 大蛇 | おろち | 「だいじゃ」とも。 大きな蛇。 蠎(うわばみ)。 |
| 御衣 | おんぞ、みけし | お召し物。 |
| 乳母日傘 | おんばひがさ | 恵まれた家庭環境で大切に育てられること。 |
| 甲斐甲斐しい | かいがいしい | きびきびしている。 |
| 匙笥 、搔笥 | かいげ | 風呂などで用いる小さい桶。 |
| 甲斐性 | かいしょう | 経済力などがあり頼もしいこと。 |
| 垣外 、垣内 | かいと | "垣内"も"かいと"と読む…"同音対義語" |
| 穎割れ 、頴割れ | かいわれ | 芽を出したばかりの大根など。 |
| 鹿驚 、案山子 | かかし、かがし | 見かけ倒しのものをたとえていうことも。 |
| 牡蠣 | かき | 「ぼれい」とも。 イタボガキ科の二枚貝。 |
| 杜若 、燕子花 | かきつばた | =燕子花 アヤメ科の植物。 |
| 鉤状 | かぎなり | 「かぎじょう」とも。 かぎのように曲がった形。 |
| 民部 、部曲 | かきべ | =部曲 古代の豪族の私有民。 「みんぶ」は律令制の役所。 |
| 陽炎 | かぎろい、かげろう | 「ようえん」とも。火光(かぎろい) 明け方にちらちら光る陽の光。 強い日光の影響で空気がゆらゆらと炎のように見える現象。 |
| 堅磐 | かきわ | 硬い岩。 不変のもの。 |
| 如此 、如斯 | かくのごとし | =如斯 このようである。 |
| 神楽 | かぐら | 神を祀る舞楽。 歌舞伎などの囃子。 |
| 神楽月 | かぐらづき | 陰暦11月。 |
| 陰日向 | かげひなた | 人前で態度を変えること。 陰での援助。 |
| 欠片 | かけら | |
| 蜻蛉 、蜉蝣 | かげろう、とんぼ | 「せいれい」とも。 "かげろう"はカゲロウ目の昆虫だが、"とんぼ"の旧称でもある。 |
| 水手 、水夫 | かこ | =水夫 船乗り。 |
| 駕籠 | かご | |
| 託言 | かごと | 言い訳。 愚痴。 |
| 挿頭す | かざす | 飾り付ける。 枝や花を頭に挿す。 |
| 河岸 | かし | 舟が寄る川の岸。 魚市場。 飲食する場所。 「かわぎし」は単純に川の岸を指す。 |
| 鍛冶 | かじ | 「たんや」とも。 金属を加工すること。 |
| 膳夫 | かしわで | =膳 宮中の料理人。 |
| 拍手 | かしわで | =柏手 手を打ち合わせて神を拝むこと。 「はくしゅ」は賞賛の意を示すもの。 |
| 瓦斯 | ガス | |
| 主計頭 | かずえのかみ | 律令制で国家の財政を担当した役所の長官。 |
| 被衣 | かずき | 高貴な女性が人目を避けるためにかぶった布。 |
| 飛白 | かすり | =絣 かすったような模様の織物。 |
| 鹿杖 | かせづえ | 先端が分かれた杖。 鹿の角をつけた杖。 |
| 方人 | かたうど | 「かたひと」とも。 歌合わせの片組。 味方。 |
| 片方 | かたえ | 「かたほう」とも。 |
| 旁旁 | かたがた | =旁 ついでに。 ~がてら。 |
| 気質 | かたぎ | 特有の性質。 「きしつ」とも。 |
| 固唾 | かたず | 緊張した時にたまる唾。 |
| 蝸牛 | かたつむり、でんでんむし | 「かぎゅう」とも。 |
| 結政所 | かたなしどころ | 律令制で書類を扱った役所。 |
| 帷子 | かたびら | 麻や絹で成るひとえの衣服。 几帳の薄幕。 |
| 徒歩 、徒、徒士 | かち | = 歩いて行くこと。 下級武士。 |
| 歩射 | かちゆみ | =徒弓 「ぶしゃ」とも。 歩きながら弓を射ること。 |
| 河童 | かっぱ | 吐く。もどす。 |
| 首途 、門出 | かどで | 「しゅと」とも。 |
| 看督長 | かどのおさ | 平安時代の牢屋の看守人。 |
| 勾引かす | かどわかす | =拐す 誘拐する。 |
| 釜殿 | かなえどの | =鼎殿 宮中で湯や膳を用意する大奥の建物。 |
| 金巾 | カナキン | 平織りの綿織物。 |
| 曲尺 | かねじゃく | 「きょくしゃく」とも。 直角に曲がった金属製のものさし。 |
| 頭槌の大刀 、頭椎の大刀 | かぶつちのたち、くぶつちのたち | =頭椎の大刀 古代の大刀の様式 |
| 鏑矢 | かぶらや | =鏑 木や角をつけた矢。 |
| 南瓜 | かぼちゃ | ウリ科の植物。 |
| 蟷螂 、螳螂 | かまきり | =螳螂・鎌切 「とうろう」とも。 |
| 蒲魚 | かまとと | 上品ぶって知らないふりをすること。 |
| 長官 | かみ | 律令制で四等官の最高位。 |
| 剃刀 | かみそり | |
| 掃部 | かもん、かもり | 律令制で宮中の掃除などを行った役人。 |
| 蚊帳 | かや | =蚊屋。 「かちょう」「ぶんちょう」とも。 |
| 掛落 、掛絡 、掛羅 | から | =掛絡・掛羅 禅僧の略式袈裟。 根付け。 |
| 揶揄う | からかう | =揶う・揄う 熟字訓+送り仮名。 |
| 機関 | からくり | =絡繰 「きかん」は別の意味。 |
| 乾鮭 | からざけ | 鮭のはらわたを干した食品。 |
| 芥子 | からし | 「けし」は別の植物。 =芥・辛子。 |
| 硝子 | ガラス | |
| 乾咳 | からせき、からぜき | 痰が出ない咳。 |
| 身体 | からだ | =体・軀 「しんたい」とも。 |
| 乾っ風 | からっかぜ | 降雨なしで吹く風。 |
| 乾拭き | からぶき | |
| 落葉松 | からまつ | =唐松 マツ科の樹木。 |
| 猟人 、狩人 | かりゅうど、かりうど | =狩人 猟師のこと。 |
| 骨牒 、歌留多 、加留多 | カルタ | =歌留多・加留多 |
| 浮石糖 、泡糖 | カルメラ | =泡糖 ざらめ糖を用いた菓子。 |
| 甲乙 | かるめる、かりめり | =上下 音の高低 「こうおつ」は別の意味。 |
| 乾飯 | かれいい | 「ほしいい」とも。 米を蒸して乾かした保存食。 =餉 |
| 為替 | かわせ | 現金ではなく手形や証書で送金する。 |
| 河原 、川原 | かわら | =川原・磧 |
| 川曲 | かわわ | 川が曲がって緩やかに流れるところ。 |
| 主神 | かんざね | =神実 神の正体。 神主。 |
| 寒復習 | かんざらい | 寒中に水を浴びて身を清めること。 |
| 強盗頭巾 | がんどうずきん | 目以外の顔を覆った頭巾。 |
| 惟神 、随神 | かんながら | =随神 「神の思し召し」を意味する神道の言葉 |
| 貫木 | かんぬき | 戸を閉めた状態にしておく横木。 相撲の技 =閂 |
| 木尺 | きがね | =木矩 模様の歪みを調べる直角定規。 |
| 聞道 、聞説 | きくならく | =聞説 聞くところによると。 |
| 木耳 | きくらげ | キクラゲ科のキノコ。 |
| 樵夫 | きこり | =樵 |
| 段段 、刻刻 | ぎざぎざ | =刻刻 「だんだん」は別の意味。 |
| 如月 、更衣 | きさらぎ | =更衣・衣更着 |
| 素地 | きじ | =生地 「そじ」とも。 本性。 すっぴん。 素焼き。 |
| 煙管 | キセル | 不正乗車を指すことも。 |
| 生蕎麦 | きそば | そば粉のみで作ったそば。 |
| 着衣始 | きそはじめ | 正月に衣更えをする江戸時代の儀式。 |
| 堅塩 | きたし | 「かたしお」とも。 未精製の塩 |
| 毬杖 、毬打 | ぎっちょう、ぎちょう | =毬打 毬を打つ正月の遊び、道具。 |
| 啄木鳥 | きつつき、けら、けらきつつき | キツツキ科の鳥。 |
| 急度 | きっと | =屹度 |
| 狐日和 | きつねびより | 不順な天候。 |
| 焦臭い | きなくさい | こげくさい。 不穏な気配がする。 胡散臭い。 |
| 後朝 | きぬぎぬ | =衣衣 男女が共に寝た翌朝。その別れ。 |
| 黍魚子 、吉備奈仔 | きびなご | =吉備奈仔 ニシン科の魚。 |
| 生真面目 | きまじめ | 融通が利かない感じ。 |
| 黄身時雨 | きみしぐれ | 和菓子の1つ。 |
| 沈菜 | キムチ | 野菜を塩に漬け唐辛子などを加えた朝鮮の食材。 |
| 肌理 | きめ | =木目 皮膚などの表面の綾。 心配り。 |
| 乾煎り | きもいり | 水や油なしで煎ること。 |
| 妓夫 | ぎゅう | 遊郭で客引きをする人。 |
| 経帷子 | きょうかたびら | 仏教の葬儀で死者に着せる服。 |
| 軽軽 | きょうきょう | 「けいけい」とも。軽々しいさま。 「かるがる」は容易くの意味。 |
| 雲母 | きらら | 「うんも」とも。花崗岩中の結晶。 |
| 布地 | きれじ | =切れ地 「ぬのじ」とも。 生地。 切れ端。 |
| 青蠅 | きんばえ | =金蠅 クロバエ科。 |
| 陸路 | くがじ | 「りくろ」とも。 |
| 探湯、盟神探湯、誓湯 | くかたち、くがたち、くかだち | 熱湯を用いた古代の裁判の方法。 |
| 傀儡子 、傀儡 | くぐつ | 操り人形。 |
| 典薬頭 | くすりのかみ | 「てんやくのかみ」とも。 律令制で医療を担当した役所の長官。 |
| 小角 | くだのふえ | =管の笛 戦場で用いた笛。 |
| 草臥れる | くたびれる | 疲れて気力がなくなる。 ぼろぼろになる。 |
| 果物 | くだもの | |
| 口下手 | くちべた | |
| 地祇 | くにつかみ | =国つ神 「ちぎ」とも。 大地の神。 |
| 蜘蛛 | くも | 節足動物。 |
| 蜘蛛膜下出血 | くもまくかしゅっけつ | 脳や脊髄を包む蜘蛛膜の下に出血する危険な疾患。 |
| 口惜しい | くやしい | 「くちおしい」とも。 |
| 倶楽部 | クラブ | |
| 内蔵寮 | くらりょう | 律令制で日用品の調達などを担当した役所。 |
| 曲輪 | くるわ | =郭・廓 城郭。 |
| 呉服 | くれはとり | 「ごふく」とも。 =呉織 呉からの渡来人が伝えた織物。 |
| 玄人 | くろうと | 専門家 水商売 |
| 蔵人 | くろうど、くらんど | 平安時代の蔵人所の役人。 |
| 黒衣 | くろご、くろこ | =黒子 歌舞伎や浄瑠璃の介添え人。 裏で他人を操る者もいう。 |
| 黒南風 | くろはえ | 梅雨の初期の南風。 |
| 窩主買 | けいずかい | =系図買。 盗品と知りつつ売買すること。 |
| 景色 | けしき | |
| 毛布 | けっと、ケット | 「もうふ」とも。 ブランケットのこと。 |
| 化粧 | けわい | 「けしょう」とも。 |
| 此奴 | こいつ、こやつ | |
| 庶幾う | こいねがう | =冀う・希う 強く願う。 熟字訓+送り仮名。 |
| 髪際 | こうぎわ | 髪の生え際。 |
| 柑子 | こうじ | 柑子蜜柑。 柑子色。 |
| 勘事 | こうじ | 勘当。 拷問。 |
| 香匙 | こうすくい | 「きょうじ」とも。 お香をすくうさじ。 |
| 羊傘 | こうもり | こうもりがさの方。 |
| 蝙蝠 | こうもり、かわほり | 「へんぷく」とも。 |
| 紙屋紙 | こうやがみ | 平安時代の高級紙。 |
| 肥担桶 | こえたご | 肥料用の糞尿を運ぶ桶。 |
| 雀躍 | こおどり | =小躍り 「じゃくやく」とも。 喜んで躍り上がること。 |
| 木屑 | こけら | =杮 材木を削った残りくず。 ※杮≠柿 |
| 此所、 此処 | ここ | =此・此処 |
| 心地 | ここち |
| 五十雀 | ごじゅうから | 小鳥。 |
| 豆汁 | ごじる | =呉汁・醐汁 潰した大豆の入った味噌汁。 |
| 秋桜 | コスモス | キク科の植物。 |
| 瞽女 | ごぜ、ごじょ | 三味線などを弾き食物などをもらう盲目の女性。 |
| 小太刀 | こだち | 小型の刀。 |
| 此度 | こたび | このたび。 |
| 拘泥る | こだわる | 熟字訓+送り仮名 |
| 此方人等 | こちとら | おれたち。 |
| 此方 | こちら | |
| 特牛 | こというし | 大きくて健康な雄牛。 |
| 部領 | ことり | 部族の長。 春宮坊の帯刀の宮。 |
| 小半 | こなから | =二合半 四分の一。四分の一升。 |
| 二合半 | こなから | =小半 四分の一。四分の一升。 |
| 小腹 | このかみ、こがみ、ほがみ | 下腹。 |
| 兄部 | このこうべ | 武家などでの力仕事の指導者。 |
| 木の葉時雨 | このはしぐれ | 木の葉が盛んに散ること。 |
| 木の葉木菟 | このはずく | フクロウ科の鳥。 |
| 木皮 | こはだ | =樸・木肌・木膚 木の皮。 木の皮で葺いた屋根。 |
| 乾分 、乾児 | こぶん | =子分・乾児 |
| 独楽 | こま | |
| 紙捻 、紙撚、紙縒 | こより | =紙縒・紙撚 和紙をひも状にしたもの。 |
| 破落戸 、無頼 | ごろつき | =無頼 住所・職業不定で悪事をはたらく者。 |
| 転寝 | ごろね | |
| 恐恐 | こわごわ | =怖怖 |
| 小童 | こわっぱ | 年少者の蔑称。 |
| 強面 | こわもて、こわおもて | =怖面 |
| 濃漿 | こんず | 米を煮た汁。 酒。 汗。 「こくしょう」は味噌で煮込んだ汁を指す。 |
| 健児 | こんでい | 関所を守った兵士。 武家の足軽。 「けんじ」は健やかな若者を指す。 |
| 巨頭鯨 | ごんどうくじら | |
| 金平糖 | こんぺいとう | |
| 搾菜 | ザーサイ | カラシナを用いた中国の漬物。 |
| 洋剣 、洋刀 | サーベル | =洋刀 西洋の細い刀。 |
| 骰子 、賽子 | サイコロ | =賽子 |
| 騒騒 | さいさい、さえさえ、ざわざわ | 揺れ動き尾とがすること。 |
| 木椎 | さいづち | =才槌 胴が膨らんだ小さい木槌。 |
| 道祖土焼 | さいとやき | 門松や注連飾りを焼く火祭り。 |
| 割符 | さいふ | 「わりふ」「わっぷ」とも。 鎌倉時代から室町時代に使われた為替手形。 |
| 道祖神 | さえのかみ、さいのかみ | =障の神・塞の神 「どうそじん」とも。 道路の安全を守る神。 |
| 造酒児 、造酒童女 | さかつこ | =造酒童女 大嘗祭で神酒を醸造する少女。 |
| 掌酒 | さかびと | =酒人 神に供える酒をつくる人。 |
| 酒祝 、酒寿 | さかほがい、さかほかい | =酒寿 酒宴を開いてお祝いすること。 |
| 月代 、月額 | さかやき | =月額 成人男子が額際の頭髪を剃った習慣。 |
| 主典 | さかん | 律令制で公文書を扱った官職。 |
| 幸魂 | さきみたま | =幸御魂 幸せをもたらす神の霊魂。 |
| 防人 | さきもり | 律令制で九州北部を守った兵士。 |
| 三狐神 | さぐし | 田圃の神。 |
| 柘榴 、石榴 、安石榴 | ざくろ | =石榴・安石榴 ザクロ科の樹木 |
| 雑魚 | ざこ | =雑喉 様々な小魚。 つまらない人物も指す。 |
| 雑魚寝 | ざこね | 同じ部屋に多くの人が寝ること。 |
| 小竹 | ささ | =笹 イネ科。 |
| 竹筒 、小筒 | ささえ | =小筒 酒を入れ携帯した竹の筒。 |
| 篠竹 | ささたけ、すずたけ | "ささたけ"(=笹竹)は「しのだけ」とも読み、群生するタケのこと。 "すずたけ"はイネ科の別の植物。 |
| 小波 | さざなみ | =細波・漣 水面の小さな波。 |
| 細雪 | ささめゆき | 疎らに降る雪。 |
| 私語く | ささやく | =囁く 熟字訓+送り仮名。 |
| 細石 | さざれいし | 小さな石。 |
| 山茶花 、茶梅 | さざんか | =茶梅 ツバキ科の植物。 |
| 銚子 | さしなべ、さすなべ | 酒を温めるのに用いる弦がついた鍋。 「ちょうし」は酒を入れておく容器。 |
| 流石 | さすが | 評判通り。 やはり。 あれほどの。 |
| 流離う | さすらう | 目的もなく放浪する。 熟字訓+送り仮名。 |
| 猟夫 、猟男 | さつお | =猟男 猟師のこと。 |
| 五月 、皐月 | さつき | ツツジ科の植物。 |
| 甘藷 | さつまいも | 「かんしょ」とも。 |
| 真田虫 、条虫 | さなだむし | =条虫 「じょうちゅう」とも。 絛虫。 |
| 早苗饗 | さなぶり | 田植えの完了を祝う祭礼。 |
| 五月蝿 、五月蠅 | さばえ | 陰暦五月ごろに盛んに活動するはえ。 |
| 然程 | さほど | それほど。 |
| 然迄 | さまで | それほどまでは。 |
| 彷徨う | さまよう | =彷う 熟字訓+送り仮名。 |
| 遮莫 | さもあらばあれ | =然もあらばあれ どうにでもなれ。 |
| 素湯 、白湯 | さゆ | =白湯 飲むお湯。 |
| 小百合 | さゆり | ユリの美称。 |
| 然様 | さよう | =左様 そのとおり。 そうだ。 |
| 然様なら | さようなら | =左様なら |
| 復習う | さらう | 熟字訓+送り仮名。 |
| 更紗 | サラサ | 模様を入れた綿や絹の布。 |
| 盤秤 | さらばかり | =皿秤 皿にのせる仕組みの秤。 |
| 粗目 | ざらめ | =結晶が粗い砂糖。 |
| 粗目雪 | ざらめゆき | 粒の粗い雪。 |
| 笊蕎麦 | ざるそば | ざるや簀にのせ、汁につけて食べるそば。 |
| 猿真似 | さるまね | 上辺だけ真似すること。 |
| 髑髏 | されこうべ、しゃれこうべ | 「どくろ」とも。 白骨の頭蓋骨。 |
| 皿鉢 | さわち | 浅くて大きい磁器。 |
| 秋刀魚 | さんま | |
| 悄悄 | しおしお | =萎萎 「しょうしょう」とも。 しょんぼりする様子。 |
| 云云 | しかじか | 「うんぬん」とも。 |
| 直足袋 | じかたび | =地下足袋 労働作業用の丈夫な履物。 |
| 信楽焼 | しがらやき | 滋賀県の陶器。 |
| 磯城 | しき | =城石で築いた砦や城、祭場。 |
| 為着せ | しきせ | =仕着せ・四季施。 季節ごとに与えられる衣服。 上からの「おしきせ」。 |
| 重播 | しきまき | =頻播 他人の土地に重ねて種を播き生長を妨げる行為。 |
| 時雨煮 | しぐれに | ハマグリなどに生姜や山椒を加えた佃煮。 |
| 淑景舎 | しげいしゃ、しげいさ | 平安京の女御や更衣の住居。 |
| 重籐 | しげとう | =滋籐 弓の持つ部分を籐で巻いたもの。 |
| 尻籠 | しこ | =矢壺・矢籠 矢を入れる容器。 |
| 無言 、静寂 | しじま | =黙・静寂 何も言わないこと。 |
| 倭文 | しず | 古代の織物。 |
| 後輪 | しずわ | 馬の鞍骨の後ろの方。 |
| 竹篦 | しっぺい | 禅宗で修行者を打ち戒める棒。 人差し指と中指で手首を打つこと。 |
| 竹篦返し | しっぺがえし、しっぺいがえし | 即座の仕返し。 |
| 尻尾 | しっぽ | |
| 為手 | して | =仕手。やりて。 |
| 為出来す | しでかす | |
| 為所 | しどころ | |
| 息長鳥 | しながどり | カイツブリの呼称。 |
| 老舗 | しにせ | 代々信用を守り続けている店。 |
| 短手 | しのびで、しのびて | =忍び手 神道の葬儀での無音の柏手。 |
| 屢屢 | しばしば | =屢 |
| 底土 | しはに | 「そこつち」とも。 深いところの土。 |
| 渋団扇 | しぶうちわ | 渋柿を塗った丈夫な団扇。 |
| 繁吹 | しぶき | =飛沫 |
| 重吹く 、繁吹く | しぶく | =繁吹く 風雨が激しい。 飛沫が飛び散る。 |
| 地吹雪 | じふぶき | 積雪が強風で巻きあがること。 |
| 斑馬 | しまうま | =縞馬。 |
| 清水 | しみず | 「せいすい」、「きよみず」とも。 地下から湧く澄んだ水。 |
| 七五三飾 、注連飾 | しめかざり | =注連飾・標飾 正月や祭礼などで用いる注連縄。 |
| 搾滓 | しめかす | =〆粕 飼料や肥料に用いる、魚や大豆のしぼりかす。 |
| 湿湿 | じめじめ | 不快指数が高い。 陰気な。 |
| 注連縄 | しめなわ | =七五三縄・標縄 神域を区別したり邪神を避けたりするための縄。 |
| 七五三縄 | しめなわ | =注連縄・標縄 神域を区別したり邪神を避けたりするための縄。 |
| 仕舞屋 | しもたや、しもうたや | 商売をやめた家。 商店街中の民家。 |
| 細枝 | しもと | 若い枝や木。 |
| 耆那教 | ジャイナ教 | 紀元前6c頃にインドでマハーバーラタが開いた宗教。 |
| 曲見 | しゃくみ | 狂女などの能面。 |
| 吃逆 | しゃっくり | =噦り 「きつぎゃく」とも。 |
| 軍鶏 | しゃも | ニワトリの種類。 |
| 和人 | シャモ | アイヌ人が用いた日本人の呼称。 |
| 洒落 | しゃれ | 「しゃらく」はさっぱりとしている様子を指す。 |
| 十姉妹 | じゅうしまつ | カエデチョウ科の鳥。 |
| 数珠玉 | じゅずだま | 数珠用の玉。 イネ科の植物。 |
| 襦袢 | じゅばん | 和服用の下着。 |
| 背負子 | しょいこ | 背中に当てて荷物を背負う木の枠組。 |
| 少輔 | しょう | 律令制で大輔に次ぐ官職。 |
| 判官 | じょう | 「ほうがん」「はんがん」とも。 律令制での検非違使の尉など。 |
| 生姜 | しょうが | =生薑 「しょうきょう」は"しょうが"の根や茎を乾かして作った薬。 |
| 漏斗 | じょうご | 「ろうと」とも。 口の小さい容器への注入を助ける道具。 |
| 女郎蜘蛛 、絡新婦 | じょうろぐも | =絡新婦 コガネグモ科。 |
| 世帯 | しょたい | =所帯 「せたい」とも。 |
| 初中後 | しょっちゅう | いつも。しばしば。 |
| 祥瑞 | しょんずい | 明朝から清朝へ移る時期に景徳鎮で作られた磁器。 「しょうずい」は吉兆の意味。 |
| 白髪 | しらが | 「はくはつ」とも。 |
| 新羅 | しらぎ | 「しんら」「しら」とも。 百済、高句麗とともに古代朝鮮で"三国"として栄えた。 |
| 白禿瘡 、白癬 | しらくも | 皮膚病の一つ。 「はくせん」とも。 皮膚病の一つ。 |
| 不知不識 | しらずしらず | 無意識の間に。 |
| 不知火 | しらぬい | 海上で夜、火影が揺れて見える現象。 |
| 素面 、白面 | しらふ | =白面 「すめん」とも。 酒を飲んでいない状態。 |
| 後方 | しりえ | 「こうほう」とも。 |
| 首級 | しるし | =首 「しゅきゅう」とも。 討ち取った敵の首。 |
| 素人 | しろうと | |
| 沈丁花 | じんちょうげ | =瑞香 ジンチョウゲ科の植物。 |
| 新発意 | しんぼち、しぼち、しんぼっち | 仏門経験が浅い者。 |
| 荵冬 、忍冬 | すいかずら | =忍冬 「にんどう」とも。 つる性の樹木。 |
| 芋苗 、芋茎 | ずいき | =芋茎 サトイモの葉柄。 |
| 芋茎祭 | ずいきまつり | 京都の北野天満宮の祭り。 |
| 清搔 | すががき | =管搔・菅垣 和琴の奏法。 三味線の曲。 |
| 清し女 | すがしめ | 清らかで美しい女性。 |
| 清清しい | すがすがしい | |
| 菅麻 | すがそ | 御祓いに用いる、スゲを裂いたもの。 |
| 木菟入 | ずくにゅう | 僧や坊主の蔑称。 |
| 次官 | すけ | 律令制で長官を支えた役。 「じかん」は省庁で大臣に次ぐ位を指す。 |
| 助柱 | すけ | 建物の傾きを防ぐ支えの柱。 |
| 助太刀 | すけだち | 敵討ちに加わること。 助っ人。 |
| 双六 | すごろく | |
| 従者 | ずさ | 「じゅうしゃ」とも。 |
| 素戔鳴尊 | すさのおのみこと | =須佐之男命 神話における伊弉諾尊 と伊弉冉尊の子。 |
| 生絹 | すずし | 「きぎぬ」「せいけん」とも。 生糸を練らずに織った薄くて軽い布。 |
| 蘿蔔 、清白 | すずしろ | =清白 ダイコンの別名で春の七草の一つ。 |
| 漫事 | すずろごと | くだらないこと。 |
| 寸寸 | ずたずた | きれぎれになること。 |
| 魑魅 | すだま | =魑・魅 「ちみ」とも。 山や石から生じる精霊や怪物。 |
| 透波 | すっぱ | =素破 スパイ。 盗人。 |
| 捨て台詞 | すてぜりふ | アドリブ。 去る際の文句。 |
| 住処 | すみか | =住み家 |
| 天皇 | すめらみこと、すめらぎ、すべらぎ | =皇尊 「てんのう」の敬称。 |
| 皇尊 | すめらみこと、すめらぎ、すべらぎ | =天皇 天皇の敬称。 |
| 角力 、相撲 | すもう | =相撲 |
| 掏児 、掏摸 | すり | =掏摸 |
| 磨硝子 | すりガラス | 金剛砂などで不透明にしたガラス。 |
| 素破 | すわ | =驚破 さあ。 |
| 女衒 | ぜげん | 女性を遊女屋に売る仕事。 |
| 冷笑う | せせらわらう | 嘲り笑う。 熟字訓+送り仮名。 |
| 蟬時雨 | せみしぐれ | 多くの蟬がしきりに鳴くこと。 |
| 台詞 、科白 | せりふ | =科白 |
| 其奴 | そいつ、そやつ | |
| 素麵 、索麵 | そうめん | =索麵 |
| 諷言 | そえこと、そえごと | 「ふうげん」とも。 擬えてそれとなく言うこと。 |
| 曹達水 | ソーダすい | 水+炭酸ガス+甘味料。 |
| 赭土 | そおに、そほに、そぼに | 顔料などに用いる赤い土。 |
| 其処 、其所 | そこ | =其所 |
| 若干 | そこばく、そくばく | =幾許 「じゃっかん」とも。 いくらか。 たくさん。 |
| 内障 | そこひ | 白内障や緑内障など眼球内の病気。 |
| 其方此方 | そちこち | あちこち。 |
| 其方 | そちら、そっち、そなた、そち | |
| 其方退け | そっちのけ | |
| 外方 | そっぽ | "そっぽを向く" |
| 背面 | そとも | 山で日の当たらない北側。 「はいめん」は一般に後ろの方を指す。 |
| 蕎麦 | そば | タデ科の植物。 |
| 蕎麦搔き | そばがき | そば粉をこねた食品。 |
| 雀卵斑 、雀斑 | そばかす | =雀斑・蕎麦滓 「じゃくらんはん」とも。 |
| 岨清水 | そばしみず | 山の断崖から流れる水。 |
| 側妻 | そばめ | =側女 めかけ。 |
| 蕎麦湯 | そばゆ | そばを茹でた残り湯。 |
| 抑抑 | そもそも | さていったい。 発端。 元来。 |
| 征矢 、征箭 | そや | =征箭 鋭い矢尻のついた戦闘用の矢。 |
| 微風 | そよかぜ | 「びふう」とも。 |
| 虚事 、虚言 | そらごと | =空事 嘘の事。 |
| 蚕豆 | そらまめ | =空豆 |
| 算盤 、十露盤 | そろばん | =十露盤 損得の計算も指す。 |
| 泰 | タイ | 国名。 熟語ではないが当て字の要素を持つ。 |
| 幇間 | たいこもち | 「ほうかん」とも。 客の機嫌をとる職業。 へつらってうまく世渡りする人。 |
| 松明 | たいまつ | =炬 松の樹脂を用いた照明具。 |
| 金剛石 | ダイヤモンド | 「こんごうせき」とも。 |
| 田人 | たうど、とうど | 田で働く人。 |
| 手弱女 | たおやめ | 美しくしなやかな女性。 |
| 鷹居 | たかすえ | 鷹狩用のタカを訓練する人。鷹匠。 |
| 高御座 | たかみくら | 天皇の位。 玉座。 |
| 手抉 | たくじり | 神への供え物を入れた土器。 |
| 栲領巾 | たくひれ | 古代、女性が肩から垂らした白い飾り布。 |
| 内匠 | たくみ | 宮廷で建築などを担当した職人。 |
| 内匠寮 | たくみづかさ、たくみりょう、うちのたくみのつかさ | 令外官にあたり宮廷で建築などを担当した役所。 |
| 梟帥 | たける | =建 古代の地方の長。 |
| 担桶 | たご | 棒で担いで運ぶ桶。 |
| 腰輿 | たごし | =手輿 「ようよ」とも。 前後の二人が柄を腰のあたりで担ぐ乗物。 |
| 蛸部屋 | たこべや | 労働者を拘束した飯場。 |
| 檀尻 、山車 | だし | 祭りで使う装飾した車。 =山車・楽車。 |
| 駄洒落 | だじゃれ | くだらないしゃれ。 |
| 田鶴 | たず | ツルの別名。 |
| 手繦 | たすき | =襷 和服の袖や袂をまくる紐。 |
| 黄昏 | たそがれ | 「こうこん」とも。 夕暮れ。 |
| 称辞 | たたえごと | 褒め言葉。 |
| 三和土 | たたき | 土や混擬土で固めた台所や土間。 |
| 踏鞴 、蹈鞴 | たたら | =蹈鞴 足で踏んで風を送る装置。 |
| 太刀 、大刀 | たち | 長くて大きな刀。 |
| 太刀魚 | たちうお | =帯魚 タチウオ科の海魚。 |
| 太刀打ち | たちうち | 斬り合うこと。 勝負すること。 |
| 帯刀 | たちはき、たてわき | 「たいとう」とも。 刀を腰に差すこと。 |
| 方便 | たつき、たずき | =活計 生活の糧、手段。 「ほうべん」は便宜的な手段を意味する。 |
| 活計 | たつき、たずき | =方便 「かっけい」とも。生活の糧、手段。 |
| 竹瓮 | たっぺ、たつべ | 竹を編んだ漁具。 "瓮"は"もたい""かめ"と読む。 |
| 殺陣 | たて | 「さつじん」とも。 斬り合いの場面。 |
| 伊達 | だて | 男気。見栄。 |
| 経糸 | たていと | =経・縦糸 |
| 立女形 | たておやま | 歌舞伎の最高位の女形役者。 |
| 伊達巻 | だてまき | 和装の帯。すだれ巻きの食品。 |
| 仮令 、縦令 | たとい、たとえ | =縦令 「けりょう」とも。 仮に。 |
| 田荘 | たどころ | =田所 田圃。 豪族の私有地。 |
| 煙草 | タバコ | =莨 |
| 足袋 、単皮 | たび | =単皮 親指以外が1つになっており、和服に合わせて履くもの。 |
| 鎮魂 | たましずめ | 「ちんこん」とも。 死者の魂を落ち着かせること。 |
| 適間 | たまひま | 偶然。 |
| 玉響 | たまゆら | 一瞬。 |
| 彩絵 | だみえ | =濃絵 桃山時代に流行した、壁などに金や銀、極彩色で描いた絵。 |
| 訛声 | だみごえ | 濁っている声。 訛った声。 |
| 頑癬 | たむし | 皮膚病。 「がんせん」とも。 |
| 躊躇う | ためらう | =躊う 迷ってなかなか決心できない。 |
| 容易い | たやすい | 熟字訓+送り仮名。 |
| 太夫 、大夫 | たゆう | =大夫 上位の芸人、遊女。 |
| 溜込 | たらしこみ | 乾かないうちに他の色を塗りにじませる日本画の技法。 |
| 達磨 | ダルマ | もと禅宗の開祖。 |
| 誰某 | たれがし | だれだれさん |
| 束子 | たわし | 洗う道具。 |
| 楽車 | だんじり | 祭りで使う装飾した車。 =山車・檀尻。 |
| 段梯子 | だんばしご | 踏み板が広いはしご。 |
| 駄袋 | だんぶくろ | =段袋 大きな布袋。 武士の訓練用のズボン。 |
| 暗争 、暗闘 | だんまり | =黙り・暗闘 |
| 乾酪 | チーズ | 「かんらく」とも。 |
| 主税 | ちから | 「しゅぜい」とも。 律令制で諸国の税を担当した役所。 |
| 茅渟鯛 | ちぬだい | クロダイの別名。 |
| 乳脹 | ちぶくら | 三味線や鼓の膨れたところ。 |
| 窒扶斯 | チフス | 細菌により感染する腸チフスなど。 |
| 血塗ろ | ちみどろ | 血塗れ(ちまみれ) 苦闘。 |
| 炒飯 | チャーハン | 焼き飯。 |
| 卓袱台 | ちゃぶだい | 折りたためる食卓。 |
| 矮鶏 | チャボ | 足が短いニワトリの品種。 |
| 手水 | ちょうず | 顔や手を洗い清める水。 便所。 |
| 手水鉢 | ちょうずばち | 茶室の庭などにある手を洗う水を入れた鉢。 |
| 手斧 | ちょうな | 木材を削る道具。 |
| 鳥渡 、一寸 | ちょっと | |
| 点点 | ちょぼちょぼ | ところどころ。 同レベル。 「てんてん」はあちこち、ぽたぽたといった感じ。 |
| 丁髷 | ちょんまげ | 江戸時代に盛んだった髪形。 |
| 月次 | つきなみ | =月並 ありふれていること。 月ごと。 |
| 土筆 、筆頭菜 | つくし | =筆頭菜 スギナの胞子茎。 |
| 熟熟 | つくづく、つらつら | よくよく。 身に沁みて。 |
| 蹲踞 | つくばい | 手水鉢 「そんきょ」は相撲や剣道の姿勢。 |
| 九十九髪 | つくもがみ | 女性の白髪。 |
| 作物所 | つくもどころ | 平安時代に宮中で調度品や料理を用意したところ。 |
| 黄楊 、柘植 | つげ | =柘植 ツゲ科の樹木。 |
| 土塊 | つちくれ | =塊 「どかい」とも。 土の塊。 墳墓。 |
| 美人局 | つつもたせ | 女が男と共謀して他の男を誘ってだまし威すこと。 |
| 葛籠 | つづら | ツヅラフジで編んだかご。 |
| 九十九折 | つづらおり | =葛折 カーブを繰り返す坂道。 |
| 伝手 | つて | =伝 縁故。 人づて。 便宜。 |
| 海石榴市 | つばいち | 奈良県にあった市場。 =椿市。 |
| 委曲 | つばら | =詳ら。"いきょく"とも。細かいこと。 |
| 旋毛 | つむじ | 髪がうずまいているところ。 「せんもう」はうずまいた毛を指す。 |
| 旋風 | つむじかぜ | 「せんぷう」とも。 渦巻いて吹く強い風。 |
| 心算 | つもり | =積り 「しんさん」とも。 ~したつもり。 |
| 頰杖 | つらづえ | 「ほおづえ」とも。 =面杖 |
| 交尾む | つるむ | =遊牝む 動物が交尾をする。 |
| 遊牝む | つるむ | =交尾む 動物が交尾をする。 |
| 強者 | つわもの | 兵。 |
| 悪阻 | つわり | "おそ"とも。妊娠初期に起こる吐き気や食欲不振。 |
| 為体 | ていたらく | =体たらく |
| 木偶 | でく | 「もくぐう」、「ぼくぐう」とも。木彫り人形。操り人形。役立たず。 |
| 木偶の坊 | でくのぼう | 木彫り人形。 操り人形。 役立たず。 |
| 出会す | でくわす | =出交す |
| 出交す | でくわす | =出会す |
| 梃子 | てこ | =梃 |
| 槓杆 | てこ | =梃・梃子 「こうかん」とも。 |
| 手練 | てだれ | =手足れ 「しゅれん」とも。 手腕があること。 「てれん」は人を操る手段を指す。 |
| 丁稚 | でっち | 職人に奉公し雑役に携わった少年。 |
| 弔上げ | といあげ | =問上げ 死者の年忌の終わり。 |
| 何奴 | どいつ | |
| 春宮 | とうぐう | =東宮 皇太子の住む宮殿。 |
| 蜥蜴 、蝘蜓 | とかげ、やもり | |
| 斎食 | とき | =斎 「さいじき」とも。 寺での食事。 精進料理。 |
| 桃花鳥、 朱鷺 | とき | 特別天然記念物。漢字より』読み仮名の数が多い。 |
| 鯨波 | とき | 「げいは」とも。 戦闘開始や戦勝祝いの声。 |
| 常盤 、常磐 | ときわ | 永久に変わらないこと。 常緑。 |
| 常磐色 | ときわいろ | 黄色がかった緑いろ。 |
| 常磐木 | ときわぎ | 常緑樹。 |
| 常磐津 | ときわず | 浄瑠璃の一派。 |
| 木賊 、砥草 | とくさ | トクサ科の植物。 |
| 鳥座 | とぐら | 塒・鳥栖 鳥の巣。 |
| 時計 | とけい | |
| 何所 | どこ | |
| 年甲斐 | としがい | 年齢相応の思慮分別。 |
| 祈年 | としごい | その年の豊穣を祈ること。 「きねん」とも。 |
| 祈年祭 | としごいのまつり | 陰暦2月4日に豊穣や平和を祈って行われた祭り。 「きねんさい」とも。 |
| 年次 | としなみ | =年並 「ねんじ」。 平年並み。 |
| 泥鰌 | どじょう | =鰌・鯲 |
| 何方 | どちら、どっち、どなた、いずかた | |
| 把手 | とって | =取っ手 「はしゅ」とも。 |
| 舎人 | とねり | 律令制で皇族の警護などにあたった官人。 |
| 宿直 | とのい | 夜、宮中や役所の警護にあたること。 「しゅくちょく」は現代、夜間に勤務先で用事にあたることをいう。 |
| 主殿 | とのもり、とのも | =殿守 律令制で宮中の掃除などをを行った役人、女官。 |
| 濁醪 | どぶろく | =濁酒 「だくろう」とも。発酵させただけの白濁の酒。濁り酒。醪酒。 |
| 濁酒 | どぶろく | =濁醪 「だくしゅ」とも。発酵させただけの白濁の酒。濁り酒。醪酒。 |
| 点火 | とぼし | 「てんか」して照らす道具類。 |
| 左見右見 | とみこうみ | 至る所を見て気を配ること。 |
| 品部 | ともべ | 「しなべ」とも。 大和朝廷に仕えていた世襲的集団。 律令制での技術者の集団。 |
| 響動む | どよむ、とよむ | |
| 響動く | どよめく | |
| 俘虜 | とりこ | =俘・虜 「ふりょ」とも。 捕虜のこと。 |
| 永久 | とわ、とこしえ | 「えいきゅう」とも。 |
| 蜻蜓 | とんぼ、やんま | =蜻蛉(とんぼ) 「せいてい」とも。 "やんま"は大形の"とんぼ"。 |
| 尚侍 | ないしのかみ | 「しょうじ」とも。 律令制で後宮の事務などを担当した役所の長官。 |
| 掌侍 | ないしのじょう | 「しょうじ」とも。内侍司で議員の取り締まりなどを行った判官。 |
| 典侍 | ないしのすけ | 「てんじ」とも。 律令制で天皇の生活や儀式を担当する役所の次官。 |
| 長道、長路 | ながじ、ながち | 遠い道のり。 |
| 中務 | なかつかさ | 律令制で天皇の側近に仕え様々な仕事を行った役所。 |
| 中稲 | なかて | 早稲(わせ)と晩稲(おくて)の間の時期に収穫するイネの品種。 |
| 香螺 | ながにし | =長螺 巻貝。 卵が"海酸漿(うみほおずき)" |
| 就中 | なかんずく | 特に。 |
| 亡軀 、亡骸 | なきがら | 死体のこと。 |
| 薙刀 、長刀 、眉尖刀 | なぎなた | 長い柄に反った刃がついた主に女性用の武器。 |
| 長押 | なげし | 柱間に水平につけた材木。 |
| 仲人 | なこうど | 結婚の媒酌人。 |
| 名残 | なごり | 余波。 心残り。 |
| 余波 | なごり | 「よは」とも。 おさまらない波。 |
| 梨子地 | なじじ | 金銀の粉をまき透明な漆で覆う蒔絵の手法。 |
| 茄子 | なす、なすび | =茄。 |
| 茄子紺 | なすこん | 紫っぽい紺色。 |
| 何故 | なぜ | 「なにゆえ」とも。 |
| 刀豆 、鉈豆 | なたまめ | マメ科の植物。 |
| 雪崩 | なだれ | 傾斜地の大量の積雪が一度に崩れ落ちること。 |
| 何某 | なにがし | =某。 |
| 何卒 | なにとぞ | どうか。 なんとかして。 |
| 名告 | なのり | 武士などが名乗りを上げること。 元服後の実名。 |
| 海鼠 | なまこ | |
| 生節 | なまりぶし、なまぶし | カツオを蒸して干した食品。 |
| 常歩 | なみあし | =並足 馬の歩かせ方で最も遅いもの。 |
| 無礼 | なめ | 無作法なこと。 |
| 無礼る | なめる | 人を馬鹿にする。熟字訓+送り仮名。 |
| 弱竹 | なよたけ | しなやかな竹。 メダケ。 |
| 寧楽 、平城 | なら | =那羅・平城 都としての"奈良"の旧表記。 |
| 形姿 | なりかたち | =形貌 姿かたち。 |
| 生業 | なりわい、すぎわい | 「せいぎょう」とも。 生計を立てるための仕事。 |
| 可成 | なるべく | =成る可く。 |
| 縄暖簾 | なわのれん | 複数の縄で作ったすだれ。 居酒屋。 |
| 新墾 、新治 | にいばり | =新治 新しく開墾した田畑。 |
| 苦塩 、苦汁 | にがり | 海水から塩分を除いたもので、豆腐の凝固剤になる。 「くじゅう」は別の意味。 |
| 和妙 、和栲 | にきたえ | =和栲 細かく織った柔らかい布。 |
| 和幣 | にきて、にぎて | =幣・幣帛 神に供えたり祓に用いたりするもの。 |
| 幣帛 | にきて、にぎて | =幣・和幣 「へいはく」とも。 神に供えたり祓に用いたりするもの。 |
| 和膚 、柔膚 | にきはだ | =柔膚 柔らかい肌。 |
| 和魂 、和御魂 | にきみやま、にぎみたま | =和御魂 柔和な徳をもった神霊。 |
| 和草 | にこくさ | 生えたばかりの柔らかい草。 |
| 和毛 | にこげ | うぶ毛のこと。 |
| 柔手 、和手 | にこで | =和手 柔らかい手。 |
| 二進も三進も | にっちもさっちも | どうにもこうにも |
| 若気る | にやける | 男が女っぽい様子である。 |
| 大蒜 | にんにく | ユリ科の植物。ガーリック。 「おおびる」は"にんにく"の旧称。 |
| 叩頭く | ぬかずく | =額突く・額衝く 丁寧に礼をする。 |
| 泥濘 | ぬかるみ | 「でいねい」とも。降雨の後に地面がぬかっているところ。 |
| 緯糸 | ぬきいと、よこいと | =横糸。 |
| 盗人猛猛しい | ぬすっとたけだけしい | 悪びれないこと。 |
| 渟足柵 | ぬたりのさく、ぬたりのき | 大化の改新の時期に蝦夷討伐のために設けられた砦。 |
| 瓊音 | ぬなと | 玉が触れ合う音。 |
| 烏珠 、野干玉、烏玉 、射干玉 | ぬばたま | 烏玉・射干玉・野干玉 ヒオウギの種子。 |
| 瓊戈 | ぬほこ | 玉で飾った戈。 |
| 微温い | ぬるい | =温い(風呂など) =緩い(規則など) |
| 微温湯 | ぬるまゆ | 「びおんとう」とも。 刺激のない弛んだ状態もいう。 |
| 寝心地 | ねごこち | |
| 螺旋 、捩子、螺子 、捻子 | ねじ | =捩・捻子・捩子・螺子 |
| 年星 、年三 | ねそう | =年三 陰陽道で生年の星をまつること。 |
| 強請る | ねだる、ゆする | 熟字訓+送り仮名 |
| 合歓 、合歓木 | ねむ、ねむのき | マメ科の樹木。 |
| 直衣 | のうし、なおし | 天皇や貴族の平服。 |
| 仰領 | のけくび | 襟足が出るようにした和服の着方。 |
| 熨斗 | のし | 皺を伸ばすための炭火の熱を用いた道具。 |
| 熨斗鮑 、熨斗蚫 | のしあわび | =熨斗蚫 儀式・進物用の、アワビを干したもの。 |
| 熨斗目 | のしめ | 能や狂言、歌舞伎の衣装に用いる絹織物。 |
| 覗機関 | のぞきからくり | 凸レンズつきの穴から中の絵を見る装置。 |
| 野幇間 | のだいこ | 宴席を盛り上げる仕事の人(幇間)の蔑称。 |
| 野阜 | のづかさ | 小高い丘。 |
| 濃餠汁 | のっぺいじる | =能平汁 肉や野菜を煮込み醤油、片栗粉を加えた料理。 |
| 長閑 | のどか | 静かでのびやかなこと。 天候が穏やかなこと。 |
| 陳者 | のぶれば | 申し上げますが… |
| 逆上せる | のぼせる | |
| 野面 | のもせ | 「のづら」とも。 野原一面。 |
| 生血 | のり | 「なまち」とも。 出て間もない血。血糊。 |
| 祝詞 | のりと、ほぎごと | 「しゅくし」とも。 "のりと"は神を祀る言葉。 "ほぎごと"(=寿言・寿詞)は一般に祝いの言葉。 |
| 惚気 | のろけ | おのろけ。 |
| 烽火 、狼煙 | のろし | =狼煙・烽 事件を知らせて上げる煙。 行動開始の合図。 |
| 灰神楽 | はいかぐら | 灰が濡れた際に舞い上がる煙。 |
| 売女 | ばいた | 売春婦。 軽い女性。 |
| 南風 | はえ | 南からの風。 |
| 延縄 | はえなわ | 長い縄に多くの釣り針を垂らして魚を獲るもの。 |
| 莫迦 、馬鹿 | ばか | |
| 博士 | はかせ | 「はくし」とも。 |
| 果敢無い | はかない | =儚い。 |
| 果敢無む | はかなむ | =儚む。 |
| 捗捗しい | はかばかしい | 順調に進む。 |
| 博奕 、博打 | ばくち | =博打 「ばくえき」とも。 賭博のこと。 |
| 馬喰 | ばくろう | =博労・伯楽 馬のよしあしを見分ける人や売買をする人。 |
| 刷子 、刷毛 | はけ | =刷毛 「さっし」とも。 |
| 方舟 | はこぶね | =箱船 方形の舟。 |
| 迫間 、狭間 、迫間 | はざま | =狭間・間 境。谷間。 |
| 剪刀 | はさみ | =鋏 「せんとう」とも。 |
| 土師 | はじ | 古代に土器や墳墓の造成にあたった人。 |
| 麻疹 | はしか | 「ましん」とも。 発疹を伴う急性の感染症。 |
| 土師器 | はじき | 赤褐色で素焼きの土器。 |
| 梯子 | はしご | =梯 |
| 敏捷い | はしこい | =捷い 頭の回転や行動がすばやい。 熟字訓+送り仮名。 |
| 二十重 | はたえ | 幾重。 |
| 旅籠 | はたご | 旅館。 旅用のかご。 |
| 飛蝗 | ばった | 「ひこう」は"ばった"が群れて移動すること。 |
| 初手水 | はつちょうず | 元日に手や顔を水で清めること。 |
| 半被 | はっぴ | =法被 職人などの袢纏。 |
| 服織 、服部 | はとり、はっとり | =服部 機織りのこと。 |
| 煙火 、花火 | はなび | 「えんか」とも。 |
| 埴瓮 | はにべ | 細かい粘土で作った瓶。 |
| 埴生 | はにゅう | 粘土のある土地。 |
| 弾機 | ばね | =発条・撥条 ビヨーン。 |
| 発条 | ばね、ぜんまい | =弾機(ばね) =撥条(ばね・ぜんまい) ビヨーン。 |
| 行纏 、脛巾、脛衣 | はばき | =脛衣・脛巾 昔の脚絆のようなもので、作業の際すねに巻いた。 |
| 羽撃く | はばたく | |
| 披鍼 | はばり | =刃針 「ひしん」とも。 外科用のメス。 鍼灸の針。 |
| 蔓延る | はびこる | 草木が茂る。 横行する。 熟字訓+送り仮名。 |
| 葬帷子 | はぶりかたびら | 葬儀で棺を覆うかたびら。 |
| 速歩 | はやあし | =早足 「そくほ」とも。 ウマの速度。 |
| 囃子 | はやし | =囃 伴奏の笛や太鼓。 |
| 疾風 | はやて | 「しっぷう」とも。 突風。 |
| 流行眼 、流行目 | はやりめ | =流行目 流行性の目の病気。 |
| 流行る | はやる | 熟字訓+送り仮名。 |
| 駅馬 | はゆま | 役人の乗り継ぎのため駅におかれた馬。 |
| 薔薇 | ばら | 「しょうび」、「そうび」とも。 |
| 同胞 | はらから | 「どうほう」「どうぼう」とも。 兄弟。 同じ国の民。 |
| 大角 | はらのふえ、はら | 戦場で用いた笛。 |
| 海狸 | ビーバー | 「かいり」とも。 |
| 麦酒 | ビール | 麦芽+ホップ。 |
| 落籍す | ひかす | 芸者や遊女の借金を肩代わりし廃業させる。 |
| 抽斗 | ひきだし | =抽出し・引出し |
| 販女 、販婦 | ひさぎめ | =販婦・鬻女 行商する女性。 |
| 提子 | ひさげ | =提 鍋型の銚子。 |
| 犇犇 | ひしひし | 身に沁みること。 差し迫っていること。 |
| 緊緊 | ぴしぴし、びしびし | |
| 一向 | ひたすら | =只管 「いっこう」は別の意味。 |
| 只管 | ひたすら | =一向 |
| 緋縮緬 | ひぢりめん | 赤く染めた絹織物の一種。 |
| 喫驚 | びっくり | =吃驚 「きっきょう」とも。 |
| 吃驚 | びっくり | =喫驚 「きっきょう」とも。 |
| 睡蓮 | ひつじぐさ | =未草 "ひつじぐさ"は"すいれん"科の植物の1つ。 |
| 単衣 | ひとえ | =単 裏地のない和服。 |
| 一行 | ひとくだり | 「いちぎょう」「いっこう」は別の意味。 |
| 人心地 | ひとごこち | 寛いだ気分。 正気。 |
| 他人事 | ひとごと | =人事 「たにんごと」とも。 自分に関係のないこと。 |
| 人状 | ひとざま | =人様 人柄、人格。 |
| 為人 | ひととなり | 人柄。 |
| 人雪崩 | ひとなだれ | =人頽 多くの人が押し合い倒れること。 |
| 人頽 | ひとなだれ | =人雪崩 多くの人が押し合い倒れること。 |
| 囚獄 | ひとや | =人屋・牢・獄 牢屋。 |
| 一人 | ひとり | |
| 独り相撲 | ひとりずもう | 自分だけ懸命なこと。 勝負にならないこと。 |
| 独り法師 | ひとりぼっち | |
| 雛芥子、 美人草 | ひなげし | =雛罌粟・麗春花・美人草 ケシ科の植物。虞美人草。ポピー。 |
| 日向 | ひなた、ひゅうが | |
| 日次 | ひなみ | =日並 日の次第。 |
| 夷守 | ひなもり | 古代の九州などの守り人。 |
| 老成 | ひね | 「ろうせい」とも。 古くなること。 大人びていること。 |
| 火熨斗 | ひのし | 炭火の熱で衣服のしわを伸ばす道具。 |
| 雲雀 | ひばり | =告天子 |
| 向日葵 | ひまわり | キク科。 |
| 神籬 | ひもろぎ | トキワギに囲まれた神が宿る場所。 神社。 |
| 日和 | ひより | |
| 日和見 | ひよりみ | 様子を窺ってから態度を決めること。 |
| 金字塔 | ピラミッド | 「きんじとう」とも。 |
| 昼餉 | ひるげ、ひるけ | =昼食 昼ごはん。 |
| 日女 、日霊 | ひるめ | =日霊 天照大神のこと。 |
| 肩巾 、領巾 | ひれ | =領巾 古代の女性の飾り布。 |
| 平伏す | ひれふす | |
| 檜皮葺き | ひわだぶき | ヒノキの皮で葺いた屋根。 |
| 備後表 | びんごおもて | 広島県の上質な畳表。 |
| 回回教 | ふいふいきょう | イスラム教。回教。 |
| 醜男 | ぶおとこ | 「しこお」とも。 |
| 醜女 | ぶおんな | 「しこめ」とも。 |
| 腑甲斐無い、 不甲斐無い | ふがいない | =不甲斐無い 意気地がない。情けない。 |
| 深傷 | ふかで | =深手 大怪我。 |
| 菜蕗 | ふき | =蕗 キク科の植物。 |
| 不器用 | ぶきっちょ | 「ぶきよう」とも。 |
| 河豚 | ふぐ | =鰒。 |
| 陰囊 | ふぐり | 「いんのう」とも。 松かさ。 |
| 巫山戯る | ふざける | おどける。 騒ぐ。 馬鹿にする。 いちゃいちゃする。 |
| 相応しい | ふさわしい | 似合っているさま。 |
| 臥所 、臥処 | ふしど | =臥処 寝床。 |
| 二布 、二幅 | ふたの | =二幅 通常の二倍の幅の布。 女性の腰巻。 |
| 二人 、両人 | ふたり | =両人 「ににん」とも。 |
| 宿酔、二日酔い | ふつかよい | 「しゅくすい」とも。 |
| 筆忠実 | ふでまめ | 文章を書くのを厭わないこと。 |
| 葡萄 | ぶどう、えび | "えび"は"ぶどう"の別名の他、エビヅルやエビ染めの色も指す。 |
| 太占 、太兆 | ふとまに | =太兆 焼いた鹿の骨で吉凶を占うもの。 |
| 吹雪 | ふぶき | |
| 吹雪く | ふぶく | =乱吹く |
| 乱吹く | ふぶく | =吹雪く |
| 古刃 | ふるみ | =古身 古い刀。 |
| 日置流 | へきりゅう | 弓術の一派。 |
| 黒死病 | ペスト | 「こくしびょう」とも。 |
| 巻子 、綜麻 | へそ | =綜麻 糸を環状に巻いたもの。 |
| 綜麻繰 | へそくり | =臍繰 密かに貯めたお金。 |
| 下手 | へた | 「したて」「しもて」とも。 |
| 糸瓜 、天糸瓜 | へちま | =天糸瓜 ウリ科の植物。 |
| 反吐 | へど | 嘔吐すること。 |
| 埴猪口 | へなちょこ | 未熟者。 |
| 粘土 | へなつち | =埴 「ねばつち」「ねんど」とも。 |
| 紅白粉 | べにおしろい | 化粧すること。 |
| 陰核 | へのこ | 陰囊。 |
| 部屋 | へや | |
| 可坊 、便乱坊 | べらぼう | =箆棒。 程度が甚だしいさま。 |
| 紅殻 | ベンガラ | =弁柄 インド産の錆止め、研磨、着色用の顔料。 |
| 反閉 | へんばい | =反陪 陰陽道や神楽で特殊な歩き方をすること。 |
| 寿歌 | ほぎうた | 「ことほぎうた」とも。 お祝いの歌。 |
| 神庫 | ほくら | 神宝を納めておく倉。 小さな神社。 |
| 黒子 、黶子 | ほくろ | |
| 木瓜 | ぼけ、きゅうり、 | 鉄脚梨(ぼけ) バラ科の樹木。 =胡瓜・黄瓜(きゅうり) ウリ科の野菜。 ="マルメロ"はバラ科の樹木。 |
| 反故 、反古 | ほご | =反古 書き損じた紙。 無駄。 破棄。 |
| 干鰯 、乾鰯 | ほしか | =乾鰯 鰯を干した肥料。 |
| 蛍烏賊 | ほたるいか | 発光器を持つイカ |
| 不如帰 、時鳥 | ほととぎす | 鳥名。 =郭公・霍公鳥・子規・時鳥・杜宇・杜鵑・沓手鳥・蜀魄・蜀魂 |
| 子規 、郭公 | ほととぎす | 鳥名。 =不如帰・霍公鳥・郭公・時鳥・杜宇・杜鵑・沓手鳥・蜀魄・蜀魂 |
| 微笑む | ほほえむ | =頰笑む 熟字訓+送り仮名。 |
| 外持 | ほまち | 臨時収入。 臍繰り。 |
| 小火 | ぼや | 大事には至らなかった火事。 |
| 吹螺 | ほらがい | =法螺貝 |
| 母衣 | ほろ | 鐙の背に付けて流れ矢を防いだもの。 |
| 襤褸 | ぼろ | 「らんる」とも。 古い布切れなど。 欠点。 |
| 微酔 | ほろよい | |
| 凸柑 | ポンカン | ミカン科の果実。 |
| 封度 、封度、英斤 | ポンド | =封・听・封度 1ポンドは約450g。 |
| 迷子 | まいご | |
| 槙皮 | まいはだ | =槙肌 マキの内皮を繊維状にしたもの。 |
| 英里 | マイル | 1マイルは約1600m。 |
| 密夫 、密男 | まおとこ | =密男・間男 夫以外の男性と関係を持つこと。 |
| 侍婢 、侍女 | まかたち、まがたち | =侍女 貴人に仕える女性。 |
| 旋網 | まきあみ | =巻網 網で魚群を取り巻く漁法。 |
| 目合 | まぐわい | 目配せ。 男女の情交。 |
| 甜瓜 | まくわうり | =真桑瓜 ウリ科の植物。 |
| 真砂 | まさご | 粒の小さな砂。 |
| 猿子 | ましこ | サル。 鳥名。 |
| 真面目 | まじめ | 「しんめんもく」「しんめんぼく」は物事の本来の姿を意味する。 |
| 不味い | まずい | =拙い 味や技術、顔が悪い。 |
| 十寸鏡 | ますかがみ | =真澄鏡 よく澄んだ鏡。 |
| 益益 | ますます | |
| 正占 | ますら | 言い当てる占い。 |
| 益荒男 、丈夫、丈夫 、大夫 | ますらお | 強くたくましい男性。 「じょうふ」とも読み、一人前の男を指す。 「じょうぶ」は別の意味。 |
| 籬垣 | ませがき | =籬 「りえん」とも。 竹や柴で目を粗く編んだ垣。 |
| 馬塞棒 | ませぼう、ませんぼう | 馬が逃げるのを防ぐ棒。 |
| 老成る | ませる | 大人びている。 熟字訓+送り仮名。 |
| 胯座 、股座 | またぐら | =股座 腿の間。股間。 |
| 真章魚 | まだこ | =真蛸 |
| 区区 | まちまち | 「くく」とも。 |
| 真っ赤 | まっか | "全く"の意味も。 |
| 松毬 | まつかさ、まつぼっくり | =松笠(まつかさ) =松陰囊(まつぼっくり) |
| 睫毛 | まつげ | =睫 |
| 真っ青 | まっさお | 血の気が引いた状態。 |
| 驀地 | まっしぐら | |
| 燐寸 | マッチ | |
| 松囃子 | まつばやし | =松囃 正月に行われた歌初め。 |
| 団居 | まどい | =円居 囲んで並ぶこと。 親しい人が集まること。 |
| 全人 | まとうど | 正直な人。 愚直な人。 「ぜんじん」とも。 |
| 正面 、真面 | まとも | =真面 「しょうめん」は別の意味。 |
| 微睡む | まどろむ | うとうとする。 |
| 俎板 | まないた | =俎 |
| 眼間 、目交 | まなかい | =目交 両目の間。 |
| 目指 、眼指、眼差、目差 | まなざし | =目差・眼差 目つきや視線。 |
| 魚味始 | まなはじめ | =真菜始・真魚始 子どもに生まれて初めて魚を食べさせる儀式。 |
| 学舎 | まなびや | 「がくしゃ」とも。 |
| 真似 | まね | |
| 忠実 | まめ | よく働くこと。 健康なこと。 「ちゅうじつ」は誠実なことをいう。 |
| 馬克 | マルク | ドイツの通貨単位。 |
| 客人 | まろうど、まれびと | =客 「きゃくじん」とも。 訪問客 |
| 満俺 | マンガン | 銀白色で炭素に脆い元素。Mn。 |
| 政所 | まんどころ | 平安時代や鎌倉時代の役所。 |
| 玉柏 | まんねんすぎ | =万年杉 シダ植物。 |
| 御灯明 | みあかし | =御灯 神仏に供える灯明。 |
| 御殿 、御舎 | みあらか | =御舎 御宮殿 「ごてん」とも。 |
| 御稜威 | みいつ | =御厳 神や天皇の威光。 |
| 木乃伊 | ミイラ | |
| 水脈 | みお | =水尾 「すいみゃく」とも。 船が通る海や川の水路。 |
| 澪標 | みおつくし | 「れいひょう」とも。 船に航路を知らせる杭。 |
| 御薪 | みかまぎ | 社寺に奉納するまき |
| 御酒 、神酒 | みき | 神に供える酒。 |
| 酒司 、造酒司 | みきのつかさ | =造酒司 律令制で酒や酢を醸造した役所。 |
| 三行半 | みくだりはん | 離縁状。離婚すること。 |
| 水分 | みくまり | 分水嶺。 |
| 御饌 、御食 | みけ | =御食 神へ供えるもの。 |
| 神子 、皇女 、巫女 | みこ | =巫女 神に仕える未婚の女性。 |
| 皇子 | みこ | 「おうじ」とも。 |
| 神輿 | みこし | =御輿 |
| 弥撒 | ミサ | カトリック教会で神を讃える儀式、歌。 |
| 身動ぎ | みじろぎ | 身動き。 |
| 稚子 、水子 | みずこ、みずご | 生まれてすぐの子。 流産した子。 |
| 不見転 | みずてん | 先を考えない行動。 思慮の浅い芸者など。 |
| 水準 | みずはかり | 「すいじゅん」とも。 水を入れて水平かどうかを調べる道具。 |
| 角髪 、角子 | みずら | =鬟・髻 ・角子 上代の成人男子の髪の結い方。 |
| 鳩尾 | みぞおち、みずおち | 「きゅうび」とも。 |
| 屯田 | みた | =御田 「とんでん」とも。 神の田。 皇室の直轄地。 |
| 恩頼 、恩賚 | みたまのふゆ | =恩賚 神の御加護、天皇の御恩恵。 |
| 御手洗 | みたらし、みたらい | 参拝前に手や口を清めるところ。 |
| 三人 | みたり | 「さんにん」とも。 |
| 嬰児 | みどりご | 「えいじ」とも。 =緑児。 |
| 見惚れる 、見蕩れる | みとれる | =見蕩れる |
| 孤児 | みなしご | 「こじ」とも。 =孤 |
| 水派 | みなまた | 水の流れが分かれるところ。 |
| 御哭 | みね | 泣き叫ぶ儀式。 |
| 刀背打ち | みねうち | =峰打ち 刀の背で斬ることなしにダメージを与えること。 |
| 御佩刀 | みはかし、みはかせ | 貴人が腰に差している刀。 |
| 屯倉 、官家 、屯家 | みやけ | =屯家・官家 大和朝廷の直轄領。 |
| 土産 | みやげ | 「どさん」とも。 |
| 御幸 、行幸 | みゆき | 「ごこう」とも。 上皇や法皇、女院の外出。 |
| 船首 、水押 | みよし | =舳・水押 「せんしゅ」とも。 船の前部。へさき |
| 嫡妻 、正妃 | むかいめ | =正妃 「ちゃくさい」「てきさい」とも。 正式な妻。 |
| 百足 | むかで | =蜈蚣・蝍蛆 「ひゃくそく」とも。 節足動物。 |
| 尨犬 | むくいぬ | =尨 ふさふさな長い毛の犬。 |
| 尨毛 | むくげ | =毳 長くふさふさな毛。 |
| 浮腫 | むくみ | 「ふしゅ」とも。 皮下組織にリンパ液や組織液がたまる症状。 |
| 浮腫む | むくむ | 皮下組織にリンパ液や組織液がたまる。 |
| 起破風 | むくりはふ | 上面が盛り上がった屋根の飾り。 |
| 虫唾 | むしず | =虫酸 逆流した胃液。 |
| 産霊神 | むすびのかみ | 万物を生みだす神 縁結びの神。 |
| 胸座 | むなぐら | |
| 斑気 | むらき、むらぎ | 気まぐれ。 |
| 漁夫 | むらぎみ | =漁翁 漁民の長や漁業の指導者。 「ぎょふ」は単純に漁師を指す。 |
| 眼鏡 | めがね | 「がんきょう」とも。 |
| 召人 | めしゅうど、めしうど | 舞楽に奉仕させる人。 和歌所の寄人。 |
| 囚人 | めしゅうど、めしびと | 「しゅうじん」とも。 |
| 右手 | めて | 馬の右の手。 |
| 目眩 、眩暈 | めまい | =眩暈 |
| 目紛しい | めまぐるしい | 追うのが大変なほど次々と発生、変化すること。 |
| 減上 | めりかり | =乙甲 音の高低や強弱。 |
| 乙甲 | めりかり | =減上 音の高低や強弱。 |
| 莫大小 | メリヤス | =目利安 伸縮性を増した糸で編んだ布地。 |
| 仮面梟 | めんふくろう | =面梟。 |
| 莫臥児 | モール | 浮き織り。 飾りひも。 |
| 痘瘡 | もがさ | 「とうそう」とも。 天然痘のこと。 |
| 虎落笛 | もがりぶえ | 冬の北風が竹垣などに当たってする音。 |
| 木捻子 、木螺子 | もくねじ | =木螺子 螺旋状の筋を持つ釘 |
| 土竜 、鼴鼠 | もぐら | =鼴鼠・土竜 |
| 木蘭 | もくれん | =木蓮 「もくらん」とも。 |
| 裳階 、裳層 | もこし | =裳層 「しょうかい」とも。 仏堂や塔の屋根の下のひさし。雨打。 |
| 猛者 | もさ | 勇猛で技術に長け行動的な人。 |
| 綟子 | もじ | =綟 蚊帳など、麻糸で目を粗く織った布。 |
| 百舌 | もず | =鴃・鵙・鶪 モズ科の鳥。 |
| 毛斯綸 | モスリン | 薄く柔らかい平織りの毛織物。 |
| 保合 | もちあい | =持合 取引市場で相場の変動が少ないこと。 |
| 糯粟 | もちあわ | 粟餅に使う粟。 |
| 糯米 | もちごめ | =糯 餅や赤飯に使う米。 |
| 盛相 | もっそう | =物相 飯の量をはかる道具。 |
| 牴牾 | もどき | 似非。 非難。 「ていご」は食い違う意味。 |
| 武士 | もののふ | 「ぶし」とも。 |
| 紅葉 、黄葉 | もみじ | =黄葉 「こうよう」は別の意味。 |
| 木綿 | もめん、ゆう | "もめん"はワタの種子からとれる繊維。 "ゆう"はコウゾの皮の繊維でできた糸。 |
| 百磯城 | ももしき | =百敷 宮中のこと。 |
| 催合 | もやい | =最合 共同で行ったり所有したりすること。 |
| 唐黍 、蜀黍 | もろこし | =蜀黍 「とうきび」とも。 イネ科。 |
| 両刃 | もろは | =諸刃 両側に刃をもつ刀。 |
| 諸諸 | もろもろ | =諸 いろいろなもの。 |
| 紋甲烏賊 | もんごういか | カミナリイカやコウイカ。 |
| 主水 | もんど | 律令制で宮中の水や氷室を担当した役人。 |
| 翻筋斗 | もんどり | 空中一回転。蜻蛉返り。 |
| 八百長 | やおちょう | |
| 八百屋 | やおや | |
| 八百万 | やおよろず | |
| 山羊 、野羊 | やぎ | =野羊 |
| 山羊鬚 | やぎひげ | あごの長いひげ。 |
| 八色の姓 | やくさのかばね | 684年に制定された姓制度。 |
| 自棄 | やけ | =焼け 「じき」とも。 |
| 火傷 、焼処 、焼傷 | やけど | =焼傷・焼処 「かしょう」とも。 |
| 八尺瓊勾玉 、八尺瓊曲玉 | やさかにのまがたま | =八尺瓊曲玉 三種の神器の1つ。 |
| 香具師 | やし | =野師・弥四 人が多い場所で見世物や出し物をする人。 漢字より読みが長い。 |
| 八握 | やつか | =八束 長いこと。 |
| 寄居虫 | やどかり | =宿借り |
| 雇女 、雇仲居 | やとな | =雇仲居 臨時に雇う仲居。 |
| 寄生木 | やどりぎ | =宿木 |
| 寄生蜂 | やどりばち | 「きせいばち」とも。 |
| 矢作 | やはぎ | =矢矧 矢を作る人。 |
| 流鏑馬 | やぶさめ | 馬を走らせながら的を射る競技、儀式。 |
| 山賤 | やまがつ | 山の中で仕事をする人やその住居。 |
| 山雀 | やまがら | シジュウカラ科の鳥。 |
| 八岐大蛇 | やまたのおろち | 神話上の酒好きの大蛇。 |
| 山祇 、山神 | やまつみ | =山神 山の神様 cf.海神(わたつみ・わだつみ) |
| 大和歌 | やまとうた | 和歌。 |
| 大和魂 | やまとだましい | 日本人の果敢で潔い心。 |
| 大和撫子 | やまとなでしこ | 日本人女性のしなやかでありながら強い精神を持つことをいう。 ナデシコの別名でも。 |
| 山脈 | やまなみ | =山並 「さんみゃく」とも。 |
| 八方 | やも | =八面 四方八方。 |
| 寡男 | やもお | 妻を亡くした夫。 |
| 寡婦 | やもめ | 夫を亡くした妻。 |
| 鰥夫 | やもめ、やもお | 妻を亡くした夫。 =鰥 |
| 守宮 、壁虎 | やもり | =家守・壁虎・蝘蜓 爬虫類。 |
| 弥生土器 | やよいどき | |
| 木綿鬘 | ゆうかずら | 物忌みを示すかつら。 |
| 木綿垂 | ゆうしで | =木綿四手 木綿(ゆう)を垂れること。 |
| 木綿四手 | ゆうしで | =木綿垂 木綿(ゆう)を垂れること。 |
| 所以 | ゆえん | 理由。いわれ。 |
| 浴衣 | ゆかた | 木綿のひとえもの。 |
| 湯帷子 | ゆかたびら | 入浴前後につけた単の着物。 |
| 所縁 | ゆかり | =縁 つながり。関わり合い。 |
| 雪消 | ゆきげ | =雪解 雪解け。 |
| 雪垂 | ゆきしずり | 枝などの積雪が滑り落ちること。 |
| 雪達磨 | ゆきだるま | |
| 行方 | ゆくえ | |
| 靫負 | ゆげい | 靫に矢を入れて運んだ集団。 衛門府。 |
| 強請 | ゆすり、ねだり | 「きょうせい」とも。 |
| 湯女 | ゆな | 温泉宿の接待役の女。 湯屋の遊女。 |
| 斎庭 、斎場 | ゆにわ | =斎場 神を祀る清めたところ。 |
| 湯熨斗 | ゆのし | =湯熨 湯気でしわを伸ばすこと。 |
| 豆腐皮 | ゆば | =湯葉・湯波・油皮 豆乳を煮、膜をすくってできた食品。 |
| 弓弭 | ゆはず、ゆみはず | =弓筈 弓の弦をかける部分。 "弭"でも"ゆはず"と読む。 |
| 浴槽 | ゆぶね | =湯船・湯槽 「よくそう」とも。 |
| 忌忌しい | ゆゆしい | ひどくて放っておけない。 不吉だ。 =由由しい 「いまいましい」は別の意味。 |
| 百合鷗 | ゆりかもめ | カモメ科の鳥。 |
| 左手 | ゆんで | =弓手 「ひだりて」とも。 |
| 横笛 | ようじょう | 「よこぶえ」とも。 |
| 良候、宜候 | ようそろ | =宜候 船の直進を意味する号令。 |
| 益無し | ようなし | 「やくなし」とも。 無駄である。 |
| 沃土 | ヨード | 消毒用のハロゲン元素。ヨウ素。 |
| 沃度丁幾 | ヨードチンキ | ヨウ素をアルコールに溶かした消毒殺菌用の液体。 |
| 寿詞 | よごと | =吉言 天皇家の栄えを祝う言葉。 「じゅし」は一般に長生きを祝う言葉。 |
| 横痃 | よこね | 「おうげん」とも。性病による股の炎症。 |
| 寄席 | よせ | 落語や講談、浪曲を演じる場所。 |
| 余所 、他所 | よそ | =他所 |
| 余所見 | よそみ | 脇見。 人目。 |
| 弥立つ | よだつ | cf.身の毛が"よだつ" |
| 夜業 | よなべ | =夜鍋 「やぎょう」とも。夜仕事をすること。 |
| 夜尿 | よばり | 「やにょう」とも。 寝小便のこと。 |
| 黄泉 | よみ | 「こうせん」とも。 あの世 |
| 黄泉路 | よみじ | あの世への道。 |
| 四方 | よも | 「しほう」とも。 |
| 終夜 | よもすがら、よすがら | 「しゅうや」とも。 一晩中。 |
| 四方山 | よもやま | あちこち。世間。 |
| 寄人 | よりゅうど | 昔の朝廷の職員。 |
| 度度 | よりより | =寄り寄り 時々。 「たびたび」は何度もの意味。 |
| 寄方 | よるべ | 頼りにする人や場所。 =寄辺 |
| 弱法師 | よろぼうし、よろぼし | よろよろと歩く僧。 |
| 蹌踉めく | よろめく | 不安定で倒れそうになる。 誘惑に乗る。 |
| 拉薩 | ラサ | ラマ教の聖地。 |
| 乱波 | らっぱ | 乱暴者。 スパイ。 |
| 羅甸 、拉丁 | ラテン | =拉丁 ラテン語、ラテン音楽、ラテン系など |
| 喇嘛教 | ラマきょう | チベット仏教の別名。 |
| 栗鼠 | りす |
| 凜凜しい | りりしい | 引き締まっていて勇ましい。 |
| 凛凛しい | りりしい | 引き締まっていて勇ましい。 |
| 淋巴 | リンパ | 高等植物の組織細胞の間を満たす体液。 |
| 淋巴腺 | リンパせん | リンパ管の結節。 |
| 坩堝 | るつぼ | 耐熱性の容器。 熱狂した状態。 様々なものが入り混じった状態。 「かんか」とも。 |
| 蓮華躑躅 | れんげつつじ | ツツジ科の樹木。 |
| 櫺子 | れんじ | =櫺・連子 窓や欄干の等間隔の格子。 |
| 分別 | わいだめ | =弁別 「ふんべつ」とも。 区別、けじめのこと。 「ぶんべつ」は分けること。 |
| 弁別 | わいだめ | =分別 「べんべつ」とも。 区別、けじめのこと。 |
| 公魚 | わかさぎ | =若鷺・鰙 淡水魚。 |
| 和布 、若布 | わかめ | =稚海藻・若布・裙蔕菜 |
| 没分暁漢 | わからずや | 「ぼつぶんぎょうかん」とも。 頑固で道理を弁えない人。 |
| 狐臭 、腋臭 、胡臭 | わきが | =胡臭・腋臭 |
| 吾妹 | わぎも | 昔の妻や恋人の愛称。 |
| 病葉 | わくらば | 病気にかかった葉。 |
| 若人 | わこうど | |
| 童謡 | わざうた | =謡歌 古代の諷刺や予言の歌。 「どうよう」は子どもの歌を指す。 |
| 謡歌 | わざうた | =童謡 古代の諷刺や予言の歌。 |
| 俳優 | わざおぎ | 神や人を笑わせ楽しませる人。 「はいゆう」は一般に役者を指す。 |
| 山葵 | わさび | アブラナ科の植物 |
| 勿忘草 | わすれなぐさ | ムラサキ科の植物。 |
| 早生 、早稲 | わせ | 早く熟す野菜や果物の品種。 早熟な人。 |
| 海若、 海神 | わたつみ、わだつみ | =海粟 海の神。 海原。 |
| 渡座 | わたまし | 貴人の転居。 |
| 戦慄く | わななく | 恐怖、怒り、寒さで体が震える感じ。 |
| 童巫子 、童巫女 | わらわみこ | =童巫女 子どもの巫女。 |
| 理無い | わりない | 分別がない。 しかたない。 関係が深い。 |
| 仙蓼 、地楡 、吾木香 、吾亦紅 | われもこう | =吾木香・我毛香・地楡・我亦紅 バラ科の植物。 |