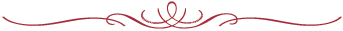
| 漢字の訳字考 |
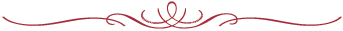
(最新見直し2015.3.24日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、漢字の訳字考をしておく。 2006.8.31日 れんだいこ拝 |
![]()
| 松尾義之著「日本語の科学が世界を変える」(筑摩選書)。飛田良文著「明治生まれの日本語」(淡交社 2002)。 母国語の日本語での科学研究だったからこそ繁栄し、独自の成果を挙げたのではないかとの仮説。日本語での科学研究を可能にしたのは、江戸末期から明治初期、輸入された科学の概念や言葉を日本語化した先人たちの功績によるところが大きい。 蘭学者の宇田川ようあんはセルを「細胞」と訳す。思想家の西周は「科学」。「連環」を造語して、数学、哲学、天文学、化学などの諸学問が互いに補う体系を表現した。 「物性」。日本独自の科学用語。物質の性質を原子論的立場から研究する「物性論」は、外国では該当する言葉がない。 |
| 「術語国字」。新語(日本語に西洋語の概念が存在しないので、日本が新たに漢字を組合わせて作った単語)。例えば、「自由」(liberty)、「社会」(society)、「自然」(nature)、個人(individual̶)、新婚旅行(honey-moon̶)、哲学(philosophy̶)、科学(science̶)、彼女(she̶)、時間(time̶)。借語(日本語に西洋語の概念が存在しないので、中国で活躍した欧米人宣教師が中国語訳した訳語を、漢訳洋書や英華辞典から借用したもの。すでに中国で宣教師などが使っていた単語の借用日本語)。例えば、冒険(adventure̶)、恋愛(love̶)、電報(telegram̶)。転語(日本語の中にあったが違う意味だった単語)。例えば、世紀(century̶)、常識(common sence)、家庭(home)、衛生(hygiene)、印象(impression̶)、権利(right)。 | |
| 中国で使われる熟語の70%は日本製 2002年10月14日、インターネット「世紀中国」に寄せた論文の中で、中国人学者王彬彬は、次のように述べている。
西周という津和野出身の明治の貴族院議員がいた。聞く処や調べた処によると、これら日本製「国字」は、西周によるものが多い。西周は明治文化の功労者の一人であり、「哲学」という国字の開発者であると共に、我国哲学界の先駆者として知られている。日本で最初にヨーロッパの諸科学体系を紹介したのは、西周の「百学(ひゃくがく)連環(れんかん)」、明治四年著作である。西は諸学問を「心理上の学」と「物理上の学」と二分類した。そして、「哲学」、「天文学」などの呼称を固定させた。西周は「主観」、「客観」、「定義」、「命題」、「前提」、「演繹」、「帰納」などの国字を工夫した。故にその後の日本の学問が大きく素早く進歩成長を遂げたのである。 前島密は、1866年(慶応2年)に「漢字御廃止之議」という建議書を将軍徳川慶喜に提出した。これは、国民の間に学問を広めるためには、難しい漢字の使用をやめるべきだという趣旨のもので、わが国の国語国字問題について言文一致を提言した歴史的な文献である。彼は青年時代、江戸から帰省したとき、みやげの絵草紙と三字経を甥に教えてみて、漢字教育の難しさを痛感し、漢字廃止を思い立った。その後も、国語調査委員としてこの問題に取り組んだ。 中国が輸入した日本製国字。エコノミーを「経済」、ソーシャリズムを「社会主義」などの国字を創出したが、中国はこれを輸入して現在でも中国の常用語になっている「名訳」なのである。中国が日本から輸入した国字は無数だが「文明」、「交通」、「哲学」、「手続」、「引揚」、「鉛筆」、「演説」、「会話」、「計画」、「原則」、「侵略」、「信用」などで中国近代化に大きく貢献しているのである。中国にはカタカナも平仮名もなく漢字だけである。中国では、テレビは「電影」、アイスクリームは「氷菓」、チョコレートは「巧克力」、エレベーターは「天梯」、自動車は「汽車」、汽車は「火車」、バスは「巴士」、タクシーは「的士」などしか翻訳しようがないのだ。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)