| 白井朗「ブントと革共同との歴史的関係について-新左翼創成の歴史を考える」 |
 (私論.私見) (私論.私見)
|
| これは別名「白井朗の黒田寛一、本多延嘉批判」とでも名付けるべきであろう内容を持つ好著である。
|
| 「年誌」への寄稿を認めていただいたことに感謝し、この機会に新左翼運動創成期を体験した者として、歴史をできるだけ正確に記録することを心がけたい。 |
| はじめに |
革共同(革命的共産主義者同盟)の創立は1957年1月27日(最初はトロツキスト連盟。同年末12月1日に改称)、ブント(共産主義者同盟)の創立は翌1958年12月10日であった。以来既に50年近くが過ぎ去り、創立時の多くの人々は亡くなり、事実を正確に記録することが求められている。
先ず頭に浮かぶのは、普通の人はこの二つの団体がなぜ別々に分かれたのか、その理由は一体なんなのか、フシギに思うに違いないということである。単に二つの組織に限らず、ほとんどの新左翼セクトの相違は、普通の市民には分かりにくかったと思う。それ以上にほとんど同じ組織が何故あんなに激しく争い、ついには内ゲバにまで至ったのか誰も納得できなかった。中でもブントと革共同とは、最もよく似た組織であった。
新左翼セクト間の争いは、中核派対革マル派、連合赤軍内部の争いの二つが最も激しく、生命を奪い合うところまで極端化した。折角70年安保・沖縄闘争で何万人もの結集をなしとげ、多くの人々から「新左翼の時代」と期待されたのに、72年連合赤軍の妙義山「総括」の事件と、さらに70年闘争の最中に開始された中核派と革マル派との激しい内ゲバは十年間も続き、多くの人々は嫌悪感を抱き運動に絶望した。支持者を失っただけでなく、新左翼の存在そのものが市民社会から忘れられていった。
こんな残念なことが、崇高な理想を掲げて出発した新左翼世界で何故起きたのか。それは創成期の歴史とは一体どんな関係があるのか、創成期の理想とは無関係で中途から誰かが、或いは何らかの予期せぬ力が歴史を捻じ曲げたのか。この問いに答えることが、新左翼の歴史を解くカギである。どんな組織でも「起源に本質がある」立場から組織論的に歴史的考察を行うとき、組織の出発時点の原形質に、その後発展した組織の問題点をえぐり出すことができる。この問いには、最後に答えることにしよう。
私は、新左翼運動創成期の歴史を忠実に事実を再現しつつ、新左翼運動・社会主義運動の再建のために、いくつかの論点について意見を述べたい。
最初に言っておくが、黒田寛一「日本の反スターリン主義運動」(1、2の分冊。68年、69年)の総括方法は、何の役にもたたず有害だということである。自分の正統性を証明する目的で超主観主義で現実の歴史を裁断し、自分の執筆した文書がすべて実現された、そうでない場合は反対派か他党派の邪悪な妨害によるとする方法は最悪である。これでは、かの悪名高きスターリン「ソ同盟共産党史」と変らない。
私は、運動の過程に生きた個々の人間をできるだけ具体的に描きたいと思う。崇高な理想を目的として行動するかの如く見えても、実際には人間臭い勘定、その最たるものとして権力欲・権力エゴイズムが、政治的人間を突き動かす場合が多い。政治的に重大な行為が、まさに「俗情との結託」を基礎とした権力主義によってなされるのである。
1950年代末の新左翼運動当時、滔々たる「左翼への流れ」が日本共産党や周辺の学生・青年労働者の心ある人々を捉え、まさに疾風怒濤の時代を創り出したことは、日本の歴史に記録されるべき事柄である。長年のスターリン主義の官僚主義、反知性主義、右翼日和見主義の制約と弾圧にウンザリしていた多くの青年学生は、新左翼運動に大きい希望を見い出した。それは今思い起しても素晴らしい希望の時代であった。
あれから五十年、この希望はかなえられたのであろうか。革共同・中核派もブントも成功したとはとても言えない。革マル派に至っては、論外である。一体何故半世紀にもわたる何万人もの活動家の血の滲む努力が実らず、逆に衰退し、日本共産党に代わる新しい労働者党を創成するのに失敗してしまったのか。
内ゲバの悲惨が70年安保・沖縄闘争に結集した数万人もの人々を失望させ、70年世代・全共闘運動の大きさにふさわしい影響を全共闘世代が社会に維持・拡大していくのを妨げたことは、否定ではない。これは、現在多くの人々の同意を得ていると思う。何故そんなセクト主義が多くの新左翼セクト、とくに中核派と革マル派を虜にし、またブントも例外ではなかったのか。この解明は必ずしも十全ではない。
私はこの問題を、単に革共同・中核派とブントとの関係の歴史を考察することによって考えるだけではなく、日本共産党の50年分裂にまで遡って考える必要を感じる。何故か。日本共産党・スターリン主義から決別し、独立した組織を創成した新左翼運動には、ブント・革共同だけではなく、最盛期には五流十三派(五流とは革共同系、ブント系、構造改革派系、毛沢東派系、社青同系)もの党派があった。その源流をたどるとき、どうしても50年分裂に行きつかざるを得ない。
1950年以来、スターリン主義的制約を脱した独立した知性を持つ批判的共産主義者は、実に十数万人にも達したと推定される。これは途方もない数である。その最先端の人々は、55年六全協以来革命運動再建に力を尽くし大きな成功を収めた。その潮流こそが50年代末の新左翼へと向う時代の流れを創った。この歴史的事実を認識できない人は去るべきである。こうした批判的共産主義者(批判的とはこの場合社会主義革命をめざす意味)のグループが一つの団体にまとまることはかなわなかったとしても、ゆるやかな連合を形成して、共産党に代わる新たな組織を如何にして創成するのか、綱領問題から組織論に至る論点について、友好的に気長に粘り強く議論し一致点を採って行くための目標に向って、何故努力を積み重ねなかったのか。三派全学連の結成と、70年闘争の時機には八派統一戦線さえ形成されたのだから、それは不可能と言えなかったはずである。
しかし革共同の歴史を反省するとき、反スターリン主義の先駆者であるという自負心からの自己絶対化が強過ぎて、自分の党を中心とし自己の利益になる統一戦線は否定しないとはいえ、新たな党を創成するために同質の党派に接近し討論、交流、連合を追求する思想的態度を欠如していた。とくにブントとの間には、その現実的可能性があったのに。
それを不可能にしたのは、レーニン主義的組織論の必然的にもたらすセクト主義である。党指導部だけが真理を持つとするカウツキー式の「外部注入論」(自組織の指導者以外には真理を創造できないから、外部にはマルクス主義はない。ましてや研究者は非実践的だから混乱をもたらすだけだ)、それを組織的に押し通すための中央集権制、その邪魔が入らぬよう党員と外との遮断(他の党派や研究者等の「非実践的理論」に被れぬ為。また党外の労働者、農民の革命的高揚が党を乗り越えたとき指導部の権威が失墜するため、その影響を防ぐため)の為の規約第一条、この三点こそ、50年分裂以来批判的共産主義者の結集を妨げた最悪の要員である。
共産党から追放された批判的な人々も、依然として共産党と同じセクト主義組織論に囚われ続け、共産党を越える人間的度量の大きさを持たなかったことが失敗の原因であった。特に中核派のセクト主義が災いした。共産党は独立した知性を持つ人々を次から次へと追放して、思想を欠如した組織統一によって議会主義的に肥大化してきた。他方、新左翼は独立した知性を持ちマルクス主義の探求を続けて来た人々が多数いたにも拘わらず、その知性を生かせなかった。思想の深化の為の長期にわたる持続的努力と組織的行動の統一を矛盾なく遂行する方法、学問的に追及する為の組織外の研究者との協同志向を持たなかったからである。気長に同志的に討論して行けば大きな統一が可能なのに、小さい論点でも見解の差異は直ちに組織対立と争いを生み、セクトの分裂に結果した。革共同がブントを中間主義と罵倒したことは、その一例である。自分だけが反スターリン主義で、ブントはスターリン主義を脱却できないとの批判である。だがこの非難は誤りであることは既に証明された。
以上の視点からブントと革共同の関係をヨリ広い視野と大きい射程の中に捉え、そうした批判的共産主義者の問題を集中的に表現するものとして考えていきたい。
次の論点に絞って考えたい。第一に、反スターリン主義の先駆者を自負していたはずの革共同指導部において、自分たちが昨日まで属していた日本共産党・スターリン主義の歴史と組織論の反省を欠如させていたこと。第二に、かの1958年6.1事件からブント創立に至る58年の決定的時機に革共同・探求派は、一体何をしていたのか率直、真摯に反省すること。第三に、61年の革共同によるブントの吸収は何であったのか。黒田寛一組織論のスターリン主義的本質の批判、この三点を中心に創成期の歴史を考えていきたい。 |
| 日本共産党の50年分裂の意味するもの |
| 私がここで50年分裂を採り上げるのは、以上の第一の論点に関わるからである。戦後の世界中のスターリン主義党の歴史において、50年分裂は最大の規模と深さを持つ分裂であり、スターリン主義の本質的問題性を照らし出そうとした歴史的事件であった。【フランス共産党においても50年代初めに政治局員アンドレ・マルティ(ロシア革命への反革命干渉戦争に出兵したフランス海軍黒海艦隊で革命に共鳴し叛乱を組織したリーダー)とシャルル・ティコンが「レジスタンスで圧倒的な指導権があったのに、何故革命に決起しなかったのか」と本質的批判を提起、だがすぐ除名され全国的な分裂には至らなかった】。 |
| 50年分裂とは、50年1月にコミンフォルムによる野坂理論批判が突然行われたのを契機に、中央委員会の徳田、野坂ら主流派の「民族解放民主革命」の右翼日和見主義路線に批判を持ち、異議を唱えた多くの批判的共産主義者・国際派が、50年春に追放されたことをさす。分裂はまさに全組織を真っ二つに割る深刻なものに発展した。国際派が多数を占めたのは、中国、関西、東北の三地方委、東京都委ほか多数に上り、大衆団体では新日本文学界、婦人民主クラブ、全学連中央の党員グループ、都内の学生細胞等であった。なかんずく最も活発な全学連は、反帝国主義を掲げて50年レッドパージ反対闘争に勝利した。この意義を没却してはならない。文学者の活動も大きかった。 |
 (私論.私見) (私論.私見)
|
| この記述は、白井氏の我田引水が際立つ。「中央委員会の徳田、野坂ら主流派の『民族解放民主革命』の右翼日和見主義路線」なる記述が違うのではないのか。後の展開から見ても分かるように、徳球と野坂の腹の内は別物だった。野坂は後に宮顕と二人三脚し始めるなど党内遊泳に成功し、徳球-伊藤律系は葬られた。ここを正確に捉えて、当局側に許容されなかった徳球-伊藤律系、許容されていた野坂系という分別で識別することなく十派一からげにするのは如何なものか。当時の党中央は徳球-伊藤律系で、野坂はその客分のような地位にあった。その政治理念は同床異夢だった。徳球-伊藤律系は、外国からの野坂批判に対して党中央の立場から客分の野坂の政治的地位を護ったのであり、野坂の平和革命路線を護ったのではない。敢えて言うなら徳球-伊藤律系は野坂の平和革命路線をも許容しつつ総合的に政権奪取式政変に向おうとしていた。そういうレベルで捉える必要があろう。 |
| 今日に至るまで新左翼世界では、50年分裂の歴史的意味、新左翼組織の創成にどんな関係があったのか、深い研究がなされておらず、歴史的意義が共有されていない。共産党はスターリン主義だから、当然自分たちは無関係であると見做している人が多い。だがそんな歴史の忘却は、自分自身の存在意義をも認識不能にする。50年分裂は55年六全協を生み出す歴史の起点となり、六全協が生み出したいわばマルクス主義ルネサンスとも云うべきイデオロギー状況こそ、新左翼誕生の土壌となったのである。 |
 (私論.私見) (私論.私見)
|
| 「50年分裂は55年六全協を生み出す歴史の起点となり」の記述は国際派的観点からの見通しである。後半の「六全協が生み出したいわばマルクス主義ルネサンスとも云うべきイデオロギー状況こそ、新左翼誕生の土壌となった」記述には不満である。六全協が「マルクス主義ルネサンスとも云うべきイデオロギー状況こそ、新左翼誕生の土壌となった」にせよ、半面で最悪の宮顕指導部が誕生し、以降、日本左派運動はその最悪の宮顕指導部の敷いた総路線に操られながら推移し今日に至っていることに対する痛苦な認識がないとイケナイのではないのか。ノー天気過ぎよう。 |
| しかるに当の新左翼指導部(中核派政治局)の中には、自分が経験したはずのかの有名な1958年6.1事件や、当時の共産党・東京都委員会(武井昭夫、野田弥三郎、安東仁兵衛らの反対派が多数を占めた)の中央・宮本顕治批判に果たした先鋭な役割をすっかり忘れてしまい、当事者自身の風化と堕落が支配的である。「都委員会は革命党の規律を守らぬケシカラン日和見主義者(清水丈夫。共産党は革命党だ)」とか、「共産党は(51年五全協の)武装闘争路線を捨てるべきではなかった」(本多延嘉。六全協は右翼日和見主義)とか、凡そ信じられぬ発言がなされて、私は愕然としたことがある。まさに「過去を記憶しないものは、自らそれを繰返す運命にある」(サンタヤナ)。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「都委員会は革命党の規律を守らぬケシカラン日和見主義者(清水丈夫。共産党は革命党だ)」とか、「共産党は(51年五全協の)武装闘争路線を捨てるべきではなかった」(本多延嘉。六全協は右翼日和見主義)の件は初耳で、清水、本多が所感派系であること、白井が国際派系であることを知らされた。これは望外の情報であり感謝する。れんだいこは逆に清水、本多の政治的感性の良さを知った。 |
スターリン主義を批判せずに反スターリン主義はあり得ない。共産主義運動に発生する健忘症は、運動発展・再生の最大の敵である。何故健忘症が生じるのか。それは、自己の生まれて来た土壌の歴史を忘却した方が、指導部権力維持に有利と思う権力主義から生じる。自分が全てを創始したとする歴史の偽造によって指導部権力を飾ろうとする権力主義者がいかに多いか、中核派の場合には戦術極左でスターリン主義を克服できる夜郎自大が思想喪失を生み出し、歴史の忘却を生み出した。
反スターリン主義の立場に立ったはずなのに、スターリン主義組織論について無反省とは、具体的に何をさすか。それは50年分裂がコミンフォルム批判なる野坂への突然の死刑判決の如き非難によって分裂を促進しておきながら、51年にはスターリン直々の裁定によって、思想的討論をヌキに国際派に所感派への理不尽な屈服を物理的に強制した事実に無知であり、眼を塞いでいることを指す。各国共産党は、組織問題に関して決定権を持たず、「全知全能のモスクワ」に追随する、この組織論を批判することを怠ったのである。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| スターリンの野坂批判から始まる所感派と国際派への分裂、スターリンに恭順する国際派ではなく自主独立の気概を示す所感派支持への帰結は、変なブーメラン廻りであるが、スターリン派が、野坂-宮顕を敵方スパイラインと見做して不信を抱いており、かのラインに党中央を任せてはならないとする見地からのブーメランであることを見て取れば首肯できる。スターリン派は、野坂-宮顕ラインの国際ユダ邪エージェント性を見抜いており、それに乗っ取られようとする日本共産党に警鐘乱打していたと思えばよい。これはスターリン裁定を支持することに意味があるのではなく、それほどまでに野坂-宮顕ラインを否認する政治的重要性を知ることに意味がある。 |
コミンフォルムの正式名は、「欧州共産党・労働者党情報局」である。資本主義国の共産党はフランス、イタリアの二つだけで、モスクワが万能の決定権を持っていた。日本共産党は非加盟で冷遇されており、野坂への非難は全く突然の衝撃であり、凡そ共産主義者の同志的な批判とは無縁であった。その批判とは、野坂が唱えていた「アメリカ占領軍は、日本に民主主義をもたらした。よって平和的に占領下において革命を達成できる」とした戦後共産党の戦略に対する批判であった。47年2.1ゼネスト中止に見られるように、アメリカ占領軍の反動性は明らかになったのに、なお野坂理論が維持された。野坂は誤りだが、コミンフォルム批判はソ連外交政策のジグザグのツケを各国共産党に回しただけであった。
1939年にスターリンは、ナチス・ドイツと独ソ不可侵条約を締結したが、41年にはヒットラーの侵略に直面し一転して「民主主義米英」との同盟に走り、戦後も維持しようとしたが、不可能になり、「米英帝国主義非難」にまたまた無節操に転換しただけの話であった。
今安倍政権のもとで憲法改悪が企(たくらま)れているとき、戦後憲法のもとで育って来た若い世代の多くにある戦後民主主義の価値の無理解は改憲阻止の障害を為す。その為若干の注釈が必要と考える。死刑条項を持つ治安維持法のもとで非合法態勢下に闘ってきた日本共産党の幹部たちが、獄中18年もの自由剥奪から一転して解放され、或いは野坂のように亡命先から帰国して大歓迎され、時代の脚光を浴びる時代に入ったその喜びは、元々憲法のもとで物心ついたときから基本的人権を保障され自由がある時代に生きて来た戦後世代にはなかなか理解しがたいところがある。 |
時代には時代特有の精神的価値が支配的である。それを学ぶのが歴史を学ぶ意味である。例えば現在問題の従軍慰安婦の「強制性」の否定議論で、安倍総理は3.27日朝日新聞夕刊で時代認識の恐ろしい欠如を暴露している。「慰安婦として拉致されたのであれば、何故横田めぐみさんのように声をあげなかったのか」と。声を上げて騒いだ記録がないから、拉致などやっていないはず。こんな歴史の認識不足を一国の総理が平然とさらけ出す。女性を軍が組織的に拉致しレイプする行為について、被害者が公然と名乗りをあげ数十年間も糾弾しているのに、国民として恥ずかしい限りである。十五年戦争当時の天皇制専制・軍部独裁のもとで、万一軍部を批判したなら日本国民はすぐに処刑された。ましてや朝鮮人は植民地支配下にあり、自由な声などあげたなら生命さえ奪われたことに安倍は認識しない。流石(さすが)に満州国総務庁次長(副首相)・岸信介の孫ではある。
また敗戦時に占領軍に見られぬように都合の悪い政府・軍の資料は全て焼却され現存していない為、慰安婦の資料も少ない。自分が資料を抹殺しておいて、証拠がないとは何ごとか。だが証拠は東京裁判に於いて、アジアの占領地各国において多数集められているのだ。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 従軍慰安婦問題を左派的反戦闘争のマターにすることには疑義がある。「証拠は東京裁判に於いて、アジアの占領地各国において多数集められているのだ」は東京裁判を肯定しており、その観点が陳腐凡庸過ぎよう。この歴史を観る際の凡庸過ぎる観点が白井氏の政治理論の限界を造っている気がする。 |
安倍に限らず、戦前・戦時下どんなに息の詰まる不自由な社会であったか、その歴史を学ぼうとしない新左翼活動家も沢山いる。そういう歴史の無知が憲法の価値を認識不足にし、改悪反対闘争への決起を妨げている。「過去を記憶しない者は、自らそれを繰返す」。中核派は「護憲ではない改憲阻止を、プロレタリア革命として闘え」と途方もない空論を主張している。中核派は護憲勢力ではない。闘争の妨害者である。
その意味で、戦後民主主義のもたらした共産主義運動の自由を、我々もしっかりと認識した上で野坂批判を行うべきだと思う。憲法の保障する民主主義的権利のもとでの労働組合運動、学生運動、市民運動の大衆的展開をいかに実現していくか、その方法を真剣に考えるべきである。この答えをしっかりと出してのみ共産主義者として野坂批判は完結する。 |
| スターリン主義組織論の犯罪性 |
コミンフォルムのこのやり方は、レーニン・コミンテルンに起源を持つ。ヨーロッパで最も革命的であったドイツ・プロレタリアートのエネルギーを独自の指導権を否認して抹殺したのは、レーニンである。ローザ・ルクセンブルクが「未だ一国でしか革命が勝利せぬ時期に国際組織を創成すると、ロシアの党と国家の利益を中心に運動する必然性があり、本当の国際主義組織にならないから創成に反対」と批判したことは、完全に的中した。コミンテルンは「大ロシア民族主義の共産主義的粉飾形態」に過ぎない。
コミンフォルム指導なるものは、余りにも不自然で人情を無視している。一所懸命に闘っている共産主義者の同志を、はるか彼方の外国から事情をよく知らぬくせに突然「マルクス・レーニン主義とは縁もゆかりもない」などと死刑判決を下す。そして無批判に追随させられる。こんな方法で共産主義者がその国、民族に根を下ろせるはずがない。
コミンテルンが1927年に山川イズムと福本イズムとの論争を双方ともダメと判定し、日本の革命運動の自立性、自律性を破壊した時から戦後に至るまで、モスクワは国際共産主義運動を破壊する役割しか果たしていない。コミンテルンさえなければ、1920年代の中東イスラーム世界の革命、ドイツ革命は必ず勝利していたと私は確信している。世界革命を敗北させた責任は、レーニンにある。個々の民族の革命運動の方針決定は、その民族の革命家に任せ独立性を尊重するのが当然である。マルクス主義は本来そういう思想である(1881年10.25日、エンゲルスからベルンシュタインへの手紙)。 |
コミンフォルム批判への最初の反応は、徳田書記長ら政治局多数派の批判に反対して「コミンフォルム論評についての所感」を発表した。このため所感派なる名称が生まれた。だが中国共産党の再度の批判で、理論外的に屈服した。反対派は中央委員会内では宮本顕治、志賀義雄、神山茂夫らで、国際批判に忠実な態度を採ろうとした為に国際派と呼ばれた。文学者の花田清輝、大西巨人らも国際派であった。闘いに於いても、綱領理論に於いても最も先鋭であったのは、云うまでもなく全学連の学生共産主義者であった。
綱領論争の最大の対立点は、国際派の特に若い全学連の活動家の中では戦略的には社会主義革命に近づく傾向を見せたのに対して、所感派はブルジョア民族主義の民族民主革命であった。現在でも日本は敗戦帝国主義としてアメリカ帝国主義に従属的位置にあり、独立しているとは言えない。それ故独立を主張することが全面的にナンセンスではないが、所感派の民族民主革命とは日本を帝国主義と見做すことを拒否し、植民地と同じと見て反帝(帝とはアメリカ)闘争の内容は反封建闘争(農村の半封建性残存を時代錯誤的に主張)にあるとし、実質的にアメリカ帝国主義と日本資本主義との闘争を避けた点に誤りがある。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| この「国際派是、所感派否」観点は、逆の観点に立つ者からすれば空々しい。 |
| また国際派は論争を民主主義的に党内で展開し、党員と支持者のエネルギーを汲みとろうとした。だがこれに対して所感派は醜い権力主義で批判派を左遷、追放、除名し、「反党・反革命分子」と弾劾して恐怖政治を創り出した。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここも言い得言い勝ちな語りに過ぎない。私には、徳球―伊藤律指導部の方が「論争を民主主義的に党内で展開し、党員と支持者のエネルギーを汲みとろうとした」ように見える。これを否定するのなら、その後の宮顕系党中央が徳球―伊藤律指導部以上に「論争を民主主義的に党内で展開し、党員と支持者のエネルギーを汲みとろうとした」のか証明せねばなるまい。それができないのなら、もう少し精密に検証して言葉を紡ぎ出さねばなるまい。私には、徳球―伊藤律指導部の指導よりも数等倍姑息卑怯な党運営しか思い当たらない。 |
| しかも所感派は勝手に非合法態勢に入り、国際派を合法態勢に置き去りにしたまま組織的連絡を断ち、臨時中央指導部(臨中)と呼ばれる機関を設立し、専ら国際派追放の仕事を請け負わせた。彼らは本部と機関紙を掌握したため、国際派を分裂主義者、トロツキスト、チトー主義者と罵り、大半の不勉強な党員は事大主義(大に事(つか)える)、権威主義から無批判的に追随した。こうして全国の組織は分裂して行った。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 当時、所感派は、国際派を特に宮顕系をスパイ集団と認識していた。そういう意味で、「国際派を合法態勢に置き去りにしたまま組織的連絡を断ち、臨時中央指導部(臨中)と呼ばれる機関を設立し、専ら国際派追放の仕事を請け負わせた」のは止むを得ない措置であった。要は、宮顕系をスパイ集団と認識するのか同志的分派と見做すのかの違いになるが、歴史の証明する処、宮顕系は左派運動撲滅解体の為に共産党内に組織的に送り込まれたスパイ集団ではないのか。白井氏は、この論を根拠を挙げて否定しなければならない。これをしないまま、所感派に対する悪口雑言は片手落ちだろう。 |
| 国際派は臨中によって組織外に追い出されたので、統一回復のための組織として「統一委員会」を組織し、自分たちこそがコミンフォルム批判の真髄を理解し実践しているから、必ず国際派を日本共産党の主流として国際的に認知されるに違いないと信じていた。自分たちは分派ではない、先に分裂したのは所感派の方だと主張し、分派と呼ばれることに極端に恐怖していた。だから綱領を創るのは分派になるからと、統一のための連絡だけだとしていた。分派と呼ばれようが、何と言われようが正しい綱領を創って革命運動を闘おうと主張したのは、野田弥三郎の共産主義者団とかの福本イズムの福本和夫派、の統一協議会の二つのグループだけだった。ちなみに私の母校法政大の国際派は福本派だった。 |
50年6月にはスターリンと金日成による朝鮮戦争が始まり、情勢は緊張した。そして国際派の願望に反為して51年には所感派が正しいとする判定が下され、「党の無謬性、唯一前衛党主義」信仰のため、国際派の人々はムリやりに自己批判させられた。それは悲惨な精神的屈服であった。何千何万人もの党員は、イヤになって戦列から離脱していつた。分裂直前には15万人の党員がいたというが、六全協当時はアカハタは3000部であった。私の六全協までイヤな数年間であった。宮本らは実権のない本部勤務員として冷遇された。武井昭夫や新日文の少数の文学者だけが自己批判を拒否し、信念を貫いた。
この51年綱領(新綱領と呼ばれた)は短文にしてお粗末の限りで、私は一読して怒りよりも呆れてしまった。当時の綱領論争は30年代資本主義論争の再版の側面があり、最も高い水準に到達したのは、戦後農地改革が半封建的寄生地主制を解体したのか残存したのか、の論争であつた。何故この論点が重大な論争になったのか。それは、当時のマルクス主義のレベルでは、まだ帝国主義論に基づいてプロレタリア革命だけが資本主義以前の生産関係の搾取をも止揚するというトロツキー理論ないしレーニン「四月テーゼ」理論がなかった為に、半封建性が基本的に残存していればブルジョア民主主義革命、消滅して居れば社会主義革命という基本戦略に関わる問題だったからである。もう一つの論争点は、日本のアメリカ帝国主義に対する従属の評価であったが、この領域では当時はまだ帝国主義論の研究が不足していたため、高いレベルには達しなかった。
農業経済学の領域では、国際派の栗原百寿の著作など、現在でも学ぶに値する高い学問的達成が見られたのに何一つ言及することもなく、ただお題目の如き文が並べられ、「反封建闘争は反帝闘争の柱」とされ、民族民主革命戦略が押し付けられていた。これは紛れもなく、反知性主義とアンチ・マルクス主義を党員に強制するものだった。「袴田を国際派代表として北京に派遣したのに、一緒に船に乗った徳田球一が恫喝して屈服させた」などというウワサが広がって、国際派はみんな切歯扼腕していた。
それから30年近く経って78年に袴田里見は、51年のスターリン判定の真相を暴露した(「私の戦後史」)。モスクワで会議が行われ、スターリン、モロトフ、ベリヤ、マレンコフと中国共産党幹部一人の列席の下に、徳田、野坂、西沢の所感派、国際派の袴田が呼び出されて、51年綱領を基準に50年分裂を解決し、統一回復が決定され、スターリンが有無を言わせぬやり方で袴田に自己批判を強制し、統一せよと強要したという。万一逆らえば粛清されただろう。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| この件りも度し難い親宮顕、反徳球のスタンスが見える。 |
ここで我々が注目すべきことは、世界の共産党で組織問題が深刻化したときには、必ずスターリンが、そしてスターリン死後もモスクワが直接に介入する事実である。この介入を止めたのは、漸くゴルバチョフ時代である。56年ハンガリア革命への弾圧も68年チェコに対する弾圧も、全て「社会主義を守るためのモスクワ独裁指導」のなせる業である。
国際派は大衆運動では、特に全学連の闘いに見られるように所感派を圧倒していたにも拘わらず、モスクワの判決に従う国際権威主義で屈服させられた。もう一つ重大なことは、社会主義革命戦略を採ろうとした分派が、必ずモスクワから弾圧される事実である。どちらの革命論が正しいのか理論的に判断されるのでは決してなく、無条件に社会主義革命派は弾圧されるのだ。ソ連は帝国主義転覆してもらっては困る反革命である。
しかしスターリン裁定の後も、あまりに理不尽な分裂の解決に到底納得できない人々は沢山いた。特に学生運動の50年レッド・パージ反対闘争の勝利を完全に否定する所感派指導に批判と怒りを持つ反戦学生同盟(通称AG。フランス語で戦争反対の意味)は、「自分たちは大衆団体であり、50年闘争の戦闘的伝統を継承する目的で運動していく。共産主義者の統一は正しいが、AGは反戦を目標とした大衆団体であるから独自の団体を維持しても分派できない」と今から考えると「苦しい」論理だが、必死で運動の継承性を守ろうとした。
だが所感派によって52年3月初め全学連中央委員会で武井昭夫委員長が理不尽に追放され、学生運動は混迷に突入する。丁度その日に、守田典彦先輩がその会議に出席し、私が高校を卒業して受験のために上京し久しぶりに再会した。先輩とは49年に九大第二分校を訪れて面識を得ていた。彼は全国に先駆けて九大でAGを組織した創始者である。当夜再会した先輩は、激しい怒りを抑えられぬ面持ちであった記憶が鮮明である。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「だが所感派によって52年3月初め全学連中央委員会で武井昭夫委員長が理不尽に追放され、学生運動は混迷に突入する」も、公正を欠いた書き方である。当時の学生運動の低迷は、所感派、国際派、学生運動指導部のそれぞれ、特に武井派が宮顕派に取り込まれた変節に責任を求めるべきだろう。あるいは朝鮮動乱と言う現実の厳しさそのものの中に原因を求めるべきだろう。 |
|
さらに52年夏立命館大学で開催された全学連大会で、所感派の全学連指導部はAG出身の代議員11人に二日二晩のテロとリンチを加え、「帝国主義のスパイであることを自白せよ」と強要した。ここに所感派の理不尽、無思想、基本的人権無視の粛清を良しとするスターリン主義が白日のもとに照らし出されたのである。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| この時の査問の原因と様子、経緯については情報が閉塞させられている。私的には、所感派が国際派学生代議員の11名に査問したのには相当の理由と根拠があったと思っている。もしこれが冤罪だと云うのなら、事件の当事者は積極的に語るべきである。史実は、事件そのものが隠蔽させられている。査問された側によほど不都合な事があり、この事件を表沙汰にしたくない事情があると推理すべきだろう。 |
リンチを受けた中に廣松渉君がいて、その悲惨な経験を私は半年後に聞いて血が逆流する想いであった。私は早熟な彼の影響で福岡県柳川市・旧制中学伝習館で1947年に社研に加入し、高校2年時に共産党に入党して、50年分裂をじかに経験した。50年分裂の際、当初理解が困難であった綱領論争に必死で食らいつきマルクス主義の勉強をしたこと、共産主義者の組織と雖も無謬性を持たないと知りえたことは人生の大いなる糧であり、私の「マルクス主義の学校」であった。
私も国際派に属していたが、51年新綱領なる無理論で人を愚弄した立場で所感派に屈服を強いられたことは、ハイティーンに過ぎない私の精神に癒し難い傷を残した。53年春に廣松渉君からリンチの事を聞いて、私は改めてAG再建に努力することを決意した。54年から京都でボチボチ連絡活動を開始し、55年に法政大学に入学して以来、富田善朗氏(山中明/氏、所感派弾圧をものともせず、AG再建のため52年6月に委員長に就任して伝統を守り抜いた先輩)の指導を得てさらに活動を数は強めた。
当時は法政大では公開活動は共産党の弾圧で不可能であり、中央大だけでAG支部は公然活動を展開していた。何の前触れもない六全協は意外であったが、AGの復権と公開的活動の全面化を心から歓迎し、教養部で一挙に20名の支部を建設した。当時の法政大では共産党細胞は百名もいたが、半分は居眠りであった。この人々を除籍しようとすると、「一票投じるだけで良いから党員の数は多い方が良い」と必ず地区委員会が反対した。大衆運動の先頭に立つと云う考え方が、所感派にはなかった。 |
| 六全協とマルクス主義ルネサンス。ハンガリア革命の衝撃 |
50年分裂がスターリン直々の裁定によって決定され、国際派の多くはその理不尽に絶望して戦列を去り、所感派に屈服した人々はただ唯一前衛党主義を信じて服従し運動の瑞々しいセンスを失っていった事実についての無理解は赦されない。この認識を反スターリン主義運動指導部の共通認識とせずして、運動が創始されたことはまことに不幸であった。革共同の幹部さえ、国際派は大衆運動で所感派と争ってオルグ力が劣っていたから敗北した、それは当然の結果だと考える人もいた。革共同創立後の新左翼のようにお互いに公然と政治的な目標を主張して党派闘争を正面から争う、これが可能になったのはまさにスターリン主義の唯一前衛党主義を新左翼が乗り越えた58年秋「左翼への転換」以来ということを、そもそも当初から理解していない。
所感派は日本を機械的に中国と同じ植民地と見做し、武装闘争、かの悪名高き火炎瓶闘争を推進したが、全く支持されず、党勢は低下の一途を辿った為に、53年スターリン死後ソ連に滞在していた袴田里美が意見を上申し、火炎瓶闘争の中止と旧国際派党員の自己批判ナシの戦列への復帰等をモスクワや野坂と協議して決定し、これが前触れなしの突然変異と私達には感じられた55年夏の六全協となって日本にもたらされた。
前衛党の無謬性をただひたすら信じていた党員は六全協決議の「党も無謬ではなかった」意味の文言に愕然とし、かなりの人が「六全協ノイローゼ」と云われる活動停止に陥った。
六全協後まもなく宮本顕治は党指導部の実権を握るが、彼は所感派を組織的基盤として権力を創り、国際派の戦略的見解を放棄、社会主義革命論を抑圧するに至る。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここの件りの「六全協後まもなく宮本顕治は党指導部の実権を握る」をこうもあっさりと記されては困る。要するに、戦前共産党を党機能的に最終的に瓦解させた宮顕派が、この時点で戦後共産党の党中央に返り咲いたことをくっきりと確認するべきで、その結果、それまでの徳球-伊藤律系の党中央よりも如何に優秀であったのかお粗末な事になったのか、私見でも良いから記すべきだろう。 |
|
六全協のもたらした所感派指導の5年間の全面否定と、引き続いて56年共産主義の総本山・ソ連共産党の20回大会でフルシチョフがスターリン批判によって大量粛清を暴露したことは、異常な興奮を全社会的に生み出し、マルクス主義ルネサンスと言えるイデオロギー状況が現出した。単に日本共産党所感派が誤りを冒しただけではなく、ソ連共産党も大変な誤りを冒し、多数の革命家の命を奪い、数千万人もの途方もない人数の無実の市民を粛清した事実を知ったことは、反革命分子として禁圧されていたトロツキーの再検討と研究の開始、ロシア革命とソ連の歴史、コミンテルン史の再検討をも大きく促した。現代思潮社がトロツキー選集の刊行を始めたことは、新鮮な感動であった。 |
イデオロギー状況の劇的な変化の中で最も印象深い事例を二つあげる。53年から刊行開始された岩波「日本資本主義講座」全十巻は、全国のマルクス主義系学者を総動員した講座だったが、所感派戦略(日本民族のアメリカへの植民地的従属論、農村の半封建的残存論、戦後改革の無意味さの強調)の低級な敷衍、解説であった為に、いっぺんに権威を喪失し、誰も顧みないゾッキ本に転落したこと。もう一つ、52年スターリン論文「ソ同盟における社会主義の経済的諸問題」が「発明」した「価値法則は商品経済の法則。資本主義の法則は剰余価値法則」という「資本論」破壊のペテンを敷衍解説したソ同盟科学アカデミア編集「経済学教科書」全四冊が大衆的学習運動でベストセラーになったにも拘わらず、これまた一挙に権威失墜していったことである。
単に日本共産党のの権威が失墜しただけではなく、クレムリンの神話の崩壊はその呪縛から自らを解放するチャンスであった。若き共産主義者はコミンテルンと日本共産党の歴史と理論の全面的再検討、従来非正統派的と見做されていた宇野経済学、主体正論の梅本哲学、対馬忠行のソ連論等々を短時日に真剣に学んでいった。中でも黒田寛一の「探求」誌はよく読まれた。津田道夫氏の「現状分析」誌も、国家論の視点からスターリン批判を深化しようとしていた。
56年ハンガリア革命は、さらに大きな衝撃を与えた。「社会主義国」で労働者・市民が武器をとって決起したのを、戦車と戦闘機で虐殺するソ連は、果たして社会主義なのか、深刻な疑問が共産党員らを捉えて離さず、良心ある党員は混迷し大混乱に陥った。本田延嘉も私もこのハンガリア革命に直面して、スターリン主義からの離反を開始した。私は当時、共産党法政大細胞責任者であり、ソ連共産党20回大会のもたらした国際共産主義運動の再検討の気運と、スターリン粛清の暴露を大いに歓迎したが、フルシチョフの「先進資本主義国では平和革命可能論」のお粗末さに到底賛成できず、呆れてしまった。細胞指導部で、この問題について率直に疑問と批判を提起したが、数人の同志は全員私に賛成した。
当時既に結成されていたトロツキスト連盟の機関紙「世界革命」が経済学部自治会宛に十部づつ毎号送られていた。私は「トロツキーに被れる者が出るとイカン」と考え、それを全て持ち帰った。だが破棄はしなかった。50年分裂の経験から対立者の見解を読んでからでなければ批判はできないと考え「そのうちに読もう」と思っていたのだ。ところが私の属していたサークル・歴史研究会の会員に黒田寛一の「弁証法研究会」に参加している人がいることを知って、「マズイ、トロツキーを批判しなきゃ」と決心し、当時刊行されていた山西英一訳「トロツキー『ロシア革命史』」を入手して読み始めた。読み進むや、今までトロツキーについて散々云われてきた膨大な誹謗、中傷は全てデマゴギーだと分かってきた。特に感銘したのは、レーニン4月―ゼによるボリシェヴィキの社会主義革命戦略への転換である。同じ個所をスターリン「ソ同盟共産党史」を熟読したはずだが、何にも理解できていなかったこと、元々理解できない書き方になっていたことがはじめて分かった。
ここまで勉強をして、私は「世界革命」編集部に手紙を出して、太田龍氏に面談を申し込んだのである。58年3月4日であった。太田氏と飯田橋の喫茶店で5時間ぐらい話し込んで、トロツキーの革命性に改めて打たれた。そして法政大細胞指導部でのフルシチョフ批判の空気を伝えて、しっかりと落ち着いて討論して行けばみんなを獲得できるとの見通しを話した。私はその場で革命的共産主義者同盟に加盟したのである。
ところがそれから後に、革共同の真髄に触れることになった。守田典彦先輩が太田氏との面談の直後にやって来て「黒田寛一に会うように」と話をした。先輩も同席して3月末に黒田に調布市の自宅で数時間話を聴いた。その際手書きの「KK(黒田寛一)とKT(栗原登一=太田龍)の対立」なる短文を見せ、太田氏のトロツキー教条主義に対して、トロツキーの反スターリン主義に踏まえつつ、マルクスに帰って革命的共産主義の思想と運動とを根源的に創造すべきだと彼は力説した。私は黒田の立場と思想に魅力を感じて、直ちに黒田の弁証法研究会・探求派に参加を決意した。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 黒田寛一との初見時に、太田龍の導きで入党していた経緯を破り捨て、黒田寛一の主宰する弁証法研究会に入会している事を変に思わず明らかにしているが、普通はそういう軽はずみは信用されない。 |
| 黒田寛一の創成期的功績 |
「探求」は黒田寛一が57年2月に発足した弁証法研究会の雑誌で、同年10月に創刊号が刊行された。58年1月に第2号刊行、「日本革命綱領の問題点」特集で守田典彦先輩が、「或る日共党員の自己省察」をペンネームで投書されている(だが黒田は、守田先輩の革共同加盟の意味を理解しなかった。後述)。九大第二分校で50年レッド・パージ反対闘争を圧倒的な大衆闘争、ストライキを闘い処分された先輩は、50年分裂で共産党からも除名された。だが九大で闘い続け、56年ハンガリア革命支持を訴え烈烈な討論の末に九大細胞の多数を獲得した先輩は、早くから「探求」に注目し、弁証法研究会・革共同に加盟した。そして私も先輩が度々上京して話しをしてくれる影響で、反スターリン主義の思想に接近した。私は「探求」2号から入手して読み始めていた。創刊号は後の連れ合いが既に入手していたので、借りて読むことになった。創刊号の黒田のハンガリア革命論は、現在でも新鮮な感激を呼び覚ます。第2号の「人間万歳」で締めくくられる論文「世界革命の基礎理論」を熟読して探求派理論を私は理解し始めた。探求派理論は、多くの先進的な学生党員の心臓に訴える思想であり、鮮やかに浸透していった。
ここで黒田寛一の反スターリン主義運動の創成に果たした役割を客観的に考えてみよう。
まず彼の歴史的功績としてハンガリア革命の意義の賞賛がある。当時のハンガリア革命の凄まじい衝撃は経験しない人には理解し難いものがあり、社会主義の権威が地に落ちた今日では想像を絶する。当時はソ連に続いて中国も社会主義になり、この二大国がまさに「東風が西風を圧倒」して全世界の社会主義化はもうすぐとの期待が支配的だった。この時にスターリン批判からハンガリア革命へとソ連の権威失墜と社会主義の理想の動揺は、多くの真摯な若い共産党員を根本的な社会主義の反省と再検討に駆り立てた。何よりも左翼的知識人がハンガリア革命については完全な沈黙を守り、一体どのように考えたら良いのか、人々は混迷した。共産党も自分の判断を全く示すことができなかった。
この情勢に「ハンガリア革命断乎支持」と黒田寛一が声を上げたのは、見事に「コロンブスの卵」の役割を果たした。「ハンガリアで労働者を虐殺するソ連は、もはやいかなる意味でも革命的な労働者国家ではあり得ない」との立場から、「スターリン主義批判の基礎」(人生社)の末尾に10.22日に追記した文言「ハンガリアの労働者階層が立ち上がったことは、20世紀の共産主義運動に於ける画期的事件として、歴史に刻み込まれるであろう」は、真実の社会主義を求めて煩悶する若い共産主義者に新鮮な感動をもって迎えられ、「探求」創刊号の黒田論文は、いっそう問題を深化し多くの人を捉えた。さらに57年5月翻訳・刊行されたハンガリア人ジャーナリスト・フェイト「民族社会主義革命・ハンガリア十年の悲劇民」を私もむさぼり読んで、ソ連の大ロシア民族主義的抑圧、基本的人権無視の粛清と恐怖政治に憤激を覚え、スターリン主義は打倒すべきだと認識するに至った。
黒田寛一の反スターリン主義創成期に果たした役割は、このハンガリア革命を労働者の革命として承認し、ソ連の反革命的堕落を痛烈に批判したことが第一である。第二にマルクス「経済学・哲学草稿」に人間主義を、マルクス主義思想と理論との根本的立場として復権したことである。従来の正統派マルクス主義が戦後のマル・エン選集の編集に見られるように「経哲草稿」をマルクス主義成立以前の未熟な思想として補巻に扱っている点を、黒田寛一は批判して人間主義こそマルクス主義の原点であることを強調したのである。
黒田の弁証法研究会に参加して、「経済学・哲学草稿」の人間主義を基礎として哲学を構築して行くべきだとする思想に初めて触れたときの新鮮な感銘を忘れることはできない。それまで哲学と言えば、ソ連式の「唯一弁証法教程」などで無味乾燥な「本質と現象・形式と内容」等々の干からびた字句解釈しか知らなかった私には、多大の感銘であった。だが黒田の功績はこの二点のみに限られ、同時に重大な誤謬をも持ち込んだ(後述)。
私が革共同として活動を開始したのは、AGが58年5月末の大会で社会主義学生同盟に転換した時である。57年頃からAGでは東京での大会や全国委員会での討論のたびに、自治会代表者の会議である全学連の会議とは違って、革命論議を真摯に行い若い共産主義者が育っていた。これは黒田寛一創刊に関わる「探求」のイデオロギー的影響に他ならない。「スターリン主義的平和共存のための平和擁護闘争」ではなく、「世界革命戦略に基づいた帝国主義に反対する反戦闘争」という論議が、社学同への転換の意義であった。黒田寛一は「探求」第2号(58年1月刊行)に「反戦学生同盟の諸君へ」を執筆し、帝国主義の戦争政策に反対する反戦闘争の先頭に立つことこそ、AGの本来の任務だと訴えた。その影響は大きいものがあった。
58年春の大会では、ほとんどの参加者が社学同への転換には賛成だが、執行部(中村光男委員長、鈴木啓一書記長、鈴木は後に革マル派・森茂)は、なおも「世界革命と平和共存が平和共存」的な意識であった。まさにその点を衝いて、スターリン主義の平和共存戦略がプロレタリア世界革命の裏切りであると説き明かし、反スターリン主義の立場から世界革命の意義を論じて批判したのが、私の大会での発言であった。守田典彦先輩も大会を傍聴していた。この私の発言が執行部によって受け容れられて初めて社学同への転換が実質的意味のある内容になったのである。ここから勤評反対闘争、警職法反対闘争を闘って全学連は転換していく。
この直後に全学連大会が開かれて、のち構造改革派的立場に立つ右派と主流派との激突が起り、さらに衝突解決のための党員グループ会議が6.1日に共産党本部で開催されて、党中央委員会と全学連指導部党員との全面衝突が6.1事件となって勃発する。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここの件をかようにサラリと記述するのはイケナイ。「党中央委員会と全学連指導部党員との全面衝突が6.1事件となって勃発」背後にあった、六全協以降の宮顕系日共党中央の反動性に対する厳しい弾劾に触れるのが筋である。全学連指導部はそれまでの戦後直後を指導した徳球系日共党中央を「左から」批判し続けて来た。その際の理論的イデオローグが宮顕であった。その宮顕が六全協で党中央を簒奪するや、徳球系日共党中央よりもはるかに「右」にシフトし、今日の日共に繋がる路線を敷くことになった。この現実に対する、全学連指導部内で喧々諤々の討議が必要であった。6.1事件前にも事件後でも必要であった。これを為し得なかった事情を解析するのが筋であろう。 |
6.1事件は、共産党中央・宮本顕治指導部と対立を続けて来た東大細胞と全学連指導部の「別党コース」を促進するに至る。既に東大細胞では六全協後の全学連再建とマルクス主義ルネサンスのもとで、指導的党員はトロツキーを貪り読み、コミンテルンと日本共産党の歴史の根本的再検討に入っていた。その中で、島成郎、生田浩二、佐伯秀光の三人が57年12月にスターリン主義では絶対禁物の分派を結成(注記)して、共産党第7回大会へ準備を進めつつあった。
島氏の文言を引用すると、「当時ブントの理論は、宇野経済学と黒田寛一の哲学、トロツキーの革命論などからの剽窃、継ぎ接ぎだと云われたが、剽窃大いに結構、良いと思われたものは片端から取り込んで同化吸収してしまえ、そんな貪欲さと謙虚さをずつと持ち続けていきたい」(島「ブント私史」の「戦後史の証言・ブント」46P)というものであった。綱領作成と思想統一は、残された大きな課題であった。 |
| (注記) |
この分派結成に向う東大細胞の動きがあった為に、廣松渉君が黒田寛一・弁証法研究会に出席して、「これはトロツキスト組織創成に向う動きだ」と感じ取り、東大細胞指導部に逐一「密告」したのを、逆に東大細胞指導部が黒田寛一に通報してしまうことが起きた。新進気鋭の哲学者(卵)・廣松渉君ともあろう人が、一体何故そんなはしたない「密告」のマネに及んだのか。しかも彼は既にアカデミズム沈潜の為、東大細胞に脱党届けを提出していたのに。それは彼が国際派のAGリンチ事件まで経験したのに、脱党後も、なお唯一前衛党主義のクレムリンの神話から脱却できず、反スターリン主義へと時代が滔々と流れていることに時代錯誤でいたからだ。
黒田寛一は私が最初に会った58年3月にこのことで廣松渉君を弾劾していた。そして革マル派は、彼が東大闘争に共鳴して名大を辞任して上京した70年5月にテロを加えた。昨年3月刊行「哲学者廣松渉の告白的回想録」で、このテロをブントの或る分派だと本人が語っている(195P)が、それは間違いである。ブントの誰に聞いても、当時彼をテロして利益を得る分派は一つもないし、ブントは黒ヘルで襲撃する卑怯なマネはしないと言明している。廣松渉君はよく誤解されるが、ブント創成に絶対反対であった。守田先輩と私とが58年秋に彼を訪問したとき、「別党はモラルに反する」と激論になった記憶が鮮明である。その際、「欧米ではともかく、日本では別の党なんて不可能」と廣松君は怒って断言したが、60年とその後の現実を見て「可能」と分かったと見え、66年頃第二次ブントにやっと同調した。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「クロカン指令による廣松渉リンチテロ事件」は歴史秘話である。本稿が初見かどうか知らないが値打ちのある情報公開である。 |
56年八中央委・九大会以来、所感派によって5年間も抑圧され、鬱積していた学生大衆のエネルギーは適切な指導を得て大爆発し、56年砂川基地闘争の勝利、原水爆実験反対闘争を経て大きく結集し、闘いを抑圧する右翼的な宮本中央との対立が深刻化して行った。多くの学生細胞は、国際共産主義運動の根本的再検討に進みつつあった。島氏の言う通り、ここで大きな影響力を発揮したのは「探求」理論であったことは間違いない。
反スターリン主義の綱領理論として、先ず確認されたのは次の点である。スターリン主義の一国社会主義論と平和共存に反対してプロレタリア世界革命を堂々と主張した点。二段階革命論に反対して社会主義革命論を主張した点。平和革命論に反対して暴力革命論を主張した点、この三点である。その前提としてハンガリア革命の弾圧を批判して、「ソ連=社会主義国」を否定し、長年にわたる国際権威主義から脱却し始めたのである。
しかし全学連指導部の中では、立命館大の星宮*生氏が当時の革共同関西派(第四インター派)の西氏の指導で、「反帝国主義・労働者国家無条件擁護」のトロツキー理論(ソ連は堕落したとはいえなおも労働者国家)の立場を採り、全学連中央執行部の人達に大きな影響を与えていた。星宮氏はアジテーターで人気のある活動家であり、オルグ能力も優れていた。それ故全学連指導部の中での革共同と言えば、残念ながら彼のヘゲモニーのもとにあるトロツキー教条主義者を意味していた。前記の本で島氏は、関西派のこの立場をスターリン主義と同じだと批判している。明らかに関西派はブントよりも右翼であった。 |
| 黒田スパイ問題と探求派の停滞 |
では探求派はどうしていたのか。ここでどうしても、黒田寛一スパイ事件という新左翼創成期にまつわる忌まわしい歴史を抉り出す必要がある。
6.1事件の約2か月後、58年7.27日に革共同のいわゆる第一次分裂が起きた。全国代表者会議で革共同を正式に「第四インター日本支部」にすべしと太田氏が主張したが、「時期尚早、トロツキー教条主義反対、創造的マルクス主義の立場を」との探求派の主張によって否決されたため、太田氏が「トロツキスト同志会」を名乗って一人で分裂したのである。
ところが、驚いたことに、黒田の最も忠実な弟子だった遠山(共産党中央大細胞員)が暫くのちに太田氏に賛成して、探求派から鞍替えしてしまったのである。それ自体は大した問題ではなかったのだが、ここで後々まで影響を及ぼす大事件が勃発した。遠山は、黒田寛一が主宰する弁証法研究会の最も初期の参加者である大川治郎(小泉恒彦)という共産党員・民青埼玉県委員のメンバーと共謀して警視庁に共産党の情報をスパイとして売り渡した事実を、関西の指導部たる西京司に暴露したのである。
ここで、この時期までに探求派に結集していたメンバーをあげておく。本田延嘉、広田広(芸大出身、故人)、白井、守田典彦、北村(埼玉大)の数人であった。これより早く黒田寛一の門を叩いたのが大川、野村文教(印刷労働者)、鷲見(法政大)、遠山の四人であった。遠山が黒田スパイ事件を知っていたことは、私達(守田先輩や本多、私などの共産党活動の経験者)が参加する以前には、黒田のスパイ事件との関りが批判もされずに、遠山は平気であった証左である。それほど初期の黒田周辺は、革命運動の厳しさとは無縁であったのだ。
西氏(共産党京都府委員、学生運動担当で星宮氏を獲得)は、当然にもビックリして黒田に問い合わせたが、否定。ここから探求派の苦難の時期が開始される。最大の問題は、黒田の事件との関りを知った本田が、消耗して直ぐに戦線逃亡して9月から12.10日のブント創立大会まで黒田を除いた探求派は。意思統一さえ不可能になってしまったことである。
一体何たることか。学生共産主義者の最も積極的なグループが大きく動いて新しい組織を創成する決定的な瞬間、反スターリン主義が広く数百名もの活動家を捉え大きく第一歩を踏み出そうとする歴史的瞬間に、思想的に先駆者であるはずの探求派同志の間でこんな低劣な問題が突然勃発し、逃亡者さえ出ると云うのは。これが探求派の歴史の真実である。探求派が意思統一もできないありさまだったため、全学連指導部の活動家の中では「革共同といえば関西派」(太田氏ほど硬直的でないがトロツキー教条主義)と見られ、残念ながらそれは事実だった。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここの件の記述が本稿の白眉である。本稿は、この「クロカン-大川の公安内通事件」を堂々と公開したところに値打ちがある。 |
ここで大川スパイ事件のあらましについて述べる。
1957年後半、大川(小泉)は、民青中央委員・常任活動家であつたが、警視庁公安部の執拗な追及を受け、情報提供を迫られ、生活に窮し精神的に動揺していた(彼は57年1月に黒田を訪れ、弁証法兼きゅょう会に参加)。大川は悩んだ挙句、黒田に相談したところ、何と黒田は即座に「そんなら民青の情報でも売って金にしたらどうだ」と返答した。二人は「対立するスターリン主義組織の情報を売っても、トロツキスト運動には何らの打撃も与えない」という点で一致した。ここに黒田・革マル派の「対立する党派を打倒する為には警察と手を組むことは積極的に意味がある」とするフハイした本質が見事に露呈している。 |
| (注記) |
| 69年に中核派が破防法適用を受けたときに、革マル派は「権力が中核派の首根っ子を押えている時に、急所を蹴り上げる」と称して内ゲバを合理化したが、その思想は創成期からあったのだ。 |
大川が警視庁当局と一旦約束を取り付け、新宿駅付近で公衆電話をかけた。その際に黒田と黒田夫人が同行したのだ。大川が所定の係に電話したが、長く待たされたため、逆探知で所在地を急襲されて連行されるのではないかと、不安に駆られて電話を切って、あわてて三人は逃げ出した。だが後に大川だけが電話を掛け直し、係と恒常的関係を結んだ。民青中央の政策や決定事項の情報を売り、また警視庁が他の労働運動、平和運動、共産党の資料を示して判断させていったところ、非常によく的中するので、優れた情報提供者の評価を得て大川は58年前半までスパイを続けた。黒田は大川から報告を受けて容認していた。しかし大川は精神的に消耗して、59年には逃亡するに至る。
事実関係は以上である。この問題の政治的特徴は、第一に黒田寛一と大川は完全に「共謀共同正犯」であること、あろうことか黒田は実行行為に参加しようとさえしたこと、第二に大川は黒田の承認を得て初めてスパイを働いたこと。元々スパイであった大川が黒田を巻き込んだのでは決してないということ。第三に数カ月に及ぶ許し難い階級的犯罪であること、第四に対立する党派を打倒する為には警察・権力と協力することは積極的にやって良い、と黒田寛一がそもそもスターリン主義運動草創期から一貫して考えていたこと、この四点である。このスパイ事件は、黒田寛一・革マル派の本質を、組織草創期の原形質において明示したのである。
反スターリン主義イデオロギーの創始者たる黒田が、こんなにも汚辱に満ちた反階級的行為に手を汚していた事実が暴露され、探求派は意思統一が不可能になるような形で本多延嘉は戦線逃亡してしまうとは、一体何ごとか。私はどんなに努力しても、本多とは連絡不可能であり、彼は連絡を断ち音信不通であった。こうして6.1事件から年末の12.10日ブント結成大会まで、探求派はこの滔々たる歴史的潮流に対して個々人で対処する以外に打つ手を持たなかったのである。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
白井氏の事件考はまだ甘い。「クロカン-大川の公安内通事件」をクロカン-大川の「共謀共同正犯」として捉えようとしているが、真相は、クロカン-公安筋がお膳立てしての大川スパイ抱き込み事件であったのではないのか。
何と、「大川のスパイ抱き込み」は未遂で終ったのではなく、「大川は58年前半までスパイを続けた。黒田は大川から報告を受けて容認していた。しかし大川は精神的に消耗して、59年には逃亡するに至る」という新たな歴史証言をしている。本稿はこの証言をすることで貴重なものになっている。
付言しておけば、構図が宮顕の戦前査問事件のそれと似ていることに気づく。巷間情報では、小畑査問の言い出しっぺは秋笹だとしているが、お膳立てされており、秋笹が言い出しっぺのようにされているのと同様である。こういうところは文書の字面だけでは分からない、却って誘導されるので、真相に向かう為には安易になぞってはいけない。 |
| 1958年12.10日ブント創立。59.8.30日革共同・全国委員会創立。 |
ここで重要なことは上記の大川スパイ事件の内容を我々が知り得たのは、実はずっと遅れて61年末から62年初めになってからということである。58年当時は関西指導部から問い合わせてきただけで、探求派に対して黒田は全面否定したため、何一つ正確な認識を持つことができない有り様であった。それはどういう意味を持つのか。関西派は遠山から得た情報で詳しい事実を知っている。だが肝心の探求派は「何かあったらしい。黒田も関与しているようだ」という推測だけで、事実を知ることができず、これでは関西派と闘うことは到底不可能であった。この圧倒的なハンディキャップのもとでは、反帝・反スターリン主義の立場での優位性を貫徹しようにも、「スパイ問題を不問に付すのか」という関西派の非難に勝つことができなかった。
その為に新たに革共同に加盟して来た全学連幹部の塩川氏、鬼塚氏等が、最初は星宮氏の工作で加盟したとはいえ、探求理論に興味と関心を持って私達に接近しつつあったのに、十全に討論する余裕もないまま翌59年の革共同大会を迎えて、探求派は敗北し元々の6名だけで退場する結果を生むこととなったのである。これが革命的共産主義者同盟・全国委員会の59年8月誕生の真実の背景である。
ブント創立よりも革共同・全国委員会創立が9カ月も遅れたことは、革共同が本来先駆者であったはずなのに、スパイ問題で革共同がブント創成に向う滔々たる全学連フラクの潮流の中で、思想的討論を活発に組織できなかったことが災いした為である。また革共同内部ではトロツキー教条主義との論争に於いて、スパイ問題に階級的なケジメをつけられぬ探求派が、綱領論争それ自体では優位に立ったとしても(ハンガリア革命の後でソ連はなおも労働者国家だと云うのは説得力がなさすぎた)、階級闘争の規律無視と責め立てられ、多数獲得に失敗したため全国委員会創立に至ったのである。大会を通して一言も発しなかった塩川、鬼塚両氏の顔が記憶に残る。
全国委員会創立に参加した革共同大会代議員は次の6名である。本多延嘉(75年3.14死去)、小野田猛史(北川昇。東工大。大会で探求派に参加。2006年死去)、広川広(芸大。68年離脱。その後死去)、野村文教(印刷労働者。61年離脱。日本共産党にとどまる)、北村文彦(埼玉大・60年代半ばに離脱)と白井。黒田寛一はスパイ問題で代議員権を剥奪。この7名で全国委員会は発足した。7名のうち現在生存しているのは私だけで、歴史を記録する責任を痛感する。私は本多延嘉の75年敗北死に至る中核派の組織論の重大な誤謬を反省し、ここに一切の虚飾を捨てて社会主義運動の再建のために真実を記録することを決断し実行するものである。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| この件も本稿の貴重証言である。 |
本多延嘉の逃亡と連絡切断、私を初め他の探求派のメンバーのスパイ問題に対する認識不可能とブント創成への統一した方針決定不可能の事態こそ、ブント創成に対して、その情熱の渦巻く中に反帝・反スターリン主義の討論を持ち込むことをなし得ずにブント創立の12.10日創立を迎えた真実の理由である。私は孤立して活動せざるを得なかったが、共産党法政大細胞では右翼的中央に反対する多数派を獲得し、さらにその積極的メンバーを革共同に加盟させた。本多が積極的に早稲田で活動していれば、細胞の多数派になる可能性は十分にあった。しかし58年後半の決定的瞬間に逃亡、無活動のため、細胞の多数はブント派になり、ブントという組織が創立されてから59年以降の工作では少数派に転落した。東京の学生運動の最大の拠点たる早稲田で、本多が3か月も無活動であったことの否定的影響は大きい。
数年前に創成期の或る労働者同志と文通で、この当時のことを対話していたとき、彼は「スパイと分かったら、疑わしいのなら、何故すぐに黒田寛一を除名して再出発しなかったのか」と激しく問うてきた。この批判は全く正しいと私は現在考える。どんなに不利な状況になったとしても、スパイ犯罪という階級闘争の規律を平気で破るような人間が、一寸良い事を書いたからといって、指導部にそのまま残すという考え方は間違いであった。その証拠に4年、5年後には革マル派との分裂で私たちは数年間の組織建設の半分を失うツケを払わされ、さらに67年からの激動期にはもっと過酷な敵対者として中核派の闘いを革マル派は妨害したではないか。もはや歴史が結論を出しているのである。
本多延嘉が何故逃亡してしまったのか。現在考えてハッキリ言えることは次の点である。第一に、彼は黒田を教条主義的に信奉し誰よりも精神的に激しく消耗したからである。彼の黒田教条主義について、私にはニガイ思い出がある。61年頃であったか、何かの事で彼が私を非難したついでに、「黒田が君からトロツキー「裏切られた革命」を借りたが、山村(白井)の傍線の引き方は自分とは違う。山村はクダラナイことに関心がある。勉強の仕方が間違っていると、黒田が言っとるぞ」と発言したことがあった。か私は大いに不愉快であった。どこに傍線を引くのか人それぞれの理論的関心の持ち方があるはずだ、何もかも黒田大先生に見習えと云うのか、と甚だしい怒りを覚えた。
ここに黒田寛一の歴史を無視する観念史観があると私は考える。彼は人間の行為の蓄積が歴史を創ること、その重みの認識が欠けていて、アタマで考えた観念がどんな類のことであれ、歴史的事実よりも尊いと見做す純粋の観念論者に過ぎない。「裏切られた革命」のスターリン主義の歴史的犯罪の事実に関心を持たず、スターリンやトロツキーの理念にしか関心を持たない人格だから、私とは感心の在り方が違うのは当然である。「論理的論理ではなく、歴史的論理が問題である」とするヘーゲル以下である。それを、「黒田とは傍線の引き方が違うぞ」などという本田はどうかしている。今考えて彼の組織に於ける思想統一の方法は思想警察的統制であり、スターリン主義そのものであったと痛感せざるを得ない。
第二に、彼はブント結成に至る学生運動の潮流の左翼性を自己の狭い視野とセクト主義をもってしか判断できないため、6.1事件後を決定的な時機と見做さず逃亡した。彼は50年分裂の「解決」後に入党し所感派独裁によって分裂の真相を全く知らされず、無批判的に所感派に追随していたため、六全協に対して所感派的抵抗を続け、国際派の全学連が50年以来激烈な闘争を展開した歴史、また六全協後にAGが復活して58年5月に社会主義学生同盟に転換したこと、そこで革共同の同志たる私が大きな役割を果たした事さえ無知であった。私は国際派についての彼の無理解と偏見を正そうとして何回も対話を試みたが、彼はトコトン逃げまくった。信じられないが、本多は総じて学生運動に無関心で、早稲田細胞に属しながら新聞界活動だけでAGが自治会活動家の中心を為していたことさえ分からなかった。所感派としての自己絶対化、常人の想像を絶する自己過信の人格であり、その為に最後に大失敗に至った。これが75年3.14の敗北死をその後ずっと30年間考え続けて私が到達した結論である。
この二点から彼は、平然と逃亡し決定的な時機を逸する行為に出たと思う。全学連の革共同メンバーは、59年6月には執行部から降りてブントに指導権を渡すに至り、遂に全学連指導部では革共同と言えば関西派という理解を、この時点までは広く大衆的に否定することはできなかった。元はと言えば黒田スパイ問題に原因がある。しかし黒田と決別しても革命党を建設しようと云う気概を欠いた本多と私の責任は大きい。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここの件も、本稿の貴重証言である。「彼(本多)は50年分裂の「解決」後に入党し所感派独裁によって分裂の真相を全く知らされず、無批判的に所感派に追随していたため、六全協に対して所感派的抵抗を続け」とある。これは国際派の白井氏側から見た記述であり、所感派の同志例えばブントの生田氏ならどう評するのか、恐らく評論の面貌が相当に変わるところだと思う。 |
さらにもう一つ、58年後半に探求派の守田先輩が革共同を去り、ブントに希望を見出して移行した事件があった。これも黒田の非同志的な態度が原因である。福岡市から度々上京しブント指導部の人々との交渉に当たっていた先輩と、福岡の夫人に、黒田は何の根拠もない誹謗、罵倒を書簡で行い革命家としての信義否定行為に出た。それは度し難い非常識であった。黒田は先輩が50年分裂以来一貫した闘士であり、ハンガリア革命に接して独自の立場からスターリン主義批判の闘いを開始し九大細胞の多数を獲得した。その重さを全然理解せず、ただ自分の理論の信奉者が一人増えたとしか考えていなかった。
当時私は先輩と親しく接していて、黒田の行為は理不尽そのものであり、誰でもあんなことをやられたら同志としてはもちろん友人としても付き合えぬと考えた。大川や野村も先輩から話しを聴いて黒田を強く批判し、黒田は返す言葉を持たずションボリしていた。こうして守田先輩は、50年全学連の同志・島氏と共に歩む途を選択して行った。黒田はこの時の自己の態度を一切反省せず、守田先輩を裏切り者と見做し61年に復讐する。先輩は去って行く、スパイ問題に打つ手なしで、私は憂鬱になり、とにかく法政を固めることに専念した。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここの件は、重み的に見て、「クロカン指令による廣松渉リンチテロ事件」に続く歴史秘話である。本稿が初見かどうか知らないが値打ちのある情報公開である。もう少しクロカンのハレンチぶりを暴露する必要があると考える。どういう理由によってか分からないがかなり遠慮した書き方になっている。 |
この時期の総括として本多延嘉が執筆した論文「革命的共産主義運動の言段階と革命的プロレタリア党創造の課題」(「共産主義者」4号、61.9月。5号、63.1月、本多延嘉著作選第5巻掲載)に「探求派の解体的危機と全国委員会の為の闘争」の小見出しで次のように述べている。
| 「探求派政治指導部は、太田派(トロツキー絶対主義者)との分派闘争に於いて圧倒的勝利を収めたにも拘わらず、その政治路線と組織戦術を廻って深刻な内部的動揺を生み出し、その結果として組織的解体状況に陥ってしまったのである。かくして探求派は事実上、政治指導部の解体した状況のもとに、共産主義者同盟の成立に至る3か月の決定的期間を過ごし、諸分野に於ける闘争は、個々の同志の孤立した指導のもとに委ねられていたのである。/政治的指導部の事実上の責任者であり、唯一の専従でありながら(中略)遠山は太田派と野合(中略)/遠山的傾向は、その端緒的段階に於いて爆睡された。だが、こうした闘争の過程において、逆に『大衆闘争の方針なぞ必要ではない。そんなものは全学連に任せておけばいいのだ』という裏返しの誤謬が生み出されたのである。/同志青山到(守田典彦先輩)によって強力に主張されたこのような思想は、根底的批判に晒されぬままに生き残り、探求派政治指導部の立ち遅れを慰める子守唄の役割を果たしたのである。(中略)探求派を代表して全学連フラクとの政治的折衝に当たっていた同志青山は、皮肉にも全学連政治家との野合を深めつつ『個人的トラブル』を口実に我が戦列から無原則的逃亡を謀り、かくして探求派政治指導部の解体的危機を決定的なものにしたのである」(本多延嘉著作選第5巻291-293P)。 |
|
これは、まさしくスターリン的歴史偽造である。自分自身の戦線逃亡によってブント創立に至る3カ月もの決定的時機を潰した事実を、全て守田先輩に責任転嫁した恥ずべき文である。「個人的トラブルを口実に戦列から無原則的に逃亡」と先輩を非難するが、自分はその間3カ月も逃亡していたではないか。先輩は黒田の耐え難い誹謗、中傷、罵倒に対して共産主義者として「こんな人格がリーダーでは革命党はできない」と決断してブント創成の途を選択した。スパイを容認するフハイした人格が、先輩にどんな仕打ちをしたのか、3カ月も逃亡していた本多は知ろうともしなかったのが真実ではないのか。ブント創成へと向う滔々たる全国の潮流に、少数の探求派がヘゲモニーを握る力を持ち得なかったとしても、早稲田細胞で本多が本気になれば多数派になれたのに、それをサボった責任をどうするのか。活動家数の極めて多い早稲田で多数を制するなら、58年の政治状況は抜本的に変わっていたであろう。東大細胞だけではブントも自由には動けなかった。探求派とブントとの関係は、探求派早稲田細胞、法政細胞の二つの軸をもって、はるかに合理的に討論、交渉する過程を創り得たと私は考える。
本多は59年に入ってから出遅れたため早稲田で少数派に転落し、ブントに遅れを取った。それを「守田先輩がブントに加担したからだ」と言う。何をかいわんやである。私の法政ではブントは存在し得なかった(60年になってから漸く支部ができた)。私はブントのメンバーにはAGの友人が多く、いずれ合流できると確信していた。だがその東大閥がキライであったし、また組織の創り方が全学連官僚主義であり(中執が一番エニイという思想)、細胞建設が基礎だという思想を持たなかった。法政の同志はこの批判に全員同意した。(だが本多は東大型偏差値主義者の本質を67年以降の激動期に暴露した。「アタマの悪い奴は良いヤツの言うことを聞け」と平然と言う)。
本多とは、ブント創立大会の日に3ケ月ぶりに再会した(彼も私も創立大会に出席した。全学連フラクは合流反対派であり、討論するチャンスがあった)が、「卒論を書いていたんだ」と胡麻化して自分の悩みを隠す卑怯な態度に出た。その後もスパイ問題について心を開いて対話しようとはしないし、私の対話の努力にも応えなかった。
私はここに全国委員会創立後の彼の活動スタイルの原点、困難にぶつかつたときに、同志と胸襟を開いて対話して方針を選択、決定して行く方法を採らない人格を見る。自分と対等の同志は存在しないという自己過信である。3.14敗北死のハラワタを引き裂かれる失敗を反省して、彼はあの逃亡の3カ月の間に、組織を創るにあたって自己の独裁を創る。他の誰にも心を開かぬと決断したと私は考える。「政治の人間関係は支配と隷属だ。それ以外にない」と彼は或る時述懐したが、それは彼の政治哲学であり、その思想こそ敗北死の原因である。
以上で、スパイ問題に関する探求派の歴史を終える。59年4月に全学連第14回大会でブントの唐牛健太郎が委員長になり、革共同・関西派から指導部が移行して後に、60年安保闘争は大衆的に発展した。関西派は残念なことに共産党・全自連と連合した為に急速に勢力を喪失し、全国委員会派はブント全学連との同盟で力をつけて瞬く間に関西派を凌駕してたいったのである。
59年11.27の国会突入は社共指導部の制約を乗り越える可能性と力とを大衆的に示し、さらに60年1.16羽田闘争、4.26国会前チャペル・センター闘争で装甲車を乗り越え、6.4ストライキ支援闘争、そして6.15国会突入闘争へと発展を遂げていく。ブントは創立後短期間に400名を全国で組織したという(島「ブント私史」51P)。全国委員会はまだ数十名であったが、東京、関西で国労・動労の労働者を組織していたことが決定的強みであつた。それは6.4ストライキで全学連が尾久機関区に支援動員した時、当時清々しい青年活動家だった松崎明の素晴らしいアジテーション(「日本の社会主義の為に共に闘おう」)で広く認識された。
総括のポイントとして、何故ブントは素晴らしい闘争を組織しながら、安保自然承認の後に大会で分解したのか、それについての全国委員会の総括(本多延嘉編著「安保闘争」現代思潮社、60年)の現時点について、私の見解を述べることにしよう。 |
| 本多延嘉の60年ブント批判と黒田組織論 |
6.15国会突入闘争に於ける樺美智子さんの死は、30万人を越える国会デモ参加者に大きな衝撃と共感を呼んだ。社会党は臨時中央委員会を招集、全学連の闘争が正当なものであることを確認した。また国民会議は、日共を除く満場一致で支持を決定した。国会へ、国会へとデモは続いた。そして6.18自然承認の日、数えられぬ数の人々が国会を取り巻いた。この日の「闘争は、何ものも大衆を統一的に捉えていないという、混沌の中で迎えた」(本多延嘉「民主主義の危機とプロレタリア運動」の「安保闘争」176P、現代思潮社、60年)。続いて彼はブント「戦旗」を引用し、18日にも国会突入すべきであった、していれば情勢は一変して「政府危機から政治危機を生ぜしめ(中略)革命的危機への転化もまた不可能ではなかった」と主張するブントを批判する。
ブントが60年安保闘争の直接の総括大会で分解、分裂したのは、確かにここで指摘されているように、安保闘争がほとど間を置かずに革命に直結すると考えた安易さにある。私も60年5月頃に島氏に会った際に彼は、「全国委員会のような小さいヤツは相手にしない。自分は今、総評をパクることを考えている。2、3年で成功する。そしたら革命だ」と述べた。失礼で思い上がった態度とその安易さに驚いた記憶が鮮明である。彼は先の「ブント私史」でも率直に6.18当日の自分の気持ちを述べている。「6.18日夜、条約自然承認の時間が過ぎて行ったとき、側にいた生田が吐き出すように呟いた。『ブントもダメだな』との言葉は、私の中でも次第に強くなっていった」(86P)。こののち大会の総括論議に失望した島氏は、ブント再建の意欲を失い、政治生活から去って行く。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「こののち大会の総括論議に失望した島氏は、ブント再建の意欲を失い、政治生活から去って行く」結果となったが、これは島氏の潔さのもたらした政治的失態となった。直後にクロカン-本多の指導する革共同命に合流して行くことになったブント諸派を繋ぎ留め、ポスト60安保ブントとしての党の歩み迄を軌道に乗せて引退すべきであった。実際には燃え尽きていた訳ではあるが。党創設者であればここでふんばらなくっちゃ。 |
島氏のこの態度はブントの展望喪失を示しており、多くの他の人も「革命に直結しない」現実に失望して戦列から去った。法政のブントを見ても6月を過ぎるとほとんどいなくなった。この時、全国委員会は本多、北川、山村の三人の執筆による「安保闘争」を逸早く刊行して総括と展望を明らかにし、理想的優位性を現実化して行く。ベストセラーになったこの著作で本多は、6.18の情勢に対して「もし、『あの時-----であったら』と」超主観主義的に願望するのではなく、「プロレタリアートが小ブルジョア的綱領の為に闘う、この逆説を転倒するものこそ----革命的プロレタリア党の為の闘争」(162P)と主張する。この著作全体がこの主張の為に執筆されたと言ってよい。
確かにブントの60年安保闘争が革命的情勢に直結し、一貫して高揚局面が続くという立場に対して、全国委員会のこの主張はその限りで有効性を持った。しかし、「前衛党建設」の一点に絞り上げていくこの方法は視野が狭いだけではなく、前衛党という思想そのものを、私は否定するものである。前衛党だけが次の情勢を切り拓く、とする思想はセクト主義であり、究極的には前衛党指導下の軍事主義に途を開くに過ぎない。もっと重視すべきは、闘争がもたらした市民の意識改革を如何に維持し拡大して行くのか、その為に様々の市民自身のネットワークを創成、維持して行くことである。その為には、闘いの先頭に立った組織のメンバー自体の中での争いで、せっかく創られた広範な市民の意識改革を拡散することを、一番避けるべきである。「党の為の闘争」と称して、闘争主体の内部で市民に理解できぬ内部の争いを激しく展開する、これほど闘争のもたらした意識改革を拡散するマイナスはない。
この「党の為の闘争」の主張は、革共同が61年のブント戦旗派(ほとんど全部)とプロ通派(少数の指導者のみ)を吸収したとき、最大の力を発揮した。そもそもブント戦旗派が接近して来たのは、守田先輩が九大細胞の闘いを基盤として、ブントのいわゆる大衆運動主義を批判し革命党建設の路線を強烈に主張し、大きい力を得た為である。全国委員会指導部は、60年安保闘争総括の60年夏の全学連大会に出席した九大代議員約十名と討論を行い、基本的に一致を得た。このように守田先輩の努力なくしてブント戦旗派との連合の方向はあり得なかった。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここの「守田先輩のハタラキ」も、本稿の貴重証言である。 |
だが黒田は58年の自己の非同志的態度を棚に上げて守田先輩のブント移行を裏切りとして彼に復讐し、指導部から排除し本多も追随した。これはブントの破産という否定し難い状況のもとで、全国委員会の僅かの優越性を拡大して黒田独裁を創出したことがらであった。
その独裁の創出には黒田組織論の「無謬性と唯一前衛党主義」理論が役割を果たした。黒田組織論は最悪のスターリン主義組織論であり、反スターリン主義は人かけらもない。この理論こそ、革共同(中核派も革マル派も共に)をスターリン主義に先祖返りさせた最大の原因である。中核派にあっては、革マル派と激しく内ゲバまで闘いながらも、批判できない。自称6回大会で黒田哲学の批判を「完膚なきまでに遂行した」と自慢しているが、黒田哲学について執筆者本人も分かっていないことが歴然とする難解な作文だけで、組織論については批判しようともしない。この組織論こそ自滅への途である。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「その独裁の創出には黒田組織論の『無謬性と唯一前衛党主義』理論が役割を果たした」はなかなかの指摘かもしれない。 |
| 黒田を否定しレーニン主義的組織論の批判へ |
| ではその黒田組織論とは如何なるものか。「組織論序説」について見ることにしよう。最大の誤りは、党の第一の前提条件として共産主義的人間の形成を挙げていることである。第二に戦略戦術の正しさ、第三に統一戦線戦術、第四に内部理論闘争(同書226P以降)である。この共産主義的人間の形成に黒田は独特の意味を込める。即ちプロレタリア的主体性の獲得である。それが階級闘争の中での自己変革ではなく先ず独立して採りあげられ、前提とされるところに黒田組織論の最大の誤謬がある。つまり黒田寛一が哲学的に考え出した「プロレタリア的主体性」を党員が獲得したのか否か、黒田寛一が判断するという意味なのである。ここから「人間的同一性の獲得」がやかましく言われて、党の独裁者が「まだオレと人間に的同一になっていない」と恫喝する仕組みなのである。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここの件の指摘は素晴らしい。「共産主義的人間」、「プロレタリア的主体性」を言い出して識別しようとすると厄介な事になり、仕舞いには「プロレタリア的ダンス」を踊って見せねばならなくなる。若者は言葉に酔い易いのでその気にさせられるが、未だ「プロレタリア的ダンス」を見た者はないし見せつけた者もいない。 |
スパイ容認の黒田が一体何をエラソウに言うのか。愚かしいにもほどがある。人間は決して同一性など獲得できない。生まれつきの性格の異質性が先ずあり、それに個人の生きて来た歴史の形成する人格の多種多様さがある。この多様な価値観を持つ人間が、政治と社会の矛盾に人間的怒りを感じて、闘いに立ち上がる。その豊かさこそ尊いのであって、同一性を主張することは貧しさの原因、組織の枯渇、徒党への転落を意味する。精神医学で解明されているが、人間はさまざまの理由から一つの事に異なった反応をすることは昔から知られている。こんな人間についての無理解をさらけ出して、己の独裁を創り出そうとするのが黒田組織論である。それは、個性抹殺の機構として前衛党を創り出し、指導部の独裁→個人独裁を必然化して、同志の創意性と自発性とをゼロにして行くスターリン主義である。
それ故それは、「自己批判の哲学」に他ならない。三頭政治時代に1924年、ボリシェビキ党第13回大会でジノヴィエフがトロツキーに向って「党が全て正しいとここで宣言し、自己の見解を捨てよ」と強要したが、クループスカヤが「そんなことは心理的に不可能」と反対して代議員多数の拍手で否定されたのが、悪名高い「自己批判」である。この時否定されたが、のちスターリン独裁が成立するに伴い反対派を征伐する最悪の武器として自己批判が強要され、ほかならぬジノヴィエフが最も苦しめられた。それは党員の考える力を奪い、指導部に無批判的に追随することをもって優れた共産主義者と評価する、組織の創造性、自発性を抹殺する人格破壊の最悪の方法に他ならない。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| ここの件も値打ちのある情報公開である。 |
| 黒田が明言しているように彼の組織論は、レーニン主義党組織論を基礎としている。だから黒田組織論を根本的に否定する為には、レーニン主義党組織論を徹底的に批判する必要がある。この課題はここでは詳説するスペースがないので、簡潔に要点のみ指摘する。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 黒田組織論を「レーニン主義党組織論」を母体にしているとする見方を披歴しているが、或る場合には「レーニン主義党組織論」、或る場合には「スターリン主義党組織論」、或る場合には「ナチズム党組織論」という風に置き換えられるものなのだが、最も近いのは「秘密結社メ―ソン党組織論」であるだろうに、誰もここを云わずによそ事をああでもないこうでもないと推理しているように見える。 |
第一に外部注入論である。労働者階級はせいぜい労働組合主義にまでしか意識は発展しない。ブルジョア・インテリゲンチャのみが社会主義学説を創造する。労働者の自然発生性に対して目的意識性をもって階級の外部から社会主義的意識を注入することこそ、革命党の役割である。レーニンはこう主張する。だが1902年「何をなすべきか」で主張されたこの論理は、1905年、ソヴェトの労働者階級自身による創成によって、既に否定されている。ソヴェトの出現に対してボリシェヴィキ・ペトログラード市委員会は、「ソヴェトがボリシェヴィキ党に従わないなら破壊すべし」と公然と言明した。レーニンは多少柔軟ではあったが、労働者の自治機関とか戦闘組織とかの評価のみで、ただの一度も革命権力の萌芽とは評価していない。ソヴェトを権力機関の萌芽として育て上げたのは、当時中間派であったトロツキーである。ここにレーニン主義党組織論は、破綻していることが鮮明である。
また1917年全期間を通してロシア革命の最大の内容を為したのは、全国にわたる農民の自発的な領主の打倒と土地の社会化である。これによってツァーリズムは権力基盤をガタガタにされていたからこそ、ボリシェヴィキの10月クーデターがトロツキー指導で可能になったのである。レーニンの17年の文章、演説を眼を皿にして読んでも、この農民革命の素晴らしい社会変革に一言も言及していない。レーニンは例え農民革命が勝利しても、自分の党が指導していないと自然発生性でレベルが低いと侮蔑して、目的意識性の名のもとに農民革命を超主観主義的に社会主義に高めるというつもりで戦時共産主義期に圧殺し農民を虐殺した。
1918年には30の県庁所在地のうち19もメンシェヴィキとエスエル左派がソヴェトを選挙で掌握、憲法制定会議でエスエルが40%もの得票率で最大多数を獲得した。しかるにボリシェヴィキは制定会議そのものの破壊に乗り出し、「民意を無視しても指導を貫徹する。大衆は愚かだから民意に従うと社会主義にならない」とレーニン主義党組織論の外部注入論を押し通した。民意を無視しても指導せよ、ここにレーニン主義の労働者階級無視がある。中央集権制と規約第1条譲渡はむとは、それを貫徹して党指導部の独裁を実現する為のシステムに他ならない。
そもそもレーニン前衛党とは、プロレタリア独裁期だけでなく、社会主義さらに共産主義社会まで労働者、農民を指導する為に永遠に存続する権力党である。レーニンは、「国家と革命」で国家死滅の崇高な理想を説きながらも論理が破綻し、事実上国家の永遠化に陥った(志摩玲介「市民社会と労働者、市民革命」年誌第2号)。私はそれは、レーニンの頭脳では、前衛党は国家ではなく社会団体であり、社会主義社会に存在しても矛盾とは考えなかった為と理解している。
マルクス的な共産主義者の党は、前衛党とはただの一度も表現されていない。「共産主義の政党は他の労働者諸党派に対立する特別な党派ではない」(「宣言」)。その党は労働者の大衆的運動に火をともす役割を果たすが、労働者大衆によって乗り越えられる存在として考えられており(「第一インターのいわゆる分裂」1872年、全集第18巻29P)、革命の勝利の瞬間には全労働者が党を乗り越えるとエンゲルスも考えている(ザスリッチへの手紙 1885.4.23日 全集第36巻)。永遠の権力党としての前衛党という思想は、「労働者政府樹立のその日から国家死滅の努力」を開始し、国家の社会への再吸収(「フランスの内乱」)を主張するマルクス思想とは無縁である。
黒田組織論は、冒頭に述べたように50年分裂でのスターリン主義組織論の反省の欠如とレーニン主義・スターリン主義の歴史と党組織論の無知の上にのみ成立しているシロモノに過ぎない。黒田独裁を創出した「自己批判の哲学」たる黒田組織論は、ブント残党の如き中間主義者と真面目に討論なんかしておられるかという思想と態度とをブントから加盟した清水ら学生指導部の中に充満させ、61年全学連大会に於ける関西ブントなどに対する内ゲバとなった。これが事態の本質である。レーニン主義党組織論こそセクト主義の基礎である。だが61年にかかる関西ブントの排除によって発足したマルクス主義学生同盟(革共同・全国委員会の学生組織)主導下の全学連は、翌年末からの革マル派の分裂によって僅か一年半しか持たなかったのである。ここにセクト主義の運命がある。 |
 (私論.私見) (私論.私見) |
| 「黒田組織論は、ブント残党の如き中間主義者と真面目に討論なんかしておられるかという思想と態度とをブントから加盟した清水ら学生指導部の中に充満させ、61年全学連大会に於ける関西ブントなどに対する内ゲバとなった。これが事態の本質である」も貴重な内部証言である。クロカンが後から加盟した清水らに汚れ役をやらせたとの意味に取れよう。 |
革共同の61年ブント吸収のセクト主義による失敗は、三派全学連の歴史に於いても繰り返され、悲惨な解放派、ブントに対する中核派の内ゲバとなって学生運動そのものの解体をもたらす。それについては別の機会に論じるが、ここで明言できることは「革共同の組織創成は企画として失敗した。探求派の初発に於いて、61年ブント吸収に於いて明白だ」ということである。私は本多延嘉の75年3.14の無残な敗北死を30年余考え続けて来て、その原因は独善的な彼の独裁を赦した組織論にあると結論を出すに至った。
守田先輩には2001年6月に30年ぶりに再会し、余りにも長かった無沙汰を謝し、中核派の総括を創立間時点に遡(さかりぼ)って自己切開して行くことを約束した。これはその第一歩である。私はブント吸収直後に政治局から3カ月事実上排除される屈辱を受けた。本多の58年後半の逃亡への批判と、守田先輩との関係に猜疑心を抱いたらしい。私は黒田、本多独裁の結果として62年末からの革マル派分裂を赦したことを、ここに全ての事実を明るみに出すことによって明白にしたい。
冒頭に組織の原形質という事柄に言及した。黒田寛一は、ハンガリア革命の賞賛とマルクス「経済学・哲学草稿」の人間主義の復権に於いて創成期的功績を持つ。しかしその組織論は悪質なスターリン主義組織論であり、最悪の結果をもたらす原因となったのである。まさに組織論こそは組織に於ける人間関係を律する理論であり、私たちは「個の自立、自立した個の結合」を掲げてレーニン主義・スターリン主義の「共産主義者は組織の歯車」論を克服して行かねばならない。現在の新左翼諸グループの個々の分野での活動を友好的に連合しつつ総合して行くとすればその途は、この立場であり、さらに共産主義運動史、ソ連史の全面的再検討、農業問題と民族問題の理論、国家論・組織論の再建が必要である。 |
| 「資本論」に無理解な黒田寛一 |
最後に黒田寛一が「資本論」に無理解であり、スターリン主義と同一の低水準であることを批判する。それは次の点に象徴的に現れている。
宇野弘蔵は、52年スターリン「ソ同盟に於ける社会主義の経済的諸問題」に於ける「資本論」破壊に公然と批判を展開した世界でもただ一人の先駆者であった。「価値法則は商品経済の法則。資本主義の法則は剰余価値法則」という捏造を行い、ソ連スターリン主義の30年にもわたる「社会主義建設」が価値法則を止揚することに完全に失敗した事実をごまかす為に、価値法則を商品経済の法則に貶(おとし)めて、「社会主義は成功した」とデマゴギー理論をふりまいたのである。しかし宇野弘蔵は労働力の商品化を資本主義の基本的矛盾と捉えるマルクス的立場から敢然とスターリンを批判した。だが他の経済学者は全てスターリンに無批判に追随した。
注目すべきは黒田寛一も、「経済学と弁証法」論文でスターリンを支持し、「スターリンの問題意識に学べ」と言明したことである。そして昨年亡くなるまで終生彼はこのスターリン支持の立場が何故誤りなのか、理解し得なかった。つまり彼は「資本論」を、梯明秀「経済哲学」の低級な敷衍でいくつかの術語の解釈をいじくるだけで、宇野弘蔵が50年代初頭に「経済原論」、「恐慌論」を刊行し、マルクスが残念ながら未完成に終わった資本論体系を完成させた巨大な意義を理解していない。宇野弘蔵の価値形態論と価値実体論との先後関係に関する「経済原論」理解せず、スターリン主義と同じである。
黒田寛一は「資本論」は一巻だけでいい。何故ならオレも二巻、三巻は読んでいないからだ」と放言するような不勉強であった。私は58年3月に黒田に最初に会ったとき、彼の反帝・反スターリン主義とマルクス主義復権に魅力を感じて探求派に加盟した。しかし一年後くらいにこの放言を聞いて「一体何という傲慢で浅はかな人か」と愕然とした。中核派の指導部では、私だけがこの点で黒田寛一を批判した(「最前線」85号 山村論文 69年)。黒田はスターリン主義から全く脱却できなかったのである。
ソ連崩壊を真摯に全面的に捉えてマルクス主義の知的刷新を志すのか、それとも象皮感覚で過ごすのか、ここに分岐点がある。 2007年4月。 |
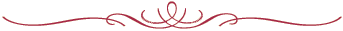
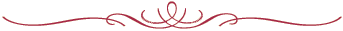
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)