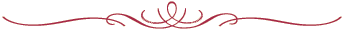
| 木下尊晤(野島三郎)追悼考 |
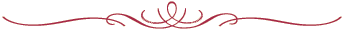
(最新見直し2011.01.24日)
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| 本サイトで中核派の同志追悼集を確認してみたい。 2011.01.24日 れんだいこ拝 |
![]()
| 【「試練」の追悼文】 | |||||||||||
ブログ「《試練》――現在史研究のために 日本の新左翼運動をどう総括するのか、今後の方向をどう定めるのか」の「革共同創設者・木下尊晤(野島三郎)氏を追悼する」
|
| 【「前進」の追悼文】 | |||||||
週刊『前進』04頁(3042号04面03)(2019/06/10)「野島三郎同志を悼む 党創成を本多延嘉同志と共にした最古参の革命家 革命的共産主義者同盟」。
|
2019.6.10日、「野島同志をしのぶ ゆかりの人々が『お別れ会』」。
|
| 【<学習講座>木下 尊晤(ペンネーム:野島三郎) 略年譜】<学習講座>※文中敬称略。葬儀当日配布の略年譜に大幅加筆。 |
| <学習講座>1936(昭和11)年12.4日、奈良県に生まれる。三男、尊晤(たかあき)と命名。 |
| <学習講座> 1949(昭和24)年、東大寺学園入学、歴史部に所属。中国古典の老子、荘子を読み始める。 |
| <学習講座> 1952(昭和27)年、県立奈良高校入学。歴史研究会に所属。古代以来の中国史、中国文学を研究。池内史郎(後に革共同に加盟。ペンネーム:浜野哲夫)と出会う。先輩の岩佐寿弥(後の前衛的ドキュメンタリー映画監督)と交友関 係を結ぶ。長兄が持っていたトロツキー著、山西英一訳「裏切られた革命」(白文社)を見せられる。 |
| <学習講座> 1954-55年、池内とともに日本共産党の最後の山村工作隊に参加。 |
| <学習講座> 1955(昭和30)年4月、法政大学文学部入学。小田切秀雄(日本近代文学研究)や廣末保(日本近世文学研究)に師事。同学年に白井朗(3歳年長)。 |
| <学習講座> 1956(昭和31)年10月、ハンガリー革命に衝撃を受け、支持を表明。 |
| <学習講座> 1957(昭和32)年12月、大阪―関西で活動していた池内と議論し、ともに革共同(西派)に加入。 |
| <学習講座> 1958(昭和33)年3月、黒田寛一主宰の「探究」グループに参加。白井から紹介されて本多延嘉(探究グループの中心、 日共早大細胞、後に革共同全国委員会書記長)と出会う。 |
| <学習講座> 同年7月、革共同第一次分裂。太田竜らと決別。 |
| <学習講座> 同年12月、共産主義者同盟(ブント)の結成に際し、島成郎(共産同書記長)が本多を機関紙「戦旗」の編集長に迎えることを提案、革共同の合流を誘う。本多が提案辞退を政治局内に提起、木下が率先して支持。共産同への合流(実質的な併呑)を拒否。この頃から組織名として「山川三郎」を使用。 |
|
|
| これは初耳だ。歴史にイフは禁物だが、<学習講座>革共同内本多派がブントに合流する線はあり得た、その方が運動体にとってずっと良かったと思う。そうすれば黒田派との余計な苦労、軋轢を背負う事もなかったのにと思う。 |
| <学習講座> 1959(昭和34)年8月、革共同第二次分裂、革共同全国委員会を結成。以降、木下は革共同労対として産別委員会の一つ、国鉄委員会(全線委員会と称す)を組織。国鉄労働者の大衆的な二つの学習会を主宰。同時に東京東部地区委員会を担当(同地区委員長)。また、スペイン内戦を中心に1930年代国際階級闘争の研究を本格化させ る。 |
| <学習講座> 同年10月、木下の盟友・池内がやや遅れて革共同全国委員会に加盟し、関西地方委員会を創立、議長に就任 (後に交代)。 |
| <学習講座>1960(昭和35)年2月、野島三郎のペンネームで『探究』に「芸術本質論序説」を発表。同論文は比較的広く知られ、高い評価を受ける。そのことに黒田がショックを受け、コンプレックスを吐露。 |
| <学習講座> 同年4、5、6月、安保反対・岸内閣打倒闘争が歴史的な大高揚。 |
| <学習講座> 同年6月、国鉄尾久機関区の松崎明らを現場指導して尾久を拠点に6.4政治ストライキ闘争を展開。ブントは、革共同の労働者フラクションによる労働者階級、とくに国鉄労働者への影響力の深さに衝撃を受ける。「国鉄に野島あり」と言われ、以後、「オルグの野島」の異名を取る。 |
| <学習講座> 同年6月、すでに兆しがあったブント瓦解が始まる。島は共産同の指導を投げ出す。戦旗派(陶山健一[岸本健一]、 守田典彦[青山到]、鈴木啓一[森茂]ら)、プロレタリア通信派(清水丈夫、青木昌彦[姫岡玲治]、北小路敏、藤 原慶久、西部邁ら)、革命の通達派(服部信司、長崎浩ら)に三分裂。 |
| <学習講座> 1961(昭和36)年1月、労対としてマルクス主義青年労働者同盟結成(議長・松崎)を指導。 |
| <学習講座> 同年2~4月 革命的戦旗派を始め、多くのブント活動家が革共同に結集・加入。そこにおいては、著作家・黒田の権威以上に、本多の構想力と高い理論性が大きな力を発揮。同時に“労働者階級に根差した党”としての革共同の底力にブント活動家が惹きつけられた要素があり、「オルグの野島」の存在も大きかった。 |
| <学習講座> 同年8月、革共同第一回大会。黒田議長、本多書記長の政治局体制。木下は正式に政治局に選出される。その後、松崎が「マル青労同議長を山川に譲る」と言い出す(ある同志の江戸川区のアジトにて)。その背景には国鉄総裁・十河信二(そごう・しんじ)による松崎への肩たたきがあった。松崎は懐柔策にぐらつき、労働者革命家の道を進むことに明らかにたじろいでいた。本多が松崎を説得、議長に慰留し、重責を分有するとして副議長に木下を据える(前同アジトにて)。 |
| <学習講座> 1962(昭和37)年9月、革共同第三回全国委員会総会(三全総)を開催。本多のイニシアティブで「戦闘的労働運動の防衛」、「地区党建設」、「統一戦線戦術の展開」、「労働者の反戦闘争・政治闘争への決起」、「『前進』の強化・拡 大」の路線・方針を決定。黒田も賛成。ところがその前段で黒田は、本多指導に対抗して、清水丈夫(学対部長)ら学生指導層による学習会フラク「Qの会」を組織。 |
| <学習講座> 同年10月下旬。黒田が三全総をもってする革共同の新たな飛躍のたたかいにひるみ、反発し、地区党の意味と意義に無理解なまま、革共同内に隠然と黒田派を結成。松崎らが参加。黒田が地区党建設に産別労働者組織を対置する論文を発表(『前進』第106号掲載)。それとは別個に、木下(山川)指導を念頭に置いた「労対指導の腐敗について」(10月30日)という私的文書を作成。三全総路線とそれをうち出した本多を面と向かって批判できないため、労対の現場指導を担う木下労対への批判を、しかも私的にやった。 |
| <学習講座> 同年11.1日、政治局会議で本多らが黒田文書の非組織的配布を弾劾、黒田が文書撤回を表明。しかし、黒田は同文書を秘密裏に配布。さらに松崎ら若干の労働者とフラク、「分裂を覚悟」と表明(11月8日)。清水が黒田に追随して、Qの会での黒田発言を文書化した「Qの会メモ」を作成し、配布。 |
| <学習講座> 同年11.14日、再度、黒田文書についての政治局会議(府中市の黒田宅)。黒田は文書撤回を表明する一方で卑劣な開き直りを示し、支離滅裂な態度に終始。本多が黒田の陰謀的分派策動を弾劾、同時に戦闘的労働運動防衛路線への無知・無理解を批判。黒田は何の返答もできず。木下が同様に清水の陰謀的な非組織的活動を批判。清水は顔面蒼白となって、「レーニン主義に反した」と自己批判。会議終了後、清水が本多の後を追い、本多派に合流。(この間、鈴木は国際部活動でヨーロッパ派遣のため不在)。 |
| <学習講座> 同年12.14日、黒田は秘密裏に分派結成を呼び掛ける。そして分派会議を開催(26日)。「分派」とは言うものの、 政治局指導拒否の実質的な別党コース=組織分裂に踏み切る。 |
| <学習講座> 同年12.25~26日、東京都学生細胞代表者会議。黒田派が清水学対部長を解任。黒田派(26人)と政治局派(13人)に完全に分裂。この過程のマル学同の会議で、清水が黒田派であった自己の反レーニン主義の誤りを自己 批判。 |
| <学習講座> 同年12.28日、政治局会議。この時点までに革共同第三次分裂となった。 |
| <学習講座> 1963(昭和38)年1.1日、政治局と関西地方委指導部の合同会議。 |
| 同年1<学習講座>~3月、本多、木下、陶山らが先頭に立って黒田批判を展開。黒田からの反論ならぬ反論。 |
| <学習講座> 同年2月、黒田、倉川(松崎)、森(鈴木)らの連名による組織分裂宣言(機関誌『共産主義者』7号を僭称・発刊)。非和解的な組織的対立が激化。マルクス主義学生同盟内の政治局派(尐数派)が「中核派」を結成。 |
| <学習講座> 同年4月、黒田らが機関紙『解放』発刊をもって「革命的マルクス主義派」を名乗る。 |
| <学習講座> 1964(昭和39)年、ベトナム・日韓闘争を指導。 |
| <学習講座> 作家・田中英光(太宰治に私淑、日本共産党員、のち離党)の全集(芳賀書店)が企画された際、依頼を受けて田中英光文学の時代背景を解説した「戦後革命の硝煙」を執筆(同全集「月報1」に掲載)。 |
| <学習講座> 1965(昭和40)年7月、 (註 1)池内が「浜野哲夫」のペンネームで社会主義労働者戦線(革共同全国委、共産同、長崎社会主義研究会)の代表として参院選に立候補。木下はさまざまな形で池内を支える。 |
| <学習講座> 同年8月、総評傘下の労働組合青年部を軸に反戦青年委員会を結成、積極的にかかわる。その後、東京反戦の世話人に就任(各派から出ていた)。この頃から、奈良県出身ということもあり政治局の西日本担当(ただし沖縄は別)となる。 |
| <学習講座> 1966(昭和41)5月、東京東部地区の労働者同志と結婚。披露宴で本多が映画『愛染かつら』の主題歌『旅の夜風』を 歌いながら曲に合わせて舞った。 |
| <学習講座> 同年9月、革共同第三回大会。木下は、大会の準備と運営の責任を取る。 |
| <学習講座> 中国の文化大革命(文革)に対して、本多とともに毛沢東批判・文革批判を展開。数本の論文を発表。 |
| <学習講座>文革批判の内容に興味あるが詳細不明なので評論不能。 |
| <学習講座> 1967(昭和42)10月、10.8佐藤首相ベトナム訪問阻止羽田闘争に東京反戦として参加。山﨑博昭(京都大 1 回生) 虐殺の報を受けて、急遽、弁天橋に合流。弁天橋上の追悼・抗議集会で、秋山勝行(全学連委員長)が木下の肩車に乗って演説。この日の闘争終了後、清水は「破防法が出るだろう。おれは潜る」と称して姿をくらます。本多が激怒、清水を呼び出し徹底的に詰問、批判。清水は顔面蒼白となって自己批判。 |
| <学習講座> 10.8直後から、関西で小川登(関西地方委政治局書記長・竹中明夫)が「プチブル急進主義反対」、「ブハーリン の電撃的攻勢論の再現に反対」を唱え、中央政治局指導を拒否して路線的反対派を形成し、関西の独立王国化を企図。竹中派が関西地方委およびマル青労同の多数を押さえる。マル学同組織はほとんどが竹中派とその路線を批判。 |
| <学習講座> 同年12月、本多の決断で木下が関西張り付き指導に入る。竹中派は「佐世保を第三の羽田に」のたたかいに反対、 『前進』配布を拒否し、党内闘争が激化。その渦中で、岡本光雄(関西地方委書記局員)、小西弘泰(マル青労同書記長)や橋本利明(京都大)ら中核派学生らとともに竹中派とたたかう。 |
| <学習講座> 1968(昭和43)1月、前年末から米原子力空母エンタープライズ入港に備えて度々佐世保現地を視察。佐世保駅前にあった共産主義労働者党の事務所をエンプラ反対闘争の連絡事務所に使わせてくれるよう、樋口篤三に掛け合う。共労党本部の許諾を得ることができ、同事務所はエンプラ闘争期間中、中核派学生及び反戦の闘争現場と本多、木下ら政治局との連絡所として使われた。 |
| <学習講座> 同年3月、竹中派が集団的に脱党、関西地方委が分裂。関西(大阪)に居を移す。ほどなく妻も大阪に着任。東京反戦世話人は藤原慶久に交代。以後、関西の労働者組織の再建に全力を挙げる。国鉄、全逓、教育労働者、自治労や民間にマル青労同組織 を建設。ほぼ2年間を要するも、1970年初めには関西地方委を再建する。 |
| <学習講座> 1969(昭和44)年、70年安保・沖縄闘争を関西の地で指導。西日本全体の決起を指導。新たな部落解放闘争と狭山差 別裁判糾弾闘争に決起した戦闘的部落青年たちを支える。 |
| <学習講座> 1970(昭和45)年7月、華僑青年闘争委員会による七・七告発をめぐって、関西での部落解放運動へのかかわりの体験から政治局内討議を積極的にリード。関西での在日朝鮮人・中国人連帯闘争、部落解放闘争、女性解放闘争、「障害者」解放闘争、在本土沖縄青年運動を原則的に、かつ思い切って発展させるべく指導を強める。 |
| <学習講座> 1971(昭和46)年 、「第2の11月決戦」を指導。 |
| <学習講座> 同年12月、カクマル派による武装襲撃、辻敏明(京都大)、正田三郎(同支社大)、武藤一郎(党三重県委員長)ら同 志の虐殺に対して対カクマル防衛戦を陣頭指揮。 全面的な非公然体制に移行。 |
| <学習講座> 1973(昭和48)年 、6月~ 沢山保太郎(全国部落青年戦闘同志会、全国部落研連合の責任者)が革共同を基盤にした 沢山天下の狭小な部落解放運動を願望し、そのために党内に「沢山党」をつくる方向を鮮明化させる。党内に 沢山フラクションを編成し、戦闘同志会や党常任など複数のメンバーに次々とテロルを振るう(8月、9月)。戦闘同志会の指導的メンバーたちが木下に沢山打倒を迫る。本多、木下ら政治局で協議。沢山打倒闘争しかないと本多が決断。 |
| <学習講座> 同年9月、沢山はフラクションメンバーとともに離党。公然と独自活動を開始。 |
| <学習講座> 同年、東京の9.21報復戦に続き、関西で対カクマル報復戦に突入。 |
| <学習講座> 同年12月、木下立案による沢山打倒のテロル作戦を発動。その直後、木下は部落解放同盟の西岡智(狭山中央闘争本部事務局長)氏を訪問。事態を納得いくまですべて説明。橋本が不必要に書き記し、作戦終了後も保管していた戦術メモが権力に奪われる。他方、沢山は権力の捜査協力を拒否、その後も黙秘を貫く。 |
| <学習講座> 1974(昭和49)年8月、本多が対カクマル戦略的総反攻を宣言。 |
| <学習講座> 1975(昭和50)年3.14日、カクマルによる本多書記長虐殺に対し、復讐戦のアピール「反革命どもに血の処刑を」を発し、革共同の同志たちを鼓舞、カクマルを震撼させる。 |
| <学習講座> 同年5月、著書「革共同の内戦論――現代の反ファシズム解放戦争」を刊行。 |
| <学習講座> 1976(昭和51)年、 「3.14宣言――革共同の新たな戦闘宣言」を執筆、発表(筆名:織田武雄)。 |
| <学習講座> 1977(昭和52)年、 「3.14アピール――勝利への怒涛の進撃」を執筆、発表(筆名:織田武雄)。 |
| <学習講座> 同年9月、編著書「現代革命と内戦」を刊行。 |
| <学習講座> 1978(昭和53)年、港合同田中機械(大和田幸治委員長)が工場占拠・自主生産をもって破産攻撃とのたたかいを開始、 これを全面的に支持、支援のたたかいを強める。 |
| <学習講座> 1982 年 1 月、三里塚二期決戦の路線を明確化させた「革共同政治局 1・1 アピール」を執筆・発表。 |
| <学習講座> 1984 年、政治局会議で財政問題を討議した席上、財政担当の白井が報告。その中で、木下の財政活動を紹介。木下がここ 10 年にわたって大学時代の友人、知識人、他党派の友人、実家から多額のカンパ(とくに親の資産からが大きかった)を集め、それらを丸ごと白井宛に上納してきた。 白井が「尐しは自分の関西指導に充てたり、個人的に使ってもいい」と言ったところ、木下は「いや、それをやる と俺の私兵を造ることになる。絶対にやってはならない。すべて中央財政に上納するのが共産主義者の原則で あり、倫理だ」と応じた。白井は木下のそうした財政的に透明な振る舞いをまるで自分がやったことかのように自慢気に報告したが、後に、木下カンパの一部を私用に蓄えていたことが発覚した。なお、白井氏は 1994 年に離党し、ほどなく本多氏を盟友といってきた態度を一変させ、自らの発言や文章で本多氏に罵詈雑言を浴びせ、 かつ木下氏の存在を抹消するなど、歪み切った姿をさらけ出した。 |
| <学習講座> 1985 年夏、 10 月三里塚決戦および 11 月国鉄分割民営化阻止決戦を前に革共同関西地方委総会を主宰。 |
| <学習講座> 1987 年 3 月、非公然体制下の男女関係問題で女性同志から告発を受ける。政治局会議で告発に関して糾問、 木下は自らの誤りを認め、全面的に自己批判。女性同志に自己批判し謝罪するも、受け入れられず。 |
| <学習講座> 10 月、政治局を解任、更迭。長期の自己批判を課せられる。 その後、脳梗塞を起こし、倒れる。非公然体制で長期の療養生活に入る。 |
| <学習講座> 1995 年、後遺症があるも、活動に復帰。「精神障害者」解放のテーマに取り組む。未発表の数本の論文を執筆。 |
| <学習講座> 1997 年~ 『清水丈夫選集』の編集に加わる。第 10 巻(97 年 7 月刊)、第 9 巻(98 年 2 月刊)、第 1 巻(98 年 10 月刊)、第 2 巻(99 年 4 月刊)、第 3 巻(99 年 9 月刊)、第 4 巻(2000 年 7 月刊)、第 5 巻(02 年 7 月刊)の各 巻末の長文の「解説」を執筆。それら「解説」は一続きの革共同党史の意味を持つ。各巻とも清水が長文の序文 を書き下ろし。ちなみに『清水選集』は第 5 巻刊行後、長期間、中断。清水執筆序文がなく、木下の「解説」もない第 6 巻をぽつんと出した(2016 年)ものの、未だに完結させることができないでいる。 |
| <学習講座>
2005 年、療養地を千葉県三里塚に移す。 11 月、住民票不実記載をこじつけられ不当逮捕、ほどなく釈放。 |
| <学習講座> 2006 年 3 月 14 日、関西地方委内で「党の革命」、実際にはテロ・リンチによるクーデター(3・14Ⅱ)が起こる。 その直前に 2 度目の脳梗塞の発作を起こし倒れる。膀胱ガンの診断も出される。そのため、3・14Ⅱに明確な態度表明する機会を得ず。 |
| <学習講座> 2014 年、三里塚を離れ、都内のアパートに移り住む。革共同を中心に日本の社会運動に関する各種資料を精力的に渉猟。以後、革共同の創成期について自らの体験を踏まえ、多くの備忘録、メモ類を作成。 |
| <学習講座> 2017 年 4 月、前立腺肥大症で都内病院に入院。腎機能障害の危険との診断。 治療を続けながら、党史再検証を進める。 |
| <学習講座> 2018 年 3 月、全身の浮腫、貧血と呼吸困難で容態が悪化、前回と同じ病院に入院。膀胱ガンおよび腎臓病、 心臓喘息と診断される。退院後も短期再入院。 病とたたかいながら執念を燃やして各種資料の読み込みと記録を続ける。 |
| <学習講座>
2019年1月、胸苦しさを訴える。腎臓病が悪化し、腎臓透析の準備のため同病院に入院。末期腎不全(ステー ジ G5)と診断される。同時に膀胱ガンの他の部位への転移が認められ、5
カ所にガンを抱える。医師は緩和治療方針を提案。 2 月初め、 腎臓透析を開始(週 3 日)。「あと 10 年生きたい。書きたいこと、語り置きたいことがある」と生への執念を語る。最後まで頭脳明晰であった。 2 月 22 日 緩和ケア棟に移る。四肢の麻痺、嚥下障害、血圧降下など日一日と重篤な状態が強まる。しかし、 見舞客を認識、反応示す。 |
| <学習講座>2 月 28 日午前 7 時 37 分、静かに眠るように逝去。享年 82。 |
| <学習講座> 註:略年譜には記述の濃淡があり、欠落も尐なくない。完成版は他日を期したい。 2019 年 3 月 4 日 代表執筆:水谷保孝 ▲野島三郎著『革共同の内戦論――現代の反ファシズム解放戦争』(1975 年 5 月刊) ▲野島三郎編著『現代革命と内戦』(1977 年 9 月刊) 註1 当初、「田中英光論を執筆」と記した箇所を修正。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)