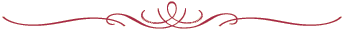
| 第3章 | 戦後学生運動2期その2 | 1951年-1953年 | 50年分裂期の学生運動 |
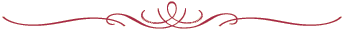
(最新見直し2008.9.10日)
これより前は、「1期、全学連結成とその発展」に記す。
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、1950年から1953年までの学生運動史論を概略する。これを仮に「戦後学生運動 2期、「50年分裂」期の学生運動概略」と命名する。詳論は「50年分裂による(日共単一系)全学連分裂期の学生運動」に記し、ここではエポックな事件を採り上げ解析する。 |
| 1951(昭和26)年 |
| 【「不破査問事件」】 |
| 2.20日、東大の国際派東大細胞内で査問・リンチ事件が発生している(これを仮に「国際派東大細胞内査問・リンチ事件」、略称「不破査問事件」と云うことにする)。この事件は、国際派の東大細胞内における指導的メンバーの一員であった戸塚秀夫、不破哲三、高沢寅男(都学連委員長)の3名が「スパイ容疑」で監禁され、以降2ヶ月間という長期の査問が続けられ、「特に戸塚、不破には酷烈、残忍なるテロが加えられた」と云われている事件である。これについては、「東大国際派内査問事件考」で別途考察する。 この事件を考察する意味は、1・これが戦後学生運動の初のリンチ事件となったということ。2・この時査問された不破らの容疑がスパイであり、その不破がその後日共の最高指導者として登場するに至ったということ。3・この時事件に介入してきた宮顕の胡散臭さが垣間見え、宮顕と不破の特殊関係を見て取ることができる、という三点で興味深い事件となっているところにある。ちなみに不破は最近「私の戦後60年」を執筆しているが、この事件に触れず口を閉ざしている。 |
|
ネット検索で「松下清雄を語る会について」に出くわした。それによると、「スパイ.リンチ査問事件の年次」で、て.「1052年2月14日」は間違いで正しくは.「1051年2月14日」であるとの指摘が為されている。れんだいこの「検証学生運動」(社会批評社、2009年)にも言及下さっている。これにより、れんだいこテキストの方も訂正しておく。これにより、「東大ポポロ座事件」と同時期のものと考えての「なぜ両事件の関わりが検証されていないが不自然なことである」と記していた下りが不要となった。判明したことは、「不自然なこと」ではなく「発生年次が丁度1年違っていた」と云うことになる。 |
| 【共産党が、四全協で武装闘争方針を提起】 |
| 2.23日、共産党が四全協を開催し武装闘争方針を提起した。これ以降,国際派と所感派の左派関係が逆転する。宮顕らが四全協の結果を見て全国統一会議を再建していくことになる。 |
| 【日本民主青年団(民青団)が発足】 |
|
5.5日、日本民主青年団(民青団)が発足している。民青団は、党主流所感派の系列で生み出されたものであり、全学連活動家のその多くが連なった。彼らは党の方針を信じ、党の軍事方針の下で工作隊となり、積極的に参加していくことになった。東京周辺の学生たちは、「栄養分析法」・「球根栽培法」等の諸本を手にしながら三多摩の山奥にもぐり込んだ。結果的にこの時期の党の武装闘争路線は破綻していくことになり、民青団も大きな犠牲を払うことになった。 |
| 【共産党が「51年綱領」を採択】 |
|
1951年、中国に渡った徳球指導部は、従来の平和革命式議会主義から一転して武装闘争路線へと転換せしめることになった。長期にわたる武装闘争によって勝利を獲得した中国共産党の経験を学び、中国革命方式による人民革命軍とその根拠地づくりを我が国に適用しようとしたものであった。 |
| 【共産党の武装闘争に対する全学連の対応】 |
| 党中央所感派が武装闘争に転換するや、それまで党中央を右翼日和見主義として批判してきていた国際派が途端に日和見始める。宮顕派は、党中央所感派が武装闘争を呼号し始めるやそれまでの「左性カムフラージュ」が剥げ落ち、右翼日和見主義し始めた。武井系全学連中央派はそれに追随した。このことが様々な軋轢を生むことになる。党の新方針によって、党中央派学生党員は急進主義化したが、逆に宮顕派の指導する全学連武井派が穏和化していくという逆転構図となった。 |
| 【国際派解体、宮顕派と全学連中央の分派対応】 |
|
8.10日、共産党.コミンフォルム機関紙「恒久平和」が4全協の「分派主義者にたいする闘争にかんする決議」を支持的に報道、続いて14日には第4回全国協議会の決議を掲載した。この結果、最左派=国際主義者団が降伏し、団結派も解散大会開催。統一協議会も解散と自己批判を余儀なくされた。統一派=春日はゴマスリ的自己批判をし、宮顕は抵抗しつつ復党したとされている。こうしてスターリンとコミンフォルムの権威によって、反徳球派の圧倒的多数の人々は徳球派に屈服することを余儀なくされた。これにより、日共党中央の全学連中執派のメンバーは非常に衝撃を受け、これを契機に再び多くの学生活動家は党中央の指導に服していくようになった。 しかし、全学連委員長武井ら20数名は国際派の首領格であった宮本顕治グループと行動を共にする道を選んだ。本来であれば、その論に忠実であれば、武井系全学連は武装闘争路線への転換を歓迎する立場であった筈であるが、今度は平和闘争への転換に逃げ込み始める。どこまでいっても顕系との一蓮托生組でしかなかったことが判明する。この両者の縁が切れるのは、1955年の六全協で宮顕系が党中央に登壇しその右翼的本質を満展開することによってである。それ故に今暫くは蜜月振りを見せられることになる。 |
| 【サンフランシスコ平和条約、日米安保条約が締結】 |
| 9.8日、サンフランシスコ平和条約、日米安保条約が締結された。 |
| 【全学連執行部内の所感派と国際派の指導権争い】 | |
|
51年秋から、党中央は、トロツキスト追放キャンペーンの激しさをました。51年の暮れから52年を迎える頃には、全学連内の対立は国際派から所感派へ優位が移行していった。安東氏は次のように証言している。
10.6日、都学連において国際派執行部が辞任させられ、反対派に指導権を渡した。しかし、この時点では、全学連中執は国際派が掌握していた。10月頃より、武井派が排斥され始め、武装闘争に向う徳球系党中央派の学生党員が指導権を握っていった。 |
|
【反戦学生同盟(反戦学同)の結成】 |
|
12.15日、武井派の音頭で反戦学生同盟全国準備委員会総会が開催された。全国委員32名、評議員・オブザーバー30余名が出席し、民青団による反戦学生同盟の解体提案をめぐって議論を白熱させた。民青団の提案は、当時の共産党中央徳球系指導による武装闘争路線を背景にしており、1・革命的情勢に応じて学生も武装闘争に参加しなければならない、2・反戦学生同盟の存在は分裂的であり、解体させ民青団に合同させねばならない等々と主張していた。当時の学生運動の危機的な分裂状態を背景にしていたことになる。採決の結果、賛成4、反対18、保留2の多数決で否決した。これにより、反戦学生同盟(反戦学同)が結成されることになった。 |
| 1952(昭和27)年 |
| 【東大でポポロ座事件発生】 |
|
2.20日、東大でポポロ座事件が発生した。劇団「ポポロ座」の演劇発表会に警視庁本富士警察署の私服警官数名が潜入していることが判明、事件となった。多数の学生が取り囲み一部暴力もふるわれ、警察手帳を奪った。押収した警察手帳には学生・教職員・学内団体の思想動向と活動に対する内偵の内容が記されていた。手帳押収に際して暴行があったとして学生が起訴された。 |
| 【東大農学部拡大中執で、所感派による国際派追放大会】 |
| 3.3日、全学連の拡大中執が東大農学部で開かれ、所感派による国際派追放大会が開催された。高沢、家坂、力石らの「君子豹変」。土本、安東、柴山、二瓶、下村らが〃国民の敵〃として非難、追放され、新しい中執が選出された。これにより、1948年の全学連結成以来日本学生運動の反帝・平和の伝統を担ってきた武井指導部は辞任することとなった。武井派は、「学生戦線統一の観点から辞任することとなった」と、総括している。指導権を握った所感派は、中核自衛隊の編成に着手し、山村工作隊を組織した。早大、東大、お茶大らに軍事組織が結成され、火炎瓶闘争を実践していくことになる。
これについて、筆者はかく思う。この経緯を「反帝・平和の伝統を担ってきた武井指導部の引き摺り下ろし」とみなして、この時の政変を疑惑する史論が為されているが、れんだいこはそうは見ない。この頃武井指導部は宮顕論理に汚染され、既に闘う全学連運動を指揮し得なくなっていたのであり、歴史弁証法からすれば当然の経過であったと拝察したい。 |
| 【「第23回血のメーデー事件」発生】 |
|
5.1日、第23回統一メーデーが全国470カ所で約138万名を集めて行われた。東京中央メーデーは「流血メーデー」となり、「血のメーデー事件」として全世界に報道され衝撃が走った。 |
| 【「第2次早大事件」発生】 |
| 5.8日、早大で第2次早大事件が発生した。神楽坂署私服・山本昭三巡査を文学部校舎に監禁。救援の警官隊と座り込み学生1500名が10時間にわたる対峙となった。9日午前1時過ぎ、武力行使。未明、吉田嘉清ら多くの活動家たちの再結集.都下大学の学生をまじえ数千人の抗議集会。党は、「座り込み」を「消極的で敗北主義的な戦術」と批判。メーデー参加者逮捕にきた刑事を監禁、奪還にきた警察と衝突、学生に多数の負傷者がでた。
5.9日、午前1時すぎ武力行使。未明、吉田嘉清ら多くの活動家たちが再結集し、都下大学の学生をまじえ数千人の抗議集会を開いた。党は「座り込み」を「消極的で敗北主義的な戦術」と批判。メーデー参加者を逮捕にきた刑事を監禁、奪還にきた警察と衝突。学生の負傷。 |
| 【全学連第5回大会、所感派が全学連中央奪還】 |
| 6.25~27日、全学連.第5回大会が2年ぶりに開かれた。54大学の代議員197名、20大学のオブザーバーら400名が参加し、所感派が国際派から指導権を奪い取ることになった。武井ら旧中執20数名の除名追放が決議された(この除名決議は55.11月になって、誤った措置として取り消されることになる)。 大会は、「反ファッショ行動組織」の結成を訴え、結語として「国会の即時解散、吉田政府打倒、民主的日本政府樹立」を宣言した。反戦学生同盟の解散決議、「27名の国民戦線からの追放」(武井委員長、安東仁兵衛、吉田嘉清、津島薫、山中明ら旧中執系20数名の除名追放)が決議された(この除名決議は、六全協後の55.11月になって、誤った措置であったとして取り消されることになる。 大会は、新たに委員長・玉井仁(京大)、副委員長・妹尾昭(東京外大)、早川正雄(立命大)、書記長・斉藤文治(東大)らを選出した。つまり、国際派に占拠されていた全学連中執を党中央系が奪い返したことになる。こうして党内の大激震下で徳球系執行部を支持する所感派学生党員は、52年の全学連第5回大会で武井委員長ら旧執行部を追放し主導権を握った。 玉井新執行部は、党の武闘路線の呼びかけと「農村部でのゲリラ戦こそ最も重要な闘い」とした新綱領にもとづき、農村に出向く等武装闘争に突き進んでいくことになっ た。こうして戦闘的な学生達は大学を離れ、農村に移住していった。この間、国際派学生党員グループは、自己批判し武装闘争に向った者、反戦学同的運動を継承しつつ主に平和擁護闘争を取り組んだ者、自己批判を拒絶して戦線離脱した者という具合に分岐したようである。留意すべきは、どちらの動きにせよ党指導下のそれであったことであろう。 |
| 【「立命館地下室リンチ事件」】 |
| 全学連第5回大会の最中、全学連による「立命館地下室リンチ事件」が発生している。徳球系日共京都府委員会の指導する学生党員(「人民警察」)による、反戦学同員に対する3日2晩にわたるリンチ査問事件となり、被害学生は関大、立命館、名大、東京学芸大、教育大、津田塾の反戦学生同盟員ら延べ11名に及んだ。注意すべきは、この時、「宮本顕治、春日庄次郎、神山茂夫スパイ説に基くCICスパイ系図」に基く査問が行われたということである。この系図はその後幻となっているが、貴重と思う故に敢えて言及しておく。 |
| 1953(昭和28)年 |
| 【スターリン逝去】 |
|
3.5日、スターリン没。 |
| 【全学連第6回大会】 |
| 6.11日、全学連第6回大会開催。70大学140自治会の代議員165名とオブザーバー500名が参加した。この頃基地反対闘争が中心課題となっていた。委員長に阿部康時(立命館大)、副委員長・大橋伝(横浜国大)、松本登久男(東大)、書記長・斎藤文治(東大)が選出された。 大会は、基地反対闘争を中心として「反吉田反再軍備統一政府の樹立」を闘いとることを宣言し、「学生は民族解放の宣伝者になろう」が強調された。この大会決議に基づいて、大会後全学連は、進歩派教授と協力して、憲法改悪反対の講演会を開き、夏休みには一斉に「帰郷運動」で農村に入った。 |
| 【内灘闘争】 |
|
6.13日、内灘座り込み闘争開始。6.15日、早大が内灘闘争報告。6.15日、この日より金沢市郊外の内難村海岸で米軍の試射演習が開始された。これは52.11月に米軍より申し入れがあり、村民の反対にも関わらず12.2日政府は施設提供を閣議決定していたことによる。反対派住民は浜辺に小屋を建てて座り込み抵抗闘争に入った。いわゆる内難基地闘争と云われる。結局、政府は試用期間を3年以内とし、住民には補償金を出すことで収拾した。 |
| 【徳球逝去】 |
|
10.14日、共産党の徳田球一が北京で没(享年59歳)。 |
| 【伊藤律幽閉】 |
| 徳球没後、後ろ盾を失った伊藤律が幽閉されることになる。野坂が、「もう一年も中連部に厄介をかけたし、今から別のところへ移ってもらう」と宣告し、鄭所長と公安職員が律を拉致し監獄へ収容した。「これは日本共産党の委託によることで、中共としてはプロレタリア国際主義の義務なので、問題を日本共産党が解決するまで致し方ない」と因果を言い含められたと述べた、と後に伊藤自身が明らかにしている。40歳前後の伊藤律は以来27年間を幽閉され、1980.9月、奇跡的な生還を遂げることになる。 |
| 【武装闘争の失敗、宮顕の党中央登壇画策】 |
| この頃党内に台頭してきたのは徳球派系の志田派であった。志田派は徳球の片腕として君臨していた伊藤律派を駆逐しながら次第に党中央を簒奪する。その志田派の指導する武装闘争が散発的に終わり失敗する。徳球が客死し、№2の伊藤律が幽閉された後、その隙に党中央に再登壇してきたのが戦前のリンチ致死事件仲間の宮顕-袴田であり、この極悪同盟が野坂派、志田派と結託し始める。 |
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)