
�@�i�ŐV�������Q�O�P�Q�D�P�P�D�O�U���j
| �@�i������̃V���[�g���b�Z�[�W�j |
|
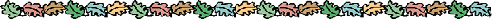
| �y�J���g�̗����z |
| �@�P�V�Q�S�N�A�����v���C�Z���̃P�[�j�q�X�x���N�i�����V�A�̃N���[�j���O���[�h�j�ɐ��܂�A�I�����n�ʼn߂������B�P�V�V�O�N�ɃP�[�j�q�X�x���N��w�����ɏA�C�B�P�V�W�P�N�A�u���������ᔻ�v�A�P�V�W�W�N�A�u���H�����ᔻ�v�A�P�V�X�O�N�A�u���f�͔ᔻ�v�ƎO�ᔻ�����o�ŁB�l�Ԃ̗����̔F���\�͂̌��E��T��A���R�ӎv�Ɋ�Â��������̍��{�ɐ������B�P�V�X�T�N�A�u�i�����a�̂��߂Ɂv���Ă��邪�A���ە��a�A�R�k�v�z�̋N���ƂȂ��Ă���B�P�W�O�S�N�v�B |
- ���̒��w���������ᔻ�x�iKritik der reinen Vernunf,
1781����/1787��2�Łj
- �u�A�E�v���I���ia priori�j�ȑ������f�v
-
- ���ځC�����̂�c���ł������B
- �J���g�́C���b�N��C�v�j�b�c��̂悤�ȁC�F�����ΏۂɈˑ���������u�͎ʁv���邾�����Ƃ����F���_�i�͎ʐ��j���C�����ł͂Ȃ��C�Ώۂ��F���Ɉˑ�����ƍl�����i�\�����j�D�ނ͂��̔������C�R�y���j�N�X�̒n�����̔����ɗႦ�āC�u�R�y���j�N�X�I�]��v�ƌ����Ă���D
- �J���g�͑Ώۂ����̂܂܂ŔF���ł���Ƃ����l������������C�����l�ԂƖ��W�ɂ��ꎩ�̂ő��݂����u�����́v�idas Ding an sich�j�͔F�����邱�Ƃ��o���Ȃ��Ƃ����D
- ��Ԃ́C�����錻�ۂ̌`���iForm�j�ɑ��Ȃ�Ȃ��C
- ��Ԃ����Ԃ��C�����̒m�o����V�I�i�A�E�v���I���j��������Ă����u�����I���ς̏����`���v�ireine Formen
sinnlicher Anschauung�j�ł���D��Ԃ⎞�Ԃ̒��Œm�o����鐢�E�́C�����܂��u���ہv�iErscheinung�j�̐��E�Ȃ̂ł���D�A�E�v���I���Ȋw��ł��邩�̂悤�Ɏv���鐔�w���C���̂悤�ȁu��ԁv�u���ԁv�Ƃ������u�������ρv���Ȃ���ΐ������Ȃ��D
- �������C�ł́C���Ԃ��Ԃɂ���Ĕc������錻�ې��E�͋q�ϓI�ł͂Ȃ��̂��C�Ƃ����ƁC�J���g�͂����ł͂Ȃ��ƌ����D
- ���Ԃ́C�����l�Ԃ̒��ς̎�ϓI�isubjektiv�j�����ɑ��Ȃ�Ȃ��D�����Ă��̎�ς�x�O������C���Ԃ͂��ꎩ�̖��inichts�j�ł���D�������Ȃ���C���Ԃ́C���悻���ۂɊւ��ẮC�K�R�I�ɋq�ϓI�iobjektiv�j�ł���
- �܂�C�J���g�͎��Ԃ��Ԃ��u�o���I�v���ݐ��iempirische Realitaet�j�͎咣���邪�C�u��ΓI�v���ݐ��͋��ۂ���D
- ���Ԃ��Ԃ́C�����܂Ō��ۂ̐��E�ɑ�����̂ł���C���̌���ł́C���ݐ��������C���ꂪ�����̂ɑ�����C�܂蒴�z�_�I�ϓ_���猩��ƁC���҂ł��Ȃ��C�܂�ϔO�����������Ȃ��C�Ƃ������Ƃł���D
- ��Ԃ��邢�͎��Ԃɂ����Ē��ς���邷�ׂĂ̂��́C�܂�C�����ɂƂ��ĉ\�I�Ȍo���̂��ׂĂ̑Ώۂ́C���ۈȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��D����������C�P�Ȃ�\�ہiVorstellung�j�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��D���̕\�ۂ͂����́q�v�z�r�ȊO�̂Ƃ���ɂ́C���ꎩ�g�Ŋ�b�Â�����悤�ȑ��݂������Ă͂��Ȃ��̂ł���D���͂��̊w�����C���z�_�I�ϔO�_�itranszendetale
Idealismus�j�Ɩ��Â���D���z�_�I�Ȏ��ݘ_�҂́C�����̊����̕ϗl�����ꎩ�̂ő��݂�����̂ɂ��Ă��܂��C������P�Ȃ�\�ۂ����ۂ��̂��̂ɂ��Ă��܂��̂ł���
- �܂�J���g�́C�u���z�_�I�ɂ͊ϔO�_�v�ł��邪�C�u�o���I�ɂ͎��ݘ_�v�Ȃ̂ł���D
- ���̂悤�ɂ��ċ�Ԃ⎞�Ԃ͌��ې��E�𐬗������邽�߂ɁC�u�Ώۂς���Ƃ���̎�ςɑ�����v�����̌`���ł������D�������J���g�ɂ��ƁC
- �o���́C����߂ĈقȂ�2�̗v�f�C�܂�C�F���́u�����v�iMaterie�j�ƁC���̎����ɒ�����^����u�`���v�iForm�C�`���j�Ƃ��܂�ł���
- �F���̍ޗ��i�����j�Ȃǂ͊����̎�e���ɂ���āC���E������D�������C���̂܂������̑f�ނɁC�`�▬����^����i�`���j�̂́C��ς̑��̎������̔\�͂Ȃ̂ł���D���̂悤�ȁC�����ɂ���Ď�����f�ނ������Ӗ��̂�����́C�����̂�����̂Ƃ��Ċ֗^����̂��C�含�̔\�́C�u�����含�T�O�v�ireine Verstandesbegriffe�j�Ȃ̂ł���D
- �������̔F���iErkenntnis�j�͐S�ӎ���2�̌��琶����D���̌���́C�\�ہiVorstellung�j������\�́i��e���|�����j�ł���C�܂����̌���́C�����̕\�ۂɂ���đΏۂ�F������\�́i�������|�含�j�ł���D���ꂾ����C���ςƊT�O�Ƃ��C�������̂��������̔F���̗v�f�ł���C���ς������Ȃ��T�O���C���邢�́C�T�O�������Ȃ����ς��C���ꂾ���ł͔F���ɂȂ蓾�Ȃ�
- �����Ă��̐�V�I���T�O���u�J�e�S���[�v�i���e�C�����含�T�O�j�ƌĂ�ŁC���̂悤�ȃJ�e�S���[�\���f���悤�Ǝ��݂��D�A���X�g�e���X�����̂悤�ȃJ�e�S���[�\���f���悤�Ǝ��݂Ă��邪�C�������ނ͂�������ʂ̈ꌴ�����瓱���o���Ȃ��ŁC�o���I�ɏE���W�߂Ă���C���������ό`���ł����āC�����Ȍ含�T�O�łȂ���Ԃ���ю��Ԃ����̂����ɓ����Ƃ�������Ƃ��Ă���ƃJ���g�͂����D
- �ł́C�J���g�̌������ʂ̈ꌴ���͂Ȃɂ��D������u���f�v�ł���D���f�̂������ނ��l�@����C�含�̍��{�T�O�͊��S�Ɍ��o�����ł��낤�D�������āC�J���g�́C�J�e�S���[�����̂悤��3����4�g�C�v12����Ƃ����D
- �@
�ʂɊւ��āiQuantitaet�j�F�P�ꐫ�iEinheit�j�C�������iVielheit�j�C�S�̐��iAllheit�j
- �A
���Ɋւ��āiQualitaet�j�F���ݐ��iRealitaet�j�C�ے萫�iNegation�j�C�������iLimitation�j
- �B
�W�Ɋւ��āiRelation�j�F���̐��iSubsistenz�j�Ƌ��L���iInhaerenz�j�C�������iKausalitaet�j�ƈˑ����iDependenz�j�C���ݐ��iGemeinschaft�j
- �C
�l���Ɋւ��āiModalitaet�j�F�\���iMoeglichkeit�j�C���ݐ��iDasein�j�C�K�R���iNotwendigkeit�j
- �����̃J�e�S���[����������ϓI�Ȃ��̂ɉ߂��Ȃ��D
���̂悤�ɁC�I�Ȓ����̔\�͂ł��銴���Ǝ����I�ȊT�O�̔\�͂ł���含�Ƃ���2�̔\�͂��������Ƃɂ���ĔF���͐�������킯�����C�����َ���2�̔\�͂�}���̂����z�_�I�\�z�́i�z���́j�ł���D
- ��P�͂Ō����悤�ɁC�f�J���g�ɂ���āC�l�ԗ����͑��̑��ݎ҂̌������݂�ۏ��邱�̐��E���o���u���z�_�I�v�����ƂȂ�D�������C����͂܂��C�����܂Ő_�I�����ɂ���Ă��̍����ۏ���Ă���̂ł���D�������C�J���g�́C���̂悤�Ȑ_�I�����̌㌩�Ȃ��ɁC�L���ł͂��邪�C���ꎩ�̂͐��E���o�Ă��Ȃ��炻�̐��E�̑��݂���b�t�����ς̓����Ƃ��Ă��u���z�_�I��ϐ��v�Ƃ��āC�l�ԗ������K�肵���̂ł���i���̂��߂ɂ̓J���g�̂����u�R�y���j�N�X�I�]��v���K�v�ł������j�D�C�M���X�o���_�ɂ����郍�b�N��o�[�N���[�́u���_�v�ispirit�j�͂܂��l�I�ȐS�I���̂ł��������C�J���g�̏ꍇ�͐�V�I�ȁi�܂�u���z�_�I�ȁj��ςȂ̂ł���C���ۂ̐��E�͋q�ϓI�Ȃ̂ł����D
- �������C���̂悤�ɁC�l�Ԃ̌含�T�O��12�����ɌŒ艻���邱�Ƃɂ́C�������甽�_���������D��Ƀw�[�Q���͂���������Ə_����C�l�Ԃ̔F���\�͂́C�ُؖ@�I�ߒ��ɂ���čی��Ȃ����債�Ă����Ƃ����D
- �i5�j �}��
- ���āC�����Ŗ��ɂȂ�̂́C���̂��Ƃł���D���Ȃ킿�C�J���g�ɂ��ƁC�Ώۂ͊�������含�ւƗ�����C�F�������D���̎��C�����ɂ��āC�����I�ȑΏۂɃJ�e�S���[��K�p����̂��C�Ƃ������Ƃł���D�����I�Ώۂւ̌含�̓K�p�́C���ړI�ɂł͂Ȃ��C���̗��҂̊Ԃɂ́C���҂̐��������킹�����Ă�����́C���Ȃ킿�C����ŏ����Ő�V�I�ł���C�����ł͊����I�ł���悤����3�̂��̂���݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��D���̂悤�Ȑ����������Ă�����̂͂Ȃɂ��D����͎��Ԃł���D�挱�I�Ȏ��ԋK��C���Ƃ��Γ������݂̋K��́C����ɂ̓A�E�v���I���ł��邩��J�e�S���[�Ɠ����ł���C�����ɂ͌��ۂ�����̂͂��ׂĎ��Ԃ̂����ɂ̂ݕ\�ۂ��ꂤ�邩�猻�ۂ���ΏۂƂ������ł���D���̈Ӗ��ŃJ���g�͐挱�I�Ȏ��ԋK����挱�I�}���idas transzendentale Schema�j�ƌĂсC�含�������Ȃ����̎g�p�������含�̐挱�I�}�����itranszendentaler Schematismus
des reinen Verstandes�j�ƌĂ�ł���D�}���͎����I�ɐ}���I�ɋK�肷���\�z�́iEinbildungskraft�j�̎Y���ł���D
- ��Ɍ����悤�ɁC�J�e�S���[�ɂ́C4�g����D���ꂼ��ǂ̂悤�Ȑ}���������Ă���̂��낤���D
- �@ �ʂ̕��ՓI�Ȑ}���́C���Ԍn��iZeitreihe�j���邢�͐��ł���D���Ƃ͒P�ʁi�����I�Ȃ��́j��P�ʂɏ����ɉ����邱�Ƃ��܂ނƂ���̂ЂƂ̕\�ۂł���D�ʂƂ��������Ȍ含�T�O��\�ۂɂ����炷���߂ɂ́C�������̒P�ʂ����X�ƍ\�z�͂̂����ɂ��肾�����ق��ɂȂ��D���̎Z�o���ŏ��Ŏ~�߂�Ƃ��P�ꐫ�������C����ɂ����i�߂�Ƃ����������C�����Č���Ȃ�������Ƃ��S�̐���������D
- �A ���̐}�������Ԃ̓��e�iZeithalt�j�ł���D���ɑ�������ݐ��Ƃ����含�T�O�������I�Ȃ��̂ɓK�p���悤�Ƃ���ꍇ�C�[�����ꂽ���ԁC���Ȃ킿���Ԃ̓��e���l����D���鎞�Ԃ��[�����Ă�����͎̂��ݓI�ł���D�ے萫�Ƃ��������Ȍ含�T�O��\�ۂ��悤�Ƃ���ꍇ�C�Ȏ��Ԃ��v�������ׂ�悢�D
- �B �W�̐}�������Ԃ̏����iZeitordnung�j�ł���D�Ȃ��Ȃ�C�W��\�ۂ���Ƃ��C�˂Ɏ��Ԃ̂����ɂ����鎖���̈��̏������l���邩��ł���D���̐��́C���݂�����̂̎��ԓ��ɂ����鎖���̍P���Ƃ��Č���C���ʐ��͎��ԓ��ɂ����鍇���I�Ȍp�N�Ƃ��āC���ݐ��͂�����̂̂����ɂ��鏔�K��Ƒ��̎��̂̂����ɂ��鏔�K��Ƃ̍����I�ȋ����Ƃ��Č����D
- �C �l���̐}�������Ԃ̑����iZeitbegriff�j�ł���D�\���̐}���͂���\�ۂ����Ԃ̏�������ʂƍ��v���邱�Ƃł���C���ݐ��̂���́C�Ώۂ����̎��Ԃ̂����ɑ��݂��Ă��邱�Ƃł���C�K�R���̂���͑Ώۂ������鎞�Ԃɑ��݂��Ă��邱�Ƃł���D
- ���̂悤�ɂ��Ă����́C�����ۂ��o���F���ւƍ��߂邱�Ƃ��ł���̂��D
- �i6�j ���z�_�I���o
- �����I���ς̑��l�����z�_�I�\���͂ɂ���Č含�̂��ƂɌ��������ꍇ�C�u����v�Ƃ����T�O���K�v�ł���D�܂�C�������邱�Ƃɂ���ē��ꂪ����̂ł͂Ȃ��C�u����v�Ƃ��������I�Ȉӎ����u�����v���\�ɂ���̂ł���C�����Ă��̓�����`�������ς̍����I�ȓ������u���o�v�iApperzeption�j�Ƃ����D
- �u���͍l����v�i�� Ich denke ��j�Ƃ����ӎ��́C���̂�����\�ۂɔ��Ȃ�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��D���͂��̈ӎ����������o�Ɩ��Â���
- ���͂�����������o�Ɩ��Â��āC�o���I���o�����ʂ���D�܂������I���o�Ƃ����Â��邪�C���̗��R�́C���̓��o���C���͂⑼�̓��o���瓱�o���ꂦ���C�t�ɂ����鑼�̏��\�ۂɔ��Ȃ��u���͍l����v�Ƃ����\�ۂ݂������Ȉӎ��iSelbstbewusstsein�j������ł���
- ���Ƃ��Ɓu���o�v�Ƃ������t�̓��C�v�j�b�c�����������p��ł���C�u�m�o�v�iPerzeption�j�����܂Ƃ߂�iad-�j�Ƃ����Ӗ��ł������D�����āC�����̂��^����ꂽ���l�ɂ���u�`�v��^���悤�Ƃ���Ȃ�C�K������ɂ́u���́c�ƍl����v�Ƃ��������I�Ȏ��Ȉӎ����K�v�ł���D������u�������o�v�Ƃ͂��̂悤�ȁu���o�v�̍����ł���C�قڃf�J���g�́u�R�M�g�E�G���S�E�X���v�ɑΉ�����D����䂦
- �����͌����đΏۂ̂����ɑ��݂��Ă��Ēm�o�ɂ���Ď��o�����悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł͂Ȃ��D���̌����͂܂������含�̂Ȃ��킴�ł���D�܂�含�́C�A�E�v���I���Ɍ�������\�͂ł���C�܂����ςɂ����鑽�l�ȕ\�ۂo�ɂ���ē��ꂷ��\�͂ɑ��Ȃ�Ȃ��D�����Ă��̓��o�̓���Ƃ������������C�l�Ԃ̔F���S�̂̍ō��̌����Ȃ̂ł���
- �Ƃ������ƂɂȂ�D������x�C�܂Ƃ߂�ƁC�����͌含�Ƃ����\�͂ɂ���Ċ����ɂ���ė^����ꂽ���l���C����J�e�S���[�̂��Ɓu�T�O�v�Ƃ��Č`��^����̂����C����ɂ́C�u���́c�Ƃ��čl����v�Ƃ������Ȉӎ��Ƃ��Ắu���o�v���K�v�Ȃ̂ł���D
- ��2�� �����ᔻ
- �i1�j �挱�I����
- ���āC�u�含�v�Ɓu�����v�͈قȂ�D�含�̓J�e�S���[���C�������u���O�v�iIdee�j�����D�����āC�含�͊T�O���������iGrundsaetze�j�����邪�C�����͗��O����C���̂����Ɍ含�̌������ō��̊�b�Â������o���Ƃ���������iPrinzipien�j�����D�����̌ŗL�Ȍ����́C��ʂɁC�含�̐��ꂽ�F���ɂ������Ė�����I�Ȃ��̂����o���C����ɂ���Ă��̓�����������邱�Ƃł���D�����痝���͖�����I�Ȃ��̂́C���Ȃ킿�����̔\�͂ł��邪�C�������Ώۂƒ��ڂɊW�����C�含�Ƃ��̏����f�Ƃ̂݊W���邩��C���̊����͂����܂œ��ݓI�łȂ���Ȃ�Ȃ��D�������ꂪ�ō��̗����I�����P�ɐ挱�I�ȈӖ��ɗ��������C�F���̌����I�ȑΏۂɂ܂ō��߂悤�Ƃ���Ȃ�C����͌含�̊T�O����I�Ȃ��̂̔F���ɓK�p���邱�Ƃɂ���Ē����I�ƂȂ�D�J�e�S���[�̂��̂悤�Ȓ����I�Ȍ�����g�p���珃���含���o�����z���Ċg�債���邩�̂悤�Ȍ��z�������Ă������\���Ƃ�����挱�I���ہitranszendentaler Schein�j�����܂��D�����̎v�ٓI���O�́C
- �@��ΓI��ς̗��O�C�v�l������̂Ƃ��Ă̍��̗��O�i�S���w�I���O�j
- �A�����鐧��ь��ۂ̑��̂Ƃ��Ă̐��E�̗��O�i�F���_�I���O�j
- �B���ׂĂ̂��̂̉\���̍ō��̏����Ƃ��ẮC�����Ƃ����S�ȑ��݂Ƃ��Ă̐_�̗��O�i�_�w�I���O�j
- ��3�ł���D�����͌o���I�Ȍ����ɂ͂܂������K�p�ł���,�\���I�����ikonstitutive
Prinzip�j�łȂ��ċK���I�����iregulatives
Prinzip�j�ł���,����̑Ώۂ������I�o�����ł͂���ɑΉ����Ă��Ȃ��Ƃ���̂���Ȃ闝���̎Y���ɂ����Ȃ��D���������Ă����́C����ł��Ȃ��o���ɓK�p�����Ƃ��C���Ȃ킿�����ɑ��݂���q�̂ƍl������Ƃ��C�܂������̘_���I��T�C�͂Ȃ͂�������T�������k�قɊׂ�D
- �����ď]���̌`����w�₢�́C���ǂ́C����3�Ɋւ���₢�ŁC����͕����̂̑��ɑ�����̂�����C�������������_�����ɂ���Ă͓������o�Ȃ��̂ł���D���̂��Ƃ��J���g�́w���������ᔻ�x���u�挱�I�ؘُ_�v�iDie transzendentale Dialektik�j�ɂ����Ď������Ƃ����D
- �i2�j �S���w�I���O
- �`���I�ȍ����I�S���w�͍��i�S�j���C�����Ƃ��������ɂ���ė�I�Ȃ��́iSeeliending�j�Ƃ��C��j�Ƃ��������ɂ���ĒP���Ȏ��̂Ƃ��C�l�i���Ƃ����q��ɂ���Đ��I�ɓ���ȉb�q�I���̂Ƃ��C�s���Ƃ����q��ɂ���ċ�ԓI�łȂ��v�l�I���݂Ƃ��Ă����D
- �������C�����͂��ׂ��u�킽���͍l����v�iIch denke�j���瓱���o����Ă��āC��������ςł��Ȃ���ΊT�O�ł��Ȃ��C�P�Ȃ�ӎ��C���Ȃ킿������\�ۂ���ъT�O�ɂƂ��Ȃ��Ă��������S���Ă���Ƃ�����S�̍�p�ł���D
- ���̎v�l��p������ĕ��ƍl�����C��ςƂ��Ă̎��䂪�q�ρC���Ƃ��Ă̎���̑��݂Ƃ��肩�����C�O�҂ɂ������͓I���Ó����邱�Ƃ���҂������I���ڂ����̂ł���D������q�ςƂ��Ď�舵���C����ɃJ�e�S���[��K�p������ɂ́C����͌o���I�ɒ��ς̂����ɗ^�����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁC���ۂ͂����ł͂Ȃ��D�ł��邩��C�s���̏ؖ��͌���������Ɋ�Â��Ă���D
- �����I�S���w�́C�����̎��ȔF���ɂȂɂ��̂���������Ƃ���̊w���iDoktrin�j�Ƃ��đ��݂�����̂ł͂Ȃ��C���P�iDisziplin�j�Ƃ��Ă̂ݑ��݂���D���Ȃ킿����́C���̕���Ŏv�ٓI�����ɉz���Ă͂Ȃ�Ȃ����E���߁C�������邱�Ƃɂ���Ĉ���ł͗��������̂Ȃ��B���_�̉��ɐg�𓊂��Ȃ��悤�ɂ��C�����ł͐���������ɂƂ��ĉ��������Ȃ��B�S�_�̂��������܂���ē����������Ƃ��Ȃ��悤�ɂ�����̂ł���D���̈Ӗ��ł���͂ނ�������ɁC���������̂悤�Ȍ������z�����D��I�Ȗ��ɂ������Ė����̂䂭�������ނƂ����������C�����̎��ȔF�������ʂ̂Ȃ����z�I�Ȏv�ق���L�������H�I�g�p�Ɍ�����Ƃ��������Ƃ݂Ȃ��悤�Ɍx��������̂ł���D
- �ƁC���̂悤�Ȍ��_���C�J���g�́C���̍����I�S���w�̔ᔻ���瓱���o���Ă���D
- �i3�j �F���_�I���O
- �F���_�I���O�Ɋւ�����́C�S�g�̃J�e�S���[�Ɋւ��āC���ꂼ��4�l������D�����ăJ���g�́C�����̖₢�ɂ͗��_�����ɂ���Ă͓������Ȃ����Ƃ��C�u�A���`�m�~�[�iAntinomie�C�w���j�v�ɂ���Ď������Ƃ����D��������咣����������̂��Ƃ�藧�iThesis�C�e�[�[�j�Ƃ����C���̔��̖���藧�iAntithesis�C�A���`�e�[�[�j�Ƃ����D�����āC�����4�g�̃J�e�S���[�Ɋւ���,���ꂼ�ꎟ��4�g�̃e�[�[/�A���`�e�[�[�ŕ\���ł���D���Ȃ킿�C
- �@ �藧�F���ԁE��Ԃ͗L���ł���D
- ���藧�F���ԁE��Ԃ͖����ł���D
- �i�ʂɂ��āj
- �A �藧�F���E�ɂ͂���ȏ㕪�����Ȃ��P���ȕ���������D
- ���藧�F���E�ɂ͂���ȏ㕪�����Ȃ��P���ȕ������Ȃ��D
- �i���ɂ��āj
- �B �藧�F���E�ɂ͎��R�̖@���ɏ]�����ۂ���ł͂Ȃ��C���R�Ɋ�Â����ۂ�����D
- ���藧�F���E�ɂ͎��R�@���ɏ]�����ۂ����Ȃ��D
-
�i�W�ɂ��āD��ꌴ��������̂��C�Ȃ��̂��D���Ȃ킿�C��ꌴ���͂��̌����������Ȃ��̂�����u���R�v�ł���j�D
- �C �藧�F���̐��E�ɂ͕K�R�I�ȑ��݂�����D
- ���藧�F���̐��E�ɂ͕K�R�I�ȑ��݂͂��Ȃ��D
- �i�l���ɂ��āD���̐��E�Ɂu�ړI�i�������͐_�j�v������̂��C�Ȃ��̂��j�D
- ��4�g�ł���D�����āC�J���g�͂����4�g���ꂼ��ɂ��āC�e�[�[/�A���`�e�[�[���ǂ�����ؖ��ł������Ƃ��ؖ������̂ł���D�܂�C���Ƃ��ΐl�Ԃ́C���ԁE��Ԃ��q�ϓI�ɑ��݂���ƐM���Ă��邩���1�A���`�m�~�[��������킯�ł���D���ԁE��Ԃ͎�ϓI�Ȃ��̂ɉ߂��Ȃ��̂�����C�L���ł������ł��Ȃ��D
- �����ŁC��1�A���`�m�~�[�Ɋւ���J���g�̏ؖ����������Ă݂悤�D�܂��e�[�[�̏ؖ�����D
- ���ɐ��E�͎��ԓI�Ȏn�܂�����Ƃ��悤�D��������Ɨ^����ꂽ�ǂ�Ȏ��_���Ƃ��Ă݂Ă��C����܂łɖ����̎��Ԃ��o�߂��Ă���C�]���Ă܂����E�ɂ����镨�̑����p�N�����Ԃ̖����̌n�߂����������ƂɂȂ�D�������n��̖����Ƃ������Ƃ́C�p���I�����ɂ���Ă͌����Ċ������꓾�Ȃ����Ƃ��Ӗ�����D�̂ɉ߂������������̐��E�n��͕s�\�ł���C���������Ă܂����E�̎n�܂�́C���E�̌������݂̕K�R�I�����ł���Ƃ������ƂɂȂ�\���ꂪ�ؖ������ׂ����̂��Ƃł������D
- ���������ȒP�Ȍ��������o���Ȃ��̂��C�Ǝv���̂����C���m���������߂ɂ͂�ނȂ��D�����ĊȒP�Ɍ����ƁC�������Ԃ������Ȃ�C���݂܂łɖ����̎��Ԃ��߂����͂��ł���D�������C�u�����̎��Ԃ��߂���v�ȂǂƂ������Ƃ͂��肦�Ȃ��D�̂Ɏ��Ԃ͖����ł͂Ȃ��D���Ȃ킿�C���Ԃ͗L���ł���D�Ƃ������Ƃ��D���ɁC�e�[�[�̂����̋�ԂɊւ���ؖ������Ă݂悤�D
- �����ł��܂����̔��i���Ȃ킿���E�͗L���ł���j��z�肵�Ă݂悤�D��������Ɛ��E�́C�����I�Ɏ��݂��Ă��镨���琬��^����ꂽ�����̑S�̂Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�D�Ƃ���ł����Ȃ钼���ɂ��Ă��C���̒����̂�����E���ŗ^�����Ȃ��悤�ȗʂ̑傢���Ƃ������ƂɂȂ�ƁC�����͕����̑����ɂ���čl������ق��Ɏd�����Ȃ����C�܂�������ʂ̑S�̂́C�������ꂽ�����ɂ�邩�����Ȃ��ΒP�ʂ�P�ʂJ��Ԃ��t�������邱�Ƃɂ�邩���Ȃ���C�ǂ�Ȃɂ��Ă��l����꓾�Ȃ��̂ł���D�]���Ĉ�̕����I��Ԃ����Ă��鐢�E����̑S�̂ƍl���邽�߂ɂ́C�����̐��E���`�����Ă����̕����̌p���I�������������Ă���ƌ��Ȃ��Ȃ���˂Ȃ�Ȃ��C��������C�����̎��Ԃ́C���������̕���]���Ƃ���Ȃ��������邱�Ƃɂ���āC�o�߂������̂ƌ��Ȃ��˂Ȃ�Ȃ��\���������̂��Ƃ͕s�\�ł���D���ꂾ���猻���I�Ȃ��̖̂����̏W���́C�^����ꂽ�S�̂Ƃ݂Ȃ��꓾�Ȃ����C�]���Ă܂������I�ɗ^�����Ă�����̂ƌ��Ȃ��꓾�Ȃ��D�̂ɐ��E�́C��Ԃɂ����鉄���Ƃ����_���猾���C�����ł͂Ȃ��Č��E��L����D
- �Ȃ�̂�������D�u�����̋�ԁv�Ƃ������̂�����ꂪ�z�����悤�Ƃ��Ă��ꎞ�ɂ͏o���Ȃ��D�����ŁC�����ȕ�������l���Ă��������Ƒ傫�����Ă����̂����C����ɂ͖����Ɏ��Ԃ�������̂ŕs�\�ł���D�̂ɋ�Ԃ͖����ł͂Ȃ��C�Ƃ������Ƃ��낤���D��Ԃɂ�����u�L�����v�̏ؖ��͐��������Ă悭�����ł��Ȃ��D�Ƃ������C���x�̓A���`�E�e�[�[�̏ؖ������Ă݂悤�D
- ���E�����ԓI�Ɏn�܂�����Ɖ��肵�Ă݂悤�D�n�܂�Ƃ����̂́C�����I���݂̂��Ƃł���C����ƕ��̑��݂��Ă��Ȃ����Ԃ���������O�ɂ���킯������C���E�����݂��Ă��Ȃ��������ԁC��������Ȏ��Ԃ����̑O�ɂ������ɈႢ�Ȃ��D�������Ȏ��Ԃɂ����ẮC���悻���̐��N�͕s�\�ł���C������Ȏ��Ԃ̂ǂ�ȕ��������̕����ɗD�悷��悤�Ȃ��́C��������C�݂̏����̕ς��Ɍ����I���݂̏������܂�ł���Ƃ����Ӗ��ŁC���̕��������ʂ����悤�Ȃ��̂������Ȃ�����ł���D�̂ɐ��E�ɂ����ẮC�Ȃ�قǕ��̑����̌n�n�܂�������Ȃ����C�]���Ă܂��߂����������Ԃɂ��Č����C���E�͎��ԓI�ɖ����ł���D
- �v����ɁC���Ԃ��͂��܂�O�C�Ƃ����̂��l���邱�Ƃ��o���Ȃ��C�Ƃ������Ƃł���D���ɋ�Ԃɂ��āC
- ���E�͋�ԓI�ȗL���ł���C�܂����E��L����ƍl���Ă݂悤�D��������Ƃ��̐��E�́C���E��L���Ȃ��悤�ȋȋ�Ԃ̒��ɂ���Ƃ������ƂɂȂ邾�낤�D��������Ƌ�Ԃ̒��ɂ����镨�̑��݊W����łȂ��C��Ԃɑ��镨�̊W�����邱�ƂɂȂ�D�Ƃ��낪���E�͐�ΓI�S�̂ł����āC���̊O�ɂ͒����̑Ώۂ��Ȃ���C�]���Ă܂����E�ɑ��鑊�֎҂����݂��Ȃ��D���ꂾ����ȋ�Ԃɑ��邱�̐��E�̊W�Ƃ����̂́C�������傭���E�̊W����悤�ȑΏۂ͑��݂��Ȃ��Ƃ������Ƃł���D������������W�͖��Ӗ��ł���C�]���ċȋ�Ԃɂ���Đ��E�Ɍ��E���t�����邱�Ƃ��܂����Ӗ��ł���D�̂ɐ��E�͋�ԓI�ɑS�����E�������Ȃ��C��������C���E�͉����Ɋւ��Ė����ł���D
- ������C���Ԃ̏ꍇ�Ɠ��l�ŁC���E�̊O�Ƃ������̂��l����Ɠs���������C�Ƃ������Ƃ��D�������C�����ł��������l���Ă݂悤�D���Ԃ��L��������Ƃ����āC���ꂪ���ԂɁu�͂��܂�v������Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���̂��C���E����ԓI�ɗL���ł��邩��Ƃ����Ă��ꂪ���E�Ɂu�O�v������Ƃ������Ƃ��D
- ���Ƃ��C�n���\�ʂ��l���Ă݂悤�D�n���Ɂu�[�v�����邾�낤���D�n���\�ʂɂ������C�n���̊O�Ƃ������͍̂l�����Ȃ��D�������C�n���͗L���ł���D�F�������l�ŁC�n�オ�n���Ƃ����O�������̕\�ʂł���悤�ɁC�F�����l�������i���Ԃ܂ōl������ƌ������j�̕\�ʂ��Ƃ���C���E�͎��ԁE��ԓI�ɗL���ł���Ȃ���C���E�́u�O�v�͑��݂��Ȃ����C���Ԃ́u�n�܂�v�����݂��Ȃ��D����F�������w�ł́C���\�ʂ̂悤�ȕ����ǂ����͂Ƃ������C�F����Ԃ͔[�N���b�h�I�ȋ�Ԃ��Ƃ���āC��ԓI�ɂ́u�[�v���Ȃ��Ƃ���Ă���悤���D
- �Ƃ���ŁC���b�Z���͎��ԁE��Ԃ���ϓI�Ȃ��̂Ƃ���J���g�̐��ɂ������āC�w���m�N�w�j�x�̒��ŁC���̂悤�Ȕ��_���q�ׂ�D���Ȃ킿�C����ꂪ�F�������Ԃ⎞�Ԃ̔z�N�ɂƂ��Ă����������Ƃ��J���g�̗��_���Ɛ����ł��Ȃ����Ƃ��w�E����D�܂�C���Ƃ��C�N���N�̊�����Ă��C��ɑ���̌��̏�ɕ@������C�@�̏�ɖڂ�����C�Ƃ����z��ɂȂ��Ă��邪�C���ꂪ�Ȃ�������������Ȃ��D�������������ɁC�N�ł����C������������ɗ����D�������C���́C�����̖ڂɗ����ł���ƒm�o�����߂������ƂȂ镨����A�Ɨ��Ƃ��Ēm�o�����������̕�����B�͕ʂł���C�������CA��B���ȑO�ɂ������킯�ł͂Ȃ��D�Ȃ�Ȃ��C���̂悤�Ȗ����ԓI�Ȃ��̂ɋN������2�̌��ۂ̎��Ԕz�˂ɓ����Ȃ̂��C���ꂪ�J���g�̗��_�ł͐����ł��Ȃ��̂��D
- �i4�j �_�w�I���O
- �@ ���ݘ_�I�ؖ��ider ontologischer
Beweis�C�{�̘_�I�ؖ��j
- �uA��B�ł���v�ƌ����Ƃ��C���́u�ł���v�́C���́u���ۓ��e�v�����������ŁC����A�u������v�K�v�͂Ȃ��D����T�O�ɑ��݂������Ă��Ă��C����̐����͂ЂƂƂ��Č���킯�ł͂Ȃ��̂ł���D�����炻�ꂪ�����鐫���������Ă���Ƃ��Ă��C����͂܂������đ��݂��Ă��邱�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��D�u������v�Ƃ����Ӗ��̑��݂����ۓ��e�ł͂Ȃ��̂��D
- ���������Ă܂���������ɍ��グ�����O����C����ɏƉ�����Ώۂ��̂��̂��ďo���悤�Ƃ������Ƃ́C�܂������s���R�Ȃ��Ƃł���C����̒m�������Ƃ����炵�����肩�������̂ɂ����Ȃ��D
- ���Ă݂�ƁC���̗L���ȏؖ��ɔ�₳�ꂽ�J��͂��ׂĖ��v�������̂ł���D�l������Ȃ闝�O�ɂ���Ă��̒m�b�𑝂����Ƃ��ł��Ȃ��̂́C���l�����̏�Ԃ����P���邽�߂ɁC�ނ̂����Ă��錻�ݍ��ւ������̃[���𑫂��Ă����̖��ɂ������Ȃ��̂Ɠ��l�ł��낤�D
- �J���g�́u���z�̒��́i�����I�j�S�^�[�����v�Ɓu�z����́i�\�I�j�S�^�[�����v�̋�ʂ��Ƃ��ėp����D�u�z����́v�S�^�[�����́C�z���u�o����v���C������Ƃ����āu���݂���v�킯�ł͂Ȃ��D�ǂ���̈ꖜ�~���u�i�ꖜ�~�j�ł���v�Ƃ����`�ŕ\����邪�C�u������v�Ƃ����_�Ō���I�ɈقȂ�C�Ƃ������Ƃ��D�_�̑��ݘ_�I�ؖ��͂��̂悤�Ȃ��̂��C�Ƃ����킯���D
- �܂�C�_�͊��S�ł��邩�炠����m��I�Ȑ����������Ă���D�u���݂���v�͍m��I�������ł����D������_�͑��݂���C�Ƃ����̂��C���ݘ_�I�ؖ��̊�{�헪�ł��邪�C�u���݁v�����̂��̂̂��u�����v�ɂ��Ă���Ƃ��낪���Ȃ̂��i�u�������݁v�Ɓu�{�����݁v���������Ă���j�D
- ��ɏq�ׂ��悤�ɁC�J���g�́C�u���݁v�Ƃ����̂́C���T�O�̎��ۓ��e�������q��ł͂Ȃ��Ƃ���D�ł́C��̂ǂ̂悤�ȓ����ɂ���āC�����́u�����I�Ɂv���݂���̂��낤���D�J���g�͂��̓�����F����ς̍s�������C�藧��p���ƍl���Ă���D
- �n�C�f�K�[�ɂ��ƁC�J���g�ɂ����Ắu�������݁v�𐬗������铭���́C�F����ς̂����Ȃ��u�m�o��p�v�C���邢�͂����ƂЂ낭�u�\�ۍ�p�v�ł���Ƃ����D�n�C�f�K�[�͂���ɕ��͂�i�߁C�J���g�̂��́u�\�ۍ�p�v�͂����ƍL���Ӗ��ł́u�����p�v�̃��@���G�[�V�����ƌ��邱�Ƃ��ł��邩��C�J���g�̍l���̍���ɂ́C�{�l���͂�����ƋC�Â��Ȃ��܂܂ɁC�u���݂���v�Ƃ������Ƃ��u�퐧�쐫�v�iHergestelltheit�j�ƌ��鑶�݊T�O������ł���Ƃ����D
- �A �F���_�I�ؖ��ider kosmologischer
Beweis�j
- �F���_�I�ؖ��́C���݂��Ă�����̂̕K�R������o������D���Ȃ킿�C������̂��������Ă���Ƃ���C���̌����Ƃ��ĕK�R�I�ȑ��ݎ҂��܂����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���D�A���X�g�e���X�ł����u�s���̓��ҁv�ł���D�������C���̏ؖ��́C��̉F���_�I�A���`�m�~�[�ɂ���Ĕᔻ����Ă���D���Ȃ킿�C���ۂ�����R�I�Ȃ��̂���o�����z���ĕK�R�I�ȑ��ݎ҂𐄘_���Ă���Ƃ�������Ƃ��Ă���D
- ���ɂ��̂悤�Ȑ��_�����F���Ă��C����ɂ���Ă͂܂��_�͗^�����Ȃ��D�����ł���ɁC��ɕK�R�I�ł��肤��̂͂�������ݐ��̑����ł��鑶�݂����ł���C�Ƃ������Ƃ����_�����D���̖�����t�ɂ��āC��������ݐ��̑����ł��鑶�ݎ҂͐�ɕK�R�I�ł���ƌ����C�ӂ����ё��ݘ_�I�ؖ��������F���_�I�ؖ��͂���Ɠ����ɂȂ�D
- �B ���R�_�w�I�ؖ��ider
physikotheologischer Beweis�C�ړI�_�I�ؖ��j
- ���̌o������o�����āC���̐��E�̎����̒����Ɛ���ō��̌����𐄘_����̂��C���R�_�w�I�ؖ��ł���D������Ƃ���ɍ��ړI�������邪�C����͐��E�̎����ɂƂ��ĊO���I���Ȃ킿���R�I�ł���D���������ĕK�R�I�Œq�b�Ɖb�q�Ƃ������č�p����Ƃ���́C���̍��ړI���̌�������������D���̕K�R�I�Ȍ����͂����Ƃ����ݓI�ȑ��݂łȂ���Ȃ�Ȃ��D���������Ă����Ƃ����ݓI�ȑ��݂͕K�R�I�Ɍ������Ă���D
- ����͐��E�̌`������C���̌`���ɂӂ��킵���\���Ȍ����𐄘_����̂ł��邪�C���̂悤�Ȏd���ł͐��E�̌`���̑n�n�҂��Ȃ킿���E�̌��z�҂������邾���ŁC�����̑n�n�҂ł�������́C���Ȃ킿���E�̑n���҂͂����Ȃ��D
- �����ł�ނ������ꑫ�ƂтɉF���_�I�ؖ��ɑ���C�`���̑n�n�҂������ē��e�̍��q�ɂ���K�R�I�ȑ��݂ƍl����̂ł���D���̂悤�ɂ��Ă����͐��E�̊��S�ɂӂ��킵�����S��L�����ΓI���݂����킯�ł��邪�C���������E�ɂ͐�ΓI�Ȋ��S�͂Ȃ�����C�����͔��Ɋ��S�ȑ��ݎ҂����ɂ������C�����Ƃ����S�ȑ��ݎ҂�ɂ͂ӂ����і{�̘_�I�ؖ����K�v�ł���D���̂悤�ɁC�ړI�_�I�ؖ��̍��q�ɂ͉F���_�I�ؖ�������C�F���_�I�ؖ��̍��q�ɂ͑��ݘ_�I�ؖ�������̂ŁC�`����w�I�ȏؖ��͂��̂悤�ȏz���o�Ȃ��̂ł���D
- ���R�������@���ɂ��������͈̂ꌩ�C���ɕs�v�c�Ȃ��ƂɌ����邪�C�J���g�ɂ��ƁC����͂��̂悤�ɐl�Ԃ̐��_�̍\�����o���オ���Ă���̂ł���D���̐������܂�ɒ��������Č����邩��Ƃ����āC�����ɐ_������̂͌��ł���Ƃ����킯���D�Ȋw�͉Ȋw�Ƃ��Ă��̐��E���Ȃ��C���������Ă���̂��ȂǂƂ������ƂɎv���ς킳�ꂸ�ɁC�@���������邱�Ƃɐ�O����悢�Ƃ������ƂɂȂ�D
- �i5�j �����C�����Č含�E����
- ������x�����܂ł̘b�����Ă������D
- �J���g�ȑO�̊ϔO�_�Ύ��ݘ_�̑��_�́C�F���͊��o�݂̂��C�m���i�m�I���ρj�ɂ���đΏۂ��\�S�ɔc���ł�����̂��C�Ƃ������ƂŁC�Ƃɂ����F���Ƃ������̂́C�Ώۂ����̂܂ܖ͎ʂ��邱�Ƃł���Ǝv���Ă����D������J���g�͂Ђ�����Ԃ��C�����̎�ς����E�𐬗�������Ƃ����D���������̐��E�͕����̂̐��E�ł͂Ȃ��C���ۂ̐��E�Ȃ̂ł���D�����͕����̂�F�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��D���������ۂ̐��E�͋q�ϓI�ɔF���ł���̂ł���D�����āC����͂����l�Ԃɐ�V�I�ɔ�����������̌`���ƁC���o�̂������Ȃ̂ł���D
- �����́C�O���̌��ې��E����̎h�����C�A�v���I���Ȋ����I�����i���������j�̌`���ł��鎞�ԁE��Ԃɂ���Đ������C�����t���Ď����D���ɂ��̎��������ې��E����̎h�����C�ʂɊւ��āC���Ɋւ��āC�W�Ɋւ��āC�l���Ɋւ��āC���ꂼ��3�i�v12�j�́C������A�v���I���ȏ����含�T�O�i�J�e�S���[�j�Ɋ�Â��āC�����ƌ含�̋��n��������\�z�́i�Ƃ�킯�����}���@�\�F�V�F�[�}�j�ɂ���đ������邱�Ƃɂ��F������D���̂悤�ɂ��āC�����́u�����́v���q�ϓI�ɔF�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ����C�u���z�_�I��ρv�ɂ���āu���ہv�̐��E�́C���ۂƂ��Ăł͂Ȃ��C�q�ϓI�ɔF���ł���Ƃ����D
- �܂�C�J���g�́C���_�����ɂ���đ����邱�Ƃ̂ł����u���ۊE�v�Ƒ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u�����̂̐��E�v�iintelligible Welt�C�b�q�E�j�Ƃ��s�ʂ���D�����������Ă����悤�ɁC�����͌o���z�����悤�Ȃ��́i���O�CIdee�G���z�CIdeal�j�����߂鑶�݂ł���D�Ⴆ�C�F�������܂�����������Č����邩��Ƃ����āC�����ɗ��R�i�����j�����߂悤�Ƃ���D�u�����v�iVernunft�j�Ƃ����̂́C�含�⊴���̏�ɗ��u�����̔\�́v�ł��邪�C���̂悤�ȗ��O�C���z��ǂ����߂鐫��������D�����āC���������߂�悤�ȗ��O�C���z�͐l�Ԃ̐��_�ɂƂ��Ă͕K�R�ł͂��邪�C�_�ł��Ȃ����́i�挱�I���ہC���z�_�I���ہj�ł���C���̂��ߌ`����w�I�ȓ�₪������̂ł���D
- �ł́C�����̗����̓����͖��ʂ̂��̂Ȃ̂��Ƃ����ƁC�����ł͂Ȃ��C�ƃJ���g�͌����D���������߂闝�O�C���z�͔F���s�\�Ȃ��̂Ȃ̂�����C�t�����H���邱�Ƃɂ�����ڎw�����ׂ����̂Ȃ̂ł���D���̂悤�ȗ����́C������ނ���C���H�I����ɂ����ĕK�R�I�ɗv������C���̈Ӗ������H�I�����̗D�����J���g�͐����D���āC�A���X�g�e���X�́C���H�I�s�ׂ��ϏƂ̕����D��Ă���Ɛ��������C�J���g�͗��_�I���������H�I�����̕�����ʂɒu�����̂��D
- �����͋q�ϓI�ɂ͏\���łȂ��ɂ���C��ϓI�ɂ͏\���ȐM�O�������Ă���D�ӎu�̎��R�C���̕s���C�_�̑��݂��C�m���ɂ͕K�v�łȂ��̂ɁC�������ɂ����ɂ������悤�Ƃ��Ă���3�̍��{�����ł���Ƃ���C�����̖{���̈Ӌ`�����H�̐��E�ɂ����āC���Ȃ킿������̊m�M�ɂ������đ��݂����̂ł���D�m�M�Ƃ͘_���I�Ȋm�����ł͂Ȃ��ē����I�Ȋm�����ł���D
- ��3�� �^���Ƃ͉���
- �i1�j �Ή����I�^���T�O
- ���āC�J���g�ɂ��ƁC�u�^���v�Ƃ͉����D�N�w�j��C�u�^���v�̒�`�Ƃ��āC�ł���{�I�Ȃ��̂́C�Ή����I�^���T�O�iadaequatio rerum et intellectus�j�ł���D���Ƃ��u�Ⴊ�����v�Ƃ����F�����^���ł���̂́C���ԂƂ��āC�Ⴊ�����ꍇ�ł���D�Ⴊ�����Ƃ������ԂƁC�u�Ⴊ�����v�Ƃ����F�������v���Ă���C�܂�^���ł���D�������ł́C�����͑ΏۂƔF�������v���Ă���Ƃǂ̂悤�ɂ��ĕ�����Ƃ����̂��낤���D�Ώۂ��̂��ׂ̂悤�Ƃ��Ă��C����ׂ��Ƃ��C�K������́u�F���v�Ƃ����Ȃ�Ȃ��D�J���g�͔F���ɂ��Ă̐^���̕��ՓI������߂�₢��s�����ł���Ƃ��Ă���D
- �^�������̑ΏۂƂ̍��v�ɂ���Ȃ�C���̂��Ƃɂ���Ă��̑Ώۂ͑��̏��Ώۂ����ʂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��D�c�Ƃ���ŁC�^���̕��ՓI��́C���ׂĂ̔F���ɂ��āC���̑Ώۂ̋�ʂȂ��Ó�����悤�Ȃ��̂ł�����̂ł���͂��ł���D
- �܂�C�ΏۂƂ̍��v�C�Ƃ������Ƃ́C������̓I�ȁC����́C�Ώۂɂ��čl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��D�Ȃ̂ɁC�u���ՓI�v��Ƃ������Ƃ́C����̑Ώۂł͂Ȃ��C���ׂĂ̑ΏۂɑÓ�������̂łȂ���Ȃ�Ȃ��D����͖������C�ƌ����̂��D
- �������C���炩�Ȃ̂́C���̊�ɂ����ẮC�F���̂��ׂĂ̓��e���̏ۂ���Ă���̂ɁC�^���͂܂��������̓��e�Ɋւ�̂ł��邩��C�F���̓��e�̐^���̊��₤�̂́C�܂������s�\�ł���C�s�����ł���Ƃ������Ƃł���D�c���������v���͂��ꎩ�g�ɂ����Ė����������ƂȂ̂ł���D
- �����ăJ���g�́C�u���z�_�I�^���v�itranszendentale Wahrheit�j�Ƃ����l���������̂ł���D
- �i2�j ���z�_�I�^���T�O
- ��4�� �J���g�̓�����
- �i1�j ���_�����Ǝ��H����
- �J���g�́u���_�����v�̑����錻�ۂ̐��E�Ɓu���H�����v�̓����������E�Ƃ��͂������ʂ��C���ꂻ��̔ᔻ��ڎw�����D���_�����̔ᔻ�̊�ڂ́C�����ɂ��ď����������A�E�v���I���ɋq�̂�F�������邩�ł���C�������Ď��H�����̔ᔻ�̊�ڂ́C�����ɂ����ӎu���q�̂Ɋւ����A�E�v���I���Ɍ��肵���邩����������D���H�����̔ᔻ�ɂ����ẮC�ӎv�̌��������ƂȂ̂ł���D���_�I�F����{���I�ɋK�肷����̂͒��ςł��邪�C�������Ĉӎu��{���I�ɋK�肷����̂͌����ƊT�O�ł���D���������āC���H�����́C�����I��������o�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��D
- �܂�C�u���݁v�Ƃ��Ă̎��R�̎�����������闝�_�����̗�����u���ׁv�iSollen�C�܂��ɂȂ��ׂ����Ɓj�̐��E�Ƃ��Ă̎��H�I�����̗���C���R�Ȋw�I�ϓ_�Ɠ����I�s�דI�ϓ_�Ƃ͂��ꂼ��܂������ʂ̒����Ɩ@���ɂ���ĕ����Â����Ă���Ƃ����̂��D���ʗ����ԁE���Ԃ̊T�O�́C���ې��E�Ɋւ�����̂ł���C���_�����̐��E�ł������D�����ł́C�����͎��R�E�s���E�_�Ƃ��������O��Nj����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������D�����C���H�����̐��E�ł́C�����ƊO�I�����̊W�ł͂Ȃ��C���I�Ȃ��́C�ӎu�Ƃ̊W�ł���C�����ɂ����āC���R�E�s���E�_�̗��O���܂��C�m���������߂����Ƃ��ł���̂ł���D
- �ł́C�ǂ̂悤�ɂ��Ď��H�����ɂ���āC���̈��ʗ��ɔ���ꂽ���ې��E�C�o�����E���邱�Ƃ��o����̂��D����́C�������iSittengesetz�j���������@�Ƃ��Ăł͂Ȃ��C�茾���@�ikategorischer
Imperativ�j�Ƃ��Ď��邱���ł���D
- �i2�j �������@�ƒ茾���@
- �������@�Ƃ́C�u�����`�Ȃ�`���ׂ����v�Ƃ������̂ł���D�������ɂ����Ă��C���̂悤�Ȃ��̂͑���������D���Ƃ��C�u�����l����M�p���ꂽ���̂Ȃ�C�R��f���Ă͂����Ȃ��v���Ƃ��u���N���͎O���̓��v�Ȃǂ�����ɂ�����D����ɂ������āC�����Ȃ��Ɂu�`���ׂ����v�Ƃ��������邱�Ƃ�茾���@�i���㖽�@�j�Ƃ����D
- �Ⴆ�C�u�����l����M�p���ꂽ���̂Ȃ�C�R��f���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ������������������Ƃ��悤�D��������ƁC���̓������́C�u�l�ɐM�p����Ȃ��Ă��\��Ȃ��v�Ƃ����l�ɂ͒ʗp���Ȃ��D�J���g�͓������Ƃ͉������@�ł͂Ȃ��C�茾���@�łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��C�ƍl�����D�u�R��f���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ������������������Ƃ���ƁC���ꂪ���Ƃ��l�������邽�߂ł������Ƃ��Ă��C�R��f���Ă͂����Ȃ��̂ł���D
- ����ɁC�������@�́C���������u��i�v�ƂȂ�D�u�`�̂��߁v�ɂƂ����l�����́C�܂��������ʗ��ɔ���ꂽ���̂��D�����̗����͂��̈��ʗ��̔��߂��瓦��悤�Ƃ��Ă���̂�����C���������Ӗ��ł��������͒茾���@�ł���ׂ��ł���C���ꂪ�u���R�v�Ȃ̂��D�Ⴆ�����́C�u�������Ȃ�����i�@��j���Ăł��j���݂�����v�Ƃ������Ƃ������u���R�v�ł���C�ƍl�����������C�����ł͂Ȃ��D�u�������Ȃ������C���݂�����v�Ƃ����͕̂K�R�ɂ����̂ł��邩��C���ʗ����o�Ă��Ȃ��C���Ȃ킿�u���R�v�ł͂Ȃ��̂��D�~�]�̂��߂ɕ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��D
- �~���\�͂̑Ώہi�����j���ӎu�̋K�荪���Ƃ��ė\�z����S�Ă̎��H�I�����́C��ʂɌo���I�ł���C���H�I�@�����������邱�Ƃ͂ł��Ȃ�
- �̂ł���D������C����K�����������Ƃ��āC���̋K�������ɂ�����C�u���̋K����������Ȃ������Ƃ�����v�Ƃ��u���̋K����j�����Ȉ������Ɓi�����j������v�Ƃ��l���Ă͂����Ȃ��D
- ���̂悤�Ȏ��H�̂��߂Ɏ������́C�ڐ�̗~�]�ɂƂ���Ȃ����߂ɂ��C�����Ō��߂��K�������悤�ɂ��ׂ��ł���D���ꂪ�i���iMaxim�C�}�L�V���j�ł���D���Ƃ��ǂ̂悤�ȏɂ��낤���C�u�R�����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ǝ����Ō��߂�����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂��D���Ƃ����ꂪ�F�l��Ƒ�����邽�߁C�ł����Ă��R�����Ă͂����Ȃ��D�����Ă��̂悤�Ȋi���́C�������C���g�̉��s���Ō��߂Ă͂Ȃ�Ȃ��D�����
- ���̈ӎu�̊i���������ɕ��ՓI�ȗ��@�̌����Ƃ��Ēʗp������悤�ɍs�ׂ���
- �ƌ�����悤�ɁC�����̊i���́C�����@�ɂ���Ē�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��D�u�������H�����̍��{�@���v�ł���D
- �i3�j �P�ӎu
- �u��ÂœI�m�Ȕ��f�́v��u�E�C�v�Ȃǂ͈ꌩ�C�u�P���v���̂��Ƃ݂Ȃ����Ƃ��o�����������C�����͂������g�p����ӎu���P���Ȃ���ΗL�Q�ɂȂ肤��D�Ⴆ�C���́u��ÂœI�m�Ȕ��f�́v��u�E�C�v��������Ă���ƍߎ҂́C�����łȂ��ƍߎ҂��L�Q�ł��낤�D���l�ɁC���͂�x�C���_�C���N�Ƃ�������ʂɁu�K���v�Ƃ������Ԃ��P�����̂��ƌ����邪�C����炪�S�ɋy�ڂ��e���𐧌�ł��Ȃ���C���������L����l�Ԃ�z���ɂ����C�����ɂ�����D
- ���̂悤�Ɍ��Ă���ƁC�l�Ԃ������邱�Ƃ��o������̂̂����Ŗ������ɑP���C�ƌ�����̂��u�P�ӎu�v�݂̂ł����D����ɁC�J���g�ɂ��ƁC���́u�P�ӎu�v�͂��ꂪ������B��������C�����ɖ𗧂����肷�邩��u�P���v�̂ł͂Ȃ��C�u���ꎩ�̂ɂ����đP���v�̂ł����āC���Ƃ��u�P�ӎu���ő�̓w�͂��Ă����̈ӎu�ɂ���ĂȂɂ��Ƃ����A�����C�����P�ӎu�݂̂��c��v�Ƃ��Ă��C
- ���̑P�ӎu�͂���������̂悤�ɁC����̑S���l�����̂ꎩ�g�̂����Ɏ����̂Ƃ��āC���ꂾ���Ō���P��
- �̂ł���D
- ����ꂪ�����Ŏv���o���̂́C�h�D���X�E�X�R�g�D�X����ӎ�`���낤�D����܂ł̓N�w�ɂ����ẮC�����́u�P�v��m���Ă���ƕK������������Ȃ����̂��ƍl�����Ă����D�������X�R�g�D�X�̓o��ɂ���āC�����͑P��m���Ă��Ȃ炪����������Ȃ�Ȃ����Ƃ��ł���Ƃ������ƂɂȂ����̂ł���D�����ăX�R�g�D�X�̌������Ƃɂ��ƁC�����͐M�����Ȃ����Ƃ��ł���D�����炱���C�����ł����Ă݂�����̈ӎu�ɂ����ĐM��I�ю�邱�ƂɈӋ`������̂ł������D
- �J���g�ɂ����Ă��C�i���C�v�j�b�c���i�h�_�ɂ�����u�~���v��ʂ��āj���̍l�����͎p���ꂽ�킯�Ȃ̂ł���D
��4�� �h�C�c�ϔO�_
��2�� �嗤�����_�ƃC�M���X�o���_
�ڎ�
- ��4�� �h�C�c�ϔO�_
- �J���g�ł́C�����́u���_�v�ƁC�����ɂ͌����ĔF�����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u�����́v��2�ɐ��E�͕�������Ă��܂��Ă����D����ɂ��̌��ʁC�u���_�I����v�Ɓu���H�I����v��2�Ɂu����v���������Ă��܂����D����2���ӂ����ѓ������邽�߂ɁC�u�h�C�c�ϔO�_�v�iDeutscher
Idealismus�j�����܂��D
��1�� �t�B�q�e�ƃV�F�����O
- �i1�j �t�B�q�e�iJohann Gottlieb Fichte�C1762�`1814�j
- �J���g�ɂ��ƁC�F������u���v�i���_�I����j�Ǝ��H����u���v�i���H�I����j�͕��Ă����D�t�B�q�e�͂��̂悤�ȃJ���g�̓_�ɕs����������D�J���g�͎���̐����������̂ɂ�鐧�����ƍl�����̂����C�t�B�q�e�́C���̂悤�Ȑ������C���䂻�̂��̂ɂ�鐧�����ƍl�����̂��D
- �ǂ�Ȍo���̂����ɂ�����ƕ��C�m���Ƃ��̑Ώۂ�����D���̓ʂ̂����ǂ���̑��ʂ����ɊҌ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��낤���D����������̏ۂ���C�����̂������C�\�ۂ͑Ώۂ̎Y���ƍl�����˂Ȃ�Ȃ��D���Ȃ킿���ݘ_�ł���D�����Ώۂ��̏ۂ���C���䂻�̂��̂�������D���Ȃ킿�ϔO�_�ł����D�t�B�q�e�ɂ��ƁC�J���g�̂Ƃ����悤�ȑ�3�̗���͕s�\�ŁC���������āC�ǂ��炩��I�˂Ȃ�Ȃ��D���̍ۂɋC������ׂ����Ƃ͎���2�_�ł���D
- �@
����͈ӎ��̂����ɑ��݂��邪�C����ɔ����ĕ����̂͂܂��������グ��ꂽ���̂ł���D�Ƃ����̂́C����ꂪ�ӎ��̂����ɂ����Ă���̂́C���o���ꂽ���̂����ł��邩��D
- �A
�ƒf�_�͕\�ۂ̔�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��D�����ł���͕\�ۂ̔�����Ώێ��̂���������C�ӎ��̂����ɂ͑��݂��Ȃ�������̂���o�����邪�C���������݂������N�������̂͂������݂ł����ĕ\�ۂł͂Ȃ��D
- ���̂悤�Ɍ��Ă���ƁC���݂���ł͂Ȃ��m������o������ϔO�_�������������̂ł���D�ϔO�_�ɂƂ��ẮC�m�����ŏ��̂��̂ł����ΓI�Ȃ��̂ł��邩��C�m���͂Ђ�����\���I�ł����ĎI�łȂ��C�܂��ɂ��̂䂦�ɂ���ɂ͍s���݂̂������đ��݂͑����Ȃ��D���̍s���̏��`���C���Ȃ킿�m���̕K�R�I�ȍs���̎d���̑̌n�́C�m���̖{�����瓱���o����Ȃ���Ȃ�Ȃ��D�J���g���J�e�S���[�����������悤�ɁC�m���̏��@�����o������E���グ��Ȃ�C�l�͓�d�̌���Ƃ��ƃt�B�q�e�͌����D���Ȃ킿�C
- �@ �Ȃ��m�������̂悤�ɍs�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��Ƃ������ƁC����т����̖@�����Ȃ����m���̓��ݓI�@���ł��邩�ǂ����Ƃ������Ƃ��킩��Ȃ��D
- �A ���ɋq�̂��̂��̂��ǂ����Đ����邩���킩��Ȃ��D���������Ēm���̏��������q�ς��C���䂻�̂��̂��瓱���o����˂Ȃ�Ȃ��D
- ���̂悤�ɂ��āC�t�B�q�e�͎���������Ƃ��đ��̂��ׂĂ̂��̂����䂩�瓱���o�����Ƃ����D���̂悤�Ȏ���́C�J���g�ɂ�����悤�ɕ����̂ɂ���Đ�������Ȃ�������Ȏ����iIch�j�ł���D�t�B�q�e�����̎咘�w�S�m���w�̊�b�x�̒��ŏq�ׂ�����Ɋւ���3���������Ă݂悤�D
- �@ ����͍����I�ɐ�ΓI�ɁC���Ȏ��g�̑��݂�藧�iSetzen�j�����i��1���{����j�F���̂悤�ȁC���炩�̓����Ƃ����s�ׂ�����Ƃ������Ƃɂ����Ă݂�����ł���悤�ȑ��݂ł��鎩����C���s�iTathandlung�j�Ƃ����D����́C�s�ׂ̌��ʁiTat�j�Ƃ��̍s�ׂ��̂��́iHandlung�j�Ƃ������ɐ����Ă���Ƃ������Ƃ������t�B�q�e�̑���ł���D������ɂ���Ă������u���ݐ��v�Ƃ����J�e�S���[��D
- �A ����ɂ������Đ�ΓI�Ȕ��iNicht-Ich�C����łȂ����́j�����藧�iGegensetzen�j�����D���u�ے萫�v�Ƃ����J�e�S���[��D
- �B
����͎���̒��ɉ��I�ȁi�������ꂽ�j����ɂ������C���I�Ȕ��藧����D������́C���Ȃ킿�C���ݐ��Ɣے萫���݂��ɔj����ƂȂ��ɂЂƂ̈ӎ��Ƃ������ꐫ�̒��֎�����Ȃ���Ȃ�Ȃ�����C�����͐���������Ȃ���Ȃ炢�D�䂦�Ɂu�������v�Ƃ����J�e�S���[��D�����Ă��̐������Ƃ����T�O�̂����ɂ́C�����iTeilbarkeit�j�C�ʂ̔\�́iQuantitaetsfaehigkeit�j�Ƃ������T�O�����݂��Ă���D
- �t�B�q�e�ɂ��ƁC������I���m���Ȃ��̂́C�ȏ�3�̌����Ős����D����́C
- ����͎���̂����ʼn��I�Ȏ���ɉ��I�Ȕ��藧����D�iIch setze im Ich dem
teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich entgegen�j
- �Ƃ����莮�̂����ɑ��������D
- ���āC���̂悤�Ɏ���Ɣ�䂪���݂ɐ��������̂ł��邪�C���̂��Ƃ��玟�̂��Ƃ�������D���Ȃ킿�C
- �@ ����͔��ɂ���Đ������ꂽ���̂Ƃ��Ď������g��藧����D�i����͔F���̑ԓx���Ƃ�j
- �A ����͋t�ɁC����ɂ���Đ������ꂽ���̂Ƃ��Ĕ���藧����D�i����͍s�ׂ̑ԓx���Ƃ�j
- �����Ƃ��Ă̎���͓����ł���̂����C�����I�ȗ����͌��E�����������I�Ȃ��̂ł��邩��C��̓I�Ȕ��Ƃ����Ώۂɓ��������邱�ƂŎ�������o����̂ł���C���̔����킪���̂ɂ��Ă����ߒ���ʂ��āC����Ɣ��̑Η����z�������O�Ƃ��Ă���Ύ���idas absolute Ich�j���������邱�ƂɂȂ�D
- �������C�t�B�q�e�̓N�w�͂�͂莩��ɑΗ�������́C�J���g�̕����̂ɑ�������������肵�Ă��āC�������ꂪ�t�B�q�e�ɂ����Ă͓��ʓI�ɂȂ��Ă���̂ł���D
- �i2�j �V�F�����O�iFriedrich Wilhelm Schelling�C1775�`1854�j
- �܂��̓V�F�����O�̎咘�w�N�w�̌����Ƃ��Ă̎���x�̈�߂����Ă݂悤�D
- �N�w�̖{�����Ȃ킿���_�͌`���╶���ł͂Ȃ��āC�܂��N�w�̍ō��̑Ώۂ͊T�O�ɂ���Ĕ}��ꂽ���̂ł͂Ȃ��āC���ꎩ�g���ڂɐl�Ԃ̂����Ɍ���������̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���D
- �t�B�q�e�̎���N�w�ł́C����Ɣ��͑Η����Ă������D�������C�t�B�q�e�͂����͎��R�̗��ɂł���ƌ����D���R�̓t�B�q�e�̌����悤�Ȏ���̓�����҂��Ă͂��߂Ē藧�������̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��C���ꎩ�g�Ŋ������Ă��鐶�����L�@�̂Ȃ̂ł���D
- ���������R�́C����ƕ���̉^���ɂ���Ă݂����犈������D���R�̂��̎��Ȋ��������V�F�����O�����ɐ��iPolaritaet�j�Ƃ����\���Ő�������D���Ƃ��C���ɐ��ƕ�������悤�ɁC���R�͔M�Ɗ��C�m��Ɣے�C�S�̂ƌʂȂǁC�˂�2�̋ɂɕ�����邱�Ƃɂ���ĂЂƂł���悤�ȑ��݂ł����D�������C���̕��ɐ��͈���̋ɂ��P�Ƃő��݂��邱�Ƃ̂��肦�Ȃ��_�ɓ��������D���ɐ��͑��݂ɑ��̋ɂ��݂�����̋ɂ̐��������ɂ��Ă���̂ł���C���̌���ɂ����Ď��R�͑S�̂Ƃ��Ă˂ɂЂƂȂ̂ł���D
- ���̎��R��������ҁidas
Unbedingte�j�Ƃ��Ă��悤�ɁC��������E�������Ȃ��_�I�ȑ��݂ł���C�݂�����̂����ɐ��_�iGeist�j��L���Ă��āC���_�̈ӎ��I�ȍ�p�Ƃ̕��ɓI�ȊW�ɂ����Ă݂�����ł��邱�Ƃ��ł���D�܂�C���R�Ƃ������E�́C�ӎ��Ƃ�����ϓI�ȓ����Ƃ��̍�p�ɂ���đΏۉ������q�ϑ��݂Ƃ̓�ɐ��ɂ���Đ������Ă����̂ł���C�]���̓N�w�́C���̕��ɂ̂�������C���_�Ǝ��R�C�ӎ��ƑΏہC��ςƋq�ρC����Ɣ��ȂǂƋ�ʂ��Ă����̂ł��邪�C���_�Ǝ��R�Ƃ͖{���͓���̂��̂ł���C����̐��E�̒P�Ȃ�2�̋ɂɉ߂��Ȃ��D���R������ꂤ�鐸�_�ł���C���_������ꂦ���鎩�R�ł���D
- ���R�Ɛl�Ԃ͂��Ƃ��ƈ�̂̂��̂ł������̂����i���̂悤�ȓN�w���u����N�w�v�Ƃ����D�X�s�m�U�̓N�w������N�w�ł���D�t�B�q�e�̏ꍇ�́C���̎���Ɣ�䂪�Η����Ă����j�C�ߑ�I�ȗ������i�u���ȁv�ɂ���āj�����������Ă��܂����D���R�Ɛ��_�̈Ⴂ�́C���I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ʓI�Ȃ����Ȃ̂��D�܂�C�V�F�����O�ɂ��ƁC���_�̒��ɂ����R�I�v�f�͂���C�����ϔO�I�Ȗʂ����������ŁC�t�Ɏ��R�̒��ɂ����_�I�ȗv�f������C�������R�I�ȗv�f�����������Ȃ̂��D�t�B�q�e����ΓI�Ȏ���̒��ɂ����F�߂Ă�����Ύ҂̊ϔO��O�ꂳ���C�����ʓI�ȓ��ꐫ�Ƃ��đΏۂ̑��ɂ��y�ڂ����̂ł���D�����āC�ߑ�m���ɂ���Ă킩���ꂽ�����̓��ꐫ�́C�|�p�Ȃǂ́u���ρv��ʂ��ĉ����C�ƃV�F�����O�͌����D�������āC����̃V�F�����O�͏@���I�Ȏv�z�ւƌX���Ă����D
- ��2�� �w�[�Q���iGeorg Wilhelm Friedrich
Hegel�C1770�`1831�j
- �i1�j ���̈�v
- �j�R���E�X�E�N�U�[�k�X�iNicolaus Cusanus, 1401�`64�j�͐_�����̈�v�icoincidentia oppositorum �j�Ƃ��Ĕc�������D�ނɂ��ƁC�_�́u��ΓI�ɍő�̂��́v�ł���C���̂����ɂ́C���ׂĂ̂��̂���܂����D�����ł́C�ő�Ȃ��͍̂ŏ��Ȃ��̂ƈ�v����D�u��ΓI�ɍő�Ȃ��́v�ɂ́C�ǂ�Ȃ��̂��Η������Ȃ��̂ŁC����͐�ΓI�Ȉꐫ�ł���D��ΓI�Ȉꐫ�͂��ׂĂ̂��̂��܂���D
- �_�ɂ����邱�̂悤�Ȕ��̈�v�𗝉����邽�߂̎�����Ƃ��āC�N�U�[�k�X�͑����̊w�̗�������Ă���D���Ƃ��Ζ�����̉~�̉~���͋Ȑ��ł���C�܂������ł���D�O�p�`�̂ЂƂ̊p��2���p�ɖ����ɋ߂Â��Ƃ�3�̕ӂ͂ЂƂ̒����ɋ߂Â��̂ŁC�O�p�`�͒����ł���D�ނ̂��̂悤�ȍl���́C�w�[�Q���ُؖ̕@�ɋ����e����^�����D
- �i2�j �^�Ȃ���̂͑S�̂ł���
- �͂��߃w�[�Q���́C�V�F�����O�Ɠ��l�ɁC�J���g�C�t�B�q�e��̎��䂩��o������N�w�ɂ������āC���݂ɐ�s������̂́C�ʓI�Ȃ��́C����ł͂Ȃ��C���ׂĂ̌ʓI�Ȃ��̂��܂�ł������ՓI�Ȃ����ł���ƍl�����D�����ŁC�V�F�����O�ƈقȂ�w�[�Q���́C���̂悤�ȕ��ՓI�Ȃ��̂��C�����ʂƍl�����C���W�ƍl����D���Ȃ킿�C��ʂ̌�������Ɋ܂��C�������g���J�����āC���R����ѐ��_�̐��E�ɕ\�������L���Ȍ����ƂȂ镁�Վ҂ƍl����D�����ŁC�w�[�Q���̎咘�w���_���ۊw�x�iDie
Phaenomenologie des Geistes�C1807�j�ɏq�ׂ��Ă���u�^�Ȃ���́v�Ɋւ���2�̃e�[�[�����Ă݂悤�D
- �@ ������E����v�_�́C�^�Ȃ���̂������P�Ɏ��̂Ƃ��Ĕc�����C�\�����邾���ł͂Ȃ��C�S�����l�Ɏ�̂Ƃ��Ă��c�����\������Ƃ������Ƃł���D
- �A �^�Ȃ���̂͑S�̂ł���D�������C�S�̂Ƃ́C�������ȓW�J��ʂ��ČȂ�����������݂̂��Ƃɑ��Ȃ�Ȃ��D
- �w�[�Q���́C�S�̂��u�ЂƂ́v�P���Ȏ��̂ł͂Ȃ��C�L�@�̓I�ȕ����̌n�ł���Ƃ����D���Ȃ킿�O���I�ȌX�̎����͂�����x�̎��ݐ��������C����́u�S�́v�̒��ɂ����ĊW�Â����Ă���̂ł���D�p�����j�f�X�́C���̂͂ЂƂ����Ȃ��̂ŁC�^����ے肵���킯�����C�w�[�Q���̎v�z�ł͐��E�����I�Ȃ��̂ł���D
- �V�F�����O�N�w�ɂ����Ă��C���Ƃ��w�[�Q�����w���_���ۊw�x�̏����ɂ����Ĕނ�ᔻ���Ă���̂́C���̐�Ύ҂̗��O�ւ̓��B�̎d���Ɛ�Ύ҂��ʂȂ��̂ƍl����l�����C�����ăV�F�����O�̌����͎��ȓW�J�I�łȂ��C���łɏo���オ�����}���i�ϔO�Ǝ��݂Ƃ̑Η��j�����܂��܂ȑΏۂւƓK�p����d���ł���D�V�F�����O�ɂ��ƁC��Ύ҂̗��O�ɓ��B����̂����ړI�Ɂu�m�I���ρv�iintellektuelle
Anschaunuung�j�������Ă�����@�ł���C����ɂ������ăw�[�Q���́C��Ύ҂ւ̓��B�́C���ۊw�̂����ň������i�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����D�����āC��Ύ҂͂��̂����ɏ���ʂ̑̌n����ݓI�ɒ藧���Ă���ƍl�����D
- �w�[�Q���ɂ����ẮC�Η��͂��łɕ��Վ҂̂����Ɋ܂܂�Ă���C���ꂪ���ȓW�J���Ă����̂ł���D�ł̓w�[�Q���́C�����ɂ��āu�^���v���\���ƍl�����̂��낤���D
- �i3�j �ُؖ@
- �ُؖ@�iDialektik�j�Ƃ́C�^���̓��I�\���𖾂炩�ɂ��邽�߂ɂ�����@�ł���D�܂��C����e�[�[�i�藧�C���j�𗧂Ă�D�����Ă���ɂ�������A���`�e�[�[�i���藧�C���j�����D���̌�C�e�[�[�ƃA���`�e�[�[�̓��e���ۑ������܂��C�����ꂷ��C����ɍ����̊T�O�̃W���e�[�[�i�����C���j�Ɏ���D���̂悤�Ȑ��|���|���Ƃ�����v���Z�X���~�g�iaufheben�C�A�E�t�w�[�x���C�g���j�Ƃ����D
- ���̂悤�ɂ��ē���ꂽ�W���e�[�[�ɂ������āC�ĂуA���`�e�[�[�����Ă��C�܂��C���̃W���e�[�[�ɓ��ꂳ��C�Ƃ����悤�ɁC�����̔F���͂�荂�x�ɂȂ�C�u�^�Ȃ���́v���Ȃ킿�u�S�́v�߂Â��Ă����D�����Ă��̎��C�S�̂́C�������C���̏��i�K�ɂ�����e�[�[�����̒��ɕۑ����Ă���̂ł���D
- �i4�j ���Ȉӎ��Ƃ��Ă̐��_
- �w�[�Q���ɂ��C��ʂɐ��_�̐��_����䂦��́C���̂ꎩ�g��m���Ă���Ƃ������ƁC�܂����Ȉӎ��Ȃ������o�ɂ���D�������C���_�͂��̂͂��߂���C���Ȏ��g�����S�ɒm������Ă���킯�ł͂Ȃ��C���܂ꂽ����̐��_�͂����܂ʼn\�I�Ȏ��Ȉӎ��ł���C����鐸�_�ł����Ȃ��D���̖���鐸�_���ڊo�߁C�\�I�Ȏ��Ȉӎ������������Ă䂭�Ƃ���ɂ��̖{��������C���_�̑��݂Ƃ́C���_�����_���Ȃ����̐����̉^���ɑ��Ȃ�Ȃ��D�����āC���_�̂��̎��o�́C�J���g�̂悤�Ɏ������g�̂����ɕ������莩�ȂȂ���Ƃ����d���ʼnʂ��������̂ł͂Ȃ��D���_���^�Ɏ��Ȃ�m�낤�Ǝv���Ȃ�C���_�͂ނ��뎩�Ȏ��g���o�āC�O�I���E�ɓ��������C�����ɉf���o����Ă��鎩�Ȃ�����ׂ��Ȃ̂ł���D���̐��_�̊O�I���E�ւ̓����������u�J���v�iArbeit�j�ł���D
- ���̘J���ɂ���ĂȂ����_�����Ȉӎ��ɂȂ�̂ł��邩�D�܂�C�u�J���v�Ƃ́C���ȁi���j�����ȈȊO�̂��́i���j�ɓ��������C��������Ȃ̖]�ތ`�ɕς��邱�Ƃł���i���j�D�܂�C�J���̎�̂́C�J����ʂ��āC����ΑΏۂ̂����Ɏ��Ȃ��ڂ�����C���ȊO���iSelbstveraeusserung�j����̂ł���D���̎��C�Ώۂ́C��̂ƑΗ�������̂ł��邩��C��̂̎v���܂܂ɂȂ���̂ł͂Ȃ��C���̂��߂ɂ́C��̎��g���ς��Ȃ���Ȃ�Ȃ��D���Ȃ킿�C�J���ɂ����āC�J���̑Ώۂ����̎p��ς���ԁC���̘J���̎�̂��ω����Ă����̂ł���D�����ĘJ�����������C�J���̎�̂��Ώۂ̂����Ɏ��Ȃ��O�����C�����ɂ�����̂�̕��g��F�߂���悤�ɂȂ����Ƃ��C���̎�͎̂����̂����Ă����\���́C���Ȃ��Ƃ����̈ꕔ�����������C���Ȃɂ���Ă͒m�邱�Ƃ̂ł��Ȃ��������Ȃ����o����̂ɂ�����ł���D�܂�C�w�[�Q���̌������o�Ƃ́C�J���������Ă̎��Ȏ����ł���C�������āC�J���̎�̂͑Ώۂ̂����Ɏ��Ȃ̕��g�����邱�Ƃ��ł���D���ꂪ�C
- ���҂ɂ����Ď��Ȏ��g�̂��Ƃɂ���D
- �Ƃ������Ƃł���C���_�͂��傫�Ȏ��R�邱�Ƃ��ł���D�������C�J�������������Ƃ��ɂ́C���Ȏ��g���ω����Ă���킯�ł��邩��C�J���ɂ���Ď����������Ȃ͘J�������������Ƃ��̎��Ȃł͂Ȃ��D�����ł���͂ӂ����ѐ��_�ɑΗ�������̂Ƃ��Č���Ă���D���̂悤�ɁC���_�́C�J���ɂ��C���|���|���Ƃ����ُؖ@�I�v���Z�X���o�Đ������Ă����D
- �i5�j ��ΐ��_
- ���̂悤�ɂ��āC���_���ُؖ@�I�ɐ������Ă����C�ŏI�I�ɊO�E�ɐ��_�ƑΗ�������̂��Ȃ��Ȃ�C���_�����ׂĂ̂��̂̂����Ɏ��Ȏ��g�����C���ׂĂ̂��̂ɂ����Ď��Ȏ��g�̂��Ƃɂ��肤��悤�ɂȂ����Ƃ��C���_�͐�̎��R���l�����C�u��ΐ��_�v�ider absolute Geist�j�ƂȂ�C���j����������D
- �w�[�Q���ɂƂ��āC���j�Ƃ́C��ΐ��_����ΐ��_�Ƃ��Ď��Ȃ����o����C���Ȏ�������v���Z�X�Ȃ̂ł���D���Ȃ킿�C�w�[�Q���ɂƂ��āC�u�J���v�Ƃ͈�ʓI�ȈӖ��̘J�������ł͂Ȃ��C���j�I�Ȏ��ƁC�A���N�T���_�[�剤�̓���������C�t�����X�v���C�i�|���I���̃C�F�i��̂��u�J���v�ł���C��ΐ��_�̎��Ȏ����̉ߒ��Ȃ̂ł���D
- ���Ȃ݂ɁC�w�[�Q���́C�ނ̎���͂���������ΐ��_����ΐ��_�ƂȂ���j�̍ŏI�i�K���ƍl���Ă����D�ނ̓i�|���I�����u���E���_�v�ƌĂ�ł���D
- �������āC�l�ԗ����̓f�J���g����͂��܂�J���g���o�āC�w�[�Q���ɂ�������ɒ��z�_�I��ςƂ��Ă̈ʒu�����S�ɕۏ����D���̂��Ƃ́C�w�[�Q���̒����w�@�N�w�u�`�x�̏����ɂ���
- �����I�Ȃ��̂͌����I�ł���C�����I�Ȃ��̂͗����I�ł���D
- �Ƃ������t�ɒ[�I�ɕ\�킳��Ă���D����͂܂�C�����̔F�߂���̂����������ɑ��݂��錠���������C���������Č����ɑ��݂��邷�ׂĂ̂��͍̂����I�ł���C�����ɂ���ČG�Ȃ��F�����ꂦ�C�����I�ɉ������ꂤ��C�Ƃ����Ӗ��ł���D
�J���g�̖�����
��܂��܂�����������Q�ƈ،h�Ƃ������āA�S���[�������̂������B�V��̐��ƒn��̓�������i����H�����ᔻ��j
��l�Ԑ����A��ɖړI�Ƃ��ėp���A�����ĒP�Ɏ�i�Ƃ��Ă̂ݎg�p���Ȃ��悤�ɂ��棁i������`����w���_��j
����N�͎�����N�w���w�т͂��Ȃ��ł��낤�B�����N�w���邱�Ƃ��w�Ԃł��낤��A�����v�����A����T�����A����̋r�ŗ��āI��i����H�����ᔻ��ŏI�߁A�����j
�@�J���g�͔ӔN�̂P�V�X�R�N�A�@���_�W��P�Ȃ闝���̌��E���ɂ�����@����������������A���ꂪ�{��q�t�̊�ɐG��āA���V�S�N�A�V�P�̃J���g�͒��߂ɂ���g���߂������ꂽ�B�ᔻ���_�̉s�����N���������ł������B�h�C�c�ł́A�N�w���邱�Ƃ͢�v����܂肬�肬��̍s�ׂ������B�i��������������S�I��j
��5�� �}���N�X��`
��3�� �J���g�ڎ�
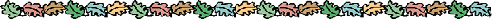




 (���_�D����)
(���_�D����)


![]()
![]()
![]() (���_�D����)
(���_�D����)