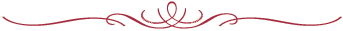
| 阿波踊り連考 |
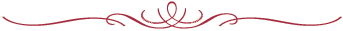
更新日/2022(平成31.5.1栄和改元/栄和4).8.15日
| (吉備太郎のショートメッセージ) |
| ここで、「阿波踊り連考」をものしておく。「阿波踊りの歴史」その他参照。 2016.2.22日 吉備太郎拝 |
![]()
| 【阿波踊りの有名連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賜天覧(してんらん)は数ある阿波おどり連でも数連しか名乗れない。その理由は、昭和25年3月、昭和天皇、皇后両陛下が御来県し、天水連、藤本連(現蜂須賀連)、のんき連、娯茶平連が、天覧踊りを披露したことに由来している。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿波おどり振興協会、徳島県阿波踊り協会等に加盟する阿波踊り連33連を「有名連」と呼ぶ。これを確認しておく。
|
| 【他にもあるよ連】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【阿波踊りのその他の連】 | ||||||||||||
| 阿波踊りを踊る団体・グループのことを「連」という。連には、地域住民などで構成された一般連や阿波踊り振興協会などの団体に加盟する有名連、学生で構成される学生連、企業で結成した企業連など、大小さまざまな連がある。阿波踊りの醍醐味のひとつは、各連の演舞や衣装、演奏を楽しめることだ。 | ||||||||||||
|
| 【阿波踊り連&所属協会】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【全国に広がる阿波踊り】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿波踊りは徳島県内各地で阿呆踊りが披露される。中でも、「徳島市阿波おどり」が本場であり、最大の規模を持ち観光入込客は120万人を超えている(徳島県平成27・28年度発表)。これは国内最大規模にあたる。県内の他の市町村各地でも次のように開催されている。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在は全国各地で次のところで阿波踊り祭りが開催され、それぞれの地域の連が徳島の連とのつながりを深めたり、徳島から各地に阿波おどりの伝統を伝える動きが活発化している。徳島は本場として正調阿波踊りを受け継ぎながらも新たな可能性を探り、次の世代へと阿波おどりの魂を引き継いでいく模索が続けられている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海外
|
| 【阿波おどり協会考】 |
| 2017.6.29日、阿波踊りの本家大名連(70人)が、所属していた徳島県阿波おどり保存協会を脱会し新団体「阿波おどり伝承会」を立ち上げた。県外連の受け皿づくりなどが主な目的という。清水理(さとる)連長(69歳、徳島市南佐古四番町)が5月に保存協会に脱会を申し出て、6月1日に開かれた協会の理事会で承認された。当面、本家大名連のみで伝承会を運営しながら、県内外の踊り連に加入を呼び掛けていく。所属連同士の交流に力を入れ、県外にも積極的に出向いて踊るという。清水連長は「世界に通じる伝統芸能である阿波踊りの魅力をさらに発信する取り組みをスタートさせたかった」と話している。
本家大名連の脱会で保存協会の所属連は7連となった。徳島市内には他に、有名連17連でつくる県阿波踊り協会と16連でつくる阿波おどり振興協会がある。 |
| 【棟方志巧(Shiko Munakata1903-1975)と阿波踊り】 |
| 棟方志巧〈一九〇三~一九七五〉 1903(明治36).9.5日、青森市で代々鍛冶職を営んできた父棟方幸吉・母さだの三男として生まれた。青森市内の善知鳥神社でのスケッチを好んだ。 1921年、ゴッホの「ひまわり」を見て画家になろうと決心する。 1924(大正13)年、東京へ上京する。帝展や白日会展などに油絵を出品するが落選が続いた。 1928(昭和3)年、油絵「雑園」が第9回帝展に初入選し、平塚運一と出会い版画を始め版画誌「版」の同人となる。第8回日本創作版画協会展、第6回春陽会展に入選。油絵「雑園」で帝展初入選。 1930(昭和5)年、文化学院で美術教師を務める。 1932(昭和7)年、日本版画協会会員となる。 1934(昭和9)年、佐藤一英の詩「大和し美し」を読んで感動、制作のきっかけとなる。 1935年、国画会会友に推挙される。 1936年、第11回国画展に「大和し美し」板画巻を出品。これが契機で、柳宗悦、河井寛次郎、濱田庄司らの民芸運動の人々と知り合い、以降の棟方芸術に多大な影響を及ぼし棟方志功の世界を一段と飛躍させた。 1938(昭和13)年、35歳の時、第2回文展に「善知鳥(うとう)」板画曼荼羅を出品し、官展への版画の出品作として初めて特選を受賞。 1939年、「釈迦十大弟子」を制作。 1945(昭和20)年、戦時疎開のため富山県西礪波郡福光町(現南砺市)に移住。 同年8.15日、敗戦により終戦。戦後も名作を次々に発表する。 1946(昭和21)年、富山県福光町栄町に住居を建て、自宅の8畳間のアトリエを「鯉雨画斎(りうがさい)」と名付けた。また住居は谷崎潤一郎の命名によって「愛染苑(あいぜんえん)」と呼んだ。現在は栄町にあった住居を移築保存し、鯉雨画斎として一般公開している。 1952年、スイスのルガノ国際版画展で優秀賞受賞。 1954(昭和29)年、この年まで富山県西礪波郡福光町に在住した。志功はこの地の自然をこよなく愛し、また多くの作品を残した。 1955(昭和30)年、ブラジルの第3回サンパウロ・ビエンナーレ版画部門最高賞受賞。 1956(昭和31)年、「湧然する女者達々」がイタリアの第28回ベニス(ヴェネツィア)・ビエンナーレ版画部門で日本人として版画部門で初の国際版画大賞を受賞。棟方志功の作品は日本のみならず世界各国で高い評価を受け「世界のムナカタ」の地位を確立した。 1956(昭和31).12.15-17日、「棟方志功芸業展」(徳島芸術鑑賞会主催)が徳島市憲法記念館で開催され、16日夕方、展覧会に合わせ来徳。志功は徳島市建設会館で開かれた座談会に出席。次のようなことを語っている。 「私が板画を始めたのは伊原宇三郎画伯にすすめられたのがキッカケです」、いっそ絵をやめて人のやらないものに手を出したら、との伊原の言葉が板画を始める契機になったという。なお、この来徳で志功は徳島新聞夕刊に「歳末徳島」を五回連載(12.18日~28日)したり、貞光へ講演会に行ったりもしている。 この年12月の冬の晩、志功が宴会の二次会で言問の料亭を訪れた。「塩かれ声で、こんな分厚い眼鏡を掛けて」とお鯉さんが志功の風貌について語る。 「熱い燗がお好きな方でした」。お鯉さんは志功のリクエストに応じて阿波風景やよしこのを唄った。お鯉さんとめぐりあった志功はうれしくなった。鮮やかな墨色の美しい躍鯉を捧げるに、お鯉さんほど相応しい人はいなかった。頃合いを見て「先生一筆、って申し出てみたら、『ヨシッ』って」。 志功はちゃぶ台スレスレに顔を近づけて、一気に、奔放に、三枚もの色紙を書き上げた。肉筆作品(志功の、いわゆる「倭画」)になる「女人図」には「爲言問大主人」の為書と「花深処」の字句を添える。芳醇で豊艶な女人にはお鯉さんの面影が重ねられていたかもしれない。「裸の女のひたいに丸い星をつければ仏になる」と語っていた志功に、お鯉さんは妙なる音楽を奏する菩薩に映った。 「わが胸の想ひのごとに舞いめぐる 土佐の白鷺 けわし しろさぎ」。志功も酔いが回ったのか「土佐」の歌となっている。もう一枚は躍り跳ねる鯉魚の図。余白には造形的な文字により、いろは歌をみっしりと書き込む。志功の倭画には「御群鯉図」や「御躍鯉図」等、鯉魚をモチーフとしたものが数多い。拓摺の「夢応鯉魚版画柵」もある。 棟方志功は江戸浮世絵の美人画「大首絵」に興味を持ち、1956年の作品「鍵板画柵」以来、多くの女性画作品を制作している。ほんのりと頬を赤く染めた吉祥天女は、ふくよかでとても女性らしい美しさを抱いている。 1960年、日展評議委員となる。左眼を失明。日版会を設立。 1963年、紺綬褒章を受章。倉敷の大原美術館に棟方館完成。 1969(昭和44).2.17日、青森市から初代名誉市民賞を授与される。 1970(昭和45).8月、万博ム-ドに湧く阿波踊りに招待され、「やっと念願果たせた/棟方さん大浮かれ」と徳島新聞で報じられている。 「黒色の足駄、赤と白の鼻緒、それに足のつま先で立っている姿がいいですね(中略)今後の作品に阿波踊りが入ってくるのが当然であり、必然であると思います」。 この年、文化勲章受賞する。文化功労者に顕彰される。毎日芸術大賞受賞。 1972(昭和47).4.6日、「南海道棟方板画」準備のため徳島を訪問、翌7日、初代天狗久の碑を訪れた後、高知へ向かった。 この年制作の「南海道棟方版画」は、翌年度安川電機カレンダーのための作品で、徳島を題材としたものに二月「天狗久彰碑の柵」、三月「阿波の木偶の柵」は中西仁智雄の『阿波の木偶』への感動、また「阿波おどりの柵」は一昨年の印象に拠って制作された。 1975(昭和50)年.9.13日、東京の自宅で肝臓癌のため逝去(享年72歳)。青森市に棟方志功記念館が開館する。 棟方志功は生涯、故郷の青森を愛し続けた。ねぶた祭りや美しい自然のある青森への思い、望郷の思いを胸に、なくなるまで旺盛な制作活動を続け、比類なき棟方芸術を創出した。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)