徳島の夏を彩る阿波踊り。本番を前にして夕方になると町のあちこちから独特のお囃子の音が聞こえてくる。徳島の人たちには小さい頃から身近に阿波踊りがあり、知らず知らずのうちに体に染みついている。阿波踊りの音色が聞こえて来ると自然に浮き浮きしてくる。
阿波踊りは踊り手と鳴り物の競演である。共通しているのは、七五七五調二拍子の独特のリズムと、それを伴奏する鳴り物に合わせての踊り、踊りを浮かせるお囃子、掛け言葉である。鳴り物は鐘(鉦鼓、しょうこ)と太鼓と篠笛(しのぶえ)と三味線の和楽器からなる。各楽器がそれぞれの役割を果たしている。大太鼓は腹の底まで響きわたる躍動感で盛り上げる。この音色がどのようにしてできあがつたのかは分からないが、いつ聴いてもテンションが上がる名調子になっている。
踊り手は連(れん)と呼ばれる踊り手の講集団に属しており、いわば連舞となっている。各連は、年齢、性別、職業等の様々な組み合わせからなり、ご縁で結ばれている。その連仲間が連特有の型を踊る。踊り手は天水とも呼ばれる。阿波踊りに絶対的な正調はない。正調はあるようでない、ないようであるという神様問答に似たものになっている。この合意のもとに各連ごとに趣向をこらし踊り方や演出を作り上げている。その為、連ごとに踊り方が違う。どの連も男踊りと女踊りに分かれて踊りを演出している。数十人もの天水が一糸乱れず鳴り物と息を合わせて揃った型を踊り、表現力、統一感、優雅さ、ダイナミックさなどを競っている。
連で皆が心を合わせて踊るときに生まれる一体感は至福の楽しさで、自ずと連に対する帰属意識や誇りが生まれて来るようになっている。各員は、その型踊りの中で自分の踊りをパフォーマンスする。天水たちは、連の型を乱さない範囲で思い思いに踊ることが許されている。してみれば、阿波踊りは型に捉われながら且つ自分の踊りを演出する個性を表現する舞台でもある。阿波踊りの楽しさは踊ることそれ自体にあり、天水たちは踊りを通じて祭り特有の解放感(カタルシス)を味わう。自分たちが楽しむばかりではなく、磨き上げられた技術を観客に披露し、喜んで(時には驚いて)もらうことにも楽しみを感じている。観客の視線や反応が自分たちの踊りの励みにもなっている。これらの「競い」が見る側、踊る側の双方に余慶に楽しさをもたらす。阿波踊りを見る者までもが興奮に巻き込まれ、初めての方の中には鳥肌を立たせられる者もいる。私も私のオヤジもそうだった。
「阿波よしこの」歌は次の通り。
エライヤッチャ エライヤッチャ ヨイヨイヨイヨイ
踊る阿呆(あほう)に見る阿呆 同じ阿呆なら踊らな損々…
ア、ヤットサァー ァ ヤットヤット♪
ヨイサー ヤットサー
ヤットサーヤットサー
ア、ヤットヤット
ヤットサー、ア、ヤットヤット
「エライヤッチャ」には、関西弁で言うところの「えらいこっちゃ」みたいな感じの「大変だ」という意味がある。活気づけや、気合いを入れる意味合いがある。同じく関西弁の「どえらいやっちゃ」の感じで「すごいやつだなぁ」という意味もある。転じて「がんばってるなぁ」という意味で、お互いを認め合い励ます言葉としての意味もある。幕末の「ええじゃないか騒動」に由来する「ええじゃないか」を煽る意味も込められていると云う。「大変なことだがへこたれんぞ平気だぞ」と云う意味にもなる。「ヤットサ ァ ヤットヤット」には、「久しぶり、元気だった?」と言う意味が込められている。
女踊りでよく聞く囃子ことばには次のようなものがある。
ひょうたんばかりが浮き物か
私の心も浮いてきた
浮いて踊るは阿波踊り
一かけ二かけ三かけて
四(し)かけた踊りは止められぬ
五かけ六かけ七かけて
八(や)っぱり踊りは止められぬ
ア、ヤットサー、ア、ヤットヤット
笹山通れば笹ばかり
石山通れば石ばかり
猪豆喰うて ホーイホイホイ
新町橋までいかんかコイコイ
お先のお方におまけなや
私しゃ負けるの大嫌い
わたしゃ負けるの大嫌い
負けてお顔が立つものか
ヤットサー ヤットヤット
徳島県内の小・中・高校では体育の授業や体育祭などで「阿波おどり」を演目として採用している学校も多数あり、徳島県民の代表的な祭りである。
|
| 阿波踊りは日本のみならず世界に誇る踊りであり、その発祥が阿波の徳島の宝であるところから徳島県民の誇りとなつている。世界ではブラジルのリオのカーニバル、ハワイのフラダンスが名高いが、阿波踊りはそれらに匹敵するどころか遜色ない優るとも劣らない世界最大級のダンスフェスティバル伝統芸能である。芸術的により高い境地を開拓しているとも評されよう。 |
| 阿波踊りを意義づければ、先祖や同胞を敬い、ここまでの命の繋がりを感謝し、これからの命の繋がりを祈念し、老若男女が今現在共に生きている喜びを表現する踊りと云えよう。踊る者と見る者が一体となって共に楽しみ、今年も踊りができる平和を謳歌し、互いの繁栄を願い、徳島市中心街一円を踊りの渦に巻き込み興奮のるつぼと化すところに特徴がある。 |
| 阿波踊りは、徳島城下の町人百姓たちが藩の禁止触れにも拘わらず伝統を守り抜き、時に応じて創造性を加えつつより楽しくより明るいものに仕上げていって今日に至っている。伝統の民衆芸能そのものの踊りです。この踊りには思想があり約束ごともある。但し、他の芸能にありがちな正調規律はない。あるのは阿波踊りの精神、リズム、囃子、鳴り物音曲であり、その土俵上で各連が自由自在自律的に連の踊りを創造し競い合うかのように演舞している姿が認められる。 |
| 「日本三大盆踊り」は、阿波おどり(徳島市)、徹夜踊りで知られる郡上おどり(岐阜県郡上市)、西馬音内盆踊り(秋田県羽後町)。「日本三大流し踊り」は、阿波おどり(徳島市)、郡上おどり(岐阜県郡上市)、黒石よされ(青森県黒石市)。どちらにも阿波踊りが選ばれている。 |
| 江戸時代から庶民に親しまれてきた阿波人形浄瑠璃も徳島の伝統文化である。いまなお徳島各地の神社の境内には、「農村舞台」と呼ばれる浄瑠璃のための舞台が作られており、車も入らないような山奥の神社で見る、木偶人形の踊りと三味線の響き。そしてストーリーに合わせて動くカラクリ舞台は、数百年前から変わらずに人々を楽しませている。 |
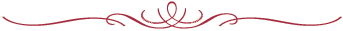
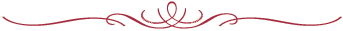
![]()
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)