| 【阿波踊りの歴史考】 |
| 昔の阿波踊りは、能面を被って踊るのが当たり前だった云々。 |
| 江戸時代、蜂須賀の歴代の藩主は、この「ドンチャンドンチャン踊り」(阿波おどりの呼称は昭和に入ってから)の熱狂が一揆につながることを懸念し何度も踊りの禁止令を出している。しかし、阿波の民にとっては古からの伝統踊りとして身に染みて継承されていたので、阿波っ子たちの心に流れる阿波おどりを完全に絶やすことはできなかった。このことが今日の隆盛をもたらしている。特に戦後の阿波おどりの復興ぶりは目ざましく、今日では日本を代表する民族舞踊の地位を確保している。 |
| 徳島藩による城下の盆踊り対策は、建て前のきびしさに対して本格的に取締ることは諸般の事情によって容易ではなかった。とくに宗教的な発生事情をもつぞめき踊りに対してはたびたび規制されているが、実際には「有来りの踊り」と規定して一貫して踊りを禁止することはなかった。 |
| 城下の盆踊りは、町切りを命じると群衆は「新町橋まで行かんかこいこい」と声を揃えて橋をめざした。これは一種の抗議行動であった。文化・文政のころからきびしく禁じられたのが笹踊りである。笹踊りは盆だけでなく神社の祭礼にも演じられていたもので、歌舞伎風の衣裳で寸劇を演じたり、仮装や裸体の演技を披露することで、広儀には俄踊りの範疇に属するといわれている。風俗の乱れに神経質であった藩としては、盆踊りに混乱を持ち込むことを恐れてきびしく禁止していた。しかし、笹踊りを実際に取締った事例は幕末の史料でしか確認することができない。 |
| 17世紀の中頃、城下の内町や新町の町人たちを氏子とする春日神社の祭礼に、各丁が組踊りをくり出して競演していた。この踊りは中世の細川・三好氏の本拠であった勝瑞城下で盛行していた風流踊りを復活したものである。この組踊りが盆行事に移されると、城下全域に波及し大踊りなどといわれ大いに人気を博した。但し、この踊りは豪華絢爛で見物する人びとを幻想の世界に誘うような芸態を特色としていたことから、財政再建をめざすたびたびの藩政改革などのとききまって禁止されるなどの措置がとられる宿命を負っていた。そのたびしばしば中断されているし、明治維新以降は盆踊りの市中から組踊りの姿が消えた。 |
| 元禄期を中心とする18世紀前半は、わが国の衣料革命の進行を背景として阿波藍の需要が急増し、藍商たちは大坂や江戸をはじめ各地の市場に進出して藍玉の売り込みに奔走した。藩内の農村は藍生産を増大させた。その栽培には大量の金肥を必要としたので、肥料商の活動も活発となるなど徳島城下は藍商や肥料商などの積極的な活躍によって活況を呈した。これら新興商人の台頭により各地の芸能が伝播された。そのうちもっとも注目されるのが俄踊りの流行だった。18世紀以降の城下の盆踊りは、伝統的なぞめき踊りと盆行事に移行した組踊りのほか、手軽に演技できる俄踊りという3種の踊りが併行して互に影響しながら盆踊りを盛り上げていた。但し、この俄踊りも明治後半の日清・日露の戦間期になると、各種の大衆娯楽の普及によって、次第に新鮮な魅力を失って、急速に衰退していった。 |
19世紀に入ると城下に藍大市が建てられるようになり、各地から良質の藍玉を需めて顧客が殺到した。その接待の場となったのは色街であり、そこは諸国の芸能を受容され、それに創造を加えて阿波の諸芸として再生産された。ぞめき踊りの変遷や俄踊りの波及にも色街の果たした役割が大きかった。
そのような芸能風土の形成は、とくに三味線の普及を契機として、城下の商家などでは娘たちに三味線を習わせることが流行するため、三味線の稽古所が続々と出現する。少し弾けるようになると発表の場が欲しくなり、その場が盆中の三味線流しとなった。親たちが競って娘に華麗な衣裳を着せて送り出し、自慢の種にしたという。こんな盆の市中を彩る情緒が定着していたのも、阿波が芸所であることを自然に表現する珍らしい行事の一つであった。 こうしてそのような多彩な盆踊りを演出したのが色街であった。色街の果たした役割や阿波踊りを演出した機能が評価されねばならない。 |
| 一方、文化・文政期に豪商としてならした藍商人たちが全国各地との文化交流の担い手となり、各地のさまざまな要素が阿波おどりに取り入れられた。阿波おどりのリズムは、奄美・八重山の「六調」、沖縄の「カチャーシー」、九州の「ハイヤ節」、広島の「ヤッサ節」などとの共通点が多く、南方に端を発する「黒潮文化のリズム」とされることがある。また「阿波よしこの節」は、茨城県の潮来節が元になっているとされている。こうして、阿波おどりは日本全国の伝統的な踊りとクロスしている。庶民のパワーによって支えられながら徳島の伝統芸能として定着してきた。 |
| 1830(文政13)年の御蔭詣では徳島城下から始まり、阿波衆は伊勢で「踊るも阿呆なら見るのも阿呆じゃ、どうせ阿呆なら踊らんせ」と囃して踊り狂ったという。この踊りがおもしろいというので大流行し、上方の豊年踊りに転化したとする有力な説がある。「ええじゃないか」は豊年踊りをモデルとしたという説がある。そのような説から考えてみると、阿波では阿波踊りが「ええじゃないか」踊りと混交したのはごく自然なことであった。ただそれまでの阿波踊りは、人形浄瑠璃の太棹が鳴物の主力を占めていたといわれるように若干テンポの緩やかな踊りであったのに対して、テンポの早い「ええじゃないか」の大流行を契機として、阿波踊りもテンポを速め、鳴物の主役も細棹に取り替えられていったとする説がある。実証することはできないが興味深い。 |
1841(天保12)年、徳島阿波藩の中老・蜂須賀一角が踊りに加わり、乱心であると座敷牢に幽閉され、厳封、改易されたとする次の記録が残っている。蜂須賀直孝は10代藩主重喜の子で、幼名は次郎吉、中老の士組頭蜂須賀一学直芳の養子となり、天保元年(1796)6月10日に直芳の死により7月19日に家督相続して士組頭を勤めた。
| 「御老中千石の蜂須賀一角様、昨年七月盆踊りのみぎり(おり)、かねて近年『御家中は踊りの場所へ出候儀は堅く御停止』のところ、抜けて踊るところを見つけられ、乱心に申し立て座敷牢に入れ候ところ、当7月牢を抜け出し讃州白鳥辺りまで参り候を、古物町商人三人参り合せ、御屋敷へ飛脚差し越し、御迎えに参り連れ帰り申すにつき右三人へ金五匁宛の御礼これあり候趣、右につき又々内牢に入れ置き候云々」。 |
蜂須賀一角は乱心扱いで入牢させられたあげくに本人追放、家族は家中預かり、つまり改易に処された気の毒な記録が残されている。 |
| 1844(天保15)年の記録には「組踊り少し、俄は多し、昼夜ともぞめきは例年のごとし、御免許町に野稽古の踊を趣向して、右発願人町役人など皆々御咎を蒙る」と記している。御免許町は西新町5丁目であるが、組踊りに武家社会を風刺する野稽古の踊りを演じたことで、きびしく取締められたというものである。
|
| 1846(弘化3)年、仮装で踊った20人の婦人が捕えられて入牢、その後に市中引廻しという厳罰に処せられたと記録されている。この史料によると坊主姿や半裸の仮装で演じた俄踊りであるが、御免許町の出し物といい、この婦人の俄といい、ともに武家支配を揶揄したり、藩の規制を全面的に無視した踊りであって、当然そこには藩政に対する抵抗の意思が城下の町人層の間に漲っていたという社会状況を象徴している。ここまでくると藩でも黙認することはできなかったのであろう。
徳島城下における盆踊りは時代とともに隆盛をみたが、いよいよ藩の危機が深刻さを増した天保期から幕末期には、踊りも大規模に展開すると、一部には藩の規制強化に対する反発も強まりをみせるようになる。
|
| 1867(慶応3).12月、「ええじゃないか」の乱舞が阿波の撫養に上陸し、翌4年にかけて阿波一円は「ええじゃないか」で浮き立つことになる。当時の数少い記録によると徳島城下では群衆が「ええじゃないか、ええじゃないか、何でもええじゃないか……」と囃しながら勢見の金刀比羅神社に練行し、そこから讃岐の金刀比羅宮や施行の船に乗り込んで伊勢神宮に向う人も多かったことを伝えている。阿波踊りと「ええじゃないか」では囃す文句も踊る所作も異なるが、通底していたとみなすべきだろう。 |
| 1870(明治3)年、版籍奉還後、阿波の盆踊りが中止させられた。その理由は庚午事変の発生にあった。この事件が徳島藩を大きく揺るがした。その翌年、廃藩置県が断行され、明治政府による相次ぐ改革が実施に移されていった。新しい時代を迎えたことによって、阿波の盆踊りが自由になったかと云うと明治初期の史料でみる限り盆踊りに対する統制はかなりきびしい。明治3年の盆踊り中止を始めとして、近代の盆踊りはたびたび中止の措置がとられている。そのような中止の理由について調べてみると、数度の戦争や大正7年(1918)3月の米騒動などのときである。 |
| 明治〜大正期にも、日本文化全体のモダン化に足並みを揃えるかのように、鳴り物にバイオリンなどの西洋楽器が取り入れられたり、派手な縞模様のぱっち(股引)の衣装が流行るなど、近代化した様子がうかがわれる。大正時代に晩年を徳島で過ごしたポルトガル人・モラエスが母国に送った『徳島の盆踊』では、その熱狂ぶりを描写するとともに、古来から続く「死者を敬う踊り」としての精神性を記述している。 |
| 大正期から「阿波おどり」という言葉が使われることはあったが、阿波おどりの発展に尽くした日本画家・林鼓浪が徳島商工会議所(当時は商業会議所)に提案し、昭和に入って「徳島盆踊り」から「阿波おどり」という呼称が定着していった。これは、観光資源として全国に広めていこうという積極的な動きの一つであったためと考えられる。 |
| 1931(昭和6)年、「お鯉さん」こと多田小餘綾がコロムビアレコードで『阿波よしこの節(阿波盆踊唄)』を録音。その名を全国に知らしめるきっかけとなった。 |
| 1937(昭和12)年、の盧溝橋事件を発端とする中国との戦闘開始以来、第二次大戦にいたるまで戦争によって阿波おどりが中止されることが多くなった。 |
| 1941(昭和16)年、封切られた東宝映画「阿波の踊子」(監督:マキノ正博、主演:長谷川一夫)で、徳島で大々的なロケが行われ阿波おどりのシーンでは芸妓たちがエキストラの踊り手として多数参加した。同作が上映された市内の映画館は観客であふれた。 |
| 1945(昭和20)年、徳島はB29による空襲で市内の約62%が焦土となった。 |
| 1946(昭和21)年、終戦翌年、ぽつぽつとバラックが建ち始めた状況の中で阿波おどりが復活した。踊りもまちまちで洗練されたものではなかったが平和への喜びとともに現在まで続く老舗連が徐々に設立されていった。 |
| 1950年代、この頃の阿波踊りの映像記録が残されており、これを見ると、腕は胸までしか上げず、手もだらりと下げて踊っている。 |
| 1957(昭和32)年、東京・高円寺で阿波おどり大会(当初は『高円寺ばか踊り』の名称)が始まり、阿波おどりが全国で開催される嚆矢となる。 |
| 1970(昭和45)年、大阪で開催された日本万国博覧会で徳島合同連が踊りを披露したり、海外遠征が行われるなど、「徳島の阿波おどり」から「日本の阿波おどり」へと広く認知されていった。こうした動きに伴い「見せる阿波おどり」への志向も強まり、昭和40年代は踊りや音が、より洗練された芸能へと変化していった。 |
| 1980年代、これは女踊りのレジェンドと言われる四宮賀代さんが、腕を高くつき上げ、指も点を指すように伸ばし、脚を高くけりあげる、今の阿波おどりのスタイルを編み出し、これが普及した。この「洗練された美」の阿波踊りを「見せる芸術」の域に高め、日本最大の祭りの一つとして人々を魅了するようになった。 |
| さらに、従来の「跳ねるリズム(2拍子、浮き拍子)」だけでなくエイトビートを叩く鳴り物の連も登場するなど、多様化への道も進んでいく。 |
| そして現在、全国各地で阿波おどり大会が開催され、それぞれの地域の連が徳島の連とのつながりを深めたり、徳島から各地に阿波おどりの伝統を伝える動きが活発化している。徳島では本場として正調阿波踊りを受け継ぎながらも、新たな可能性を探り、次の世代へと阿波おどりの魂を引き継いでいく模索が続けられている。守るべきものを守りながらも、時代の変化を取り込んでいく。それこそが阿波おどりの伝統であり、未来へと続いていく力であると言える。 |


![]()
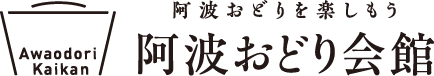
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)