
更新日/2021(平成31.5.1栄和改元/栄和3).12.5日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
ここで、アイヌ史の日本中世史上での関わりを確認しておく。「アイヌ民族の歴史年表」その他を参照する。
2008.5.19日 れんだいこ拝 |
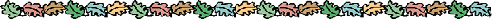
平忠常は、将門公の伯父にあたる平良文(たいらの よしふみ)の孫にあたる人物。現在の千葉県である房総半島の3国のうち、上総国と下総国を支配していた大豪族だった。最南端の安房国を手に入れれば房総半島を完全に支配できた。そこで忠常は安房国を手にいれるために、安房国に赴任していた朝廷の役人、安房守惟忠(あわのかみ
これただ)を焼殺した。「安房守」は官職名。姓はおそらく「平」(たいら)。といっても将門公や忠常の「平」とは全然別系統の平氏。朝廷から直接派遣された役人を殺した忠常は謀反人となった。
1028(長元元)年、平直方(たいらの なおかた)が忠常討伐に派遣された。平直方は平将門公を討ち取った平貞盛(たいらの さだもり)の孫。しかし3年経っても乱を鎮める事ができず、代わりに派遣されたのが源頼信(みなもとのよりのぶ)・源頼義(
よりよし)父子。頼朝の先祖。
1031(長元4)年、頼信父子は乱を鎮め、平忠常は頼信公の家来になる。頼信は一切戦闘行為はしていないらしく話し合いで解決した。まさに江戸城から800年先立った無血開城。
最初に直方が派遣された理由はおそらく直方が忠常と敵対していた常陸国の勢力と関わりが深かったからだろうと考えられる。乱に乗じて忠常を討伐すれば、自分が仲良くしている常陸国の勢力が拡大し、自分も恩恵を受けられる。しかし、忠常は手強かった。直方の代わりに派遣された頼信公に忠常があっさりと降伏したのも、そこら辺の駆け引きがあったと思われる。なんせ頼信公は、かの藤原氏の全盛期を築いた藤原道長殿の直属の部下で「道長四天王」と呼ばれていた方である。坂東のド田舎の豪族にとって、これほど心強い後ろ盾はなかろう。そして、頼信公も忠常を家来にした事で、忠常が持つ坂東の軍事力を統括できるようになった。これがのちに頼朝が鎌倉幕府を開く基盤となった。
平忠常の乱平定後、頼信は相模守となる。そしてこの時に、直方は鎌倉の領地を、頼信の息子・頼義に譲っている。実は頼義と直方の娘が結婚している。頼義と直方の娘の子孫が頼朝になる。つまり頼朝が鎌倉に幕府を開いたのは、先祖伝来の土地だったことになる。加えて……頼朝と婚姻した北条氏は平直方の子孫を自称している。子孫同士でまた結婚したというわけだ。そして、元々鎌倉の所有者であった直方の子孫が再び鎌倉で権力を持ったとも言える。
東北地方と源氏の関係に迫る。「鎌倉殿の13人」13人って誰のこと? 人物一覧
「鎌倉殿」とは鎌倉幕府将軍のこと。「鎌倉殿の十三人」は、鎌倉幕府の二代将軍・源頼家を支えた十三人の御家人の物語です。和樂webによる各人物の解説記事はこちら!
1. 伊豆の若武者「
北条義時」(小栗旬)
2. 義時の父「
北条時政」(坂東彌十郎)
3. 御家人筆頭「
梶原景時」(中村獅童)
4. 頼朝の側近「
比企能員」(佐藤二朗)
5. 頼朝の従者「
安達盛長」(野添義弘)
6. 鎌倉幕府 軍事長官「
和田義盛」(横田栄司)
7. 鎌倉幕府 行政長官「
大江広元」(栗原英雄)
8. 鎌倉幕府 司法長官「
三善康信」(小林隆)
9. 三浦党の惣領「
三浦義澄」(佐藤B作)
10. 「中原親能」
11. 「二階堂行政」
12. 「足立遠元」
13. 「八田知家」
「平忠常(たいらの ただつね)の乱平定」で、坂東(関東地方)は、源頼朝の先祖、頼信(よりのぶ)公によって平和が訪れた。それから約20年の時が流れた。
1048(永承3)年、源頼信公が亡くなり、河内源氏の家督が息子の頼義(よりよし)公に譲られた。
この頃、東北地方に嵐が吹き荒れる! この頃の東北地方には朝廷に従わない勢力である蝦夷(えみし)と呼ばれる者たちがいた。奈良時代から大和朝廷と戦い続けていたが、長い年月の間に蝦夷の中にも朝廷に従うものがでてきた。彼らを「俘囚(ふしゅう)」と呼ぶ。その俘囚の中でも安倍一族が、東北地方で大きな勢力を誇っていた。その安倍一族は朝廷から派遣されてきた国司(こくし=地方行政官。現在の県知事のようなもの)とは折り合いが悪かった。安倍氏は次第に朝廷への納税を怠るようになった。
1050年、多賀城の国司/藤原登任は朝廷に安倍氏討伐をもとめる。安倍頼良は役務を怠り、税金も納めず、衣川を越えて南に支配を拡げようとしていたとされる。
1051(永承6)年、
11月、前九年の役が始まる。朝廷は、陸奥国の国司(陸奥守)藤原登任(ふじわらの なりとう)に命じて、安倍氏を攻めた。
鬼切部(おにきりべ、現在の宮城県鳴子温泉の鬼首(おにこうべ)が合戦の地)で朝廷軍と安倍軍が激突。官軍は散を乱して壊走し安倍氏の勝ち。藤原登任は解任され東北から追い出された。
新しく陸奥国の国司に任命されたのが、源頼義。最初、安倍氏は頼義公をもてなし、仲良くしていた。この頃の安倍氏の長は安倍頼良(あべの よりよし)という名だったが、頼義公と同じ名であることを憚って、頼時(よりとき)と改名している。頼義公が任期を終える直前にイザコザが発生する。
1056(天喜4)年2月。頼義公は安倍氏の所領である胆沢(いざわ)城から国府の多賀(たが)城へ帰る途中、阿久利(あくり/あくと)川で野営をしていた。そこに頼義公の部下である藤原光貞(ふじわらの
みつさだ)が何者かに襲われたという報告が入る。運よく助かった光貞に犯人の心当たりを訪ねるとこう答えた。「安倍頼時の長男・貞任(さだとう)が私の妹を妻にしたいと願い出ていた。けれど俘囚になど嫁にやれんといって拒絶しました。それを恨んだのに違いありません」。頼義公は光貞の主張を鵜呑みにして、検証しないまま貞任を呼び出して処罰しようとした。当然、頼時は息子を守るため、出頭を拒絶。頼義公と安倍氏の仲は決裂した。いろいろとキナ臭い事件だが、当時から陰謀論がささやかれていた。
頼義公は、安倍氏の勢力だった津軽の俘囚を味方につけることに成功。これに慌てた安倍頼時は津軽に向かうが、攻撃を受けて討死してしまう。頼時の後を継いだ貞任との戦が激化する。
1057(天喜5)年11月、源頼義は兵隊1800余りを率いて北上。川崎の柵(東磐井郡川崎村)近くの黄海(きのみ、現・岩手県一関市藤沢町)で衝突。頼義軍は寡兵の上に食料不足で惨敗。戦死者は数百人に達する。源頼義・義家父子はわずか6騎になって貞任軍の重囲に陥るが、かろうじて隙をついて脱出。地の利がある安倍氏に軍配が上がった。命からがら逃げ切った頼義公は、関東、東海、畿内の武士に呼びかけて兵力増強をはかった。1062(康平5)年の春。ついに頼義公の陸奥守としての任期が切れてしまい、戦の途中ではあるが京へと帰ることとなった。
しかし頼義公に従っていた俘囚たちは後任の陸奥守に従わなかった。「東北の内乱を終結させる!」とやる気満々だったが、何もすることができずに京に返るハメになり、再び頼義公が陸奥守となる。再び東北に戻ってきた頼義公は、いままで中立を保ってきた出羽国(秋田県)の俘囚の豪族、清原光頼(きよはら
みつより)を味方につけた! 光頼は弟の武則(たけのり)を総大将として軍勢を頼義公に派遣した。これにより形勢が一気に逆転する。
1062.8月、出羽に勢力を持っている狄賊の清原一族を味方に引き入れた源頼義が安倍一族に再挑戦。小松の柵の戦いで安倍軍に大勝。
1062(康平5)年9月。
安倍氏の最後の拠点、厨川の城が陥落し、深手を負った安倍貞任は頼義公の前に引き出された。その時貞任は頼義公を一瞥し、何も言わずに息を引き取った。
安倍貞任の遺児高星は津軽藤代に逃れて安東太郎と称する。他の安倍氏の一族も伊予や大宰府に流され、奥州の安倍一族は滅亡した。そして頼義公に協力した清原武則は鎮守府(ちんじゅふ)将軍という役職を与えられ、清原氏は東北地方の覇者として君臨する。そして頼義公も陸奥守から伊予守となって京へと帰っていった。
この時、頼義公は「鎌倉の楯(たて)」と呼ばれる屋敷を貰っている。元々は平直方(たいらの なおかた)の屋敷だったが、娘婿である頼義公をとても気に入り、この鎌倉の楯を譲ったらしい。頼朝が鎌倉に幕府を開いたのは、この先祖伝来の屋敷があったからなのだ。ちなみに北条氏は平直方の子孫を自称している……。この戦では坂東武者の先祖たちも参戦している。頼義公の下で活躍した東国の武士の1人は三浦半島に領地をもらい、三浦一族の先祖となった……とされている。これで、東北地方に平和が訪れた……というわけではない!! この戦で活躍した者たちの子世代で新たな火種が東北地方で勃発する!!
1065年、「衣曾別嶋」(えぞのわけしま?)の荒夷(あらえびす)と、閉伊の山徒が反乱。多賀城の源頼俊が制圧。衣曾別嶋は青森から下北あたりを指すと考えられている。
1074年、延久蝦夷合戦(津軽半島と下北半島までの本州全土を朝廷の支配下に置く)。
1094年、藤原清衡白河より外ヶ浜(青森市)まで道を開く。
1111年、出羽国で反乱。守護源光国は任務を放棄。このころ、鎮守府将軍の藤原基頼、北国の凶賊を討つという。
1126年、藤原氏(清衡)の支配津軽にも及ぶ(推定)。
1189年、鎌倉幕府、奥州に侵攻し平泉の藤原秀衡を滅ぼす。幕府は奥州惣奉行を設置、御家人を行政官として派遣し奥州の支配を強化。結果、津軽周辺以外の「俘囚」の豪族の勢力は衰退・解体される。
1189年、大河兼任津軽で反乱。安東氏が津軽外三郡(興法・馬・江流末)守護・蝦夷官領を命ぜられる。
1191年、鎌倉幕府の代官南部氏が、甲斐の南部から陸奥九戸、糠部へ移住。
1200年頃、擦文文化の時代が終わりを遂げるとともに、大和文化の影響を色濃く受けたアイヌ文化が登場。6つの独立した部族グループがあったと考えられている。擦文文化に並行してオホーツク文化があったが、その後消滅。
1216年、鎌倉幕府が、強盗海賊の類50余名を蝦夷島に追放する。
| 【安東家が蝦夷管領に】 |
| 1217年 執権・北条義時、安東太郎(堯秀)を蝦夷管領(代官)に任命。「東夷を守護して津軽に住す」。安東家が交易船からの収益を徴税し、それを北条得宗家に上納する仕組み。 |
1223年頃、十三湊、西の博多に匹敵する北海交易の中心となる。アイヌの交易舟や京からの交易船などが多数往来した。廻船式目によれば、十三湊は「三津七湊」の一つに数えられる。「夷船京船群集し、へ先を並べ舳(とも)を調え、湊市をなす」賑わいを見せる。
1229年、藤代(藤崎?)の安東氏、十三湊を支配する十三左衛門尉藤原秀直を萩野台合戦で破る。藤原秀直は渡島に追放され、安東氏が十三湊(とさみなと)に移る。安東氏は出羽の湊(土崎)と能代川流域の檜山、宇曾利(下北)および萬堂満犬(まつまえ)も勢力下に納めた。
| 【樺太アイヌ(骨嵬)の元帝国との戦い】 |
|
1250年頃、蒙古は黒龍江の河口の奴児干(ヌルガン)に東征元帥府を置いて、河口から樺太にかけての吉烈迷(ギレミ)を支配下に置く。
1264.11月、樺太に住むアイヌ骨嵬がニヴフ吉烈迷を攻撃。吉烈迷は蒙古に救援を求める。蒙古軍が3千の軍勢が骨嵬を攻撃し樺太を占領。骨嵬は蒙古への朝貢を約束。骨嵬は樺太アイヌ、吉烈迷はギリヤーク(ニブフ)人と言われる。
|
1268年、津軽で蝦夷の蜂起がおこる。 蝦夷管領安藤五郎が殺される。仏教を夷島に持ち込み強制したのが原因とされる。
1274年、元軍が北九州に襲来(文永の役・弘安の役)。
1281年、元軍が北九州に二度目の襲来(弘安の役)。
1283年、元、骨嵬(クギ)に対して兵糧用の租税を免除。阿塔海が日本を攻撃するための造船を進める。
1284年、樺太アイヌ骨嵬は元に反旗を翻す。戦いは86年まで続き、元は1万以上の兵力を投入。
1295年、日持上人が日蓮宗の布教活動の為に樺太南西部(後の樺太本斗郡本斗町阿幸)へ渡り、布教活動を行ったとされる。
1297.5月、瓦英・玉不廉古らが指揮する骨鬼軍が反乱。海を渡りアムール川下流域のキジ湖付近で元軍と衝突。(日本の津軽地方を本拠地とする蝦夷管領安東氏がアイヌを率いてシベリアの黒竜江(アムール川)流域に侵攻)
1300年頃、『吾妻鏡』に、強盗や山賊などを捕えて蝦夷が島に流したとの記載。
1308年、骨嵬が元に降伏。これ以後、樺太アイヌは元に安堵され、臣属・朝貢する関係となる。
1320年、出羽の蝦夷が蜂起。戦いは2年におよぶ。安東季長が鎮圧に乗り出すが、蝦夷に返り討ちにされる。
1322年、津軽大乱が始まる。安藤氏で内紛。惣領安藤又太郎(季長)と従弟の五郎三郎(季久)が対立。両軍は岩木川を挟んで外が浜(青森市)と西が浜に対峙する。
1326年、鎌倉幕府、陸奥蝦夷の鎮圧のため工藤祐貞を派遣 。実体は安東家内紛への介入。季久を蝦夷管領に任命し、西が浜の合戦で安藤季長を捕える。季長郎従の季兼は「悪党」を集めて抵抗を続ける。十三湊の下の国安東氏(宗家)と大光寺城に拠点を置く上の国安東氏(分家)に分かれる。
1327年、幕府は宇都宮高貞・小田高知を「蝦夷追討使」として派遣。1年後に安東家の和議に成功。季長の所領を没収し、季久の地位を安堵する。
1331年、元弘の乱。津軽で大光寺・石川・持寄等の合戦起こる。
東北地方における覇権争い
1333年、鎌倉幕府が滅亡。建武中興。北畠顕家が奥州に下向。
1335年、足利尊氏が建武政府に反旗。南北朝の対立がはじまる。曽我・安藤家は足利につき南部師行・政長・成田泰二と戦う。
1356年、「諏訪大明神絵詞」のなかでアイヌのことに言及。
1368年、元が中国大陸の支配権を失い北走、満州方面を巡って新興の明を交えての戦乱と混乱が続き、樺太への干渉は霧消する。
14世紀には、「渡党」(近世の松前藩の前身)、「日の本」(北海道太平洋側と千島。近世の東蝦夷)、「唐子」(北海道日本海側と樺太。近世の西蝦夷)に分かれ、渡党は和人と言葉が通じ、本州との交易に従事したという文献(『諏訪大明神絵詞』)が残っている。また、津軽地方の豪族である安東氏が、鎌倉幕府北条氏より蝦夷管領(または蝦夷代官)に任ぜられ、これら3種の蝦夷を統括していたとする記録もある。
15世紀から16世紀にかけて、渡党を統一することで渡島半島南部の領主に成長していった蠣崎氏は豊臣秀吉・徳川家康から蝦夷地の支配権、交易権を公認され、名実共に安東氏から独立し、江戸時代になると蠣崎氏は松前氏と改名して大名に列し渡党は明確に和人とされた。
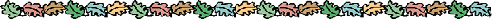



 (私論.私見)
(私論.私見)


![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)