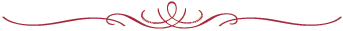
| 公取委によるジャスラックの独占禁止法違反抵触告発考 |
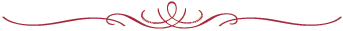
更新日/2019(平成31).4.15日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| JASRACの独占禁止法抵触の実態が明らかになりつつある。これを検証しておく。 2007.10.18日 れんだいこ拝 |
![]()
2006(平成18).9.8日、JASRACは、音楽使用料徴収マーケットを事実上独占している状態であるとして公正取引委員会の監視対象事業者にされた。違反の内容により、次のような措置が採られることになる。
(参照、 「公正取引委員会 」、「ガイドライン・公正競争規約」、「音楽著作権管理業者認識と公正取引委員会回答箇所読解の試み」) |
| Re:れんだいこのカンテラ時評395 | れんだいこ | 2008/04/24 |
| 【再びジャスラック問題を訴える、ジャスラックの独占禁止法違反抵触考その1】 2008.4.23日、公正取引委員会が、著作権管理団体の日本音楽著作権協会(JASRAC、以下ジャスラックと云う)に対して、テレビやラジオなどの放送局に音楽の使用料を一括して支払わせていることについて、同業他社の市場への新規参入や事業展開を不当に制限しており独占禁止法違反(私的独占)の疑いがあるとして、同協会の本部(東京都渋谷区)に初めて立ち入り検査した。 ジャスラックは、作詞家や作曲家から著作権を預かり、音楽の利用者から使用料の支払いを受けて著作者に還元する業務を行っている。1979(昭和54)年、NHKや民放各局に対し、歌唱演奏放送が著作権侵害であるとして課金制を適用する旨通告し、これに応じた各社と契約を締結した。 その際、番組内で流す楽曲の使用料については使用する回数が多いことと使用状況が把握しにくいことから流した回数や時間ごとに計算するのではなく、つまり実際の歌唱演奏に課金するというのはもなく、放送局の年間放送事業収入(NHKは受信料収入)に一定率(1.5%)を掛けたものを音楽著作権使用料として徴収する包括的利用許諾契約を締結した。 ジャスラックは、各放送局のサンプリング調査をもとに、作曲家らへの配分を計算していると云う。しかし、そもそもみなし課金であるので、実際の配分はさじ加減にならざるを得ない。優遇配分される著作権者は良いとして不遇の著作権者からの不平は絶えない。これが問題とされ燻り続けているのが実際である。 音楽放送分野の市場規模は年間約260億円で、ジャスラックは、約264万6000件の音楽著作物のうち約261万4000件を管理しており、シェア占有率は約99%となっている。2006年度は全体で約1110億円の音楽著作権使用料を徴収している。2001年以降に参入した事業者は数億円程度だという。 音楽著作権の使用料を徴収し、作曲家や作詞家に分配する業務は、かってはジャスラックの独占市場だった。これに対し、ネット配信の普及を狙う音楽出版社などから自主的な管理を希望する声が拡大し、2001(平成13).10月施行の著作権等管理事業法改正で業者の新規参入が認められ、それまでの文化庁への認可制から登録制になった。現在イーライセンス等7社がすでに事業を開始している。 関係者などによると、新規事業者は楽曲が使用されるごとに支払う個別処理方式での契約にしていたが、ジャスラックが包括契約方式をとってきたため、放送局はジャスラック以外に新たな追加支出コストが発生するのを嫌って新規事業者の管理楽曲の使用を控え、作曲家など権利者も新規事業者への楽曲の管理委託をとりやめるなどするため、新規のライバル社の参入を困難にしている疑いがあるという。こうして、参入はしたものの、ライバル社は使用料徴収額で圧倒的な差を付けられている。 楽曲の使用をめぐる独禁法違反事件では、公取委が2005.3月、音楽配信会社への利用許可を不当に制限したとして大手レコード会社5社に排除勧告を出した例がある。 ジャスラックは、こたびの立ち入りに対し次のようにコメントしている。 概要「検査が入ったことを真摯に受け止め、立ち入り検査には全面的に協力している。具体的な容疑は分からないが、我々は適正に音楽著作権の管理業務をしてきた。検査の結果が出しだい、迅速に対応していきたい」。 2008.4.24日 れんだいこ拝 |
||
| Re:れんだいこのカンテラ時評396 | れんだいこ | 2008/04/24 |
| 【再びジャスラック問題を訴える、ジャスラックの独占禁止法違反抵触考その2】 れんだいこは、ジャスラックの解体再生を指針させている。この論法は靖国神社考と通底している。その趣旨は後で述べるとして、こたびジャスラックが「独占禁止法違反の疑い」で公正取引委員会の立ち入り検査を受けたとの報道が為されていることにつき見解を述べておく。これまでジャスラックは手前達が立ち入り調査することはあれ、初めてされる立場に追い込まれたことになり皮肉である。 この事件をどう受け止めるべきであろうか。れんだいこは、ジャスラックが特有の著作権論を編み出し、課金制と暴力金融並みの強引な取り立てによる悪徳商法に走っており、その結果なるほど売上は定向進化で巨大化し続けているが、同時にその使用料金徴収実態が社会問題化しつつあり、そういうこともあってこたび公正取引委員会がようやく重い腰を上げざるを得なくなったと見立てている。 れんだいこは、公正取引委員会の摘発とは違う面でジャスラック商法のイカガワシサを告発している。公正取引委員会は、独占禁止法違反で実態解明に向かえば良い。そもそも公益性の強い社団法人格であるはずのジャスラックが民間の営利企業さえ恥じろいたじろぐばかりの儲け商法に走り始め、市場独占し続けている不当性は糾弾されて然るべきと考える。政治家は、パーティー券をたくさん買ってくれるので知らぬ顔をしているという腐敗がある。 れんだいこは、ジャスラックの偏狭強権的な著作権論に着目し、著作権法並びに音楽著作権法違反で実態解明に向かおうと思う。以下、れんだいこの趣意を述べる。 ジャスラックは、著作権法並びに音楽著作権法が本来要請していない著作権侵害論を編み出し、人民大衆の音楽愛唱演奏にのべつくまなく課金し、その責任を店舗経営者に転嫁し、強引な取立で顰蹙を買い続けている。一体全体、人民大衆が歌唱演奏したとして、店舗がカラオケ機器を置いて営業利用したとして、何でそれが著作権侵害であるものかは。ジャスラックは本来、音曲文化の裾野形成として喜ぶべき事象に対し、著作権侵害だとして罵詈雑言しつつ取り立てに向かっているが、狂気の沙汰ではないのか。 暴力団はその昔、恐いお兄さんやオジさんを連れてきて嫌がらせをしてミカジメ料を取り立てた。ジャスラックは暴力団の代わりに弁護士を連れてくる。それでもラチがあかないとなると法廷闘争で脅迫する。この時、請求額が、暴力金融さえ驚く高額請求に跳ね上がっている。これができるよう一応法律で通しているが、金銭消費貸借でもない著作権侵害で、金銭貸借上の延滞金利上限枠以上の暴利を取ることができるのかどうか。これを誰も問題にしていないが違法性が強いと云うか違法そのものだろう。仮に著作権侵犯だとして、金銭貸借以上の制裁を科すのは狂気の沙汰ではないのか。 そういう問題があるというのに、裁判所司法はジャスラックに迎合的で、あたかも手足の如く立ち振る舞う。裁判官から書記官、執行官までがグルになっている。人民大衆は、ジャスラックの強引さに反発しつつも司法当局まで巻き込んだ権力の壁の前で切歯扼腕し、滂沱の涙を余儀なくされる仕掛けになっている。ここにジャスラック問題の由々しき深刻さがある。 れんだいこはこれに闘う。ジャスラックの著作権理論にどこが問題があるか。これに答えられる者はそう多くは無い。むしろ、ジャスラック的著作権理論を最近流行の知的所有権論の一種として受け入れ、尻馬に乗って講釈したり薀蓄たれたり説教する者が殆どである。人は、文明的だとか先進的だとか知的所有権云々と聞かされると、これに異議を唱えると知性がないことを見破られるのを恐れて、分かったような顔をして相槌を打つ。これが、ジャスラック式著作権論をのさばらせる要因になっている。 れんだいこは、ジャスラック式著作権理論の野蛮性を告発している。著作権槍で文化の森を突いて獲物を追う姿をダブらせている。何が先進的で文明的であるものかはと。これに合点する者が少ない、というか居ない。しかしながら、れんだいこの著作権論の方が数等倍洗練されていることがそのうち分かるだろう。今は堪えるしかない。 ジャスラック式著作権理論の野蛮性は、音楽の奏でられるところなら何でも金儲けの対象とするところにある。歌唱演奏それ自体を著作権侵犯とする野蛮な法理論を構築している。問題の原点はここにある。しかし、考えてもみよう。本来の著作権法の引用転載条項は、1・「できる」規定している。2・但しとして同一性保持や著者名、出典元、引用先の明記を条件つけている。3・著作者が敢えて拒否するときその意思が尊重されるとしている。これを仮にソフト型著作権論と命名する。 これに対し、ジャスラック式著作権論は、1・引用転載は原則として不可として理論構成している。2・利用するなら事前通知要承諾制であるとしている。3・引用転載するなら承諾の対価料を支払えとしている。こういう三段論法を編み出している。こうして課金制が生み出されているが、ここにマヤカシがある。これを仮にハード型著作権論と命名する。 しかしこれは何もジャスラックのみが咎を受けるものではない。昨今の自称インテリの著作権論は皆これにシフトしている。従って、ジャスラック式著作権論は彼らの論法の当然の帰結であり、独りジャスラックのみが責められる筋のものではない。新聞協会の著作権論然り、出版協会、放送協会、各種学会の著作権論然りである。彼らは皆、同じ穴のムジナである。故に、ジャスラック的行き過ぎを咎められない。咎めれば、お前もナーと返答されるからである。 違いがあるとすれば、ジャスラックが承諾対価料としての課金制をシステムアップして実践していることにある。しかも、弁護士を尖兵として裁判所を巻き込んで、云う事を聞かなければ利息制限法さえたじろぐ高額の懲罰金制裁を課し、更に延滞金利でも稼ぐと云う傍若無人、無法ぶりで取り立てている。つまり、理論的には他の業界のそれも似たり寄ったりだが、ジャスラックが傑出して理論を生硬に実践しているところに特徴が認められる。 ならばどこが間違いと云うべきか。ここで、れんだいこが伝授しておく。そもそも著作権法は、人民大衆の著作権付き著作物の利用に関して対価制を認めたものではない。この観点をしっかり持つことが肝要だ。そもそも著作権法は、著作権者と版権所有出版者と同業他社との関係に於いて、海賊版を取り締まることから始発しており、当時に於ける在るべき姿を定めた権利調整法であると弁えるべきである。(ここでは、権力側が、不都合情報を規制する為に設けた経緯の面は問わない)つまり、業者間規制法であり、そういうタガハメされた法として生まれたものである。この観点をしっかり持つことが肝要だ。 このようにして始まった著作権法がやがて一人歩きし始める。著作権法の打ち出の小槌的活用に目をつけた或る邪悪な勢力が、これを悪徳商法的に利用し、人民大衆の利用に対する課金制へと発展させたのが現代強権著作権論である。この理論は1970年代に始まり、80年代から強力に吹聴されてきているという経緯がある。今日では、こちらの著作権法の方が通念化している。 この悪智恵を誰が付けたのかはここでは問わない。いずれにせよ、この飛躍は大いなる不正である。この観点をしっかり持つことが肝要だ。始発時点での著作権の目的趣旨からすると、著作権者と版権者の権利を擁護しつつ業界と目指す文化の健全な発展が義務付けられている。この後段の「業界と目指す文化の健全な発展」を阻害してまで著作権者と版権者の権利を擁護することまでは法が予定していない。にも拘らず、著作権者と版権者の権利を万能化させたのが現代強権ハード型著作権論である。この観点をしっかり持つことが肝要だ。 それはあたかも、憲法9条が有りながら、警察予備隊が自衛隊となり国防軍とならんとしている現下の状況、防衛庁が防衛省となり、イージス艦が漁船を真っ二つにしても直ちに救助活動せず被害漁民を放置し行方不明に追いやった様と似ている。法や機関がどんどん本来の目的から疎外しつつある。著作権法も叉弁えのない方向にどんどん資質劣化させられつつある。 れんだいこは、かく捉えている。だがしかし、このような著作権論が生まれず、現代強権ハード型著作権論に引きずられっぱなしで定向進化し続けているのが現下の状況である。何がうれしいのか知らんが、自称インテリは自分の首を絞めて恍惚している。その程度のインテリが多過ぎる。これを如何せんか。ジャスラックへの公正取引委員会の立ち入り事件は、この由々しき事態を考える記念すべき元一日にしたい。 2008.4.24日 れんだいこ拝 |
||
| 【JASRACの加藤衛理事長の居直り記者会見考】 |
| 2008.5.14日、日本音楽著作権協会(JASRAC)の加藤衛理事長は、この日の定例記者会見で、公正取引委員会から独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査を受けたことについて次のように述べた。(「JASRAC理事長、公取委の立ち入り検査『どこが問題なのかとびっくり』」その他参照) 加藤理事長は、「具体的な疑義の理由がわからない。公式な見解は調査結果が出ないとコメントできない。調査には全面的に協力する」としながらも、問題視されている著作権料の包括許諾契約については「いきなり来られてびっくりした。包括契約はそもそも放送事業者の要望で始めた仕組み。どこが問題なのかという気持ちが強い。30年も続いている仕組み。利用者ニーズに対応したものだ」と存在意義を訴えた。 JASRACには1曲ずつ使用料を許諾する仕組みもあるが、利用曲数の多い放送局やラジオ局などがすべての利用状況を把握することは困難。JASRACは利用楽曲を自動的にカウントするシステムの開発にも取り組んでいるが、導入のメドは立っていない。加藤氏は「ユーザーにとっても便利な仕組みという自負がある。楽曲を自由に使えるのは音楽文化の多様性を担保しているとも言える」と理解を求めた。 |
| 【2009.2.7日、公取委が、私的独占の疑いでJASRACに排除命令事前通知】 |
|
2009.2.7日、公取委は、公取委は昨年4月に立ち入り検査した結果を踏まえ、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区)が、テレビなど放送される音楽の使用料をめぐり同業者の新規参入を阻んだとして独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を出す方針を固め、協会に事前通知した。
関係者によると、JASRACはNHKや民放各局と、著作権を管理するすべての曲の放送や放送用録音を一括して認める「包括利用許諾契約」と呼ばれる形態の契約を結んでいたが、公取委はこの契約方法が他事業者の新規参入を阻害していると指摘した。JASRACの契約方法では、管理する楽曲数が多く、包括契約で一定額を支払えば、その楽曲を好きなだけ使えるため、放送局側にとっては別の業者と新たに契約を結ぶことは追加支出が必要になる。公取委は、解消の具体的な方法には触れない方向で調整しているが、実際の使用頻度に応じて徴収する方法に改めるなどして独占状態を解消するよう求めるとみられる。
|
| 【2009.2.27日、公取委が、私的独占の疑いでJASRACに排除命令】 |
| 2009.2.27日、公正取引委員会は、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区、以下「ジャスラック」と記す)に対し、テレビ局など放送事業者向け音楽の著作権管理事業に於けるテレビなどで放送される音楽の著作権使用料をめぐり、同社が他事業者の新規参入を阻んでいるとして、独占禁止法違反(私的独占)で排除措置命令を出した。 公取委によると、ジャスラックはNHKや民放各局約550社との間で、放送事業収入の1・5%を徴収し、管理楽曲の放送を一括して認める「包括的利用許諾契約」を結んでいる。この方式では、放送局にはジャスラックに対する著作権料の他に他事業者が管理する楽曲利用に対して他事業者ごとの「追加負担」が生じることになり、楽曲放送上由々しき煩雑さと著作権料負担を強いられることになる。結果的に、ジャスラックの管理する楽曲のみを選択させることになっており、このことが「新規事業者の管理する曲が放送でほとんど利用されない状態になっている」と認定し、「放送事業者側に他社との契約を回避させ、新規参入を阻んでおり、現状は私的独占にあたる」として改善を命じた。 放送事業者による楽曲使用料の市場規模は年間約206億円、ジャスラックのシェア(市場占有率)は99%以上となっている。2003年、公取委の研究報告は、2001年にジャスラック以外の業者による楽曲管理が可能となった後に於けるジャスラック式徴収方法の問題点を指摘している。2005.9月、日本民間放送連盟も、競合他社の市場参入を見越し、ジャスラックに使用料の減額を提案したが、ジャスラックは拒否していた。 |
| 【ジャスラックが徹底抗戦声明】 | |||||||||||||||||||
| これに対し、ジャスラックは即日、加藤理事長(中)と菅原常務理事(左)、顧問弁護士の矢吹氏が約50人の報道陣を前に記者会見し、加藤衛理事長が代表して次のように反論した。 正当性を次のように主張した。
審判請求する方針を明らかにし公取委と全面的に争うとして次のように述べた。
具体的に次のように反論した。
公取委の「使用料減額提案」に対して次のように反論した。
独占禁止法では排除措置命令が下された時点で効力が生じるが、具体的な徴収方法については、3.2日、公正取引委員会がジャスラックに説明することになっている。ジャスラックは、排除措置命令に不服がある場合、公取委に審判を請求できる。ジャスラックと公取委が互いに主張を述べ合い、審判官(公取委職員)が1・命令取り消し、2・変更、3・請求棄却などの審決を出す。審決に不服がある場合、東京高裁に審決取り消し訴訟を起こすことになる。審判・裁判終結まで命令の執行を免れたい場合は、東京高裁に「執行免除の申し立て」を行う。 ジャスラックは、公取委の説明をもとに対応を検討することになるが、加藤理事長は、「2カ月以内に審判請求を申し立てる。一方的に歩み寄ることはない。公正取引委員会に主張を理解してもらうことで円満に解決することが一番」と強気の姿勢を見せた。 ジャスラックは、公取委に対して徹底抗戦の構えを示したことになる。 会場からの質疑応答では、放送分野でのシェアの高さが指摘されたが、この点について加藤理事長は次のように説明した。
ジャスラックは、インターネット動画配信事業者や動画共有サービス事業者とも包括契約を結んでいる。YouTubeやニコニコ動画など動画共有サイトの運営者と締結している包括契約は、運営者が使用楽曲をすべて報告することが前提。サービス利用者がアップロードした動画に使われている楽曲を1曲ずつ調べ上げて報告する契約になっている。今回の排除措置命令がYouTubeやニコニコ動画などの動画共有サイトに与える影響について質問され、、ジャスラック常任理事の菅原瑞夫氏は次のように説明した。
放送における使用楽曲の全曲報告について、次のように説明した。
|
|||||||||||||||||||
「プレスリリース」の2009.2.27日付け「JASRACKの公正取引委員会に対する審判請求について」を転載しておく。(ゴシックはれんだいこ分責)
|
| 【各界の反応】 | |
|
一方、日本作曲家協議会の小林亜星会長は「新規参入が促されることは当然で、ジャスラックは命令に従うべきだ」と歓迎している。公取委が立ち入り検査した昨年4月以降、協議会はJASRACに説明を求めてきたが、正式な報告はなかったことを明らかにし、「もっと積極的に情報を公開すべきだ」とジャスラックの姿勢に注文をつけた。
当事者の放送事業者、レコード会社は静観の構えだ。NHK(広報局)は「ジャスラック以外の音楽管理事業者とも契約を締結し、利用している。ジャスラックの対応を当面見守り、必要があれば適切に対応する」とコメント。 |
| Re::れんだいこのカンテラ時評546 | れんだいこ | 2009/03/01 |
| 【公取委とジャスラックが全面対決模様事件考】 2009.2.27日、公正取引委員会は、社団法人「日本音楽著作権協会」(JASRAC、東京都渋谷区、以下「ジャスラック」と記す)に対し、放送事業者向け音楽の著作権管理事業に於けるテレビなどで放送される音楽の著作権使用料をめぐり、同社が他事業者の新規参入を阻んでいるとして、私的独占による独占禁止法違反で排除措置命令を出した。3.2日にも、具体的な改善策を指示する方針を示している。 これに対して、ジャスラックは即日、加藤理事長と菅原常務理事、顧問弁護士の矢吹氏が約50人の報道陣を前に記者会見し、加藤衛理事長が代表して縷々反論し、徹底抗戦する旨を決意表明し驚かせた。一体ジャスラックとは何者かと。 驚くのも無理はない。この事件の興味は、社団法人格の事業体が国家機関である公取委の行政指導に公然と叛旗を翻しているところにある。通常であれば、人民大衆の支持が得られるところであるが、この場合はどうであろうか。れんだいこは逆に公取委を支援しようと思っている。むしろ、これまでさんざん国家機関の司法裁判所や警察を使って攻勢的に弱いものイジメしてきたジャスラックが初めて逆に防戦を強いられているケースとして注目している。 ジャスラックは追う立場から追われる立場へと移った。してみれば遂に時代の潮の流れが変わったということであろう。ということは、知的所有権とか先進国権利だなどと云われると、分けもわからいのに何となく追認してきた多くの著作権病者がそろそろホンマかいなぁーと反省し始める契機になることを意味する。「公取委とジャスラックが全面対決模様事件」の歴史的意義はここにある。 今、公益法人が儲けるのはケシカランとして漢字検定協会が槍玉に挙げられている。同じような例として財団法人やら社団法人の幾つかが藪を突かれつつある。しかし、マスコミはこれまで、売上の桁が二桁も違うジャスラックに対してはなぜだか及び腰で言及を避けてきた。アンフェアこの上ないが、これが実際の話である。ジャスラックは社団法人なのだが、マスコミ記者諸君はまさか国営企業だとは思っては居るまいに、これまでいつもジャスラック的正義をプロパガンダしてきた。 しかし、ジャスラックは自ら墓穴を掘りつつある。公取委の行政指導に対してが楯突くと云う前代未聞のドラマを開演しつつある。当然相応の責任が伴う。真実と実態が解明されねばなるまい。遂に臭いものの蓋が開いた感があり、今後否応無く注目を浴びることになるだろう。そうなればなるほど、ジャスラック式著作権論の著作権法を無視したえげつないマルチ商法振りが露見することになるだろう。官僚天下りの実態が白日のもとに晒されることになるだろう。利用料金取立ての権利暴力ぶり、サラ金をも驚かせる暴利ぶりが明るみにされることになるだろう。余りにも数多くの理事、評議員がぶら下がっており、利権に群がっている生態が暴かれることになるだろう。 そういうこともあって、れんだいこは成り行きに注目している。それにしても我々はそろそろ、あるべき著作権行政の確立を目指して奮闘せねばならない。問題は靖国神社同様であり、単に機械的に反発するのではなく、革命的再生を目指さねばならないだろう。業の理念と業界の利益と著作者の権利のあるべき在り方を同時的に追求達成する制度を創造せねばなるまい。 その為にも、現下のジャスラックの実態解明、検証に向かわねばならない。良い季節になった気がする。小泉政権の売国奴ぶりと同様、国会で採り上げ、喚問し証言させるべきであろう。問題は、切れ味鋭く糾さねばならないのだが、質す者がジャスラック式強権著作権論を信奉しているようではどうもならん。それが心配だ。 2009.3.1日 れんだいこ拝 |
||
| 【考】 | |||
2019.4.14日付け「JASRACはもう一つのエンジン手に入れる」浅石理事長が語る「著作権管理」の未来」を転載しておく。
|
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)