
| 32258 | 日本の陽明学者 |

|
徳川幕府は明朝と同じように朱子学を擁護していた。朱子学の理は太極という人知を超越した外在するものから与えられているという思想が権威主義や保守主義につながりやすかったためと考えられる。幕府の寛政異学の禁により、幕府及び諸藩の学校内では朱子学だけが公認されていた。 |
| 〔日本の儒教〕 |
|
儒教は,日本には5世紀のころつたえられたといわれ,政治や社会に影響をあたえてきたが,最もさかんになったのは江戸時代である。徳川家康に仕えた藤原惺窩(ふじわらせいか)や林羅山は朱子学者であったため,朱子学が幕府や諸藩でさかんになり,封建制度をささえる道徳として発達した。 |
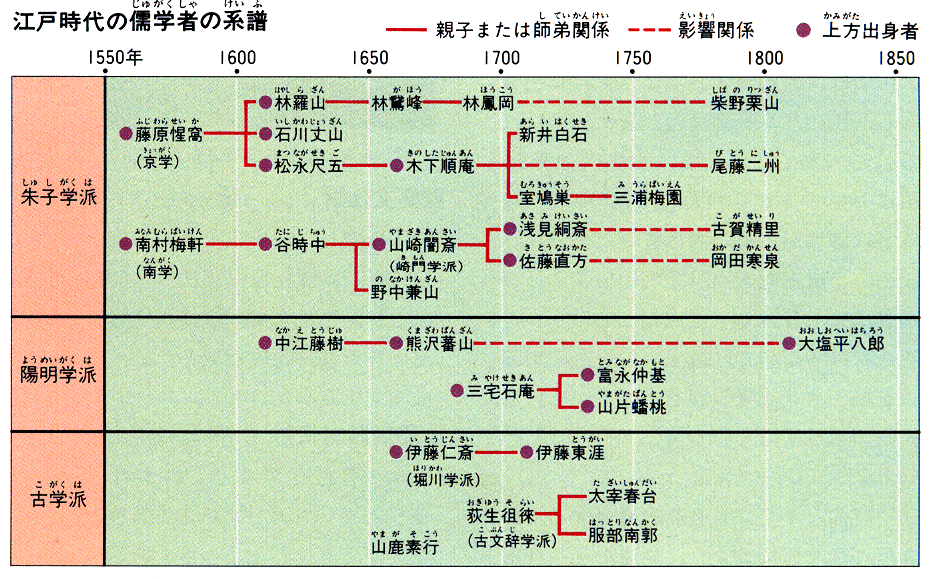 |
| これを解説すれば次のようになる。 |
| 【朱子学派】 |
| 朱子学は、江戸幕府に奨励された当代一の学問であった。 日本近世の儒学の祖と言われる藤原惺窩(ふじわらせいか/1561〜1619)はもともとは相国寺で仏教を学んでいたんだけど、公家や僧侶の教養として学ばれていた儒教を独立させて、儒教定着のきっかけを作ったんだ。彼自身は徳川家康に仕官、つまり召し抱えられることはせずに、弟子を推挙、もっと簡単な言葉を使おう、推薦したんだ。 その弟子が林羅山(1583〜1657)。彼もまた、幼い頃から建仁寺に入ってたんだけど、朱子の書を呼んで、朱子学を志したんだ。そして21歳の時、藤原惺窩に師事して、24歳の時に幕府に仕えることになった。彼の思想は、武士に対して人間関係と人間のあり方について目を開かせ、このころ安定しはじめた身分秩序を正当化する理論を築くものだった。その理論は、上下定分の理を重んじた。これは、天が上にあって地が下にあるは、あらかじめ定まってることで、それとおんなじように、身分にも上下があるとして、これによって当時の士農工商身分秩序を正当化した。 また、彼は存心持敬と説いた。常に心の中に敬を持ち、また上下定分の理を身をもって体現することを意味させていた。これは、朱子学でいう「居敬」であり、この「敬」というのは、「うやまう」ではなくって「つつしむ」(自分の心の中に私利私欲が少しでもあることを戒めて、常に道理と一つであることを求める)ということを指していた。 こういった、高貴な人格を保とうとする考え方は、武士たちに深い共感を持って受け入れられた。彼の著書に『春鑑抄』『三徳抄』などがある。また、彼の死後も、林家は代々幕府に登用された。1690年に綱吉の援助で昌平坂に林家の私塾がつくられ、のちに昌平坂学問所(昌平黌)として幕府公式の学問所になった。 |
| その他の朱子学者として山崎闇斎(1618〜1682)。彼は敬と義を原理とする倫理を説いて、修養主義を唱えた。また、彼は神道も学んでいて、儒教と神道を結合した垂加(すいか)神道を唱えた。彼の学派を崎門(きもん)学派と呼ぶ。 貝原益軒(1630〜1714)。彼は非常に博学で、本草学(中国から伝わった、動植物や鉱物などの効用を中心とした薬物学)や教育・経済・歴史などにも大きな業績を残した。益軒の著書には『大和本草』『養生訓』などがある。朱子学というのは、一面では身分制度を守るものであったが、一方で窮理を重視する傾向があり、合理的で批判的だったために、益軒のような「信ずべきを信じ、疑うべきを疑う」という、実証主義的な思想も育った。これが、西洋科学を受け入れる素地になったとも言われている。 その他の朱子学者として、木下順庵(1621〜1698)、佐藤直方(1650〜1719)雨森芳州(1668〜1755)などがいる。 |
| 【古学派】 |
|
古学派の思想は、それまで学んでいた、漢・宋以後の儒学者の解釈ではなく、孔子や孟子の原典に直接触れて、その真意を読みとろうとしたことに特徴がある。ここから古学派と呼ばれる。古学派として有名なのは、山鹿素行の古学、伊藤仁斎の古義学、荻生徂徠の古文辞学である。 |
| 【日本陽明学派の系譜】 |
| 日本の陽明学の開祖は中江藤樹。その高弟に熊沢蕃山。次に有名どころは、赤穂浪士の堀部安兵衛・弥兵衛親子の友人でありました、討ち入りを陰で応援した細井広沢という陽明学者がいます。あと赤穂浪士のメンバーに木村岡右衛門と吉田忠左衛門という、この忠左右衛門が一番年配ですから大石内蔵助の一番の片腕になりますけども、この2人が陽明学者です。 幕末期にはいりますと、山田方谷よりちょっとさかのぼりますが、浦上玉堂(1745〜1820)。大阪に懐徳堂が開塾され、東の昌平黌と並び称される学校となった。懐徳堂は、陽明学者の中井甃庵と中井竹山らが指南していた。大塩平八郎。 江戸の昌平黌の佐藤一斉。 佐久間象山。その弟子筋として吉田松陰。その弟子筋として高杉晋作。漢詩人で梁川星厳という京都で主に活躍した方がおります。西郷隆盛、西郷の盟友大久保利通。河井継之助。 二・二六事件で刑死した北一輝。安岡正篤。変わり種とでも申しますか、実は陽明学を勉強した人、学んだ人の中には三菱財閥の岩崎弥太郎、伊藤忠商事の創始者の伊藤忠兵衛、それから藤田観光・同和鉱業のいわゆる藤田組の創始者の藤田伝三郎も陽明学を学んでいます。 最近では作家の三島由紀夫も晩年約5年間ほど、やはり陽明学を学んだと言います。学んでいても、正しく理解しているということとは別問題ですので、その辺はお考え下さい。 林田明大講演録より抜粋 日本陽明学派の系譜については、「真説・陽明学」入門(三五館)に詳しく書かれてますので参考にして下さい。 |
| 【陽明学者寸描】 |
| 中江藤樹(なかえとうじゅ)(1608〜1648) |
| 江戸時代初期の儒学者。わが国の陽明学の開祖。近江国(滋賀県安曇川)の生まれ。はじめ朱子学を学んだが、37歳の時に『王陽明全書』に出逢って共鳴、陽明学に転向した。孝を重んじ、民衆の教化につとめた。かれはすぐれた活動によって「近江聖人」と尊敬され、藤樹書院という塾を開いて子弟の教育にあたった。
地元では「近江聖人」と呼び崇められ、その遺跡はほぼ完全に保存整備されている。中江藤樹の著書には『翁問答』、『大学解』などがある。
中江藤樹は江戸初期の儒学者であり 当初学んだのは当然のことながら「論語」・「大学」・「中庸」・「孟子」の四書をベースにした朱子学であった。 その後「王陽明」に触発され朱子学の限界と誤りを感じ、目を転じて陽明学に傾倒し深く入り込む事になった。藤樹は陽明学の思考を深め実践するため、27歳で武士の身分を捨て生まれ故郷に帰って、地元の庶民大衆を相手に陽明学を解り易く教え普及せしめる事に生涯を捧げた。 徳川幕府は、身分制を肯定し上下秩序を重んじる朱子学を精神的道徳規範とし、為政者の公認学問としていた。 そのため一般庶民大衆と同じ目線で物事を見る革新的傾向の強い陽明学はむしろ警戒され公式には受け入れられなかった。 しかし直弟子の熊沢蕃山はじめ 後には佐藤一斎、大塩平八郎、佐久間象山、吉田松陰、橋本左内、西郷隆盛など陽明学の流れをくむ逸材が輩出した。 藤樹の教えのエキスは 「心即理」 を出発点とし、「致良知」 「知行合一」 を説くものである。 その講堂藤樹書院のパンフレットにはこう解説されている。 「人は誰でも良知という美しい心を持って生まれてきているが、多くの人は醜いいろいろの欲望のために つい美しい良知を曇らせる。 人間は自分のいろいろな欲に打ち勝って、この良知を鏡のように磨き、何事もその良知の指図に従うようにしなければならない」。 「致良知」を王陽明は「良知を致す」と読んだが、藤樹は「良知に致(至)る」と読ませている。 この教えこそが藤樹教育思想の核心とされている。彼の学統には、熊沢蕃山、渕岡山等がいる。また、大塩平八郎、吉田松陰など異才も生まれている。 藤樹思想の特質は、すべての存在根拠となるのは孝であるとしたことにある。徳は、孔子以来、儒教で重視していた徳目であったが、藤樹は、孝の心の本質とは愛敬、つまり、まごころをもって人に親しんで、目上の者をうやまい、目下の者を決してあなどらない、と更に踏み込んで解釈し、これは、親子関係にとどまらず、主従関係や夫婦関係、兄弟や友達といったような人間関係を成立させるものであり、その孝の心は、時(時期)と処(場所)と位(身分)を考慮して実践すべきだと具体化させた。 身辺随想 |
| 熊沢蕃山(くまざわばんざん)(1619〜1691) |
| 藤樹の門弟。非常に有名な財政家で、財政・経済コンサルタントとしては当時日本でナンバーワンの人物。礼法も時・処・位、つまりその状況において妥当するもので、決して普遍的なものではない、としたんだ。また、聖人と呼ばれる人の教えをただ学ぶのではなくって、その心を学ばねばならない、と主張した。著書に『集義和書』がある。 |
| 浦上玉堂 |
| 岡山潘士ですが、そういう意味では山田方谷とは隣近所にいた陽明学者で、いまではミュージシャン、琴の演奏するミュージシャン・琴士として知られています。本職は琴士なんですけど、鴨方藩という支潘の大目付まで出世した人物で、あとは人生50歳を限りに脱藩しまして日本を放浪して生活をするという、琴士であり、なおかつ水墨画の画家としても知られています。川端康成がこの人の「東雲篩雪図」という水墨画をわざわざ買い求めて、それは国宝なんですが、ペンが進まないときにその水墨画の前に正座して、ずーっとその絵をながめていたという、そういういわくつきの絵なんです。川端康成記念館に玉堂68歳の時のこの作品「東雲篩雪図」は今でも保存してあるといいます。とにかく、この人はものすごく面白い陽明学者です。 |
| 大塩平八郎(おおしおへいはちろう)(1793・寛政5−1837・天保8) |
| 代々家職の大阪町奉行所与力を勤める家柄に生誕。幼少の折父(敬高)を失う。14歳の1806(文化3)年頃、祖父の後見で大阪東町奉行所に与力見習として出仕し、文化5年には定町廻役を務め、文化8年定町廻。江戸の林家に入門し朱子学を学ぶ。祖父の没後、家督を相続。1816年(文化13)年頃呂新吾『呻吟語』を読み、知行合一の実践を説く陽明学に転じる。1817(文化14)年に私塾洗心洞を設け、子弟に陽明学を講ずる。
26歳の文政元年(1818)の時祖父政之丞の跡を継ぐかたちで東町奉行所与力となった。以来、天保元年(1830)に38歳で与力を辞職するまで吏務を尽くし、この間誘惑の多い役職に有りながらその間清廉潔白にして、留守中に町方が付け届けをしたものさえ送り返すほどであったと伝えられている。いくつかの難事件(文政10年のキリシタン逮捕事件、同12年の奸吏糾弾事件、同13年の破戒僧処分事件)をも見事に解決し名声を挙げた。1830年大坂東町奉行の高井山城守実徳が江戸に転任したおり、与力職を養子格之助に譲り隠居。 その後私塾洗心洞で陽明学の教授と学問・著述に専念。頼山陽に「小陽明」と評されるほど陽明学者として名をなした。天保4年には、「洗心洞さっ記」を著してその思想を述べた。大塩の学問は『中斎学派』と云われ、学者としての一派を為す見識を備えていた。特に、自己の意思を貫き通し、世の不正を黙過することを拒否する清廉さと行動力を重視していた。その著『洗心洞さっ記』にも、「身の死するのを恨まず、心の死するを恨む」とある。 1836(天保7)年天保の飢饉の際、豪商の手先となる町奉行らを見て憤り、格之助を通して町奉行跡部山城守良弼に飢饉救済を申し入れるが一蹴される。さらに三井・鴻池ら豪商に救済費の借金を申し入れるがこれも断られる。平八郎は蔵書5万冊を売り払い、その金を窮民救済に当てる。 檄文を摂津・河内・和泉・播磨に飛ばし、1837(天保8)年自邸に火を放ち門弟数十名らと「救民」の旗を立てて挙兵、豪商の蔵を討ち毀し金や米穀を窮民に与えたが、半日にして大坂城代・近隣諸藩の武力に鎮圧される。約40日後、格之助との隠れ家を発見され、捕吏に包囲された中で爆薬により自殺。二人の黒焦げの死体は塩漬けにされ、のち磔にされる。その後、同年6月生田万の乱などしばらく大塩一党と自称する百姓一揆が続いた天保8年天保の飢饉に際し、「救民」を掲げて挙兵したが、鎮圧され自殺、その生を遂げた。 大塩平八郎資料館 |
| 佐久間象山 |
|
信州松代藩士。23歳で江戸に出て朱子学を学ぶ。次第に陽明学の方に心惹かれていき佐藤一斎門下に入る。更に洋学を摂取し、西洋軍事(砲)術を学ぶ。真に憂国の士となり、海防論、国防論、藩政改革論等「常に国家の存亡を我が身で担っているという、強い自負心に燃え続けた」。この間慕う者多く、門弟300人とも言われる。吉田松陰、勝海舟、坂本竜馬等々の面々が輩出している。 |
| 吉田松陰 |
|
長州藩士。佐久間象山の門下。国許で松下村塾を開く。門下生に、高杉晋作、久坂玄瑞、木戸孝允。 「道の為にし、義の為にす、どうして名を計らんや。誓ってこの賊と生を共にせず」 「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬともとどめおかまし大和魂」 |
| 西郷隆盛 |
| 薩摩藩士。「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕末に困るもの也。この仕末に困る人ならでは、艱難を共にして、国家の大業は成し得られぬなり」。「己を愛するは善からぬことの第一なり。修行のできぬも、事の成らぬも、過を改むることのできぬも、功に伐り、驕慢の生ずるも、皆自ら愛するが為なれば、決して己を愛せぬものなり」、「万民の上に位する者、己(おのれ)を慎み、品行を正しくし、驕奢(きょうしゃ)を戒め、節倹を勉め、職事に勤労して人民の標準となり、下民その勤労を気の毒に思う様ならでは政令は行われ難し」。 |
| 河井継之助 |
|
河井継之助は文政10年(1827)元旦に長岡城下同心町の河井代右衛門の長子として生まれた。藩校の崇徳館の高野松陰に私淑して8歳の頃より陽明学を信奉し、15才で、藩校嵩徳舘に入学。高野松陰は、藩校では朱子学を表看板にしますが、陽明学も教えたようで、長岡に初めて体系的な陽明学を教えたと言われている。
17歳の時、屋敷の庭に王陽明を祀り生け贄の鶏を割き、立志を誓ったと言われている。継之助のルーツは陽明学にあってよいと断言できるエピソードの一つである。幼少の頃から英才をうたわれ、長岡の青年時代の写本が残されているが、佐藤一斎「言志録」は高野松陰から借りたものだと伝えられている。 そして嘉永5年、継之助26歳にして江戸留学に赴き、佐藤一斎のもとで学び、塾頭も勤めた。斎藤拙堂、古賀謹一郎、佐久間象山、山田方谷と親交があった。遊学中は放蕩を尽くし、学問に頓着はしなかったという。そして、嘉永6年ペリーの来航。この事件で継之助に転機が訪れる。国難に際して継之助の富国強兵の献言が長岡藩主の幕府老中牧野忠雅の眼に留まったのである。これにより継之助は御目付役評定随役に任じられるものの、藩閥の頑迷な封建体制は新参者を拒み結局改革案は通らず不本意な結果に終わる。 継之助の第二の転機は、安政6年に訪れる。安政2年に藩主の養嗣子忠恭の学問指南役の御聴覧に任命されるもこれを辞退し、翌年の安政6年、再度江戸留学に赴いた。この安政6年の遊学中には備中松山藩宰相、山田方谷を訪ね、方谷に師事し藩政改革を学んだ。さらに足を延ばして四国・九州に遊学している。 そして継之助の第三の転機が訪れる。文久3年、藩主忠恭が京都所司代に任じられた際、公用人として京都に入った。当時の京都は尊王攘夷の乱暴狼藉が極みに達しており、この時の勤王家の印象は継之助の今後に大きく影響されていくことになる。小千谷会談決裂も岩村精一郎にこの当時の勤王家の影を見たのではないだろうか。 1850年春24才で、梛野嘉兵衛の妹すが(16歳)と結婚。 慶応元年、継之助39歳にて外様吟味役に挙げられ、藩政改革に乗り出し、同10月郡奉行に就任。山中騒動を治め、その後も藩政改革を次々行ってゆき、村政・町政、行政機構、兵制の改革を断行した。その後も継之助は累進し、慶応3年4月に奉行職になり、小諸騒動を治めた。同年11月には家老職となり、有能な人材を抜擢、三間市之進、花輪馨之進、植田十兵衛、村松治右衛門らを藩首脳部に上げ、着々と藩政改革の実を上げた。その最中、将軍慶喜は大政を奉還。長岡藩は時代の渦に巻き込まれることとなる。 戊辰戦争以後、すがには非常に過酷な運命が待ち受ける。戊辰の役は、鳥羽伏見の戦いから、勝海舟と西郷隆盛の江戸開城、彰義隊討伐、会津征伐、そして函館五稜郭の戦いと進んで行きますが、官軍が最も苦戦を強いられたのは北越戦争と呼ばれる徳川譜代の越後長岡藩との戦いだった様です。一般的には西国諸藩が、早くから西洋技術に目覚め、軍備も洋式化していたにもかかわらず、東国諸藩は、武備は戦国時代から大きくは変わらず、慌てて装備した洋式銃も多くは旧式銃を買わされて結局のところ、軍事力に大差がついた戦いになっていました。そんな中で、新式銃を装備し砲兵も持ち、さらにはガトリング・ガンと呼ばれる機関銃まで長岡藩は装備していた。長岡公国の創設に奔走し、貨殖の才を発揮し藩庫に莫大な余剰金を蓄え、武装中立の立場を宣言していたが、結局、藩もろとも一気に散っていった惜しまれる人物であった。  継之助の父母、妻すがは新政府軍に捕らえられ、高田の牢屋に入れられる。 8ヶ月後にようやく牢から出て、父母と共に会津へ行き、継之助の遺骨を持ち帰り、長岡の菩提寺の栄涼寺へ弔う。しかしながら長岡の人々は、継之助を戦争犯罪人として許さず、家族にまで中傷と罵声を浴びせる。中傷は収まらずに、翌年も更にその翌年も、続いたと言われている。そのような中で、父の代右衛門は、精神的に苦しみながら死んでいく。しかしながら、それでも中傷や嫌がらせは止むことがなかったと伝えられており、ついに、すがも母を連れて明治5年に、長岡を離れ北海道の江別へ移る。 雪明かり 吐く息つらし わが病 これは、すがが病の床で詠んだ歌です。病気は肺結核でした。明治27年、河井すがは、北海道で61才の生涯を閉じる。明治22年に明治政府は、戊辰戦争で賊軍と呼ばれた多くの獅子たちに恩赦を与え、継之助の賊軍の汚名は消え去ったが、すがは長岡へ帰ろうとはしなかった。その遺骨はしばらくして、長岡へ移し、菩提寺の栄涼寺に継之助と共にある。参考 「河井継之助の妻「すが」の証言」島宏著 柏書房 |
「峠」(上)新潮文庫
この男の知的宗旨である陽明学の学癖のせいか、つねに他人を無視し、自分の心のみ対話の相手にえらぶ。たとえば陽明学にあっては、山中の賊は破りやすく心中の賊は破りがたし、という。継之助はたとえ山中で賊に出遭うことがあっても、賊の出現によって反応するわが心の動きのみを注視し、ついでその心の命ずるところに耳を傾け、即座にその命令に従い、身を行動に移す。賊という客体そのものは、継之助にあっては単なる自然物にすぎない。(P.36)眼前に、難路がある。これも、継之助の思考方法からみれば山中の賊であろう。継之助は、難路そのものよりも、難路から反応した自分の心の動揺を観察し、それをさらにしずめ、静まったところで心の命令をきく。(P.37)
外的状況は内的状況である。というある人の言葉を思い起す。外的状況がどのようなものであろうとも、それを受け取る個人がどのように受け取るかということにかかっている。
星、月、山、川、人間など、あらゆる実在というものは、本当に実在するのか。朱子学にいわせると天地万物(実在)はちゃんと客観的に存在する。石ころも、道ゆく犬も、堤防上の松も、いっさいが客観的存在である、という。が継之助の陽明学では、そうは見ない。それら天地万物は人間であるオノレがそのように目で見、心に感応しているからそのように存在しているので、実際にはそんなものはない。たとえば継之助はあるとき佐吉にいった。
「春がきて花が咲く。ありゃうそだ」
というのである。桜は客観的に存在しないし、花も咲かないし、春というものもありえない。人間が心でそれを感応するから天に春があり、地に桜があり、かつは春に花がひらくという現象がある、という。人間の目と心があればこそ天地万物が存在するというのである。つまり、天地万物は主観的存在である、という。いわば、唯心的認識論といっていい。
要するに、人間が天地万物なるものを認識しているのは、人間の心には天地万物と霊犀相通ずる感応力があるからであるという。いやいや、その天地万象も人間の心も二つのものではない。天地万象も人間の心も、「同体である」という。
「だから心をつねに曇らさずに保っておくと、物事がよくみえる。学問とはなにか。心を澄ませ感応力を鋭敏にする道である」
と、継之助は佐吉によくいう。
――心は万人共同であり、万人一つである。
というのが、継之助のいう王陽明の学説であった。どの人間の心も一種類しかない、心に差はない、という。この場合心とは、精神・頭脳と言うことであろう。
「しかし、それはおかしい。現実に人間には賢愚があるじゃありませんか」
と佐吉がいうと、継之助はいい問いだ、といった。なるほど現実に賢愚がある。
しかしそれは本質的なものではない、というのが王陽明の説であった。
「というと?」
「人間には、心のほかに気質というものがある。賢愚は気質によるものだ」
わからない。
それを継之助は懇切に説いてくれた。気質には不正なる気質と正しき気質とがある。気質が正しからざれば物事にとらわれ、たとえば俗欲、物欲にとらわれ、心が曇り、心の感応力が弱まり、ものごとがよく見えなくなる。つまり愚者の心になる。
継之助によれば学問の道はその気質の陶冶にあり、知識の収集にあるのではない。気質がつねにみがかれておれば心はつねに明鏡のごとく曇らず、ものごとがありありとみえる。
「つまりその明鏡の状態が、孟子のいう良知ということだ」
そこまでは、朱子学の初歩をおさめた佐吉でも抵抗なくわかる。しかし陽明学はさらにそれより一歩すすめて良く知ることは知るだけでとどめず実行をともなわせる。はげしい行動主義が裏打ちになっている。(P.119)
自分の内的状況に依存しない外的状況は存在しない。外的状況を自らの心を静めて把握し、自らの思想信条に照らして、心静かに考え決断する。決断したら、その決断に従って行動していく。ただ、それだけのことである。
Last Updated on 1999/03/26
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)