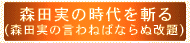

| 孔子・孟子の儒学 |
春秋時代末期の思想家、孔子(BC551〜BC479)を祖とする、中国を代表する思想。ほかに孟子(BC372〜BC289)、荀子(BC298?〜BC235?)などが知られている。個人の道徳と社会の理想を説く。周代(BC1044〜BC771)の理想的な治世を再現しようと試みたことから、「先王の道の教え」という意味で「道教」と呼ばれることもあった。
「修己治人(しゅうこちじん)」、「修身、斉家、治国、平天下」、「経世済民」の学。徳治主義。
孔子、孟子らはその実践を身を持って躬行した。しかし、後世の儒家たちは専ら解釈の為の学問すなわち「訓言古(くんこ)学」にした。
孔子(こうし)
(紀元前551ころ〜前479ころ)中国,春秋時代の思想家。儒教を始めた人として,のち日本にも大きな影響をあたえた。
孔子の人生について記した古い文献で私が知っているのは漢代の歴史家・司馬遷の『史記』のなかの「孔子世家」である。それによると、孔子の名は丘(きゅう)、字(あざな)は仲尼(ちゅうじ)。父は著名な武人だった。当時は貴族中心の社会で、武人は貴族に仕える立場にあった。父と母の関係は正規の関係ではなかったようだ。しかも幼くして父母と死別している。孔子の幼少時代は実に貧しく、苦労したようである。
このような逆境のなかで孔子は武人の道ではなく学問の道を選ぶ。当時の中国には地方ごとに「序」と呼ばれる学校があった。貴族の子弟は13歳で入学するが、貴族の出ではない孔子は15歳で入学した。
「序」を卒業したあと孔子は貯蔵配給係、牧畜係などの仕事に就いたようだ。40歳ごろ孔子は魯国に仕えて官吏になる。そして非凡な才能を認められて魯の高い地位につく。大司冦(だいしこう)という地位である。これは現代風にいうと「大臣」か「最高裁判所判事」のような高い地位のようだ。孔子は外交官としても非凡な能力を発揮し、名声が高まる。
政治力をつけた孔子は理想主義に燃え、貴族の横暴な政治を批判する。そして、これを打倒するために新興勢力として急速に台頭してきた武士階級、官僚、知識層を結集して、当時魯国の政治の実権を握っていた三桓氏の寡頭政治に戦いを挑む。だが、孔子の革命運動はいま一歩のところまで敵を追いつめるが、最後に敗北し失脚してしまう。
生まれた国の魯(山東省)で政治をとって失望した孔子は、失意のうちに祖国を捨てて流浪の旅に出た。自分の政治理想を実現しようと,弟子とともに14年間諸国をめぐった。孔子は時に孔子は56歳。13年間の流浪の旅の間、孔子は三度も生命の危険にさらされた。孔子が貴族階級から危険人物とみなされていたためだった。流浪の旅のあと教育者になった孔子のもとには多くの弟子が集まった。その数3000名と『史記』は書いている。
魯において築こうとした理想国家を他の地に築こうとの願望を秘めた旅だったが、成功せず、13年間の流浪ののち、68歳で再び祖国・魯に帰り、以後、数え年七四歳で没するまで子弟の教育や古典の整理に専念した。かれは,社会には礼とよぶ秩序が必要であり,それには人を思いやる仁とよぶ心が大事だと説いている。孔子と弟子たちとの問答をまとめた本が『論語』である。
孔子はソクラテス、マホメット、釈迦とともに世界四大聖人といわれてきた大思想家である。孔子は波乱の人生を歩んだ。孔子の生涯の一時期は政治革命家のようなものだったのではないかというのが私の解釈である。孔子の言葉の重みはこうした波乱の人生と無関係ではないように私には感じられるのである(森田実)。 政治革命家としての孔子
儒教はもともと、すぐれて政治的な宗教であり、政治を離れて儒教の存在は有り得ない。にもかかわらず、日本人は、その政治的な部分をまったく無視し、単なる一種の人間学にしてしまった。(小室直樹「田中角栄の遺言」)
孔子をはじめ儒家の人々は、宰相となり国を治めたいという政治的野望をもっていたが、実現には至らなかった。儒家の人々の現実の生活の糧は葬儀業であったようである。「当時の官僚失業者群には二種あって、一つは老子流の非政治的隠者であり、一つは孔子流の政治的遺賢である。」(長谷川如是閑「孔子と老子」『評論集』p.169)とある。
孔子の理想は,孟子などが発展させてひろがり、漢代には国教とされてさかんになった。前漢時代(BC202〜AD8)、武帝が董仲舒(BC176?〜BC104?)の建言をいれて儒教を国教に定め(BC136)、官吏登用試験の必須科目としたことから、儒教は全盛期を迎えた。その結果、これ以降の中国は、儒教を中心とした官吏国家という特徴をもつこととなった。
儒教に基づく官吏任用制度(科挙など)が中国社会に与えた影響は、士大夫という文化の担い手としても重要な階級を生み出したことのみならず、この制度からの落ちこぼれを中心とした隠者的な文化・思想潮流を生み出したという意味でも非常に大きいといえる。このころから,儒教の古典の読み方や意味の研究が行われ、唐代には、古典の解釈が統一された。
思想としての儒教は、漢の滅亡後停滞したが、北宋時代(960〜1127)に新儒教(宋学)という形で再び活性化することとなった。南宋の朱子(朱熹・しゅき)(1130〜1200)は宋学を朱子学(理学)にまとめ仏教哲学に対抗する哲学としての体系をまとめた。
同時代の陸象山(1139〜1192)は朱子学とは異なる学理を述べており、明時代陽明学の先駆けとして評価されることになる。陸象山は、朱子の性即理説に対置して気(心)と理は一つのものであるという心即理を唱えた。
明時代になると、王陽明(1472〜1528)が陽明学(心学)を興し、儒学に新風を送った。
しかし、明末になるとその勢いも衰え、朱子学はほとんど歴史学と区別のつかない考証学となり、陽明学は仏教・道教と融合する方向へ進んだ。政治思想の面も、『春秋』の解釈学である公羊学という形で生き延びるのみであった。このなかで儒教の影響力は次第に弱まり、清の滅亡によりその最後の力を失った。
〔儒教思想の特質〕
・道家思想と比較すると、儒教は人為に重きをおいた人間中心の思想であるといえる。祭祀・儀礼を重視したのも、信仰ではなく政治的儀式としてであった。
・周代の初めを手本とし、礼による社会秩序の回復・維持を説くことから、保守的・権威主義的な傾向をもっている。
・政治は力ではなく徳により行われるべきである、という理想主義を掲げた。徳の中で最も重要なのは仁であり、その基本は孝、つまり祖先や親への愛や道徳であるとする。
・人間はもともと天から授かった性(道徳性)を備えているが、それは天からくだされる命(運命)によって限界づけられていると考える。(金谷治『死と運命』p.145)
・孟子は「礼はもともと人々に備わっている」という性善説を、荀子は「強いられなければ誰も礼などもたない」という性悪説をそれぞれ唱えた。性悪説は、社会の安定には法による規制が必要とする法家思想に近いといえる。
・孟子は「人民を幸せにしない君主には天命がないのであるから辞めさせてもよい」という革命の論理を唱えた。
・儒教は、安定した社会における組織の維持・管理を得意としたが、飢饉や戦乱などによって社会が混乱したり、長期政権が退廃した場合には力を失い、人々は道家思想や仏教に救いを求めることとなった。このような動きは漢末や唐末などに特徴的にみられた。
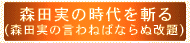

2000.7.31
経済政策を大いに議論しましょう(その2)
古典に学ぶ−日本経済再生の方向
『書経』という本があります。儒教で尊重される5種類の教典のことを五経といいますが、『書経』はこのなかの一つです。五経とは『易経』『書経』『詩経』『礼記』『左氏春秋』のことです。『書経』は尭舜から秦の穆公(ぼくこう)に至る政治史・政教を記したものです。
『書経』のなかに次の言葉があります。
「政(まつりごと)は民を養うに在り」 「正徳、利用、厚生、惟(こ)れ和(わ)せよ」
前者の意味は、「政治の基本は民をよく養うことにある」というものです。
後者の意味は、「道徳を正すこと(正徳)、民の力と財を有効に活用すること(利用)、民の生活を豊かにすること(厚生)−この三つを調和させることが『民を養う』道である」というものです。
正徳、利用、厚生−この三つを調和させるような経済政策をとるべきだという『書経』の教えは、今日の日本にも有効だと思います。
第一に、道徳が乱れていては経済はよくなりません。政治家、経済人、官僚が率先して道徳を守り、国民の模範とならなければなりません。指導者が不道徳になれば国民社会は腐敗します。まず道徳を正すことが大切です。これは現在も同じです。
第二に、国民の力と財力をうまく活用することです。日本国民は勤勉です。そのうえ教育水準は高いのです。貯蓄性向はきわめて強いのです。今は強すぎるほどです。この力を生かすことです。国民の消費性向が上向けば景気は回復します。
質の高い職業教育を強めて新しい技術の普及をはかり、労働生産性を高めることも必要です。日本国民の巨大な貯蓄も有効活用すれば、巨大な経済効果が生まれます。
さらに「厚生」です。福祉・社会保障をより高度化することです。国民が日本の将来に自信をもち、安心感をもつことができるようにするには、社会保障の拡充が必要です。
この三つがうまく調和するような経済政策をとれば、日本経済の前に立ちふさがる暗雲を払いのけることは不可能ではないと私は思います。
このためには政治家とくに政府与党指導者がしっかりしなければなりません。
「正徳」を背を向けるような政治家は排除すべきです。
「利用」のためには、少なくとも政府は国民に信頼されなければなりません。政府が信頼できる政権になることが先決です。このためには政権交代が可能です。
「厚生」のためには、新たなアプローチが必要です。従来の厚生省の政策の延長では福祉は崩壊してしまいます。【この項さらにつづけます】
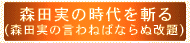

2000.7.31
経済政策を大いに議論しましょう(その2)
古典に学ぶ−日本経済再生の方向
『書経』という本があります。儒教で尊重される5種類の教典のことを五経といいますが、『書経』はこのなかの一つです。五経とは『易経』『書経』『詩経』『礼記』『左氏春秋』のことです。『書経』は尭舜から秦の穆公(ぼくこう)に至る政治史・政教を記したものです。
『書経』のなかに次の言葉があります。
「政(まつりごと)は民を養うに在り」 「正徳、利用、厚生、惟(こ)れ和(わ)せよ」
前者の意味は、「政治の基本は民をよく養うことにある」というものです。
後者の意味は、「道徳を正すこと(正徳)、民の力と財を有効に活用すること(利用)、民の生活を豊かにすること(厚生)−この三つを調和させることが『民を養う』道である」というものです。
正徳、利用、厚生−この三つを調和させるような経済政策をとるべきだという『書経』の教えは、今日の日本にも有効だと思います。
第一に、道徳が乱れていては経済はよくなりません。政治家、経済人、官僚が率先して道徳を守り、国民の模範とならなければなりません。指導者が不道徳になれば国民社会は腐敗します。まず道徳を正すことが大切です。これは現在も同じです。
第二に、国民の力と財力をうまく活用することです。日本国民は勤勉です。そのうえ教育水準は高いのです。貯蓄性向はきわめて強いのです。今は強すぎるほどです。この力を生かすことです。国民の消費性向が上向けば景気は回復します。
質の高い職業教育を強めて新しい技術の普及をはかり、労働生産性を高めることも必要です。日本国民の巨大な貯蓄も有効活用すれば、巨大な経済効果が生まれます。
さらに「厚生」です。福祉・社会保障をより高度化することです。国民が日本の将来に自信をもち、安心感をもつことができるようにするには、社会保障の拡充が必要です。
この三つがうまく調和するような経済政策をとれば、日本経済の前に立ちふさがる暗雲を払いのけることは不可能ではないと私は思います。
このためには政治家とくに政府与党指導者がしっかりしなければなりません。
「正徳」を背を向けるような政治家は排除すべきです。
「利用」のためには、少なくとも政府は国民に信頼されなければなりません。政府が信頼できる政権になることが先決です。このためには政権交代が可能です。
「厚生」のためには、新たなアプローチが必要です。従来の厚生省の政策の延長では福祉は崩壊してしまいます。【この項さらにつづけます】
「儒教に取って最も大切なことは忠孝即ち親への孝行と殊勲への忠義である。主君が辱められたら、家臣は死を賭けてでもこの恥をすすがなければならない。その場合、主君の方に難があってもそれに目をつぶることもある」(井沢元彦「逆説の日本史・乗っ取りの大戦略編」)