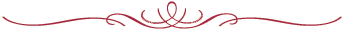http://xfs.jp/PzFbIu
選挙管理委員会御中 有権者の会
<500票バーコード票のPC開票集計システムの不正・誤作動の防止のお願い>
バーコードリーダー読取り「前」の500票束の束数と、バーコードリーダーで読み取り「後」に電子データ化された500票束の束数とが、「トータル数」で一致しないことの防止チェックおよび不正・誤作動防止のお願い。
私は有権者です。この文書の目的は、選挙における不正・誤作動を防止していただくことにあります。選挙では最初に同一候補者・政党ごとに100票束にしてから、その後、100票束を5個まとめて「500票束」にした後に、バーコード票を上につけます。バーコード票をバーコードリーダーで読み取った後は電子データ化されてPC内の開票集計システムで処理され出力されます。
<米国では大統領選挙でも不正選挙が行われていることが社会問題化している>
昨今、米国大統領が「不正選挙が存在している」と公言し、そのあと、NBCテレビなどで「選挙における不正が見つかった」と報道され米国大統領選挙でも不正選挙が横行していることが明らかになりました。トランプ大統領は、不正選挙を検証する第三者委員会を設置する大統領令にサインをしています。
<日本でも不正選挙は行われているという指摘が市民団体から多数ある>
実際に、大阪の堺市選挙管理委員会の元職員は、市民68万人の有権者情報を外部に持ち出していたとして、刑事告発されて逮捕されています。仙台市青葉区選管の職員の期日前投票用紙の流用による懲戒解雇、高松市選管職員の不正による有罪判決等ありますが選管職員が不正を行っていました。選管に対する信頼は地に落ちています。
<注意喚起をしたい項目>
「開票時に「500票ごとにつけられるバーコード票」を「バーコードリーダー」で読み取ったあとに電子化された票データが、出力時に候補者や政党名を入れ替えて出力されていないかです」。
<米国で不正選挙として問題になっているのは「電子選挙過程の部分」であり、日本ではバーコード5百票をバーコードリーダーで読み取り後のPC内での集計過程が該当する>
この電子データ化された後の処理が米国大統領選挙でも「不正が存在する」と問題になっている箇所であり日本でも過去に不正が発覚する時はこの5百票バーコードがバーコードリーダーで読み込まれた後の部分が、不正の原因箇所になっています。なぜなら、500票バーコードリーダーで読み取った後は、電子データにPC内で変化するからです。この電子データに変化した後の選挙データというものは、PCプログラムのバグ、悪意あるプログラムの存在、またはハッキングなどによる操作または誤動作が可能になってしまいます。電子データとして入力された後に、午後10時頃などに「候補者の振り替え認識」をPCプログラムが作動していても、対抗できません。
<米国での経緯>
もともと米国では最初は「電子投票機」という形で「票を電子データに変化させてPCプログラムによって不正が行われる」という形で導入されて、一大社会問題となっています。ですから日本では、5百票バーコード票がバーコードリーダーで読み取られた後に「電子データ」に変化します。この電子データに対して、PCプログラムが、候補者に対する認識を振り替える動作を、開票時間がスタートしてから時間的に遅くなったころ(例 夜10時頃)に作動しはじめても実質わからないようになっています。
<日本には当初、電子投票機として入ろうとしたが、選挙無効事件になったため、形を変えてバーコード票として電子投票過程が入り込んできた>
日本にも当初、電子投票機という形で入ろうとしましたが、岐阜県可児市の可児市長選挙においてこの電子投票機はトラブルになり、選挙無効請求訴訟となり名古屋高裁で選挙無効という判決がなされ、最高裁で確定しています。そのため電子投票機という形では日本には入れませんでしたが、その後、民主党政権の事業仕分けにおいて、「バーコード票とバーコードリーダー」という形になって外国人シニアアナリストの提案によりこの「電子投票過程」は導入されてしまいました。(この時に選管の大幅な経費削減と開票時のアルバイトの導入、バーコードの導入が提案されて採用されています) これ以降、バーコードの誤作動は、各地で見つかっています。
過去に この500票バーコードの不正(誤作動)が発覚したのは、平成24年の衆議院議員総選挙と猪瀬都知事選とのダブル選挙だったときの国分寺市選管の事例です。このときは、民主党の候補者と自民党の候補者を互いに逆にカウントしていました。これは、選管責任者はまったく気づかず、開票の立会人も気づきませんでした。外部からの指摘によってはじめて気づき、選管の開票責任者は後のヒアリングで「忙しすぎて、チェックなどまったくやる余裕がなかった」と答えています。平成27年の沖縄県議選でも、「電子画面上できちんとチェックしていたが、出力される候補者の票数は異なっていた」ことが、途中で発覚して、やり直しています。これも選管の責任者も開票の立会人も全く気づきませんでした。外部から指摘があってはじめて、気づき、深夜に数えなおしています。(平成27年6月6日に朝日新聞他が報道)
静岡県議選補選の伊豆の国市などでも不正が発覚しています。この場合は3候補者の順位が、それぞれすり替わっていました。(A候補者、B候補者、C候補者の順に票数が多かったのが、結果は、A候補者の票を、B候補者の票としてカウントし、それぞれひとつずつずれていた。)また、新潟県知事選では、開票立会人が、深夜12時近くなったときに、バーコード票の付け間違いに気づいて指摘したところ、それを修正し数えなおしたということを聞いています。大阪では、いくら開票立会人が「おかしい」と指摘しても、「その場では絶対に再開票するな」という、不正を隠ぺいすることにもつながるような注意書きがなされています。そして他にも開票立会人が、不正に気づいて、「おかしい」と指摘しても、開票立会人の責任者が、それをとりあげず、強
制的に終わらせるということが多く起こっています。なぜなら開票立会人の責任者も、公平中立とは言いがたいからです。
お願いしたいのは、各候補者の「500票バーコード票をバーコードリーダーで読み取る前の票の束数」を、台にわかりやすく積み上げていただき、PC出力される「バーコードリーダーで読み取った後の各候補者の束数」が本当に一致しているのかをトータルで参観人もチェックできるようにしていただく公明正大なプロセスです。
<過去の不正発覚の事例では、選管職員や開票立会人が気づかずにいた事例が多数ある>
なぜなら、過去の不正発覚の事例では、「選管職員が、不正に気づいておらず、また開票立会人も気づかなかったが、外部からの指摘によって初めて気づいた」という例が多数あるからです。ですから、不正の発覚について、「選管職員や、開票立会人だけにまかせて彼らが何も指摘しなかったから不正はなかったのだ」とは、いえません。参観人にも わかりやすいように、バーコードリーダーで読み込まれた各候補者の票の束を積み上げて、何束あるのか、そしてPC出力された各候補者の票数が、本当に一致しているのかどうかを「トータルで」チェックしないと本当のチェックにはならないのではないでしょうか?
<米国では一切のバーコード票やPC集計プログラムを使わずに、手作業に戻すべきだと不正選挙の訴訟や啓発で主張されている>
米国はニューヨーク市立大学の教授が、「不正選挙」(亜紀書房)の中で、不正選挙を防止するためには、一切の電子選挙過程を排除してすべて、人間の手作業でやるべきだということを提唱しています。日本の場合は、5百票バーコードからバーコードリーダーを使って読み取り、電子データに変化してPC集計される部分です。ここは本来は使用しないほうがよいと思えるほど、おかしな事例が多数出ています。
<100票までのチェックや500票までのチェックはきちんとやっているが、「バーコードリーダーで読み込まれた後」のデータがきちんとPC内で集計、計算されているかはノーチェックな場合が多い>
「100票までのバーコード票の中身があっているかどうかはきちんとチェックしている。それが500票のバーコード票にまとめられて、500票がそれぞれきちんとそろっているかはきちんと再度チェックしている。しかしこの後、バーコードリーダーで読み取られて、電子データに変化してからはノーチェックである」という選管が非常に多くあります。
<バーコードリーダーで読み取られた後に、電子画面上で合致しているかをチェックしていてもそれではチェックにはならない>
また、バーコードリーダーで読み取られた直後に、「機械の電子画面」上で合っているかどうかを確認して、それで合っていると判断するという選管もありますがこの電子画面上のチェックというものは、悪意のあるプログラムが混入している場合はまったく当てになりません。(入力時に合致していてもトータルで束数が違った事例がある)
<最初はきちんと動作していても、時間的に途中から候補者の認識を振りかえるPCプログラムが混入していれば、不正は可能>
スポットできちんと動作しているかどうかをチェックしているという例もありますが、これでは、最初はきちんと動作しているが、時間が10時頃などのように後になってから、PCプログラムが悪意のあるプログラムまたは誤作動を起こして、途中から候補者名を、振り替えて誤った認識をし始めた場合は対抗できません。そして米国で一大社会問題となっている「不正選挙」というのは、まさにこの部分を指しています。電子データ化された後に、PCプログラムが入り込み、認識を候補者・政党同士で振り替えるのです。ですから、500票バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数を積み上げてトータルで PC出力される数字とあっているのかを、チェックするということをお願いします。たとえば、A候補者が、500票バーコードリーダーで読み取られた票が10束B候補者が500票バーコードリーダーで読み取られた票が15束、C候補者が、500票バーコードリーダーで読み取られた票が20束あればそれぞれの束を、A候補者 B候補者 C候補者と 台に紙を書いて、開票立会人にも、特に参観人にも見えやすいところにおきます。(現状では、一番奥の方に置かれ、参観人が双眼鏡を持たないとチェックできないようにされているところが多い)そして、バーコードリーダーからPCが読み取って出力されるデータはA候補者が、500票束×10束=5千票、B候補者が、500票束×15束=1万5千票、C候補者が、500票束×20束=2万票、なら合っています。
これをわかりやすく、500票束を「正」の字で表示して選管職員も開票立会人も参観人も、500票のバーコードリーダーで読み取られた後にPCが誤作動や誤ったトータル集計をしていないか、もししていたらその場で指摘できるようにしていただきたくお願いします。これが、時間的に後の方になってから候補者を相互にたがえて集計認識をしていると思われる事例が各地で起こっています。以上、最大限の監視をお願いします。
また、開票時には、アルバイト募集をしてやらせている選管が多いですが東京都選管では、開票アルバイトには、(主任以外は)研修を全く行わず、当日にぶっつけ本番でやらせているところが多数あります。機械では票を読み取るときに、赤いマジックやカラーペンなどで書かれた票を無効票にしてしまうと聞いています。その無効票は本来、きちんと候補者名や政党名が判別できるのであれば有効票にしないといけないところ、まったく研修を受けていないため開票のアルバイトや人材派遣によりそのまま無効票にされた例が多数参院選であったという目撃談があります。また、開票集計システムの誤作動が起こりやすいのは時間的に最初の方ではなく後の方に起こります。比例票を数えることは「各政党の候補者の票を数えた後」の深夜に行うとされているところが多いですが、参観人が帰り、開票立会人も疲れている深夜に、比例票の開票が始まるためノーチェックに近くなります。過去に誤作動ではないかと思われるのは比例票が多いため比例票が一番トータルチェックが必要です。参観人などが公明正大にチェックできる時間帯に比例票も開票を始めていただいて不正を予防するチェックを参観人もできるような体制をお願いします。以 上