何と、侍従長・正親町(おおぎまち)実正が、大正天皇の手元にあった印を暴力的に奪取した様が明らかにされている。天皇制護持論者よ、こったらことが許されるのであろうか教えてくれ。
| 大正天皇実像論、押し込め考 |
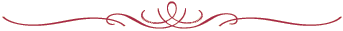
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| しかと聞け。いわゆる天皇制右翼は、以下に記す「大正天皇押し込め」について見解を披瀝せねばならない。君達は、史的連綿なる国体的皇室制度を単に制度としてのみ護持せんとするのであるのか。この場合は何を護ろうとしているのかはっきりさせよ。以下に記す大正天皇の悲劇をどう観るのか返答せよ。それとも、戦前の昭和天皇に極致された現人神的天皇制イデオロギーをのみ信奉しようとするのであるのか。あるいは、明治天皇の御世に憧憬しているのか。それとも何か、実際の天皇は単に人形的飾りであり、尊崇を及ぼさず、その理念をのみ拝戴せんとしているのか。 しかと答えよ。いずれにしても、あちらを立てればこちら立たずで、どちらで返答しようとも戦前並みの感覚で云えば、不敬罪の匂いがするぞ。天皇制護持を云うならそれはそれで構わない。しかし、理論的には結構厄介なるものであるぞよ。そのことを指摘しておく。 2003.11.28日 れんだいこ拝 |
| 【大正天皇の実像考その1】 | |
このことは指摘したが、もう一つ思案してみねばならぬことがある。戦後の昭和天皇の御世、平成天皇の御世において、もし評価される行為があるとすれば、何とそれはほとんど皆大正天皇に淵源を発しているということである。アットホーム的な家族愛の育成、巡啓、巡幸、身近な御言葉、世界平和の念願等々、これ皆大正天皇の事跡である。その大正天皇が「押し込め」られ、今もって「押し込め」られているところにこそ、天皇制護持を生命線とするという右派思想の得手勝手性がありはしないか。君達は何か、都合の良いところだけを見、拾ってくれば、それで思想が形成されるのであるのか。 もっとも自称左派諸君にも云わねばなるまい。大正天皇の脳病観をもっとも強く打ち出し嘲笑してきた君達の歴史観は、全く無力でむしろ反動的でさえあるのではないのか。右翼の全肯定に対するに全否定なる構図のままに天皇制論議してきたその姿勢は運動上の益するもの何も無く、実践的に何も生み出さずむしろハーモニーしており、単に商売的な棲み分けでしかないのではないのか。 本来なら、天皇制の歴史性を踏まえ、その矛盾を見てとり、その内部抗争に関心を持つべきではないのか。それを何ら為さず、一事万事であるが、「敵」と看做したらその規定だけで全て解決済みなる精神こそ無能の極まりではないのか。 2004.2.16日 れんだいこ拝 |
| 【大正天皇の実像考その2】 | ||
| 大正天皇像として一般に知られているのは生まれつき病弱で、脳を患っていたというものであろう。その流れで、帝国議会で詔紙を巻いて遠眼鏡のようにして議員席を見回したというひょうきん話が象徴的に流布されている。しかし、最近の検証で判明しつつあることは、どうやら「為に為された作り話し」ということのようである。 長い間、左派系もこうした類の話を鵜呑みにしてきた風がある。恐らく、皇室制度批判に丁度都合の良い題材だったのだろう、むしろ積極的に面白おかしく巷間に流布させてきたように思われる。しかし、れんだいこに云わせれば、そうした態度は、大正天皇の御世に立ち現れていた矛盾に無頓着で、天皇及び皇室制度に歴史的に内在している対立に対しての無知を晒しており、そういう水準を暴露しているに過ぎない、それは反動的な見立てでさえあるということになる。 「大正天皇の御世に立ち現れていた矛盾」に対しては別章で考察するとして、「天皇及び皇室制度に歴史的に内在している対立史」につき大雑把な考察をしておく。ざっと拾い出すだけで、1・古代の「国譲り物語」で寓意されている一大政変、2・神武系、崇神系の国開きの系譜如何、3・邪馬台国と大和朝の継承関係、4・天智対天武の抗争の背景、5・南北朝対立時代の皇統譜問題、6・幕末期の孝明天皇の変死、7・明治天皇すり替え問題、8・大正天皇押し込めの背景事情等々に関しては重大なる関心が払われねばならないだけの理由がある。これらの経緯を踏まえずの天皇及び皇室制度批判は非歴史的凡庸に過ぎよう。 さて、大正天皇の話に戻る。大正天皇は、子供の頃は確かに病弱で、病気で勉強がなかなか進まなかった。が、結婚を境として頗(すこぶ)る壮健になっており、皇太子として沖縄を除く日本の全ての道府県をまわり、大韓帝国にも行ったりと常人以上の健康ぶりを見せている。その人物像は、感受したことを素直に問う性格で、国民と話をするのが大好きで、道にいた小さい子供に「いくつになる」とたずねたり、学習院時代の友達の家で話をし過ぎて行事に遅刻したという逸話もある。また、家族団欒を愛し、子供を可愛いがり、昭和天皇をはじめとした4人の皇子とは鬼ごっこなどをしてよく遊んだという。一言でいえば、人間味あふれる天皇であった。 その大正天皇が「押し込め」られ、裕仁皇太子の治世に入る。その後の大正天皇は、ビリヤードをして過していたことが伝えられている。しかし、ビリヤードは非常に神経を使うスポーツで、このことから脳を患っていたわけではないことが判明する。となると、「脳病説」の背景にあった真相こそ凝視されねばならない。しかし、蟄居閉塞させられた環境が次第に大正天皇を鬱屈させたか病気がちになったとされており、大正15.12.25日に47歳の若さで崩御する。 つまり、大正天皇の実像は流布されているようなものではない、ということが判明しつつある。原武史氏は、著書「大正天皇」の中でそのことを衝撃的に明らかにした。著書「大正天皇」はそういう意味での歴史的価値がある。原氏は次のように述べている。
そう指摘する原氏は、大正期に日本で最初の政党内閣を誕生させた原敬の「原敬日記」の重要性に着目する。原氏は、1921.2月に書いた遺書の中で、「余の日記は数十年後はとにかくなれども当分世間に出すべからず。余の遺物中この日記は最も大切なるものとして永く保存すべし」と遺言していたが、その真意は奈辺にあったのかと紐解く。結論として、「原が日記の中で、大正天皇に関する知られざる記述を残していた」ことにあったのではないかと推理している。 原と大正天皇との交流は皇太子時代から始まっており、大正天皇の原への信頼が厚く、日記には両者の遣り取りが数多く残されている。特にとしては1919(大正8).2月に宮内次官から「大正天皇の脳のご病気」を知らされてからの間近に見た大正天皇の動静が記録されている点で、「原敬日記」は歴史的文書として希少な第一級文書となっている。その原敬は1921(大正10).11.4日に凶弾に倒れる。その数日後の11.25日に裕仁皇太子が摂政に就任し、大正天皇は「押し込め」られる。つまり、大正天皇と原敬は命運を共にしていた感がある。 そういう歴史的因果関係を持つ原敬の日記には、大正天皇の非凡且つ英明な姿が記述されている。原氏は、著書「大正天皇」の中で次のように云う。
そして云う。概要「だからこそ原は、日記の公開を恐れたのではないか」。 原氏は、「大正天皇の実像が白日のもとにさらされることを、何よりも恐れたのではなかろうか」と結んでいるが、素直に論を受け継いでいけば、「非凡且つ英明な大正天皇を押し込めて云った当時の支配層の愚劣が白日のもとにさらされることを、何よりも恐れたのではなかろうか」と云う事になるであろう。 |
| 【大正天皇の生来の病弱性について】 | |||||
| 大正天皇が生来の虚弱体質であったことは疑いない。幼少期の天皇の持典医であった漢方医の浅田宗伯氏の記録には、概要「飲食させても吐き、頭頂部の縫合に難あり」と記されており、他にも裏付ける資料が多い。しかし、幼少期のこの症状はままあることであり、むしろ成長するに従い虚弱体質が壮健へと向う例も多い。大正天皇の場合、この例であったと拝察し得る。 ところが、大正天皇「押し込め」となった1921(大正10).11.25日、皇太子裕仁(ひろひと)親王の摂政就任に際して、この時宮内省から大正天皇の病状経過に関する5回目の発表が為されている。それによると、大正天皇の奇行は、幼少時の病弱を因とする脳の病気によるものであるとして次のように云い為されている。
別文の宮内省公表文「聖上陛下御容体書」も次のように記して、「生まれながらの病弱な天皇イメージ」を喧伝している。
大正8.11.8日付け原敬日記には次のように記されている。
これらから推理するのに、大正天皇は、親王時代も含め結婚した20歳から即位するまでの32歳頃までの皇太子時代にはむしろ元気であったことが読み取れる。この実像研究について、原武史著「大正天皇」(朝日新聞社・平成12.11月刊)は克明な調査で、「髄膜炎によって病弱で影が薄かった説のベールを剥がして、行動的で活発、多弁な全く別人のような大正天皇像を明らかにしている」。 原氏は、同書の中で、宮内省の5回目の発表に対する当時大正天皇の側近であった四竈孝輔氏の日記を紹介している。それによれば、四竈氏は次のように抗議している。
牧野宮相の意図に強く抗議している。四竈氏をしてそのように言わしめた牧野宮相派の動きの背後にはどのようなものがあったのか。実は、本来ここが解明されねばならないところであろう。 |
| 【明治天皇と大正天皇の違い】 |
| 大正天皇は、気質の上で非常にユニークである様が窺える。この気質気性がどこより由来したのかは定かではないが、明らかに明治天皇のそれとは異なっている。皇太子時代の各地への行啓時の様子は、明治天皇の巡幸時の荘重さ演出に比較して極めて大衆的である。 |
| 【大正天皇の治世観と反軍感情考】 |
| 強面の明治天皇。気さくな大正天皇。聖域を拵える明治天皇。家族団欒主義の大正天皇。事情の許す限り、夕べの家族団欒を楽しみ、妃がピアノ演奏、それにあわせて女官交えて唱和する。乗馬練習の帰りに皇孫御殿を不意に訪れ、皇子たちと一緒に相撲や鬼ごっこをした。 |
| 【大正天皇が強制的に閉居させられる。「押し込め」考】 |
| 大正天皇は、この強制的引退に抵抗した模様である。侍従長・正親町(おおぎまち)実正が天皇の使う印鑑を摂政に渡したいと取りに行くと、天皇は不快感を露にし、いったんは拒んだ。その後、侍従武官長が天皇の元に出ると、「さきほど侍従長はここにありし印を持ち去れり」と云ったという(四竈孝輔(しかまこうすけ)「侍従武官日記」)。 |
|
何と、侍従長・正親町(おおぎまち)実正が、大正天皇の手元にあった印を暴力的に奪取した様が明らかにされている。天皇制護持論者よ、こったらことが許されるのであろうか教えてくれ。 |
| 【原武史(はら・たけし)著「大正天皇」(朝日新聞社、2000年)の衝撃】 | ||
| (著者の略歴)1962年、東京都に生まれる。東京大学大学院博士課程中退。東京大学社会科学研究所助手,山梨学院大学助教授を経て,現在,明治学院大学助教授。専攻は日本政治思想史。著書に『直訴と王権』(朝日新聞社,韓国語版は知識産業社),『(出雲)という思想』(公人社),『「民都」大阪対「帝都」東京』(講談社,サントー学芸貰受賞)がある。 | ||
|
| 【河西秀哉氏の書評「大正天皇を巡る風説に疑問を投げかけた原武史著『大正天皇』(朝日選書)(原武史)」 】 |
| 河西秀哉氏は、「近現代史演習レポート 日本史学専攻M2」で、「原武史著『大正天皇』(朝日選書)(原武史)」を「大正天皇を巡る風説に疑問を投げかけた原武史著『大正天皇』(朝日選書)(原武史)」と題して次のように評している。 |
| 明治天皇と昭和天皇という時代に象徴された輪郭のはっきりした天皇の間にあって、作者によれば「天皇にあるまじき過剰なまでの人間性を保持しようとしたところに由来した」大正天皇の不運。遠眼鏡事件を検証して脚色された風説だったと指摘し、客 観的な大正天皇を描こうとする。大正という時代がどういう時代だったのか。天皇と なって病状悪化が進み、摂政の皇太子とともに「昭和」が始動して、悲劇の天皇と 「大正」が忘却されていく。 |
近現代史演習レポート 日本史学専攻M2 河西 秀哉
つまり、第一次世界大戦後の世界情勢において、ロシア・オーストリア・ドイツなどが革命によって王制が打倒され、そうした革命が、日本に波及することに対する危機感が政府および宮中にあった。そうした状況下にあって、大正天皇では心許ない、カリスマ的権威を持つ、国民統合のための「強い」天皇の必要性があったのだ、と著者は言うのである。そのために、大正天皇は宮内大臣牧野伸顕によって「押し込められた」と推測している。本書において、序章のこの推測は非常に重要な部分であり、この考え方が本書の様々な記述の中に貫かれている。 第二章からは前述のように、大正天皇の生涯が時系列的に記述されている。生まれながらにして病弱であった嘉仁皇太子は、病気がちのため、就学年齢となってもすぐには学習院に入学せず、個人授業でそれが補完されていた。そのため、「規則という様な事に就いて、何等御観念も御発達が無」く、学習院入学後は学校の規則が悪影響を及ぼし、体調を崩したと述べている。そうした病気によって、皇太子に学習の遅れが生じ、一八九四年の学習院中退後は個人授業が再開された。これは、国学の本居豊頴や漢学の三島中洲が侍講となって、詰め込み式で教育されたものであった。著者はこうした「詰め込み教育」が皇太子の健康を悪化させ、より教育の遅れを生むという悪循環を生み出したとしている。その後、有栖川宮威仁親王が東宮輔導となり、九条節子との結婚を機に、皇太子の健康は回復していく。 第三章以下の、皇太子の「巡啓」に関しては、本書の中でもっとも多くの記述が割かれた部分である。一九〇〇年の三重・奈良・京都への地方巡啓では、非公式の、非政治的な「微行」とされ、皇太子が授業で学んだことを実地で見学することが目的とされていた。この中で皇太子は、人々に気さくに声をかけており、著者は皇太子が教育によって性格を矯正されなかったからこそ、このように純粋に感情を発露させることができたと推測する。その後の北九州巡啓・信越北関東巡啓・和歌山瀬戸内巡啓も同様に、皇太子は人々に気さくに声をかけたり、意表をつく言動をしたり、自らの都合でしばしば予定を変更したりなどしていた。こうした巡啓中の皇太子の健康状態は非常に良好であり、巡啓には「転地療養」の意味合いがあったのではないかと著者は指摘している。この頃になると、明治天皇の体調不良により民衆には明治天皇の実体が「見えなく」なっていき、その反動として皇太子が民衆に「見える」ようになっていく。 第四章では日露戦争後の皇太子が大元帥・天皇を補佐する政治主体として認識されるようになり、巡啓も公式ないし事実上公式となったことが述べられている。この頃の皇太子の巡啓は、全国に「皇恩」を行き渡らせる役目を持っていた。 第五章になると一部、皇太子の東京での生活が描かれている。家族との団らんの中での皇太子は人間的で、気さくであった。また、日露戦争後の巡啓では軍事演習の見学を目的とするものも加わり、より一層、明治天皇の代理としての役割が強くなった。 第六章では即位してからの大正天皇が描かれている。天皇になってからは、多忙な公務のために生活が激変し、行幸は軍事目的のものか国家的なイベントに限られるようになった。そのため、天皇が一般市民と実際に接触する機会はほとんどなくなり、直接天皇の身体を見せなくすることは天皇の政治的な権威を一層確立させたと著者は述べている。こうした生活環境の激変は、天皇の体調を悪化させることとなった。一九一九年八月頃になると、病状は目に見えて悪化し、原敬首相は天皇の病気を「国家の重大問題」として認識するようになっていた。その一方で、裕仁皇太子は見学のための全国巡啓を開始するようになり、皇太子が「見える」存在として認識されるようになる。 終章では大正天皇の病状発表をめぐる経過について述べられている。発表に伴う一連の動きは非常に高度な政治的判断に基づかれたものであり、一九二〇年一〇月の病状発表文中にある、幼少の「脳膜炎様の疾患」という文言が発表されるまでは紆余曲折があった。大正天皇は言葉の自由がきかない状態の中で、病状発表および摂政設置に対して、精一杯の抵抗の姿勢を見せたが、宮内大臣牧野伸顕をはじめとする宮内官僚によって強制的に「押し込め」られたのではないかと著者は述べる。その後、裕仁皇太子の摂政就任により、皇太子と「臣民」の一体感が強まり、大正天皇の死後、「明治ブーム」が到来し、「大正」が次第に忘却されていくようになる。
第二の疑問として、「見える」天皇と「見えない」天皇に関する解釈である。著者は大正天皇の行幸の様子が写真付きで報道されることについて、「生身の姿がマス・メディアを通じて伝えられ……多くの人がそれを知るようになった」、「明治天皇とは異なる大正天皇の意向」と評価しているのに対し、行幸において一般市民と実際に接触する機会を失ったことに関しては、「大正天皇の身体を直接見えなくすることで、政治的権威をいっそう確立させる」「天皇個人の自由な意思が受け入れられることはなかった」と評価している。こうして見ると、著者は場面ごとで都合良く「見える」天皇と「見えない」天皇を使い分けていないだろうか。 明治天皇を素材としてこうした問題に取り組んだ佐々木克氏は、六大巡幸期は、天皇イメージは「揺れ」ていて、地方における臣民形成のために、たびたび天皇は生身の姿を見せなければならなかったとしている。その後、一八八九年の大日本帝国憲法と皇室典範の制定によって、天皇像は完成し、この完成された天皇像を図像化したのが「御真影」である。この記号化された「御真影」が全国に広がっていくことによって、天皇の生身の姿は見えなくなっていく。(佐々木克「明治天皇の巡幸と『臣民』の形成」『思想』平成六年一一月号一九九四)本書が対象とする時期において、大正天皇をどのように「見せよう」「見えないようにしよう」としていたのだろうか。著者には、佐々木氏のように実際の政治の動きの中で、マス・メディアの発達とも関連させて、もっと大局的に深く検討して欲しかった。それによって、著者の目指す近代天皇制の特質により迫れるのではないかと思われる。 第三の疑問として、著者が「押し込め」の一つの原因としてあげた当時の国際情勢と君主制の問題である。著者はロシア、ドイツ、オーストリア、トルコなどのヨーロッパでの君主制の崩壊によって、その危機感が日本に伝わり、その状況下において大正天皇では心許ないと思った宮内官僚に「押し込め」られたとしているが、ロシア以外は第一次世界大戦の敗戦国であり、戦勝国の日本とは全く違う状況だったのではないだろうか。日本はロシアのように総力戦で大戦にも参加していないし、国内もそれほど疲弊していなかったのではないだろうか。ロシア革命は、君主制が云々というよりは、国内における共産主義思想の取り締まり、つまり治安体制の強化を促すという方向に向かっていったのであり、これらを外的要因として「君主押し込め」を言うにはやや無理があるのではないだろうか。 最後の疑問として、大正天皇の政治的行為の問題がある。本書は、安田浩氏の指摘した大正天皇および天皇制における絶対的権威の低下については触れられていないように思われる。(安田浩『天皇の政治史』一九九八)天皇「権威」の問題や天皇の政治行為の問題について、その統治能力という観点から、本書でもっと触れて欲しかったというのが率直な感想である。これまでの研究史を見てみると、飛鳥井雅道氏は、明治後期から天皇の「機関」化が進み、大正天皇の登場はその流れをより押し進めたとし、大正デモクラシーもこうした「機関」化と権威低下が無関係ではないと指摘している。(飛鳥井雅道「近代天皇像の展開」『日本通史』第一七巻一九九四)また増田知子氏は、政党と内閣の妥協という一九〇〇年体制の成立が天皇主権と国家主権の並立状態を生み出し、天皇は大権諸機関が衝突した場合に限り、その調整を行って裁定を下す調整力・決断力が求められたとしている(それは、安田氏の言葉を借りれば、「限定的親政権力」の行使ということになるだろう)そして、大正天皇の登場はその判断力のなさから、君主の意思に頼ることなく、どう大権を一元的に運用するかという問題が、美濃部達吉の「大臣責任論」「天皇機関説」と関連して生み出されることとなったとしている。それによって、国務大臣は機関化された天皇に忠誠を誓うのではなく、統治権を有する国家の意思に服従するという状態が生み出されることとなった。(増田知子『天皇制と国家』一九九九)このように、従来の研究史においては「機関」化の流れを指摘されている天皇が、なぜ「押し込め」られなければならなかったのか。天皇が超国家的私的権力を発揮する立場でなく「機関」ならば、その権威を低下させてまで「押し込め」る必要はないのではないか。安田浩氏は、幼児より「脳病」の人物が「親裁」し、「親政」を行っていたという事実の公表が招く天皇権威の低下の問題について、統治能力なき大正天皇の恣意的行動による政治的混乱を避けるため、その権威が低下することもやむを得ない選択だったと指摘しているが、それについて著者はどのように考えているのだろうか。(安田氏前掲書) 本書においては、人間的な大正天皇について多く記述されているが、政治的な大正天皇がどうであったのかはあまり触れられていない。つまり、本書では主に、巡啓などを通じて、天皇と人々が触れあうときの言動やそのイメージや印象といった、君主の社会的側面から大正天皇を扱っているように思われる。が、これまでの研究史で問題になっているのは、上記で指摘したように、君主の政治的側面からである。察するに、著者は君主の人格的側面や社会的側面を強調することによって、君主の政治的側面からの理解を凌駕できると考えたのではないだろうか。評者の考えを述べれば、「天皇」という立場である以上、その政治性について深く探る必要性があり、君主の社会的側面からだけではこれまでの通説的理解を突き崩すのは難しい。飛鳥井雅道氏『明治大帝』(一九八九)刊行後、天皇の人格的側面や社会的側面に焦点を合わせた研究が注目され、本書もそうした研究動向の流れに乗っているものと思われる。大正天皇のこうした側面を描き出した本書の意義は大きいが、大正天皇の本格研究のためには、そうした側面とともに、従来の政治的側面も含めて考える必要性があるだろう。 以上、評者なりにいくつかの疑問について述べてきたが、誤読や的はずれな指摘もあるかもしれず、その点については著者の御寛恕をお願いしたい。 |