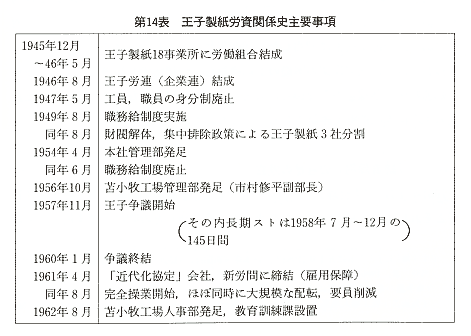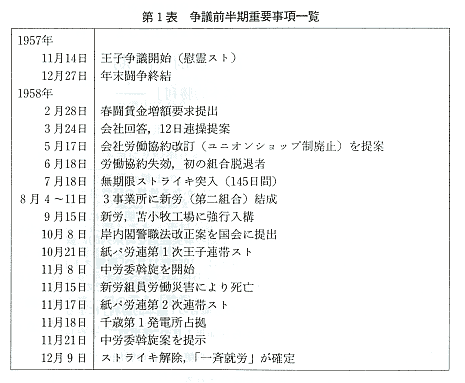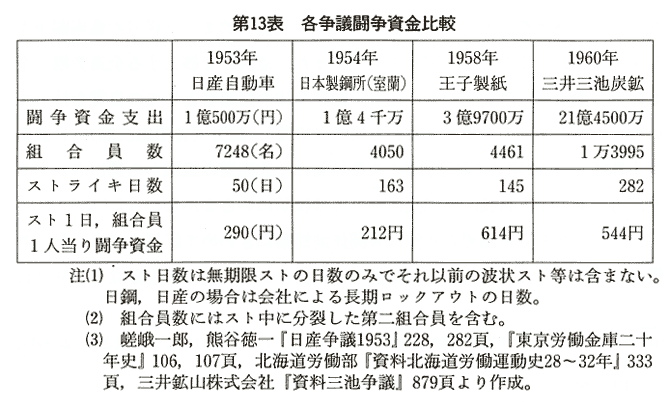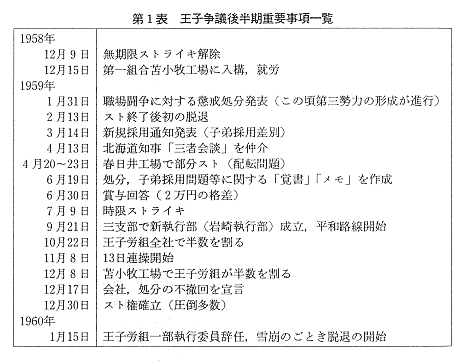�@
�@����Y�Ǘ�������͓����n���Y�}�����̎w���ɂ����̂Ȃ̂������R�����I�ɐ��܂ꂽ���̂Ȃ̂����R�Ƃ��Ȃ��B���̎������L����ŏI�I�ɗ��Y�����B�P�X�S�U�D�P�O�D�Q�T���A�J�n�^�ɂ��Ƣ�J���҂͂��̐�����i�삷�邽�߂ɕ����I�ɐ��Y�Ǘ������Ă��邯��ǁA����Ƃĉi�������]�͖�����Ƃ���悤�ɁA�P�X�S�U�D�P�O�����̓}�����͎w����������\�͂������Ȃ������悤�ł���B����́A���ړI�ɂ͓����̘J���ҊK���̍��h���n���x���������Ă���A�^���_�I�ɂ͓����ψ������n�ߓ����̎w�����̎w���\�̖͂��ł���A������ɂ����o���ł������悤�Ɏv����B������j�ςɂ��A�����}������Ĉȗ��̉E�h���̉e�����傫���ƌ���B���̌�̓��{���h�^�����A���̎����̢���Y�Ǘ�������̈Ӌ`��F�߂Ȃ��܂܂ɐ��ڂ����̂́A���������������傫�ȑ����ƂȂ��Ă���悤�Ɏv����B�i����Y�Ǘ������̈Ӌ`�ƍ�����Q�Ɓj