| 第47部 |
1985年(昭和60年)の主なできごと.事件年表 |
|

更新日/2018(平成30).11.6日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
2002.10.20日 れんだいこ拝 |
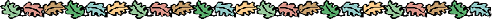
| 【1985年度政府予算案】【中曽根内閣】 |
一般会計3.7%増で引き続き50兆円に乗せたが、一般歳出が前年比マイナス*.*%の緊縮財政の中で、4年続きのマイナス・シーリングの中で引き続き防衛費だけ6.9%増で突出、遂に3兆円を突破した。GNP比率0.997%。昭和51年11月の閣議決定(三木内閣)の「GNP比率1%を超えないことを目途とする」の線まで89億円を残すだけとなった。
ODA(政府開発援助)は10%増。「総合安全保障」傾向が一層強められた。
国債発行額は、11兆6800億円(建設国債が5兆9500億円、赤字国債は5兆7300億円)で、前年度当初より1兆円減、国債依存度は22.2%になった。年度末の国債残高は133兆円と見込まれ、国債費は10兆円を超えて、歳出の**.*%を占め、1位の社会保障費を抜き、支出項目の第1位に踊り出た。 |
| 【田中角栄目白邸の新賀の様子】 |
| 1.1日、目白邸に例年を上回る600人が年賀の挨拶。この時の角栄の挨拶は、「沈黙は金。謹賀新年。正月元旦。これで終わり」というだけの奇妙な挨拶であった。 |
| 【キッシンジャー元国務長官が目白の私邸に田中角栄を訪れる】 |
| 1.8日、来日中のキッシンジャー元国務長官が目白の私邸に田中角栄を訪れる。 |
| 【竹下派が「創世会」立ちあげの動き】 |
1.23日、「創世会」の第2回準備会(拡大世話人会)が開かれた。新たに衆議院・亀岡高夫、山村新治郎、野中広務、榎本和平、塩島大、参議院・梶木又三、井上吉夫、中村太郎、岡野祐、志村哲良が加わり、前回よりも11名増の25名の国会議員が集まり、勉強会として「創政会」の旗揚げを決議。「創政」とは、竹下の後援会機関誌名「創政」から名づけられた。席上、竹下が「私は、竹下登の全てを燃焼し尽くし、一身を国家に捧げる覚悟で参りました」と決意を述べた。2.7日の設立総会を確認。
1.27日、四日後、田中-竹下会談。竹下が「創世会」の設立を伝え次のようなやり取りをしている。
| 竹下 |
「全国各地に勉強会を拡大したい。また、中堅、若手を集めて勉強会を開きたいと考えております」。 |
| 角栄 |
「県会議員出身で首相になった例は太政官発布以来ない。君がなれば初めてだがなかなか大変だぞ。『勉強会大いに結構。但し、稲門会(雄弁会)のような早稲田グループだけに偏ってはいかんよ、いろんな連中を入れて、幅広くやれよ』と注意しておいておいた」。 |
この頃の田中の思惑は、「一に二階堂進、二に江崎真澄、三に後藤田正晴だ。順序を間違っては駄目だ」。
2.4日、「創世会」の旗揚げを廻って、二階堂進・小沢辰男・金丸・竹下の四者会談が、梶山と小沢の立会人で行われた。 |
1.26日、暴力団山口組組長ら3名が一和会系組員に射殺され、抗争激化する(87年終結)。
1.28日、日本福祉大学の大学生らを乗せたバスが国道から長野県笹平ダムに転落、25名が死亡する。
1.28日、 中曽根康弘首相が防衛費GNP比1%枠突破の可能性を言及、衆議院予算委員会が混乱状態になる。
| 【田中六助・前幹事長の遺言】 |
田中六助・前幹事長が長らく病床にあったが、この日心筋梗塞で逝去(享年62歳)。政界宛て遺言状には次のように認められていた。
| 「私は陰ながら元総理の白を信じてできる限りのことをやって参りましたが、その実を実現しないまま先に旅立つことをお詫び申し上げます。達磨様は9年間石の上に座したと云われますが、よく十年間もこの批判に耐えておられるお姿は神仏にも等しい姿です。私は誰よりも尊敬していることを素直に申し上げます」。「私が最後にお世話を被りたいお願いの一つは、田中角栄元総理の問題に取り組む姿勢です。何か問題が起るたびに、この問題と結びつける政界の姿勢を早く改めてもらいたいことです」。 |
|
| 【竹下-金丸連合が「創政会」を発足】 |
2.7日、幹事長・竹下登、金丸信による政策勉強会「創政会」旗揚げ正式発足。平河町砂防会館新館で、衆院29名、参院11名の計40名(田中派の3分の1)が出席。梶山が司会、渡部が開会の挨拶、橋本が経過報告、竹下が会長としての挨拶を行った。後に、「竹下派七奉行」と呼ばれる、小渕恵三、橋本龍太郎、小沢一郎、羽田孜、梶山静六、奥田敬和、渡部恒三ら40名が参加した。表向きは、政策勉強会であったが、実際は、竹下総理総裁を目指す、「派中派」であり、田中派の亀裂が鮮明化した。「経世会」の前身となるものである。
その背景は次のように説明できる。田中派の総帥・田中角栄元首相は田中政権後も政界に睨みを利かせ「田中支配」と云われる権力の二重構造を現出させていた。しかし、ロッキード事件に見舞われ、田中以来10年以上も、総裁選に自前の候補を立てることができなくなり、田中派内に不満が鬱積していた。その気分が遂に竹下登を押し立てて「創政会」発足に繋がった。創政会発足直後、田中は脳梗塞で倒れるが、この後、田中派内は、竹下「創政会」グループと田中直系の二階堂グループとの対立が続き、分裂状態に陥ることになる。角栄激怒し、切り崩し工作も行われる。 |
2.9日、社民連第四回全国大会を岡山県建部町友愛の丘にて開催。田代表辞任、後任江田五月、阿部昭吾書記長。「再生・前進」を掲げた。
2.13日、竹下が創世会幹部二人(橋本、梶木)を連れて目白邸を訪問、田中と会談する。田中は、「同心円で行こう」と云ったと伝えられている。
2.19日、小沢・羽田・梶山が目白邸を訪れ、田中と会談する。「お-っ、お前等よく来たな。本当によく来てくれた。しかし、お前等も強引にやるもんだ」と云ったと伝えられている。
2.21日、田中派が123人になる。
財界の中山素平、今里広記が目白の田中邸を訪れ、電電公社民営化後の初代社長に真藤総裁を当てることが財界の総意だと説得に努めたが、角栄は頑なに北原副総裁に固執して、話はまとまらなかった。
| 【日共が、日中出版党員を除名する】 |
2.22日、柳瀬・安藤氏は、除名された。2.24日赤旗に、「柳瀬宣久の除名処分について」が掲載された。一方的に都合のよい「党規律違反の概要」が書きなぐられていた。次のように罵倒している。
| 「まして、前衛党たる日本共産党の場合、党員は、党の政策や方針に反対する見解を党外で勝手に表明することを明確に禁じた規定を含む党規約を自ら承認して入党しているのであって、党員にとってはその規約を守ることが、党にとってはその規約を守らせることが、すなわち『結社の自由』の重要な内容なのである。この党規約を認めて入党する以上、党員が自らの出版や言論の自由をこの『結社の自由』と両立させつつ積極的に行使することは、本来、外部からの強制ではなく、本人の自発的意思である。(なお、党の政策や方針に対する意見、異見は、党内で表明する道が党規約で保障されている)前衛党の党員が、『出版の自由』ということで、党攻撃を目的とした出版が勝手にできるなどという柳瀬の議論は、党の上に個人を置くことを求めるだけでなく、党破壊活動の自由を党自身が認めよというものであり、綱領と規約の承認を前提に自覚的に結集した前衛党を解体に導く途方も無い誤りの議論である。それは、前衛党の『結社の自由』のあからさまな否定に他ならない」。 |
 (私論.私見) 「柳瀬宣久の除名処分について」の論法について (私論.私見) 「柳瀬宣久の除名処分について」の論法について |
これは、宮顕の戦前日共党中央委員小畑リンチ致死事件の際の居直り弁明時のそれと瓜二つである。つまり、宮顕は、同事件に対して何の反省もしていないことになる。「党員にとってはその規約を守ることが、党にとってはその規約を守らせることが、すなわち『結社の自由』の重要な内容なのである」とは、入党後の個人は煮て食われようが焼いて食われようが、党中央に対して何ら文句言えないとする恐るべき誓約を強いらることを示唆している。それが、「結社の自由の法律的意味である」とまで云う。無茶苦茶な論法であるが、これが罷り通っているみとの方が不思議だ。互いに頭がおかしいに違いない。
2006.11.24日再編集 れんだいこ拝
|
|
| 【田中角栄の最後の公的スピーチ】 |
2.25日、田中角栄が羽田孜の後援会パーティー「羽田孜を励ます会」に出席。次のようにスピーチしている。
| 「最近は、世代交代とか、田中がどうのこうのという声がない訳でもない。しかし、召される時は、神様が否応なく引っ張っていく。心配要らない」。 |
2.26日、田中派閣僚経験者の「さかえ会」に出席(赤坂の料亭「川崎」)。次のようにスピーチしている。
| 「賢者は聞き、愚者は語る。オレは今日からは賢者になる。何か云うことがあればなんでも言って来てくれ」。 |
これが田中の公の場での「最後の肉声」となった。 |
| 【NTTの初代社長を廻って、今里広記が乗り込み田中角栄と協議】 |
| 2.27日、日本精工相談役にして新電電設立委員長の今里広記(85.6.30日没)と田中角栄が、目白邸で、4.1日より民営化する日本電信電話株式会社(NTT)の初代社長を廻って協議した。中曽根の推す現公社総裁の真藤恒(ひさし)と田中角栄の推す副総裁の北原安定が初代社長のイスを廻って確執しており、今里は中曽根の意向を受け説得に乗り出した。北原は、早大理工学部電気工学科卒、同軸ケーブル方式の研究により工学博士の経歴を持つ親田中系の大物であった。
|
| 【田中角栄倒れる】 |
| 2.27日夕刻、竹下登らが旗揚げした創世会が波紋を広げる中、田中角栄元首相が脳梗塞で倒れる。午後8時半、東京逓信病院に入院(5.5日判明)。以降、長期療養生活に入ることになった。「政界の田中支配終焉」となる。 |
新電電人事は、真藤社長、北原副社長、阿部非常勤取締役という形で決着した。
3月、胡錦濤中華全国青年連合会主席(中国青年代表団団長)が訪日。
3.10日、ソ連のチェルネンコ共産党書記長死去。3.11日、後任にゴルバチョフ政治局員がソビエト連邦共産党書記長に就任する。中曽根首相がソ連訪問。
3.17日、茨城県筑波研究学園都市で国際科学技術博覧会が開催、入場者2000万人以上(17日~)。
3.21日、日本初のエイズ患者を認定する。3.22日、厚生省が日本人エイズ患者第1号を発表する。
4.1日、電電公社が株式会社NTTに、専売公社が日本たばこ産業(JTT)に生まれ変わった。
| 【党中央の「葦牙(あしかび)」攻撃】 |
4月以降、日共党中央は、葦牙(あしかび)派に対する批判キャンペーンを開始した。前衛、民主文学、文化評論、赤旗評論特集版で17回にわたって展開した。その後、党からの排除、粛清をした。
| (1) |
霜多正次は、「離党届」を出したが、党中央は彼の“離党の自由”を認めず、4カ月間放置し、その上で規約に基く除籍措置にした。これは除名処分と同質の党外排除である。霜多は、「ちゅらかさ―民主主義文学運動と私」を発行し、そこで「4月号問題」とその経過を克明に分析、発表した。 |
| (2) |
中里喜昭は、1987年3月、「離党届」を出した。しかし、党中央はその受け取りを拒否し、半年後の9月、彼に「除籍を通告した。彼は、葦牙誌上で、党中央の葦牙批判キャンペーンへの反論・批判文を書いた。党中央は、17回の葦牙批判キャンペーン中、「中里喜昭の変節と荒廃」など6回にわたり名指し題名の批判文を掲載した。 |
| (3) |
武藤功は、キャンペーンへの反論文だけでなく、「宮本顕治論」を発行し、そこで宮顕の「あとがき」内容を詳細に分析、批判した。党中央は、武藤を「党内の問題を党外に持ち出した」として査問した。その「党内の問題」というのは「民主集中制」を一般公刊の書物で批判したことであった。葦牙関係で査問したのは武藤一人である。査問は2日間行なわれ、場所は茨城県委員会の建物の一室だった。中央委員会を代表して文化局長が、武藤の党籍のある水戸まで出張し、茨城県委員会からは3人の常任委員(副委員長、書記長、文化担当常任委員)が党側のメンバーとして立ち会い、査問の上、彼を除籍した。彼は、「葦牙1993年1月号」で、「久野収とのインタヴユー“市民権思想の現代的意義”」を行なった。その内容、とくに丸山真男「戦争責任論の盲点」からの引用個所に宮顕は激怒した。久野による引用内容は、「日本共産党の非転向の指導者たちはたしかに思想的には立派にちがいないが、政治的にはどうなのか。彼らは軍旗ごと捕虜になってしまった部隊ではないのか。軍旗を下ろさなかった点ではまことに立派であるが、丸山眞男ふうに言うと、木口小平は死んでもラッパを離しませんでした、というような結果になりはしないか」というものであった。13回にわたる丸山真男弾劾キャンペーンはここから出た。しかも、そのキャンペーンは、第20回党大会での党綱領改悪の基礎となった。 |
| (4) |
中野健二は、第10回大会で編集長を辞めさせるという党中央戦略が失敗した後も、辞任に抵抗し続けた。しかし、彼が、他の常幹たちとともに辞任したので、事実上の除名処分である除籍措置にはせずに離党を許可した。 |
| (5) |
第20回党大会前後の丸山真男批判大キャンペーンには、丸山のプロレタリア文学運動論への批判も中心の一つだった。山根献は、『葦牙』の「丸山真男追悼集」で、「政治の優位性」論への批判を、丸山の見解と対比しつつ、緻密に展開している。 |
| (6) |
葦牙同人会は、その後、隔月刊誌「葦牙ジャーナル」も、吉田悦郎を編集責任者として発行した。 |
| (7) |
元常幹上原真は、そこで、毎号「深夜妄語」を連載している。さらに、同人会として、霜多正次全集全5巻を刊行した。彼らは、インターネットHP葦牙において、『文学運動における「自主」と「共同」』を追求しつつ、「4月号問題」とその経過を解明する、特集記事、論文を多数載せて、批判活動を続けている。 |
葦牙』側は、党中央による批判キャンペーンにたいして、繰り返し反論文を掲載した。その中で、以下は、これらの背景に関して葦牙側が反論として行なった、宮本『文芸評論集第一巻』「あとがき」分析の要点である。1970年代は、高度経済成長による社会構造や生活意識の変化が大きくなった。そのため、民主主義文学同盟作家たちは、現実の変革主体の形成をめぐって、これまでのような単純にたたかう労働者よりも、職場や地域での、人びとの共同・連帯をつくりだすための地道な努力を重視し、それぞれ独自の方法を追及、模索していた。二度の石油ショックで世界経済が深刻な打撃をうけたなかで、日本の企業は徹底した「減量経営」で労働者への収奪をつよめ、労働組合運動の右傾化が一段とすすんだ。1980年には、「社公合意」(社会党と公明党が共産党排除の政権構想に合意)ができ、つづく衆参両院のダブル選挙では自民党が大勝するという事態になって、宮顕委員長は「戦後第二の反動攻勢の時期」と規定した。
「4月号問題」とは、1980年11月、宮顕が「文芸評論集第一巻」を出版し、その「あとがき」の思考を、傘下の民主主義文学同盟運動、作品に“強行持ち込み”をしようとしたものであった。彼は、そこで「プロレタリア文学運動」の「戦後的総括」を試みた。しかし、その戦後的文学の内実をしっかりと把握できていなかったために、「社会的発展性」とか「科学的法則性」とかいう空疎な観念でしか、文学創造の方法を見出すことができなかったという事態に立ち至った。それは「戦前回帰」というよりは「戦後認識の欠落」の文学的な現れだった。それは政治的には、政治における「戦後認識の欠落」と軌を一にする事態だといえる。当時、「4月号問題」における“宮本代理人5人”と民主主義文学同盟常幹たちとの議論で意見が分かれたのはまさにその文学における「戦後問題」だった。つまり、辞任した10人の常幹たちは、戦後的な情況における人間認識・把握については、そのヒューマニズムや人権のあり方、男女のあり方、政治的自由のあり方など多様な実態を固定的にではなく、ビビットに描くべきだと主張したのにたいして、“宮本氏の「戦後的総括」に忠実な代理人5人”は、「社会発展の方向」を描けとか「先進部分の闘い」を描くべきだというような「戦後的階級史観」を強固に主張し、ノンポリ化やマイホーム主義を批判すると称して実質「政治の優位性」の戦後版というような作品の創造を主張した。その文学路線の違いが「4月号問題」の根底にあったのである。
|
4月、彭真全人代常務委員長が訪日。
4.23日、民社党第三十回大会。4.24日、長老支配を巡って佐々木委員長と春日常任顧問が対立。4.25日、塚本三郎委員長・大内啓伍書記長を選出)
5.2日、第11回先進国首脳会議,ボンで開く。
5.2日、山形県で自動販売機に置かれていた除草剤入りのドリンク剤を飲んだ男性が死亡、同様の事件が全国各地で発生する。
5.8日、「月刊越山会」に田中真紀子が「父の近況ご報告」寄稿。「父が今までのように実務一本槍の人ではなく、更に深く思索に裏づけられた『哲人政治家』として蘇ってくれることを願っています」。
5.16日、ロッキード裁判丸紅ルート控訴審で、東京高裁が贈賄側と収賄側の分離審理を決定。
5.17日、北海道の三菱南大夕張鉱でガス爆発が発生、死者62人。
5月、長崎と福岡で中国総領事館がそれぞれ開設。
6.6日、イトーピアの田中事務所が閉鎖される。田中直紀氏が発表した。「全く寝耳に水」の発表だった。
6.18日、 豊田商事の詐欺事件についてマスコミが取材中、報道陣の前で豊田商事の永野一男会長がテレビカメラの放列の前で暴漢2人に刺殺される。
6.19日、投資ジャーナルの中江滋樹元会長ら11人が詐欺容疑で逮捕される。
6.20日、二階堂グループが、ホテル・ニューオータニで「人間・二階堂進を語る会」を開き、8千名が集まる。
| 【中曽根的なるもの政治としての国鉄内の角栄派と中曽根派の人事抗争、中曽根派が勝利する】 |
6月24日、国鉄総裁の仁杉巌氏が辞任。中曽根総理は仁杉総裁のみならず全重役の辞表を出すことを要請、重役陣の一部に抵抗があったが、角栄派的な隅田国武理事をはじめ全理事が退陣させられた。仁杉の後任には、前運輸事務次官の杉浦喬也が就任。杉浦新総裁の改革がやりやすいような体制ができあがり、これより以降、国鉄「改革」が加速した。中曽根は自著「天地有情」の中で、「仁杉、隅田両君のクビを取ったから改革がスムーズに運んだ」と述べている。
杉浦は国鉄分割民営化に励み、干されていた松田昌士(後のJR東日本相談役)、井出正敏(同JR西日本相談役。JR福知山線脱線事故後に辞任)、葛西敬之(同JR東海会長)の「改革3人組」を中枢ポストに呼び戻し、国鉄民営化を強行して行くことになる。「国鉄改革三人組」は次第に実権を握り始め、やがて強硬路線に転じる。分割・民営化などへの協力を求める労使共同宣言を提案し、国労は賛否をめぐって内部対立が深刻になったものの結局は拒否し、動労、鉄労、全施労が応じる。続いて、国鉄当局側は「人材活用センター」を作り、余剰人員であるとして国労組合員を隔離し始めた。その実態は、本来の職務をさせず、草むしりなどの雑用をさせたものであった。「日勤教育」は人材活用センターの手法を受け継いだものといわれている。
中曽根首相の直轄機関として、省庁の枠を超える権限を持つ国鉄再建監理委員会が発足する。委員長に亀井正夫(住友電工社長)、委員長代理に加藤寛(臨時第4部会長、慶応大学教授)、他に住田正二(元運輸事務次官)、隅谷三喜男(東京女子大学長)、吉瀬維哉(日本開発銀行総裁)が選ばれた。この委員会で、国鉄「再建」策が練られ、7月、最終答申が提出される。87.4.1日JR7社が誕生していくことになる。
|
6月、松崎が動労本部の委員長に就任する。松崎委員長は、国鉄の分割・民営化路線協力に舵を切る。
6月、田中角英事務所が閉鎖する。
7.1日、大阪地裁が豊田商事に破産宣告、被害総額は2000億円、被害者は全国で3万人。
7.5日、労働者派遣法成立。
7.10日、国際環境保護団体グリーンピースの核実験抗議船「にじの戦士」爆破される。
| 【東大院生支部の『宮本解任決議案』問題発生】 |
党内反宮本派清掃第18弾。この頃東大院生支部の「宮本解任決議」騒動が発生している。宮地健一氏の「共産党、社会主義問題を考える」の「第4、東大院生支部の党大会・宮本勇退決議案提出への粛清事件 1985年」で詳述されているのでこれを参照する。
7月、東大院生支部指導部が、11月開催の第17回大会に向けて「宮本解任決議案」を東京都委員会に提出すると云う事件が発生した。宮顕解任理由は、党中央委員会とくに議長宮顕が、1・1977年の第14回大会後から誤りを犯し、国政選挙10年来停滞の指導責任がある。2・敗北主義・分散主義等党員にたいする様々な「思想批判大キャンペーン」をする誤りの責任があること等を問うものであった。その根底には、第14回大会以降の「民主集中制の規律強化」.「自由主義、分散主義との全党的闘争」を推し進め、ユーロコミュニズム・先進国革命とは逆方向に向かう宮顕路線への、東大以外も含めた学者党員、学生党員の党中央批判の感情、意見が反映されていた。院生支部は、規約に基く正規の提出スタイルを求めて、中央委員会と1回、都委員会と2回協議し、不破にも「質問書」を提出した。
9月、党中央は、支部に対して、「1.大会議案は提出できる。2.提案は支部でなく代議員個人」と正式回答した。
10月、東大大学院各学部支部から選ばれた代議員60人で構成される東大大学院全学支部総会が開かれた。都党会議の代議員枠2人枠に対して4人が立候補した結果、宮顕勇退派1人、党中央派1人が選出され、党中央の宮顕勇退派落選工作が失敗した。投票内容は、宮顕勇退派23票、伊里一智13票の60%獲得に対して、中央支持派は17票と7票で40%しかなかった。宮本解任・勇退派の60%もの得票率は、院生党員内だけでなく、東大全学における宮顕逆路線批判の強烈度合いと、その共同意志をも示すのではないかという、“今そこにある危機”を浮き彫りにした。
先に党中央は、「個人なら、規約上提案できる」と回答していたので、選出された都党会議の代議員Y氏は「代議員個人」として、まず都党会議で「宮本解任決議案」を出す雲行きとなった。東大教職員支部、院生支部と学生支部はこれに強い関心と共感、暗黙の支持で見守ることとなった。「宮本解任決議案」提起運動は、「安田講堂封鎖」以来の東大全学共産党3組織の共闘となった。かの時は封鎖をどう解除するかという共闘であったが、こたびは宮本逆路線批判への決起行動共闘となった。
宮顕がこれに如何に対処したか。宮顕はこの動きを断じて認めなかった。1・東大全学60%の宮顕批判をバックにして「宮本解任・勇退決議案」討論が都党会議だけでなく第17回大会まで上程されるのか。2・宮顕側が強権発動で非常手段を採るのか、という危機管理上の選択となった。宮顕は、躊躇せず後者の選択肢を選んだ。いかなる卑劣な「規約違反」手段を採ろうともYの代議員権を剥奪することを指令した。
11.5日、東京都常任委員会は、「決議案は当初5人の連名である。それは多数派工作によるものであり分派活動である」と、でっちあげた。直ちに、その5人を査問し、権利停止6カ月処分にした。さらに、査問中、権利停止中であることを理由としてY氏の代議員権を剥奪した。
11.11日、都党会議が開かれた。この時、上田が党中央を代表して、「Yと伊里一智一派の分派活動なるもの」を40分間にわたって批判する大演説をした。上田は宮顕忠誠派の本質を曝け出し、以後“上耕人気”は急速に低落することとなった。
|
| 【志位.河邑の大活躍と大抜擢】 |
この粛清劇で、志位和夫と河邑重光幹部会委員・赤旗記者が大活躍した。この時志位は、5人の査問.権利停止処分とY氏の代議員権剥奪を直接担当し、粛清の先頭に立った。宮顕との直通ルートでひんぱんに連絡し指示を受けた。そして、宮顕勇退勧告派の動きを、「分派の自由を要求する解党主義、田口富久治理論のむしかえし」と批判した。河邑は、伊里一智批判の大キャンペーンで、「負け犬」、「ビラまき男」とするレッテルを貼った。伊里一智の思想的人格的低劣さを捏造する記事を乱発した。その記事は、宮顕の事前の校閲を直接受けていた。宮顕は、従来から、自分に対する批判者の排除、党内外からの宮顕批判への反論記事内容については、細部にわたって直接、指示.点検.事前校閲するのがならわしだった。
志位と河邑は宮顕秘書出身ではなかった。しかし、宮顕秘書団よりも忠誠度が高かった。志位は、最も党派性(自分への盲従性)の高いヤングマンとの「お墨付き」を頂戴した。宮顕は、功を認め大抜擢で応えた。論功行賞として、志位を次回の第18回大会で「最年少の准中央委員(33歳)」にした。志位はさらに第19回大会で「中央委員、新書記局長(35歳)」に“超・超・大抜擢”されることになる。第20回大会では河邑が「常任幹部会委員」に抜擢される。これが「宮顕―不破―志位の重層的指導体制」誕生秘話である。戦前のリンチ仲間宮顕-袴田コンビのそれに劣らない。 |
7.19日、埼玉県草加市の残土置き場で、八潮市の中3女子の遺体が発見され、15歳の少年ら5人が殺人の容疑で逮捕される。
7.29日、ロッキード裁判丸紅ルート、丸紅3被告の控訴審初公判。
7月、中日原子力協定調印。
7月、国鉄再建監理委最終答申が閣議決定され、この時点での国鉄職員27万6千人のうち9万3千人が余剰人員とされ、首切り攻撃が始まった。動労が、この10万人首切りの先兵として国鉄労働者の前に登場することになる。
8.6日、東京麹町の料亭に、反創世会の会合が開かれる。呼びかけ人は内海英男、高島修、佐藤信二の3名。集まったのは僅か12名。
| 【日共の出版妨害事件とその余波】 |
去る1984.8.9日、日中出版社が、党中央の妨害を跳ね除けて「原水協で何がおこったか、吉田嘉清が語る」を緊急出版したが、この頃この出版に関与していた日中出版社の党員に対する査問が開始されていった。この経過を見ておく。
昨年の出版騒動からほぼ9ヶ月になる6.17日、日中出版(代表・柳瀬宣久)の女性編集者・安藤玲子宅に、「日本共産党中央委員会」名の配達証明便が届けられた。「通知」書が封入されており、「党勢委員会は、党規約第33条に規定する権限にもとづいて、貴同志の規律違反について調査することを決定した。よって、左記に指定する日時に出頭されたい」と記載されていた。規律違反容疑として、党中央の意向に反して「原水協で何が起こったか、吉田嘉清が語る」を出版した「柳瀬の反党活動に協力するという重大な規律違反」を挙げ、「こうした貴同志の行為は、重大な規律違反として、党規約にもとづく処分はまぬかれない」とあった。同様通知書が、日中出版社員に送付されていた。
安藤氏は無視しようとも思ったが、実家へ連絡される不憫を思い、決着つけようとして6.26日、「日本共産党中央委員会統制委員会」宛に返信した。概要「既に離党していること、今更『同志』として決定を知らされても驚きと疑問を感じざるを得ないこと。『出頭』はしないし、こうした『通知』は今後一切貰いたくない」旨記していた。ところが、10日後の7.6日、統制委員会より新たな通知書が日中出版気付で送られてきた。概要「統制委員会は、このような貴同志の裏切り行為に対して、党規約にもとづいて厳重に処分することを決定し、党規約第69条にもとづき、弁明の機会をあたえることにした。よって、左記に指定する日時に出頭されたい」、続けて、党規約では離党届を提出すれば離党となるのではなく「貴同志が党機関との話し合いを拒否しているため、この手続きは完了していないことを指摘しておく」と記されていた。
これによれば、「党員には離党の自由が無い」ということになる。今でもこのような党規約にされているのであろうか、恐ろしい事ではある。7.9日、安藤氏は、「祈るような思いで」日本共産党中央委員会宛てに「改めて『出頭』して弁明する必要もありませんので、右、書面にて、お断りする次第です」としたためて投函した。
篠崎氏も同様の遣り取りをしているが、篠崎氏の方が明確に答弁していることもあって、この方は争点があからさまとなっている。「基本的人権をも党は拘束できるとしているが、これは出版人としての私には許容できないものです。私は、柳瀬宣久氏の除名処分は撤回されるべきものと考えています」(6.15日付け「通知に対する返書」)。これに対して、統制委員会は、7.4日付け「通知」で、「反党分子に転落した柳瀬とともに党を攻撃するという、極めて悪質な規律違反であり、党と階級の利益を裏切るものである」と罵倒している。篠崎氏も負けていなかった。7.12日付けで返書し、党中央の出版差し止め騒動こそ自己批判すべきであり、柳瀬氏の除名処分は撤回されるべきであり、党規約第3条第4項で「党員は、中央委員会に至るまでのどの級の指導機関に対しても質問し、意見を述べ、回答を求めることができる」と定めていることを指摘し、「私が率直に自分の考えを述べたことが、『極めて悪質な規律違反』に問われることは納得できない。この点に関する統制委員会の明確なご返答を文書にて寄せられるようお願い申し上げます」と記した。
しかし、何の回答も為されぬまま、8.17日付け赤旗に、「篠崎泰彦、安藤玲子、矢田智子ら3名の反党分子の除名について」論文が掲載された。7段3分の1を費やす「公示文」になっていた。これまで分析してきた通りの駄文を繰り返して、党中央への拝跪論理を振り回している。日中出版の「出版の自由」に対して、「前衛党を解体に導く途方も無い謬論」として、「以上に述べた篠崎、安藤、矢田ら3名の党規律を真っ向から蹂躙した行為は、その変節、転落、堕落が救いがたい状態に到達していることを示すものである」、「よって、除名処分する」としていた。
|
 (私論.私見) (私論.私見) |
奇態なことは、これらの経過に見合うかのような宮顕の次のような言及があることである。宮顕にとって文章は美辞麗句でしかなく、実際にやることを見たほうが良い。「(党員の処分にあたっては、)事実の綿密な調査と深い思慮が必要だということです。この思慮を欠いてことを行うならば、事実に合わず、道理に合わないことになって、その決定は当事者の苦しみはもちろん、党にとって有害なものにならざるを得ません。‐‐‐先入観にとらわれず、機関及び被処分者の申し立てなどを事実に基づいてそれぞれつき合わせ、それぞれの側にただしてまず事実を明確にすることが特に重要であるという点であります」(第11回党大会における宮本報告)。こういう言葉を弄びながら、確信的に裏腹のことをやるという宮顕の陰険な性癖に対して、我々は氏をどう評価すべきだろうか。異常性格か、もしそうでなければスパイ特有の三枚舌文言として見ておくべきかと思われる。
2006.11.24日再編集 れんだいこ拝 |
|
8.12日、グリコ森永事件の犯人グループから一連の脅迫事件の終わりを告げる声明文が届けられる。
| 【日航ジャンボ機、御巣鷹山山頂に墜落事件】 |
| 8.12日、羽田発大阪行き日航ジャンボ機が御巣鷹山山頂に墜落。日航ジャンボ機墜落事故(日本航空123便墜落事故)」 乗員・乗客524人を乗せた日本航空のジャンボ機が群馬県の御巣鷹山に墜落、歌手・坂本九を含む死者520人をだす世界航空史上まれにみる大惨事に。翌日には奇跡的に4人の生存者が発見・救出される(「1985日航ジャンボ機の御巣鷹山墜落事故事件考」で詳解する。
|
| 【中曽根首相が戦後初の靖国神社に公式参拝】 |
| 8.15日、中曽根首相及び政府閣僚の多数が、戦後の首相として初の靖国神社に公式参拝し、日本の野党、民間団体がこれに強く反対。中国の世論は日本の閣僚が侵略戦争を美化したものと批判。9月、反日デモ。
|
8.30日、社民連全国代表者会議・夏季研修会。
9.2日、ロッキード裁判丸紅ルート控訴審田中側の初公判が東京高裁で開かれる。本人不出廷。
9.11日、 ロス疑惑の三浦和義が逮捕される。
9.11日、女優・夏目雅子が急性骨髄性白血病のため死去する。
9.19日、メキシコ南西部でM8.1の大地震,死者5000人以上。
| 【G5、プラザ合意】 |
9.22日、「先進5カ国(米・英・西独・仏・日)蔵相・中央銀行総裁会議」(「G5会議」)がニューヨークのプラザホテルで開かれ、日本からは竹下大蔵大臣、澄田智日銀総裁、大場智満財務官の一行が出席した。国際金融局長の行天豊雄は、「米欧の10人くらいの仲間と隣の部屋にいた」。「プラザ合意」が為され、「各国通貨の対ドル相場の秩序ある上昇」を目指す為替市場協調介入強化が合意された。日本はその後、バブル時代に入る。
この背景には、アメリカの双子の赤字(85年度の財政赤字・2123億ドル、貿易赤字1485億ドル)問題があった。ジェームズ・ベーカー財務長官が日本と西ドイツ(ゲアハルト・ショトルテンベルク蔵相)に頭を下げて、「ドル安誘導の為に政策協調して欲しい」と要請した、と伝えられている。この頃の日本の対米貿易赤字は、82年に約121億ドルであったのが、84年には約370億ドルに達していた。西ドイツの対米貿易黒字は79億ドル。
ベーカー財務長官は、アメリカの貿易赤字解消策としてドル安、円高、マルク高となるよう政府の強力な指導を要求した。当時、1ドル=240円台、一ドル=2.9マルク台であった。ところで、西ドイツはマルク高に誘導しなかったが、日本は真っ正直に一ドル240円台から150円台へと円高政策を導入していった。この間、アメリカの貿易赤字は減らず、日本の対米貿易赤字も減らなかった。アメリカの貿易赤字は、86年1443億ドル、87年1592億ドル。日本の対米貿易黒字は、86年約514億ドル、87年約520億ドルとむしろ増大している。但し、「円高不況」が進行し始め、GDP(国内総生産)の伸び率は、84年5.0%、85年4.7%、86年2.4%に落ちている。
特筆すべきは、日銀の過激な金融緩和政策が採られたことで、円の発行高は、84年末が約24兆5000億円、85年末が25兆5000億円、86年末が26兆9000億円、87年末が約29兆2000億円、88年末が約32兆3000億円と急増していった。公定歩合も、86年1月に4.5%、3月4%、4月3.5%と下げられていった。こうしてバブル景気の下地が準備されていった。日本の資金は為替市場を通じてアメリカに還流されて行った。
|
| 【「G5、プラザ合意」考】 |
|
プラザ合意とは何か? 森永卓郎は、1985年、中曽根政権時代のプラザ合意こそ、その後の日本経済低迷、凋落の最大の原因であったと指摘している。
https://www.youtube.com/watch?v=YvSWhT5RccY
https://www.youtube.com/watch?v=FB8inYFW34Y
ウィキ プラザ合意の解説
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E5%90%88%E6%84%8F
一般的な解説
https://www.mo-ney.net/history/plaza.html
「プラザ合意とは何か? (東海アマブログ)」。
http://tokaiama.blog69.fc2.com/blog-entry-446.html
|
|
プラザ合意、陰謀説
2006/9/18 「アメリカはいかにして日本を滅ぽしたか」。以下に、この内容を長々と引用するが、経済に疎い私が、拙い用語を使って説明するより、12年前の、この文章を引用した方が、読者の理解が進むであろう。
http://sun.ap.teacup.com/souun/130.html
ビル.トッテン著”日本は日本のやりかたで行け”から、マィヶル・ハドソン氏の{1985年プラザ合意の教訓とその影響}と題する諭支の要約。
1985年9月22日、ニューョ-クのプラザ・ホテルで、日本は金利を引き下げることにより、ドルの為替相場を支えることに同意した。当時大蔵大臣だった竹下登は、日銀を含む日本の投資家にアメリカの貿易赤字の資金援助を行なうよう働きかけることにより、日本経済を歪めることに合意した。日本が輪出で稼いだドルを米財務省証券(米国債)に投資させたのだ。日本人は余剰ドル(日本の貿易黒字)を円に換えて日本国内(および海外の新しい生産設備)に投資するのではなく、そのドルをアメリカへ融資するよう求められたのである。アメリ力の狙いは、これによって「ドルの還流」を刺激することであった。アメリカ側は、もしこの要請を日本が受け入れなけれぱ、円に対するドルの価値を引き下げると脅かした。ドルの価値が下がれば、海外における日本製品の価格が上がり、日本の輸出業者が苦しむことになる。またアメリカや他のドル地域(カナダやラテンアメリカ)に、日本がすでに投資した円換算の投資価値も目減りしてしまう。そのため日銀は、価格の高い(すなわち、金利の低い)財務省証券を購人せざるをえなかった。この取引によって日本は低金利政策を敷くことになり、またアメリカでも日本から大量の資金が流入してきたことが低金利につながった。そこに銀行の安直な融資が加わり、両国内で金融バフルが膨らんだ。こうして日米は1980年代後半、バブル経済へと突人したのである。日本に大量に米国債を買わせておきながら、アメリカ人自身は国債は購入せず、アメリカの株式や不動産市場で儲けていた。金利を意図的に低く仰えることによって、日本と同様アメリカ市場も活性化した。しかしアメリカの場合、日本がその要請に従ったがゆえの活況だった。結局、日本の大蔵省は、自国の経済に低金利の貸し付けをあふれさせただけではなく、アメリカ経済へも巨額の資金を流出させ、アメリカの低金利をも可能にしたのである。
アメリカにとっては、まさにこれがプラザ合意の目的であった。当時は健全であった日本経済は、不健全なアメリカ経済への資金援助のために、自国の経済均衡を犠牲にするよう求められた。インフレを誘発するアメリカ経済が均衡を保てるよう、日本の通貨制度を不安疋にしてアメリカと釣り合わせることを要求されたのである。このプラザ合意では、「釣り合い」と「均衡」を回復するためにという大義名分が掲げられたが、それは不健全な経済を健全にするのではなく、健全な経済を同じように不健全で不均衡でインフレ過剰のものにすることによって維持されたのである。これを実現可能にしたのが日本であり、その結果、日本は深い痛手を負った.当時のアメリカはレーガノミクスによって、巨額の財政支出にもかかわらず富裕者の税金は削減され、貿易赤字と財政赤字が増加するにもかかわらず、金融緩和策がとられ金利は下げられていた。この後に統いた通貨供給量の増加と産業の空洞化はさまざまな問題を引き起こしたが、その治療をするよう求められたのはアメリカ国民ではなく、日本だった。日本はブラザ合意でアメリ力の抱える双子の赤字に資金援助を行なうことに応諾したのである。この治療こそ、バブル経済で知られる状況である。プラザ台意のお膳立て=金本位制に代わる財務省証券制なぜこのとき、日本はドルを支える必要性を感じたのか。この答えは、アメリカがいかにして自国の貿易赤字を他国に支払わせることができたかの理由にもなる。貿易赤字を抱えていれば、通常は消費や投貸の抑制、さらには歳出削減や冨裕者、特に不動産役資家への増税を行なう。そのために景気は減速する。
では、アメリカはいかにして、これを回避したのか。ドルの還流政策がとられ始めたのは、アメリカが金本位制を廃止した1971年であった,べトナム戦争でアメリカは海外に莫大なドルをぱら撒いていたため、世界中の中央銀行が米ドルを一オンス35ドルで金に交換し始めた。しかし、日本のように国際収支が黒字の国は継続してドルを受け取っていた。たとえば、べトナムのアメリカ兵が休養と娯楽のために日本に送られてくると、アメリ力は日本で使うために何十億ドルもの米ドルを円に交換した。この間のアメリカ経済は、消費財ではなく、いわゅる「べンタゴン資本主義」とも言える武器製造に集中した。原価に術定の利益を加算する原価計算方式によって、企業の経営者は製造費用をできるだけ高くし、価格にそれを反映させて儲けたため産業界は豊かになった。これは市場競争にとってよい経験とはならなかった。コスト削減意識が培われなかったためである。政治制度もまた、べトナム戦争とそれに関連する軍事支出に反対する多数の団体を買収することで成り立っていた。このような状況下でアメリヵの消費者は急速に、自動車や電化製品などを海外のサブライヤ-から購入するようになっていった。
日本製品もアメリカ市場で売れるようになったが、日本のメーカ-はそこで得た米ドルを日銀で円に交換し・その円を生産設備の充実や住宅その他の投資に便った。日銀は集まったドルの使い道を決めなければならなかった。フランスでは、ドゴ-ル将軍が余剰ドルを毎月金に換えていた。しかし敗戦の痛手から抜け出せなかったためか、日本は他の主要国に比べて金の保有高を少なくするょうアメリカに圧カをかけられた。つまり、余剰ドルをアメリカ保有の金や、さらには公開市場でも金に換えないように要請されたのである。したがって、日本の輸出業者やその他のドル受領者が稼いだドルのうち、輸入やアメリカへの民間投資に必要な分を除いた余剰ドルを日銀はどうすることもできなかった。唯一残された選択肢は、日銀がドルを外貨準備金として、財務省証券の形で保持することだけだった。このようにしてアメリカの対日貿易赤字は、日銀を経由してアメリカの財務省に還流していたのである。通常は、貿易赤字を抱える国はなんとかしてそれを穴埋めしなければならない。米ドルが金にリンクしていた1971年まではアメリカは金を売却することで赤字を埋めていた。
しかし、アメリカの金保有高が底をつきはじめると、金本位制を廃止して、別の方法を選択したのである。つまり、金利を上げて民間部門を外国資本に引きっけるのではなく、日銀に余剰ドルを財務省証券に投資するよう働きかけたのだ。財務省証券の利率は当時の市場の状態(およびその後のドル安)を考えると低かった。日銀がこの財務省証券で得た金利は、アメリ力の投資家が海外直接投資で稼いだ金利よりずっと少なかっただろう。アメリカに還流した日本の資金は、日銀の余剰ドルばかりではない。日本が金利を意図的に低く仰えることによって、アメリ力への投資は儲かるという幻想を抱かせることになったのである。それは、確実に日本全体の経済を歪めていった。つまり、アメリカの外交官が日本の高官に圧力をかけたのと同じように、日本政府は日本の投資家に「アメリカに投資しなさい」とささやきかけたのだ。その結果は、もうお分かりだろう。バブル当時、多くの日本企業がアメリカの不動産や企業を買収し、またドル建て債券に金を注ぎ込んだが、その多くは膨大な損失となって日本経済を餌む一因となったのである。こうしてアメリカは、金本位制から財務省証券制(米国債制)とでも言うべき体制を作り上げていった、そうして、まるで詐欺のような財務省証券制の成立に、もっとも貢献したのが日本なのである、日本は詐欺の片棒を担ぐというより、自国の経済を犠牲にしてアメリカに協力したのだ。
***********************************
上の解説は、晴耕雨読からの引用だが(ビル・トッテンの引用)、相当に的を射たものであり、補足も必要ないほど正しく事態を解説している。
要約すれば、文末に書かれた「アメリカは金本位制から米国債制に変え」、この犠牲を、すべて日本に押しつけたという下りが本質であり、プラザ合意の成立以前に、日本の貿易黒字の始末を、米国債購入に振り向けたのが中曽根政権=竹下大蔵相であって、このことによって、日本経済は、アメリカの飼犬であるとともに、すべての利益を献上する家畜=奴隷にすぎなくなった。この合意による、日本経済の円高から、日本の構造的不況が取り返しのつかないほど累積するようになり、バブルが崩壊し、暗い崩壊局面に入り、33年を経ても、未だに経済は暗黒の泥沼のなかから一歩も出ていない。したがって、戦後日本経済を崩壊させたのは、間違いなく、プラザ合意を締結した中曽根康弘政権である。安政条約ではあるまいし、これほどの不平等合意が、何をもたらすか分からぬほど中曽根政権も暗愚ではあるまいし、これは明らかに、アメリカを支配する、ユダヤ人コミュニティ=イルミナティの明確な陰謀指図であり、CIAスパイとして知られた中曽根康弘による、日本売国政策であったと断言してもよかろう。中曽根が、なぜ、ここまで露骨なアメリカ盲従の売国政策を行ったのか? 日本の致命的不利が分かりきっていたプラザ合意に応じたのか? これは歴史の秘密であったが、森永卓郎は、日航123便の真相をアメリカに握られ、脅されて要求をのまざるを得なくなったのではないかと示唆している。
https://www.youtube.com/watch?v=4-Zkfkq5_8Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=H7MVF14ir8Q
日本のような、輸出型の貿易立国では、通貨高が致命傷になって自国経済を崩壊させてゆくことは常識中の常識であるが、日米の関係において、プラザ合意を押しつけられて、恒常的円高基調を呑まされるような理由は存在していない。中曽根政権=竹下蔵相は、反論らしい反論もしないまま、貿易黒字だけを理由に、後々のまた後々まで、経済を二度と浮揚できないような不平等取り決めを受け入れてしまった。特に問題なのは、日本が貿易黒字を作ったなら、それで必ず米国債を購入させられるという下りで、その米国債は、驚くような低金利であって、しかも長期保有を義務づけられ、日本にとって良いことは一つもないような異様な代物であった。このため、日本経済は、イノベーションの資金をすべてアメリカに奪われる形となり、プラザ合意以降は、国内各社は、研究資金も、国内投資資金も失ってしまって、イノベーションによる新しい経済を生み出す力を失ってしまったのである。 これがバブル崩壊後の沈水日本の本質であろう。
1997年、この「米国債を売る」と冗談をかました橋本龍太郎は、たちまちCIAの標的となり、中国人愛人による情報漏洩から首相を追放され、2006年、殺害されてしまった。死因となった「腸管虚血性敗血症ショック」というのは、ポロニウムやアメリシウムなど極めて毒性の強い核種を飲食させられたときに出る症状に似ている。これらはCIAによる毒物殺人のパターンに含まれている。
|
|
9.29日、入江相政侍従長が急死(享年80歳)。10.1日付で勇退する予定であった。
9.下旬、「日中国交正常化10周年」を記念して、鈴木善幸が北京訪問。
9月、動労千葉が、定期大会で、「悪者にされ3人に1人が首を切られて黙っていられるか。敢然とストライキに打って出て社会に信を問おう」と満場一致でスト方針を採択。同年11月28~29日の24時間スト(運休243本)に決起する。
10.2日、関越自動車道(練馬-長岡)全通。
10.11日、 政府が1987年4月1日付での国鉄分割・民営化を正式決定する。
10.28日、南魚沼郡大和町の浦佐駅前に、田中元首相の銅像除幕式。
10月、中日友好病院が北京で落成。鈴木前首相がオープンセレモニーに出席。
10月、趙紫陽総理、中曾根康弘首相とニューヨークで会談。
10月、国労の修善寺大会が開催される。大会は労使共同宣言を否決したが、闘う方針を確立できなかった。
11.2日、社会党結党四十周年記念式典。
11.13日、コロンビアのネバドデルルイス火山が噴火、2万5000人が火砕流に巻き込まれて死亡する。
| 【「伊里一智」事件発生】 |
11.19日、第17回大会会場入口で、伊里一智は、東大院生支部の「宮本解任決議案」問題の経過を書いたビラを配った。1986年1月、党中央は、伊里一智を査問し、除名した。
「伊里一智」に対し党中央側のキャンペーンを河邑記者が行った。河邑は、それらのキャンペーン記事によって、東大全学60%における宮本逆路線批判共同意志問題を隠蔽し、伊里一智一人だけの、気狂いじみた「ビラまき男」問題に矮小化させた。実に“赤旗・ペンの力は偉大である”。1977年第14回大会以来の宮本逆路線を批判する、最初の組織行動という、この問題の性格は、志位と河邑の宮本直接指令を受けた大奮闘によって、「負け犬の、ビラまき男による党大会会場入口事件」にすり替えられ、一人の気狂い党員の行動として、葬り去られた。志位と河邑2人は宮本ボディガードを自ら志願して宮本を“今そこにある危機”から救出した。上田も、その一翼を担ったが‐‐‐。宮本・志位・河邑・上田4人組による“弦楽四重奏”が、「都党会議」.「第17回大会」.「赤旗」で鳴り響いた。東大大学院支部粛清の“葬送カルテット”の騒音に怒って、多数の党員が離党した。 |
11.29日、国鉄でゲリラが発生、東京都や大阪府などの国鉄が運行停止する。
11月、国家秘密法案立法化に日本新聞協会が反対表明。
11.15日、自民党立党三十年記念式典。「特別宣言」「政策綱領」を発表。
11.19日、ジュネーブで米ソ首脳会談。
11月、第17回党大会。
85ゴルバチョフ書記長就任
12.12日、グリコ森永事件の犯人グループが駿河屋を脅迫。毒入りチョコレートを置いたと犯行声明を出し、東京と名古屋で8個の青酸ソーダ入りチョコレートが見つかる。
12.12日、平河町のマンション「メゾン平河」の2階6室188㎡に佐藤昭子の「政経調査会」を発足させた。会長に高島修、理事に梶山、羽田、小沢、渡部恒三ら12名が名を列ねた。
| 【第二次中曽根第2次改造内閣】 |
| 12.28日、第二次中曽根第2次改造内閣が成立。官房長官・後藤田正晴を再度起用。安倍外相、竹下蔵相留任、渡辺美智雄通産相、海部俊樹を文相。
|
12月、1983.12月にロッキード事件で田中角栄元首相に1審有罪判決(懲役4年の実刑判決)が下った2年後のこの頃、国会史上初の倫理チェック機関として政倫審が発足した。当時、衆院議運委員長として同審査会設立に動いたのが小沢一郎であった。
| 【社会党の迷走】 |
この頃の社会党の迷走について、社労党の「日本社会主義運動史」は次のように記している。
| 概要「この長期低落傾向に歯止めをかけようと、70年代末には『道』見直しが叫ばれ始めたが、彼らの見出した再建策は社会党をいっそう“右傾化”させることでしかなかった。その最初の到達点は、安保五人男の一人で非武装・中立論のチャンピオンだった石橋委員長の下でのニュー社会党路線への転換、新宣言の採択であった。しかし、その内容は自衛隊の違憲・法的存在論を目玉とする全くインチキなものであった。それは労働者の社会党離れをいっそう促したに過ぎず、新宣言の採択された85年の総選挙では85議席へと転落した」。 |
|
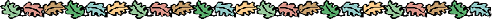



 (私論.私見)
(私論.私見)
