| 1952年通期 |
| 1952年当時の主なできごと.事件年表 |
| 「武装闘争路線」の混迷 |
|

更新日/2022(平成31.5.1日より栄和改元/栄和4).8.28日
この頃の学生運動につき、「戦後学生運動論」の「第2期、党中央「50年分裂」による(日共単一系)全学連分裂期の学生運動」に記す。
| (れんだいこのショートメッセージ) |
2002.10.20日 れんだいこ拝 |
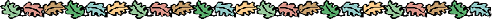
| 【1.1日スターリン・メッセージ】 |
1.1日、スターリンは日本国民に向けて次のメッセージを発表している。
| 「外国の占領に伴い不幸な事態に陥っている日本国民に対し、ソ連国民は深い同情を寄せている。‐‐‐かってソ連国民が為し遂げたように、日本国民が祖国の復興と独立を勝ち取るものと信じています」。 |
|
| 【「第21回中央委員会」が開かれ、武力革命の具体的構想が練られる】 |
1月、「第21回中央委員会」が開かれた。この時、「中核自衛隊」の実践的な組織問題が討議された。ここでは武力革命の三段階が次のように提議されていた。
| 第1段階 |
軍事委員会の指導下に中核自衛隊を組織し、大衆闘争に武装行動の必要を認めさせつつ、これを革命的闘争に引き上げていく。 |
| 第2段階 |
中核自衛隊の指導下に、広く大衆を抵抗自衛組織に組織していく。 |
| 第3段階 |
大衆闘争を国民的規模にまで拡大し、抵抗自衛組織を人民軍にもりあげ、武力革命に突入する。 |
この構想に基づき、地下の単一指導部に中央軍事委員会を設け、以下各級のビューローに属してそれぞれの軍事委員会の組織系統がつくられていった。地方軍事委は、北海道.東北.関東.中部.西日本.九州の6ブロックにもうけられ、中央軍事委員会の最高責任者には志田重男が任じていると見られた。こうして軍事委員会の指導による武装組織と武装闘争の計画が進められていくこととなった。
|
| 【東京都党軍事委員会の責任者であった大窪敏三氏の告白】 |
この時の地下軍事委員会の様子が宮地氏のサイト「占領下の共産党軍事委員長」で明らかにされている。東京都党軍事委員会の責任者であった大窪敏三氏の告白となっている。注目すべきは次の語りだろう。
| 概要「軍事方針っていうのは、差し迫っている暴力革命のため、なんてもんじゃねえよ。軍事方針のほんとうの意味は二つあった。一つは、権力の弾圧に対する抵抗自衛、そして、もう一つは、朝鮮戦争に出動する米軍の後方撹乱(かくらん)だった」。 |
 (私論・私観) (私論・私観) |
| この指摘は貴重である。 |
抵抗自衛の正当性について次のように説明している。
| 概要「当時半非合法化されていた共産党と共産党傘下の労働運動の抵抗自衛だよ。全面的な弾圧がはじまっていたわけだからな。共産党自体が、半分非合法化されちゃった。そうしたら、合法的な抵抗だけでなく、非合法的な実力による抵抗自衛を組織しなくちゃならないのはあたりめえだろ。それだけのことだよ。武装蜂起の準備とか、そういうことじゃねえわけだよ。実力行動っていうのは、デモやストライキのときだって必要なんだよ。ましてや、半非合法化されちゃったら、法に頼るんじゃなくて、実力に頼る度合いが高まるのはあたりまえだ。だけど、それと武装蜂起の準備なんていうのは、まったく次元が違うんだよ。半非合法のもとでは、法に頼らない実力防衛が必要だ。それは明らかなことだし、俺たちがやってたのは、そういうことだったんだよ。法に縛られない運動の防衛の手段をとる。それだけのことだよ」。
|
朝鮮戦争に出動する米軍の後方撹乱の責務について次のように説明している。
| 概要「日本は、朝鮮戦争の重要な出撃基地、兵站(へいたん)基地、補給基地になってた。そこで、こいつを妨害して、できるだけ米軍に打撃をあたえる。それが半非合法化された日本の共産党の任務だと、俺たちゃあ思ってた。俺は、俺たち軍事委員会が組織する破壊活動を含む純粋の軍事行動っていったら、これしかねえと思っていたよ」。 |
宮顕系党中央の「50年武装闘争総括論」との違いを知るべきだろう。 |
| 【白鳥事件発生】 |
| 1.21日、北海道札幌市警の警備課長が、帰宅途中射殺される。
|
| 【右派社会党(書記長・浅沼)党大会開催される】 |
| 1月、右派社会党(書記長・浅沼)の党大会が開かれ、「民主社会主義の理念に立脚する」など反共主義を明確にした「七原則」を確認し、ドイツ社民党やイギリス労働党など社会主義インター系の諸党をお手本とする道を進むことを決めた。また、昭電疑獄で除名された西尾が復党し、実権を握ることになった。 |
| 【コミンテルンフォルム機関誌に、徳球書記長の論文が掲載される】 |
| 2月、コミンテルンフォルム機関誌に、徳球書記長の日本革命に関する論文が掲載されていた。スターリンが公式化した植民地従属国における革命方式が日本に直接適用されていた。従前の「右翼的日和見」的な野坂式「内外の新しい諸条件を考慮して『革命の平和的発展』を模索する』という観点が完全に放擲されて、替わりにアメリカ帝国主義の全一的支配に対する闘争という点が強調されて、日本の革命の条件や性質が旧中国の建国革命方式とほとんど変わらないものにされていた、とある。論文内容そのものが開示されていないのでこれ以上は分からない。
|
| 【武装闘争教本密かに出回る】 |
2.1日付け「内外評論」に、無署名論文「中核自衛隊の組織と戦術」論文が発表された。「この論文は、前に発表された『我々は武装の準備と行動を開始しなければならない』に続くものであり、これを基礎にしたものである」と前置きして、以下のような章立てとなっている。
7章に分けられ、1・中核自衛隊の任務、2・隊の組織と構成について、3・武器と資金について、以下「志気と政治教育」、「軍事行動と大衆行動」、「遊撃戦術について」、「作戦と行動」などについて指導していた。(「日本共産党の過去の武装闘争時代」の資料面を参照)
「(二)隊の組織と構成」は次のように記している。
| 1 |
人を選ぶべきであって、「武器をとって戦う意志と決意と能力を持つ人」、「勇敢でかつ軍事行動に耐える強い体を持つ人」をもって組織すること。 |
| 2 |
綱領、規約によって部隊の編成を明確にし、とくにそのなかにおいて、死を賭して戦うこと、及び秘密を守り、隊を裏切らないこと。 |
| 3 |
十名以内で一隊を組織すること。 |
| 4 |
隊に隊長と政治委員を置くこと。隊長は軍事委員会の指揮を受け、軍事行動について隊を指揮し、政治委員は大衆闘争との結合、大衆闘争の組織に関する方針を定めるものであって、隊長と政治委員は一体となって指揮・指導すること。 |
| 5 |
政治委員は党の指導部に参加し、党の方針を軍事行動に反映させること、隊員は通常の細胞活動から解除される。 |
武力革命は三段階に分けて遂行すべきとされた。第一段階では、軍事委員会の下に中核自衛隊を組織し、大衆闘争に武装行動の必要を認めさせつつ、これを革命闘争に引き上げていく。第二段階では、中核自衛隊の指導下に、広く大衆を抵抗自衛組織に組織していく。第三段階では、大衆闘争を国民的規模にまで拡大し、抵抗自衛組織を人民軍に盛り上げ、武力革命に突入する-という構想であった。
田川和夫「日本共産党史」は次のように評している。
| 「四全協当時においては、まだ都市プロレタリアートの蜂起を中心とする地方的武装闘争が中心に置かれていたが、五全協以後は全く遊撃隊戦術一本槍に転化していった」。 |
「中核自衛隊の組織と戦術」論文は、中国建国革命を指導した毛沢東の「遊撃戦論」を下敷きにしてそれを戯画化したものでしかなかった。概要「我々は今、戦略的には防御戦の段階にあり、敵と正面から対峙し、戦うのではなく、敵の弱点や隙間を奇襲して、これに打撃を与え、攻撃の後には、誰の行動か分からないようにすることである」、「この段階の戦闘は、強大な敵の軍事力の弱点を破壊して、味方の軍事力を蓄えるように行われる。この戦闘は、味方が攻撃し、主導権を持つから闘いは大きな会戦ではなく小さな奇襲の継続である。この小さな戦闘を無数に拡げ、これを繰り返すことによって、敵と味方の軍事的な比重を変えることが、この段階の軍事的な目的である。我々はこの力の比重を根本的に変えることによってはじめて防御戦の段階から敵を徹底的に打ち破る攻撃戦の段階に入ることができるのである。これが日本の革命戦争における我々の戦略である」とある。異様に「専ら奇襲をこととする」方針に転換されていたことが分かる。
「回想・・・戦後主要左翼事件」(警察庁警備局)は次のように記している。
| 「地方軍事委員会は、北海道、東北、関東、中部、西日本、九州の六ブロックに設けられ、中央軍事委員会の最高責任者には志田重男が任命された。しかし、志田に特別に軍事知識や経験があったわけではないので、大阪・箕面出身で陸士帰りの吉田四郎が、言ってみれば参謀役を演じている。武装闘争のキーパーソンの一人であった」。 |
増山太助の著書「戦後期・左翼人士群像」は次のように記している。
| 「1951年10月時点で、全国で55の中核自衛隊ないし独立遊撃隊が存在し、その人員は2500人に達していたという。しかし、このなかには『文化工作隊』や『レッドパージ』された人たちの『行商隊』もふくまれているから、『地下に潜った』『Yメンバー』といわれる人たちの数は北海道・東北で各400人、関東350人、九州300人、近畿200人、東海、中国、四国、各百人、計2000人前後ではないか」。
|
「中核自衛隊の組織と戦術」の第三項目は「武器と資金」について次のように述べている。
| 「中核自衛隊の主要な補給源は敵である。中核自衛隊はアメリカ占領軍をはじめ、敵の武装機関から武器を奪い取るべきである」。 |
| 「武器は敵の使用しているような近代的なものだけではない。大衆の持っている刀や、工作道具、農具も武器となりうるし、また竹槍や簡単に作ることのできる武器も使用できる。特に、敵を襲撃するために必要な輸送専用のパンク針、手榴弾、爆破装置の様な簡単なものは、ただちに製作する事が必要である」。 |
| 「武器についで資金を必要とする。この資金もアメリカ占領軍から奪い取ることが原則である。すでに横田や佐世保の基地等では、労働者がいろんなかたちで、真鍮、砲金などの敵の軍需品を破壊して持ち出し、売り払っている」
。 |
このため、交番を襲って巡査のピストルを奪ったり、米軍基地から真鍮や砲金などを持ち出して売り払う「事件」が各地で頻発し、「レッドパージ」された新聞社の文選工が自分のいた職場に潜り込んで大量の活字を持ち出し、これで「アカハタ」の後継紙を印刷したというような話が手柄話として流布されたりした。
この方針に基づいて起こされた事件は、派出所(交番)や警察官を襲って、拳銃を強奪六件▽警察署等襲撃96件▽米軍の基地・キャンプ、兵士、車両襲撃13件―である(いずれも、宮地健一作成資料から)。
武装行動と抵抗自衛組織の思想は、労働組合.農民組合を始めあらゆる大衆団体の間に持ち込まれ、宣伝されだした。偽装のパンフの形で配布された。五全協の結語は「さくらに貝」の表題で、決定の方は「ラジオの集い」という表題で。「孟子抄」、「栄養分析表」、「料理献立表」、「Vノート」、「軍事行動の前進の為に」、軍事組織の機関誌中核、軍事ノート別に「国民の武装の為に」が発行された。全て非合法。
2月頃、軍事委員会全国会議が開かれ、徐々に表面に動き出した。
|
| 【講和条約発効に向けての動き】 |
| 2.13日、日米安保条約に基づく日米合同委員会が設置され、新しい従属体制への移行の準備がすすんだ。2.28日、日米行政協定が調印された。 |
| 【東大でポポロ座事件発生】 |
| 2.20日、東大でポポロ 座事件発生。劇団発表会に私服警官が潜入していることが判明、問題となった事件であった。破防法反対闘争なども取り組まれている。
|
| 【所感派系の軍事行動】 |
| 2.21日、蒲田署警官襲撃事件。共産党が「反植民地闘争デー」を期して軍事方針に基づき行動した集団暴行事件であり、この日の午後5時過ぎ、大田区糀谷の電業社付近に約70人が集まった。不穏な状況に対し蒲田署K巡査が職質したところ、「この野郎、人民の敵だ、殺してしまえ」と襲いかかり暴行、手錠をかけ拳銃を強奪した。その後250人ぐらいに増え2隊に分かれデモを行った。目つぶし、投石てせ派出所を襲撃、破壊した。 |
|
2.23日、京都税務署を日本共産党員が襲撃。
|
|
2.28日、荒川署を日本共産党員が襲撃。
|
| 3.16日、鶴見、川崎税務署火炎瓶襲撃事件。 |
| 3.20日、京都の派出所を日本共産党員が襲撃。 |
| 【所感派系が全学連中執に選出される】 |
| 3.3日、全学連の東大農学部拡大中執で、所感派による国際派追放大会が為された。高沢、家坂、力石らの「君子豹変」。土本、安東、柴山、二瓶、下村らが「国民の敵」として非難、追放され、新しい中執が選出された。こうして3月3日全学連拡大中央委員会において、1948年全学連結成以来日本学生運動の指導部を形成していた武井指導部は引き摺り下ろされることになった。武井派は、「学生戦線統一の観点から辞任することとなった」と、総括している。
|
 (私論・私観) 武井執行部の辞任について (私論・私観) 武井執行部の辞任について |
| この経緯を「反帝・平和の伝統を担ってきた武井指導部の引き摺り下ろし」とみなして、この時の政変を疑惑する史論が為されているが、れんだいこはそうは見ない。この頃武井指導部は宮顕論理に汚染され、既に闘う全学連運動を指揮し得なくなっていたのであり、歴史弁証法からすれば当然の経過であったと拝察したい。
|
3月、破防法国会提出。
3.28日、非合法機関紙「平和と独立」の印刷所、配布先など全国1850ヶ所が捜索された。
| 【武井グループの四散】 |
| 4月、全学連の安東、柴山、松下らが常東農民組合へ。武井は文芸評論を志す。「文学のブの字も口にしたことのなかった武井昭夫は『文学の批評でもやってみたい』といって私をおどろかせた」とある。 |
4.6日、武蔵野署火炎瓶事件。
4.9日、もく星号墜落。
4.17日、池上署矢口交番襲撃事件。
4月、日本とインドが国交樹立。2ヵ月後に平和条約を締結。この時インドは、全ての対日戦争賠償請求権を放棄している。
| 【講和条約(サンフランシスコ平和条約、日米安保条約)発効】 |
| 4.28日、講和条約(サンフランシスコ平和条約、日米安保条約)が発効した。「GHQ」の廃止が発表され、実質的にアメリカ帝国主義の全面軍事占領であったものが終結し、軍事基地が要衝に残置された。 |
「Toshiyuki Niigata 日本は独立国ではない」。
1952.4.28日に発足した日米合同委員会(米軍が日本を統治する機関)は、委員会とは名ばかりの日本統治機関で、月2回木曜日に開かれ、米軍高官が霞が関官僚に指令を出す、そこで決まった事柄は全て機密事項、米国務省も日本の首相も口を挟めない、そこで決まった事柄(密約)により、官僚が政策を作り、政令を作る、それらは閣議に提出されるが、閣議で議論されることは無く、花押が署名されて、盲判が捺される、所謂セレモニーに過ぎない、日米安全保障条約体制がこの国に君臨して、行政・立法・司法の三権分立をも阻害して機能不全にしている、米国務省もそのような属国のような関係は止めるべきだと勧告しているが、国防総省(ペンタゴン)は日本人(外務官僚)が良いと言っているのだから、良いじゃないかと取り合わない、
統治権行為論が米軍問題・原発問題の解決を阻んでいる、
田中耕太郎・最高裁判所判決(判決に外国政府の意向が反映)(要旨・八)、最高裁判所(大法廷、裁判長・田中耕太郎長官)は、同年12月16日、「安保条約の如き、主権国としてのわが国の存立の基盤に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否の法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査に原則としてなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外にあると解するを相当とする」。
http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/0526.html
|
| 【内閣調査室設立】 |
| 4月、内閣調査室設立。政界復帰前の緒方竹虎が、吉田茂、村井順とともに、アメリカのCIA、イギリスのMI5、MI6などを参考にして、内閣総理大臣官房に「調査室」という小さな情報機関を設立した。これが現在の内閣情報調査室の源流である。
|
| 【アカハタが復刊】 |
| 5.1日、メーデーをきしてアカハタが復刊された。党が公然化の機会があったが、引き続き非公然化にとどまった。 |
| 【日華平和条約締結】 |
| 日華平和条約締結。台湾との関係を正常化させ、戦争状態を終結させた。但し、内地中華人民共和国とは正常化為し得なかった。つまり、わが国の中国政策は、台湾の国民政府を正当な中国側代表として平和条約を結んだ。この結果、中華人民共和国とは、政経分離の民間ベースでの交流へと向かった。野党は、中華人民共和国こそ中国を代表する唯一の政府として、「二つの中国」政策に反対していくことになった。
|
| 【「第23回血のメーデー事件」発生】 |
5.1日、第23回統一メーデーが全国470カ所で約138万名を集めて行われた。東京中央メーデーは「流血メーデー」となり、「血のメーデー事件」として全世界に報道され衝撃が走った。
東京中央メーデーは皇居前広場の使用許可が得られなかったために神宮外苑を会場にして開催された。演壇には「講和、安保二条約粉砕」、「民族の独立を闘いとれ」、「朝鮮即時休戦」、「破防法反対」などのスローガンが掲げられていた。復刊されたアカハタ第1号が配布された。由井らが岩田英一の指示によりメーデー会場にて赤旗を販売、とぶように売れた。デモ隊の一部から誰言うともなく「人民広場に行こう」の声があがり、人数不祥の多数のデモ隊員が突然演壇に駈け上がり、演壇のマイクを奪って「人民広場に行こう」と呼び掛けた。かくて数万のデモ隊が人民広場に向かっていった。この時、デモ隊の一部が暴徒化していたとも云われているが前後の絡みが不明である。
これに対し、警察当局は、デモ隊を広場へ引き入れた後数千人の武装警官隊によって襲撃させた。戦後初めての公権力によるデモ隊襲撃の阿修羅図となり、デモ隊も応戦して「まるで市街戦のような真昼の流血」となった。労働者.学生2000名の応戦も激しく4時間にわたる大乱闘の白兵戦となったと云われている。「5、広場における滝沢林三の体験の体験2」が次のように証言している。
| 「馬場先門から広場に入り二重橋前に到着して一息いれていたデモ隊の先頭集団は、突然武装警官隊の襲撃に遇いました。デモ隊側は、石を投げ付けたり、プラカードを壊して作った角棒で抵抗した一部のデモ隊員を例外として、他は一目散に退却しましたが、先がつかえて転倒する者が続出し、棍棒のあらしと催涙ガスにやられて、警官隊の思うがままに蹂躙されました。早大の隊列は雪崩を打って退却してくる先頭部隊にあっというまに巻き込まれてしまい、ちりぢりばらばらになってしまいました」。 |
| 「この後、先に馬場先門から広場に入った中部コース組と祝田橋の阻止線を突破して広場に入った南部コース組が合流してデモ隊は大部隊にふくれ上がりました。その間の状況は、資料(2)『広場の証言』三十~三十三頁の写真に写っています。この大部隊は再び警官隊と対峠しますが、ここでもデモ隊の前に立つ指揮者は誰一人現れませんでした。しばらく対峠している間に投石する者やら、角材を槍のように掲げて警官隊に向かって気勢をあげる者やらが部分的に動いているだけで、他の大多数のデモ隊員は空しく時を過ごすだけだったのです。すでに早大の隊列は影も形もなくなってしまい、私は全体の指揮者はいないのか、指揮系統はどうなっているのかと内心いらだちながら、いたずらに立ちんぼをしているだけでした。そうしているうちに数千人のデモ隊員は無残にも警官隊の第二次総攻撃に曝されてしまったのです」。 |
翌5.2日、田中警視総監は、「警察官の重傷68名、軽傷672名」と発表している。5.6日、木村法務総裁が「外国人の負傷は13名、暴徒側の負傷者は200人と推定、デモ側に死者1名、奪われたピストル3丁、焼失した米軍車両14台、損傷した車両101台」であることを確認している。最高検察庁は、騒擾罪を適用して、1100名の大検挙を行った。
法政大学学生含む2名が射殺され5人が死亡し、300名以上が重傷を負い、千人をこえる負傷者がでた。当局は、事件関係者としてその後1230名(学生97名)を逮捕した。最高検察庁は、騒擾罪を適用して、1100名の大検挙を行った。
早大生は夕方から夜にかけて200名ばかりで演説会を行い、学内をデモ行進、早大から千人近く参加。キャンバスは騒然とした雰囲気であった。包帯を顔に巻いた学生たちが集会を開いていた、とある。
予想外の大事件の勃発に対して、総評指導部は、「共産分子が行った集団的暴力行為」、「メーデーを汚した反労働者的行為である」と激しく非難した。党が武装闘争方針を明確にしていたことから党の軍事組織がこれを計画し実行したかのように受け取られたということである。
党は、徳球書記長が地下から「最も英雄的行為、日本における革命運動の水準がいかに高いかを示した」と機関紙で評価し、「人民広場を血で染めた偉大なる愛国闘争について」(組織者6.1日第11号社)では、大衆の革命化が党の組織的準備を上回っており、党の実践のほうがむしろ立ち遅れているとみなした。党中央は、この群衆のエネルギーのなかに、武装闘争を推進させる条件が存在していると判断し、火炎ビン闘争を推進した。それは党にとっての史上初の武装闘争の道であったが、当然当局の取締り強化とのせめぎ合いであり、いかんせん党内でさえ足並みが揃わぬままの突っ走りとなったこともあり、結局は徳球党中央を自壊させる道となった。
|
 (私論・私観) 「血のメーデー事件」の背景についてて (私論・私観) 「血のメーデー事件」の背景についてて |
| 今日なお、「血のメーデー事件」の背景が見えてこない。はっきりしていることは、1・数千人の武装警官隊があらかじめ配置されていた、2・党中央の軍事方針にもとづく計画的騒乱ではなかった、の二点だけである。この間隙を埋めるのは、3・急進派の用意周到な裏工作に拠る挑発、4・当局スパイ派に拠る挑発、のどれかであろう。党の軍事方針にもとづく計画的騒乱とする説もあるが、この場合でも何か裏がありそうだぐらいには受け取らねばなるまい。 |
| 【「北京機関」が「自由日本放送」を開始】 |
5.1日、北京機関が「自由日本放送」を開始した。これは毛沢東の指示によって周恩来が準備した、日本共産党の地下放送であった。スタッフ約30名、伊藤律が指導した。放送の主目的は、「51年綱領」の普及と、その実践的な指導にあった。「北京機関と自由日本放送(藤井冠次)」は次のように証言している。
| 「放送体制は、総責任者徳田球一の下に、編集長伊藤律が全般を指導し、私は律の下で、デスク兼プロデューサーとして、スタッフを組織することになっていた」。 |
5.2日付け朝日新聞は、「なぞの放送始まる・共産系“自由日本”」の見出しで、「東京で傍受したところによれば、5.1日夜から『自由に本放送』と称する共産系の日本語放送が開始された。同放送は、毎晩8時半から同9時まで短波で行われ、放送局の所在は不明。一日夜は、日本共産党のメーデー・スローガン、世界労連のメーデーに対するメッセージ、「日本国民は必ず勝利する=解説」などを放送した」、「なお同放送の所在地は不明であるが、周波数一一・九メガで毎日定期的に行われるところからみても日本国内ではなく、北京、平壌またはハバロフスクとみられている」(読売新聞)と報道していた。
「北京機関と自由日本放送(藤井冠次)」に拠れば、当時の様子を次のように伝えている。
| 「徳田ははじめ私に、コミンフォルム機関紙掲載の徳田論文『新綱領の基礎について』を渡し、『これを当面、放送の編集方針とするように』と命じた。加えて『今後とも新綱領を基本方針として、党の統一と団結に努力してもらいたい』という。一般的には綱領の普及、組織的には分裂した党の統一回復と団結強化が当面の最重要課題であると強調した」。 |
|
| 【「北京機関」をめぐって】 |
| この当時共産党の実質的指導部は北京機関であった。指導部には、徳球、野坂、伊藤、高倉テル、聴涛克巳、土橋一吉、西沢、岡田文吾らであった。その他工作員がいた。徳球は、伊藤律に対して、「野坂君は中共の中にファンがたくさんいて、いい気になっているが、そんなことお構いなしに、キミ、党の為にこの機関をしっかり握って仕事をしてくれ」と督励していた。
|
| 【アカハタ復刊】 |
| 5.1日、4.28日のサンフランシスコ対日講和条約の発効を期して、発行禁止命令の法的根拠が失われたことにより、第三種郵便の申請を行ない、5.1日のメーデーの日にアカハタが復刊した。週間で復刊され、
7.5日、5日刊となる。9.9日、3日刊となる。発行主体は、「日本共産党中央指導部」と記されており、「日本共産党中央機関紙」と明記されていた。発行名義が「中央指導部」から「中央委員会」に変わるのは、六全協直後の1955.8.3日付からである。 |
| 【党中央青年学生対策部が「学生運動の方針(案)」を発表】 |
| 5月、「学生運動の方針(案)」が共産党中央青年学生対策部によって発表され、直後の全学連第5回大会の指導方針となった。
|
| 【この頃の伊藤律をめぐる党内の動き】 |
当時国際派の連中は、徳球のアキレス腱として伊藤律を標的にして、非難.攻撃を集中していた。5月のこの頃スターリンとの会談の席でこのことが持ち上がり、この時徳球は次のように発言している。
| 「律は戦時中誤り(転向のこと-注)を犯したが、ゾルげ事件については政治局で調査済みである。律スパイ説は敵の反共デマである。彼は戦後よく働き、努力している有能な幹部、アメリカ帝国主義のスパイなどではない、と説明して先方も納得した。が、今後も画策する奴があるかも知れないから用心せよ。徳田は北京に帰ってきてから私にこう語った」(1982.10.13日長谷川浩宛書簡)。 |
|
| 【伊藤律証言による、この頃の北京の党機関での徳球対野坂・西沢との対立】 |
| この時の様子を伊藤律は次のように伝えている。伊藤は、51年秋口密航し北京の党機関に入ったが、この時既に、表面上穏やかなうちにも徳球対野坂・西沢間に底流での対立が横たわっていることをキャッチした。徳球書記長が野坂に対し、表面上はつとめて平静な態度をとっていたが、強い批判と不信を抱いている様子が知れた。徳球書記長は娘婿の西沢に対しても嫌悪しており、既に精神的に絶縁していた。「西沢と野坂は同じ思想だ。彼を日本へ帰してしまう」とまで云い切っていたが逡巡しているうちに徳球が倒れることになった。
|
| 【徳球対宮顕の対立の根深さ】 |
| 徳球田対西沢の対立に興味深い史実が「伊藤律回想録」で明かされている。それによると、徳球対西沢の対立は、51年春のモスクワ訪問の時から先鋭化したようで、微妙に宮顕問題が絡んでいた。西沢が宮顕との妥協を進言したのに対し、徳球が断固これを受け付けず、以来徳球は西沢を娘婿としても義絶すると言明するに至ったと云う。徳球対宮顕の対立の根深さを物語っていよう。 |
5.8日、早大構内巡査暴行事件。
5月13日、広島地裁で傍聴席の朝鮮人150名が被告を奪取し逃亡させる。
| 【共産党の軍事行動の一環としての栃木県那須郡金田村村役場事件】 |
| 5.17日、栃木県那須郡金田村村役場事件。日共党員らにより三月以来、人糞の投げ込み、集団脅迫、傷害が続いていたが村役場での会議中20名あまりの日共党員が乱入、「山林解放を妨害しているのはキサマか!」、「この野郎ふてえ野郎だ、ぶん殴れ!」、「ひきずりだせ」など罵声、鎌や鉈をもって迫った。駐在所の警察官にはさらに執拗に、妻や子にまでも行われた。妻の「私が家を離れたら(実家に帰っては)共産党に負けたことになるから、死んでも家からは出ていきません」との一言がこの駐在警察官を支えたそうである云々。 |
| 【赤旗が第三種郵便物の認可を得る】 |
| 5.30日、赤旗がこの日、第三種郵便物の認可を得た。朝鮮戦争勃発の翌日1950.6.28日に30日間の、やがて無期限の発行停止命令がGHQよりなされ、この間に第三種認可資格を喪失して以来の合法紙獲得となった。対日講和条約が発効した二日後の1952.5.1日のメーデーを期して、発行停止命令の根拠が失われたとしてアカハタを復刊した日本共産党は、ただちに第三種認可再取得の申請を行い承認された。この間の二年近くの発行停止中に、日本共産党臨時中央指導部などによってアカハタの後継紙として「平和と独立」などの定期刊行物が半非合法的に刊行されていた。
|
| 【自由党内部に「民主化同盟」発生】 |
| 5月頃、自由党内部に「民主化同盟」発生。吉田政権を揺さぶることになる。鳩山派、石橋派、中間派が結集し、5月中旬には60数名の勢力となった。石田博英議会運営委員長を中核として、塚田.倉石.小金、吉武労相.水田政調会長。舞台裏には三木武吉、河野一郎の策士、三浦義一、児玉誉士夫らが見え隠れしていた。「反乱軍」とネーミングされた。長期政権に対する「飽き」気分が背景にあった。吉田派側近は、逆に「四者同盟」を結成して対抗した。広川弘禅農相、池田蔵相、佐藤逓政相、保利茂官房長官の4名であった。 |
| 【各地で武装闘争発生、武装闘争路線の混迷】 |
メーデー事件以降党は冒険戦術に突進していくこととなった。5月から7月上旬にかけて、火炎瓶闘争を含めた武力行動がいたるところで展開された。
5.30日、全国各地で「5.30記念集会」。新宿駅事件発生。500人のデモ隊が警官に火炎瓶や石灰袋を投げかけ、乱闘を演じた。新宿で、早大,東大,お茶大らの軍事組織がはじめて火炎瓶闘争。「破防法粉砕総蹶起大会」が開かれ、三方向から,各10人ぐらい,一人2本ずつの火炎瓶。〃私のあずかり知らない火炎瓶闘争が新宿駅を皮切りに出現した〃。
2名の死者を出した板橋岩之坂派出所襲撃事件も発生している。
5.30日、「岩之坂交番事件」が発生している。この事件は、南坊義道氏によって雑誌「現代の眼」(昭和40年8月号)に「日共軍事方針の謎」として発表された。以下概略する。
この日は、昭和24年5.30日に東京都公安条例反対闘争で東交労組の橋本金二氏が警官隊に虐殺された日を記念し、毎年「自由と人権を守る日」として記念集会が各地で挙行る日であった。東京都城北地区でも、合法的集会と非合法的集会の二つの集会が開かれた。非合法的集会の方は、都軍事委員会の指導の下で計画され、中核行動隊員・一般党員・民青団員で構成されていた。当日午後7時過ぎに「5.30記念破防法粉砕城北都民総決起集会」として、板橋区板橋の日本化工機工場内で約350名の参加者で開催された。集会は約30分で終わり、参加者を三班に分けて強行デモに移った。デモ隊は夕闇の中を多数の私服に囲まれながら進んだ。この時、岩之坂交番には多数の武装警官が隊列していた。デモ隊が罵声を浴びせながら交番を通り過ぎようとした時、警官隊は隊伍を整え水平撃ちで一斉に発砲した。デモ隊は大混乱となったが、既に3名が倒れ(2名が死亡)、他にも十数名が負傷した。四散したデモ隊は怒り狂い、警官隊と激しい衝突を試みた。結果、増援の警官隊の到着により鎮圧され、学生・自由労働者・看護婦など35名が逮捕された。女性を含む15名が起訴され、12月から69回にわたって東京地方裁判所で審理が行われることになった。
「被告達は生活に追われ苦しい中で孤立無援の裁判闘争を進めなければならなかった。なぜならば、その後、党は極左冒険主義を否定したために、その結果、被告達は逆に極左冒険主義の典型として党から非難され、党の援助を期待することが出来なかった」(しまね・きよし「もう一つの日本共産党」P111)からである。
| 6.2日 |
菅生事件。これは大分県菅生村の駐在所爆破事件であった。6.4日、襲撃首謀者逮捕される。「山村工作隊の中に警察官が潜入し、その挑発によって事件が発生するというようなことまであった」(しまね・きよし「もう一つの日本共産党」P107)とある。 |
| 6.7日 |
反破防法ゼネストに呼応して起こった火炎瓶闘争。17日.20日も同じ。 |
| 6.9日 |
長野地裁松本支部公廷で朝鮮人被告らが暴れ、検事に椅子を投げる。 |
| 6.10日 |
京都で朝鮮人50人が警官隊と衝突、パトロール車に火炎瓶投入、警官ら火傷。 |
| 6.25日 |
朝鮮動乱2周年記念集会の前夜祭のこの日、日本共産党の指令下、学生、労働者、朝鮮人約1000人が結集し、”人民電車”を動かし吹田で警官隊と大乱闘となった。大阪北部吹田操車場を舞台にして展開された反戦闘争で、大規模な騒擾事件となった。これを「吹田衝突事件」と云う(脇田憲一「朝鮮戦争と吹田・枚方事件」に詳しい)。 |
|
この日、大阪枚方の軍事工場襲撃事件、阪神国道で乗用車の米軍将官火負傷。姫路事件、東京新宿駅での硫酸ビン事件。新宿歌舞伎町国際平和記念大会後、デモ隊2500名が新宿前で警官隊4000と乱闘衝突。東口広場は”火炎瓶広場”と化した。<新宿事件>竹槍、石、火炎瓶が飛び交うデモ対策として大阪警視庁は東京での木製盾から一歩進んだジュラルミン盾を作成。
|
| 6.28日 |
東芝府中工場火炎瓶事件。 |
| 7.4日 |
破壊活動防止法案(破防法)が衆院本会議で可決成立。武装路線を打ち出した共産党への対処策であった。 |
| 7.7日 |
名古屋大須球場で訪ソ・中視察報告大会があり、その後デモに移るや、球場付近でデモ隊と警官隊とが衝突した。石や火炎ビンが飛び交い交番が襲われ、警察は拳銃発射で応戦し、愛知県立半田高校3年生が警官の発砲を受け死亡、県立明和高校の生徒が多数逮捕されている。「検証、大須事件の全貌」によれば、「水平発射した銃弾で朝鮮人少年の半田高校生申聖浩の後頭部を打ち抜き、即死させた。拳銃連射と警官隊いっせい襲撃に驚いて後ろ向きに逃げてきた申少年は18歳だった」。「愛知県立明和高等学校史」によると、「多くの聴衆がスクラムを組んで会場からなだれ出、待ち構えていた警官隊と衝突し、デモ隊の投擲する火炎ビンと警官のピストルの威嚇応酬の中で1人の高校生が射殺され、双方84名と5台の炎上車を出す惨禍を招いた。事件によって逮捕された者は269名に上ったが、中に女子生徒を含めて十数名の明和生が含まれていた」。警察は121人を検挙し騒乱罪を適用した。これを大須事件と云う。党と同調団体の関係するあらゆる大衆集会が、火炎瓶闘争の利用対象とされ、中核自衛隊の武力闘争の目標にされた。
|
| 7.12日 |
警視庁が共産党の不穏行動に備え夜から一斉に非常警戒態勢に入る。 |
| 7.16日 |
都下恩方村山村事件。前村長宅に数名の”山村工作隊”の男が表門のくぐり戸をぶちこわして侵入、風呂場のガラス戸15枚、玄関脇十畳間の雨戸五枚を破壊しこぶし大の石を投石。付近の電柱塀には「山はおれたちのものだ。○○から山林を取り上げてみんなのものにしよう」と書いたビラ二十枚ぐらいが貼られていた。(○○は前村長の本名)
|
| 7.30日 |
山梨県曙村山村地主襲撃事件。就寝中の小中学生3人を含む家族を竹槍で突き刺す。3人は血の海の中に息も絶え絶えになって横たわっているところを駆けつけた警官に救われた云々。 |
しかし、これらの全国的な火炎瓶闘争も、一部の青年.学生.朝鮮人らの行動を中心に若干の労働者を巻き込んだだけで、大衆的な軍事行動にまで発展せず、ましてや全国にわたる人民武力革命の気運の昂揚にはならなかった。逆に、次第に散発的となっていった。
この方針は、大衆からの遊離を決定的にさせ、党の革命事業に損失を与えた。極左主義の具体的現れと総括されている。
この武装闘争の経過は次のように整理することができる。
| 昭和26・12・2 |
東京・柴又日共軍事スパイ事件 |
| 昭和26・12・27 |
練馬署警官惨殺事件 |
| 昭和27・1・21 |
札幌白鳥警部射殺事件 |
| 昭和27・2・21 |
蒲田署警官襲撃事件 |
| 昭和27・2・28 |
荒川署警官襲撃事件 |
| 昭和27・3・16 |
鶴見川崎両税務署火炎瓶事件 |
| 昭和27・3・29 |
小河内村山村工作隊事件 |
| 昭和27・4・6 |
武蔵野署火炎瓶事件 |
| 昭和27・4・20 |
池上署矢口交番襲撃事件.東大内巡査暴行事件 |
| 昭和27・5・1 |
血のメーデー事件 |
| 昭和27・5・8 |
早大構内巡査吊し上げ事件 |
| 昭和27・5・30 |
5・30新宿流血事件.板橋岩之坂交番襲撃事件 |
| 昭和27・6・24 |
大阪吹田警官襲撃事件 |
| 昭和27・6・25 |
新宿交番火炎瓶事件 |
| 昭和27・6・28 |
東芝府中工場火炎瓶事件 |
| 昭和27・7.7 |
名古屋大須事件 |
| 昭和27・7・16 |
名古屋大須警官襲撃事件 |
| 昭和27・7・30 |
山梨曙村山林地主襲撃事件 |
| 昭和27・8・7 |
埼玉県横川代議士宅襲撃事件 |
|
 (私論・私観) 武装闘争の戯画性について (私論・私観) 武装闘争の戯画性について |
こうして武装闘争が実際に試みられたがことごとく鎮圧された。元々アリバイ的闘争、デッチアゲもあり、総じて戯画的なそれでしかなかった。それは方針の誤りなのか、日本的社会における武装闘争そのものの限界なのか、指導の問題なのか未だ考察されていない。戯画的な結果になったにせよ、それなりに評価されるべきものではなかろうか。後付の罵倒的批判は有害ではなかろうか。
伊藤晃氏の「抵抗権と武装権の今日的意味」がこの問題を検証している。これをれんだいこ風に要点整理する。6全協後、党中央の指導権を握った宮顕-野坂系党中央は、旧指導部徳球系の路線的誤りとして単純に全否定し、この時代の武装闘争の史実がまともに検証しようとせず、むしろ史実的に隠蔽抹殺を企図している。これに対し次のように批判している。
| 「けれどもこの時期、日本共産党に所属していた在日朝鮮人活動家を含む多くの人が、ここに共産党の革命運動があると信じて武力闘争に加わったことは歴史的事実である。総括されるべきは彼らにとっての歴史であって、あれこれの党内私的派閥の歴史ではあるまい。ことに武力闘争は、おりから戦われていた朝鮮戦争に対し実力をもってする反対運動という意味があった。大衆的な運動で戦争に反対し、介入しようとしたのは、近代日本において始めてのことである。なかでも在日朝鮮人活動家の場合、祖国での戦争を食い止めようという目的は明確であった。彼らが武力闘争で主力ともいうべき重みをもったのには理由があった。日本人と朝鮮人との運動の場での共闘、これもこのような規模ではかつてなく、またその後も経験されていない」。 |
「武装闘争方針の実態と実践レベル」の検証を通じて、もっと積極的な意味づけと教訓を得ることこそ努めなのではあるまいか。 |
| 【「吹田衝突事件顛末記」】(脇田憲一「朝鮮戦争と吹田・枚方事件」参照) |
6.25日午前5時30分、電車部隊と山越部隊が須佐之男命神社で合流し千数百名の大集団となった。殆ど全員が竹槍、棍棒、火炎瓶等を持って武装しており、且つ、北朝鮮旗、赤旗を押し立て、太鼓を叩き、ラッパを吹き鳴らし、歌を高唱し、或いは喚声を挙げたり等して大いに気勢を挙げて意気まことに旺んなものがあった。
5時40分、デモ隊が、朝鮮米軍むけ輸送拠点である国鉄吹田操車場に向けて行進し始め、目前に控えた山田村字市場についた。そこに機動車三台に満載された警官隊約130名が鉄兜とピストルで武装して待ち受けていた。警察代表が進み出てデモの解散を要請したが、一蹴された。デモ隊は実力突破の構えを見せており、気圧された警官隊は後退し始めた。
デモ隊の太鼓が打鳴らされ、「駆足」(かけあし)号令が出された。デモ隊は一斉に喚声を挙げ、産業道路上に居並ぶ警官隊の真正面に突き進んでいった。太鼓がさらにはげしく打鳴らされるに応じて突撃に変わった。「ワーッ」の喚声と共にデモ隊が突こんだ。石が投げつけられ、棍棒が払われ、火炎ビンが飛んだ。警官隊が下がり、こうしてデモ隊は駆足で一挙に警備線を突破し、吹田操車場に向かって突進した。警官隊はそのあとを追うのが精一杯の様子であった。操車場に入り込んだデモ隊は、「軍臨はどこだ」、「軍臨を止めろ」、「吹操の労働者よ、アメリカの武器を運ぶな」、「アメ公の手先になるな」、「夏季手当をかちとれ!」、「職制反対、売国奴、ダラ幹をやっつけろ、徴兵反対!」等々スローガンを叫びながら約30分デモを続けた。
6時頃、吹田操車場で新たな部隊の合流が為された。竹槍のデモ隊が登場し、構内をジグザグデモで進む。国鉄労働者が呼応し、吹田操車場に非常サイレンがけたたましく鳴りわたった。アジア侵略のための軍事輸送動脈吹田操車場の軍事作業はついに停止した。
警官を見つけると、「犬は帰れ」、「ポリ公帰れ」等の罵声やら投石をしつつ、「戦争反対!」、「軍事輸送やめろ!」、「労働強化反対!」、「軍用列車はどこだ!」とシュピレヒコールしながらデモ隊が駅中央を突破した。走りゆく機関車の上から「がんばれ」と手をふり激励する国鉄労働者の姿が見える。非常サイレンはひきつづき鳴っている。警官隊はもはや為すすべがなかった。
午前6時43分頃、デモ隊は構内を出て千里丘駅方面に向かって行進し始めた。6時50分頃、須佐之男命神社の東側、千里丘小学校前付近に差しかかった時、産業道路を京都方面に向かって一台の乗用車が疾走してきた。その乗用車には駐留軍西南地区司令官米軍陸軍准将カーター・ダブリユー・クラークが搭乗していた。これを目撃したデモ隊員が喚声を挙げて路上に飛び出し、いっせいに石、木片、竹棒、硫酸瓶を投げつけた。乗用車は全力疾走してその場を通過したが、投げつけられた棒は車の車の風防ガラスを突きやぶり、硫酸液は車内に飛散し、同准将は顔面に治療19日間の傷害を負った。同准将がなぜその時刻、その場所を乗用車で疾走してきたのか、いまだに謎である。
午前7時10分頃、デモ隊が吹田市内に入り、吹田市消防署岸部出張所に差しかかった時、デモ隊後方を追尾していた茨木市警ウィーポン車が急にデモ隊に割り込んで前方に出ようとした。車内には同署警察官28名が搭乗していた。これを見たデモ隊は喚声を挙げて車の走行を妨害し、いっせいに投石を始め、火炎瓶、ラムネ弾が車内に投げ込まれた。乗車していた10数名の警官が火達磨となって車外に転落し、危難を避けようと路上に飛び降りた。ウィーポン車は車外に落ちた警官を見捨てて急発進し前方吹田方面に走り去った。
車外に転落した警察官および路上に飛び降りた警察官は、デモ隊に取り囲まれ投石、殴打されるなどの暴行を受けた。さらに、逃走した警察官は追い駆けられ、逃げ遅れた警察官は竹槍で突かれ、棍棒で叩きのばされ、気を失い、拳銃二挺が奪われた。また、近くの民家に逃げ込んだ警察官は、追い駆けてきたデモ隊員によって火炎瓶を投げつけられた。これにより、茨木市警27名の警察官はそれぞれ治療一週間ないし四週間の火傷、打撲傷を負った。その内訳は治療3週間3名、治療2週間6名、治療1週間18名、うち4名が入院治療を要した。
怒りのおさまらないデモ隊員は、片端から沿道の吹田市警の岸部巡査派出所、片山巡査派出所、片山西巡査派出所の三カ所の派出所を襲撃し、窓ガラスや電話機等を打ち壊した。三帰省吾、夫徳秀ら指導者はデモ隊の統制を強化し始め、火炎瓶の使用を禁止した為、火炎瓶は投げ込まれなかった。デモ隊は同駅手前で流れ解散となった。
午前8時過ぎ、吹田駅構内で惨劇が発生した。大阪方面に帰るデモ隊員は同駅西改札口から大阪方面行きの下りホームに入った米原発大阪行き8時7分、吹田発第911列車(一三両連結)内に喚声を挙げて乗り込んだ。その後を突然約30名の警官隊が拳銃を構えて突入してきた。本件警備作戦の失敗を挽回する吹田市警察長の面子と独断で臨時に編成された報復の攻撃隊であった。デモ隊員は乱入した警官に対して竹槍、棍棒で応戦し、ホームの警察官に向けて火炎瓶、硫酸瓶、ラムネ弾等を投げつけた。警官隊はホーム上に伏せの姿勢をとってデモ隊員を狙い撃ちした。デモ隊員、警官が大勢負傷した。巻き添えを喰った乗客にも怪我人が出た。デモ隊員の負傷者が多数(23名)逮捕されている。
8時16分、デモ隊の大半が乗り込んだ第911列車が大阪駅に向かった。ホームの反対側の線路に飛び降りて線路の中を隊列を組んで行進し、東淀川駅から淀川鉄橋方面に逃げた隊員たちもいた。午前8時25分、911列車が大阪駅に到着した。デモ隊は竹槍、棍棒、火炎瓶、ラムネ弾等多数の「武器」を車内に残して全員下車した。
大阪警視庁は吹田市警より吹田駅から乗車したデモ隊の検挙要請を受けて曾根崎署長を指揮官とし、曾根崎署員を主体とする120名、同署に待機していた機動隊102名、合計322名の警備隊を大阪駅に出動させ、デモ隊の検挙に当たった。デモ隊は大阪駅構内を縦横に逃げ回り、城東線や西九条線に逃れて乗客の中に潜り込み、吹田駅同様拳銃と火炎瓶の応酬する衝突が展開された。その結果三帰省吾以下4名が大阪駅で、夫徳秀以下14名が城東線桃谷駅で逮捕された。残りの隊員はそれぞれ乗客に紛れて警官の包囲網を脱出した。
デモ隊のこの警備線突破が吹田事件騒擾罪、威力業務妨害罪容疑に問われることになる。この警備線突破によってデモ隊は「暴徒化」したとされ、騒擾罪、威力業務妨害罪が適用された。
|
| 笹川良一邸襲撃?。 |
| 【全学連第5回大会】 |
この頃の学生運動につき、「戦後学生運動第2期」に記す。
6.25~27日、全学連第5回大会が開かれた。2年ぶりの大会となった。54大学が正式に代議員を送り、20大学が傍聴者をおくった。武井ら旧中執20数名の除名追放が決議された(この除名決議は55.11月になって、誤った措置として取り消されることになる)。
新たに玉井仁(京大)委員長、斉藤文治(書記長)らを選出した。つまり、国際派に占拠されていた全学連中執を党中央が奪い返したことになる。こうして党内の大激震下で徳球系執行部を支持する所感派学生党員は、52年の全学連第5回大会で武井委員長ら旧執行部を追放し主導権を握った。この時反戦学同の解散を決議している。
玉井仁新執行部は、党の武闘路線の呼びかけと「農村部でのゲリラ戦こそ最も重要な闘い」とした新綱領にもとづき、農村に出向く等武装闘争に突き進んでいくことになっ
た。こうして戦闘的な学生達は大学を離れ、農村に移住していった。
この間国際派学生党員グループは、反戦学同的運動を継承しつつ主に平和擁護闘争を取り組んだようである。留意すべきは、どちらの動きにせよ党指導下のそれであったことであろう。
|
| 【全学連が内灘、妙義、浅間などのアメリカ軍事基地反対闘争に転換】 |
| 5回大会以後、全学連は極左的傾向を漸次改め、内灘、妙義、浅間などのアメリカ軍事基地反対闘争に取り組み、浅間闘争では東大でクラス討論を重ねて3000名の学生を動員して戦った。
|
| 【全学連.立命館地下室リンチ事件】 |
6.26日、全学連で立命館地下室リンチ事件が発生している。日共京都府委員会の指導する学生党員(「人民警察」)による反学同員に対する3日2晩にわたるリンチ拷問事件であり、被害学生は関大、立命館、名大、東京学芸大、教育大、津田塾に及んでいた。
この事件に関して、山中明氏は、次のようなことを明らかにしている。
| 「ちなみに彼らの示した『CIC のスパイ系図』なるものには宮本顕治、春日庄次郎、神山茂夫の各氏が中心人物にすえられてあった。これはいまでこそ噴飯ものにすぎぬことであったが、当時そのことが血で血を洗う事件となり、皮肉なことだが、党内闘争は『武装闘争』の如き観を呈していたのである。この13校27名にわたる追放リストには武井昭夫、安東仁兵衛、吉田嘉清、津島薫の諸氏及び山中明が含まれていた」。
|
|
 (私論・私観) 「CICのスパイ系図」について (私論・私観) 「CICのスパイ系図」について |
| 今日この時の「CICのスパイ系図」が完全に闇に葬られている。れんだいこから見て、「CIC のスパイ系図なるものには宮本顕治、春日庄次郎、神山茂夫の各氏が中心人物にすえられてあった」とはかなり貴重な資料になり得るように思われる。これを明らかにしている山中氏自身が「噴飯ものにすぎぬ」としているが、れんだいこはそうは見ない。それは余程の確証によった作成されたものではなかろうか。貴重なこの「CICのスパイ系図」の具体的中味を更に知りたいがこれ以上は分からない。 |
| 【徳球書記長論文をめぐる動き】 |
7.4日、これが最後の徳球書記長論文となる「日本共産党創立30周年に際して」がコミンテルンフォルム機関誌「恒久平和と人民民主主義の為に」に掲載された。文中で徳球は、ストやデモに没頭して選挙の問題を軽視する一部の幹部の傾向を批判し、党員は「公然行動と非公然行動との統一に習熟」する必要が有ると警告を発した。これを機に武装火炎瓶闘争が下火となった。中央スポークスマンは、今後選挙運動.平和運動などの合法活動を推進することを強調した。
他方で、徳球論文にも関わらず、「我々は拠点経営における労働者の政治的経済的要求をスト委員会に結集し、これを武装化する為に闘わなければならない。これは当面している軍事委の任務の一つである。それと共に、独立遊撃隊を含む中核自衛隊をこの経営の闘争の中から組織し、パルチザン人民軍の方向へ発展させるよう指導しなければならない」(7.28日付け軍事ノート第5号)と、スト武装化、遊撃隊の組織、パルチザン人民軍の発展という基本方式を強調した。しかし、8月から10月にかけて次第にトーンダウンしていき、「我々はもっと大衆と密着し、大衆の要求と行動の中で行動するという原則に立ち返って、この火炎瓶一揆主義を克服していかなければならない」(10.6日付け軍事ノート第10号)となった。
秋になると、軍事方針や中核自衛隊の活動が大衆の志向や要求から浮き上がっていることが明白となった。これに対して党内からの意見が起こらなかった。分派闘争の締め付けが一定そうさせた。原則的な誤りが明白となっているのに、党指導部が非合法体制や極左冒険主義戦術との見直しに向かえなかったことは、その後ますます党を自己解体の方向に押しやった。
|
 (私論・私観) 火炎瓶闘争後遺症について (私論・私観) 火炎瓶闘争後遺症について |
火炎瓶闘争は、山村工作隊戦術と共に、これに取り組んだ多くの党員に対して癒すことの出来ない傷跡を残した。この戦術を忠実に実践した青年党員達は、以降長い間当局の追及を受け、裁判に掛けられ、貴重な青春を奪われることになった。後で見ていくことになるが、六全協で指導部を簒奪した野坂-宮顕グループは、徳球系指導に従った相応の責任として見殺しにしていった。「党と革命の事業に極めて大きな損害を与えた」(「日本共産党の50年」)と総括することにより、党中央の側から突き放していった。その結果、自殺する者、転身する者、沈黙を余儀なくされる者という地獄絵巻を現出することになった。
徳球書記長論文となる「日本共産党創立30周年に際して」の意義は無視された経緯がある。これは偶然か何らかの事情によってか、詮索されねばならない史実として残されている。 |
6月、文相の諮問機関として、中央教育審議会が発足。
| 【労働運動の転機】 |
| 6月から8月にかけて総評の第3回大会、日教組、私鉄総連、合化労連、国鉄労組など主要単産の大会が相次いで開かれている。それまでの露骨な右翼的指導からやや左派系への転換が見られた。「総評の改良主義的な限界の中での左旋回」が為され、労働戦線の再編成を推し進めることになった。 |
| 【山口武秀の率いる常東農民組合が党から離脱】 |
| 日本農民組合における山口武秀の率いる常東農民組合の動きが注目された。党中央と対立した山口グループは、12月に常東農民組織総協議会を結成して、独自の行動のみちをとることになった。
|
| 【ダレス国務長官が国防要請発言】 |
| ダレス国務長官が、朝鮮戦争の後始末の為の勧告訪問後に東京に立ち寄った。「日本は東南アジアの中心国として、もっと積極的な防衛努力をしてほしい。イタリアは、日本よりもはるかに共産圏から離れているのに、国民所得の7%を防衛費に使っている。日本はわずかに2%だ」、「保安隊を35万に増強せよ」と要求している。 |
| 【池田政調会長使節団がワシントンに派遣される】 |
| 池田政調会長を代表とする使節団がワシントンに飛んだ。会談の相手役はロバートソン国務次官補。池田.ロバートソン会談。この時の池田政調会長の言葉。「シナには五十歩百歩ということわざがあるが、それは抽象的な思惟についてのことであって、現実の政治では五十歩と百歩とは違う。現実では、ある段階に『量』が『質』に転化する。一つの国民心理と一定の経済と成文化された憲法がある場合、ここまでは許せるが、その先は無理だという限界が自ずから存在する」。けだし名言であると思う。「最もいけないのは、生活水準を引き下げても防衛をやれという考え方、これは絶対にダメだ。むしろ生活水準を上げて、守るに値する生活を作り上げることの方が健全な防衛意識を高める為に効果がある」。後の所得倍増と高度経済成長政策の発想がここに垣間見えている。
|
7.7日、日中貿易協定調印を果して中国から帰国した議員の歓迎式会場となった大須球場に集まった共産党員や座主日朝鮮人約1000名が火炎瓶で警察車両を炎上させ、約270名が逮捕されている(大須事件)。「血のメーデー事件」、「吹田事件」、「大須事件」は戦後の最大騒擾事件と呼ばれる。
7.15日、党創立記念日闘争。徳田論文発表「日本共産党創立30周年にさいして」が発表された。伊藤律の書き上げたものであった。
| 7.17日、早大.滝沢林三、榊原喜一郎、破防法粉砕全都蹶起大会、早大責任者として、無期停学。
|
7.21日、破壊活動防止法案、公安調査庁設置法公布で公安調査庁発足。
7.31日、天皇が明治神宮参拝戦後始めて10.16日靖国神社にも戦後始めての参拝。
8.6日、都下町田町の朝鮮人集落とマーケットより、時限爆弾製造法等が書かれた秘密文書「料理献立表」などが押収され、金森駐在所投石事件などの有力証拠を得た。共産党員の容疑者8人(7/31、8/4合計)が逮捕される。
8.7日、横川元商工大臣が埼玉県河村で襲撃され重傷。共産党員の容疑者3人が逮捕される。
| 【IMF(国際通貨基金)に加盟】 |
| 8月、IMF(国際通貨基金)に加盟。IMFは、世界の為替相場の安定と為替取引きの自由化推進を目的として設立された国際機関であるが、これに加盟が認められたことによりIMF14条国として国際社会復帰を果たした。
|
| 【第25回衆議院選挙、講和後最初の総選挙】 |
8.28日、吉田首相が衆院を解散。「抜き打ち解散」と云われる。憲法7条を根拠とした始めての解散となった。吉田派と鳩山派が対立し始め、吉田首相が反吉田派の体勢が整わないうちに抜き打ちで解散した、と評されている。
8.31日、党中央指導部は選挙方針を発表したが、「民族解放民主統一戦線」と称し、全ての「民主的政党愛国人士」と堅く結合し、51年綱領を徹底させるというものであった。
10.1日、第25回衆議院選挙が行われ、自由党は解散時議席を45減じて240議席となり実に僅か3名という議席数で過半数を越すことになった。改進党85、社会党は左右両派で111(右派58、左派58?)の議席を確保した。特に左派の躍進が目覚しく、解散時の16議席から一挙に3倍を越える54議席となった。右派も30議席から57議席とほぼ倍増していた。左右両派拮抗の図となった。労農党4、諸派7、無所属19。
この時、戦犯追放解除者329名が立候補し、鳩山一郎・石橋湛山ら139名が当選した。天皇制官吏から転身した官僚出身者も82名当選している。その後活躍する要人として、片山哲、鳩山一郎(15年衆院当選)、三木武夫、岸信介、重光葵、石井光次郎、賀屋興宣、三木武吉、大野伴睦などがいる。
大蔵省を退官した大平は、郷里香川県から名乗りをあげ初当選。政界入りとなった。この時42歳、田中は33歳の青年代議士であった。この時、田中が自分の選挙区にいる時より長いほど応援演説に駆け回っている。 この時福田も議席を得ている。以来、福田は岸、佐藤の系譜で活動していくことになる。
共産党は完敗全滅した。自党候補115名と統一候補8名を擁立して闘ったが、党候補得票数89万6千票、統一候補15万2千票、合計104万8千票、当選者皆無という結果に終わった。
この時、選挙後一ヶ月以上にわたって政治的空白が続いている。選挙の結果、吉田自由党はそれまでの絶対多数から辛うじて過半数を越えるところまで議席数を落とし、鳩山、河野、三木らの民主化同盟側も大きな痛手を負い、相互に支えあわねば政局運営に支障をきたすまでになった。吉田首相は、総選挙に際して民主化同盟幹部の河野一郎、石橋湛山を除名していたが、鳩山は両名の除名取消し、党民主化の促進、憲法調査委員会の設置の3条件を突きつけ、吉田はこれを了承することにより、鳩山らは第4次吉田内閣に協力することとなった。民主化同盟から三木武吉が総務会長に就任し、形の上では民主化同盟を主流派に組み込んだが、三木ら民主化同盟は反吉田的活動をやめず、吉田も3条件の実行を先延ばしにしていくことになる。 |
| 【井汲塾】 |
| 1952年の夏に国際派が解散して極左軍事方針が党是とされていたこの時期に、久我山の井汲卓一宅で、国際派のイデオローグ達の勉強会が行われることになった。参加した人士は、上田兄弟、佐藤経明、力石、内野、竹中一雄、長森久雄、富塚文太郎、内山達四郎らがレギュラーで、勝部元、高島喜久雄らも時折顔を出していた。54.4月頃から安東も参加するようになったとある。井汲の類まれなる自由な気風と頭脳の賜物により、毎回諸々のテーマで話題や議論を自由活発に行ったとある。この流れが58年の「現マル派」の誕生へと続いていくことになる。
|
| 【徳球倒れる】 |
| 9月末、徳球と伊藤律と李初梨が対談中、徳球が昏睡状態に陥った。急遽病院へ担ぎ込まれることになった。徳球は入院前、伊藤律に「中連部がお前を攻撃するのは、オレを孤立させ、野坂・西沢に包囲させて宮顕を担ぎ出すためだ。だが、毛さんはじめ中共首脳はオレを信頼してくれてるから気にするな」と語っている。
|
10.15日、警察予備隊が保安隊に改組。
10.19日、東京地裁のメーデー事件公判で傍聴者らが騒乱し開廷不能。
10月下旬、第22回中央委員会。選挙闘争を終わってその教訓に学べ、党内教育の方針等を決定。
| 【第4次吉田内閣成立】 |
| 10.30日、第4次吉田内閣成立。官房長官・緒方竹虎、幹事長林譲治、総務会長・益谷秀次、外相・岡崎勝男、法相・犬養健、蔵相・向井忠晴(財界)、文相・岡野清豪、厚相・山県勝見、農相・小笠原三九郎、通産相・池田隼人、運輸相・石井光次郎、郵政相・高瀬荘太郎、労相・戸塚九一郎、建設相兼北海道開発庁長官・佐藤栄作、国務相保安庁担当・木村篤太郎、国務相自治庁担当・本多市郎、林屋亀次郎、大野木秀次郎の布陣であった。
|
| 【鳩山派旗挙げ】 |
| この後、鳩山派が旗挙げし、党民主化同盟が結成されている。25名が結集し、鳩山と三木武吉を御輿に乗せて、委員長・安藤正純で発足した。
|
| 10月下旬、秘密裏に「第22回中央委員会総会」を開催した。武装闘争の基本方針を確認した。 |
| 【池田勇人通産相答弁が「5人や10人、中小企業が倒産し、自殺するのはやむをえない」発言として報道され舌禍辞任】 |
11.27日、池田勇人通産相が、衆院本会議で、再び過去の発言を取り上げた右派社会党の加藤勘十の質問に対し、「ヤミその他の正常な経済原則によらぬことをやっている方がおられた場合において、それが倒産して、また倒産から思い余って自殺するようなことがあっても、お気の毒でございますが、止むを得ないということははっきり申し上げます」と発言した。これに対して野党からは「中小企業を倒産させてよいのか」というヤジと怒号が飛び、議場は一時騒然となった。翌日の新聞は「5人や10人、中小企業が倒産し、自殺するのはやむをえない」発言として報道した。これを受けて野党が池田通産相不信任案を上程し、これに与党内の反吉田派の民主化同盟25名が造反し、その欠席により7票差で不信任案が成立した。11.29日、辞任。これが戦後最初の不信任決議による辞任となる。
その後、池田は自宅に引きこもってしまったが、宮沢喜一秘書官の証言では「これで終わった。明日は土曜日だな。週末旅行でもするか。」と話して、さばさばした様子であった。なおこの辞任記者会見の際に「私は正直すぎた。政治家として終戦以後色々あったが政治家には向いていないのかもしれない」という政治の道を諦めるかのような発言をしている。 |
 (私論・私観) マスコミの「5人や10人、中小企業が倒産し、自殺するのはやむをえない」発言報道について (私論・私観) マスコミの「5人や10人、中小企業が倒産し、自殺するのはやむをえない」発言報道について |
「れんだいこのカンテラ時評617 マスコミの発言歪曲記事報道考」は次のように述べている。
もう一つの「中小企業の一部倒産もやむを得ない。経済原則に違反して、不法投機した人間が倒産してもやむを得ない」発言については、「第015回国会 本会議 第7号」で確認できる。
(ttp://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/015/0512/01511270512007c.html)
今、これを読み取ると、1952(昭和27).11.27日、池田通産相は次のように答弁している。「なお、特に御質問のありました昭和二十五年三月一日の私の言として新聞に載りましたことにつきましては、その直後、この壇上で私の心境を話しております。その後におきましても何らかわりはございません。ここではつきり申し上げますが、インフレ経済から安定経済に向いますときに、この過渡期におきまして、思惑その他の普通の原則に反した商売をやられた人が五人や十人破産せられることはやむを得ない――お気の毒ではありまするが、やむを得ないということをはつきり申しておきます」。
これに対し、加藤勘十・社会党議員が、問題発言であるとして次のように述べている。「ただいま私の質問に対して、各大臣はまつたく焦点をはずれた、でたらめな答弁をされておる。(拍手)のみならず、外務大臣は答える道を知らない。このような不誠意な内閣が一体どこにあるか。(拍手)しかも、通産大臣のごときは、みずから五人や六人……。〔発言する者多し〕。一体、五人や六人の国民は死んでもいいのか、それはどうかと聞いておるのである。これに対して通産大臣は一体何と答えたか。(拍手)ひとり議員を侮辱するばかりではない。全国民を侮辱するものである。(拍手)私は、通産大臣の明確なるお答えと、外務大臣のはつきりしたお答えを聞きたい。(拍手)」。
社会党らしい揚げ足責めが見えてくる。池田通産相が大局的に分析して企業淘汰論を述べているのに対し、社会党は、個別特殊例をことさら取り上げて、「一体、五人や六人の国民は死んでもいいのか」と迫っている。これに対し、池田通産相は次のように述べている。「私の心境は、インフレ経済から安定経済に参りますとき、やみその他の正常な経済原則によらぬことをやつている方がおられた場合において、それが倒産をし、しこうしてまた倒産から思い余つて自殺するようなことがあつてお気の毒でございますが、やむを得ないということははつきり申し上げます」。
このやり取りを、池田再食言として問責報道して行ったのが当時のマスコミであった。果たして、正確であったであろうか。事実は、朝鮮動乱下の好景気に沸く中での企業倒産に対してまで責任を持てない云々と、ある意味で当たり前のことを述べているに過ぎない。池田通産相は、この発言報道により、翌日に不信任案が提出可決され辞任に追い込まれている。こうなると報道責任もあるように思われる。本当にケシカランのはどちらであったのだろうか。 |
| 12月、全国軍事会議を開き、結語を採択し具体的方針を確認した。 |
| 【 戦後党史第二期】/ 【ミニ第④期】=伊藤律失脚、志田派が党中央完全掌握 |
| 3月、突如スターリンの死去発表され、10月には徳球書記長も亡命先北京で客死した。こうして一つの時代が終わった。伊藤律が失脚させられ、この後党内は伊藤律派と志田派の後継争いが激化し、志田派が実権を握る。志田派は、更なる武闘路線を目指しつつも成果が上がらず、その反動として党内の整風化に注力し「党内点検運動」に向かう。この経過で志田派と宮顕派の野合が画策され、55.7.28「六全協」で党の再統一が為される。この期間を【ミニ第④期】とみなすことができる。 |
| 【伊藤律査問、幽閉される】 |
12.24日、徳球が緊急入院した。以来、伊藤律と野坂・西沢間に激しい論争が発生していくことになった。2ヵ月後のこの頃、野坂が突然「モスクワから重要なことを云って来た。緊急幹部会議を開く」と幹部会を招集した。出席者は野坂.西沢.高倉輝.聴涛克巳.土橋一吉.中連部副部長李初梨で、伊藤律への査問が開始された。野坂・西沢と中連部の李初梨副部長ラインの合作で為されたことになる。李初梨は、当時中共党中央の日本課長といわれていた対日政策の責任者であった。毛沢東路線に反対し、日共との連絡線は野坂・宮顕ラインに置いていた。1965年の文化大革命と同時に失脚することになる。
野坂が一枚の紙片を取り出しながら、スターリン直々の我が党への勧告である、名目は勧告であるが違反はできないと前置きして、「伊藤律は節操のない人間であり、政治局はその証拠を持っているはずである。直ちに一切の職務から切り離し、問題を処理せよ」、「協力によって得るものは利益だけである」と声明した。伊藤律は形成利あらずとして指示に従った。西沢の「とにかく伊藤君を他所に移してから、話をしよう」提案により移動させられ、以来北京郊外の某所に軟禁されることになった。伊藤律39才と6ヶ月の時であった。この時の北京機関の他の面々の態度は、土橋・聴涛が伊藤律の隔離審査に反対し、高倉は保留であった。
1980年に至って伊藤律は奇跡的生還を遂げることに成ったが、9.19日付け赤旗は、野坂参三議長の次のような声明を載せている。これまで公式的に伊藤律とは東京で別れて以来会ったことがないとしてきていた野坂が、伊藤律生還という事態に対して種々弁明している。そのハイライトは次のくだりである。
| 「こうして西沢と私とは、『北京機関』内部の問題と同時に、今言ったような過去における彼の行動、特にゾルゲ事件に彼の発言、行動がきっかけをつくったというのが事実とすれば、これは重大問題だと考えました。そして、この際、伊藤律の問題を『北京機関』の問題として取り上げなければならない、ということを、私と西沢で決めました。その時は、徳田君のほうは脳溢血で倒れて、これには関与できない状態になっていました。そこで、周恩来など中国側の最高幹部とも協議して、伊藤律を『北京機関』から離し、別のところに住まわせて、十分に時間をかけ、深くこれらの問題を調査する必要があるという結論に、我々は到達したのです。これが1952年の10月ごろです。伊藤が北京に来てから、丁度1年目ぐらいです」。 |
|
 (私論・私観) 伊藤律幽閉に関わる野坂の動きについて (私論・私観) 伊藤律幽閉に関わる野坂の動きについて |
| 今日では野坂はスパイであったことが判明している。そのスパイによって、伊藤律がスパイ容疑をかけられ、幽閉されていったという経過が直視されねばならない。 |
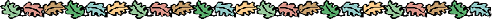



 (私論.私見)
(私論.私見)
