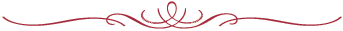戦場の捕獲物である女・子供をはじめとする「掠奪された人びと」が、ポルトガルの黒船によって東南アジアで売りさばかれていたと述べた。一説にはその数十万人以上という。当時、マカオやマニラには多数の日本人奴隷がいた。九州では、伴天連(バテレン)の協力を得て、ポルトガル商船が多くの日本人男女を買い取り、平戸と長崎からせっせと東南アジアに積み出していたのである。伴天連たちにとっての権威であるイエズス会が、日本から少年少女を奴隷として積み出そうとするポルトガルの人買い商人に輸出認可証を発行していたのである。
当時のヨーロッパ人の通念として、ポルトガル人たちも「正しい戦争によって生じる捕虜は、正当な奴隷である」と考えていた。では、どれが正しい戦争で、どれが正当な奴隷なのか。イエズス会は、日本人にはそれを判別する習慣がなかったので、必然的にその判別能力はないとしたのである。十四、十五世紀から二十世紀までのヨーロッパ人というのは、人類史上例をみない残虐な傲慢さを露骨に表に剥き出した、実に醜い存在であったと言っていいだろう。
天正十五年(1587)、豊臣秀吉は「島津征伐」(九州征伐)を敢行し、島津氏を破り、遂に九州全域を支配下に置いた。この時点で、秀吉は北条氏支配下の東国以北を除く日本列島のほぼ半分を支配下に置いたことになる。島津征伐の軍を返す時、秀吉は博多でイエズス会宣教師;コエリュを詰問した。ポルトガル人が多数の日本人を奴隷として買い、南方へ連れて行くのは何故か、と。この時、コエリュは「ポルトガル人が日本人を買うのは、日本人がポルトガル人にそれを売るからである」と、“見事な”回答をしている。この台詞、どこかで聞いたことがあるではないか。「山があるから登るのだ」・・・あれと同じである。私は、如何にも“毛唐人”らしい言い方であると思う。つまり、「売る」方がいるから「買う」者が出現する、買われて困るのなら、売らなければいいという開き直りとも言える。
宣教師;ガスパール・コエリュ。インドのゴアでイエズス会に入会し、ポルトガルのアジア侵略拠点;マカオを経て元亀三年(1572)に来日、長崎南部の加津佐を中心に活動した。『イエズス会日本通信』を著した人物といえば、学校で習ったことを思い出される方も多いだろう。この『イエズス会日本通信』が書かれたのは天正十年(1582)であるが、この年、「天正遣欧少年使節」がローマを目指して旅立っている。コエリュによれば、この時点で、日本のキリシタンは、有馬・長崎・大村・平戸・長崎、そして京・安土を中心にして約十五万人に膨れ上がっていた。
余談ながら、あの有名な四人の「天正遣欧少年使節」は、キリシタン大名と言われる大友宗麟、大村純忠、有馬晴信の名代としてローマへ派遣されたものであるが、彼ら大名の領内はキリスト教以外の宗教を認めないというほどのキリシタン独裁国家であった。私たち日本人は、明治以降の官軍教育によって、伴天連=キリシタンは一方的に迫害を受けた宗教弾圧の被害者であったとしか教えられていないが、この時代に於いては全く逆である。キリスト教という宗教は、一元主義の排他性の強い宗教であるが、その特性通り彼らは仏教をはじめとする他の宗教を徹底的に弾圧した。
大村純忠領内では強制的な改宗が展開され、百姓領民はことごとく伴天連に改宗させられ、その数は四万人に達した。また、有馬晴信は、仏僧に改宗を迫り、これを拒んだ僧を追放し、約四十に及ぶ寺社を破壊した。御一新直後の長州人たちによる気狂いじみた「廃仏毀釈」について述べたことがあるが、あれと全く同じことが「天正遣欧少年使節」の故郷で行われていたのである。宣教師たちは「仏僧は諸人を地獄に落とす者であり、この国の最良のものを食い潰す存在である」と民を扇動した。現在も長崎県南部では、破壊、焼き打ちの結果として当時の仏教石造物、寺社建造物は存在しない。今から十三年前(1998)、有馬氏の本拠;日野江城跡から破壊された石塔、五輪塔など135点が発掘された。何とそれらは大手口の石段に使われていたことが判明したのである。つまり、キリシタンは人びとに「踏み絵」を強要していたと考えられるのである。
コエリュと並んで著名な、前述したルイス・フロイスも、実は激しい弾圧を行った張本人の一人である。人びとが有馬の仏像を口之津近くの小島の洞窟に移して隠そうとしたが、これを捕え、大きい仏像を燃やし、小さい仏像を見せしめとして仏教徒の子供たちに村中を引き回させたのである。当時の宣教師たちは、自ら認めているように日本侵略の先兵であるが、仏教徒をはじめとする既存宗教に対する弾圧者としての彼らと伴天連たちの実相を一度白日に晒し、彼らの罪業は遡って糾弾されなければならない。勿論、細川ガラシャもそういう仲間の一人として認識されなければならない。
『伴天連ら、日本仁(人)を数百、男女によらず黒船へ買い取り、手足に鉄の鎖を付け、船底へ追い入れ、地獄の呵責にもすぐれ~』――当時の記録が残っている。どうやらイエス様もマリア様も、伴天連以外は人間としてお認めにならなかったようである。
既にこれ以前より、奴隷と武器は東南アジア向けの日本の主力輸出品であった。弘治元年(1555)に多くの日本女性がポルトガル商人によってマカオに輸入されていることが、マカオ側の記録によって確認されている。ところが、当初ポルトガル商人に対して日本人の輸出認可証を発行していたイエズス会は、日本人奴隷の輸出が日本における布教の妨げになることに気づき始めた。日本侵略という本来の目的に照らせば、本末転倒になることに気づいたのである。このことは、織田信長や九州のキリシタン大名たち以外の日本の権力構造を構成する戦国大名たちにも彼らの視線が広く、深く注がれるようになったことを意味する。信長に庇護され、九州のキリシタン大名だけを相手にしている時代は、事は簡単にみえた。
ところが、信長亡き後、権力が豊臣秀吉に移り、キリシタン大名たちの勢力というものも俯瞰してみて、日本の武士階級の精神構造にも理解が深まっていくと、戦場から吐き出されてくる捕獲物としての日本人を自国の商人へ安易に売り渡し、暴利を貪(むさぼ)っていることが布教の障害になることが明確になってきたのである。そこでイエズス会は、一転して本国の国王に日本人奴隷の売買を禁止するよう要請した。これを受けてポルトガル国王は、元亀元年(1570)、日本人奴隷取引の禁止勅令を出すに至った。イエズス会自身もその後、「少年少女を日本国外に輸出する」人買い商人に対する破門令を数度に亘って議決するのだが、既に効果は全くなかった。インド、マカオを中心に東南アジア全域に幅広く展開していたポルトガル人たちは、日本人奴隷を買うのはあくまで「善意の契約」に基づくものであり、「神の掟にも人界の法則にも違反しない」として勅令を完璧に無視したのである。日本人の売買に関しては、イエズス会自身が脛に傷をもっている。勅令さえ無視する者がイエズス会の破門令などを恐れる訳がない。かくして、捕獲物としてポルトガル商人に売り飛ばすという「掠奪した人間」の販路は依然として健在であったのだ。
天正十五年(1587)、コエリュとやり合った秀吉は、コエリュの態度に余程怒りを覚えたのか、すぐさま「伴天連追放令」を発令し、その中(第十条)で「人身売買停止令(ちょうじれい)」も併せて発動したのである。江戸幕府にも継承されるキリスト教の禁止という基本方針は、この時の禁令が端緒なのだ。つまり、キリシタンの取り締まりと人身売買の停止は、不可分のテーマなのである。それは、日本のキリシタンやその指導者であるイエズス会が、日本人を輸出品として売り飛ばすことによって利益を上げていたからに他ならない。
秀吉は、追放令をイエズス会に通告する際、次のような添え書きを申し送っている。――九州に来航するポルトガル人、カンボジア人、シャム人たちが、多くの日本人を買い、諸国へ連れ去っていることをよく承知している。これまでにインドをはじめ各地へ売られたすべての日本人を、日本へ連れ戻すことを求める。それが無理だというのなら、せめて現在、ポルトガル船に買われてまだ日本の港に停泊している日本人だけでも速やかに買い戻して解放せよ。その分の対価は後日与える――
これに対する伴天連サイドの反論は、以下のような内容であった。――人身売買の廃止は、イエズス会の永年の方針である。問題は日本側にあり、特に九州の大名たちは日本人の売買を厳しく禁止しようとはしていない――
反論にはならない単なる苦しい抗弁に過ぎないことは言うまでもないが、ここでキリシタンが言っている「九州の大名たち」というのが所謂「キリシタン大名」を指すことは言うまでもない。それにしても、永年日本人を売り飛ばす片棒を担ぎながら、人身売買の廃止が「永年の方針」であるとは、笑止千万である。
秀吉は、「人身売買停止」という命令を国内の仲介商人たちにも適用し、現実に掠奪されて売られてきた日本人をポルトガル船に運んだ舟の持ち主を磔刑に処した。これは、九州を征討した秀吉のポルトガル人=キリシタンに対する防衛外交の一環とみることができるが、皮肉なことにその秀吉の軍が朝鮮半島に於いて多数の朝鮮人を捕獲していたことも、また事実なのである。更に、倭寇の活動まで遡れば、東アジアに於ける奴隷売買の実態はまだまだ全容が解明されていないのである。いずれにしても、戦場で捕獲された百姓や子供たちがキリシタンやポルトガル商人たちの手によって輸出品として売られるという仕組みがあったからこそ、人の掠奪が「稼ぎ」になったのである。勿論、「稼ぎ」の仕組みはこれだけではなかった。