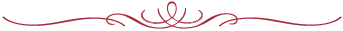
更新日/2023(平成31.5.1日より栄和改元/栄和4).1.20日
| 金地院崇伝vs南光坊天海/考 |
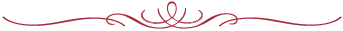
更新日/2023(平成31.5.1日より栄和改元/栄和4).1.20日
| (れんだいこのショートメッセージ) |
| ここで、「金地院崇伝vs南光坊天海/考」をものしておく。 2023(平成31.5.1日より栄和改元/栄和4).1.20日 れんだいこ拝 |
![]()
| 2023.1.19日、「家康の側近だった黒い僧侶たち~金地院崇伝vs南光坊天海の勝者は? 」その他参照。 寛永十年(1633年)1月20日に亡くなった金地院崇伝(以心崇伝)は、【黒衣の宰相】とも呼ばれる。このアダ名は彼固有ではなく、他に5人ほど候補が挙げられる。◆源平時代の藤原信西、◆室町時代の満済准后、◆今川家の太原雪斎、◆毛利家の安国寺恵瓊、◆徳川家の南光坊天海。全員キャラが濃い。果たして金地院崇伝は本当に黒いのか。いかにして徳川家康に重用されたのか。その生涯を振り返ってみる。 金地院崇伝(以心崇伝)の出身は一色家 崇伝は永禄十二年(1569年)、一色秀勝の子に生まれた。一色家は室町幕府の重臣の家。父の秀勝はあの剣豪将軍こと足利義輝に仕えていた武将である。大河ドラマ『麒麟がくる』でもご存知の通り、当時の幕府は凋落著しく、一色家も厳しい状況にあった。そのためか、崇伝は若くして南禅寺に入り、まずは玄圃霊三(げんぽれいざん)という僧侶の弟子になっている。醍醐寺三宝院でも学んだりして順調に修行を積んでいった崇伝は、その後、37歳で、臨済宗及び禅寺の中で最も格の高い南禅寺で住職になった。金地院崇伝の「金地院」とは、このころ再興したお寺から来ている(江戸や駿府にも金地院を建立している)。このとき、徳の高いお坊さんにしか与えられない【紫衣】を後陽成天皇から賜っている。 表舞台へ出てきたのは関ヶ原後
崇伝が政治の舞台に出てくるのは、慶長十三年(1608年)のこと。意外にも関ヶ原の戦い後である。西笑承兌(さいしょうじょうたい)という、これまた家康の知恵袋だったお坊さんが亡くなってしまったので、その代わりが務まる僧侶ということで駿府へ招かれた。承兌は、直江兼続が例の慇懃無礼な果たし状【直江状】を出したときの宛て先でもある。ちなみに、こうした僧侶が重んじられるのは、学識を備えた彼らが外交・文化面で活躍したからである。日本国内のみならず、このころ家康はアジア各国との交渉にも及んでいて、正式な国書に用いる「漢文」に精通した崇伝が活躍しました。現代の政治でいえば有識者会議みたいなものである。黒いライバル・南光坊天海 承兌という実力者の後任を任された崇伝ですので、当初からある程度の権力と仕事を任されていた。特に江戸幕府の根幹となる法律の制定に大きく関わっている。【武家諸法度】や【禁中並公家諸法度】、はたまた【キリスト教の禁止】や豊臣家を潰した【方広寺鐘銘事件】など。この時期のテストに出そうな単語にはだいたい絡んでいる。豊臣家を潰した方広寺鐘銘事件について最近の通説では「崇伝の描いたシナリオではない」とされているが、豊臣方への詰問をしたそうで、いかにも頭脳のキレるタイプであることが伺える。まぁ、そうでなければ家康に重宝されませんよね。文化面でも『日本後紀』や『続日本後紀』をはじめ『類聚国史』や『律令』など多くの記録を残していくよう命じたりしている。さすが僧侶出身。彼が、江戸時代初期の知識面を支えていたと言っても過言ではない。しかし、徳川政権においては、そのまま崇伝の独壇場とはならなかった。同じく家康の側近だった南光坊天海との対立があった。特に家康が亡くなったとき、この二人は火花が飛びそうな争いようでした。というのも……。崇伝は明神様を推していたが、結局、権現様に 崇伝と天海が喧嘩する火種になったのは、家康の神号。一般人からすると「なぜ仏教のお坊さんが神道の祭り方に口を出す?」と言いたいところですが、江戸時代の時点で千年以上神仏習合をやってる日本ではよくある話ですね。真面目に考えると、僧侶としてではなく家康・幕府の重臣として話し合っていたということなのでしょうけども。崇伝は「明神」という号がいいと考えていた。これは神様の中でも特別に祀られる場合に用いられる名称で、神田明神や稲荷大明神などが有名です。まあ江戸幕府の開祖ですし、無難といえば無難ですね。これに対し、天海は「権現」にしようと主張していた。権現とは「仏様が日本の神様の姿で現れた」ということを意味するもので、山王権現や愛宕権現などが有名。どっちもそれなりの理由があって「こっちがいい!」と言っていたので揉めたわけですが、ここで大問題が発覚する。豊臣秀吉が「豊国大明神」になっていたことです。これでもし、家康を同じ明神号で祀ってしまうといろいろマズイですよね。秀吉からすれば息子を殺しくさったヤツと同じ号になるなんて真っ平御免ですし、世の人からしても「一時は主君だった人の家を滅ぼしたくせに、同じ神号にするなんてどこまでタチが悪いのかしらー、いやーねー」(※イメージです)とか言われかねません。そのため家康は明神ではなく、権現として祀られることになった。忠興宛の手紙に「ありえないわー」 いわば崇伝側の負け。よほど腹に据えかねたのか、崇伝は細川忠興宛の手紙で「前代未聞でありえないわ」と不満を綴っています。もちろんこの一件で徳川幕府からの信頼がなくなるようなこともありません。徳川秀忠の息子・つまり徳川家光の名前を考えたり。朽木元綱に「娘の結婚式をいつの日取りにしたら縁起がよいですか?」と相談されたり、あるいは九鬼守隆や丹羽長重らから頼まれて芸術品(絵画や茶道具)の鑑定に携わったり。当代一流の知識人だったことがわかりますね。紫衣、勝手にもらったら島流し そんな崇伝が関わったもので、最も大きな一件が【紫衣事件】でしょう。江戸時代初期の幕府と朝廷のゴタゴタで、ことの発端は、朝廷がやたらと紫衣を与えるようになってしまっていたことでした。紫衣とは、お寺の中でも高僧だけが朝廷から賜ることのできるもので、朝廷にとっては収入源の一つでもあります。上記の通り、崇伝は若い頃実力で紫衣を賜っていますから、怒りもひとしおだったことは想像に難くありません。このとき紫衣を取り上げられた僧侶達から抗弁書が出たときも突っぱね、離島への流罪を主張しています。彼よりは温厚だったと思しき天海らによって、これも軽減されてしまうのですが。多分こんな感じで天海に頭を抑えられるようなことが何回かあったせいで、崇伝のほうが知名度低いのかもしれません。あるいは天海=明智光秀説なんてのもありますので、天海のほうが有名なのかも。個人的には正体不明すぎて怪しい(というか胡散臭い)天海より、ちょっとキツくても現実味がある崇伝のほうが好きです。当時は「大欲山気根院僭上寺悪国師」とか「天魔外道」とか散々な言われようだったようですが、政治の世界で意志が強くなければ何もできない気がします。幕府設立の功績からすると多大なものがあり、単純にブラックとは思えないですよね。亡くなった(遷化した)のは寛永十年(1633年)のこと。腹や背中の痛みに身悶え、病に苦しみながら亡くなったことが記録されています。享年65でした。 |
| 2022.7.24日、「紫衣事件はナゼ起きた?そもそも紫衣とは?そして後水尾天皇は譲位へ 」。 慶長20年(1615年)5月。大坂の陣で豊臣家を滅ぼし天下人となった徳川家康。大きな法律を立て続けに出す。その代表が・武家諸法度と禁中並公家諸法度。前者は全国の大名に向けて規範を定めたものであり、後者が皇族貴族向け。要は「幕府に逆らうんじゃないよ」ってなコトを全国の大名や皇族貴族に対して通告したもの。そしてこの法律から程なくしてある事件が起きる。寛永六年(1629年)7月25日の紫衣事件。この日、僧侶の玉室宗珀(ぎょくしつそうはく)や沢庵宗彭(たくあんそうほう)らが流罪にされる。まず気になるのは紫衣事件の「紫衣」。長い修業を経て徳を身につけた僧侶だけが朝廷から授けられる特別な法衣である。この頃には紫衣の基準があいまいになっており、まだ修行の浅い若い僧侶に紫衣が与えられることが増えていた。戦国時代を経て僧侶の世界も秩序が乱れていた。これを厳密なものにすべく、幕府は元和元年(1615年)以降に紫衣の勅許を受けた者に対し、取り消すなどの処置を寛永四年(1627年)7月に実施した。【禁中並公家諸法度】と【諸宗本山本寺諸法度】などで、幕府は朝廷に対し「紫衣の勅許をそうホイホイ出されては困ります。これからは幕府にご相談ください」(意訳)としていたが、しかし朝廷は無視し続けた。 幕府も黙っていられない。老中・土井利勝、京都所司代・板倉重宗、そして幕府のブレーンの一人である僧侶・金地院崇伝らが連名で、朝廷へ抗議の書面を出す。当然、朝廷や勅許を受けた僧侶たちは強く抗議した。おそらくは『武士が、高貴な我々に何を偉そうなことを!』というような反感もあった。ただでさえ、禁中並公家諸法度で頭を抑えられ始めて日が浅い。幕府も妥協案を出したが、僧侶側の一部はさらに抗議し、江戸までやってきて直談判する。幕府としてはせっかく妥協したのに、さらにゴネられてはさすがに黙っていられない。江戸まで来た四名の僧侶を流罪に決めた。ここまでの一連の流れが一般的に紫衣事件とされ、一般的には以下のような意義があったとされる。ときの将軍は三代・徳川家光。・朝廷と幕府の力関係を明らかにした・そして幕府は独裁色を強めた(朝廷のナァナァな姿勢にメスを入れた)ちなみにこの時、幕府側の僧侶の間でも意見が割れた。金地院崇伝は厳罰を、南光坊天海は軽い処罰を主張していたとか。天海は「光秀じゃないか?」といわれていることでも有名な僧侶ですね。 |
| 幕府への抗議を込めて突然譲位する これに対し、ときの帝である後水尾(ごみずのお)天皇が機嫌を損ねる。この方は歴代の天皇の中でも、特に自分の意志をはっきり表す御方でした。紫衣事件について立腹だったらしく、幕府への通達なしで娘である興子内親王(明正天皇)に突然譲位してしまう。突然の譲位を重く見てか、罰された僧侶たちは天海の取りなしにより、三年ほどで罪を許されて江戸に帰った。しかし、許されてからも二年の間は帰京を許可が出ず宙ぶらりん状態になる。罰されたうちの一人・沢庵宗彭は徳川家光の信頼を得て、帰京した後は毎年江戸に参上し、繰り返し紫衣勅許に対する理解を求めていた。最終的には、「京都所司代の承認を経てからならOK」という形で落ち着き、幕府と朝廷の火花は収まった。 |
| 家光自らが上洛しての歩み寄り |
| 紫衣事件により、朝廷と幕府の仲は冷え込むかに見えた。しかし、寛永十一年(1634年)に家光自ら上洛し、後水尾上皇に謁見して院政を認めるなど、幕府側が歩み寄る態度を見せている。家光は将軍就任時(元和九年=1623年)と、後水尾天皇の二条城行幸の際(寛永三年=1626年))にも上洛している。後水尾上皇の中宮は家光の妹・和子(東福門院)なので、直接会って話したほうがいいと判断したのでしょうか。寛永十一年の上洛の際は、家光は姪である明正天皇や和子にも謁見している。家族という点を利用して、数年間続いていたであろう紫衣事件の余波を収めようとしたのかもしれない。こうして京都との揉め事は一段落したが、この後【島原の乱1637-1638年】が起き、家光時代のトラブルはまだまだ続く。 |
![]()
![]()
![]() (私論.私見)
(私論.私見)