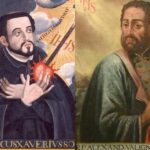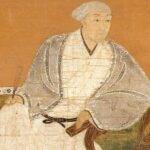1615年2月3日(慶長20年1月6日)は戦国武将の高山右近が、フィリピンの首都・マニラで亡くなった日。
日本からフィリピンへ……というと、昨今は強盗事件の容疑者ルフィを思い浮かべてしまうかもしれませんが、右近が旅立った理由はもちろんそんなことではありません。
彼は武将であると同時に敬虔なキリシタンでもあり、洗礼名は「ジュスト」となります。
漢字で表記すると「寿子」らしく、なぜ二文字目、それにしたし……。
ともかく、右近は何のため海を越え、異国に没したのか?
ご想像通り、それには彼の信仰が関わっておりました。
お好きな項目に飛べる目次 [とじる]
高山右近の高山家は三好に仕えていた
右近は摂津国(現・大阪府)の国人の家に生まれました。
国人とは正式な国主として認められてはいないものの、地元の有力者として勢力を持っていた人々のことです。国衆という言い方もします。
彼等一人一人の影響力は国を動かすほどではないけれど、かといって大名はこうした国人たちと上手く付き合わなければ国の運営は成り立たず、逆に国人の中には戦国大名へと発展するケースもいました。
有名な例では毛利元就とか、あるいは真田昌幸・真田信之・真田信繁親子あたりも大名化した国人に含まれるでしょう。
そんなわけで右近のトーチャン・高山友照も地元ではそれなりに名が知れており、近畿の有力な大名だった三好長慶に仕えていました。
さらにその重臣・松永久秀からは大和国(現・奈良県)に城をもらっています。
本来の領地は摂津のままなので、飛び地のような感じですね。
しかし、右近が12歳の頃に長慶が亡くなると、三好家では内紛やら裏切りやらのゴタゴタで急速に衰えていきました。
このころ両親と共にキリスト教の洗礼を受けており、もしかすると教えに感銘を受けただけでなく、こうした時勢の変化も影響していたのかもしれません。
惟政に反発して台頭してきた村重
一方、高山家の地元でも他の家が力をつけつつあり、緊迫した状況が続きました。
そんな時期の京都に織田信長が足利義昭を連れてきます。
義昭は十五代将軍になると、まずは地固めということで摂津に自分の直臣である和田惟政(これまさ)を置きました。
”将軍様”の意向には従わないといけないので、高山家も惟政に仕えることになったのですが……血筋的に正しいとはいえ、ついこの前まで逃げ回ってた人の家臣にそうそう人心がなびくわけもなく、余計に混乱を招いてしまいます。
そしてついに惟政へ反感を持つ人々が挙兵。
右近にとっても大きく関係することになる荒木村重です。
村重は池田家というこれまた摂津の大名の家臣でしたが、主家を乗っ取った上で信長と連絡を取り、「摂津は私のものにしていいですよね!?」「おk」(超訳)というお墨付きをもらいました。
当然のことながら村重は大喜びし、いろいろ頑張った結果、摂津のうち石山本願寺領(だいたい現大阪市)以外を手に入れました。
首の半分を斬られて重傷って……
当然ながら、和田家がこれをよく思うはずもありません。
しかしこの間に代替わりがあり、跡を継いだ惟長がまだ若年ということで叔父さんが口を出してきます。
と、もうこの時点でイヤな予感がしますね。
案の定トラブルが起き、この叔父さん、殺されてしまいます。
惟長は次に信用できそうな人物として高山家を頼りましたが、和田家のお偉いさんはまたしてもこれが気に入らず、よからぬことを企み始めます。
そしてついに暗殺騒ぎとなり、右近は首の半分を斬られるという重傷を負ってしまうのです。
奇跡的に助かった右近はこの後、より一層信仰を深めていくことになります。
でもこの傷、暗いところでドタバタ騒ぎになったせいで起きた同士討ち(未遂)だった可能性もあるようで……。
事前に村重へ「何かウチら命狙われてるっぽいんですけど」と相談していたおかげで、この騒動の後、高山家はお咎めなしとなり、和田家がいた高槻城をもらうことができました。
ちなみに惟長は、和田家の地元である甲賀(現・三重県)まで逃げたそうで、そのままそこで亡くなったそうです。
高山家の当主になったら村重が謀反
その後、トーチャンの友照が「キリスト教最高!」(超訳)という政策を掲げ、領内の寺社が破壊されたりキリスト教以外の聖職者が迫害されたり、あまり穏やかでないことも始めてしまいます。
一神教の全てが悪いわけではありませんが、この極端さがいただけませんよね。
このころ右近は高山家の当主になります。
そして間もなく大事件が……。
荒木村重が突如、信長に反乱を起こしたのです。
村重は、一度は信長からの使者に従って謀反を取りやめようとしました。
が、安土城に向かう途中で家臣から「信長がそんなことで許すはずないじゃないですか」とそそのかされて引き返していますので、決意は固かったようです。
これには右近も驚き、新たに人質を差し出してまで村重に説得を試みましたが聞き入れてもらえません。
もはや話は通じまい――。
そう判断した信長は、ついに攻撃を決断。
高山家がいた高槻城は戦略上重要な地点だったため、まずここへやってきました。
信長の怒りを増さず人質を助ける方法
信長は、直ちに高山右近への攻撃には取り掛かりませんでした。
旧知のイタリア人宣教師オルガンティノたち、つまりキリスト教関係者を使って右近の説得を試みているのです。
摂津どころか京都にいた宣教師達を全員集めたといいますから、できるだけ殺さずに事を収めたいと思っていたのではないでしょうか。
とはいえ「できなかったらどうなるかわかってんだろうな☆」(超訳)なことも言っています。
以前から右近を見知っていたオルガンティノは、右近が「名誉のためにも人情としても人質を見捨てられないだろう」と理解していました。
それも含めてよく考えるよう伝えるのが精一杯で、結局彼の力だけでは事の解決に至りません。
高山家の中でも、徹底抗戦派と降伏派で真っ二つに割れていたからです。
そこで右近は、信長の怒りを増さずに人質を助ける方法を考え出します。
たった一人、紙衣(和紙の着物・下着によく使われていた)に丸腰で信長の下へ向かったのです。
これなら城と兵ごと信長の元へ行ったわけではないので村重を裏切ったことにはならず、信長へは反抗する意思がないことを示せるということになります。頭いいなあ。
信長は右近の意思を汲み取り喜ぶと、そのとき着ていた服や馬、そして改めて高槻城主の地位をやっています。
手こずらせた割には人的被害がなかったのがよかったのでしょう。
「お古の服なんて嬉しくないんでは?」と思われた方もいらっしゃるでしょうが、当時エライ人が着ていた服をもらうというのは名誉なことでした。
旧暦11月=だいたい新暦12月のことですから、「それだけじゃ寒いだろ、とりあえずこれでも着とけ(´・ω・`)つ」というちょっとした優しさもあったかもしれませんね。
高槻周辺の寺社は衰退との記録残る
村重も、右近の予測通り人質を殺すことはせず、高山家は穏便に済ませてもらうことができました。
その後、黒田官兵衛を有岡城内に幽閉し、籠城で粘った挙げ句、ついに諦めた村重が一人で城から逃亡。
村重の一族や妻子は、信長の指示によってかなり残酷な殺され方をしてしまいます。
この一件から豊臣秀吉が台頭してくるまで、右近が大きな動きをした記録はあまりありません。
ただ、トーチャンと同じようにキリスト教以外には厳しかったらしく、高槻周辺では「高山右近の時代に衰退しました」とする寺社の記録も多いそうです。
右近は多くの大名がキリシタンになるきっかけになるくらい影響力を持っていたので、民衆がそれにならった結果、寺社が廃れたのかもしれませんが。
九州のキリシタン大名として有名な大友宗麟については「寺社を徹底的に破壊しました」という記録が一致しているので、右近のほうがまだ優しかった可能性は高そうです。